不動産投資へのこだわり!18 【新刊】急成長企業の社長&不動産投資のプロが登場!『融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる!』10月4日発売!
元証券ウーマンが不動産投資で7億円

FIRE(早期リタイア)への近道!
たった5年で資産7億5000万円
年間家賃収入7000万円
フリーキャッシュフロー(純現金収支=手元に残るお金)年間2000万円
◎知識ゼロから不動産投資で
安定的に資産を増やせる方法を教えます!
不動産投資を始めて5年、資産7億5000万円を築いた。
出身地の愛知、それに東京・千葉にアパート6棟とテナントビル1棟を所有。
年間家賃収入7000万円、
諸経費や税金を差し引いたフリーキャッシュフロー年間2000万円を得ている元証券ウーマンが、
「知識ゼロから不動産投資で安定的に資産を増やせる方法」を教えます。
◎不動産投資で勝つ6つの力を徹底解説
☆逆算する「計画力」
☆人生のビジョンを持つ「成功力」
☆調査する「営業力」
☆自己アピールする「交渉力」
☆理性と感情の「行動力」
☆自分を客観視する「投資力」
野村證券の社員だった20代の頃、
不動産投資に目覚め、わずか5年で7棟資産7億5000万円の不動産オーナーとなった。
でも1棟目を購入するまでは、たいへんな道のりだった。
証券会社勤めということもあり、株式投資のノウハウはあったけれど、不動産投資はズブの素人。
不動産投資に関する書籍を100冊以上読むところから始め、
不動産会社を50社以上巡ったものの、不動産投資初心者の20代OLはナメられて、まともには相手にされなかった……。
その1年後、ついに運命の1棟目に出会う。
築18年の重量鉄骨造のアパート(全10室)で、販売価格は4800万円。
翌日には即、購入を決め、貯金から自己資金250万円を入れ、不動産業者から紹介された金融機関で返済期間32年のローンを組んだ。
4500万円を超す借入金にも、一切ためらいはなかった。
ローンを抱える怖さより、「これでようやくスタートラインに立てたんだ! 」という興奮のほうがはるかに大きかった。
それは不動産投資で成長できると思っていたから。
そこからとんとん拍子で物件を増やし、7棟資産7億5000万円の大家さんになり、
年間家賃収入7000万円、フリーキャッシュフロー(手元に残るお金)年間2000万円を得ている凄腕ウーマンのテクニックを初公開!
【新刊】急成長企業の社長&不動産投資のプロが登場!『融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる!』10月4日発売!
株式会社幻冬舎メディアコンサルティング(本社:東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目9番7号、代表取締役:久保田貴幸)は、新刊「融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる! 」(著者:穴澤 勇人)を10月4日に発売いたしました。

『融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる! 』詳細
融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる! | 話題の本ドットコム : https://wadainohon.com/books/978-4344931237/
書籍内容
画像 : https://newscast.jp/attachments/GNNXhNHkyd32CkCTl4SQ.jpg
減価償却を活用して現金資産を最大化!
不動産投資のプロが教える、「物件を買い続ける」方法
資産形成の手段として「不動産投資」を検討する人が増えていますが、
不動産投資を取り巻く環境は2~3年ほど前から大きく変わっています。
金融機関のスタンスが厳しくなり、個人投資家の間からは
「もはや買い進めることは不可能」といった悲鳴が聞こえてきています。
それでは、不動産投資で資産を築くのはもはや不可能なのかというと、
けっしてそうではありません。
現状でもなお、融資上限を気にすることなく、
物件を買い進めることのできる方法があります。
(「はじめに」より一部抜粋)
不動産投資で資産を拡大するためには、まずどの程度リスクを取り、
どれだけのリターンを得るかといった目標を設定したうえで、
どのような物件を購入するか決定することが重要です。
そして減価償却や税制を理解し、
安定したキャッシュフローで資産規模が拡大するサイクルを確立すれば、
現金資産を最大化して「現金でアパートを買い続ける」ことも可能になるのです。
著者は20代から投資に取り組むことで資産形成を行い、
資産運用会社で売買責任者として年間200棟・100億円超の取引に携わった経験を生かして、
個人投資家の資産運用をサポートする会社を創立しました。
本書では、急成長企業の社長として注目を集める著者が、
不動産投資の基礎知識から資産規模を効率よく拡大する方法、
賃貸トラブルの実例と解決策に至るまで徹底解説します。
目次
巻頭カラー 「中古1棟」再生事例集
Case1 築40年以上の旧耐震RCマンションを3000万円かけてリフォーム
想定利回り45%を実現
Case2 取得時の入居率は0% 先行募集により、リフォーム完了前に満室
Case3 屋根が大規模に損壊した物件(台風・落雷)
Case4 下水トラブルが発生した現場
Case5 孤独死が発生した現場
Case6 ごみが散乱する集積場の改善例
はじめに
序章 不動産投資に本気で取り組む人が、初めに知っておくべきこと
日本の教育では投資と税の本当に大事なことは教えてくれない
どこまで「経済的に自由」になりたいのか?
小遣い稼ぎではなく「不動産賃貸業者」として規模拡大を目指す
これまでの不動産投資に潜んでいたたくさんの落とし穴
これから区分ワンルームに訪れる悲劇とは
不動産投資では物件購入の順番を間違えるな
規模拡大が最速で進むのは「中古1棟アパート」
物件のキャッシュフロー+節税効果での所得税還付+本業からの貯金
不動産投資は時間の勝負、「楽待」「健美家」物件で十分に勝てる
最終ゴールは「毎年現金でアパートを購入できる」状態
序章のまとめ
第1章 常識にとらわれた不動産投資では、
資産規模拡大はあっという間に止まる
資産形成は山登りと一緒
始める前に「目標設定」しましたか?
区分ワンルームは節税しているふうで節税になっていない
サラリーマン属性一本足打法では融資上限になったら終わり
1法人1物件スキームによる拡大はもうできない
「融資が出るからとりあえず買った」あとに待ち受けているもの
「利回り星人」の10年後
「最終的な手残り」と「資産性」のバランスが規模拡大の肝
第1章のまとめ
第2章 不動産投資でまず必要なのは
「最低1000万円の余裕資金」と「減価償却の知識」
物件が買えない人、財を成せない人の共通点
年間いくら手元に現金を貯められるのか
手元に現金は残っているのに帳簿は赤字?
収益不動産における減価償却の基礎知識
これまで納めてきた所得税の額、把握していますか?
損益通算による「所得税の還付」の具体例
貯めた資金をキャッシュマシーンに変換する
多くのリスクはキャッシュがあれば対応可能
投資初期の基本戦略は「5年以内にまた買い増せる状態」に
第2章のまとめ
第3章 「キャッシュは王様」
減価償却を理解して現金を最大化する
新築区分ワンルーム、中古1棟木造アパート……収益不動産のタイプ別比較
節税効果の具体例と「変動と固定の両輪」
新築アパート利用時との比較
物件選びで勘違いしてほしくないこと
不動産投資におけるお金の流れ
中古1棟木造アパートにおける段階別収支とトータル収支
最終収支を読み解く
早めにリスクを取れば、その分リターンも得やすい
第3章のまとめ
第4章 金融機関と上手に付き合いながら、
年収に応じて資産規模を着実に拡大する
自分は今どこにいるのかを認識する
ロードマップ1【年収700万~1000万円編】
ロードマップ2【年収1000万~3000万円編】
ロードマップ3【年収3000万円以上編】
「毎月10万円の収入があればいい」という方へ
第4章のまとめ
第5章 融資の限界突破!!
「物件を買い続ける」効率良い方法
融資の限界突破の秘策は「共同担保の提供」
「売ってもいい、もっていてもいい」が理想の物件
毎月100万円の手残り収入ができたら、切り売りスタート
キレイな物件をもつのは資産形成が終わってから
売却時(出口戦略)が不安な方へ
第5章のまとめ
第6章 不動産投資は住む人の生活を預かる「事業」
管理をおろそかにしては資産拡大は実現できない
大家業とは「そこに住む人々の生活を預かること」
事業者としてやるべきこと、やってはいけないこと
必ず想定しなくてはいけない「リスク」とは
重大リスクについての考え方
第6章のまとめ
第7章 実例に学ぶ
賃貸トラブルとその対応
トラブルの実態を知る
管理会社に電話をかけてくる人々
保証会社から連絡があるケース
入居者から連絡があるケース
近隣から連絡があるケース
不動産所得は実は不労所得ではないかもしれない
管理会社の悲哀
結局どんな会社に管理を任せるのが一番なのか
第7章のまとめ
おわりに
書籍概要
書籍名 :融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる!
著者:穴澤 勇人
価格:1650円(税込)
体裁 :150ページ
ISBN-10:4344931238
出版社 :幻冬舎メディアコンサルティング
URL:https://wadainohon.com/books/978-4344931237/
融資上限は怖くない! 税制と収益不動産をフル活用した資産形成アパートを「毎年」「現金」で買えるようになる! | 話題の本ドットコム : https://wadainohon.com/books/978-4344931237/
著者プロフィール
■ 穴澤 勇人/アナザワ ハヤト
1987年11月30日生まれ。神奈川県平塚市出身。宅地建物取引士。
神奈川県立平塚工科高等学校卒業後、田中貴金属工業株式会社に勤務。
会社員のかたわら、自ら株式投資・FX・不動産投資などさまざまな投資に取り組み、
個人・法人で20代から資産形成を行う。
その後、武蔵コーポレーション株式会社にて売買責任者を務め、
年間200棟・100億円超の収益用不動産(1棟アパート・マンション)の取引に従事。
2018年8月、コスモバンク株式会社を神奈川県横浜市で創業。
主に収益用不動産の売買・管理業を営み、
第2期(2019年8月1日~2020年7月31日)の売上高は約19億円、第3期売上高は約23億円。
急成長企業として注目を集める。
中長期経営目標として上場、将来的には宇宙開発・3Dプリンターによる住宅建築等、
さまざまな事業に取り組む予定を掲げている。
YouTubeチャンネル「穴澤勇人のMIQTV」を2020年12月開設、動画配信中。
不動産投資に限らず、投資全般の話題について触れ、
現代日本の教育システムではなかなか教えてくれない金融リテラシーが身につけられる
動画を配信している。
会社概要
商号 : 株式会社 幻冬舎メディアコンサルティング
代表者 : 代表取締役 久保田貴幸
所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-9-7
設立 : 2005年6月27日
資本金:42,250千円
事業内容 : 出版を通じた企業のブランディング支援・コンサルティング業務
URL :https://www.gentosha-mc.com/
本記事に関する問い合わせはこちら
株式会社幻冬舎ウェブマ
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目9番7号
TEL:03-5413-0701
URL :https://www.gentosha-webma.com
E-Mail:info@gentosha-webma.com
▼学びは本からというあなたへ「話題の本.com」
話題の本.com(ドットコム) | 学びは本から!というあなたへ。 : https://wadainohon.com
早期リタイアした東大博士が教える「不動産投資」に向いている人の特徴
向いている性質(1)
不動産が好きなこと
性格や性質という面からも不動産投資(不動産経営)の向き不向きがあります。
何をおいての大前提は、不動産が好きなことです。
これは断言できます。好きでないとやっていられませんし、好きならばたいていの困難は乗り越えられます。
向いている性質(2)
慎重さと決断力と行動力
不動産経営では扱う金額が大きく、気をつけなければならないことがたくさんあります。つまり、慎重すぎるくらい慎重なほうが向いています。石橋を叩いて渡るという言葉が当てはまります。
僕は、戦術的にも戦略的にも、短期的にはマイナス思考で、中長期的にはプラス思考を心がけています。不動産以外でもそうなので、そのような思考回路の人間といえばそれまでですが。ともかく、いろいろな事柄をできるだけ想定内になるように準備しておけば、とっさのときでも対応できます。
それでも想定外のことが起き、金額が大きかったりするのが不動産経営ですが、トラブル対処法を普段から考えておけば、その組み合わせで解決できます。一番怖いのはパニックになっておかしな判断をすることです。
他方で、慎重すぎて石橋を叩き割ってはいけません。好機ならばすぐ動く、物件情報が入ったらすぐ見に行く、人を紹介してもらったらすぐ連絡を取って会いに行くのは当然のことです。
不動産経営では一瞬の判断が必要な瞬間があります。要は、バランスです。
向いている性質(3)
人間力
不動産投資は不労所得で、収益物件を買ったらもう社会とかかわらなくていいと思われているフシがあります。しかし、不動産経営は人が相手なので、まさに「人間力」が重要です。
一般的に不動産投資と言いますが、「不動産経営」なのです。
言いたいことを伝えること、言われている意味を受け止め、裏の意味も読み取ること、不動産以外の話題で場を和ませることなどが必要です。こういう「幅」というものは、無理をして身につけようとするものではなく、普段から何げなく身についていくものです。コミュニケーションという意味では、話題の引き出しは多いに越したことはありません。
向いている性質(4)
客観性
物事を客観的に見ることが必要です。
自分が不動産屋だったら、どういう人に物件を紹介したいか、どういう大家の物件に入居者を斡旋したいか。金融機関だったら、どういう人にお金を貸したいか。入居者だったら、どういう物件に住みたいか。どういう大家、どういう管理会社ならば住み続けたいかなど、客観的に考える必要があります。
そのためには、それぞれの目線から不動産に関する情報も読んで頭に入れておき、自分の行動に活かしましょう。自分がこう考えて行動する、だから相手も同じように考えて行動するだろうし、そうするべきだという自分目線は、不動産経営に限らず、まったく通じません。
向いている性質(5)
粘り強さ、情熱、楽天的、自信
不動産経営は、物件を買うまでも、また、購入後の経営も、粘り強さが必要です。アパートを買おうとして訪ねて行った不動産屋で笑われたり、物件候補を持ち込んだ金融機関で門前払いを食らったりしたくらいでくじけていてはいけません。そこからが勝負です。
一度断られたくらいでへこむ人は、金融機関も、不動産屋も相手にしません。そんなことでは不動産経営はできないからです。これは情熱の表れです。
長期的には楽天的なことが重要です。マイナスの点も想定しつつ、「最終的にはきっとうまくいく」「自分は運がいい」と、漠然とでも思うことです。
何とかなるし何とかするという自信が必要です。そう思えるためにこそ、普段の勉強、想定外のことを想定内にする準備を続けることが必要です。
向いている性質(6)
誠実さ
不動産に限らず、あらゆることの基本は誠実さです。
不正をしないということだけではなく、たとえば時間を守る、連絡をする、書類を提出するなど、些細かもしれないことこそ誠実さの表れです。
社交辞令ではなく、本当にできることはできると言って実行する、できないことはできないとはっきり言うことも誠実さです。つまり、ある意味では「普通」に行動していれば「誠実」と評価されるということです。
向いている性質(7)
記憶力
記憶力は重要です。以前の経験を記憶しておけば次に活かすことにつながります。
日頃のやりとりでも、金融機関や不動産屋はけっこう忘れることがあるので、過去の経緯を記憶していると、行うべき事柄や、当初とは話が違ってきている点などが分かります。
また、かつて売りに出ていた物件が再度売りに出た場合に、前はいつ頃、どの不動産屋からいくらで出ていたかを覚えていると、高値づかみをしないで済みます。
記憶力に自信がないなら当然ですが、記憶力がよくても、重要と思われる事項は記録しておくことが必要です。実際、僕も細かに記録し、時折復習します。
向いている性質(8)
計画性
不動産経営は、短期・中期・長期の計画が必要です。
たとえば、入ってきたお金をぱっと使う人には向いていません。普段からお金や資産の管理はもちろん、購入や日常業務、売却、申告など、すべてにおいて物事を計画立てて行う人が向いています。
リタイアを目指すなら、不動産投資は地方都市がいい
最近注目されている不動産投資。FIRE(経済的に自立して早期リタイアする)の手段として、多くのサラリーマンが関心を寄せている。しかし、人口減少経済の中で不動産投資の先行きに不安を感じている人も多い。不動産投資は、人口が集中する都心部でしか成り立たないのだろうか。『東大博士が書いた石橋を叩いてでも成功したい人のための「不動産投資」大全』の著者が、不動産投資を始めるのに向いているエリアについて解説する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock人口が多い都会での
不動産投資の特徴
どのような立地で不動産経営をすればいいでしょうか。都会と地方での違いを見ていきます。
都会の長所としては、何といっても人口が多く、賃貸の需要があることです。
都会の人はなかなか持ち家を持てない(持たない)ことは、不動産賃貸業の立場から見れば有利です。車所有が少ないので、物件の駐車場が不足していても問題がないことも有利でしょう。
都市銀行・メガバンクも含めて金融機関が多数存在し、売りに出る収益物件も多く、また、買い手が多いため売却もしやすいことになります。また、不動産屋、リフォーム業者などが多くあることも有利です。各種セミナーやコンサルタントも多く、大家の交流も活発です。
他方で、都会は土地が高く、建物価格も高く、利回りは低くなってしまいます。諸経費も、たとえば固定資産税(都市計画税)は高いです。
また、人口が多く賃貸の需要があるとはいえ、物件数も多いので、賃貸需要と供給を割り算すれば、人口比では地方都市とあまり変わらないことも考えられます。さらに、競争が激しく、入居時に大家が不動産屋に支払う(支払わざるをえない)広告料(要はお礼のようなもの)が高騰している地域もあります。
リタイアをしたい人は
投資効率を考えるべき
リタイアを目指すには、家賃収入の額自体が多いこと、さらに、手残り額を多くすることが必要で、そのためには利回りが高く、諸経費が少なくなければなりません。そこで、ターゲットとなりうるのは地方都市です。
人口は都会より少なくとも、物件数も都会より少ないので、割り算すれば賃貸需要と供給はある程度釣り合っています。建物価格は都会と変わらないと仮定しても、土地が安いので物件価格は都会より安いです。家賃は安いですが、都会と比べた場合の物件価格の低下ほどには家賃は低下しません。
たとえば物件価格が都会の3分の1だからといって、家賃が3分の1にはなりません。あくまで一般的な傾向ですが、地方の物件は、都会の物件より(1)価格そのものが安く、(2)利回りが高い物件があり、(3)固定資産税などは安いので、(4)手残り額が多くなりうるということになります。
つまり、地方において、利回りが高く、ある程度の規模の物件を買い進めることが、リタイアを目指す有力な選択肢になります。絶対的な借入額(返済額)を抑えながら早期リタイアするには、地方物件を中心に購入するほうが有利です。
忘れてはいけない
地方でのデメリット
もちろん、地方での不動産経営には、都会での長所と裏返しの短所があります。
地方は、持ち家率が高いです。分譲マンションは数が少ないのですが、土地が安くて広いので、20歳代で中古戸建のみならず新築建売の購入、さらに注文住宅を建てる人もいます。昨今の賃金の低迷で住宅ローンが組めないと思うかもしれませんが、地方の金融機関では、かなり低い年収でもサラリーマンなら住宅ローンを借りることが可能です。
相続や親からの金銭的援助、親のお金による二世帯住宅の建築も都会より非常に多いです。もちろん親との同居も多いです。そのため、賃貸需要が都会より少ないという短所があります。
また、駐車場が必須です。地方は中心都市でも車がないと仕事も生活もできません。1世帯に1台は当然で、普通は夫婦ともそれぞれ持っています。つまり、戸数×1、できれば1.5~2倍の台数分の駐車場を、敷地内または近隣に借りて確保する必要があり、その分コストがかかります。
金融機関が少なく、不動産屋も少ないので選択の幅がありません。また、売りに出る物件も少なく、逆に売ろうとしても買い手が少ないという短所もあります。そもそも世間が狭くて、いろいろやりにくいこともあります。
どのくらいの地方都市がいいのか
日本国全体の人口が減っているのは、個人の力ではどうしようもありません。
地方のほとんどの自治体で人口が減少・流出しています。流出数と流入数の差による人口の「社会増減」を見ると、東京などが増、地方はほぼ減になります。なお、東京の出生率(人口の自然増減にかかわる)は全国最低ですが、あまり報道されていません。
では、地方のどんな地域で不動産経営をすればいいのでしょうか。
地方都市でもエリアを選ばなければなりません。具体的に、まず、人口50万人を超えてくると、都会と似た状況になってきます。50万~100万都市はケース・バイ・ケースで、その地域在住・出身ならば対象になりえます。
他方で、人口が少なすぎると、ほとんどの人は持ち家になるので、そもそも賃貸需要がありません。つまり、ある程度の人口、そして、ある程度の入れ替わりが必要です。転勤族は社宅がなければ賃貸に住みますし、会社が社宅として借りることもあります。
僕は、人口の下限の一応の目安として、人口10万人の地方中心都市としています。
注意しなければならないのは、地方中心都市、また、大都市でも、周辺の市町村を合併した場合があります。たとえば旧○○町部分だと、人口密度も低く、インフラも、人口の入れ替わりも違います。
地元なら分かりますが、県外だとピンときません。
また、地方から都会に人が出て行くように、県内の小さな市町村(地方の地方)から、その地方の中心都市に人は集まってきています。周辺部の高齢化が進めば、買い物や通勤通学、さらに通院などに便利な地方の中心都市に移住してきます。
政府の方針として、商業地、医療施設、行政サービスを一定範囲に集め効率化を図る「コンパクトシティ」を整備する流れになってきており、それぞれの地方・県の中心都市が想定されています。
そのほか、家庭の事情で都会から地元に戻る場合も、元々の出身地よりは便利なその地方の中心都市に戻ることが多いです。
つまり、地方中心都市ではまだまだ賃貸の需要があります。東京一極集中と言われますが、他方で、都会から、また、地方の地方から、それぞれの地方中心都市への移住の流れもあります。
不動産投資で失敗したくなければ、何年以内の売却を意識すべき?
「12年以内」の売却を意識していくと良い

自分の目指す姿として「2000万円物件の隔年購入」と「5件の物件取得」をルール化しようと考えた…と紹介しました。
つまり、2000万円程度の物件5戸を隔年で購入しながら、資産の洗い替えの意味合いで10年ちょっとの保有期間で随時売っていくという当初計画です。
この「10年保有」の設定には、もう一つの理由があります。
一般的なマンション(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造)は47年が償却期間となっていて、その期間までは35年ローンを組むことが可能です。ということは、新築のマンションを買って「12年以内」に売却すれば、次に買った人は35年ローンをほぼ間違いなく組めることになるわけです。
そのため私は、物件を購入した際には12年以内に売却するよう意識していくことを、自身のルールの一つに加えました。つまり、「次の人が買いやすいように売る」ことを意識しようと考えたのです。
次に買う人のことまで考えて、物件を売る時期を決める必要があるのか? 読んだ方はそう思うかもしれませんね。けれども、次の人が買いやすい、というのはイコール、扱う不動産業者が「売りやすい」ということです。
そこに紐づくのが、私が心がけてきた不動産投資のポリシーなのです。つまり、「自分が不動産業者にとって、有益な存在であり続けること」。不動産の営業マンが喜ぶ提案をすれば、ひいてはそれが自分に跳ね返ってきます。自分が営業マンに優良な新築物件を紹介してもらえる源泉になるわけです。
こうやって不動産の営業マンとWIN―WINの関係を作るのが、失敗しない不動産投資の秘訣であり、成功するために必要な、いたってシンプルな考え方だと言えるのです。
その意味では、あなたが不動産サイトなどで物件を探すとき、見ているマーケットにおいて、新築から「12年落ち」の中古物件を検索するのも面白い手法の一つと言えるかもしれません。
たとえば、あなたが2000万円の新築物件を買おうと思っているマーケットで、12年落ちの物件の価格が1800万円で出ているとしましょう。そして、12年が経った後のあなたの残債予定が1600万円であるとしたら、200万円ほどが利ザヤとして稼げる…という見通しの把握ができるわけです。
中古の物件情報を見るときには、新築のプレミアム物件を購入するための参考値としての見方をしていくのもまた、面白いと思います。
経済感覚に狂いが生じるような投資の成果は望まない
プレミアム・ワンルーム投資の成功ルールを説明するために、「アパート1棟買い」との違いについて説明してみましょう。
プレミアム・ワンルーム投資は、利回りを中心とした月次の収益性は薄くとも、プラスのキャッシュフローを層状に重ねていくイメージで、堅実性と確実性のある安定型の投資法です。複数の物件を持ちながら、売却対象案件やタイミングを適切に選択でき、定期預金を解約するかのごとく売却することで利益確定ができます。
いっぽうで、私が考える1棟買い物件の一番のデメリットは、売却によりキャッシュフローが一気に無くなってしまう点です。
ワンルームマンションを複数所有する投資方法であれば、10~12年ごとに売却を進めて、時機に応じてキャピタルゲインを得ながらインカムゲインを継続させることが可能です。ところが1棟買いの場合には、規模感が大きすぎて複数案件を同時に保有し続ける事が困難で、唯一の案件を売却すればその時点でキャッシュフローが一気に無くなるなど、不安定な推移をたどることになります。
キャッシュフローでも地点選定の観点からもAll or Nothing(オール オア ナッシング)で分散効果が効かず、売却すると月々のキャッシュフローがゼロになってしまう投資法は、やはりおすすめしません。
つねに5件か6件の物件を持っていれば、同時に数百万円もの定期預金を貯めていくイメージで、資産を持ち続けることができます。購入と売却のタイミングをうまく時間分散しながら、複数のワンルームマンションを持つ方法が堅実だと、私は思うのです。
これは不動産投資でよくあるケースなのですが、新築の物件を4~5戸買ったあと、次の投資先として、アパート1棟買いに移行するというパターンが見られます。
不動産投資のノウハウが何となく分かった気持ちになり、もう1ランク上の投資を実践してみたい…という欲が出る部分もあるでしょう。
たとえば、新築のアパート1棟は高価格で手がでなくても、中古であれば何とかなるのでは…と考えることがあるかもしれません。けれども、そこには往々にして落とし穴が待っているのです。
たとえば、5000万円クラスの中古物件のアパート1棟買いは失敗しやすい事例の一つで、とっつきやすさから中古物件のアパート1棟を買ったものの、投資した金額を家賃収入で回収することができず、結果的に損失のほうが大きくなってしまう…というケースがあり得ます。
さらに、損失を補おうと売却しようとしても、購入時よりもかなりの安値でしか売れないのが中古アパート物件の欠点です。「出口」についての戦略が描けず、売りたくても売れないという負のスパイラルに陥ってしまうことがある点で、注意が必要なのです。
ここで一つ、若干余談めいた話を付け加えましょう。
これは不動産の価値とは少し違う話ですが、アパート1棟を売却した際に大きなキャピタルゲインを得ることは、人間の心理として別のリスクを生む危険性があると、私は思います。
人間の行動や心理を一括りにはできませんが、本書の中心テーマが、サラリーマン属性の方にすすめたい堅実な不動産投資術であるのは確かなところです。
そうした属性のみなさんに、一度にドカンとキャピタルゲインのお金が入るような「成果」がもたらされることは、従来のライフスタイルを崩すことにもなりかねないのでは…? と懸念するわけです。
よく言うところの、宝くじが当たったことで不幸になる…といった、経済感覚の狂いが生じるような投資効果は歓迎しないというのが私の立ち位置です。
意図した月々のキャッシュフローを安定的に維持しつつ、一方で確実にお金が貯まっていく投資こそが目的なので、そこから大きく逸脱することは避けるべきでしょう。それも私が考える、失敗しない不動産投資のルールです。
パタヤ不動産投資のメリット・デメリットは?リスクや注意点も
1.パタヤの不動産に投資するメリット
パタヤの不動産投資は、タイが好きで購入した物件を自分でも使いたい人などに向いています。また、物件の売却先として日本人だけではなく外国人も候補に入る点が、パタヤの不動産に投資するメリットです。
1-1.リタイア後の移住先として適している
パタヤは、タイのビーチリゾートとして人気があり、ゴルフリゾートとしても有名です。赤道に近く年中温暖な気候を持っていることもあり、世界各国から人が集まっています。
また、タイは日本人からも移住先として人気が高く、日本人駐在員がタイでの生活を気に入った結果、リタイア後もタイに住みたいという希望からタイ不動産を購入するケースもあります。
パタヤはバンコクから車で約2時間の距離にあり、バンコクに住みながらパタヤの物件を別荘にすることも検討できます。アーリーリタイアを目指すまたは、リタイア後はリゾート地に移住したいなどの希望を持っている場合に、パタヤの不動産投資は有効と言えます。
1-2.自己利用も見据えた投資に有効
パタヤは移住だけではなく旅行先としても人気があるため、購入した物件の自己利用を考えている場合にも、パタヤの不動産投資を検討しやすいといえるでしょう。
東南アジアには、タイ以外にもフィリピンのセブ島やマレーシアのペナンなど、ビーチリゾートとして有名なエリアが複数あります。なかでもパタヤは海外からの旅行者が多く、にぎわっている点が特徴的です。
市街地の中心部に位置している物件は静かな環境を好む人には向いていない一方で、都会的なリゾートを好む方にとっては適した選択肢となります。なお、地元住民よりも海外からの移住者などを入居者のターゲットにしたい場合、できる限り都心に近く利便性の高いエリアを選ぶことも重要な視点となってきます。
1-3.物件の売却先として外国人投資家も候補に入る
パタヤは外国人からの人気が高いエリアなので、不動産投資の出口で物件を売却するにあたっては、外国人投資家も売却先の候補に入ります。
日本人投資家が海外不動産投資をする場合は、日本に拠点を置く不動産会社を通じて物件購入するケースも多くなります。このような背景から、他のエリアでは投資の出口として主に日本人同士での転売を想定することになります。
一方でパタヤは日本人以外の外国人からも人気を集めている背景により、外国人投資家や移住者なども物件の売却先として有効と言えます。
新興国での海外不動産投資では不動産市場の変化が大きいことから、出口戦略も不透明になりがちです。あらかじめ選択肢を多めに持っておける点で、パタヤの不動産投資にはメリットがあります。
2.パタヤの不動産投資で要注意のリスクやデメリット
パタヤの不動産投資で注意すべきポイントとして、物件を購入するだけでは短期賃貸ができない点や、外国人の入居者を探す難易度は高い点などが挙げられます。
2-1.タイでは無資格での短期賃貸が違法とされている
パタヤは有名なリゾートエリアなので、物件のホテル運用が上手くいけば大きな利益も見込めます。
しかし、タイでは無資格者による30日以下の短期賃貸が法律で禁止されている点に要注意です。
例えば、2021年9月時点、フィリピンでは民泊に関する法律がないためAirbnbなどを活用したホテル運用も海外不動産投資の選択肢の1つになります。このような選択肢が取れないことは、パタヤ不動産投資の大きなデメリットと言えるでしょう。
そのほか、パタヤにはホテルも多いため、仮に宿泊運用が問題ないとしてもホテルとの競争に勝つ戦略が必要になってきます。パタヤ不動産投資では、不動産会社から情報収集を行って入居者のターゲットを明確にしつつ、入居者のニーズに適した物件を選ぶことが重要になります。
【関連記事】セブ島で不動産投資、メリット・デメリットは?
2-2.空室期間が長引くリスクもある
パタヤの周辺にはタイの首都バンコクを始めとして、フィリピンやシンガポールなど外国人による人気の高いエリアが多いものです。ショートステイを繰り返しながら各国を渡り歩く人も多いため、パタヤで年単位の賃貸借契約を希望するような外国人を見つけるのは難しいと言えます。
また、パタヤではバンコクほど産業が発展しているわけではなく、地元住民の所得はそれほど高くありません。パタヤで投資用物件として販売されている物件に入居できる地元住民は少ないのが実態です。
このような背景があることから、パタヤの不動産投資は純粋な不動産投資による利益を狙っている人よりも、自己利用を物件購入の目的とする人に向いていると言えます。
2-3.日本の不動産と比較すると施工が粗末な物件も
タイでは外国人による土地の所有が禁止されているため、パタヤで不動産投資をする場合も、投資対象は集合住宅であるコンドミニアムになります。
タイを含む東南アジアでは、プレビルドと呼ばれる完成前のコンドミニアムが投資用物件として販売されていることも多いものです。パタヤを含むタイの不動産投資では、仕上がりを確認してから物件を購入できるケースが少なくなります。
プレビルドの物件が完成した結果、仕上がりが良くないために賃貸できないといった失敗例も見られます。また、パタヤは海に近いエリアなので、潮風の影響により物件が劣化するスピードが通常よりも早い点に注意が必要です。
そのほか、プレビルドの物件が完成せずに引渡しを受けられない竣工リスクにも要注意です。プレビルドの物件では建設工事が途中で中断されてしまうリスクがあり、工事が中断されてしまうと物件の引渡しを受けられないほか、支払い済の資金が返金されないケースもあります。
物件の仕上がりにまつわるリスクや竣工リスクを軽減するためには、タイ国内または海外で大手のデベロッパーが分譲している物件への投資を検討することが重要となります。
まとめ
パタヤの不動産投資のメリット・デメリットを比較してみると、パタヤ不動産へ投資するのであれば、最終的に物件の自己利用を重視したい人に向いていると言えるでしょう。
家賃収入による長期継続的な利益を狙っていきたい人にとっては、入居者を見つける難易度が高い点などを鑑みてもハイリスクな投資先であると考えられます。
そのほか、パタヤの不動産投資では、竣工リスクを軽減するために物件の売主であるデベロッパーについて、会社規模や分譲実績などを事前に確認することが重要です。パタヤ不動産を購入する際はこれらのメリット・デメリットやリスクを確認し、慎重に投資判断をしてみましょう。
東大博士が解説する「不動産投資」9つの特徴
最近注目されている不動産投資。FIRE(経済的に自立して早期リタイアする)の手段としても、多くのサラリーマンが関心を寄せている。ただし、株式投資や投資信託などに比べると、なじみがないのも事実だ。そこで、『東大博士が書いた 石橋を叩いてでも成功したい人のための「不動産投資」大全』を上梓した菅原吉祥氏に、不動産投資の特徴をうかがった。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock特徴(1)
不動産収入は「キャピタルゲイン」と「インカムゲイン」
不動産の売買で利益が得られることがあります。とくにバブルの頃は、不動産価格が右肩上がりで、普通に買って売るだけで利益が得られました。つまり、不動産投資は「キャピタルゲイン重視」だった時代があります。
この頃は、不動産価格が高く、さらに金融機関は元々資産を持っている人や会社に購入資金を高金利で融資していたため、サラリーマンが新規に参入することは困難でした。転売するたびに価格が上がりましたが、最後にバブルがはじけ、価格が急落し、売るに売れない不動産が世の中に溢れました。
一概には言えませんが、キャピタルゲイン重視の投資はリスクが高く、価格の暴落も考えなければなりません。
他方で、不動産では家賃収入がインカムゲインです。バブル崩壊後、不動産価格は下がりましたが、賃貸用(とくに居住用)の不動産の家賃は、不動産価格の下がり方ほどには下がりませんでした。つまり、不動産価格は下落し、家賃はそれほど下落しなかったので、不動産賃貸による家賃収入、つまりインカムゲインが注目されるようになりました。
不動産の価格が下がり、家賃はそれほど下がらなければ、不動産価格に対する家賃収入の割合(「利回り」と言います)は上昇するわけです。また、金利も下がったので、金融機関から融資を受けて賃貸用物件を購入する際の借入金利よりも、利回りのほうが高くなり(これを「イールドギャップ」と言います。運用利回りと借入金利の差のことです)、融資を受けて物件を購入し、家賃を得るというインカムゲイン狙いの不動産投資が成立するようになりました。
市場では、物件価格に対する利回りが年10%の物件は、探せば普通にあります。他方で借入金利は年2%として、「運用利回り-借入金利」(イールドギャップ)はプラス8%となります。
つまり、バブルの頃には不動産投資に手が出せなかったサラリーマンも、金融機関から低金利で融資を受け、不動産を購入し、家賃収入(インカムゲイン)を得られるようになりました。また、サラリーマンは金融機関に対して信用があるので、長期間の融資を受けやすいという長所があります。
さらに、売る際にうまく売れば、買ったときより高く売れることもあるので、キャピタルゲインも得られます。ただ、やはり基本は長期保持によるインカムゲイン狙いとなります。不動産は、継続的に家賃収入があるということで「ストックビジネス」の典型とされます。なお、継続性がないビジネスを「フロービジネス」と言います。
不動産投資は、時間がたつほどに収入が蓄積され、金融機関への返済が進んで借入金の元金が減る(つまり資産部分が増える)という意味で、「時間を味方にする投資」と言えます。時間は誰にでも平等なので、この「時間」を資産を生み出すために活かすことで、大きな資産を築くことが可能です。
特徴(2)
実物であること
不動産は実物そのものが資産で、かつ、収益を生み出すものなので、まず、インフレに強いです。インフレ時には現金・預貯金の価値は目減りしますが、不動産は実物資産であり売却時の物価相当の価格になるので、その価値はそれほど目減りしません。
実際は、日本は長くデフレですが、デフレでも家賃はそれほど下がらず一定の収益を生み出しています。つまり、インフレ、デフレにかかわらず、危機の時代は実物資産が好まれます。実物資産の中でも不動産は家賃収入を生み出すという点で、金やプラチナといったほかの実物資産と違います。さらに、土地・建物の価値が完全にゼロになることがないことも不動産の長所です。
特徴(3)
この世に一つだけのもの
不動産は、みな、この世に一つしかありません。いわゆる区分マンションも、別の場所にあれば立地が違いますし、同じ建物でも部屋が違えば別物です。これを「特定物」と言います。
特定物とは、取引の目的物として当事者がそのものの個性に着目した物で、そうではない「不特定物」と民法などで区別されて扱いが異なります。不動産は新築でも土地のみでも、この世に一つしかないという、まさに特定物の典型です。動産も、たとえば中古車だと特定物になります。
特徴(4)
金額が大きい
投資対象とする不動産の種類にもよりますが、少なくとも数百万円以上のお金が動きます。価格変動そのものは少ないのですが、金額自体が大きいため、資産も利益も大きくなる一方で、損失も大きくなる可能性があります。
特徴(5)
時間的拘束は比較的少ない
物件を買うまで、さらに買った後もそれなりに時間がかかりますが、少なくとも不動産のことを1日中考える必要はありません。
それぞれのプロにお任せし、自分がやるのは、判断を下す・指示をする、たまに書類を集めたり記入したりすることが中心になります。物件の管理や入居者募集、修繕・リフォームなどを自分でどこまでやるかによっても違いますが、株やFXに比べれば時間は自由になります。
不動産そのものが収入を生み出す資産です。つまり、不動産経営は「仕組み」をつくってしまえば、時間はそれほど取られないということです。だからこそサラリーマンの副業に向いていますし、セミリタイアした後も文字通り「リタイア」に近い状態になることが可能です。
特徴(6)
簡単に売買ができるわけではない
不動産は、株やFXに比べ、「流動性が低い」「換金性が低い」と表現されます。
株やFXは価格を気にしなければ瞬時に売買できます。不動産は、買うのも大変なうえに、すぐに売ることも困難です。そもそも買い手がつかなければダメですし、また、金融機関から融資を受けて返済中の場合、価格を下げすぎると、売却してもまだ借金が残ってしまいます。
他方で、買う際・売る際は、不動産屋がプロの立場から見解を述べてくれます。そのためにも、有能で信用できる不動産屋が必要です。さらに、金融機関や税理士、司法書士といった専門家も検討に加わってくれます。個別の物件、個々の取引相手という点で、株やFXの一般的な情報・分析とは異なります。
急な出費などに対応する現金(預貯金)を別に確保しておくことで「換金性の低さ」には対応できます。
特徴(7)
金融機関からの資金調達が可能
不動産投資の最大の特徴は、資金を金融機関から調達できるということです。つまり、融資を受けて物件を購入することが可能です。
「株を買いたいのでお金を貸してください」と金融機関に言っても相手にしてくれません。しかし、収益物件を買う際には融資を受けられます。
その理由は、買おうとする不動産自体に価値があること(担保価値)、また、そこから十分な収益が見込めること(収益性)で「事業」として成立するからです。
金融機関の融資を受けることで、大きな資産を築くことが可能になります。これが不動産投資における「レバレッジ」です。
たとえば自己資金1000万円で1億円の物件を購入(9000万円借り入れ)すると、レバレッジは10倍となります。自己資金ゼロで買うことができればレバレッジは無限大となります。自己資金ゼロで買い進めることができれば「無」から大きな資産を築くことも可能なのです。
この場合、借金といっても、お金(資産)を生み出すための借金です。そもそも、金融機関から借金できるということは「信用」の表れで、むしろプラスのことなのです。融資を受ける場合、原則として、団体信用生命保険(団信)に入るので、生命保険代わりになる点も不動産投資の長所です。
特徴(8)
「人」が相手
不動産は、ほかの投資に比べて「人」(人の集まりである会社・組織も含む)が相手という特徴があります。
物件探しはインターネットで済ますとしても、買う場合は不動産屋を通します(売主・買主との直接の売買はお勧めしません)。融資を受けるなら金融機関が相手になります。購入後に管理を任せるなら不動産屋、自分で管理(自主管理)するにしても、入居者募集などの業務はやはり不動産屋が相手になります。
つまり、不動産経営では、購入においては金融機関と不動産屋、購入後は不動産屋が極めて重要です。物件そのものがよくても、金融機関や不動産屋という「会社・組織」、そこにいる「人」の部分で成功も失敗も決まります。
税についても、規模が拡大していくと税理士が不可欠です。もちろん各種法律や制度については司法書士や弁護士といった専門家の手を借りることもあります。
そもそも、家賃収入は、入居者、つまり他人からの収入です。入居者は家賃を払っていただく大事なお客様ですが、要望・クレームも言ってきますし、滞納・夜逃げもありえます。その対応や処理も、また不動産屋や法律の専門家といった「人」に相談したり依頼したりします。
僕の個人的な見解ですが、最後に人を動かすのは、計算や理屈ではなく「情」です。この「人」相手というのは、いい意味でも悪い意味でも、不動産投資(不動産経営)の大きな特徴ですので、とくに述べておきます。
特徴(9)
定型化されている
不動産投資(不動産経営)は、物件購入、融資、日常業務などが定型化されています。成功した人のやり方を完全に再現することはできませんが、ある程度の「型」はあります。
つまり、いったん覚えて慣れてくれば、あとは知識を加える・更新していくことで対応できます。
お金を生み出すシステムをつくることが不動産投資(不動産経営)の中心です。金融機関から融資を受けて物件を購入し、入居者の家賃で返済して資産を増やし、その物件を維持・拡大することが仕事です。
二度失敗を経て福岡での不動産投資で大成功…『投資のドン』に教わった「医師」という肩書きを活かした投資法とは?
注目が集まる医師の不動産投資
東京都中央区のとあるタワーマンション。
大理石で敷き詰められた広いロビーには、シンプルながらもセンスの良いソファーやテーブルが配置され、引きたてのコーヒーが味わえるカフェも併設されている。ここを待ち合わせ場所に指定され、手持ち無沙汰に待っていると、エレベーターホールから医師の松田孝樹さん(仮名)が現れた。
松田さんは現在、この都内のマンションとは別に、東京に1件、福岡に2件、青森に2件不動産を持っている。いわゆる「不動産投資家医師」だ。
今回は、「医師の不動産投資」が最近注目されている中で、松田さんがタワマン投資を始めた経緯と実情をインタビューさせていただいた。
給与格差に悩む公立病院医師の自分
松田さんが勤務するのは、都内の公立病院。
新卒で採用されてからずっとそこで勤務医として働いている。
「若手の頃といったら、まあ多忙でしたね(笑)。忙しすぎてもうほとんど覚えていません。がむしゃらに働いていたら、いつのまにか中堅になっていましたよ」
日々忙殺され、あっという間に中堅医師となったと話す松田さん。
ふと立ち止まると、周りとの差を感じたという。
「公立病院は他の病院―――例えば民間病院で働く医師や開業医と比べて給料が低く、時間外手当などの恩恵も受けづらい。民間病院で働く大学の同期との給料が思ったよりも違うことに驚いて、その時初めて焦りを感じました」
1500万円の年収と半分近くとられる税金
中堅医師になって以降も、電子カルテ導入などの影響で雑務が減ることはなかった。結局、忙しさは変わらず、だんだんと給料が見合っていないと感じ始めたのだそう。
また、当時の年収は1500万程度だったが、あまりの税金の高さに頭を抱えることが増えたと話す。
「子どもが2人いまして。当時まだ娘も息子も幼稚園でしたけど、このまま多忙な日々が続く上に、税金は吸い取られて貯金も増えなかったら……。子どもたちの進学費用なども満足に出せないかもしれないと不安になりました。私立の医学部に行かせるとなると、やはりかなりの資金が必要ですからね」
人生で初めて向き合った株式投資
現状を変えなくてはと思い悩んでいた松田さんに契機が訪れたのはそんな最中のことだった。
病院の食堂で昼食休憩を取っていた時、周りの医師が話している会話が聞こえたという。
「投資の話でした。彼らは私より5個くらい年下でしたけど、同じく給料に不満を持っていて、行き先が不安だから株式投資を始めたのだという話でした。こんな若い彼らでもちゃんと考えて行動していたのだと少し驚くとともに、『これだ!』と思いすぐに飛びつきました(笑)」
「昔から思い立ったら早いんです」そう話す松田さんは、その週末のうちに株式投資のセミナーに参加、すぐに株式投資を始めたという。
元々勉強は好きだったという松田さん。
株式投資についても勉強を重ね、動きに合わせて着実に運用できれば、早期的に利益獲得が可能と知り、うまく運用できそうだと安心していた。
「始める前に気付くべきだった…」株式投資失敗の理由
しかし―――
「思ったようにいかなかったですね。というより時間がなかった。知識はついたしやり方も理解できたので、時間さえあればうまく運用できたと思います。ただ、流動性の高い株式投資は、株の動向をずっと注視している必要がある。ただでさえ多忙な私のライフスタイルには全く向いていませんでしたね。やり始める前に気付くべきでした」
意気込んで株式投資を始めたものの、うまくいかず、結局ふりだしに戻ってしまったという。
しかし、投資への可能性を感じていた松田さんは他の方法を探し始めた。
「株では失敗しましたけど、勉強した際に投資には色んなやり方があることを知りました。だから、今度は自分のライフスタイルと投資スタイルを見比べて、どの方法なら成功できるか考えました。結果、不動産投資に行きついたわけです」
友人が語った「不動産投資のリスクが高い理由」
不動産投資を始めようと考えた松田さんは、大学の同期の投資好きの医師仲間に相談を持ち掛けたのだとか。
しかし、松田さんから不動産という言葉を聞いた途端、その友人は「やめとけ」とひとこと言ったそう。
「『リスクが大きい』彼はそう言ったんです。彼は株式で成功していました。父親が開業した医院で働いていたので、時間があったんですよね。確かに彼なら不動産より株式の方が向いているのかもと思いましたよ。でも、私が納得できなかったのは、彼の言った理由。特に具体的なデータは示さずにただ、『リスクが大きい』という言葉を繰り返していたんです」
松田さんの友人のように、不動産投資について「リスクが大きい」と敬遠する人は多い。
確かに動かす金額が大きい不動産投資では、当然リスクも伴う。
しかし、そこには「医師」ならではのメリットも存在することを忘れてはいけないと松田さんは語る。
融資額が年収の25倍?医師だからこそのメリット
「調べる限り、医師は融資の面でかなり優遇されると知っていました。通常、融資額は年収の10倍程度ですが、当時、医師なら25倍前後で融資してくれることもありました。年収も1000万以上とある程度あれば、低金利で融資してもらえることが多かったので、かなりメリットは高いと考えていました」
結局、友人の意見でなく自分の調べたことを信じ、不動産投資を開始することにしたそう。
これが松田さんの運命を大きく左右することになる。
「まずは、東京の駅近のワンルームマンションを所有することに決めました。築年数は立っていましたが、立地の条件も手伝って、入居者はすぐに決まりました。味を占めて次はファミリー向けのマンションを…、と思いましたが、都内だとかなり高額になります。株で一度失敗しているので、どこか不安で。結局東京ではなく、札幌でファミリー向けマンションを所有することにしました。札幌にした決め手は、観光地でもあり、程よい人気があること。これは空室を避けるためですね。もう一つは、物件がほぼ新築であるにもかかわらず安かったこと、この2点です。銀行からの融資額も想定よりだいぶ多かったですし、今度こそうまくいく気がしていました」
「入居者は決まらない」「家賃はたったの6万円」
「次こそ…!」と意気込んだ松田さん。
入居者が決まるのが待ち遠しくて、何度も不動産会社に連絡したのだとか。
「でも、入居者は数か月たっても決まらなかった。春でしたし、新社会人とか転勤族の会社員と帯同家族の入居が間違いなくあると予測していたんですけどね…大きな穴を見落としていたんです」
その大きな落とし穴とは、札幌の特性にあったのだという。
札幌は確かに人気地だ。
しかしその分、そこに狙いをつけて、その地で不動産投資を始める人も多い。
その結果、需要と供給のバランスがだんだん崩れ始め、今では供給過多、つまり不動産が余るという状況に陥っているのだそう。
「結局、入居者が決まったのは半年後。しかも、家賃は共益費などすべての費用込みで6万ぽっきり。考えられないほどの破格でやっと『住んでもらっている』という感じです(笑)」
そう笑って話すが、当時は手に汗握る状況だったという。
初めての不動産投資での予想外の失敗。しかも株式に続いて2度目の失敗だ。
もう投資はやめた方がいいのかもしれない。
そう思ったのだとか―――
「でも、正直そこでやめるわけにはいかなかった。娘や息子の教育費のために貯めていたお金を投資に使って、結局ダメでしたなんて、許されるはずがないじゃないですか。次が最後と妻とも約束して、最後の投資を始めました」
松田さんにとってのラストチャンス。
それは意外な形で幕を開けた。
『投資のドン』と出会いと、目から鱗の投資アドバイス
「私が投資でうまくいってないことを聞きつけた同僚が『投資のドン』を紹介してくれたんです(笑)その同僚の大学の先輩でした。そのドンは、不動産投資で成功しているから、一度話を聞いてみたらどうかと引き合わせてくれました。今思えばあの出会いがなかったら、また失敗していたかもしれません」
そうして松田さんは「投資のドン」と会い、色々な話をしたという。
自分が今までしてきた失敗を話し、次で絶対成功させたいことを伝えた。
その結果、
・福岡にタワマンを購入する
・ターゲットを決め必要に応じてリノベーションする
・融資はメガバンクから引く
の3つのアドバイスをもらったのだそう。
「福岡は日本の中でも珍しい、今後2030年代に向けて人口が増えると言われている都市。天神や博多の再開発計画もされている中、不動産が増えることは予測されますが、その分人口が増え続ける今なら投資を始めるのにまだ間に合うと言われました。そして、以前失敗した要因である物件の築年数。新しければいいものではないということも教わりました。新築に近ければその分、購入費用が高くなるので、オススメはしないと。そこそこ外観のいいマンションであれば、中が多少古くてもターゲットを絞ってそれに合わせたリノベーションすれば問題ないと言われたんです」
次々と出てくるアドバイスに面食らったという松田さん。
しかし、その指摘全てが納得いくものばかりで、札幌での投資はまさに教科書のような失敗例だったと苦笑い。
「融資についても、どこから引いてくるのが一番いいのかいまいちわかっていませんでしたが、ドンは『メガバンク一択だ』と言っていました。メガバンクというと、金利が低い代わりに、年収や職業等、審査基準が厳しいイメージ。だからこそ肩書や年収がしっかりしている医師は有利なんだとか。メガバンクは借りるのに少し抵抗があったので、これも目から鱗でした」
「東京のタワマンに憧れるファミリー」をターゲットに
こうして、『投資のドン』のアドバイス通りに準備を再開。
一番悩んだのは、ターゲット層を絞ることだったという。
「ドンの言うことはほとんど納得のいくことばかりでしたが、ターゲットを絞るというのはそれこそリスクが高いことのように感じました。勝手に「こういう人に借りてもらいたい」と自分で決めて、それに合う部屋作りをする。でもそれはあくまでも架空のターゲット。本当にそんな人が現れるのかと不安でしたね。結局、『東京のタワマンに憧れているけど、そこまでの資金はなく、福岡でタワマンを借りることにしたファミリー』をターゲットにすることにしました。なかなか面白いでしょう」
福岡はほどよく都会で、ほどよく田舎。
都会に憧れて地方から出てくる人もいれば、田舎暮らしがしたくて都会からやってくる人もいるのだそう。
そして今回のターゲットは都会に憧れるファミリー層。
ある程度の経済力はあるが、東京のタワマンを購入できるほどの資金はない、そういった具体的なファミリー層に絞ったのだと話す。
「ターゲット層が絞れたので、あとはトイレや玄関、キッチンを東京のオシャレなタワマンを参考にリノベーションしました。都会に憧れている家族が思わず声を上げたくなるように、内装にはかなり拘りましたね。金額はそこそこかかりましたけど、もともとの物件が新築でなく安かったのでできたことでした」
不動産投資で最も大事な、融資についてもかなりうまくいったのだそう。
「これもドンの言う通り。メガバンクにして正解でした。審査は時間がかかりますが、何の問題もなく通り、かなりの融資額を引いてくることが出来ました。バックが大きいと安心ですし、優遇されるのは単純に嬉しかったですね」
不動産投資の成功で子どもの教育費を賄えた
こうして、始まった3回目の不動産投資。
「投資のドン」のアドバイスと抜け目ない準備のおかげで、わずか数週間で入居者が決まり、順調な出だしを切ったそう。
「そこからは、毎月かなりの額の家賃収入が入ってくることへの驚きと興奮でしばらく浮かれていました。自分で家賃を決めておいてなんですけど、そこそこ高めに設定していたので、ちゃんと投資できているということに感動しました。そこで同じような理由で青森にも物件を買ったんです」
ターゲット層が年収上位層だとやはりトラブルも少ないのだそう。松田さんは特に大きな問題を抱えることなく資産を順調に形成。目標だった子どもたちの教育費の資金調達も間に合ったと言います。
「一番の目的はそこでしたから。無事に、子どもたちを私立の医学部へと入れてやることが出来ました。最初2回、株式と札幌での不動産投資で失敗した時は、呆然としましたけど、ちゃんと取り戻すことが出来て、本当に良かったです」
医師こそ不動産投資に向いている最大の理由
現在、管理職となりながらも相変わらず忙しい日々を過ごす松田さん。最後に「医師」の不動産投資について聞かせてもらった。
「不動産投資をすることの最大のメリットって、『不労所得』であることだと思うんですよね。いったん軌道に乗れば、ある程度の管理でなにもせずにお金が入ってくる。これはうまくいけばかなりいいビジネスだし、時間のない「医師」こそやるべきです。日々忙殺され、気付けば貯金も大してなく、労働力として搾取されて終わる人生だけは避けなければいけない」
そう言って、広すぎるロビーを見渡した。
失敗と苦労を重ねてきた松田さんだからこそ見える景色がそこにはあるのかもしれない。
50代、60代が「絶対にやってはいけない」不動産投資3選
私のYouTubeチャンネル「ウラケン不動産-浦田健公式」は幅広い年代の方にご視聴いただいていますが、50代、60代の方も40%近くいらっしゃいます。
これから不動産投資を始めようという人は30代、40代が多いと思いますが、最近は50歳を超えても不動産投資を始めたいという人が多くなってきているように思います。
もちろん、年齢に関係なく新しい投資に興味を持つことは良いことですし、不動産投資を始めるのに年齢は関係ありません。しかし、30代の方がするような投資を60代の方にもおすすめできるかといわれれば、決してそんなことはありません。
なぜなら、年を取れば取るほど、若い人と同じようなリスクを取った投資ができなくなるからです。そこで今回は、「50代、60代が絶対にやってはいけない不動産投資3選」というテーマでお話しします。ぜひ最後までご覧ください。
■50代 60代が絶対にやってはいけない不動産投資とは?
まず理解していただきたいのは、50代、60代の方は20代、30代と同じような「リスクを取った不動産投資」はできないという点です。
リスクを取るとはどういうことかというと、ローンを引いてレバレッジを効かせた投資をするということです。たとえば、退職金を全額頭金にしてローンを目一杯引いて、表面利回り5%程度の新築アパートに投資する・・・なんていうのはまさにNGですね。
また、キャピタルゲイン狙いの投資もすべきではありません。キャピタルゲイン狙いの投資とは、売却益を目的とした投資のことですが、50代、60代は失敗した時にリカバリーをする時間がもう残されていないため、リスクが高すぎるのです。
投資にはリスクがつきものですので、50代、60代の方は過度なリスクを取らないことが重要になってきます。また、資産を大きく増やす投資をするよりも、減らさない投資をすることが重要です。
以上を理解していただいた上で、50代、60代がやってはいけない不動産投資について具体的に見ていきましょう。
■キャピタルゲインを目的にした不動産投資はやってはいけない
たとえば、早期退職金とローンでタワーマンションを購入し、将来の値上がり益を期待するというような投資はやめましょう。
これは50代、60代に限った話ではありませんが、日本で不動産投資をする場合は、値上がり益を目的とした投資ではなく、毎月の家賃という収益を目的とした投資をすべきです。
将来の値上がり益を期待して投資したとしても、いつどれくらい値段が上がるかわかりませんし、逆に値が下がってしまう可能性もあります。仮に値が上がったとしても、その時に80代になっていたとしたら、結局お金の使い道は限られてしまいますよね。
以上の理由から、キャピタルゲインを目的にした不動産投資はしない方が賢明でしょう。
■新築アパートに投資してはいけない
新築アパート投資には、自分で土地を購入して新築するパターンと、出来合いの新築物件を購入するパターンがありますが、これから不動産投資を始めようという50代、60代の方には、どちらもおすすめできません。
まず、土地を購入してアパートを新築するとなれば、少なくとも「不動産実務検定( https://www.j-rec.or.jp/ )」のマスターレベルの知識を持っていない限りは難しいでしょう。
また、新築の区分マンション投資は、50代、60代に限らず絶対にやってはいけません。
なぜなら、デベロッパーが販売している新築物件の表面利回りは非常に低いからです。ローンや管理費を支払った後の実質利回りで見れば1%以下の場合も多く、不動産投資としての運用効率が悪いのです。
50代、60代の方は、退職後などの「比較的近い将来に使えるお金が欲しい」と思っている方が多いと思いますが、新築の不動産投資でそれを叶えるのは不可能に近いのです。
■わからないものに投資をしてはいけない
これも50代、60代に限った話ではありませんが、不動産投資に失敗する人の特徴として「よくわからないものに投資をしている」という点が挙げられます。
たとえば、女性専用のシェアハウス「かぼちゃの馬車」で失敗した人たちは誰もがこのパターンですし、新築区分マンションや出来合いの新築アパートに投資する人も、大抵は「よくわからない」まま投資をしています。なお、「かぼちゃの馬車」で投資家が騙されたからくりについては、ウラケン不動産( https://www.youtube.com/watch?v=fFUVnU4CjTE )で詳しく解説しています。
不動産業界は「コンサルタント」を自称する専門家もどきが、実は質の悪い不動産セールスマンだった・・・ということが非常に多い世界です。結局は自分でしっかりと勉強して、自分の理解できる範囲内のものに投資するのが一番ということです。
■おわりに
以上、50代、60代がやってはいけない不動産投資について見てきました。
投資を始めるなら、できるだけ若いうちに始めるのが理想的です。なぜなら、若ければ若いほど失敗した場合でもリカバリーができますので、より高いリスクを取ることができるからです。
では、50代、60代の方は不動産投資を始められないのか?というと、そんなことはありません。50代、60代であっても、狙うべき物件や目指すべきリターンをしっかり定めてから投資をすれば、成果を出すことは十分可能です。
次回は、50代、60代で不動産投資を始めたいという方におすすめの投資法について解説したいと思います。どうぞお楽しみに。
サラリーマンが海外不動産投資を始めるメリット・デメリットは?注意点も
1.サラリーマンが海外不動産投資を始めるメリット
サラリーマンの方が海外不動産投資を始めるメリットとしては、分散投資ができることや、日本国内よりも安い物件に投資できることなどが挙げられます。
1-1.資産分散によるリスクヘッジが可能
海外不動産投資が持つ代表的なメリットとして、資産分散によるリスクヘッジがあります。
例えば、日本国内の不動産だけに集中投資をしていると、日本の円と物価の価格変動の影響を大きく受けることになります。
このような状況でドル高・円安のような市況になったとき、資産を集中させてしまっているために分散効果が得られず、米ドルで換算すると相対的に資産を目減りさせてしまっているということになります。
一方、海外不動産へ投資をしていると、対象国の外貨で家賃収入や売却益を得ることになります。このような為替リスクや国家間のインフレリスクを回避できる点が海外不動産投資の大きなメリットです。
1-2.一等地の物件を安く購入できることも
海外不動産投資の投資先として選べる国は複数ありますが、一部の国では首都の一等地に立地している物件を日本国内よりも安価に購入できます。
例えばカンボジアやフィリピンなど東南アジアを中心とした新興国では、首都の中心地に立地している物件を1,000万円前後など安価に購入できることもあります。
一方、東京23区内の都心では、25㎡のワンルームマンションが2,000万円以上などの値段で売られていることもめずらしくありません。首都圏内のマンションが比較的安価に購入できる点は大きなメリットといえるでしょう。
またこのような新興国の物件は、比較的に価格が安いものの、日本以上に首都一極集中が起きていることも多く、適切な物件選びができれば住宅需要の拡大とともに売却益を得られることがあります。
不動産投資では家賃収入に対して物件価格が安ければ高利回りになるため、海外不動産投資では日本国内よりも効率的な投資ができる場合も少なくありません。
1-3.海外では人口増加の傾向にあるエリアが多い
2021年時点の日本において、少子高齢化を背景にした人口減少が続いています。このまま人口が減少傾向にあると不動産の賃貸需要も比例して大きく減少してしまうため、国内不動産投資では将来的な賃貸ニーズのシミュレーションが最も重要となります。
一方、海外不動産投資の対象国となりやすいアメリカや東南アジア諸国では、人口増加率や経済成長率が長期的にプラスで推移しており、不動産の値上がりが期待されるエリアも少なくありません。
このような人口増加を背景にした不動産需要の増加を見込める点は、海外不動産投資の大きなメリットといえるでしょう。
2.サラリーマンが海外不動産投資を進めるデメリット
サラリーマンが海外不動産投資を進めるデメリットとしては、ローンによる資金調達が困難な場合もあることや、物件選びが国内不動産投資よりも難しい点などが挙げられます。
2-1.日本国内よりもローンの条件が厳しい
日本国内の不動産投資では、一定の収入を見込みやすいサラリーマンの属性を活用し、不動産投資ローンを利用しながら投資規模を拡大していくことが検討できます。
また、一部の金融機関では中小企業の経営者などよりもサラリーマンの方が一定の収入を見込めるために、ローン審査でプラスに評価されるケースもあります。
一方、海外不動産投資の場合、日本国内の金融機関で海外不動産に対して積極的にローンを提供しているところは多くありません。日本国内と比較して物件価格が安いとしても、自己資金の割合を多く求められる可能性は高いと言えます。
そのほか、日本国内の不動産投資では、ローンを使えれば必要な自己資金は物件価格の30%以下に収まることが多いものです。
しかし、海外不動産投資ではローンを使えても物件評価額の50%が限度融資額となることが少なくありません。必要な自己資金額が日本国内の不動産投資より多い点は、海外不動産投資のデメリットになると考えられます。
【関連記事】海外不動産投資の融資を受けやすい金融機関はどこ?主な3行を紹介
2-2.気軽に現地を見に行けない
不動産投資における物件選びでは、実際に現地を訪問して情報収集することは重要なポイントとなります。スーパーや駅までのアクセスや騒音などの住環境など、実際に訪れることでわかる情報が少なくないためです。
しかし、海外不動産投資ではタイやフィリピンなど東南アジアの国でも、飛行機で6時間程度の移動が必要です。また、コロナウイルス感染症が終息していない2021年9月時点では、海外渡航が困難な場合もあります。
サラリーマンにとっては特に、海外不動産投資では日本国内の不動産投資と違って気軽に足を運べない点がデメリットです。
コロナ下における海外不動産投資で物件を選ぶためには、現地の様子を細かく共有してくれる不動産エージェントを選ぶことが重要なポイントになります。
2-3.税制改正により減価償却費の経費計上ができない
税制改正により、2021年(令和3年)以降は海外不動産の所得を計算する場合に、その経費と所得の合算が損失額となった際、建物の減価償却費は経費として計上できないようになります。つまり、決算上の海外不動産の赤字を他の所得と損益通算できないため、サラリーマンとしての所得を圧縮することができなくなったということになります。
一方、法人が保有する中古の海外不動産は規制の対象となっておらず、法人税については規制が入っていません。簡便法による4年間での減価償却も、法人の事業利益との損益通算も可能です。
個人であるサラリーマンにとって、減価償却費の損益通算ができない点は大きなデメリットといえるでしょう。
※出典:国税庁「第41条の4の3((国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係」
3.サラリーマンの海外不動産投資で要注意のリスク
サラリーマンが海外不動産投資を進める上で特に注意すべきリスクとしては、慎重に不動産会社を選ばないと失敗する確率が上がる点や、空室リスクなどが挙げられます。
3-1.不動産会社に関するリスク
日々いそがしく仕事をしているサラリーマンの方の中には、不動産投資における情報収集の時間を確保するのが難しいという人も少なくないでしょう。海外不動産投資では特に、不動産会社や物件に関する情報収集の時間を確保することが課題になると言えるでしょう。
海外の情報は英語など現地の言語で作られていることが多い上に、信憑性の高い情報を見極める難易度が上がります。
海外のデベロッパーが建設している物件を選ぶ場合は、ベロッパーの会社規模や分譲実績などを検証することが重要になります。小規模なデベロッパーや分譲実績に乏しいデベロッパーの物件を購入した結果、物件が完成せずに引渡しを受けられないというトラブルが起きることがあるためです。
しかし、専門的な用語も使われることが多い不動産業界の情報を、英語ベースで収集するには大きな手間がかかります。海外不動産投資で不動産会社に関するリスクを軽減するためには、できる限り日本の不動産会社の手を借りることもポイントと言えるでしょう。
3-2.空室リスクの見極めは慎重に
例えば人口増加や経済成長を継続しているエリアでの不動産投資では、物件の値上がり益や将来的な家賃の上昇などを見込めます。新興国では特に、データの上ではこれらの利益を狙える環境が整っている国も少なくありません。
しかし、不動産の収益性はそれぞれの物件によって異なるため、国全体のデータを確認するだけでは投資用不動産を購入しても本当に入居者が入るか検証しきれないのが実態です。空室リスクを検証するためには、個々の収益物件のスペックを確認するなどして、ミクロのデータを検証することも必要になります。
また、海外には日本ほど公的な情報が整備されていないエリアも多く、投資家個人では情報収集が困難な場合もあります。そのほか、賃貸管理を委託する不動産会社によっても空室リスクが左右される点に要注意です。
海外不動産投資で空室リスクを見極めるためには、物件現地の周辺情報に詳しい不動産会社の手を借りることが重要になります。まずは不動産会社の見極めに重点を置いてから、物件の比較を行ってみましょう。
まとめ
海外不動産投資はサラリーマンの属性を活用した資金調達や、日本国内よりも安い物件に投資できることなどのメリットがあります。また、人口増加している国の不動産を所有することで、値上がり益を見込んだ投資が検討できる点もメリットと言えるでしょう。
一方で、投資の資金調達や海外現地の情報収集については注意を要します。物件選びに関するリスクや空室リスクの対策として、パートナーとなる不動産会社を慎重に選ぶことが重要となります。これらのメリット・デメリットを比較しながら、慎重に投資判断をしていきましょう。
税制改正で節税メリット減少も…「米国不動産投資」が放ち続ける魅力とは【税理士が解説】
令和2年度の税制改正で、何が変わったのか?
令和2年度の税制改正で、「国外中古物件の不動産所得に係る損益通算等の特例」(以下、「特例」)が創設された。
日本の税制では、取得した建物が新築の場合、住宅用の木造建物は22年、鉄筋コンクリート造(RC造)は47年というように、法定耐用年数が定められている。建物を取得した価格は、その年の費用として全額を一度に計上できるわけではなく、法定耐用年数に応じて配分し、その期に相当する金額「減価償却費」を費用に計上する。
ところが、法定耐用年数の全部を経過した中古の固定資産の場合、「簡便法」という計算方法を用いることで新築に比べて大幅に短い償却期間を適用させることが可能だ。
たとえば、築22年を超える木造の住宅用建物ならば、法定耐用年数の5分の1つまり4年(22年×20%で4.4年から端数を切り捨て)を耐用年数として減価償却することができる。
米国不動産の場合、5,000万円の中古不動産(木造住宅)を購入すると、建物価額は購入価額の80%程度(土地価額は20%程度)となる。日本とはまったく異なる建物価額比率が、米国不動産の特徴の一つだ。
この比率から建物価額を4,000万円とした場合、「簡便法」で減価償却費を計算すると、1年あたりに費用計上できる減価償却費は1,000万円、4年間にわたって4,000万円ほどの費用計上が可能となる。

「個人の方の場合、米国不動産を購入後賃貸して事業用資産とすることにより、多額の減価償却費を費用計上することで不動産所得に赤字を発生させ、その赤字を給与所得、事業所得などの他の所得から差し引くこと(損益通算)で、節税効果が得られるというものでした。この効果に着目し、節税目的で米国不動産を購入される富裕層の方が、平成20年以降増えておられたと思います」と中谷税理士は話す。
しかし、冒頭に述べた「特例」の施行によって、米国をはじめとする海外で取得した中古物件について、個人を対象に、簡便法を用いた減価償却費の計上方法が改正された。
「簡便法は、昭和26年に作られた省令で、経済情勢や国際情勢が大幅に変わった現代においても一律に適用されることに無理があったのかもしれませんね。
その改正により、以前のように多額の減価償却費から生み出される赤字を計上し、給与所得などから差し引くこと(損益通算)はできなくなりました。
そのため、アメリカ不動産は、以前のような大型の節税商品という立ち位置では無くなったといえます。なお、今回の税制改正では、個人の方が対象となっており、法人は対象となっておりません。法人においては、引き続き簡便法を使用した4年間の減価償却が可能ですので、『節税型』+『投資型』として、従来通りの活用をしていただければ問題ないのではないでしょうか」(中谷税理士)
「トータルの収支」で考える、米国不動産の投資効果
では、個人において、米国不動産に投資する意味は完全になくなってしまったのだろうか。
「海外不動産の投資効果は、『トータル収支』(賃貸期間中の各年の損益と税金、売却時の損益と税金)がプラスになったのかどうかで考える必要があります。最初の4年間で多額な減価償却費を計上し、計上した期間は劇的な節税ができたかもしれませんが、その後(5年目以降)がどうであるのかが、とても大事です。
空き状況が続いて、賃貸収入が思うように入ってこない……売却したが、思うような金額で売れなかった……このようなお話は、海外不動産投資をされた方から時折お聞きしますが、節税はできても、購入から売却までのトータル収支で効果がなければ、いかがなものでしょうか……節税した意味も無くなるのではないでしょうか……」(中谷税理士)
「米国の中古物件は築年数が古くても、しっかりと維持管理された物件を購入することで、値上がり期待が大きく、物件次第では大きな売却益(キャピタルゲイン)や、購入してから売却するまでの賃料収入(インカムゲイン)が見込めます。
税制改正前は、米国不動産を6年目ほどで売却すれば、『トータル収支』で十分な投資の効果が得られるケースが多かったようです。
税制改正後は、『トータル収支』に効果が出るまでの期間は長くなりますが、それでも8~10年程度保有すれば、十分に投資効果が表われる可能性は高いと考えます」(中谷税理士)
中谷税理士によると、「トータル収支」の結果には、売却時の税金が大きく影響するという。
税制改正後、減価償却費は、「簡便法」を使用しないとなれば、新築物件(住宅用)を購入した際と同様の耐用年数「22年」を使用して計算することになる。税制改正前に比べ計上できる累計の減価償却費の額は大きく減少するが、反対に建物の簿価が多く残ることになる。
そして、売却時だが、不動産の売却(譲渡)所得の計算上、建物や土地の簿価価額は、取得費として必要経費に算入する。
税制改正前(簡便法の適用)では、建物の簿価は減価償却費で費用計上しているので、取得費に計上するのは土地の簿価のみであった。
税制改正後(耐用年数22年適用)では、10年経過していても建物簿価は半分程度残っており、土地の価額とともに経費に計上できることになる。つまり、税制改正前(簡便法の適用)に比べ、譲渡所得の金額が大きく減少することとなり、税金も大きく減少することになる。
「節税効果の減少」があっても「売却時の税金の減少」を踏まえて「トータル収支」を考えた場合、税制改正前での投資の効果(6年目)に、税制改正後での投資の効果は、10年程度で追いつくことが可能といえる。
参考だが、少しでも節税効果を出したいという人のために取得費をさらに細分化して分別する「コスト・セグリゲーション」という減価償却の計算方法を利用する動きも出ている。コスト=取得費、セグリゲーション=分別という意味で、これは、建物を一個の固定資産として計上するのではなく、建物本体から構造物や付属設備(電気設備、給排水設備、ガス設備など)などを分けて計算する方法だ。
上述したように、建物(木造 住宅用)の耐用年数は22年だが、付属設備などは10年前後と短いため、建物を細かく分類することによって、1年当たりの減価償却費を早期に多く計上することが可能だ。中谷税理士によると、「内訳を示す正確な報告書を不動産鑑定士などから用意できるのであれば、利用を検討してみても良いでしょう」とのこと。

米ドル資産の所有により「分散効果」が得られる
「特例」の施行によって、個人所得税の節税効果は薄れたものの、日本の不動産と違って中古でも値上がり益が期待できること、さらに人口増加や潜在的な経済成長力とともに家賃相場も上がっていることから、中谷税理士は「米国不動産の投資対象としての魅力は、まったく色あせていないと思います。個人の方の場合、シンプルに『投資型』と見ていただければいいのではないでしょうか。実際、コロナ禍以降も米国の住宅需要はまったく衰えていないようですし、むしろニューノーマルな働き方が浸透したことで、より広い家への住み替えや移住が進み、住宅市場はますます活況を呈しているようです」と話す。
中谷氏は米国不動産のメリットとして、十分なキャピタルゲインやインカムゲインが見込めることのほかに、基軸通貨である米ドル建ての資産を持つことで資産分散効果が期待できる点を挙げる。
「もちろん、その裏返しとして為替変動リスクが存在し、ハリケーン被害のような災害リスクも想定されます。あくまで不動産投資として考えていただき、様々なリスクが、他の投資商品と同様に存在することは認識してください。
また、どんなに有望な市場でも、物件を選び間違えると十分な利益が得られなくなることもあります。
米国不動産だから、すべての物件で満足のいく投資の効果が得られるとは考えないでください。これは国内不動産と同様だと思います。大事なのは物件ではないでしょうか。物件の質は、安定した賃貸収入、売却額などにも非常に影響するでしょう。
そのためにも、物件選び、契約関連の手続き、物件の管理をしてくれる業者は慎重に選んでいただく必要があると思います。投資は買って終わりではなく、買ってからがスタートです。信頼できる業者を選ぶことが投資の効果を最大に生み出す一番のポイントではないでしょうか」
中谷 義宏
中谷義宏税理士事務所
今一番ベストな副業は不動産投資?【書籍発売『会社を辞めずに大富豪になるプレミアムマンション投資』】
株式会社ぱる出版は『会社を辞めずに大富豪になるプレミアムマンション投資』(若月りく 著)を8月26日に発売しました。本書は一部上場企業に務めながら、不動産投資で合計3000万円を超える年収を得ている著者の実体験を紹介した本です。
◆名刺を不労所得に変える方法とは?
著者は名刺を銀行へ持ってゆきその力を活かすべきだと述べます。名刺は公務員や上場企業、あるいは医師のような専門職や、弁護士、会計士といった士業の人たちほど信用度が高くなります。融資審査において銀行が求めているのは、借主属性の安定性、健全性、実績であり、信用のある名刺ならば最低でも年収の7倍、最高で20倍のお金を借りられるそうです。そのお金を不動産投資へと向けるのです。
しかし何千万円もの不動産を購入するのは不安もあるかもしれません。しかし、資産価値と借り入れ金額が等価なため、資産価値が維持されやすい好立地物件の場合、借入額の多寡自体を不安視する必要はないと著者は述べます。こうした発想の転換こそ重要だと気付かされます。著者自身、不動産投資を進める中で「銀行はいくら貸してくれるのか」と前向きな気持を楽しむようになったといいます。
◆副業として気軽に始められる不動産投資
不動産投資は、著者の勧める都心部プレミアム・ワンルーム(トップワン)投資ならば、まず失敗はありません。家賃相場は安定しているため、株やFXなどほかの投資に比べてローリスクであり、精神的な制約も時間的な制約もなく、何より就業規則にも抵触しないため、副業として手離れ良く始められるそうです。
◆実体験に基づく鉄則ルールを紹介
著者は、本業を持つ多用な方が、不動産投資を行うにあたり「鉄則」と言える幾つかのルールを紹介しています。その内容は以下です。
・買うなら好立地新築一択(12年以内の築浅を推奨。中古物件はメンテナンスなど費用がかかる)
・「マーケットリンク」より「コストリンク」を意識(新築物件は価格設定が明瞭。中古は市況で価格変動が相対的に大きい)
・空室リスクを少なくする立地環境の良いトップワン物件を狙う
・物件の条件は複数路線を持つ駅から徒歩7分以内を守る
・12年以内の売却を意識して購入(新築マンションの償却期限は47年のため、次の購入者が35年ローンを組める)
・アパート1棟買いなどの経済感覚が狂うような投資は避ける(高い収益性が期待できるが投資ハードルが高くなる)
こうした見ると、すべての条件に合理的な理由があるとわかりますね。投資は堅実なものだとわかるでしょう。
さらに、おいしい物件を持ってきてもらう営業マンとの付き合い方などについても「どういう質問をすべきか」などポイントが紹介されています。
◆会社員でありながら経済と時間の自由を手に入れるための一冊
著者の若月りく(わかつきりく)さんは理系国立大学の大学院を終了後、大手一部上場企業に入社し、その傍ら副業として不動産投資を始めました。会社員として自分の時間が限られている中で、経済的時間的な自由を手に入れるにはどうすれば良いかを考え、不動産投資に行き着きました。明日には一攫千金で億万長者といったものではありませんが、中長期的に堅実に利益が得られ、時間をかけて大富豪を目指したい人にはおすすめの方法だとわかります。何より著者の立場を踏まえれば、説得力のある言葉でしょう。
【書籍情報】
『会社を辞めずに大富豪になるプレミアムマンション投資』(2021年8月26日発売
¥1650(税込)
Amazonページ短縮URL: http://ur0.work/7RmV
不動産投資、地震や火災など災害リスクへの対策方法は?それぞれ解説
1.不動産投資で想定される災害リスクとは
不動産投資で想定される代表的な災害リスクについて、統計なども用いて解説します。特に気を付けるべきと考えられるリスクは3種類の災害です。
1-1.地震による損壊または全壊のリスク
地震大国などと報道されることもあるほど、日本は世界的に地震が多い国の一つです。しかし、例えばRC造のマンションでは、地震で全壊するほどの被害を被った事例は多くありません。
国は大きな地震が起こるたびに建築基準法で定める要件などを見直しているため、法律に則った基準で建設された建物であれば、大きな被害に遭うリスクはそれほど大きくないと言えます。
社団法人高層住宅管理業協会が発表した資料によると、東北地方および関東地方で、東日本大震災によって建て替えが必要なほど大破したと言えるマンションは、調査対象の中にはありませんでした。具体的な被害の状況については、以下の表のようになっています。
- 被害の程度:調査対象に占める割合
- 建て替えが必要なほど致命的な被害:0%
- 大規模な補強や修繕を要する被害:0.04%
- 外壁タイルの剥落やひび割れなどの被害:2.01%
- 外観上は目視できないレベルのきわめて軽微な被害:14.43%
- 被害なし:83.52%
※参照:社団法人高層住宅管理業協会「東日本大震災の被災状況について」
なお、調査対象地域には宮城県と福島県も含まれており、調査棟数は46,365棟となっておいます。ただし、戸建やアパートなどで木造の物件については、RC造の物件とは強度が違うため、地震による被害のリスクは高いと考えられます。
1-2.火災のリスク
不動産投資では地震に加えて火災による被害も想定できます。自らが所有する部屋で火災が起きた場合だけではなく、近隣の住戸で火災が起きた場合に延焼する場合もある点に要注意です。
火災の程度によっては壁紙や設備の交換で済む場合もありますが、万一全焼してしまった場合には修繕費用も高額になります。
1-3.水害のリスク
河川が近くにある場合は特に水害リスクにも要注意です。洪水と呼べるほどの被害は長期的な目線で見ればそれほど多くありませんが、大雨によって1階部分が浸水したなどの被害は東京都や神奈川県などの都心でも発生しています。
マンションに投資している場合は、投資家が所有する住戸に直接の被害がなかった場合でも、自動ドアやエレベーターなどの共用設備が故障すれば、管理組合から修繕費用を徴収される可能性があるので要注意です。
2.災害リスクに備えるための方法
地震や水災などの災害によって被害を受けた場合は、火災保険に加入していれば大半の場合は保障を受けられます。火災保険の活用は災害リスクに対する備えとして最も代表的です。
2-1.火災保険に地震保険の特約を付加する
地震保険に加入していれば、被害の程度によって保険会社から保障を受けられます。ただし、地震保険は火災保険の特約としてしか取り扱いがないことと、地震保険の保障を受けるためには基準以上の被害を受けている場合に限られることには要注意です。
各損害保険会社は地震保険単独での加入を受け付けていません。地震保険は火災保険の特約として取り扱われており、1度火災保険に加入すると途中から特約を付加できない点に要注意です。
地震保険に加入するためには、物件を購入した時に新規で加入した地震保険に特約を付加するか、すでに火災保険に加入している場合は、一旦保険を解約してから再度加入し直す必要があります。
2-2.保険の対象について理解する
火災保険などの保障内容は、保険会社が発行する約款に記載されています。しかし、約款には専門用語が使われていることも多いほか、内容が多岐に渡っているため、内容をしっかり把握しているという人は少ないものです。
火災保険が保障対象としている災害は、火災だけではなく多岐に渡っています。例えば以下のようなものです。
- 火災
- 落雷
- 大風による窓ガラスの破損など
- 雹が降ったことによる被害
- 水災
例えば、突風によって物が飛ばされてきた結果窓ガラスが割れてしまったなどの場合も、火災保険による保障の対象となります。そのほか、高温によって窓ガラスにひびが入ってしまうことを熱割れと言いますが、熱割れも火災保険の保障対象です。
例えばマンションでは、外気に触れる窓ガラスは共用部分とされており、管理組合の管理範囲内です。窓ガラスが熱割れを起こした場合などは、マンションの管理会社へ連絡すれば、管理組合が加入している火災保険で対応してくれます。
なお、保険会社や保険商品によっては加入が任意とされている内容もあります。火災保険に加入する前に、どの被害が保障対象となるのか理解することが重要です。そのほか、免責金額も選択できる場合があるので、掛金と免責金額のバランスを取る必要があります。
2-3.物件購入時にハザードマップを確認する
火災保険の加入以外にも、水害の恐れが少ないエリアの物件を選ぶことで備えとすることも有効です。水害の恐れが少ないエリアを確認するためには、ハザードマップを見るのが役立ちます。
ハザードマップとは、過去の水害事例などを参考として水害による被害が出ると想定されるエリアを示した地図のことです。ハザードマップは国土交通省や各市町村が作成しており、ハザードマップポータルサイト上で確認できます。
2-4.不動産を複数戸(棟)に分散して所有する
一つの物件に自信の資産を集中して投資していると、避けられないほどの大きな災害にあったとき、大きく資産を棄損してしまうリスクがあります。運用対象の不動産のエリアを分散させておくと、このような災害リスクへの対策になります。
また、エリアを分散させておくことで特定エリアにおける環境の変化や入居率の低下などのリスクも分散させることが可能になります。一つの投資対象に投資資金を集中させず、分散投資を心がけてみましょう。
まとめ
不動産投資では地震・火災・水災などの自然災害リスクに要注意です。これらの自然災害に備える方法として、まずは火災保険への加入を検討してみるとよいでしょう。
なお、火災保険の保障内容には任意の項目もあるため、保険加入時に保障内容を確認することが重要です。そのほか、水災に対する備えとしては、あらかじめハザードマップを確認してからエリアを絞り込むことも有効と言えます。
不動産投資型CF、キャピタルゲインを狙えるサービスは?注意点も
1.不動産投資型クラウドファンディングのキャピタルゲインとは
不動産投資型クラウドファンディングにおけるキャピタルゲインとはどういったものなのか、その内容を確認しておきましょう。
1-1.売却で得た利益を投資家に分配する
不動産投資型クラウドファンディングでは、投資家から集めたお金で不動産を購入します。取得物件の運用が終了した後、不動産の賃料収入や売却益を投資家へ分配していきます。
例えば、投資家から1億円を集め、運用終了後に不動産が1億1,000万円で売れれば、売却後に1,000万円の利益が生まれます。こういった売却益のことを、キャピタルゲインと呼びます。
売却益が出た場合その利益を投資家に分配するかどうかは、不動産投資型クラウドファンディングの案件ごとに方針は異なっています。売却益も投資家に分配する案件であれば、投資家への利回りが高くなる可能性があるのです。
1-2.不動産市況の影響や仕入れ値の影響を受ける
一方、不動産は必ずしも高い値段で売れるわけでありません。不動産業界の景気や日本経済全体の影響を受けます。
また不動産購入時の価格が相場よりも安ければ売却益が大きくなりやすいと言えますが、相場より高い値段で購入された物件は、売却時に購入時より安い価格でしか売れない可能性が高まります。不動産会社の仕入れ能力や販売能力次第で利益が出る可能性が変わってくるのです。
1-3.案件情報で予定分配率が確認できる
キャピタルゲインによる分配の数字がどの程度を想定されているのかは、不動産クラウドファンディングの案件情報に掲載されています。
キャピタルゲインを中心に利益を投資家に分配する案件なのか、インカムゲイン中心に利益を投資家に分配するのかなど、ファンドごとの方針や運用の仕組みが記載されているので、案件情報は細かくチェックしておきましょう。
2.キャピタルゲインが狙える不動産投資型クラウドファンディング
実際にキャピタルゲインが狙える不動産投資型クラウドファンディングにはどのようなサービスがあるのかをご紹介します。
2-1.COZUCHI(コヅチ)
COZUCHIは、LAETOLI株式会社が運営している不動産投資型クラウドファンディングです。
LAETOLI株式会社は1999年に創業した不動産会社で、不動産ファンドを中心にした事業を行っています。リノベーションや買取なども行っていることから、投資用不動産のノウハウが蓄積されていることが伺えます。
例えば、「品川区 五反田Ⅱ」というファンド(現在は募集終了)では、リノベーションによりバリューアップしたオフィスビルを投資対象としていました。募集時の予定分配率9%に対し、63.1%の実績をあげています。
2-2.CREAL
CREALは累計募集実績100億円を超える実績を誇る不動産投資型クラウドファンディングです。CREALでは、居住用不動産マンション以外にも保育所やレジャー施設など多様な種類の不動産案件を取り扱っています。
CREALのマンション案件を見ると、インカムゲインを分配するものも多いのですが、インカムゲインとキャピタルゲインを組み合わせて年利5~6%以上という高めの利回りを分配する案件も増えています。
例えば「(仮称)Rakuten STAY博多祇園」という案件では、インカムゲインが3.4%、キャピタルゲインが2.6%、計6%の予定分配率に設定されています。
2-3.TSON FUNDING
TSON FUNDING(ティーソンファンディング)は、愛知県名古屋市に本社を構える株式会社TSONが運営する不動産投資型クラウドファンディングサービスです。株式会社TSONは2008年創業の不動産事業や関連事業を営む企業で、TOKYO PRO Marketに上場しています。
TSON FUNDINGではキャピタルゲイン型とインカムゲイン重視型の2種類のファンドがあり、投資家のポートフォリオに合わせた投資方法を選択できます。
キャピタルゲイン型には、新築一戸建てを投資対象とした「森林再生シリーズ」と、造成した土地を投資対象とした「LANDシリーズ」の2タイプのファンドがあります。例えば、森林再生シリーズの「森林再生13号(愛知県一宮市・北名古屋市)」では、想定利回り6.7%となっています。
3.不動産投資型クラウドファンディングでキャピタルゲインを狙う時の注意点
キャピタルゲインを狙った不動産投資型クラウドファンディングでは、大きなリターンを見込める反面、リスクが高まってしまうデメリットがあります。次に、キャピタルゲインを狙ったファンドへ投資する際の注意点を見ていきましょう。
3-1.必ずしも利益が出るわけではない
不動産投資型クラウドファンディングでキャピタルゲイン目的のファンドに投資する時には、キャピタルゲインはインカムゲインと異なり一定の収益が見込める投資手法ではないという点に注意が必要です。
インカムゲイン目的のファンドでは毎月の賃料収入が投資家に分配されるため、空室が起きなければ分配金の減額が起こりにくくなっています。
しかしキャピタルゲインは、高値で売ることに成功した場合に分配が行われるため、市況の悪化などが起きれば高値で売ることができず、購入価格よりも安い値段でしか売れないことも起こりえます。
キャピタルゲイン目的の案件では、大きな損失が発生する可能性もあることを知っておきましょう。
3-2.劣後出資割合に注目する
不動産市況の影響を受けやすいキャピタルゲイン目的の案件に投資する時には、劣後出資割合が高いファンドに投資することで、リスク対策を検討しましょう。
劣後出資割合とは、不動産物件の取得の時に不動産会社が出資する金額の割合です。例えば1億2,000万円の物件を取得する時に、投資家が9,000万円、不動産会社が3,000万円を出資していれば、劣後出資割合は、3,000万/1億2,000万=25%となります。
不動産の売却時に損失が発生しても、不動産投資型クラウドファンディングの運営者である不動産会社の出資分から損失が計上されていくので、劣後出資割合が高ければ投資家の損失が発生しにくくなります。
劣後出資割合の数字は、不動産投資型クラウドファンディングの案件情報で公開されているので、数字をチェックしてから投資先を選んでいきましょう。
なお、有線劣後構造のファンドであっても運営会社が倒産してしまう場合には、劣後出資分を支払うことができない状況になる可能性があります。運営会社の資金力や経営状況についても注意しておくことが大切です。
まとめ
不動産投資型クラウドファンディングサイトには、キャピタルゲインを狙えるサービスが複数あります。高いリターンを得たい人にとって、投資検討しやすいファンドの形態と言えるでしょう。
ただし、リターンが大きくなる分のリスクも存在するため、できるだけ劣後出資割合の高い案件に投資したり、他の案件と組み合わせて分散投資したりするなど、大きな損失が発生しにくいような対策を行っていくことも検討することが大切です。
事業性だけでない不動産投資にも 不特法に期待、共感のまちづくり
国土交通省は7月20日、「不動産特定共同事業(FTK)の多様な活用手法検討会」の中間とりまとめを行った。FTKは不動産証券化スキームの1つで、不動産特定共同事業法(不特法)により、個人投資家などから小口出資を募り、運用・売却益を分配する。金融機関の融資対象になりにくい中小規模の再生案件や、財政状況が厳しい自治体の開発案件などで利用可能だ。
FTK案件数は2020年度に295件と増加傾向にあり、出資募集総額は1,556億円。国土交通省建設経済局・不動産市場整備課の渡邉明博氏は、「検討会はFTKを多くの方に知ってもらい、FTKを活用したまちづくりの事例を増やすことが目的だ」と話す。
FTKのメリットは、大きく3つ。1つ目は、地方での事業や空き家の活用など金融機関の融資対象になりづらい事業や、改修費用を賄う自己資金が足りず不動産の担保価値も低いため、不動産の改修費用を賄うほどの多額の融資が見込めない事業について、まちづくりを応援する地元関係者や、理念に共感する個人などの一般投資家から資金調達ができることだ。2つ目は、まちづくりへの市民の積極的な関与を促し、関係人口を増やせること。投資家が利用者にもなり得るため、施設の稼働率向上や運営の安定も期待されている。3つ目は、自治体が所有する歴史的建築物の保存・活用で費用拠出を継続的に行うことが難しい場合や、自治体が保有する土地を活用して地域に必要な施設を開発したいが財政状況が厳しい場合に、民間資金を有効活用して行政費用を抑制できることだ。「物件の改修にも利用できるため、空き家問題の解決にもつながるのではないか」と渡邉氏は話す。

太陽光発電投資と不動産投資、今から始めるならどっちがいいの?実際に両方やってる人に直撃調査!
[株式会社和上ホールディングス]
6割近くが「それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で太陽光発電に優位性がある」と見ている!
株式会社和上ホールディングス(本社所在地:大阪府大阪市、代表取締役:石橋 大右)は、太陽光発電投資と不動産投資の経験者を対象に、「太陽光発電投資と不動産投資」に関する調査を実施しました。
コロナ禍は既に1年以上が経過しましたが、事態は収束するどころか、変異株への感染拡大が相次ぐなど状況はさらに深刻になっています。
経済活動も大きな打撃を受けており、いわゆる“コロナ倒産”に陥る企業も後を絶ちません。
先行き不透明な“withコロナ時代”の真っ只中にあるという状況から、
「収入を確保するためにも投資を始めよう」
とお考えの方も多いでしょう。
投資商品は様々なものがありますが、皆さんはどのような投資商品に魅力を感じていらっしゃいますか?
激動の時代とも言える現在、そしてさらなる激動が起こる可能性もあるこれからの時代、
「安定した収入の確保が見込めるものや、今後の発展が見込めるものを選びたい」
というのが本音だと思います。
そのような思いから、不動産投資や再生可能エネルギーである太陽光発電投資に目を向けている方も少なくないかもしれません。
もちろん、あらゆる投資にはメリットだけでなくリスクも伴います。
例えば、太陽光発電投資と不動産投資とでは、どちらがよりメリットが大きいのでしょうか。
いずれの投資も経験している方からの率直なご意見を伺うことができれば、大いに参考になりそうですよね?
そこで今回、産業用太陽光・メガソーラー・中古発電所の日本最大級売却・購入サイト『とくとくファーム』(https://wajo-holdings.jp/farm/)を運営する株式会社 和上ホールディングスは、太陽光発電投資と不動産投資の経験者を対象に、「太陽光発電投資と不動産投資」に関する調査を実施しました。
【太陽光発電投資&不動産投資】現在の投資比率はどれくらい?
はじめに、皆さんの現在の投資比率について伺っていきたいと思います。
「現在の太陽光発電投資と不動産投資のおおよその比率を教えてください」と質問したところ、『太陽光発電5:不動産5(39.8%)』と回答した方が最も多く、次いで『太陽光発電7:不動産3(23.6%)』『太陽光発電3:不動産7(21.2%)』と続きました。
約4割の方が、現状では同じ比率で太陽光発電投資と不動産投資に取り組んでいることが明らかになりました。
しかし一方では、合計すると35%以上の方が太陽光発電にウェイトを置いていることもわかります。
かなりの方が、太陽光発電に軸足を移しつつある様子が見える結果とも言えるでしょう。
この太陽光発電投資と不動産投資の比率、皆さんはどんな理由で決定されているのかも興味深いところです。
例えば、今般のコロナ禍から何か影響を受けることはあったのでしょうか?
そこで、「コロナ禍以降、太陽光発電投資と不動産投資の比率を変えましたか?」と質問したところ、3割近くの方が『太陽光発電投資の比率を上げた(27.9%)』と回答しました。
“withコロナ時代”は、将来性について以前よりもシビアな判断が求められます。
その中で、太陽光発電へのシフトを決めた方が多いことが、この結果から明らかになりました。
太陽光発電は、将来性が評価されていると言えそうです。
【保険代わりになる?空き家リスクが高い?】不動産投資のメリット・デメリット
先程の調査では、かなりの方が、“withコロナ時代”以降の世界において太陽光発電の将来性を評価していることがわかりました。
しかし、不動産投資も投資としては強い魅力を持っています。定番の投資としてイメージされる方も多いでしょう。
ここからは、その不動産投資について、皆さんのお考えを伺っていきたいと思います。
「不動産投資のメリットを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『節税効果が得られる(42.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『安定したリターンが得られる(36.2%)』『保険代わりになる(26.3%)』と続きました。
『節税』『安定』『保険』という、ある意味で“守り”をイメージさせる回答が多く集まる結果となりました。
皆さんは不動産投資について、堅実な面をより評価されていると言えそうです。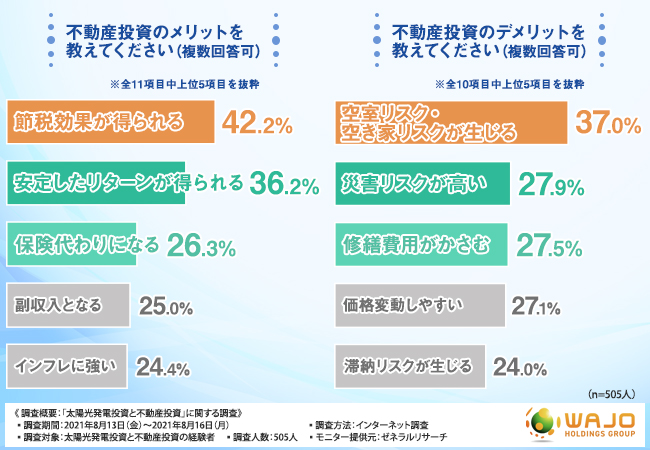
続いて、不動産投資のデメリットについてもお聞きしようと思います。
「不動産投資のデメリットを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『空室リスク・空き家リスクが生じる(37.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『災害リスクが高い(27.9%)』『修繕費用がかさむ(27.5%)』と続きました。
『空室・空き家』『災害』『修繕』という、いずれも不動産投資ならではの、そして避けることができないリスクについて多くの回答が集まりました。
中でも『空室・空き家』の回答率は高く、最多となっています。『災害』『修繕』による出費も痛いですが、そもそもの収益が減ってしまう『空室・空き家』は何よりも大きなデメリットと感じられるのかもしれません。
【ローリスク・ハイリターン?天候に左右される?】太陽光発電投資のメリット・デメリット
では皆さんは、太陽光発電投資についてはどのような考えをお持ちなのでしょうか?
ここからは、太陽光発電投資のメリットとデメリットについて伺っていきたいと思います。
「太陽光発電投資のメリットを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『高利回り(27.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『節税効果が得られる(27.7%)』『圧倒的な収益安定性(24.8%)』と続きました。
『高利回り』『節税』『安定』がかなり近い比率で多くの回答を集めています。
一方で、『節税』『安定』は不動産投資と同じ回答ですが、最多となったのはある意味で“攻め”をイメージさせる『高利回り』となりました。
皆さんは太陽光発電投資について、より積極的なスタンスの投資であると認識されているようです。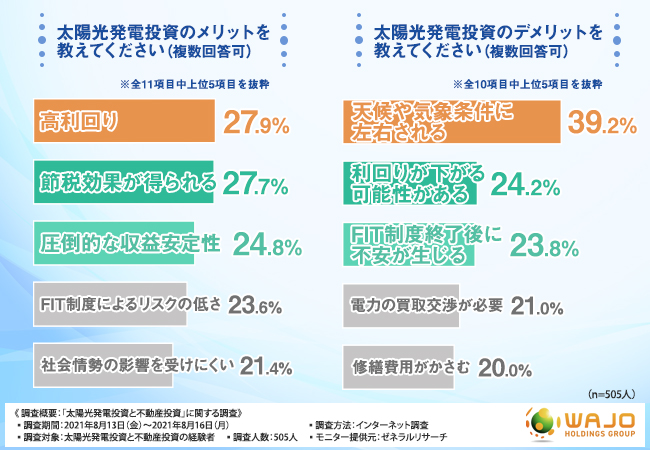
続いて、太陽光発電投資のデメリットについてもお聞きしました。
「太陽光発電投資のデメリットを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『天候や気象条件に左右される(39.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『利回りが下がる可能性がある(24.2%)』『FIT制度終了後(20年後)に不安が生じる(23.8%)』と続きました。
太陽光発電にとって避けられない『天候』に関するリスクが、突出して多くの回答を集める結果となりました。
『利回りが下がる』『FIT制度終了』というのも収益減に繋がる難題ですが、『天候』リスクは収益以前に販売する電力そのものが減少してしまいます。
多くの方がデメリットと考えるのも、やむを得ないことと言えるのかもしれません。
【太陽光発電投資 VS 不動産投資】どちらも経験している方から見た本当の優位性
ここまでの調査で、皆さんが太陽光発電投資と不動産投資にそれぞれメリット/デメリットを感じていることが明らかになりました。
実際に投資に取り組む方ならではのシビアな目線で、双方の特性をしっかりと見定めていることがわかったと思います。
では、そんな皆さんは、太陽光発電投資と不動産投資のどちらが優れているとお考えなのでしょうか?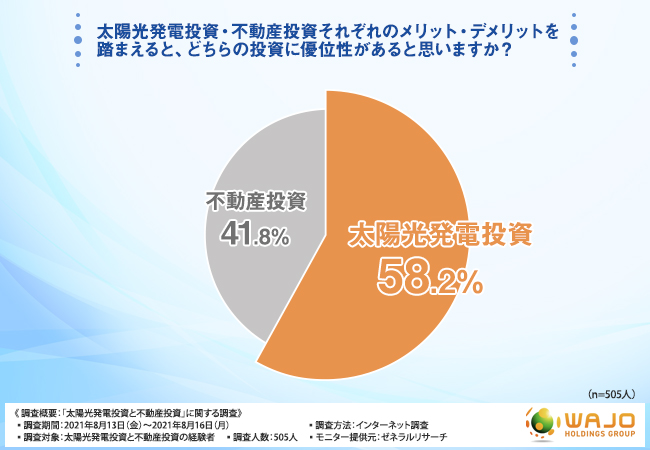
そこで、「太陽光発電投資・不動産投資それぞれのメリット・デメリットを踏まえると、どちらの投資に優位性があると思いますか?」と質問したところ、6割近くの方が、『太陽光発電投資(58.2%)』と回答しました。
過半数の方が、太陽光発電を選ぶ結果となりました。
最初にお聞きした「現在の投資比率」の結果とも近いものが感じられます。
皆さんは、不動産投資のメリットを充分に理解した上で、実際の投資も現状では取り組みながらも、軸足は太陽光発電投資に動きつつあるのかもしれません。
『太陽光発電投資』と回答された方には、回答の理由についても詳しく伺いました。
■太陽光発電投資の方が優れてるのは、こういうところ!
・高利回りだから(20代/男性/埼玉県)
・好感が持てるから(30代/男性/東京都)
・災害時に不安要素が少ないから(40代/男性/東京都)
・やはり空室リスクは避けることができない(50代/男性/静岡県)
・時代にマッチしていて、SDGsのテーマに合っている(60代/女性/神奈川県)
収益面でのメリットに関する回答も多いですが、リスク面でのメリットを評価する声も目立ちます。
また、収益とは直接関係なさそうな「好感」「時代にマッチ」といった面も、融資や周囲との調整などの際には、アピールできる要素としてかなり有効的であると言えそうです。
【これからの時代は太陽光発電!】太陽光発電投資をオススメする理由
先程の質問では、投資経験者の6割近くの方が太陽光発電投資は不動産投資より優位であると考えていることがわかりました。
しかし、皆さんはあくまでも経験者です。初心者とは見る目も異なるでしょうし、投資先の評価や選択もおのずと変わってくるでしょう。
そこで、これから投資を始めようとしている初心者にとっても、太陽光発電投資は不動産投資より優れているのかどうかをお聞きしました。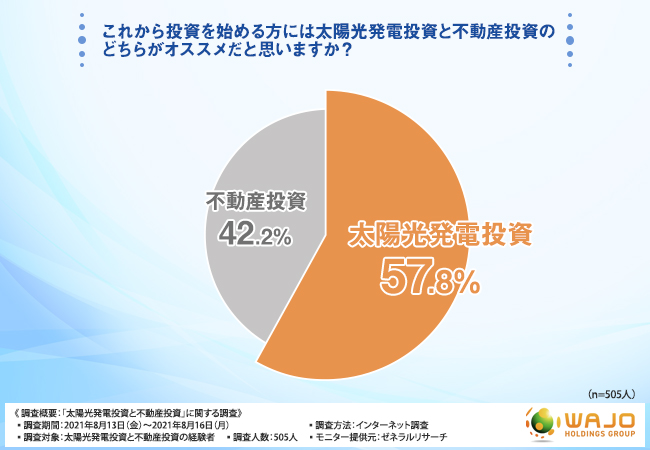
「これから投資を始める方には太陽光発電投資と不動産投資のどちらがオススメだと思いますか?」と質問したところ、こちらも6割近くの方が『太陽光発電投資(57.8%)』と回答しました。
皆さんご自身の選択をお聞きした先程の質問と、比率を含めてほぼ同じ結果となりました。
皆さんが「初心者にとっても太陽光発電投資は優れた投資先である」と考えていることが、明確にわかります。
投資初心者にも太陽光発電投資はオススメできると回答した方には、その理由も伺いました。
■太陽光発電投資、だからオススメです!
・土地が余っているから(20代/女性/岡山県)
・日本は天気が良い日が多いから(30代/男性/香川県)
・イニシャルコストが不動産投資より安く済むから(40代/男性/千葉県)
・SDGsに貢献していない企業は市場で資金調達しづらくなる(50代/男性/神奈川県)
・環境の時代を先取りした投資だから(60代/男性/東京都)
イニシャルコストやリスクの低さを評価する回答も多いですが、ここでもやはり「環境」「資金調達」といった社会性に関する声がかなり集まりました。
コロナ禍以降、ひたすら利益だけを追求する姿勢に対して批判の目が向けられることが多くなっています。
こうした時代の変化も見据えて、投資家の皆さんは社会性の高い発電方法である“太陽光発電投資”をオススメしているのかもしれませんね。
【まとめ】withコロナ、そしてカーボンニュートラル時代は太陽光発電投資に明るい未来が!
今回の調査で、太陽光発電投資・不動産投資のいずれも経験している方からの貴重なご意見を伺うことができました。
太陽光発電投資・不動産投資に限らず投資にはリスクが付きものですが、今回の調査結果から考察すると、デメリットを上回るメリットを持つのは太陽光発電投資と言えそうです。
また調査では、初心者の投資先としても太陽光発電投資は優れている、と皆さんが考えていることもわかりました。
太陽光発電投資と不動産投資の双方を経験している皆さんだからこそ、太陽光発電投資のメリットの大きさを実感しているのかもしれません。
コロナ禍はしばらく続くことが予想されますし、同時に世界はSDGs推進やカーボンニュートラル時代に向けて着実に動いています。
そして、持続可能な社会を実現するためには、太陽光発電はなくてはならない存在です。
これから投資を始めようとお考えの方にとって、未来を見据えた太陽光発電投資を検討する価値は、とても大きいと言えるでしょう。
産業用太陽光・メガソーラー・中古発電所の日本最大級売却・購入サイト『とくとくファーム』
株式会社 和上ホールディングスが運営する『とくとくファーム』(https://wajo-holdings.jp/farm/)は、再生可能エネルギー投資をワンストップで始めることのできる、新・中古の太陽光発電売買サービスです。
和上ホールディングスグループのこれまでの実績と経験をもとに、お客様のご希望に沿った案件をご提案いたします。
太陽光発電所・用地の売買や賃貸は専門的な手続きの連続なので、スタッフと連携した無償税理士サポートもご用意しております。
また契約後は同グループ内のO&M事業とくとくサービスのアフターフォローおよびメンテナンスまで、一貫したサービスをご提供いたします。
【買いたい方】
★太陽光発電に関する全てのサポートが可能!
ご購入時の銀行紹介、税務のサポート、発電所のメンテナンスまでトータルでサポート。
他社と比較した上で、資産運用のベストパートナーをお選びください。
★経験豊富な専門スタッフによるスピード対応
とくとくファームでは、経験豊富な専門スタッフが多く在籍しています。
最短即日の物件紹介といったスピード対応もお任せください。
■買いたい検索はこちら:https://wajo-holdings.jp/farm/?searchbutton=%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B&csp=search_add&feadvns_max_line_1=5&fe_form_no=1
【売りたい方】
★即日査定!最短10日で現金化×売却益を残すための強力税務サポート
とくとくファームだからできる、査定専門スタッフによるスピード査定×弊社独自のとくとく査定システムにより、最短即日の明確査定、また、最短10日での現金化が可能です。
★残るお金は、税金対策で全く違う!?
あなたの利益最大化のための税務相談を無料で実施。
あなたの大切な資産を守るベストパートナーを目指しています。
■かんたん査定のお申し込みはこちら:https://wajo-holdings.jp/farm/contract/
先の見えない“withコロナ”の時代、そして持続可能な社会の実現に向けて、今、この時代に求められている再生可能エネルギー投資をワンストップで始めてみませんか?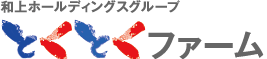
■とくとくファーム:https://wajo-holdings.jp/farm/
■お問い合わせ:https://wajo-holdings.jp/farm/contact/
■TEL:0120-409-522(24時間365日受付 営業時間10:00~19:00)
■株式会社 和上ホールディングス:https://wajo-holdings.jp/
調査概要:「太陽光発電投資と不動産投資」に関する調査
【調査期間】2021年8月13日(金)~2021年8月16日(月)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】505人
【調査対象】太陽光発電投資と不動産投資の経験者
預貯金4000万円で初めての不動産投資、業者との接触方法は?
【属性】
・神奈川県の私学教員43歳
・年収920万
・預貯金は4000万で有価証券、学資保険を含む
・借金は住宅ローン1730万のみ。58歳時点で返済終了
・持ち家有り。4000万円程度で売却可能
まだまだ初心者の域を出ませんが、知識が増えたところで、実際に業者に話を聞いてみたいと考えています。どういった業者とどういう形で接触するのが一番いいのでしょうか? 諸先輩方の意見と経験をお聞きしたいです。
・ネットで「不動産投資、神奈川、評判、いい」等で検索し、よさそうと思ったものにこちらから連絡をする
・町の不動産屋さんに飛び込みでお話を聞いてみる
・楽待で物件を検索し、いいと思った不動産に資料を請求する。ただ、どの物件も浅井佐知子先生や五十嵐未帆先生のストレスをかけたシミュレーションをすると、キャッシュフローが最初のうちは赤字になってしまいます
・楽待から送られてくるメールのセミナーに片っ端から参加して、この業者なら信頼できると感じるまで動き続ける
質問が支離滅裂で長くなってしまった気がしますが、どうやって最初の業者と接触するかを知りたいです。購入したい物件は「区分中古マンション、築浅一棟マンション、アパート・築古一棟マンション・アパート」など好みはありません。キャッシュフローが出ればOKと考えています。
■回答者:melm954938 さん
私ならこうするだろう、という「考え方」をお示しします。
(1)預貯金のうち、最悪なくなっても破綻しない「余裕資金」を区別する→学資保険を投資資金に計上している時点で失格です
(2)そのうち2000万円程度を、投資を考えている地域の信金に預ける
(3)必ず信金から「お尋ね」があるので、投資を考えていることを告げる。地域密着型の金融機関であるほど、相談に親身に応じてくれるでしょう
(4)信金に、投資用不動産で実績のある業者を紹介してもらう
そのほか、何点かアドバイスします。
・街の不動産屋と投資用不動産の業者は別モノです。同じ学校でも小学校と大学ぐらい違います
・不動産業者は「客に好感を持たれる」プロです。「よさそうと思った」「信頼できる」という思い込みで間違った投資をする人が後を絶ちません。彼らは「キャッシュフローが出ればOK」と考えている無知な小金持ちを狙ってセミナーを開きます
・投資する対象に基準を持ちましょう
・最良の投資への道は、実際に不動産投資で成功している先輩を見つけ、その人に教えを請うことです
・くれぐれも区分は止めましょう
スマホで不動産投資、おすすめサービスは?5社の特徴やリスクを比較
1.スマホで不動産投資をする2つの方法
不動産投資は、投資家が足を使って物件を探し、関連する業者と対面で交渉しながら行われていました。しかし、現在ではスマートフォンを使って、インターネットを介して不動産投資ができるサービスが提供されています。
不動産投資の新しい形として注目されている不動産投資型クラウドファンディング、少額から投資できる不動産投資信託(REIT)などは専用アプリやウェブサイトから投資可能です。
不動産投資に掛かる時間や手間などは、スマートフォンによって大幅に短縮されているといえます。以下よりそれぞれの仕組みや特徴、提供しているサービスについてご紹介します。
2.不動産投資型クラウドファンディングで投資する
不動産投資型クラウドファンディングとは、不動産の取得にかかる費用を多数の投資家から集め、投資金額に応じてリターンを分配する投資方法です。直接不動産を取得することはできないものの、サービスによっては一口1万円程度の少額で投資することが可能です。
また、実際の不動産運営や管理は運営事業者が行ってくれるため、投資をした後にほとんど手間がかからない特徴があります。不動産投資を手軽にスマートフォンで行いたい方にとって、検討しやすい投資方法と言えるでしょう。
スマホで不動産投資ができる不動産投資型クラウドファンディングサービスとして、ここでは下記3つのサービスを紹介します。
- WARASHIBE
- Rimple
- CREAL
2-1.WARASHIBE
WARASHIBEはLAETOLI株式会社が運営する不動産投資型クラウドファンディングです。
運営会社が不動産ファンド事業をメインに展開する不動産会社であり、投資用不動産に対する豊富な知識・ノウハウを生かして、厳選した投資ファンドを提供しています。
最低出資額は1万円で少額から投資でき、優先劣後方式によるリスクを抑えた投資が可能です。また、ファンドの運用途中での解約できる数少ないサービスの1つで、急な事情で現金が必要な場合でも、出資金を翌月には換金することができます。
「インカムゲイン重視型」「キャピタルゲイン重視型」など、ファンドのタイプによって利回りが4.5%~12.0%と異なるため、自分のポートフォリオに合ったファンドを選択しやすくなっているのも特徴です。
2-2.Rimple
Rimpleはプロパティエージェント株式会社が運営する不動産投資型クラウドファンディングで、スマホでの不動産投資が可能です。プロパティエージェント株式会社は東証一部に上場する不動産開発・販売を手掛ける企業で、都内で厳選した投資用マンションを対象にしたファンドを提供しています。
物件の運営・管理を運営会社が行うため、賃貸経営や投資に関する知識が乏しくても資産を運用できます。
Rimpleでは1口1万円の少額から投資できるほか、優先劣後方式によって投資家の出資金が保護される仕組みがあるため、投資に掛かるリスクが軽減されています。
また、「リアルエステートコイン」という独自のコインサービスを導入しており、1コイン=1円に換算して投資に利用できるほか、永久不滅ポイントなど他社のポイントをリアルエステートコインに交換して利用することもできます。
2-3.CREAL
CREALはクリアル株式会社が運営する不動産投資型クラウドファンディングです。個人では投資対象にするのが難しいホテルや学校、保育園などの施設にも1口1万円から投資できる点が大きな特徴です。
また、投資家からの出資金を分別管理されているほか、優先劣後スキームによって一定割合までの損失を運営会社側が負担するなど、投資家を保護する体制が整っています。
CREALでは、投資家への登録や投資案件情報の閲覧、投資の申込み、運用状況の確認といったすべての手続きや作業をスマートフォン1つで完結させられるため、手軽な投資を検討している方でも取り組み安いメリットがあります。
3.REIT(不動産投資信託)で投資する
REITは(リート)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)の略称です。また、日本国内で運営されているREITは、JAPANのJをつけてJ-REITとも呼ばれます。
REITは運営会社が投資家から資金を集め、その資金でオフィスビルやマンション、テナントといった不動産を購入し、購入した不動産の運用によって得られた利益を投資家に分配します。
法律上では投資信託の1つに数えられ、日本では2001年から証券取引所でREITの売買が行われるようになりました。
上場投資信託であるため、証券口座を開設することで購入することが出来ます。下記、REITの取り扱いがある主な証券会社をご紹介します。
- SBI証券
- 楽天証券
3-1.SBI証券
SBI証券は不動産に少額投資ができる不動産投資信託(REIT)の取引にも対応しており、国内REIT53本・海外REIT136本を取り扱っています。
また、Tポイントサービスと提携しており、取引ごとにTポイントを貯めたり、もらったりすることができるうえ、ポイントで投資信託を買付することも可能です。
3-2.楽天証券
楽天証券も不動産投資信託の取引に対応しており、国内海外含め112本のREIT銘柄を取り扱っています。
SBI証券と比較してREITの取り扱い銘柄は多くありませんが、ポイントプログラムが充実しており、楽天スーパーポイントを利用して投資信託や国内株式の現物取引を行えたり、貯まったポイントを他のサービスで利用したりすることも可能です。
3.各サービスを利用して不動産投資を行う場合の注意点
不動産投資を行う場合、必ずリスクが伴います。
今回紹介した5つのサービスは、それぞれ「不動産投資型クラウドファンディング」「不動産投資信託(REIT)」に投資を行えるサービスであるため、影響するリスクが多少異なります。それぞれ詳しくみていきましょう。
3-1.不動産投資型クラウドファンディングの注意点
不動産投資型クラウドファンディングに伴うリスクとしては、下記のものが挙げられます。
- 元本割れリスク
- 災害リスク
- 流動性リスク
- ファンドに応募できないリスク
不動産投資型クラウドファンディングでは、投資物件の運用次第では投資元本を毀損するリスクがあります。また、不動産を投資対象としているため、地震や台風、火災などによって投資物件が被害を受け、不動産価値や大きく下落するケース(災害リスク)もあります。
また一部のサービスを除き、多くの不動産投資型クラウドファンディングでは、運用期間内の途中解約ができなくなっています。このようなサービスには流動性リスクがあり、急な事情で手元にお金が必要になった場合でも、出資金を換金できない場合があります。
さらに、人気の高いサービスやファンドでは応募者が殺到し、応募したくてもできない場合があります。投資機会を得るために複数のサイトへ登録を行うなど、工夫が必要です。
3-2.REIT(不動産投資信託)の注意点
不動産投資信託への投資に伴うリスクとしては、下記のものが挙げられます。
- 価格変動リスク
- 金利変動リスク
- 災害リスク
- 倒産リスク
- 上場廃止リスク
不動産投資信託は、不動産市場や金利環境、経済情勢などの影響を受けることで、売却価格や配当金が変動するリスクがあります。配当を想定通りに得ていても、REITの基準価額が下落していると売却した時にトータルで損失の方が大きくなっているケースもあります。
不動産投資型クラウドファンディングと異なり、自由なタイミングで売買ができる一方、上場していることにより価格変動が起きる点に注意しましょう。
また、出資金以外に金融機関からの借入を行っているファンドでは、金利が変動することで収益に影響を及ぼす可能性(金利変動リスク)があります。
その他、不動産投資型クラウドファンディングと同じように、実物不動産が投資対象のため、災害リスクにも注意が必要です。
まとめ
今回はスマホで不動産投資ができるサービスについて紹介しました。かつて、不動産投資は手間と資金が必要なハードルの高い投資でしたが、現在では少額から投資できたり、スマホで完結したりする投資方法が登場しています。
しかし、手軽に不動産投資ができるようになったからといって、投資に伴うリスクがなくなったわけではありません。どのようなリスクがあるのかを理解したうえで、利用するサービスを検討してみましょう。
不動産投資CF「利回り不動産」で札幌市の新規ファンド公開、想定利回り6%
株式会社ワイズホールディングスは8月27日、少額・短期間の不動産投資商品を集めた不動産クラウドファンディング(CF)「利回り不動産」で新規案件「利回り不動産8号ファンド(メゾンクレスト中島公園)」の情報を公開した。募集金額495万円、最低成立金額440万円で出資は1口1万円から。募集期間は9月6日正午から9日午後11時59分。運用期間6ヶ月、予定分配率6.5%。匿名組合型で募集は抽選式、優先劣後関係は投資家90%(優先部分)、ワイズホールディングス社10%(劣後部分)となる。
対象物件は北海道札幌市中央区南十三条西1丁目の賃貸マンションで、交通は市営地下鉄南北線「幌平橋駅」徒歩5分、「中島公園駅」徒歩10分。敷地面積は約584㎡、建物は鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造で竣工は1990年2月、延床面積2392.31㎡、全体戸数64戸。専有面積は30.27㎡、バルコニー6.36㎡。「募集金額は少なめだが、札幌市の物件で、地域分散したい方に適したファンド」と同社。
利回り不動産は、1万円からできる不動産CFサービスで、今年7月13日から提供開始した。不動産物件を小口化し、少額かつ短期間で投資を開始することができる。開発や賃貸など不動産にまつわる様々な事業を展開してきたワイズグループが、より多くの人が気軽に、安心して投資活動を行えるサービスとして設計している。
ファンド型の共同出資で1万円から投資額を設定できるのため、ライフプランに合わせた柔軟な投資活動を行える。申込み手続きはウェブサイトで完結。不動産投資経験がなくても気軽に開始できる。優先劣後出資を採用し、運用終了時の不動産売却損失が生じた場合でも、投資家出資分が優先出資となり、同社出資分が劣後出資となり、劣後出資の範囲で優先的に損失を負担するため、投資家が出資した元本の損失をできる限り抑える仕組み。
会員登録はWEBサイトから行い、本人確認審査のため、確認書類(免許証など)を用意する。ファンドへの応募はサイトの「ファンド一覧」より行う。応募の際は、事前に「契約成立前書面」の確認が必要。ファンド成立時はメールで通知が届く。出資応募に当選した場合、契約成立時書面の確認をもって契約締結となる。投資する度に「ワイズコイン」が貯まり、コインは利回り不動産で出資する際に1コイン1円で現金と同様に使用できる。
8月31日まで、新規会員登録者全員にAmazonギフト券1000円をプレゼントするキャンペーン中。
不動産投資の法人化~給与を出すべきか否か~
1.給与を出す場合の問題点
法人を設立すると、代表者が1名だけであっても社会保険の強制加入となります。
よく「従業員5人未満なら社会保険の加入義務はない」と言う方がいますが、それは個人事業主の場合です。
法人の場合には、従業員の人数には関係なく加入の義務があります。
社会保険料の負担は、健康保険と厚生年金と合わせて、給与支給金額の約30%。
例えば、年収が500万円の場合の社会保険は、約150万円になります。
この保険料は、会社と従業員(役員)の折半で払うことになります。
給与金額の約15%(上記の例の場合、約75万円)が会社負担してくれるので、従業員にとっては非常によい制度とも言えます。
しかし、不動産投資家が法人化した場合は自分の会社(同族会社)なので、会社負担といっても自分が負担するのと変わりがないのです。
社会保険に加入すると、金銭的な負担が大きくなり、法人による節税メリットがなくなってしまうのです。

社会保険料を払わない方法として簡単なのは、給与を支給しないことです。
支払わなければ、社会保険に加入する必要はありません。負担もゼロです。
給与を支払わないと会社に利益が残ることになるため、法人税等がかかります。
しかし、資本金1億円以下の中小法人であれば、法人税の実効税率が低いため(課税所得800万円以下であれば、約24%)、社会保険に加入するよりも負担は少なくなります。
したがって、サラリーマンなどで勤務先の社会保険に加入している場合には、あえて給与を支給しない方がよいと言えます。
ちなみに、勤務先の会社と自身の会社で社会保険の加入になると、社会保険料の算定は、それぞれ払われた給与の合計金額によって行われます。
算定された保険料を、それぞれの給与額で按分して負担することになります。
2.非常勤役員になれるか
役員でも非常勤役員の場合には、社会保険の加入をしなくてもよくなります。
非常勤役員に給与を出しても、社会保険の負担はなくなります。
しかし、非常勤という名称で判断するのではなく「業務が経営の参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が経常的に支払いを受けるもの」であるかを基準として判断するとしています。
日本年金機構における疑義照会では、具体的な判断材料として下記を挙げています。
②法人における職以外に多くの職を兼ねていない
③法人の役員会等に出席している
④法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事している
⑤法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていない
⑥法人より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって、実費弁償程度の水準にとどまっていない
上記を満たさない場合には、社会保険に加入しなくてよい非常勤役員となります。
なお、上記は例示なので、実際には給与額も含めた実態で判断されます。
給与支給額が常勤と変わらないくらいの金額で支給されているのであれば、非常勤と判断されない可能性があります。
3.75歳以上かどうか

年齢が75歳以上になると後期高齢者保険制度に移行するため、社会保険には加入できません。
なお、厚生年金は70歳未満の方は加入の義務があります。
つまり、75歳以上は完全に社会保険の加入の義務はなくなります。
給与を出しても社会保険には影響しません。
しかし、給与の支給を多くすると、所得税・住民税の増加、後期高齢者保険料の増加、医療費・介護費の自己負担の増加につながる可能性があります。
支給するにも金額のバランスが必要となります。
4.国民健康保険料が高い場合
勤め先もなく、どこの社会保険にも加入しない(扶養にもならない)となると、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険料の計算は自治体によって若干変わりますが、前年度の合計所得金額から基礎控除を引いた金額を基準に算定されます。
配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除は考慮されないのです。
つまり、所得税は低くても、国民健康保険料は高く計算されることがあるのです。
国民健康保険料は世帯で計算され、上限額もあるため一概に高くなるとは言えませんが、社会保険料(厚生年金保険料を含む)の最低額(東京の場合)は、月額給与63,000円未満であれば、個人法人合わせて約28万円です。
給与支給額を少なくして、健康保険料を抑えることが可能です。
なお、60歳未満であれば国民年金保険料の負担はあります(一律年間約20万円)。
社会保険に加入する70歳以上の方は、厚生年金保険料の負担はありません。
家族全体でシミュレーションして、全体の保険料が抑えられるかどうかで判断しましょう。
画像提供:ピクスタ
アメリカ不動産投資、確定申告の手順は?必要書類や手順を詳しく解説
1.アメリカ不動産投資では、アメリカの確定申告も必要
アメリカでは、アメリカ国内で発生した所得に対して、外国人についても所得税の課税対象となります。したがって、アメリカの不動産の賃貸や売却による所得について、外国人でも確定申告をして納税することになります。
連邦所得税と州所得税の申告、納付手続きが必要となります。
1-1.連邦個人所得税の申告、納付
アメリカの不動産投資について、アメリカの連邦個人所得税の支払いは、源泉徴収方式あるいは、確定申告方式によることができます。
源泉徴収方式による場合は、テナントが家賃支払いの際にオーナーに代って、家賃の30%を源泉徴収して支払います。管理会社等に委託することを検討してみましょう。
確定申告方式による場合は、日本の場合と同様に、家賃収入から、固定資産税、支払利子、修繕費、管理費、維持費、保険料、仲介手数料、減価償却費などの必要経費を控除して、純利益を翌年4月15日までに申告し、これに累進税率を乗じた税額を納付することとなります。
手順の基本的な流れは、日本の場合と同様ですが、たとえば、課税所得の計算において、控除が所得調整控除と項目別控除の2段階になっているなど、税金計算の仕組みが日本と異なります。
申告、納付をする際は、アメリカ税務に詳しい国際税務を扱う税理士などの専門家に依頼することを検討してみましょう。
1-2.州個人所得税の確定申告
アメリカの不動産投資では、連邦個人所得税以外に、不動産が所在する州に対して、翌年4月15日までに所得を申告し、州個人所得税を納付する必要があります。
州個人所得税は、州ごとに大きく異なりますが、源泉徴収方式によることはできず、確定申告をおこなうことが基本となります。
2.アメリカ不動産投資、日本での確定申告の手順
アメリカ不動産投資の場合であっても、日本でおこなう確定申告は、基本的に日本国内で不動産投資をおこなっている場合と同様となります。日本国内の居住者に該当すれば、国内外において生じた全ての所得について課税対象となるからです。
不動産投資で発生する家賃収入は、不動産所得として所得税と住民税がかかります。税金のかかる不動産所得がいくらなのか、毎年、税務署に対して確定申告をおこなう必要があります。
不動産所得は、「不動産収入―必要経費」によって算出されます。税金は、収入総額に対してかかるのではなく、必要経費を控除した後の利益に対してかかってくるため、この必要経費を漏らさずに計上することが重要になります。
また、サラリーマンなど、不動産所得以外の所得がある人は、給与所得などの他の所得と不動産所得を合算し、その合計額から所得控除を差し引いて、所得税の課税対象となる所得を計算します。
これらを踏まえ、確定申告の手順は大まかには下記のような流れになります。
- 必要書類・環境を整える
- 不動産所得の帳簿を作成し決算をおこなう
- 所得税の確定申告書を作成・提出する
- 所得税・住民税を納税する
それぞれの手順を詳しく見て行きましょう。
2-1.必要書類・環境を整える
まず、確定申告に必要な書類を整えます。家賃収入があって確定申告をおこなう不動産投資家であれば、確定申告書(B様式)と収支内訳書もしくは青色申告決算書を提出することになります。
海外不動産投資の申告では、外国税額控除に関する明細書の作成も必要になります。これらの書類を作成するために必要な書類を準備します。自分で申告をおこなう場合は、税務署で所定の様式を揃えておくとよいでしょう。
環境については、確定申告の手続きの一部を自分でおこなう場合に準備が必要になります。帳簿の作成を自分でおこなうのであれば、会計ソフトとパソコン、ネット環境が必須です。会計ソフトで帳簿を作成すると、税務署に提出する書類まで一通り作成することが可能です。
収入に関する書類の収集
収入帳や預金出納帳などの収入に関する帳簿を作成するために、家賃の入金されている通帳や管理会社が発行する家賃明細などを収集する必要があります。
必要経費に関する書類の収集
現金出納帳、経費帳などの必要経費に関する帳簿を作成するために、管理費や修繕費の領収書などが必要になります。
所有不動産の固定資産台帳を作成するために、所有不動産の購入時の売買契約書なども必要になります。
他の所得や所得税の控除に関する書類の収集
所得税の確定申告書(B様式)を作成するために、給与所得の源泉徴収票などの不動産所得以外の収入明細が必要です。また、所得控除に関する書類として、医療費の領収書や寄附金の領収書などが必要になります。
なお、社会保険料や生命保険料、地震保険料も控除対象になりますが、サラリーマンであれば年末調整で調整済なので、源泉徴収票を用意すれば充分です。
会計ソフト、ネット環境などの準備
上述した帳簿は、会計ソフトを利用することで作成可能です。会計ソフトにはPCにインストールするタイプと、ウェブブラウザで起動・操作するクラウドタイプがあります。
小規模の不動産所得であれば、ソフトを使わずにエクセルで帳簿を作成して集計することも可能でしょう。いずれにしても、帳簿作成を自分でおこなうのであれば、PCとネット環境が必要になります。会計ソフトもできれば用意しておくことも検討してみましょう。
青色申告の65万円控除を受けるために、e-Taxで電子申告をおこなうというのであれば、マイナンバーカードとカードリーダーも必要になります。
2-2.不動産所得の帳簿を作成し決算をおこなう
必要書類・環境を整えたら、不動産所得の収支内訳書もしくは青色申告決算書を作成します。
そのために、不動産所得の収入帳や経費帳などの帳簿を作成、整理して一年分の収入と経費の集計をおこないます。この一年分の集計をおこなって収支内訳書もしくは青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)を作成する作業を「決算」と呼びます。
以下、簡易帳簿の作成と決算手続き、収支内訳書もしくは青色申告決算書の作成方法について説明します。
なお、令和3年分の確定申告より、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設され、国外不動産の減価償却費の計上によって生じる国外不動産所得の損失は、不動産所得内および、他の総合課税の所得との損益通算ができなくなっています。(※参照:財務省「令和2年度税制改正の大綱:3 租税特別措置等」)
簡易帳簿の作成と決算
不動産所得の簡易帳簿を作成して決算をおこなう場合、青色申告の届出を提出することで、不動産所得から10万円を控除することができます。簡易帳簿とは、現金出納帳、収入帳、経費帳、固定資産台帳のことを指しています。
現金出納帳は、不動産貸付用の現金の出し入れの状況を取引順に記載する帳簿です。現金で支出した必要経費は、現金出納帳に記載します。家賃収入が預金口座に入金される場合、預金出納帳を作成して記載していきます。
収入帳には、家賃収入を取引ごとに記載します。入金ベースではなく、賃貸借契約ベースで未収家賃も記載していきます。
経費帳は、不動産の貸付けに関する必要経費を、必要経費の科目ごとに分けて記載、集計する帳簿になります。
固定資産台帳は、不動産貸付用の建物や附属設備などの取得費用を、減価償却費として各期間の必要経費に配分していく計算をする帳簿になります。
アメリカ不動産投資では、収入や経費の計上の際、円換算することが必要となります。レートは原則、取引日の仲値を用います。物件を継続保有する場合は、収入は買い相場、経費は売り相場の金額を用いることも可能です。
決算では、未収家賃や未払経費、減価償却費の計上をおこなってから、一年分の簡易帳簿を集計して、収支内訳書や青色申告決算書に転記していくことになります。簡易帳簿による場合、損益計算書の作成のみとなり、貸借対照表は作成しません。
複式簿記による帳簿の作成と決算
不動産所得の帳簿を複式簿記によって作成して決算をおこなう場合、青色申告の届出を提出することで、不動産所得から55万円を控除することができます。
複式簿記とは、取引を、現金と資産の増減という二つの側面(貸方と借方)から記録することで、網羅性・検証可能性・秩序性を備えた帳簿を作成する方法です。正規の簿記の原則を満たす条件でもあります。
作成する帳簿としては、上記の簡易帳簿に加えて、仕訳帳と総勘定元帳になります。仕訳帳とは、すべての取引を日付順に、二つの側面から記録した帳簿です。
一方、総勘定元帳とは、すべての取引を科目ごとに並べて集計した帳簿です。収入、必要経費、資産、負債などのすべての項目ごとに作成することになります。決算でおこなう集計の調整は、簡易帳簿の場合と基本的には同様です。
手間を考えると、複式簿記による帳簿を作成するには、会計ソフトを利用すると良いでしょう。多くの会計ソフトでは、帳簿の作成と同時に決算をおこなった集計結果を青色申告決算書の様式に出力することができます。
複式簿記による決算では、貸借対照表と損益計算書という2種類の決算書を作成します。複式簿記による決算をおこなうには、簿記の専門知識が必要になるため、税理士などの専門家に任せることも検討するとよいでしょう。
2-3.所得税の確定申告書を作成・提出する
不動産所得の決算書の作成が終了したら、所得税の確定申告書(B様式)を作成します。
確定申告書は、決算で集計した不動産所得の金額や給与所得の金額を集計し、社会保険料控除、医療費控除などの各種控除の金額を控除して、所得税のかかる所得を算定し、実際の所得税額の計算をおこなう書類です。
アメリカ不動産投資の申告では、外国税額控除に関する明細書の作成も必要になります。海外で納付した所得税がある場合、一定の算式により計算した金額を外国税額控除として、所得税および復興特別所得税から控除することができます。
これらの申告書類は、通常は、会計ソフトや税務ソフトに情報を入力して作成することがほとんどです。作成の際には所得税の知識が必要になります。
すべての書類を作成したら、管轄の税務署に提出します。提出方法は、直接持参するか、郵送、あるいは電子申告であればインターネットで送信することによって提出します。所得税の確定申告書等の提出期限は、翌年の3月15日となります。
2-4.所得税・住民税を納税する
書類の提出と納税は別々におこないます。所得税は、納税の期限が3月15日になっており、確定申告書等の提出期限と同じです。現金で支払う場合は、納付書を用いて金融機関等で納めます。口座振替の手続きをすれば、口座振替も可能です。そのほか、クレジットカード納付やコンビニ納付などもできます。
住民税は、確定申告の情報を下に、それぞれの市区町村が税額を計算し、6月以降に納付書を送ってきます。サラリーマンであれば、特別徴収という形式で勤務先企業が給与所得から天引きして納めてもらっています。
なお、普通徴収といって住所に納付書を送ってもらい自分で納めることも可能です。普通徴収であれば、通常は4回の分割払いになります。
3.アメリカ不動産投資に強い税理士の探し方
税理士によって得意な分野は異なり、その費用も依頼先の税理士事務所によって異なります。複数の税理士と面談を行い、費用や受けられるサービスの質などを比較してみましょう。特に、アメリカ不動産投資のような海外の確定申告を行う場合、実施経験があったり、現地の税法について詳しい税理士への依頼を検討することが大切です。
効率的にアメリカ不動産投資に強い税理士を探すには、税理士紹介サイトを利用する方法があります。税理士紹介サイトでは、コーディネーターが、相談者のニーズに合った税理士をピックアップし、面談を調整してくれます。税理士との依頼内容の調整や、料金交渉などもコーディネーターに任せることが可能です。
税理士ドットコム
税理士ドットコムは、全国5,900名の税理士の中から無料で希望に沿った税理士を紹介してもらえるウェブサービスです。複数の税理士を比較することができるうえ、「費用はいくら?」「どんな税理士を選ぶべき?」といった税理士を選ぶ際の相談も可能となっています。
報酬引き下げの実績も豊富なため、すでに税理士と契約している方でも利用が可能です。コーディネーターが複数の税理士に相見積りをとり、費用についての交渉までサポートしてくれます。
利用時の主な注意点としては、提携している税理士の紹介しか受けられない点です。提携外の税理士も比較していきたい方は、自身で探してみたり、不動産会社に相談してみたりなどと並行して、利用を検討すると良いでしょう。
まとめ
アメリカ不動産投資で必要となる日本の確定申告手続きは、基本的に日本国内の不動産投資と同様です。
異なるポイントとしては、円換算が必要となること、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が適用されること、外国税額控除に関する明細書の作成提出が必要であること、であるといえます。
また、アメリカでの連邦個人所得税、州個人所得税の申告、納付が必要となる点にも注意しましょう。
連邦個人所得税は源泉徴収方式によることも可能ですが、州個人所得税は確定申告が必要となります。国際税務専門など、アメリカ税務に詳しい税理士などに手続きを依頼することを検討してみましょう。
国内の確定申告についても税法の取り扱いは複雑であり、税制改正も毎年おこなわれるため、誤った申告をしてしまうリスクは低くありません。判断に迷ったときや、実際に確定申告をおこなうときは、税理士などの専門家に相談することを検討してみましょう。
不動産投資型CF、東京以外の物件に投資するメリット・デメリットは?
1.不動産投資型CFとは
不動産投資型CF(クラウドファンディング)とは、一般の投資家からの出資金を利用して不動産の取得・運用を行い、得られた利益を投資家に分配する投資商品の1つです。
現物の不動産投資では、不動産の取得に多大な資金が必要になるうえ、物件の管理・運営を投資家自らが行う必要があります。
一方、不動産投資型CFでは最低1万円程度の少額から投資できるうえ、クラウドファンディング事業者が物件の管理・運営を行うため、投資に掛かる手間を省くことができます。
なお、ファンド型の不動産投資ができる投資商品には、REIT(不動産投資信託)があります。不動産投資型CFでは投資物件を投資家自身が選択できるのに対し、REITでは投資する信託商品の投資割合を事業者が選択するため、投資家が投資物件の選定を行うことはできない、といった違いがあります。
2.不動産投資型CFで東京以外の物件に投資するメリット
不動産投資型CFで東京以外の物件に投資する場合、下記のメリットがあります。
- 想定利回りが比較的高い
- 一部の地方都市は地価上昇率が高い
- 少額から投資できる
- 分散投資ができる
2-1.想定利回りが比較的高い
サービスによって異なりますが、東京都の物件を対象にしたファンドと比較して、地方の物件を対象にしたファンドの方が、想定利回りが高く設定されているケースが多いといえます。
不動産を購入するための価格を比較した場合、東京よりも地方の購入価格が少なくて済み、家賃収入によっては想定利回りが高くなるためです。
国土交通省の「令和2年都道府県地価調査」で発表された「住宅地の都道府県別価格指数」をみると、東京と比較してすべての道府県で価格指数が低くなっています。東京の平均価格指数を100とした時、2位の神奈川で47.4、3位の大阪で39.9と、大きな差があることが分かります。
なお、これらのデータは県内の平均価格を比較したものであり、地方都市の中でも一部のエリアにおいて東京と変わらない高水準の家賃帯となっているケースもあります。そのため、家賃水準が高い地方都市の不動産を対象にしたファンドでは、取得費を安く抑え、想定利回りが水準よりも高くなることがあるのです。
2-2.地価上昇している地方都市もある
東京だけではなく、地価が上昇傾向にある地方都市があります。国土交通省が発表している「土地白書」によると、令和2年の地価変動率(前年比)は全国で+0.8%、三大都市圏(東京・大阪・名古屋)で+1.1%、地方圏で+0.5%となっています。
ファンドの投資不動産を売却する際に、購入時よりも地価が上昇している場合、キャピタルゲインを期待しやすくなります。投資前には、対象不動産の地価推移についても注意してみましょう。
2-3.少額から投資できる
現物不動産に投資する場合、数百万円~数千万円以上の資金を調達する必要があり、投資規模の大きさから、運用に失敗してしまった時の損失も大きくなるというリスクがあります。特に地方都市の場合は地価下落リスクが高く、大規模な投資を行ってしまうとハイリスクになりすぎてしまうデメリットがあります。
不動産投資型CFでは、地方都市の不動産でも1万円~数十万円から投資できるため、現物不動産よりも投資に対するハードルが低く、リスクを限定的にできるメリットがあります。
2-4.分散投資ができる
東京の不動産にだけ投資している場合、台風や地震などの災害が発生すると投資物件すべてに影響する可能性があります。そのため、不動産へ投資する際は、できるだけエリアを分散した投資を心がけておくことも重要なポイントです。
不動産投資CFでも、一つのエリアだけでなく、複数の地域の不動産に投資することで分散投資ができます。東京の不動産と距離が離れた地域の不動産の両方に投資することで、災害リスクを軽減することができます。
3.不動産投資型CFで東京以外の物件に投資するデメリット
一方で、不動産投資型CFで東京以外の物件に投資する場合には、下記のデメリットも考えられます。
- 空室リスクが高い
- 家賃相場の下落リスクが高い
- 流動性が低い
3-1.空室リスクが高い
地方都市の不動産に投資する場合、空室リスクが高くなるというデメリットがあります。
不動産投資においては、賃料収入と物件の売却益を得られることで利益が発生します。そのため、人が集まる立地を選ばなければ需要を見込むことはできません。
空室リスクはすべての不動産投資に伴うリスクではありますが、人口が流出しやすい地方都市では特に賃貸需要が減少傾向にあるエリアも多く、東京と比較して空室リスクは高くなってしまうデメリットがあります。
これから始めて不動産投資型CFを始める初心者の方は、マスターリースによる賃料保証がある案件や、運用期間の短い案件を選ぶなど、リスクを抑える工夫をしてみましょう。
3-2.家賃相場の下落リスクが高い
地方都市の不動産に投資する場合、家賃相場が下落するリスクも高くなるというデメリットがあります。
地方都市は東京や大阪、福岡などの都市圏と比較して人口が少ないため、景気が悪化した際の影響を受けやすくなります。
また、先述したような賃貸需要が少ない地方都市の場合、入居者を確保するために相場よりも家賃を下げざるを得なくなることもあります。空室リスクと同様に賃料収入に関わるため、案件を選択する際は慎重に検討しましょう。
3-3.流動性が低い
地方都市の不動産は東京と比較して買い手が少なく、流動性が低いというのもデメリットです。
特に、賃貸不動産の流動性は人口が増加している都市で高くなり、減少している都市で低くなります。人口が増加している地方都市もありますが、大半の地方都市では人口が減少しているため、物件を売却する際の買い手が付きにくくなります。
売却益を想定利回りに加えた案件の場合、想定価格での売却ができないと、最終的な投資家へのリターンに影響する可能性があります。買取保証が付いているか、その場合の利回りはどのように変化するのか、事前に確認しておきましょう。
4.東京以外の物件に投資できる不動産投資型CFサービス
東京以外の投資物件を紹介している不動産投資型CFには下記のようなものがあります。
- WARASHIBE
- CREAL
- 信長ファンディング
- TSON FUNDING
4-1.WARASHIBE
WARASHIBEはLAETOLI株式会社が運営する不動産投資型CFで、東京都以外に神奈川県や静岡県の不動産に投資することができます。
LAETOLI株式会社は不動産ファンド事業をメインに展開する企業で、投資不動産に関するノウハウを豊富に持ち合わせており、厳選された投資不動産に対して1口1万円の少額から投資できるのが特徴的です。
インカムゲインをメインにしたファンドでは4%~6%、キャピタルゲインをメインにしてファンドでは100%を超える利回りとなったものがあるなど、ファンドの種類によっては高い利回りを期待できます。
詳細な物件情報を手に入れられるほか、優先劣後方式によるリスク対策や途中解約ができるなど、投資家の資産を守りやすくなっているのもWARASHIBEの特徴といえます。ただし、案件によっては手数料の支払いが発生するケースがあるため注意しておきましょう。
4-2.CREAL
CREALはクリアル株式会社が運営する不動産投資型CFです。居住用物件や保育園、学校、ホテルなどさまざまな種類の物件・施設を投資対象にしており、東京都、福岡県、山梨県、沖縄県、千葉県の不動産に投資できるファンドを提供しています。
不動産投資における情報の不透明さをクリアにすることをコンセプトにしており、各ファンドの投資対象別件の内容が詳細に記載されているのが特徴です。
1口1万円からの少額投資が可能であり、優先劣後スキームによって損失から投資家を守るためのシステムが採用されているなど、リスクコントロールを優先しながら投資したい方に向いているサービスとなっています。
4-3.TSON FUNDING
TSON FUNDING(ティーソンファンディング)は愛知県名古屋市に本社を構える株式会社TSONが運営する不動産投資型CFで、愛知県内の不動産物件をメインに東京都や埼玉県に不動産に投資できるファンドを提供しています。
運営会社が不動産事業や関連事業を展開していることを活かして、月に1回のペースでファンド組成をしています。
ファンドにはキャピタルゲイン型とインカムゲイン重視型の2種類があり、投資家のポートフォリオに合わせて選択できるのが特色です。
1口1万円からの少額投資が可能で、優先劣後方式によるリスク対策や手数料を支払うことで途中解約による現金化が可能であるなど、投資がしやすい環境が整っているほか、運営会社が上場している点も特徴的です。ただし、譲渡・解約事由によっては譲渡・解約を断られてしまうケースもあるため注意しましょう。
4-4.信長ファンディング
信長ファンディングは、愛知県名古屋市に本社を構える株式会社ウッドフレンズが運営する不動産投資型CFです。
「尾張発の不動産投資クラウドファンディング」をうたっており、愛知県や岐阜県など東海エリアの不動産ファンドを提供しています。また、不動産によるESG投資をテーマに掲げ、国産の資材を積極的に活用するなど、独自の取組みを行っています。
最低投資額は1口10万円となっていますが、運営会社がJASDAQと名古屋証券取引所に上場している点や、優先劣後方式を採用している点などから、リスクを軽減しながら投資した方に向いているサービスといえます。
まとめ
今回は不動産投資型CFで東京以外の物件に投資するメリットやデメリットについて紹介しました。
不動産投資型CFでは、東京の投資案件がまだまだ多く、地方物件への投資機会は少ない状況と言えます。しかし、地方都市の物件に投資できる案件も少しずつ増えており、高い想定利回りや投資エリアを分散し、投資の分散効果を期待することができます。
また、地方ファンドは投資機会が少ないことから募集と同時に目標額に達してしまい、投資をしようと思ってもなかなかできないことも少なくありません。各サービスの投資家登録を早めにすませておき、募集時に素早く検討できるよう準備しておくと良いでしょう。
20歳で不動産投資家になる決意、22歳で購入。2年かけて自分で改修した物件に入居希望者殺到
20歳で不動産投資家になろうと決意、22歳で物件を購入、2年間自分で住みながら手を入れ、24歳で完成した2階を賃貸に出した加藤達也氏。半分を貸しただけだが、それで表面利回りは8.6%。これが第一歩で、まだまだこれからという加藤氏に話を聞いた。
会社員にはなりたくない、
だから不動産投資を
加藤氏が不動産を購入しようと決意したのは20歳の時。大学受験に2度失敗、これからをどうしようかと考えて図書館で様々な本を読み、真剣に考えた結果だ。

「しょっちゅう遅刻するので会社員としては働きたくないと思いました。遅刻が問題にならない仕事は何かと考えた時に思いついたのは大家さん、不動産投資家でした。そこで投資に関する書籍を読み、何がリスクになるのかを考えました。その結果、入居者を獲得するためにはきれいで他物件との違いがあれば良いと思うに至ったのですが、それを実践として考えるとリフォームが大事だなと。そこでハローワーク経由でリフォーム訓練校に通うことにしました」。
自分で物件をいじれれば出費を抑えられるし、大工は80歳、90歳になってもできる仕事である。技術を身につけておいて損はないと考えたのだ。
そこで半年ほど通って基本を身に付けたところで、縁があって工務店に勤務することに。そこでも遅刻はしょっちゅうだったそうだが、その分、手は早かったと加藤氏。
「遅刻するので働く時間は短くなりますが、その分、時間内にやり遂げられるよう、作業効率よく仕事しようと考えました」。
購入したのは
無接道の空き家、650万円
その会社には3年勤務したが、勤務して1年目に物件を購入した。根岸線山手駅から歩いて8分、横浜市中区にある、現在トトノン山手として貸している木造2階建てのアパートで、本体価格は650万円。諸経費などを入れて700万円ほどで手に入れたという。

駅からの距離、住所だけ聞くと一等地と思うが、価格から分かるように難がある。山手は高台はお屋敷街で立派な住宅が並ぶが、急坂の多い凸凹な土地で坂の下では風景が異なる。
小さな区画に小規模な古いアパート、一戸建てが並んでおり、そのうちには空き家も多数。加藤氏が購入した物件も数年以上は誰も住んでいなかったらしく、雨漏りがひどかったそうだ。

加えて無接道である。公道からしばらく私道を入り、物件までの最後の部分は人ひとり通るのがいっぱいという幅。工務店関係者、不動産関係者からはどうしてこんな物件を買った!と怒られるやら、非難されるやらだったそうだ。
購入後は自分で住み込み、2年をかけて改修をした。雨漏り、水道本管の引き直しなどもあったが改修費は200万円まではかかっていないという。もちろん、自分でやったので本来ならかかる人件費もゼロという計算になっている。かなり大変だったようで、「次回は人を入れて一緒にやりたいですね」とも。
設備類は
ヤフオク、メルカリで安く購入
面白いのは設備類の購入。ヤフオク、メルカリなどをフル活用して、ホームセンターで買うよりはるかに安く手に入れているのである。たとえば2階は元々風呂無しの2室があったのだが、それを1室にして水回りを設置しており、そこに入れたトイレはメルカリで新品を購入。4万円ほどだったという。

また、ユニットバス、給湯器はヤフオクで購入。ユニットバスは新品で11万円ほど、給湯器は中古だったが3万円ほどで、それ以外の工具その他を含めて全体で16万円前後だったという。

ひとつ、失敗したと思ったのは1階のトイレで、こちらは最新に近い機能の付いた商品で中古で5万円。それ自体は安いのだが、購入後に基板の修理が必要であることが判明、それに3万円ほどかかったという。中古品の場合、修理が必要だと高くつく可能性もあるわけだ。
ちなみにこうしたネットオークションは店と違い、いつでも欲しい品が揃うわけではないものの、1週間も見ていれば欲しい品が出てくることが多いのだとか。急に必要という場合には向かないかもしれないが、1週間かそこら待つ余裕があれば問題はなさそうだ。
また、分からない作業についてはYouTubeを参考にしたという。たいていの作業の動画はアップされているので、それを参考にすればかなりのことができるそうである。
黒い部屋にプロは疑問、
ユーザーは殺到
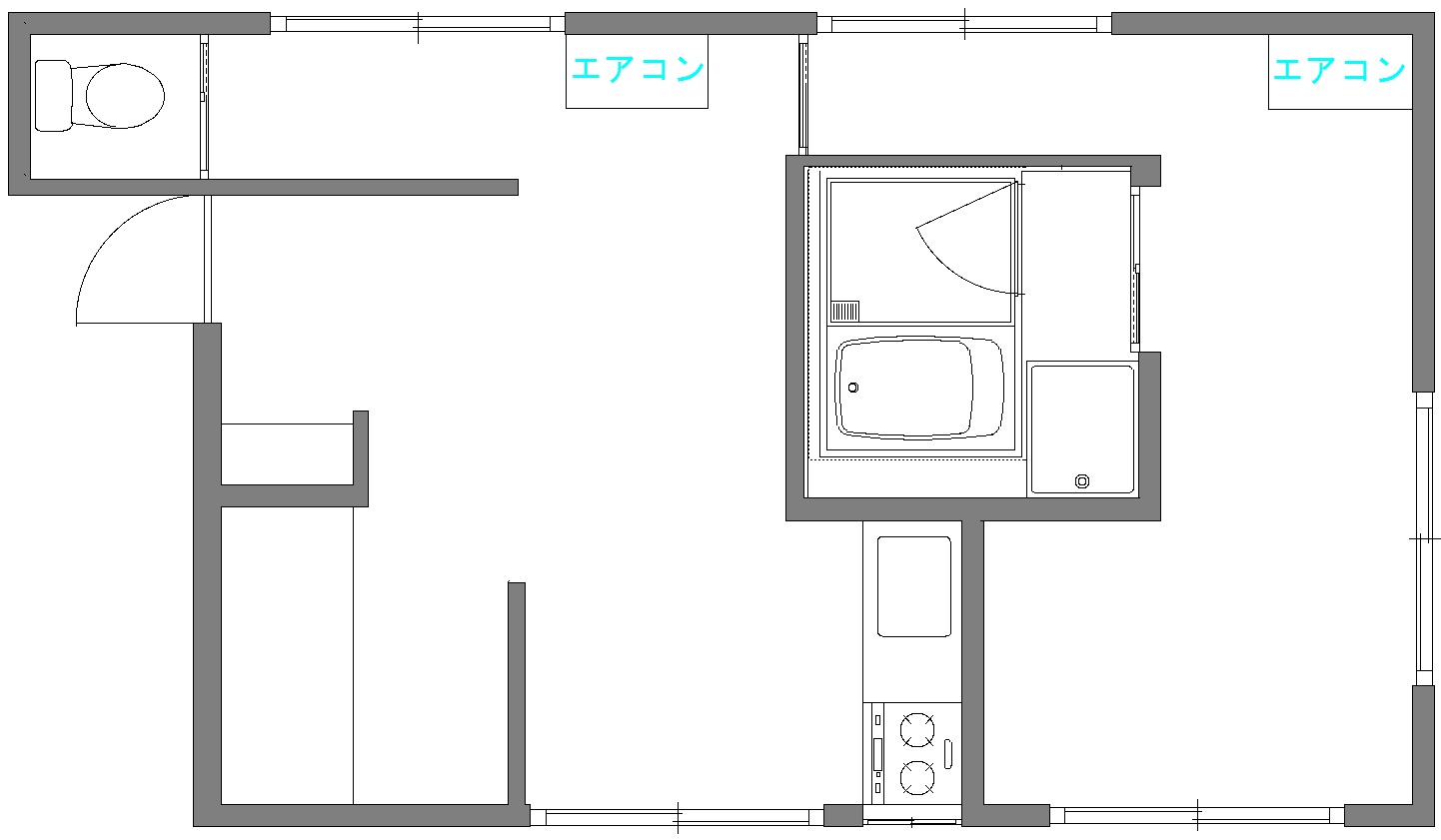
そして完成した2階の部屋は33㎡の2DK。入ったところにDKがあり、キッチン、水回りを挟んでもう1室というもので、黒い内装にオレンジの建具、水色のトイレと個性的なカラーリングが印象的。外装にも黒を使っているのだが、これも不動産等のプロからは不評。こんな部屋で借り手がつくのかと言われたという。



だが、消費者はこの部屋に殺到した。募集を担当したオリエンタルサンの山田武男氏によると募集開始以降電話が鳴りやまず、問い合わせが15件、内見が4件あり、うち一目惚れしたという女性が借りることになった。募集開始から入居までで1カ月ほどである。

「物件そのもののビジュアルが非常に映えることに加え、水道、ガス代が賃料に込みであること、坂が大変なことを見越して電動自転車をプレゼントするとしていたこと、この3点が他との大きな違いとなり、あっという間に決まりました。他と違う物件を作ることの強さを実感しましたね」。

賃料は6万5000円。物件価格700万円に改装材料代200万円(実際にはそこまではかかっていないそうだが)を足した900万円で6万5000円の賃料を考えると、表面利回りは8.6%。半分しか貸していないのに、良い数字である。
滞在して修理という手段
ちなみに最初の資金は親から借りたという。大体の場合、1軒目の投資は資金をどうするかがもっとも大きなハードルになることを考えると、その点は非常に恵まれている。
だが、1軒目をクリアできればそれが次の投資への大きな助けになることを考えると、若いうちの投資なら親に頼るのも手ではなかろうか。
加藤氏は現在、会社は辞めているものの、月に数回、声をかけてもらって仕事をしているそうで、「それほどお金を使うタイプではないので、家があり、多少の仕事があれば十分暮らしていけます」とのこと。
加えて今月からしばらくは訓練校時代の先生に言われて、使われていない別荘のリフォームをしに行くという。
滞在しながらの工事とのことで、今回は他人の所有する不動産だが、以降自分が所有して滞在、手を入れて貸すというやり方を繰り返せば、資産を増やしていくことも十分可能。自分で体を動かすことが苦にならないのであれば、この手は十分あり得るのではなかろうか。
健美家編集部(協力:中川寛子)
不動産投資、「東京のワンルーム」がコロナ後も「安全」と言えるワケ
人気の高いマンション投資・マンション経営
2020年、コロナ禍は私たちの生活を大きく変えた。特徴的なのは、テレワークの普及などにより、郊外へ移住する動きが増えたことだ。「都心・駅近」物件やタワーマンションの価格が過熱しすぎたこともあり、ファミリー世帯がそれを避ける傾向も見られる。
とはいえ、都内の一戸建てやワンルームマンションなど、東京エリアの住居用物件は依然として非常に人気が高い。それはつまり、不動産投資のチャンスがまだまだ眠っているということだ。
1990年の創業以来、30年以上にわたり、東京エリアの不動産投資・マンション経営を提案・サポートする明光トレーディング。専務取締役の立花秀一氏は、自身でも東京のワンルームマンション経営で「自己資金ゼロ」からの資産形成・運用を実践してきた。
 明光トレーディング専務取締役の立花秀一氏
明光トレーディング専務取締役の立花秀一氏立花氏は、マンション経営は投資初心者でもまったく難しくないと、経験から語る。
「マンション投資やマンション経営は大変なんじゃないかと言う方もいらっしゃるんですが、基本的には『ほったらかし投資』です。一部屋単位で保有して、部屋の中は賃貸管理会社、建物全体の管理は建物管理会社にすべておまかせでOK。
ご多忙な会社員、公務員、医師・医療従事者の方、会計士や税理士などの方が、株式投資などと併行して取り組んでいます。
始めるにあたって、まずは『何のためにやるのか?』を意識してください。あくまでも長期的な『将来の年金プラス家賃収入』が目的・ゴールです。年金や、預貯金を切り崩すだけで『ゆとりある老後生活』は難しいです。必ず現役時代からの『自助努力』が大切になります」
なぜ「東京」の「ワンルーム」なのか
「『東京』の『ワンルーム』マンション投資をご提案しているのは、不動産投資の中で最もリスクが低いタイプだからです。その理由として、物件が空室になっている期間が、非常に短いことが挙げられます。
総務省による統計(2019年)を見ると、東京都の転入超過は約8万人、東京圏で約15万人となっています。愛知県、大阪、福岡などの都市以外は、転入よりも転出が多いのです。それを加味しても、東京エリアの人気は圧倒的です」
「今度は東京都のデータですが、1995年のデータから見ても都内の単身世帯は年々増えていて、2040年には東京都の総世帯数の54.4%が単身世帯になるという予測もあります。
それに加えて、東京のワンルームマンションは、ストックの数と毎年の新規供給数が足りていません。もともと東京は余っている土地が少ない東京ですし、築年数が経過しても資産価値が下がりにくいのです。
また、大手ポータルサイト『アットホーム』のデータで、ここ数年の東京都のワンルームマンションの賃料の推移を見ると、最近のコロナ情勢でも変動が少なく、 むしろ中長期的には緩やかな上昇傾向にあります。こうしたことからも、大きな値崩れはしにくいと言えるでしょう」
なぜ30代・40代の社会人が「自己資金ゼロ」で?
それでもやはり不動産投資には、ある程度まとまったお金を持っていないと実践できないというイメージが私たちにはある。なぜ、30代・40代の社会人でも「自己資金ゼロ」で始められるのか。立花氏は現役世代だからこその「強み」を解説する。
「社会人の最大の武器は『信用力』です。会社員の場合は、勤めている会社の信用力なんですね。その信用力に応じた与信枠をうまく利用し、他人資本、すなわち金融機関からお金を借り、マンション経営ができる。実はこれはすごい特権です。
そして借りたローンは、自分ではなく物件を借りている人の家賃を元手にして返済します。つまり、他人資本を他人の資力で返済する、この仕組みが不動産投資の大きなメリットだと考えています。
10年、20年と家賃からローン返済を進めていくと、必ず残債が減っていきます。私もすごく実感しているのですが、自分で減らしているわけではないのに『純資産』ができていく。これが『貯蓄効果』です。
もちろん最終的には『ローンのないマンション』から家賃収入を得ることが目的ですが、仮にその前に売却したとしても、残債が減っていれば十分に利益が出ます。すべての投資は、一般的に長く取り組むほど安定した利益が期待できますが、マンション経営はその中でも特に『負けない投資』なのではないかと思います」
「信頼できるパートナー」の重要性
不動産投資の場合、インフレや地価の下落など、先の見えない要素を読みきらなければならないイメージがある。だが、都心のワンルームに投資対象を絞れば、老後資金を見据えた長期的な運用でも、ある程度リスクは回避できるというわけだ。
ではそうなると、不動産投資の明暗を分けるポイントはどこにあるのか。立花氏は次のようにまとめる。
「まず家賃と資産価値が安定した物件、立地を必ず選ぶことです。もうひとつ重要なのは、信頼できるパートナー、賃貸管理会社を選ぶこと。有利な提携ローンで資金計画を提案できるかどうか、賃貸管理がしっかりしているかどうか、さまざまなリスクに対応してくれるかどうかが大切です。
ローンを組む金融機関や賃貸管理会社、もっと言えば、入居者もパートナーです。ある意味、購入した物件もひとつのパートナーでしょう。そのチームがみなさまの資産を作っていくということになります。そのため、しっかり選ぶ必要があります。
マンション経営に難しいスキルは必要ありません。インカムゲイン、すなわち家賃収入を蓄積する、比較的安定した投資手法です。ただ、自分ひとりで投資が完成するものではないということは、覚えておいてください。
マンション経営で成功するためには、やはり現在の『信用力』を活かす必要があります。あとは『時間』で、やはり30代・40代など早いうちから始めたほうが、時間はたくさんありますから、それを生かして行動することが大切です。行動すれば、不動産投資からその先の資産形成も実現できるはずです。
人生のリスクに『何もしないリスク』が存在するということを、覚えておいていただきたいと思います」
次世代不動産投資「みんなで資産運用」新ファンド発売
実質利回り3.0%という、ファミリー区分マンションのファンドが登場。不動産投資を考えている人はチェックしてみよう。

収益不動産を活用した資産運用コンサルティング事業を展開する大和財託は、8月16日(月)より、次世代不動産投資『みんなで資産運用』新ファンドを発売。
■『みんなで資産運用』について
スマホで一口一万円から出資ができ、手数料無料でいつでも現金化手続きが可能。資産運用ニーズが高まる現代にぴったりな、次世代不動産投資サービス。従来の不動産投資の費用面やリスク等の懸念を取り払い、「手軽・簡単」「安定収益」「安心」をさらに追及した、新しい不動産投資のスタイルだ。
■新ファンドについて
本ファンドは、インカムゲイン(運用期間中の家賃収益)を重視しており、神戸市にあるファミリー向け分譲マンション一室を運用。分配金は入居者からの家賃収入を原資とし、出資した金額に応じて分配する。
投資家には大和財託と匿名組合契約を締結の上、優先出資者として参加。今回はファンド総額の95%を募集し、残り5%は大和財託が劣後出資として出資することで、万一の価格下落から元本の安全性を高める仕組みを採用している。
本ファンドは既に入居済の為、分配金の原資があり、入居者が退去した時点で運用終了となる為、空室により分配金が減るリスクもない。

<神戸市東灘区ファミリー区分マンションファンド>
実質利回り/年:3.0%(税引前)
募集金額:1,600万円
募集期間(抽選方式):8月16日 ~ 8月30日17:00
抽選予定日:8月30日
運用開始:9月1日
運用終了:令和5年6月27日
最低出資金額:1万円/1口
安全性の高い資産運用ができるかもしれない。
公式サイト: https://yamatozaitaku.com/minna/
ファンド紹介ページ: https://yamatozaitaku.com/minna/fund/8-1/
申込~契約までの流れ: https://yamatozaitaku.com/minna/flow/
不動産投資の確定申告、税理士に依頼する費用は?メリット・デメリットも
1.不動産投資ではほとんどのケースで確定申告が必要
不動産投資では、家賃収入等の利益がある場合、所得税・住民税の確定申告と納付をする必要が生じてきます。
赤字であっても、確定申告をすることで、税金の軽減などの優遇措置を受けられることがあり、確定申告をしないと無申告加算税などのペナルティを課せられる可能性があります。
1-1.不動産所得の所得税・住民税を申告・納付する必要がある
サラリーマンの方などが副業で不動産投資をおこなっている場合、不動産所得が20万円を超えていると翌年3月15日までに所得税の確定申告をして、納付する必要があります。
不動産所得には住民税も課せられますが、住民税は不動産所得が生じていれば、申告・納付が必要といえます。住民税は、所得税の確定申告に基づいて、各市区町村が翌年6月頃に決定し、賦課してきます。所得税の確定申告をしていない場合、住民税の確定申告が必要になります。
また、不動産投資を専業でおこなっている場合は、不動産所得が基礎控除である48万円を超えていれば、所得税の確定申告が必要といえるでしょう。
不動産所得とは、家賃収入等で生じた利益のことであり、総収入金額-必要経費の算式によって計算されます。
不動産所得が赤字であっても、給与所得などの他の総合課税の所得と損益通算することによって、源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。このように、損益通算による税金軽減などの税制の優遇措置を受けたい場合にも確定申告をする必要があります。
1-2.適正な確定申告をしないと、ペナルティがある
確定申告をしないと、無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。
無申告加算税の額は、本来の納税額の15%~20%となっており、納期限から申告書提出日までの延滞税が課されます。延滞税の税率は、年ごとに変わる特例基準割合によって決定されます。
また、税法の法令に基づいた適正な確定申告をしていなかったことなどにより、納めた税金が少な過ぎた場合、後日、税務署から指摘を受けることがあります。そのような場合、新たに納める税金に加えて、その税額の10%~15%相当額の過少申告加算税がかかります。
2.不動産投資の確定申告を税理士に依頼するメリット
不動産投資の確定申告を税理士に依頼するメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- 正確な確定申告をおこない、税務リスクを減らすことができる
- 税額を適正に軽減する不動産所得計算ができる
- 自分で確定申告をする手間を省き、本業に集中できる
- 不動産投資の運営や相続などについてもアドバイスを受けることができる
2-1.正確な確定申告をおこない、税務リスクを減らすことができる
税理士は税務の専門家ですので、税法の法令に基づいた確定申告をおこなうことができます。
また、確定申告業務は、単なる書類の作成代行ではなく、納税者に代わって税務署に主張を伝えるという税務代理業務であるため、税務署から問い合わせなどがあった場合、税理士に対応してもらうことが可能です。万一税務調査が入った場合でも、確定申告を税理士に依頼していれば、対応を依頼しやすいでしょう。
このように、税理士に依頼することで確定申告に関連する税務リスクを減らすことができます。
2-2.税額を適正に軽減する不動産所得計算ができる
不動産投資の確定申告では、所得税の申告書を作成する前提として、不動産所得を計算する(決算をおこなう)必要があります。
不動産所得を計算する際に、税法の法令に基づいて必要経費を漏れなく計上し、青色申告の特別控除などを利用することによって税金を軽減できる場合があります。
ただし、必要経費計上にかかる税法の取扱いには、減価償却費の計算方法や家事関連費の按分方法など、税法の専門知識が必要となるケースも多いといえます。
また、青色申告の特典を受けるには、不動産所得の計算において、貸借対照表、損益計算書を作成できるような正規の簿記による帳簿作成、あるいは一定の簡易的な帳簿を作成する必要があります。これらの帳簿作成には、簿記や会計の専門知識が必要となります。
このように、法令に基づいて必要経費を余すことなく計上し、適正に税金を軽減するためには、不動産所得の計算から税理士に依頼した方がよいといえます。
2-3.自分で確定申告をする手間を省き、本業に集中できる
不動産売却の確定申告を一般人が初めておこなうには、調べなければならない事項や面倒な手続きもあり、申告期限までにすべての作業を間違いなく完了させるためにある程度の労力が必要になるでしょう。
確定申告のために労力をかけると、本業に影響が出てくる可能性もあり、税理士に確定申告を依頼することでそのような不安をなくし、本業に集中できるというメリットもあります。
2-4.不動産投資の運営や相続対策などについてもアドバイスを受けることができる
不動産投資を専門とする税理士であれば、不動産投資の運営についてのコンサルティングや収益不動産の相続対策などを業務としておこなっている場合があります。
そのような税理士に不動産投資の確定申告を依頼し、顧問契約を締結することで、不動産投資に関する会計、税務だけでなく、不動産投資の運営や相続対策について日常的にアドバイスをもらうことができるようになります。
税務リスクに適切な対応をするには、税務に関する届出書の提出など期限があるケースもあり、税理士との顧問契約は税務リスクの軽減にも役立ちます。また、不動産投資の運営や相続対策は税務と密接に関係しており、税務の専門家の視点から、長期的、総合的なアドバイスを受けることができるのもメリットといえるでしょう。
3.不動産投資の確定申告を税理士に依頼するデメリット
不動産投資の確定申告を税理士に依頼するデメリットとしては、費用がかかってしまうこと、ノウハウが身に付かないこと、が挙げられます。
3-1.税理士に対して支払う費用がかかる
不動産投資の確定申告を税理士に依頼すると、税理士に対して報酬を支払う必要があります。また、税理士との打ち合わせや資料収集など、最低限自分でおこなう作業もあることもデメリットでしょう。
不動産投資の確定申告を税理士に依頼することで軽減できる税務リスクや、税務と密接に結びついた運営や相続対策などの効果は、規模が大きくなったり、運営が長期化したりするほど大きくなる傾向があります。費用対効果を見極めて依頼を検討してみましょう。
3-2.確定申告についてのノウハウが身に付きづらい
不動産投資の確定申告を税理士に依頼した場合、確定申告や税務についてのノウハウは身に付きづらいと言えます。
不動産投資の運営と税務は密接に結びついています。収益不動産の売却や修繕、相続などの運営についての判断は、投資家自身がおこなう必要があります。投資家が税務についての知識も身に付けることで、より投資目的に沿った運営判断が可能になるケースも少なくありません。
税理士に依頼する場合でも、積極的に税務上の法律やルールについて質問を行うなどして、投資家が自らノウハウを身につけられるよう工夫をすることも大切です。
3-3.不動産の税務に詳しくない税理士もいる
税法の解釈は多岐に渡り、事業内容によって計上できる売上や経費の区分が大きく変わることも珍しくありません。また、不動産に関連した特例も数多くあり、これに対して適切に適用していくためには、不動産投資に強い税理士へ相談することも重要なポイントとなります。
ただし、税理士によっては不動産関連の税務に詳しくなく、最低限の申告しかできないケースもあります。積極的にアドバイスを受けたい場合、不動産税務に強い税理士を探す必要がある点はデメリットと言えるでしょう。
4.不動産投資の確定申告を税理士に依頼する費用
不動産投資の確定申告を税理士に依頼する費用は、家賃収入に応じた料金体系となっている事務所が多いでしょう。また、帳簿作成を依頼するかどうか、個人か法人かでも料金は異なります。
4-1.確定申告の依頼費用
不動産投資の確定申告を依頼する際の費用相場をみていきます。
個人、法人の場合で異なります。帳簿作成(記帳代行)を自分でおこなうか、確定申告と合わせて税理士に依頼するかでも費用が異なります。
以下で紹介するのはあくまでも相場の目安であり、料金体系は税理士事務所によって様々ですので、実際に問い合わせて確認するようにしましょう。
個人の場合
決算+確定申告のみ依頼する場合と、それに加えて決算の下となる不動産所得の総収入金額、必要経費を計算する帳簿作成(記帳代行)も合わせて依頼する場合とで、料金を分けている税理士事務所が多いでしょう。
上記を踏まえておおまかに、以下の金額が相場となります。貸室数や不動産収入が増加するごとに増額する料金体系となっている場合が多いといえます。
- 決算+確定申告のみ依頼する場合:5万円~15万円
- 決算+確定申告と帳簿作成を依頼する場合:10万円~25万円
法人の場合
個人と同様、決算+確定申告のみ依頼する場合と、それに加えて帳簿作成も合わせて依頼する場合とで、料金を分けている事務所が多いでしょう。
法人の場合は個人より料金は高くなる傾向があり、不動産収入が増加するごとに増額する料金体系となっている場合が多いといえます。上記を踏まえておおまかに、以下の金額が相場となります。
- 決算+確定申告のみ依頼する場合:20万円~35万円
- 決算+確定申告と帳簿作成を依頼する場合:30万円~50万円
4-2.顧問料
不動産投資の規模が大きくなってきたり、法人を設立して不動産投資をおこなっていたりする場合は、帳簿作成の手間が増え、確定申告や税金に関連する手続きが複雑になって来ます。
税務関係の手続きには期限があることが多く、適切な判断をタイムリーに処理していくことが求められます。税務リスクを減らすためにも、顧問契約を検討するとよいでしょう。特に法人の場合、顧問契約が前提となっている税理士事務所も少なくありません。
顧問料の相場は、個人、法人別に以下の金額帯となります。
- 個人:月1万円~3万円(決算・確定申告は+4カ月~6カ月)
- 法人:月2万円~4万円(決算・確定申告は、+4カ月~6カ月)
顧問契約の場合、打ち合わせの頻度が増えるのに応じて顧問料が増額される場合もあります。
5.複数の税理士に見積もりを依頼して費用を比較する
税理士の依頼費用は、不動産所得の規模や依頼する範囲によって異なるうえ、税理士事務所によって設定されている価格が異なります。実際に税理士への依頼を検討する際は、複数の税理士へ見積もりを比較し、依頼できる内容や費用について比較してみることが大切です。
効率的に不動産投資に強い税理士を探すには、税理士紹介サイトを利用する方法があります。税理士紹介サイトでは、コーディネーターが、相談者のニーズに合った税理士をピックアップし、面談を調整してくれます。税理士との依頼内容の調整や、料金交渉などもコーディネーターに任せることが可能です。
税理士ドットコム
税理士ドットコムは、全国5,900名の税理士の中から無料で希望に沿った税理士を紹介してもらえるウェブサービスです。複数の税理士を比較することができるうえ、「費用はいくら?」「どんな税理士を選ぶべき?」といった税理士を選ぶ際の相談も可能となっています。
報酬引き下げの実績も豊富なため、すでに税理士と契約している方でも利用が可能です。コーディネーターが複数の税理士に相見積りをとり、費用についての交渉までサポートしてくれます。
利用時の主な注意点としては、提携している税理士の紹介しか受けられない点です。提携外の税理士も比較していきたい方は、自身で探してみたり、不動産会社に相談してみたりなどと並行して、利用を検討すると良いでしょう。
【関連記事】税理士ドットコムの口コミ・評判は?メリット・デメリットや利用手順も
まとめ
不動産投資の確定申告を税理士に依頼することで、税務リスクを軽減でき、税法に基づいたアドバイスを受けることが可能です。
確定申告を税理士に依頼する場合、家賃収入や貸室数に応じて費用が変わり、帳簿作成を依頼するかどうか、個人か法人かでも費用は変わります。まずは確定申告を依頼した場合の見積もりを出してもらい比較検討してみるのも良いでしょう。
不動産投資を長期的におこなっていく上で、売却や修繕、相続などの重要な判断をする局面では、税務リスクは常に関係してきます。投資目的に沿った適切な判断をおこなうことができるようにするために、税理士に依頼する費用との費用対効果を見極めて依頼することを検討してみましょう。
不動産投資に影響ある日本の人口は12年連続で減少。賃貸オーナー「上から目線」の経営では行き詰まる時代に
総務省が公表した2021年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態を見ると、日本人住民の人口は2009年をピークに12年連続で減少した。
現行調査開始(1968年)以降、2006年に初めて減少し、2008年と2009年に増加したが、2010年から減少が続いている。全国の人口総計は1月1日時点で1億2665万4244人(△48万3789人、△0.38%)だ。このうち外国人住民が281万1543人(△5万5172人、△1.92%)だった。
三大都市圏(東京圏、名古屋圏、関西圏)の人口は、外国人住民を含めた総計で6639万5732人となって人口割合は69.53を占めているが、三大都市圏は調査開始(2013年)以降で初めて減少した。
出生者数から死亡者数を引いた自然増減数では、日本人住民の自然増減率は△53万608人となり、自然減少数が13年連続で拡大して1979年度以降で最大となった。一方、外国人住民の自然増減数はプラス1万884人と拡大傾向で2012年度以降で最多だった。
あらためて人口の減少が進んでいることがわかる。賃貸住宅経営にとって、この人口動態は将来の稼働率を占う上で外せない統計である。都道府県別でみると、人口が一番多いのは東京都で1384万3525人だった。この総計に占める外国人住民の割合も東京都は3.95%を占めて全国で最も大きかった。
総務省の統計からは、賃貸住宅を経営する上で東京の優位性が変わらず大きく、人口規模が小さい地方の賃貸オーナーにとっては入居者を確保するための工夫が今まで以上に求められていることがうかがえる。

安心感を与える快適な生活の提供
賃貸住宅管理会社や賃貸住宅業界にいくつかある業界団体などからは、
「これからの時代は、賃貸オーナーの意識に、住むところを提供している、貸してあげている、という上から目線の発想ではいずれ経営が立ち行かなくなるだろう」
「地方だけではなくてオーナーの顔が見えない賃貸経営では、都市部でも空室が埋まらない状況になってしまう。賃貸オーナーの生活費やローン返済、物件の管理費など諸々の費用はすべて家賃から出ていることを忘れてはならない」
このように危機感をあらわにする発言が聞かれ、賃貸住宅を管理する会社も含めて気持ちを引き締めるべき時期に来ている。
入居者に安心感を与える要素が非常に重要だ。入居者に対して、家主と管理会社はなにをどこまでできるのかを明確にしておくこと。例えば、エアコンが故障して使えなくなったときに夜でも電話できるのか、壊れた設備を入居者が修理していいのか、修理した場合その修理の請求先はどこになるのか。
賃貸借契約時になにも知らされないまま、確認されないまま、いざその場面になったときに入居者が不安になる物件は珍しくない。国民消費者センターなどに寄せられる賃貸住宅に関するトラブル事例にも挙がってくる。入居者に寄りそう丁寧な対応は快適な生活の提供で最上位に位置付けられていなければならない。
賃貸住宅から最寄り駅までの距離が近くて商業施設や病院、役所・出張所など生活利便性を高める施設が周辺にある場合はそれだけで入居者から選ばれそうだが、そうではなく真反対の住環境は賃貸住宅になんらかの特徴やメリットがないと入居者に選んでもらえない。
『入居者にどういう快適な生活を提供できるのか』。入居者から選んでもらえるキーワードとして、このフレーズは、これまで以上に重要になってきている。

地方の創意工夫に入居者を集める賃貸経営のヒント
賃貸住宅市況については、地方と都市の格差が拡大しつつあるが、もちろん全てが悪くなるわけではない。なかには入居者が順番待ちという人気の賃貸住宅があり、地方でも満室で稼働している物件がある。そうかと思えば、大都市の賃貸住宅で空室に悩んでいるオーナーもいる。
入居者にどういう快適な生活を提供できるのか、を考えたときに無料インターネットやモニター付インターフォン、24時間ゴミ出し可能、宅配ボックス設置、身一つで入居できる家具家電付きといった賃貸が増えているが、このようなハード面に対処していくだけでなく、賃貸借契約時に工夫をすることで入居者を集めている好例もある。
苗加不動産(石川県金沢市)では、敷金・礼金・仲介料・退去修繕費が全部タダという『タダ賃』を提供している。
初期費用を抑えて気軽にひとり暮らしが始められるサービスとして展開しているものだが、その賃貸運営方法は、抑えた初期費用を契約時から2年間の家賃に分散して上乗せしている仕組みとなっている。しかし、更新料もタダであることから、更新した後は初期費用の分散分がなくなり家賃が安くなる。『長く住めば住むほどお得感が増す』という工夫で入居者を集めているのが特徴だ。
賃貸物件の稼働率を向上させるために家賃を下げる。そうすると確かに入居希望者が増えるかもしれないが、賃貸オーナーとしては地域の相場にあった家賃か相場以上の家賃が取れることができればそちらの方がうれしい。
リノベーションやDIYはそこに向けての手段である。入居者が自由に室内の模様替えができるようにしたり、退去時にリノベーションやDIY前の原状回復を求めないなど一昔前に比べて入居者にとっての多様性が広がった。
コロナ禍でお家時間が増えたことでリノベーション需要も増加しているようだ。クラスココンサルファーム(石川県金沢市)は、自社ブランドで展開するリノベーション「リノッタ」の2020年6月~2021年5月の施工数は1067室とコロナ前の2019年6月~2020年5月の施工数と比較して1.3倍に拡大したという。
リノッタ後の平均家賃上昇率は33.3%となり、リノベーション施工後の平均成約期間は25日としている。
人口減少によるネガティブな見方に意に介さない地方の取り組み。東京など大都市の賃貸オーナーほど地方の創意工夫から学べることがありそうだ。膨大な情報量に埋もれているだけでは能がなさすぎる。情報の取捨選択が運用実績に影響を与える。
不動産投資でFIREを達成するために必要なたった一つの基準とは?
普通のサラリーマンが、経済的自立を伴った上で早期リタイアする「FIRE」を実現するにはどうしたらよいのか。
普通のサラリーマンから投資を始め、不動産からの家賃収入を中心に年間3,000万円の不労所得を得て2年前にFIREを達成した「無敵の投資家」こと村野博基氏(45)には、不動産投資を始めた当初から今まで変わることがない一つの基準があるといいます。
村野氏が考える、不動産投資で失敗しないためのポリシーとは――。
(※本稿は、村野博基『43歳で「FIRE」を実現したボクの“無敵”不動産投資法』(アーク出版)の一部を再編集したものです。)
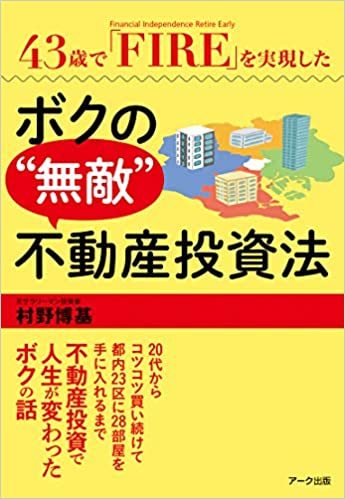
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
「長く続けられること」を第一の基準に
いろいろな不動産会社と商談しましたが、最初の物件として港区芝公園の物件を選んだ基準は「長く続けられること」でした。本当に長く続けられるかどうかはわかりません。
その可能性ができるだけ高い物件を、その可能性が高い不動産会社の営業マンから購入した」ということです。このことは不動産投資を始めた当初も今も変わっていません。
考えている方向性が一致していたC社
C社は20代半ばの不動産投資の経験も知識もないボクにも、ていねい、親切に対応してくれて、「当社は毎月、着実にマンションを仕入れて販売し、特に管理に力を入れています」といった会社の方向性を明快に示してくれました。管理に力を入れるということは、売って終わりではなく、これから長くお付き合いをするということです。そして、管理で収益を上げていればその会社はつぶれません。
売買だけで会社を維持していかなければならないと、必然的に売買での利益を多く確保する(つまりボクに高いものを売って利益を稼ぐ)必要がありますが、この会社であれば、売買で利益が上がらなくても、そののちの管理で利益を確保できる、と考えました。その方向性が当時の自分の考えていることに近く、親近感を覚えたのです。
契約が終わったあと、担当のTさんが「将来的には村野さんやお仲間の方から、毎月1戸マンションを買ってもらえるようになる」と語っていました。不動産は大きな買い物ですので、「マンションを毎月、周囲の人だけで購入するなんてムリだよ」と思っていました。でも、今ではボクの仲間たちだけでそれがほぼ実現できていますから、その担当営業マンの「予言」はあたっていました。
ボクは「結局〝運のいい人・ツイてる人〟についていったほうがいい」とも思っています。当時、その運のいい人・ツイてる人がC社のTさんだった……ボクがうまくいったのはただ、それだけということもできます。
将来に夢を持って購入する
誤解を恐れずにいえば、不動産会社の人はちょっとコワモテで、お金儲けの好きそうな〝山っ気〟のある人が多いような気もします。でも、このことに気圧されてアレコレといっても、結局、そのなかから誰かを選ばないといけないのです。
相手に押し切られて物件を買うのでは、自分の投資に夢が持てず、楽しくありません。せめて「他人・他社を悪くいわない」とか「聞いたことには、すぐ、きちんと答えてくれる」とか共感できる面があり、しかも、自分が望んでいることに的確にアドバイスしてくれて、長い付き合いができそうな人のほうがいい。
大手がいいとか全国網があるとか、よくある不動産会社の選択基準とは少し異なるかもしれませんが、ボクは今もこのようなことを重視して、担当営業マンと不動産会社を選んでいます。
不動産投資ローン、繰り上げ返済はするべき?メリット・デメリットを比較
1 繰り上げ返済にはいくつかの種類がある
繰り上げ返済とは、ローンの返済中に毎月の返済額とは別に返済をすることです。これによって借入金の元本を減らすことができるため、支払う利息を減らすことができ、返済期間を短くできるなどのメリットがあります。
この繰り上げ返済には大きく分けて2つの方法があります。それは、残額の一部を返済する一部繰り上げ返済と、すべてを返済する一括繰り上げ返済です。
また、一部繰り上げ返済には、繰り上げ返済後の返済期間を短縮する期間短縮型と、毎月の返済額を減らす返済額軽減型の2通りがあります。それぞれに特徴がありますので、次の表で確認しておきましょう。
| 繰り上げ返済方法 | 毎月の返済額 | 返済期間 | 利息軽減効果 | メリット |
|---|---|---|---|---|
| 期間短縮型 | 同じ | 短縮 | 大きい | 総返済額が減る |
| 返済額軽減型 | 減額 | 同じ | ややある | 毎月の返済額が減る |
ご自身の経営状況を確認して、どちらの方法を選択するのか慎重に検討しましょう。
2 不動産投資ローンの繰り上げ返済をするメリット
不動産投資ローンを繰り上げ返済するにはどのようなメリットがあるのでしょうか。詳しく見てみましょう。
2-1 不動産投資ローンの利息の支払額を減らせる
前項でも紹介した通り、不動産投資ローンを繰り上げ返済すると借入金の元本が減らせます。ローンは元金を返済するだけではなく、お金を借りた使用料という意味合いを持つ利息を支払います。
この利息は金利と元本の大きさに対して決まるため、元本を減らすことができれば、その分支払う利息も減らすことができるのです。元本を減らせば減らすほど利息が減るため、繰り上げ返済をすることで総返済額を減らすことができるのです。
2-2 不動産投資ローンの金利変動リスクを軽減できる
不動産投資にはいくつかリスクがありますが、繰り上げ返済をすることで金利変動リスクを抑えることが可能です。変動金利でローン契約を締結した場合、景気の状況によって金利が上下するため影響を受けますが、借入金の元本を減らしておけば、金利が上下しても影響は小さくなります。
2021年8月現在、金融緩和政策によって不動産投資ローンの金利は過去と比較して非常に低い水準で推移しています。繰り上げ返済を行うことは、金利が上昇する時に備えたリスクヘッジとして有効な手段と言えるでしょう。
2-3 金融機関からの信用が上がる
繰り上げ返済で予定より早く不動産投資ローンを返済することで、金融機関に対して支払い能力や経営能力があることをアピールすることに繋がります。その他、新規ローンの審査では申込時点のその他の借入についても調査されますが、返済総額が減ることで返済比率が下がるため、新しいローン審査でもプラスに評価されるポイントとなります。
返済能力が高いことを金融機関に印象付けできれば、次の物件に対しての融資が得やすくなるのです。ひとつの物件だけではなく、2つ目、3つ目と増やしていくことを目標にしている場合、繰り上げ返済を行うことで借入金を減らしておくことにはメリットがあると言えます。
3 不動産投資ローンの繰り上げ返済をするデメリット
不動産投資ローンの繰り上げ返済にはデメリットもあります。それぞれ見て行きましょう。
3-1 手数料が掛かる
融資を借り入れるときは金融機関が「ローン返済計画書」や「ローン返済予定書」を作成します。しかし、繰り上げ返済を行うと、その通りに行かなくなり、新たに返済計画を作成することになります。こうした事務的な手続きが必要になるため、ほとんどの金融機関では繰り上げ返済をする際に手数料を徴収しています。
例えば、三井住友信託銀行の「アパートローンの商品概要説明書」では、下記のように手数料の金額も明記しています。
・繰上返済を行う場合は、以下の手数料または違約金をお支払いいただきます。
変動プラン(1)一部繰上返済 5,500円(税込み) 、(2)全額繰上返済 5,500円(税込み)
※引用:三井住友信託銀行「アパートローンの商品概要説明書」
その他、固定金利を選択している場合は、繰り上げ返済ができないようになっています。ただし、違約金や損害金を支払うことで繰り上げ返済ができるようになります。
みずほ銀行の「アパートローン」には、下記のように記載されています。
固定金利選択方式および全期間固定金利方式・・・繰上返済は原則として行えません。当行が繰上返済を認める場合には、別途当行所定の方法により算出した損害金をお支払いいただきます。
※引用:みずほ銀行「アパートローン」
繰り上げ返済をする場合は、前述した手数料と同様に違約金を支払っても総返済額が減額になるようにある程度の金額をまとめて行うようにしましょう。
3-2.投資効率を下げることに繋がる
不動産投資ローンの繰り上げ返済を行うと、手元の現金資産を減らすことになります。手元の現金が減ることで、その他の投資機会を失うデメリットがあります。また、繰り上げ返済によって不動産投資ローンによるレバレッジ効果が薄れ、自己資金効率(CCR)が低下します。積極的に投資効率を上げて行きたい場合、注意しておきたいデメリットと言えるでしょう。
その他、突発的な災害や事故に対応するために、ある程度の現金資産を手元に残しておくことはリスクヘッジに繋がります。2021年8月時点、市中金利が低金利の水準であることからも、繰り上げ返済を行いすぎてしまうとメリットよりデメリットが大きくなり、逆に投資に対するリスクを上げてしまう可能性がある点に注意しましょう。
3-3 所得税の負担が増える可能性もある
不動産投資ローンを返済する際に支払った利息は経費として計上できます。そのため繰り上げ返済をすると、支払う利息が減り経費が削減されるということになります。所得税などの課税対象額が増え、支払う税金が増える可能性があります。
不動産所得を求める計算式は下記のようになります。
不動産所得=家賃収入-必要経費
繰り上げ返済をすると利息の支払いを抑えることができますが、その分、税金の支払いが多くなる可能性がある点に注意しましょう。
【関連記事】不動産投資、確定申告の手順は?計上できる経費や適用できる控除も紹介
4 不動産投資ローンの繰り上げ返済をする際の注意点
これまでメリットとデメリットについて解説しましたが、繰り上げ返済をする際に注意しておきたい点も紹介します。
4-1 金利の高いローンから繰り上げ返済をしていく
不動産をいくつか所有している場合、あるいは複数のローンを抱えている場合は、ローンの金利や返済期間、残高などを考えてから繰り上げ返済するローンを選ぶ必要があります。
ポイントは次の2つです。
- 金利の高いものから:金利が高い方から返済していくと、元本が早く減ることで、支払う利息も少なくなる
- 残額の多いものから:同じ金利の場合、残額が大きい方が支払う利息が高くなるため、残額が多い方から返済する
複数のローンを抱えている場合は、繰り上げ返済をするにもコツがあります。手数料や違約金などもローンによって異なりますので、詳しく調べてから行うようにしましょう。
4-2 ローン完済後は抵当権抹消登記の手続きをする
不動産投資ローンの場合、通常は融資対象の不動産に金融機関が抵当権を設定しています。そのためローンの全額を繰り上げ返済する際は、抵当権の抹消登記を行う必要があります。ご自分で行う場合は手続きの手順などを確認しておきましょう。
抵当権を抹消する際は、金融機関から書類を預かり法務局で手続きをします。金融機関では書類を用意してくれますが、下記のものが必要になるので、漏れのないように確認しておきましょう。
- 弁済証書:ローンを完済したことを証明する金融機関の書類
- 抵当権抹消の委任状:抵当権者である金融機関に代わって抹消手続きを行うための委任状
- 金融機関の資格証明書:抵当権者である金融機関の資格を証明する書類(必要ないケースもあり)
ご自身で行うことが難しい場合は司法書士などに依頼することもできます。
まとめ
不動産投資ローンの繰り上げ返済には返済比率を下げられるメリットがありますが、投資効率を下げてしまう点や、手数料・違約金が発生する可能性がある点はデメリットとなります。これらのメリット・デメリットを理解したうえで、繰り上げ返済をした方がいいのか、しない方がいいのか、判断していきましょう。
不動産投資を行う目的は各オーナーによって様々であり、物件の収益性やローンの残債・残年数によって繰り上げ返済を行うべきかどうかはケースバイケースと言えます。この記事を参考に、慎重に検討してみましょう。
初めて築古戸建を買うなら、オーナーチェンジ物件が良い?《楽待新聞》
リフォームの経験が無いので、オーナーチェンジ物件にしようか、一からリフォームして客付けまで一通り経験するか迷っています。また価格的に魅力のある再建築不可物件も、投資対象にしても良いもよいものかも判断出来ずにいます。
本は10冊程度は読んでいますが、高額セミナーに参加はしたことがありません。一度は参加した方が良いのでしょうか。
■回答者:築古大家のコージー さん(不動産投資家)
初めての場合はオーナーチェンジ戸建てはオススメです。因みに私もオーナーチェンジ戸建てから始めました。リフォーム・賃貸付けなどないのでハードルが低いし、購入すぐに家賃が入ってきます。
ただし、どんな状態から賃貸付けされた物件か、入居者はどんな方かなど、情報が取れない物件はおすすめできません。
空き家をリフォームから入る場合は、事前にリフォーム業者の目ぼしがついていて、買う前に同行して見積してもらえるのがベストです。どの程度のリフォームでどの程度の家賃を目指すべきか? これは賃貸仲介業者にヒアリングしておくことをお勧めします。間違っても売買業者の言うことは信じてはいけません。
再建築不可を選ぶ場合は、周囲の接道ある物件にくらべ3割安で相場価格が目安です。半額とかだったら視野にいれてもいいかもしれません。ただし、全く担保価値はないものと考えてください。借入は今後もあまり考えず、現金買いで買い進める方ならありです。
築古戸建てから入ろうとされる方が、高額セミナーを受けても全くもって無駄です。どちらかというと、築古戸建てのリフォームばかりやってる大家さんの会や飲み会とか、1回数千円+飲み代くらいの会に参加され、情報収集されることをおすすめします。
特に大阪は複数あるので是非出かけてください。他の大家さんが、一体どんな地域にどんな物件を持っていて、いくらくらいで入居づけできているか? などの情報が得られると思います。仲のいい大家さんができればリフォーム業者の紹介してもらうとかも期待できるでしょう。
「不動産投資とFIRE」を1200人に調査……FIRE実現の50代以下は約2割! 7人に1人が「経済的自由」を達成
今回の調査においては、「経済的自由」とは、不労所得のみで日々の生活費を賄える状態「FIRE」は、不労所得のみで日々の生活費を賄える状態となったうえで、いわゆる早期退職(脱サラ)まで実行した場合と定義し、提示しました。2021年6月時点で、不労所得のみで日々の生活を賄える状態である「経済的自由」を達成している人、FIREを実現している人はどのくらいいるのでしょうか?
大都市圏と地方、不動産投資に適しているのはどっち?
1万円の利益は、東京で稼いでも四国のすみっこで稼いでも同じ1万円です。地方都市のほうが市場の熟成度が低い分勝てるチャンスが多いのでは? と考えています。
質問者たちの感覚も、現在の自分の状況より大都市圏よりに目が向いているような印象です。
大都市圏、中都市、地方都市くらいの分類にしたとき、土地勘はどこでも同程度と仮定してどの規模の都市が利益が出しやすいと考えますか? また、その具体的な理由がありますか?
■回答者:二代目大家かずみ さん(不動産投資家)
土地勘や知識などがきちんとあるのでしたら、どこでもいいと思います。ここでは、住居の賃貸が多いですが、不動産賃貸は住居だけではありません。
大切なのは「柔軟な発想」と「具体的な実行力」だと思います。それから「手持ちのお金」ですね。
海外不動産投資に必要な自己資金は?ローンを受けやすい国・手順も解説
1.海外不動産投資でローンを利用しやすい国と自己資金
数は少ないものの、日本国内にも海外不動産投資に融資している銀行があります。ローンを利用できる投資先や、必要な自己資金の考え方について解説します。
1-1.ハワイを含むアメリカ
2021年8月時点、海外不動産投資の中で最もローンを利用しやすい投資先はアメリカです。
日本国内の金融機関で海外不動産投資に融資するところは少数派です。しかし、アメリカ不動産投資であれば、購入物件のエリアを限定する条件で融資しているところが複数あります。
例えば、ハワイ州オアフ島のホノルルエリアであれば、東京スター銀行やSBJ銀行などでローンを利用可能です。そのほか、カリフォルニア州の物件であれば香川銀行のローンを使えます。
海外現地の銀行で外国人向けに住宅ローンを出しているところもありますが、情報の有無やローン利用の可否については、不動産エージェント次第であることも否めません。
外国人向けの住宅ローンについては、インターネットで情報を収集するのが困難であり、現地の不動産エージェントが個人的に情報を持っているケースも多くなります。また、ローン申込の条件として該当する銀行での口座開設や、投資先の国における継続的な収入を求められることも少なくありません。
初めての海外不動産投資であれば特に、日本国内の銀行で融資元を探す方がローンを利用できる確率は高くなります。
【関連記事】【7分で分かる】アメリカで不動産投資を始めるための10のステップ
【関連記事】ハワイ不動産投資のメリット・デメリットは?リスクや注意点も
1-2.オリックス銀行の不動産投資ローン
アメリカ以外の国で投資したい場合は、オリックス銀行の不動産担保ローンを利用することも検討できます。オリックス銀行のローンは、原則、投資先の国について制限がありません。(※参照:オリックス銀行「不動産担保ローン」)
ただし、オリックス銀行の場合は、購入する物件とは別に日本国内の首都圏など限られたエリアに立地した不動産を担保に入れる必要があります。アメリカ不動産投資に利用できるローンでは、購入物件を担保に入れるため別途担保不動産を用意する必要がありません。
オリックス銀行のローンは、すでにローン完済済みの自宅か別の投資用物件を持っていないと利用できない点に要注意です。そのほか、前年度の税込み年収が700万円以上など複数の申込条件があります。利用を検討する場合は、申込条件の事前確認が必須です。
1-3.海外不動産投資で必要な自己資金
日本国内の銀行が提供するローンでは、それぞれ商品説明書には明記されていないものの、おおむね物件評価額の50%が融資限度額となっています。このため、例えば評価額が2,000万円の物件を購入する場合は、諸経費を含めると1,000万円以上の自己資金が必要です。
また、物件価格ではなく評価額の50%が限度である点に注意を要します。銀行はローン審査にあたって独自に現地の評価機関等から物件の評価レポートを取得し、評価レポートに基づいて融資額を決定しています。
価格が2,000万円の物件を購入するからと言って、必ず1,000万円のローンを利用できるわけではありません。周辺相場よりも高価格の物件を購入する場合は特に、審査の結果として融資額が下がることも考えられます。
なお、オリックス銀行のローンを利用する場合に融資額の根拠となるのは、担保とする日本国内の物件評価額です。評価額が高い物件を担保に入れられれば、物件購入額の大部分をローンで調達できる可能性もあります。
2.海外不動産投資でローンを利用する手順
海外不動産投資でローンを利用する場合は、日本国内での不動産投資とは異なる複数の手順を要します。手続きをスムーズに進めるためには、スケジュールの事前確認が重要です。
2-1.物件購入の申込
海外不動産投資を進めるためには、最初に投資先の国と不動産エージェントを選び、購入する物件を決めます。ローン利用上の注意点としては、物件購入前に不動産価格の周辺相場を調べておくことです。
評価額よりも大幅に高い価格の物件を購入してしまうと、物件価格に対する融資額の比率が下がるために必要な自己資金額が上がります。ローンを利用して自己資金比率を下げるためには、可能な限り評価額が高く、周辺利回り相場と合致した物件を購入することが重要です。なお、物件購入の申込が済んだら、手付金もしくは申込金を売主に支払います。
2-2.不動産売買契約を締結
申込金の着金が確認されたら、買主と売主との間で売買契約を締結します。なお、売買契約書にはキャンセル条項が入っているか、契約締結の前に確認することが重要です。
キャンセル条項とは、買主が物件購入にあたってローンを利用する場合に、審査を通過できなかったら契約をキャンセルできるという条項のことです。キャンセル条項には契約締結後の期限が設けられており、期限と審査期間の目安とが合致しているか確認することが重要になります。
2-3.不動産投資ローンの審査を受ける
売買契約の締結が完了したら、銀行に申込書類を提出してローン審査に入ります。本審査の場合は1週間~2週間前後の日数が必要になるので、あらかじめ銀行へ目安の期間を確認することが重要です。
なお、審査にあたってはサイン済みの売買契約書に加え、収入証明など複数の書類が必要になるので、あらかじめ用意しておくとスムーズに手続きを進められます。
2-4.公証役場での認証手続き
銀行の審査を通過できたら、公証役場で認証手続きをします。認証手続きをするのは、購入対象の不動産について、投資先の国で銀行が抵当権を設定するためです。アメリカ不動産投資でローンを利用する場合は特に、認証手続きが必ず必要になります。
なお、すでにご紹介したオリックス銀行のローンを利用する場合は、日本国内の不動産に抵当権を設定するため認証手続きは不要です。
また、公証役場は平日の日中しか認証の対応をしていないことに注意を要します。土日には対応していないため、平日のスケジュール調整が必要です。多くの銀行ではローン契約の当日に認証手続きをします。
2-5.ローン実行および決済資金の送金
ローン契約および認証手続きが完了したら、決済日に合わせてローンが実行されます。なお、融資額の振込先が契約者の銀行口座になるのか、物件売主が指定する口座になるのか事前に確認することが重要です。
契約者の銀行口座になる場合は、融資額の着金を待ってから売主の指定口座へ決済資金を送金することになります。海外送金は日本国内の資金送金よりも完了までに日数を要するため、決済日に間に合わせるためには余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
2-6.登記済証の提出
日本と違って、海外では物件所有権の登記済証が発行されるまでに時間がかかることもあります。ローン実行後に銀行または保証会社から登記済証の提出を求められることがあるため、登記済証の発行スケジュールを事前に確認することが重要です。
例えば、アメリカではそれほど時間がかかりませんが、新興国の不動産投資では、発行までに数ヶ月以上の期間がかかることもあります。あらかじめ売主に必要期間を確認しておくと、ローン契約の時に銀行へ説明できるためトラブル防止に役立ちます。
まとめ
海外不動産投資で最もローンを利用しやすいのはアメリカ不動産投資です。ハワイやカリフォルニアなどエリアはある程度限定されるものの、ローンを利用できる銀行が複数あります。
なお、売買契約書が外国語で書かれていることや、ローン契約後に認証手続きを要する点などが日本国内の不動産投資との違いです。また、国によっては登記済証の発行に時間がかかる場合もあるので、あらかじめ発行スケジュールを確認することが大切です。
不動産投資、空室が埋まらない原因は?物件の収益性を高める5つのステップ
1.不動産投資で空室が発生する3つの主な原因
不動産投資をするうえで注意しておきたいリスクの一つに「空室リスク」があります。空室リスクとは、保有している物件に入居者が入らず、空室となってしまい、家賃収入が入ってこない状況となるリスクを言います。
不動産投資は、入居者が家賃を支払ってくれれば比較的手間がかからず、「不労所得」というイメージがありますが、そう考えられていた時代は既に過去のものとなっています。
国内の総住宅数(2018年10月1日時点)
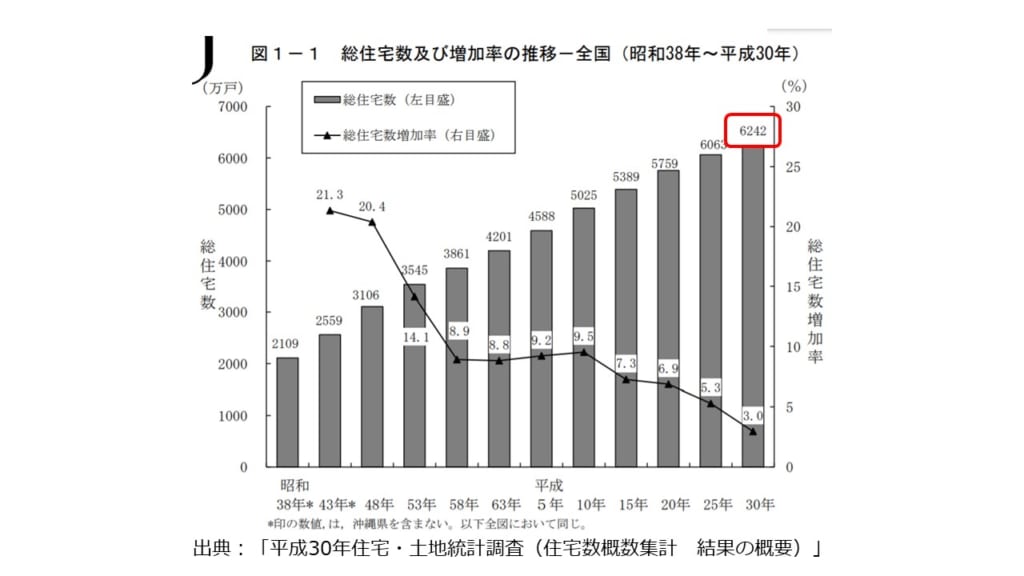 総務省統計局が2019年に発表した「平成30年住宅・土地統計調査(住宅数概数集計 結果の概要)」を見てみますと、2018年10月1日時点における国内の総住宅数は6242万戸で、2013年と比較して、179万戸の増加となっています。
総務省統計局が2019年に発表した「平成30年住宅・土地統計調査(住宅数概数集計 結果の概要)」を見てみますと、2018年10月1日時点における国内の総住宅数は6242万戸で、2013年と比較して、179万戸の増加となっています。
空き家数及び空き家率の推移
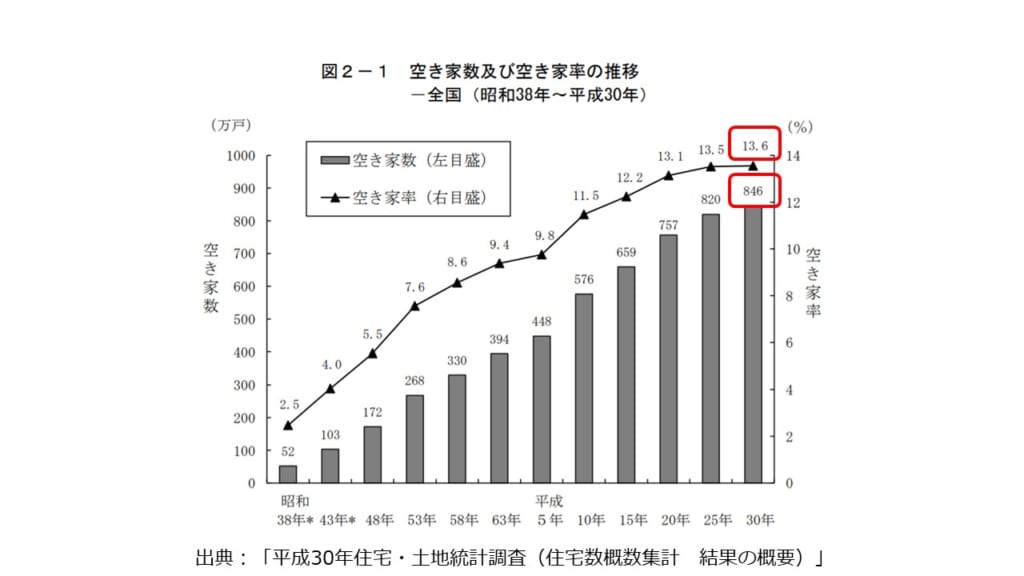 そして、居住世帯のない住宅のうち、「空き家」は846万戸と、2013年と比較して26万戸(3.2%)の増加となっています。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%であり、2013年から0.1ポイント上昇して、過去最高となっています。
そして、居住世帯のない住宅のうち、「空き家」は846万戸と、2013年と比較して26万戸(3.2%)の増加となっています。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%であり、2013年から0.1ポイント上昇して、過去最高となっています。
少子高齢化によって、日本は人口の減少が大きな社会問題となっています。その一方で、アパートやマンション等の新築物件は毎年どんどん建設されています。つまり、需要と供給に大きなギャップが生まれているのです。
この供給過剰の状況の中、不動産投資家が自身の保有する物件に空室をつくらず、高い入居率で運営していけるかは、空室が発生する原因を知り、いかに対策をしていくかにかかっています。
前述した国内の人口の減少、国内全体での物件の数そのものの増加といったマクロ的な環境以外に、この記事では特に、不動産投資で空室が発生する主な原因として、次の3つの点を挙げたいと考えます。
- 賃貸ニーズは高いものの、物件価格が割高な駅の物件を購入する(エリアの問題)
- 物件の家賃や設備が周辺相場・ニーズと合っていない(物件の競争力の問題)
- 管理会社がリーシングに強くない(パートナーの問題)
私は、賃貸ニーズの高いエリアで、入居者が必要とする設備がある物件を保有して、適切な家賃を設定し、リーシング(入居者募集)に強い管理会社に賃貸管理をお願いできれば、空室リスクを低く抑えることができると考えています。
1-1.賃貸ニーズは高いものの、物件価格が割高な駅の物件を購入する(エリアの問題)
これから不動産投資を始めたい、という投資家の方から、「不動産投資はどのエリアでやるのが良いでしょうか」、という類の質問を多くもらいます。
収益用でも居住用でも物件を購入する際、エリアの選定はとても重要です。リクルート住まいカンパニーが発表した「SUUMO住みたい街ランキング2021関東版 ~住みたい街(駅)~」調査によれば、恵比寿駅や吉祥寺駅、中目黒駅等誰もが知っている駅名が上位を占めており、その傾向は毎年ほとんど変わりません。
しかし、私の経験上、不動産投資をするうえでは「投資対象エリア」と「自分が住みたいエリア」は完全に分けて考えた方がうまく行くケースが多いと考えています。
恵比寿駅や吉祥寺駅、中目黒駅は、今後も人気ランキング上位に入り続けると予想していますが、物件価格は獲得できる家賃が高いこととエリアの希少性もあり、相対的に割高になる傾向があります。
この場合、稼働率は高まりますが、キャッシュフローはあまり出ないでしょう。また、融資を活用して物件を購入する場合、ローン返済等でキャッシュフローを気にして設定家賃を間違えると、知名度が高い人気駅であっても賃貸は付かなくなる可能性が高まります。
では、不動産投資をするうえではどのような駅を選べば良いのでしょうか。あまり知られていない狙い目の駅として、例えば、リクルート住まいカンパニーが発表した同調査で、「順位が上昇した街ベスト10」の9位に川口駅があります。川口駅は、ARUHIが発表した「本当に住みやすい街大賞2021」では1位を獲得しています。
川口駅は、JR京浜東北線が使えて、東京駅や新宿駅、渋谷駅に30分程度でアクセス可能です。再開発も進んでおり、駅前にはタワーマンションも多く建設されています。アリオ等の大型商業施設や商店街も多いので、生活もしやすい環境と言えます。
隣駅の赤羽駅は東京都内ですが、川口駅は埼玉県内となり、都心主要駅のアクセスが便利なうえに賃料相場が相対的に低いのが人気の理由であると考えられます。
居住用エリアで人気の高い物件は価格も高くなりがちです。ただし、物件価格が2倍でも、家賃が2倍取れるかと言えば、必ずしもそうなりません。人気エリアの物件をコレクションしたい、というのであれば話は別です。しかし、空室リスクを抑えた、賃貸ニーズの高いエリアの物件を割安で購入する方が投資効率は高く、キャッシュフローも出やすいと言えます。
首都圏以外の地方で物件を探す場合には、前述した視点に加えて、人口動態や最寄り駅の1日の乗降客数等も参考にして探すことが重要です。
1-2.物件の家賃や設備が周辺相場・ニーズと合っていない(物件の競争力の問題)
空室を避けるためには、物件の家賃や設備が周辺相場や入居者が求めるニーズと合っているかどうかを確認することが必要です。
全国賃貸住宅新聞が発表した「人気設備ランキング2020」では、コロナ禍では、人気設備の傾向はコロナ前と比較して少し変動があるように見えます。エントランスのオートロックは変わらず高い人気ですが、TVモニター付きインターフォンの順位が上がっているのはコロナ禍で家に滞在する時間も増えている中、防犯意識が高まっていると読み取れます。
また、ランキングの中で、最も順位を上げたのが、ファミリー物件での宅配ボックスの設置ニーズです。Amazon等のオンラインショッピングのニーズは今後もますます増えてくると見られ、単身者向け物件でも重視されやすいポイントと言えます。最近ではアパート等の1棟物件でも後付けで設置できる宅配ボックスが登場しているので、設置を検討してみると良いでしょう
インターネット設備に関しては注意が必要です。コロナ前からインターネット無料はランキングでは上位でした。つまり、あって当たり前になってきた感があります。コロナ禍では、社会人のテレワーク、学生のオンライン授業等で利用頻度が急速に高まってきており、無料であることに加えて、今度は通信速度が課題になってきています。
経験がある方も多いかと思いますが、インターネットは無料であっても通信速度が低すぎると快適に仕事をすることは困難になります。賃貸仲介会社の知人に確認をしてみたところ、実際にどのくらいの通信速度が出るのか問い合わせもあるようで、今後同様の問い合わせは増えてくるだろう、とのことでした。
空室を極力避けるためには、これらのランキング上位のニーズ対策の重要度は高いと思われます。
1-3.管理会社がリーシングに強くない(パートナーの問題)
不動産投資をするうえで、管理会社は重要なパートナーです。物件の家賃収入を1円でも多く上げ、稼働率を少しでも上げるためには、いかに空室を少なくするかを戦略的に考えなくてはいけません。
不動産投資家の中には、修繕計画を綿密に立て、コストを下げることに終始する人をよく見ますが、まずは企業経営で言うところの売上高(=家賃収入)を確実に確保することが肝要です。
売上高を上げる仕組みとして、リーシングに強い管理会社を見極め、常日頃から関係値を高めていくことができるかが、引きも切らない入居者募集、ひいては高い入居率につながっていきます。
2.管理会社と連携して、空室を減らし収益性を高める5つのステップ
不動産投資、その中でも特に1棟物件投資は、受け身の対応では決してうまくいきません。1棟物件投資は、「賃貸不動産経営」です。その業務内容を理解して、プロの管理会社と強力に連携することが、空室を減らして物件の収益性を高めることにつながります。
不動産投資家の役割は、1棟物件の維持管理に必要な各業務を管理会社に依頼し、満室経営に向けてマネジメントすることです。そこで、ここでは、空室を減らして収益性を高める5つのステップを解説します。
2-1.【ステップ1】リーシングに強い管理会社と戦略を共有する
どのような管理会社に管理を委託するか、によって不動産投資の収益は変わってきます。一番に見るべきはやはり管理実績です。1棟物件の管理にしろ、区分マンションの管理にしろ、業界では管理戸数は3,000戸を超えていることが一つの目安になります。業歴も確認するべきですが、実際にどれだけの戸数の物件を管理しているかが重要です。
管理会社はどこも、まずは管理戸数1,000戸を超えることを当面の目標としています。1,000戸までは力技で何とかなることもありますが、私の経験上、3,000戸を超えるとなると組織として機能をしていないと入居者のニーズに応えることはまずできません。
管理業務は、管理戸数が多ければ多いほど、スケールメリットが効いてきます。管理戸数が多い管理会社では、リフォーム工事の発注単価も低くなり、パートナー企業が積極的に良い商品の紹介をしてくれるようになります。そして、管理戸数が5,000戸を超えると業界でも一目置かれ、10,000戸を超えるとそのエリアでも有数の管理会社として認識されます。
会社の経営方針にもよりますが、管理戸数が増えてくると、様々な管理業務(入居者募集・入居者対応・清掃等の建物管理等)等の窓口を1人でこなすことは難しくなってきますので、セクション(課・チーム)を分ける等、明確に役割分担している管理形態を取っている会社もあります。
また、1棟物件の場合には、管理物件の入居率が90%を超えているかどうかが任せて良い管理会社であるかどうかの一つの目安(指標)になります。入居率の計算方法は、その算出の仕方によって異なりますので注意が必要ですが、主に1棟物件を取り扱っている管理会社で管理戸数が3,000戸以上、入居率が95%を超えていたら優秀であると言えます。
そして、管理会社に管理を委託するうえで、重要なポイントがリーシングに力を入れているかどうかです。管理戸数が多い管理会社はたいていリーシングに注力しています。リーシングの実務面で留意するべきポイントは、入居者付け(仲介業務)を自社で行っているかどうかです。
不動産投資家としては、ともすると、管理会社が店舗を持っていて自社で直接入居者付け(仲介業務)をした方が効率良いと思いがちです。しかし、管理会社の役割は、仲介手数料を獲得することではなく、不動産オーナーの利益を最大化し、空室をなくすことです。
リーシングで大事なことは、入居者を募集する窓口を幅広く持つことです。管理会社が自社で店舗を持っていると、仲介手数料のノルマ(店舗・個人)獲得の観点から、物件を自社の店舗ネットワークだけで囲い込みしようという意識が働き、結果として募集の窓口が自社だけに狭められてしまうのです。
前述したとおり、全国的にも空室率が高まっており、そして今後は、部屋が大量に余る時代です。そのような時代の中、不動産投資家から預かった部屋を自社の店舗ネットワークの中で囲い込んで、果たして想定どおりの条件で決まるのか疑問があると思います。
私が勤務していた不動産会社はグループに管理会社を持っていましたが、自社では店舗を持っておらず、賃貸営業部のメンバーが毎日50~60件飛び込みで店舗を訪問し、空室となった部屋(商品)の紹介に駆けずり回っていました。実績を出している担当者の携帯電話にはひっきりなしに店舗から連絡が来ており、多い日は1日に30件以上は着信履歴があったほどです。
この管理会社は、自社では店舗を持たず、空室となった部屋を広く賃貸仲介会社に紹介することで、私が在籍時に管理戸数は5,000戸を超えていましたが、入居率も常に95%を超えていました。地方郊外の物件も多く取り扱っており、1棟物件の管理会社で、この実績はエリア内でも屈指であったと記憶しています。
2-2.【ステップ2】管理会社と空室が起きている原因を特定する
さて、どれほど素敵な物件を保有していても、入居者を見つけることができなければ賃貸経営は成り立ちません。アパートのほか、区分マンションの一室でも、やり方を間違えてしまうと空室は長期(3ヶ月以上)にわたり、収益率が低い物件となってしまいます。
空室が起きている原因を分析すると様々なことがわかってきます。ほとんどの不動産投資家は、空室が発生していることを認識しても、その原因を調査分析して対策までしているケースは少ないものです。
入居者の退去の原因がわかれば、退去を減らして長期的な入居につなげるため、不動産オーナー側から管理会社に提案することもできます。入居者確保に向けた不動産投資家の積極的な姿勢は今後さらに重要になってきます。
部屋が埋まらないのには必ず理由があります。管理会社をとおして、賃貸仲介会社へヒアリングをかけてもらう必要があります。時間があればヒアリングは自身で行うことも可能ですが、要領を得ない質問や偏った質問は大きな先入観を生んでしまうこともあります。自身でヒアリングをする場合には、管理会社から事前にコツを教えてもらうのも良いでしょう。
空室が発生し、それが続いてしまう原因には様々なものがあります。主には下記の4つの原因が考えられます。
- 賃貸仲介会社に部屋の認知がされていない
- 相場に合っていない家賃が設定されている
- 部屋(商品)の差別化がされていない(=特徴が見えない)
- 入居者のニーズに合った間取りや設備ではない
ヒアリングの結果、上記が原因であると考えられる場合には、管理会社と連携して早急に対策を講じる必要があります。
2-3.【ステップ3】入居者が住みたいと思う部屋を作る
賃貸仲介営業マンに、「入居者にあの部屋を紹介したいな」、と思ってもらうためにも、入居者が住みたいと思う部屋を作ることは重要です。入居者に気に入ってもらうためには、適度なリフォームを実施して、清潔感のある部屋を作る必要があります。
さて、リフォームには、汚れ等をきれいにする原状回復工事と、部屋の資産価値を向上させるグレードアップ工事があります。物件が古い場合、もしくは、古くなってきた場合には、単に原状回復工事をするだけではなく、入居者が住みたいと思えるような付加価値を付けることも重要です。
実際に私が体験した話をします。コロナ禍では、テレワークが浸透しました。毎日、会社に通勤する必要がない一方、毎日、同じ部屋(空間)にいると気が滅入ってくることもあります。ある入居者から管理会社に、「部屋のクロスが真っ白で息がつまりそう。模様変えできないか」、と連絡がありました。
このとき私は管理会社から連絡を受け、管理会社と相談をしたうえで、壁の一部をアクセントクロスにすることを提案しました。入居者は、毎日テレワークをしていたのですが、「一日中、パソコンと白いクロスを目の前にして参ってしまっていた」、とのことでした。私は入居者の生の声になるほど、と思ったものです。
アクセントクロスをうまく使うと、単調になってしまいがちな部屋も一気におしゃれになります。文字どおり、部屋のアクセントになるように、色や柄を選んで、壁の一部分を張り替えれば簡単に完成します。
リフォームに関しては、単に費用をかければ良いというものではありません。家賃収入に応じて、物件価格が決まりますので、将来売却を視野に入れている場合には、投資対効果を考慮してリフォームする必要があります。
管理会社は、業務量が非常に多いので、リフォーム業者に部屋を視察してもらい、見積もりをもらう際、いちいち部屋を見ないケースも多くあります。できれば、投資家自身で部屋を確認して、必要なリフォームを見極めることが重要です。
若干費用がかかっても、物件の付加価値を上げてみたい場合には、システムキッチンの導入を検討してみるのも良いでしょう。前述の「人気設備ランキング2020」では、単身者向け物件でも、コロナ禍で部屋にいる時間も増えるため、システムキッチンのニーズが上がっています。
2-4.【ステップ4】賃貸仲介営業マンに直接アプローチをする
入居者が住みたいと思える部屋を用意できたら、いよいよ幅広く募集をして部屋(商品)を売り込みます。
管理会社にREINS(レインズ)に部屋情報を掲載してもらった後は、マイソク(賃貸募集のチラシ)を作成して、管理会社からお付き合いのある賃貸仲介会社に一斉にメールやFAXをしてもらいます。物件が所在する最寄駅はもちろん、ターミナル駅も重要なターゲットになります。
例えば、西武池袋線の江古田駅に物件があった場合、江古田駅の周辺の賃貸仲介会社をはじめ、隣の駅の桜台駅や、都営大江戸線の新江古田駅周辺の賃貸仲介会社にもアプローチをします。実務上は、ターミナル駅である練馬駅や池袋駅からの客付けがメインとなりますので、練馬駅や池袋駅の賃貸仲介会社にも積極的にアプローチをしていきます。
次に、管理会社から、取引実績のある(顔が見える)賃貸仲介営業マンに電話で部屋を紹介してもらいます。私も不動産会社勤務時に、部屋の紹介をしたことがあります。メールやFAXだけではなく電話を使うと、営業マンと直接の面識がなくても、話が弾むこともあり、その流れで部屋を紹介してもらえたりします。
そして、最も重要なのが賃貸仲介会社への直接訪問です。この手間を惜しんでしまっては、空室は埋まらないと断言できます。私が勤務していた不動産会社の賃貸営業部のメンバーは1日に50~60件店舗訪問をしたと書きましたが、やはりこの効果は絶大で、あっという間に空室が埋まっていったことを鮮明に覚えています。
エリアによっては、毎週、賃貸営業部のメンバーが、名刺や資料を置いていくので、賃貸仲介会社(店舗)の担当者も社名を覚えてくれます。例えば、私が勤務していた不動産会社は、当時北関東(特に、埼玉県や栃木県)で、その社名を知らない不動産会社はないと言えるくらい徹底的な営業活動を展開していました。
このように管理会社が賃貸仲介会社を直接訪問することができれば理想ですが、投資家自身も時間があれば、賃貸仲介会社を訪問してみましょう。空室が埋まらない原因の一つに、賃貸仲介会社に部屋の認知がされていないことにありますが、実際に訪問をすることでそれが良くわかることがあります。また、賃貸仲介会社の担当者と直接話をすることで、自身の部屋の実力値を知るきっかけにもなります。
私が実践している自身で訪問する際のやり方をご紹介します。まず、物件が所在するエリアにある賃貸仲介会社をGoogle Mapで調べて、全てノートに書き出し訪問します。管理会社と事前に確認をして、管理会社と取引実績がない会社を訪問する、エリアの有力会社を中心に訪問する等、優先順位を付けて訪問するとメリハリが出ます。店舗によって定休日もまちまちですので事前に調べてから訪問することを検討してみましょう。
1棟物件は中々入居が決まりづらい部屋があるかと思いますが、訪問時に営業マンに「空室が埋まらないのはなぜか、どのようにしたら空室が埋まるのか」をヒアリングします。家賃が相場と見合わないからなのか、入居者ニーズのある設備が設置されていないからなのか、理由を教えてくれます。
毎日、実際に入居者に部屋を案内している営業マンの意見はとても説得力があります。自身の部屋に問題点があった場合、例えばそれがインターネット環境等の設備の問題であれば、管理会社と早急に相談をして対策を練ることが重要です。
直接訪問をする場合、店舗の店長さんと面識を持つことができれば良いですが、運悪く不在のこともあります。そこで私は、その店舗で一番仲介実績を挙げている営業マン(トップ営業マン)の名前を教えてもらって、後日再度アプローチをする等、顔が見える営業を心掛けていました。やはり、人は電話やメールでのアプローチだけの場合と、実際に直接顔を見てアプローチされる場合では、印象の残り方が大きく違ってきます。空室を1日でも減らしたいときには、不動産投資家が自ら直接訪問をするのも有力な手法であると考えます。
2-5.【ステップ5】賃貸仲介営業マンから物件を入居者に提案してもらう
入居者が住みたいと思える部屋を作り、賃貸仲介営業マンを直接訪問しても、まだ、それだけでは空室は埋まりません。
なぜなら、ここまでは、他の不動産投資家も管理会社と連携して実施しているからです。そして、同じような部屋は市場に沢山あります。では、どのようにしたら良いかと言えば、最後は賃貸仲介営業マンから入居者に、自身の部屋(商品)を提案してもらう必要があります。
そしてこれが最も重要なステップです。わかりやすい事例をお話します。私は、電機メーカーに勤務していたことがあります。会社のエンジニアは日々、ユーザーに喜んでもらうために、商品をできるだけ小さくしたり、軽くしたり、様々な機能を付けることに腐心していました。
例えば、デザインも洗練され、新機能が付いたパソコンを作って世に送り出すために、何十人、何百人のエンジニアが血の滲む努力をします。皆、自社の商品が一番優れている、と思うわけです。他社にはない優れた機能が付いたパソコンであったらユーザーは皆、そのパソコンを購入する可能性が高いです。
しかし、実際には自社よりもスペックが劣る競合他社の商品が選ばれることは珍しくありません。家電量販店に行って観察すればわかりますが、ユーザーはショップの店員の提案(意見)によって決めていることがあるためです。パンフレットには魅力的な新機能の説明がされていますが、実際には店員の口頭による説明が購入の決め手になることが少なくありません。
賃貸不動産経営も同様です。数ある同じような部屋の中から、営業マンに自身の部屋を選んでもらい、入居者に提案をしてもらわなければ入居申込みは入りません。
では、営業マンに部屋を提案してもらうにはどのようにすれば良いのでしょう。それは、営業マンになるべく手間がかからないようにすること、そして広告料(業界用語で「AD」と言います)を効果的に活用すること、に尽きます。
営業マンはとにかく時間に追われています。多忙な営業マンに気持ちよく部屋を提案してもらうためには、営業マンにスムーズに動いてもらう環境づくりが重要です。例えば、契約書の作成を管理会社が代行してくれる、鍵が物件にあるので入居者に案内しやすい(鍵を管理会社まで取りに行かなくて良い)、等は基本的な対策です。
また、マイソク(賃貸募集のチラシ)に必要な情報がわかりやすく記載されていることもポイントです。仲介手数料や広告料の具体的な記載がなければ、営業マンは案内する気になりません。
また、物件の外観写真や部屋の間取り等が大きく、わかりやすく掲載されていれば営業マンだけでなく、入居者もイメージしやすいでしょう。問い合わせ先に、担当者の携帯電話番号まで記載があれば、チャンスを逃すことも少なくなります。
そして、営業マンが物件を提案し契約に至った場合、どのくらいの売上が立つのかが重要です。それが入居者から支払われる仲介手数料とは別に不動産投資家サイドから支払われる広告料なのです。
3.賃貸仲介営業マンと広告料について
宅地建物取引業法では、賃貸仲介会社は入居者の物件成約時に、入居者とオーナーから、合計で家賃1ヶ月分を上限として仲介手数料をもらえる旨が規定されています。
法律で規定されているのですが、実際の賃貸市場では入居者からもらう1ヶ月分の報酬では会社を維持することが難しいのが現状です。そこで実務的には、賃貸仲介会社はオーナーからもらう1ヶ月分の報酬を広告料として収受しているのが現状です。
ここで私自身の部屋探しの体験をお話します。インターネット上で住みたいと思った部屋を見つけ、賃貸仲介会社に問い合わせをして仲介して欲しい旨を伝えましたがはぐらかされ、提案されたのはまったく別の物件だったのです。
私が借りたい部屋はまだ残っていたので、なぜ別の物件を提案するのかと聞いてみたところ、「実入り(報酬)が少ないので、別の部屋を提案しました。実状をわかって欲しい」とまで言われました。
つまり、私が借りたかった部屋をオーナーから預かっているのは別の管理会社で、この部屋を仲介したところで、仲介手数料は1ヶ月分。それであれば、仲介手数料とは別に広告料をもらえる自社で預かっている(管理している)部屋を提案して、家賃の2か月分をもらいたかった、ということでした。
このように宅地建物取引業法の仲介手数料の規定は実務上機能していないと言えます。仲介手数料とは別に、「広告料」という名目で対価を得ることができなければ、入居者に部屋を提案しない、と言っているのと同じです。
首都圏では、最寄り駅から距離がある、もしくは差別化が難しい物件では広告料を3ヶ月分(時期によっては4か月分)支払わないとそもそも提案をしてもらえない、という物件も存在します。物件購入時にレントロール等を確認するだけではわからないことが多く、広告料の相場を熟知していないと空室を避けることはできません。
ほぼ似たようなスペックの部屋で、早期に入居者が決まる部屋とそうではない部屋では、この広告料が影響している可能性が高いと考えられます。特に、オーナーがファンド等の法人の場合、賃貸市場を熟知していますので、広告料を相場以上に支払って早期に空室を埋める傾向があります。このようなときに、広告料の仕組みを知らない不動産投資家は大きく出遅れてしまうリスクがあり、注意を要します。
賃貸仲介営業マンは、給与が歩合制で定められていることが多く、広告料が出ない物件には積極的な営業活動を行わない可能性があります。逆に言うと、あまり差別化ができていない物件でも相場以上の広告料を支払えれば営業マンは積極的に提案してくれるのです。場合によっては、空室期間の大幅な短縮と相場以上の家賃で決まる可能性もあります。
まとめ
不動産投資には、空室リスク以外にも天災や金利上昇、建物の劣化等様々なリスクがあります。空室率の上昇が見込まれる昨今、不動産投資家としては、これらのリスクに適切に対応しなければ入居者の確保はままなりません。
これまで見てきたように、空室リスクを回避するということは、企業経営で言うところの売上を上げる、確保することにつながります。コスト削減等の交渉も大事ですが、経営はまずは、売上を上げないことにはどうしようもありません。
そして、不動産投資(賃貸不動産経営)をする以上は、利益を出し続けなければいけません。将来の個人年金として考えている投資家も、直近のキャピタルゲインの獲得を考えている投資家もこれは同じです。
ここでは、戦略を立てて、パートナー(管理会社)と連携して商品(部屋)を作り、パートナー(賃貸仲介会社)に販売(仲介)してもらう、という一連の流れを解説しました。これからの大空室時代を乗り切るために、少しでも参考になれば幸いです。
不動産投資ローン、抵当権と根抵当権の違いは?抹消手続きの方法も
1.抵当権・根抵当権とは
まずは抵当権・根抵当権とは何か、根抵当権の「極度額」についてお伝えしていきます。
1-1.抵当権と根抵当権
投資用ローンにおける抵当権とは投資用不動産を担保に設定し、返済が滞った場合に不動産を差し押さえ競売にかけられる権利を指します。
金融機関は抵当権を設定し、競売による売却又は担保物件を貸し出し、賃料といった収益を弁済に充てることにより、返済されない債務を回収できる可能性があります。ローンを完済した時には、法務局で抵当権抹消登記の手続きを行い、不動産から抵当権を外すことが出来ます。
一方、根抵当権は「継続的な取引」を前提としたもので、不動産の価値を基に算定された貸し出し金額の上限を「極度額」として設定、極度額の範囲内で担保する抵当権です。
抵当権は特定の不動産を対象としているのに対し、根抵当権は不特定の債権を対象としています。継続的に融資・返済を繰り返す場合、根抵当権を設定することで、抵当権の設定・抹消手続きを行う費用と手間を省くことができます。
1-2.根抵当権の「極度額」
根抵当権にはあらかじめ融資する人とされる人の間で取り決めた「極度額」が設定されます。
金融機関によっては「借入金額は極度額の○%以内まで」と設定するところもありますので、「極度額=貸出限度額」ではないということをおさえておきましょう。なお利害関係者の合意があれば、極度額は変更する事ができます。
2.抵当権・根抵当権、4つの違い
抵当権・根抵当権には主に以下の4つの違いがあります。
- 対象となる債権
- 権利の抹消
- 連帯債務者
- 元本の確定
2-1.対象となる債権
抵当権の担保となる債権(借入金)は主に購入予定の不動産ですが、根抵当権の担保となる債権は特に定められていません。そのため何度でも融資を受ける事ができます。
根抵当権を設定する際には、債権者と債務者があらかじめ契約日や金額、返済、利率などと共に極度額と債権の範囲を話し合い、決めた内容を契約書として書面化、契約を締結します。
2-2.権利の抹消
抵当権は担保となっている不動産のローンを完済することで、事実上消滅します。登記簿上で抵当権は設定されていますが、金融機関から必要書類を受け取り、法務局で抹消の手続きを行い権利が抹消できます。
一方で根抵当権は、1件の借り入れと返済が終わった後でも再びやり取りが行われる可能性があるため、当事者間で合意が無いと抹消手続きを行う事ができません。
2-3.連帯債務者
抵当権には1つの借り入れに対して連帯して債務を負う「連帯債務者」の設定が可能ですが、根抵当権ではほとんどのケースで連帯債務は認められていません。
抵当権は特定の不動産に対して設定されますが、根抵当権は返済金額や期間、対象が定められてないため連帯債務が出来ない形となっています。
2-4.元本の確定
不動産をローンで購入する際、抵当権を付ける場合には返済金額や期間が既に確定しています。根抵当権は、設定した時には元本が確定されておらず、定める場合もあれば定めない場合もあります。
設定時から3年経過すると元本の確定を請求できるようになり、請求から2週間後には元本を確定することになります。
3.根抵当権の抹消手続きの方法
基本的に抵当権が付いた不動産は売却ができないため、抹消手続きが必要となります。手順は以下の通りになっています。
- ローン残債と売却価格の相場を比較
- 金融機関と相談
- 根抵当権の抹消手続き
3-1.ローン残債と売却価格の相場を比較
不動産を売却する時にローンが残っている場合は、ローン残債と売却価格の相場を比較しましょう。ローン残債は金融機関に尋ねる、売却価格の相場は不動産会社に査定を依頼する事で分かります。
不動産会社の査定で提示された査定額とローン残債を比べ、ローン残債が上回る時はオーバーローンとなります。
根抵当権は特定の不動産を担保としたものではありませんが、オーバーローン状態の家は金融機関が根抵当権を外すことに同意しない可能性が高いと言えます。オーバーローンの不動産は、金融機関に売却の可否・価格の了承を得て、権利を外す「任意売却」を検討してみましょう。
【関連記事】不動産の任意売却とは?メリット・デメリットや売却手順を解説
なお、通常の抵当権は残債が無くなることで抹消されますが、根抵当権は借入金をすべて返済しても消滅することはありません。以下の手続きが必要になるため、注意しましょう。
3-2.金融機関と相談
根抵当権を外す際は、当事者の合意が必要となりますので、金融機関と相談を行います。合意が得られた際は話し合い、元本を確定します。金融機関と未返済額や金利、返済期限などについて話し合い、返済額を明確にする「元本確定」を行います。
3-3.根抵当権の抹消手続き
管轄の法務局で根抵当権の抹消手続きを行います。必要となる書類は以下の通りです。
- 根抵当権抹消登記申請書
- 登記原因証明情報
- 抵当権設定契約書(登記済証)
- 代理権限証明情報
- 会社法人等番号の分かる書類または資格証明情報
- 委任状(代理人に依頼する場合)
「根抵当権抹消登記申請書」は法務局のホームページで印刷する事が可能です。2~5の書類は、金融機関から送付されてきます。いずれも日付や基本情報に誤りが無いか、確認しておきましょう。
登記手続きは法務局の窓口で直接書類を持参する方法のほかに、オンライン・郵送でも申請が可能です。
自身で手続きを行う事が困難である方は、費用はかかりますが司法書士への依頼も検討しましょう。代行を依頼する際には、押印済みの委任状が必要となります。
まとめ
抵当権と根抵当権は対象となる債権や抹消の方法が異なります。一番の違いは根抵当権が「債権を特定しない」ことで、抹消には金融機関の合意が必要となり通常の抵当権抹消より手間がかかります。
根抵当権が設定されている場合、返済が完了しても消失しない特徴があります。売却時にトラブルとなるケースもあるため、事前に抹消手続きの手順・方法について確認しておきましょう。
個人がリスクの高い不動産投資をするよりも、REITを推奨する理由
投資用不動産はリスクが高い
投資として貸家を持つ人が少なくないようだ。利回りが高いという宣伝を見れば、魅力を感じるのは自然なことだろう。しかし、表面上の利回りは高いけれども、それなりのコストがかかるしリスクもあるので、慎重に検討すべきだ。
コストとしては、税金や管理費といった経費に加え、借り手が変わるたびに壁紙を張り替えたり、場合によっては設備を入れ替えたりするほか、時間の経過とともに大規模な修繕や建て替えが必要になる場合もある。法人であれば減価償却費を計上すべきであるが、個人であっても費用として認識する必要があるわけだ。
リスクとしては、空き家になって家賃収入が得られない、家賃の下落、物件それ自体の価格の低下などがある。人口が減少していくので、家賃や不動産価格には全体として、下落圧力がかかるはずだ。
特に、新しく借家に入居するであろう若い世代の人数は急激な減少が懸念される状況だ。空室や家賃下落のリスクは、立地によってはかなり大きいと覚悟しておくべきである。
30年間家賃を保証する、といった業者もいるようだが、契約内容を慎重に検討すべきである。たとえば保証するのは現在の家賃ではなく、その時々の周辺地域の家賃相場に応じた額を保証する、という程度かもしれない。
それ以外にも、借家人とのトラブルが発生する可能性もあろうし、地震で建物が倒壊することも考えられる。ちなみに地震保険は、建物の建て替えに必要な費用は出ないので、完全な補償ではないことに留意すべきであろう。
さらには、金融商品と比べて圧倒的に流動性が低いので、資金が必要になったときに、すぐに売れるとは限らないし、急いで売ろうとすると安い値段で買いたたかれる可能性がある。
そもそも、自宅に加えて投資用不動産を持つことは、資産総額に占める不動産の比率が高くなりすぎるであろう。資産は、預貯金、不動産、株式、外貨などにバランスよく分散することでリスクを抑えることができるのに、それができないこと自体が大きなリスクなのである。
貸家保有のメリットとして、相続税対策が挙げられるが、そもそも相続税の負担額はよっぽどの資産家でない限り、大した金額にはならないのであって、「上級庶民」のレベルであれば相続税対策の方が相続税より怖い、というのが筆者の認識である。
その意味では、相続税対策としての貸家を検討する際には、まず自分の相続税を計算してみることをお勧めしたい。
REITの方がマシ
不動産投資信託(REIT)という投資商品がある。株式投信と似たような商品で、プロが小口の資金を集めて不動産を購入し、賃貸料収入や売買益などを得て投資家に配当するという仕組みだ。これを持つことで、投資家は小口資金でも、投資用不動産の一部を持つのと同様の効果が得られるわけである。
上記のように、筆者は貸家の保有をお勧めしていないので、REITについても積極的にお勧めしたいとは思わない。しかし、自分で貸家を持つよりはマシだと考えているので、貸家保有を検討している人はREITも検討してみるといいだろう。
また住宅資金を貯めている人は、その分をREITで運用するというのが合理的かもしれない。住宅購入金額の1割が貯まったから、住宅を10分の1だけ買う、ということはできないので、貯金している間に住宅価格が上昇してしまうリスクがあるが、そうしたリスクへの備えとしてREITが使えるからだ。
REITは株式投信と仕組み的には似ているが、大きく異なるのは、プロに頼むメリットが大きいということである。
株式投信の最大のメリットは、小口資金で多くの銘柄に分散投資ができることであって、プロに銘柄を選んでもらうことのメリットはそれほど大きくない。上場株式が値上がりするか否かは、プロでも判断が難しいので、プロに頼む投資信託を買っても素晴らしい値上がり率が期待できるというわけでもなく、一方で結構な手数料を取られる。
しかしREITの場合には、投資用不動産を選んで買うという作業だけでも、素人とプロとでは技量に大きな差が出る。借家人との交渉も当然、プロの方が慣れているだろうし、壁紙の張り替え等々もプロの方がスムーズだ。
実際にはREITは、普通の個人が買えないようなオフィスビルやホテル、テーマ―パーク、一棟買いのマンションなどの物件を取得するが、入退去にまつわるもろもろの作業負担やリスクは、運営する法人や管理会社が一手に引き受けてくれる。
さらに大きいのが、大量購入のメリットである。上場株式は1000株買っても100万株買っても同じ値段だが、ワンルームマンションを1部屋だけ買うのと1棟買うのでは当然、値段が大きく異なる。
というわけで、自分でワンルームマンションを購入するよりも、同額の資金でREITを購入する方が、プロに任せるメリットが期待できる。加えて、売りたいときに市場で簡単に売れるし、REIT投資それ自体が多くの投資用不動産に少しずつ投資する「分散投資」となることを考えれば、REITという選択肢は検討に値する。
最後に、税法上のメリットについて税理士と相談してみるといいだろう。自分で不動産を所有すると、賃料の所得に対して所得税が累進課税で課せられるが、REITには法人税がかからないので、REITを持っていれば得られる値上がり益や配当に対して20%強の源泉分離課税を負担するだけでいいからだ。
本稿は、以上である。なお、本稿は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する組織などとは関係がない。また、当然であるが、投資は自己責任でお願いしたい。
「中村アン」に知ってほしい住宅ローン「アルヒ」の“犯罪” 「なんちゃって」物件と契約者の収入額改竄
横須賀の「階段地獄」物件は買い? 小説で学ぶ不動産投資
そんなことを思いながら、俺はスマホで地図を確認しつつ、神奈川県横須賀市のとある道を歩いていた。
不動産会社「2ndエモーション」で働く俺は、売り主からの依頼があれば(そして、上司からの指示があれば)どこにだって出かける。そして、この10年間ずっとやってきたように、売りに出された物件の「マイソク」を作成するのだ。
マイソク。物件の間取りや所在地、築年数、利回りに価格…さまざまな情報をまとめたこの資料作りは、地味な作業だと思う人も多いだろう。だが、自分でも不動産投資をやってみたいと思う俺にとっては、いろいろな物件と出合え、かつ収支を計算して「俺が不動産投資家だったら」と妄想を繰り広げられる時間でもあるのだ。
そのひと時こそ、俺にとっての「人生最高の時間」である。
◇
今回の物件があるのは、神奈川県横須賀市。横須賀中央駅から歩いて少し行った場所だ。横須賀は山や坂が多いのが特徴で、丘陵地に建っていて、入口まで何段もの階段を上らないといけない戸建ての物件も少なくない。
これまで俺が見てきたマイソクによれば、そうした「階段物件」の家賃相場は、間取りや築年数にもよるがだいたい5万円。入居者は、単身だが広い物件に住みたいという人がターゲットになりやすいが、やはり客付けに苦労しやすいとも聞く。
今回の物件は、果たして―。
セミの声が、やけに大きく聞こえる。やっぱり、暑い。歩いているとどうにも暑い。間違って長袖シャツを着てきたのも敗因だ。
物件に着く前に、冷たい飲み物でも飲んで一息つこうと、道端の自動販売機でアイスコーヒーを買った。一口飲んでその冷たさを楽しんでいると、そばを通り過ぎる若いカップルの、なんてことない会話が耳に入ってくる。
「最近観た映画、めっちゃつまらなくって」
「なんの映画?」
「恋愛映画なんだけどさー」
映画か、最近観てないな。つまらない映画にあたると、何とも言えない切なさに襲われるんだよな。それが映画館に観に行っていたりすると、余計に……。
見知らぬ男女の会話に心の中で勝手に参加していると、「そういえばさ」と彼女が彼氏の前で立ち止まった。
「なんで『つまらない』って、『つまる』に『ない』をつけるのかな? 面白いときに『つまる』って言わないじゃん?」
「ああ、確かに言われてみれば……。そういう時はさ、『文明の利器』を使ってみるんだよ」
彼氏の方が、ポケットから「文明の利器」ことスマホを取り出して検索をし始める。
「へー。もともとは『つまる』って……」
ネット検索の結果が表示されているらしいスマホを、2人がのぞき込む。その光景が、なんだか感慨深かった。何かがわからないとき、そのわからないことを自分で調べてみるって、仕事でもどんな時でも基本だよな。10年この仕事をしていると、つい経験と勘に頼りがちになって、調べることを怠ってしまう。俺も初心を忘れないようにしないとな。
◇
スマホの地図が、俺が目的地に到着したことを示している。だが、目の前に物件はない。あるのは……横須賀名物「階段地獄」だ。なるほど、今回の物件も、横須賀の「階段物件」だったらしい。
会社の部長である渡良瀬さんは、「段数が50を超える物件は、客付け会社やリフォーム会社から敬遠されるんだよな~」とこぼしていたが……。さて、今回の物件はどうなんだろうか。
階段の1段目に足をかけ、心の中で「1」とつぶやく。「勝手に階段数え大会」の始まりだ。
2、3、4……。順調に数は増えていく。残念ながら、頂上に着く前に50をコールしてしまった。残り10段ちょっとあるから、全部で60段くらいって感じか。しかし、こうも立地が悪いとなると、あとは物件の状態にかかってるな……。
残りの階段を上り終え、ようやく物件の全貌を見ることができた。
横須賀市内にある木造平屋の戸建て。間取りは4DKと広めだが、築年数は不詳らしい。ぱっと見、50年くらいは経過していそうな印象を受けるが、状態は悪くない。売り主の倉田さんは「480万円で売りたい」と言っていると営業の人間からは聞いた。
俺の中の「不動産投資家ゴコロ」がむくむくとわいてくる。じっくりと外観を眺めて物件をチェックしていると、屋根の上のアンテナが折れていることに気づいた。それに、屋根がトタンだ。台風や大雨の時が少し心配だな。
「お邪魔します」
小さく言って、中へ入る。全体的にきちんとリフォームされていて、きれいな状態だ。作りは昔ながらで、なんだか、子供の頃住んでいた石川県の実家を思い出した。
今回の売り主である倉田さんは、築古戸建てを安く買い、DIYで修繕して入居者に貸すスタイルをとっている投資家だ。この物件でも随所にDIYを施したと聞いている。例えば床は畳をはがしてクッションフロアに。さすが倉田さん、抜かりないリフォームだ。踏みしめても、床がへこむようなところもない。
キッチンも新品に交換されていたし、風呂場の状態も悪くない。これなら、この物件を購入したとして、入居付けのためのリフォーム費用はそこまでかからなさそうだ。
あとは建物全体でゆがみがないか、扉などの開け閉めをして確認するのも大事だ。これが途中でつかえてしまうようなことがあれば、その扉や建具に不具合があるか、あるいは地盤が沈むなどして、建物自体にゆがみが生じてしまっている可能性がある。そうなると修繕に多額の費用がかかったり、最悪解体を余儀なくされたりするから、物件購入前には絶対に押さえておきたいポイントだ。
この物件の場合は、いくつかの扉や窓で確認したが、どこもスムーズに動かすことができた。建物のゆがみに問題はないと判断していいだろう。
「ん?」
ふと、天井に謎のたわみがあるのが目についた。雨漏りだろうか……。雨漏りがあるとなると、修繕費は覚悟しておかないといけない。原因の特定も容易じゃないしな。
さっき外観をチェックしていても気になったが、台風などでトタン屋根が全部だめになる可能性もあるし、ここは要注意ポイントだ。
◇
そういえば、このエリアの物件は利回りどの程度なんだろうな。まあだいたい10%前後ってところか? そうなるとこの物件の利回りは……。
いやいや。そこまで考えて、俺は思考を止めた。さっきあのカップルを見て初心を忘れないようにしようと決めたばかりじゃないか。勘や経験に頼るばかりではよくない。わからないことは、きちんと調べないと。
文明の利器であるスマホを取り出し、ブックマークから収益物件情報サイト「楽待」を選択する。横須賀エリアの戸建てに絞って情報を見てみると、だいたい表面利回り11~12%で売りに出されている物件が多いようだった。
数年前の相場は約13~14%だったから、値上がりが顕著だな。最近は特に初心者向けに戸建て投資は人気だし、その影響もあるのかもしれない。
そんなことを思いながらなんとなく部屋の隅に目を向けて……俺は思わず「それ」を二度見してしまった。日本最大級と言われるアシダカグモがそこにいたのだ。ゴキブリを食べてくれるらしく、益虫という人もいるそうだが、俺はクモは気持ち悪くて苦手だ。しかもなんだよ、手のひらくらいのその大きさは……。早いところマイソク用の写真を撮って、仕事を終えよう。
クモは見なかったことにして、空室の物件をさまざまな角度から撮影する。これで十分だろう。なんだかカサカサという音も聞こえるし、早いところ外に出たいところ、なんだが。
―この物件、いくら儲かるんだろう。
やっぱり、不動産投資家妄想が膨らんできてしまう。俺の脳内で、数字がくるくると踊り出した。
◇
物件価格は、売り主の希望金額である480万円で計算してみる。家賃は階段物件の相場、5万円で考えてみるか。
そうすると、年間家賃収入は「5万円×12カ月=60万円」。表面利回りは、「60万円÷480万円×100=12.5%」。なるほど、表面利回りだけでいえば、このエリアの他の物件と同じか少しいい感じだな。
じゃあ、かかる経費も加味するとどうだろう。
管理費はだいたい家賃の5%として、月々2500円。年間だと3万円だ。
固定資産税・都市計画税も、年間でだいたい3万円くらいかな。あとは火災保険料が1万円。これらを年間家賃収入から差し引くと、「60万円-3万円-3万円-1万円=53万円」。単純計算で「53万円÷480万円×100=11%」だな。
物件価格的には相場と同程度だから、そこまで旨味は大きくないんだよな。どうにか交渉して400万円程度まで価格を下げられればいいんだけど、これだけしっかりリフォームしてあると、修繕を理由にした大幅な指値は難しそうだ。
そもそもの話、俺がもしこの物件を購入するとなったら、購入費用はどうすべきだろうか? 築古戸建て物件への融資はなかなか厳しく、受けられるかどうかは微妙なところだ。かといって現金で買うと言っても、今の俺の貯金額だと、急な修繕が発生する可能性を考えれば少し心もとない。
それに、この60段以上もの階段の上にある立地だ。客付けがすんなりうまくいくかといえば、不安な面もある。入居付けのための修繕だって、費用を抑えるためにDIYせざるを得ないかもしれないが、俺はDIYに関しては門外漢だしな……。
―この物件、俺が不動産投資家なら、購入は見送りだ。
◇
俺にとっては見送りでも、資金に余裕のある人にとっては「買い」の場合もあるかもしれない。
やはり、俺が不動産投資を始めるにあたっては、自己資金を貯めることがまずは急務になりそうだ。
不動産投資で
有利な融資を得るための
3つのポイント
最低でも5行に融資を持ち込もう
どうやって有利な融資をしてくれる銀行を開拓したらいいか? あるいは優秀な銀行の担当者を紹介してもらえるのか? という読者の皆さんからの最大の疑問にお答えしよう。その答えは、大きく以下の3つだ。
①成功している大家仲間とセミナーなどで知り合い、銀行を紹介してもらえるように、ギブ・アンド・テイクの精神で仲良くなる。ポイントは、洗練された大家はあまり表に出てこないことと、本当に紹介に足る人物と事業性でないと自分の大切な銀行担当者を紹介してくれない。礼儀を尽くしつつ、自身のやれる宿題、恩返しはしっかりと行おう。
②融資獲得に長けているコンサルタント、もしくは大家仲間にコンサルタント費用を払って融資のアレンジをしてもらう。これは一番手っ取り早い。そしてお互い本気で動けるので、より有利な融資条件を引け出せる可能性が高い。実際に僕も過去にはお世話になったし、そのおかげで年間の支払い金利が減り、ローン後キャッシュフローが増えるのだから、コンサル費用を払って余りあるリターンがある。
③自分でひたすら銀行を訪問する。これはハーバード式不動産投資術のDo Your Homework精神に慣れてきた皆さんなら、ぜひやってもらいたい方法だ。門前払いはざらだが、そこからの学びは非常に大きい。そして、銀行に突撃訪問をすればするほど、自分独自の銀行開拓ができる。僕の場合もはじめて融資OKをもらった銀行は自身で突撃した銀行で4行目だった。
なお、本連載で説明してきた投資事業計画書(プロ・フォルマ)は英語で作成することができれば、世界中どこでも通用する共通言語となる。今回は、僕の経験と日本の融資事情に合わせて、実際に僕自身が銀行に提出して、有利な条件での融資を獲得している事業計画書を共有する。
ぜひ、この事業計画書をダウンロードして、ご自身が取り組もうとする物件の数値を入れてもらい、銀行に持ち込んでみてほしい。もちろん1行ではなく、最低でも5行に。きっと担当者の反応が変わるはずだ。https://www.kurofune-dh.com/contact
不動産投資で活用できる銀行の特徴と融資姿勢
以下にざっと、不動産投資で活用できる銀行の特徴と融資姿勢をまとめておく。
・大手都市銀行系(三井住友、三菱UFJ、みずほ)
基本的には三井住友銀行が不動産融資を長らく手掛けてきたことで一歩リード。ただし、リーマンショック以降は資産家でもない限り融資額は総投資額の70%で自己資金が30%必要だったりと、難攻不落。金利は当然安い。
・準都市銀行(りそな銀行、埼玉りそな銀行)
僕のメインバンクでもあり、不動産投資に積極的に取り組んでくれる。難しい不動産であっても、銀行内の不動産部が活躍してくれて、時にはディールをまとめてもくれるので非常に頼りになる。スルガショック以降は80%から85%ローンにはなっているものの、金利も安い。審査態度は支店にもよるので、地元支店にまずはヒアリングしてみよう。
・地方トップ銀行(横浜銀行、千葉銀行、静岡銀行、東京スター銀行他やご自身の地域の地銀)
比較的、不動産投資に理解があり、しっかりとした事業計画書とある程度の貯金があれば、いろいろと柔軟にローンを考えてくれる、ありがたい存在。担保評価などを独自に行っている場合もあり、都市銀行系で融資額があと一歩のときに頼れる存在。金利はやや安い。
・不動産特化型銀行(スルガ銀行、オリックス信託銀行)
実は僕も家族でリーマンショック後に仕込んだ中古マンションは、スルガ銀行にお世話になったし、新築物件で少し評価が難しい物件でお世話になったことがある。金利も交渉で徐々に下がり、現在は地方銀行並みの金利なので借り換えもせず、いい関係を続けさせていただいている。
スルガショックのイメージから敬遠する方も多いと思うが、買い付けでの競合が多いケースで融資獲得のスピード感が必要な場合や、キャッシュフローが十分出ている場合だが中古耐用切れ物件などでは大いに活用機会がある。いや、あった、というべきか。現在は両銀行とも不動産融資について慎重な姿勢のため、不動産投資ゲームからしばらくは降りている状態だ。
・ノンバンク系銀行(アサックス、SBI、セゾンなど)
金利は高いが審査は非常に速い。賢くローンを引くためには、あまりお世話にならない銀行だ。使い所としては、残債が減ってゆき、担保余力が出てきた物件をもとに、追加融資を引き、海外不動産など特殊な案件の獲得に充てるなど。
・政策金融公庫
これは特殊解だが、不動産融資も受けられなくはない。民間の銀行と違って、女性やシニア起業を支援していることもあり、条件が揃えば、有利な条件が引けることもある。金利は中程度。また、特殊な使い方として、不動産担保ローンに加えて、自身の不動産で旅館業やシェアオフィスなどの運営を行う場合にも借入ができたり、担保余力があれば第二抵当での融資も可能だったりする。使い方はクリエイティブに考えていい。
建築家・不動産投資家
KUROFUNE Design Holdings Inc. 代表取締役CEO
ハーバード大学デザイン大学院で不動産投資と建築デザインを学び、投資理論とデザインの力を融合させたユニークな不動産投資を行う。
鹿島建設入社4年目に不動産投資を開始。数々の不動産投資セミナーに足を運び、不動産関連書籍を数十冊読破。そんな中で出会ったメガ大家集団をメンターに持ち、指導を仰ぎながら不動産投資をスタートする。最初に行った東京・神楽坂での新築マンション開発では超狭小地に苦労し、辛酸を舐めつつも独自の不動産投資スタイルを確立する。現在5棟の超優良物件を保有。保有物件の中では投資額が4年間のうちに26倍になったものもある。
1982年高知県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科、同大学院卒業後に鹿島建設入社。
大学院卒業時にリゾートホテル開発プロジェクトにより早稲田大学小野梓芸術賞を受賞。
同社では国内外で建築設計や大規模な都市開発業務に従事。鹿島建設社長賞、グッドデザイン賞、SDレビュー賞などを受賞。2016年、ハーバード大学デザイン大学院(GSD)へフルブライト留学。2018年、GSD不動産デザイン学科を卒業、外資系不動産ファンドでの投資業務を経験した後、KUROFUNE Design Holdings Inc.(デザイン事務所兼不動産ファンド会社)を創業し独立。現在はハーバード学生寮生活で得た原体験をもとに、住まいと学びを融合させた国際学生寮「U Share」を開発運営する。また、慶應義塾大学SFC特任講師、早稲田大学特任講師として「不動産デザイン」について教えている。初の著書に『ハーバード式不動産投資術 資産26倍を可能にする世界最高峰のノウハウ』(ダイヤモンド社)がある。
不動産投資 赤字でも売らないほうがいい物件とは
投資用アパート・マンションは、収益を目的として投資し所有するものですから、最終的な手取りが赤字となり、それを解消できる術がないならば、売却するのが得策と考えられます。しかし、相続対策で取得した投資用物件に関しては、売却が得策ではないケースがあります。
55歳の女性から相談がありました。10年前に、その女性の母親(当時85歳)が相続対策のために新築一棟収益物件(1階は歯科医院、2階以上は賃貸マンション)を取得しました。しかし、1階のテナントが最近退去したことから収益性が落ち込み、最終手取り額が年100万円程度の赤字になっていることが分かったため、売却すべきかどうか悩んでいるというものです。
この賃貸物件には、まだ2億5000万円もの借入金が残っていることもあり、一人娘である相談者は、将来そのような負債を背負いたくないという思いが強かったようです。95歳の母親は入院して久しく、相談していた不動産仲介会社からは、「新たなテナントをすぐに見つけるのは簡単ではない」「借入返済額が大きいため、新たなテナントが見つかっても大幅黒字にはならない」「母親の意思がしっかりしているうちに売ったほうがよい」「今なら4億円程度で売却できる」といったアドバイスがあったと言います。
不動産仲介会社のアドバイスに従うか
このような事案はよくありますが、不動産仲介会社の言う通り、すぐに売るべきなのでしょうか。
赤字に陥っている場合、まずは空室を埋める工夫や運営コストを削減できる方法がないかを確認します。打つ手がない、あるいは入居者を入れても採算が合わないと判断した場合には、売却を検討することになります。ほかに収益を生む不動産を保有している場合は、借り入れによって取得した赤字物件を売却することで、借入金の返済が減少し、最終手取り額が思った以上に改善されることもあります。こうしたことから、赤字解消が難しい物件を売却することは、ある一面においては決して間違ってはいないのです。
相続税への影響も考える
しかし、相続税を視野に入れると見え方が大きく変わってくる場合があります。今回のケースについて、簡単にシミュレーションしてみましょう。まずは売った場合の手取り額の概算です。

右の表のとおり、売却想定価格4億円、本物件の取得費(取得時の土地価格、減価償却後の建物価格、取得時の各種費用を合計したもの)を3億円とした場合、譲渡にかかる税金は約2000万円となります。ですから、売却想定価格から税金と借入金を返済した後の残りとなる1億3000万円が最終手取り額となることが分かります。
次に相続税を概算してみます。相続税は、簡単に言えば、プラスの財産(不動産や現金などの金融資産)からマイナスの財産(借入金など)を差し引いた金額に税率を乗じて求めます。ここで重要なことは、借入金を返済してしまうと、相続税の対象となる財産が増加し、税額が増えてしまうことです。

この物件の相続税評価額は、1億5000万円(路線価にて求めた土地評価額1億円、家屋の固定資産税評価額5000万円)でした。ですから、この物件を売却すると、1億5000万円の不動産が減少、1億3000万円の現金が増加、相続財産全体から控除できる借入金2億5000万円が減少するので、結果的に相続財産は2億3000万円増加することになります。仮に相続税の限界税率が40%だったとすると、相続税が9200万円も増加することになります。
このケースでは、ほかにも収入を得ることができる不動産をいくつか保有していたことから、年100万円の赤字に十分に耐えられることが分かり、売却しないことに決定しました。ただ、その2年後に相続が発生し、しばらくしてから相談者は売却を実行しています。
このように、相続対策を目的として借入金で収益物件を購入している場合、仮にキャッシュフローが赤字に陥ったとしても、その赤字額の負担が過大でない場合は売却しないほうがよいことが多いものです。相続前に売却して、後で大変な負担を負うことになったケースはよくあるので注意が必要です。
投資用マンション売却の注意点は?失敗しない売却の手順・相場の調べ方も
1 投資用マンションを売却するときの注意点
通常の不動産の売却を経験したことがある人でも、投資用マンションとなるとまた少し違う知識が必要になります。注意点を紹介しますので、見ていきましょう。
1-1 査定価格は収益還元法を参考にする
不動産の売却をする際に販売価格の目安となるのが不動産会社が行う査定です。通常の不動産であれば、物件の状態や類似の取引事例などを加味して不動産会社が査定価格を算出します。
これらは「取引事例比較法」や「原価法」と言われる方法ですが、自分が住むための不動産ではない投資用物件の場合は違います。投資用物件には収益性があるため、先ほどの査定方法に加えて「収益還元法」という方法が用いられます。
収益還元法は、その投資用マンションが生み出す収益力に基づいて不動産の価格を求めていく方法です。求め方は、直接還元法とDCF法の2つあります。
- 直接還元法:投資用マンションが生み出す1年間の収益を、還元利回りで割り戻して求める方法
- DCF法:Discounted Cash Flowの略で、将来得られると予想できる収益から現在の価値を引いて求める査定価格
ここでは、初心者でも分かりやすい「直接還元法」の計算式を見て行きましょう。
年間家賃収入÷還元利回り×100=査定価格
還元利回りはキャップレートとも言われ、周辺エリアの類似物件の利回りを参考にして決めます。例えば、年間の家賃収入が240万円で、還元利回りが6%であれば、240万円÷6×100の計算式から、査定価格は4,000万円ということになります。
住居用の不動産とは違い、査定価格の算出には収益還元法を加えて行われます。不明や疑問に思ったことは不動産会社に説明を求めてみましょう。
1-2 空室での売却はできるだけ避ける
投資用マンションは、所有する部屋を貸す代わりに家賃収入を得ることで事業として成り立ちます。そのため入居者がいる投資用マンションを購入すると、買主は「利益がいくらあるか」や「投資したお金はいつ回収できるか」などが予測しやすいメリットがあります。
一方、空室の物件を購入すると、家賃収入を得るために新たに入居者を募集しなければいけません。購入後すぐに収入が得られないばかりではなく、入居者がいつ決まるのか確約もないため、買主候補者にしてみると空室の投資用マンションを購入するのに二の足を踏んでしまうこともあるのです。
また空室の投資用マンションは、部屋の中を確認してもらえるメリットもありますが、値引き交渉の理由にされやすいというデメリットもあります。売買を成立させるために価格を下げることにもなりますので、できるだけ満室状態にしてから売りに出すようにしましょう。
1-3 キャッシュフローからも売却時期を考える
事業用の不動産は住居用物件とは違って、手元に資金をどう残すか、を考えて売却するタイミングを選ぶこともできます。その基準のひとつがデッドクロスです。
不動産投資におけるデットクロスとは、主に「ローンの元金返済額が減価償却費を上回る状態」を指しています。
事業用の不動産を購入すると、その購入費用は減価償却として毎年経費に計上することができますが、減価償却ができるのは物件の法定耐用年数によって期間が決まっています。つまり減価償却期間が終わると、計上できる経費が減少してしまい、利益が増えることで税金も増えてしまうのです。
こうした知識がないと、手元に残るキャッシュが知らずに減っているということもあるのです。売却する際は、減価償却がいつ終わるのかも考えてみましょう。
1-4 税金の仕組みを理解しておく
不動産投資は税金との関わりが少なくありません。不動産を取得するには、不動産取得税、所有時には固定資産税などがかかります。また、不動産投資によって得られる所得が増えることで支払う税金も増えていきます。
こうした税金の仕組みを知らないと、気づかずに損をしていることもあります。特に売却の際に知っておきたいのは、短期譲渡所得税と長期譲渡所得税の適用期間です。
短期譲渡所得税と長期譲渡所得税
投資用マンションを売却する際に注意しておきたいのは、売却するときにかかる譲渡所得税です。この譲渡所得税は不動産を持っている期間によって、税率が変わってきます。
譲渡所得には、下記のように短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つがあります。短期譲渡所得は所有していた期間が5年以下で、5年以上になると長期譲渡所得となり、下記のように税率が違います。
- 短期譲渡所得税=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
- 長期譲渡所得税=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
※参照:国税庁「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
つまり所有して4年以内で売却するよりも、5年経過してから売却した方が譲渡所得税が減額することになります。投資用マンションを売却する場合、この5年のひとつの目安と検討してみると良いでしょう。
2 失敗しない投資用マンション売却の手順
投資用マンションを売却するときの流れは、通常の物件を売却するときとほとんど変わりません。ただし売却活動の際には不動産会社や購入希望者に入居状況やレントロール(家賃収入表)を提示する必要があります。また、売買が成立した後は賃貸借契約の引き継ぎを行い、入居者にはオーナーが変更した旨を通知します。
手順としては下記のように進んでいきます。
- 査定を依頼する
- 媒介契約を結ぶ
- 売却活動を始める
- 買主が見つかったら売買契約を結ぶ
- 物件を引き渡す
投資用マンションの売却を失敗しないためには、まずは売却活動をしてくれる不動産会社の選定を慎重に行うことです。そのためには複数の不動産会社に投資用マンションの査定をしてもらうことですが、不動産一括査定サイトを活用することで効率的に不動産会社を探すことができます。
下記の表には、代表的な不動産一括査定サイトをまとめています。不動産会社を選ぶ際に活用してください。
主な不動産一括査定サイト
| サイト名 | 運営会社 | 特徴 |
|---|---|---|
| すまいValue | 不動産仲介大手6社による共同運営 | 査定は業界をリードする6社のみ。全国900店舗。利用者の96.7%が「トラブルなく安心・安全に取引できた」と回答 |
| リガイド(RE-Guide) | 株式会社ウェイブダッシュ | 15年目の老舗サイト。登録会社数800社、最大10社から査定を受け取れる。収益物件情報を掲載する姉妹サイトも運営、他サイトと比べて投資用マンションや投資用アパートの売却に強みあり |
| LIFULL HOME’Sの不動産売却査定サービス | 株式会社LIFULL | 全国3100社以上の不動産会社に依頼できる。匿名での依頼も可能 |
| HOME4U | 株式会社NTTデータ スマートソーシング | 全国1800社から6社まで依頼可能。独自審査で悪徳会社を排除 |
| イエウール | 株式会社Speee | 全国1600社以上、悪徳企業は運営企業が排除。最大6社に無料で不動産の一括査定 |
【関連記事】不動産査定会社・不動産売却サービスのまとめ・一覧
不動産会社から査定結果が返ってきたら、複数社を比較して仲介を依頼する不動産会社を選定しましょう。依頼先の不動産会社と媒介契約書を締結しますが、この契約には下記の3種類があります。
媒介契約の一覧
| 項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 複数の不動産会社への依頼 | ○ | × | × |
| 自分で見つけた買主との単独契約 | ○ | ○ | × |
| 指定流通機構への登録義務 | 無 | 有 | 有 |
| 販売活動の報告義務 | 無 | 有 | 有 |
| 契約期間 | 規制は無し | 3ヵ月以内 | 3ヵ月以内 |
一般媒介契約は複数の不動産会社と締結できるメリットの反面、不動産会社が競合してしまい積極的な売却活動が期待しづらいデメリットがあります。好立地で収益性が高いなど、不動産需要が多い時に検討しやすい契約形態と言えるでしょう。
一方、専任・専属専任媒介契約は1社の不動産会社としか締結することが出来なくなりますが、レインズへの登録義務や活動内容の報告義務などがあり、契約期間中の積極的な売却活動が期待できます。これらの違いを比較して、契約形態を選んでみましょう。
購入検討者が見つかったら、詳細な売買条件について交渉し、売買契約書を作成します。不動産会社が契約書の作成を行いますが、契約締結後の無条件破棄は原則できないため、不明点があれば遠慮なく相談するようにしましょう。
契約後は、契約書に記載されている不動産の引渡し日に決済を行い、不動産の所有権移転登記が行われます。
以上が、不動産売却の主な手順・流れとなります。不動産売却に失敗しないためには、売却のパートナーとなる不動産会社の選定が重要なポイントとなるため、複数社を比較し、慎重に選ぶようにして行きましょう。
3 投資用マンションの相場価格の調べ方
投資用マンションの売却を失敗しないためには、相場の価格をあらかじめ知っておくことも大切です。ご自分でも不動産の相場を調べる方法がありますので、この項目で紹介いたします。
3-1 成約事例情報サイトで調べる方法
不動産売買が成立した事例を詳細に載せている成約事例情報サイトから、類似物件の取引事例を見ることでおおよその相場を探ることができます。
成約事例情報サイトとして情報を代表的なのは、国土交通省から依頼を受けて運営している不動産流通機構の「 レインズマーケットインフォメーション」です。直近の一年間に成立した売買取引の販売価格や成約価格が掲載されています。
検索する際にエリアや沿線、駅、専有面積、築年数などの絞り込みができますので、売却を予定している投資用マンションに近い物件の成約事例を見ることができます。
また国土交通省が運営する「 土地総合情報システム」でも同様に不動産取引価格についての情報が検索できます。こちらはアンケートによる情報をまとめたサイトになります。この「土地総合情報システム」では地価公示も掲載していますので、土地の価格について調べたいときにも役に立ちます。
3-2 不動産ポータルサイトで調べる方法
「LIFULL HOME’S」「suumo」「athome」などの不動産ポータルサイトには、売り出し中の不動産情報が多数掲載されています。この不動産ポータルサイトでも絞り込み検索をすることで相場価格を知ることができます。
それぞれのサイトによって違いますが、「地域」「物件種別」「専有面積」「最寄り駅」「間取り」「築年数」などの条件をご自身の投資用マンションに合わせて検索することで、現在売り出されている物件が一覧で掲載されます。
この物件の価格を検討することによって、ご自身の投資用マンションがいくらで売れそうか、だいたいの価格を予想することができます。
ただしあくまでも表示されるのは販売価格で、実際に売買が成立した成約価格ではないので注意してください。
まとめ
今回のコラムでは、投資用マンションの売却に関わる注意点を紹介しました。
今すぐ売却する予定がなくても、売却の際に戸惑ったり、想定外のことが起きて慌てたりといったことがないように、適切な知識を蓄えておきましょう。
また売却時を見据えることは、投資用マンションを運営していくのにも役立ちます。明確な売却予定がない場合でも、定期的に不動産価格を調査しておくなどの対策をして行きましょう。
住宅ローンと不動産投資ローンの違いとは? どちらを先に組むべき?
不動産投資マンスリーレポート 2021年6月度 年収1,200万〜1,400万円未満の成約者割合が過去最高
【本件のポイント】
- 年収1,200万〜1,400万円未満の成約者割合が過去最高に
- 購入物件の広さは30平米未満の物件の割合が過去最高に(79%、前月比+6pt)
- 成約顧客のうち投資経験がある人の割合が増加(64%、前月比+6pt)

2019年11月度より、 RENOSYでは、資産運用型中古マンション販売実績 2年連続No.1(※1)のRENOSY不動産投資の顧客動向を毎月公開しています。2021年6月度においては、成約顧客の年収のうち、年収1,200万〜1,400万円未満の成約者の割合が14%となり、マンスリーレポート開始以来、最も高くなりました。詳細は、以下の6月度レポートをご覧ください。
RENOSYは、「不動産とお金」に関する透明性の向上を目指して自社で蓄積した様々な不動産データを公開し、1人でも多くの人が、ライフステージに沿ったベストな不動産の選択ができる社会の実現に向けて貢献してまいります。
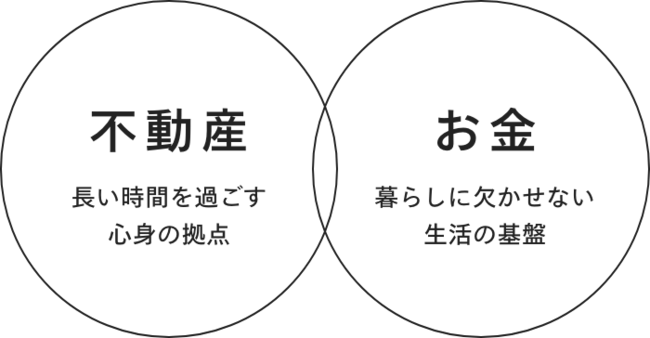
◆ RENOSY 不動産投資マンスリーレポートについて
・内容:「RENOSY 不動産投資」の成約顧客属性、成約顧客動向、販売物件情報
・期間:1ヶ月
※各データは、成約時点でのデータとなります。なお、端数処理のため、構成比の合計は100%とならない場合があります。
2021年6月度レポート: https://www.renosy.com/magazine/entries/4905
RENOSY 不動産投資サービスサイト:https://www.renosy.com/asset
- 2021年6月度 RENOSY 不動産投資マンスリーレポート トピックス
成約顧客の年収は、100万円単位、1,000万円以上は200万円単位で分類しています。ボリュームゾーンは17%の500万円台で、次いで、 15%の600万〜700万円未満、1,200万〜1,400万円未満の割合が14%となりました。
1,200万〜1,400万円未満の割合は、マンスリーレポート開始以来最も高い割合となっています。
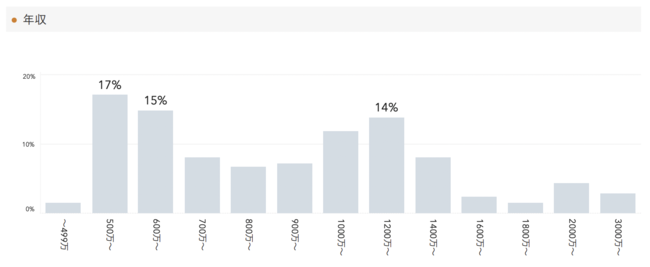 RENOSY 不動産投資マンスリーレポート 2021年6月
RENOSY 不動産投資マンスリーレポート 2021年6月
購入物件の広さは、30平米未満が79%(前月比6ptアップ)、次いで、50平米未満が11%、20平米未満の割合が9%となりました。 30平米未満の割合はマンスリーレポート開始以来最も高くなりました。
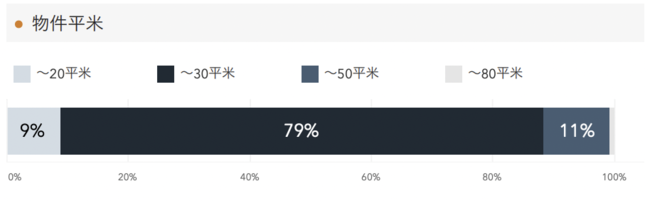 RENOSY 不動産投資マンスリーレポート 2021年6月
RENOSY 不動産投資マンスリーレポート 2021年6月
成約顧客の投資経験は、成約時点で「投資経験あり」の割合が64% (前月比6ptアップ)、投資経験のない人の割合が36%となりました。
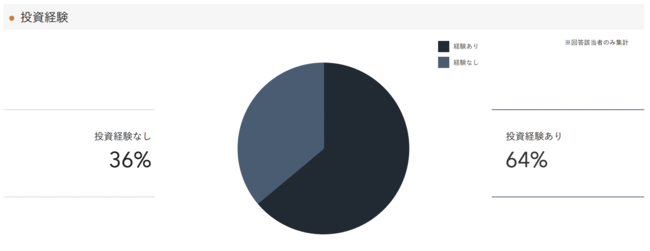 RENOSY 不動産投資マンスリーレポート 2021年6月
RENOSY 不動産投資マンスリーレポート 2021年6月
不動産投資を始めようと思ったきっかけや決断に至るまで、RENOSYのオーナー様の体験談や、生の声をサービスサイトに掲載してます。
URL:https://www.renosy.com/asset/voice
| 「キャッシュフローシミュレーションで、具体的にイメージできた」40代前半 / 男性 / 年収1300万円台 複数の物件を並行して紹介していただいたことと、キャッシュフローシミュレーションをいくつかのパターンで提示いただいたことで、具体的にイメージできた。 目的:生命保険代わり、 信用(ローン)活用 決め手:リスクが許容範囲だった 物件: RENOSYで初めての購入 / 1件 / 駅徒歩1分 / 築21年 / 2,000万円台前半 口コミ掲載日:2021年6月09日 |
「細かなサポートで、経験がなくても安心して始められる」30代前半 / 女性 / 年収1200万円台
物件紹介、検討、契約成立、その後の管理まですべて細かくサポートしてくださったことで、経験がなくても安心して投資できました。 |
◆ 不動産テック総合サービス「RENOSY(リノシー)」について
※RENOSY会員数は2021年6月時点、建物掲載数は2020年10月末時点の数字です。

◆ RENOSY 不動産投資について
RENOSYの不動産投資は、都市部の中古コンパクトマンションを主力としており、 2021年2月に東京商工リサーチが行った調査では、昨年から2年連続で中古マンション投資における販売実績全国No.1を獲得。新築も含めたマンション投資における販売実績でも、今年初めて全国No.1を獲得しました(※1) 。
不動産投資としては珍しく、20代後半から30代前半の会社員の方々が顧客の過半数を占めています。また、特徴として、(1)テクノロジーを活用したオンライン取引の推進、(2)賃貸管理から収益特化型のリノベーションまで一気通貫のサービス、(3)業界平均1/20のスピードで在庫を回転させる(※2)AI・テクノロジーを活用した物件の仕入れ力などが挙げられます。

(※1)東京商工リサーチ「2021年2月 投資用中古マンション販売に関する調査」における実績
(※2)物件を仕入れてから販売するまでの期間を在庫回転期間と呼び、在庫がどの程度の数量出入りしているのかを表す指標としています。
当社の在庫回転期間の実績は約14日/回(2020年度の月平均数値)で、自社調べによる同業他社8社の平均は約277.5日(2020年10月末時点)となっています。
◆ GAテクノロジーズ 概要
社名:株式会社GA technologies
代表者:代表取締役社⻑ CEO 樋口 龍
URL:https://www.ga-tech.co.jp/
本社:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立:2013年3月
資本金:72億859万9831円(2021年6月末日時点)
事業内容:
・PropTech(不動産テック)総合サービス「RENOSY」の運営
(不動産情報メディア、不動産売買仲介、不動産販売、設計施工、不動産管理)
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
・AIを活用した不動産ビッグデータの研究
・中国人投資家向けプラットフォーム「神居秒算」など海外PropTech事業の運営
主なグループ会社:イタンジ株式会社、株式会社Modern Standard、株式会社神居秒算など他8社
資産100億円の不動産投資家が「金融機関を勝手格付け」、資金調達で頼れるのは?
不動産が得意か否かで
金融機関「二極化」
金融庁は2018年に投資用不動産向け不正融資があったとしてスルガ銀行に、19年には西武信用金庫にも投資用不動産向け融資の審査体制で不備があったとして、それぞれ業務改善命令を出した。この影響を受けて19年になると個人不動産投資家向けの融資は一気に絞られた。
総資産100億円超という個人の専業不動産投資家でトップクラスの保有資産を誇る玉川陽介氏は近年の融資環境について、スルガショックを受けて「重い腰を上げて不動産市場に参入しようとしていた一般金融機関は『やはり、やらなくてよかった』と消極路線に戻った」と語る。
金融機関全てが投資用不動産への融資から手を引いたわけではない。不動産投資は金融機関にとって「やっていいなら目いっぱいやりたい融資対象」であると玉川氏。「バブル期以降ようやく底を打ち、下値不安が小さく、担保価値は不滅であるという土地神話は銀行内で根強い」という。
つまり融資先としては“おいしい”。なぜなら「経営の不安定な中小企業に無担保で小口運転資金を貸すよりも土地担保の方がロットも大きく保全もできる」(玉川氏)からだ。
「今後は不動産が得意な金融機関は融資を出し、不得意な金融機関はやらないという二極化が起こる」と玉川氏はみる。では不動産投資の資金調達で頼れる金融機関とはどこなのか。
玉川氏が「不動産投資家が頼れる金融機関勝手格付け」を作成した。
年収1000万円超の不動産投資家が「物件を買い続ける」ための戦略

PHOTO: Hiroko/PIXTA
不動産投資で資産形成をしていくにあたって、「どのような物件を購入すべきか」「規模拡大のための戦略をどのように立てればよいのか」といった悩みを持つ初心者は多い。大家デビューを果たしたものの、2棟目以降融資が下りない、と頭を抱える人もいるだろう。
こうした悩みに対して、「買い進められていない人は、1棟目から3棟目にとるべき戦略を誤っている」と指摘するのは、22歳で不動産投資を始め、20代のうちに家賃年収6000万円を達成、現在は不動産会社「コスモバンク」の代表取締役を務める穴澤勇人氏だ。
では、物件を買い続け、安定した収入を得るためにとるべき戦略とはどのようなものなのだろうか。
物件を買い続けて、投資規模拡大し、安定的な資産形成を行っていくための考え方を聞いた。
不動産投資家が「買い続けられない」理由
―穴澤さんは、20代で家賃年収6000万円を達成されたそうですね。
約10年前に、22歳で約3200万円のアパートを購入して、不動産投資を始めました。個人では最大13棟を所有し、家賃年収6000万円を達成したのは27歳の時です。2018年に自分の不動産投資の考え方を引き継いだ不動産会社を立ち上げ、会社で約25棟、家賃年収約3億円、年間1億8000万円のキャッシュフローを得ることができています。現金買いも含め、総投資額は約30億円です。
―不動産投資をする上で気にしなくてはいけない数字はいくつかあるかと思いますが、穴澤さんが最も重視しているのはどんな数字でしょうか?
私が重視しているのは、「手残り=税引き後のキャッシュフロー」です。これをいかに最大化できるか考えています。最終的には「不動産投資から得られた現金だけで、継続的に物件を買い続けられる」という状態が理想だと思っていますね。
―「買い続ける」ための戦略が、穴澤さんの不動産投資で重要視しているテーマだと伺いました。
多くの不動産投資家の願いじゃないですか。「問題なく買い続けたい」「どんどん規模を拡大していきたい」というのが。でも、実際には2棟目、3棟目でつまずいてしまっている、途中で規模拡大ができなくなってしまっている、という不動産投資家は非常に多いです。
なぜ彼らがそういう状態に陥ってしまっているかというと、規模拡大のことを考えないままに、1棟目から3棟目にとるべき戦略を誤ってしまっているからです。不動産投資は非常にシンプルで、「キャッシュを生み出せる物件かどうか」を重視しなくてはいけないんです。
特に、「生命保険代わりになる」とか「年金代わりになる」「節税になる」なんてうたい文句に乗って、まったく手残りがない物件を買っている人もいます。じゃあ、それで実際に節税になるのか、というと、計算してみると節税にならないんです。不動産投資をしようとしているのに、税の知識が乏しい人が多すぎます。
―不動産投資家は、税金の知識もしっかり身に着けておくべきだと考えますか?
当然です。特に、年収1000万円以上であれば、税金の知識があったほうが絶対に良いです。不動産投資で言えば、物件を毎年買い続けられている人は、例外なく税金の知識がある人です。
―どのような知識を持っておくべきなんでしょうか?
これは後で説明しますが、不動産投資でキャッシュを生み出す戦略をとるためには、減価償却の知識は必要ですね。それと、所得税、累進課税の仕組みについては最低限知っておくべきだと考えます。
何より、特にサラリーマンの方は、自分が支払っている税金がいくらなのかを把握するところから始めてほしいです。
買い続けるための「3本の柱」
―買い続けたいと思っているのであれば、不動産投資初期に、規模拡大を見据えた戦略を考えるべきだということでしょうか。
その通りです。あとでもう少し詳しくご説明しますが、1棟目から3棟目には、しっかりとキャッシュを生み出す物件を選び、そして家賃収入を得ることが重要だと思います。
そして、こうした家賃収入を含めて、「1年で1000万円の現金が作れる」というベースさえできれば、その後も順調に規模拡大、資産形成ができます。
―「1年で1000万円の現金が作れる」という環境を整えることが、買い続けていくために必要なことですか?
そうです。その仕組みさえ作ることができれば、資産形成は可能です。ですが、思うように資産形成ができないサラリーマン不動産投資家も多いでしょう。そういう人は、「家賃収入」に頼り切りの1本足戦略になっていると感じます。
本当にきちんと増やし続けたいのであれば、「3本の柱」をしっかりと作り出すべきです。
―「3本の柱」とはそれぞれどういうことでしょうか?
1つ目は「家賃収入」。これはもちろんですね。2つ目が、先ほどから話している「減価償却による税金の還付」になります。3つ目が、「本業の収入とその貯金」です。不動産を増やす間は、家や車にお金を使うのではなく、極力貯金をしていく。この3つの柱で、1年間で1000万円の現金を貯められるようにしていくのです。
これは、年収1500万円ほどのサラリーマンであれば、問題なくできる範囲です。
一例で言えば、まず所有物件から家賃収入の手残りとして400万~500万円を得る。所得税については減価償却と損益通算をフル活用して、本業の所得をつぶし切って200万円に近い還付を受ける。加えて、本業から得た給与から200万円以上を目標に貯める。これだけで1年で1000万円弱が作れます。もちろん物件規模や構造、耐用年数にもよるので一概に簡単という訳ではありませんが、十分可能な数字だと思います。
―1年間で作った1000万円を利用して、また次の物件へ、と規模拡大していくんですね。
例えばそれを2年繰り返して、貯まったお金で物件を現金買いし、それを共同担保に入れて…ということもできます。そうすれば返済比率も下がりますから、銀行にも喜ばれて、融資承認が下りやすくなります。
一法人一物件スキームだとか、不正融資だとか、そんなことをしてまで融資を受ける人がいますが、正直に言って、なぜそんなことをしているのかと思います。個人で借り続けるためには、銀行が貸したくなるように、無担保の物件を持つとか現金を一生懸命作るとか、そういうまっとうなことをシンプルにし続ければ良いだけなんですよ。
1棟目から3棟目まででとるべき戦略とは
―1年で1000万円貯めるために、しっかりキャッシュを生み出す物件を選ぶべきだということですが、その「1~3棟目にとるべき戦略」について教えてください。
先ほども話しましたが、私は不動産投資において、何よりも「手残り=税引き後CF」を最大化することが一番大切であると考えています。そして、手残りを最大化するために、1~3棟目では「金利を気にせず、それよりも融資期間をできるだけ長くとる」べきです。
―なぜそのように考えているのでしょうか?
不動産投資は「雪玉」のようなもので、転がすことでどんどん大きくすることが可能です。ですが、もしその「雪玉」の芯がしっかりしていなかったら、いびつな形になってしまったり、途中で割れてしまったりしてしまうでしょう。不動産投資では、その「芯」が1棟目から3棟目にあたります。ここで手残りをしっかり生み出せる仕組みを作っておくべきなんです。
融資期間が長ければ、もちろん返済総額は増加しますが、手残りも多くなります。貯まった現金で次の投資への弾みをつけることができるのです。
―どういった物件を購入すべきなんでしょうか?
やはり、中古・築古で、しかし土地値が一定程度ある物件です。こうした物件を、30~35年程度の期間で引くべきです。減価償却の観点から建物は耐用年数を超えている方が節税には有利にはたらきやすいです。相対的に利回りが高くなりやすいのもいい点ですね。
実際、融資自体は難しいという側面もありますが、耐用年数を超えても融資する地銀や、ノンバンクなどの金融機関も複数ありますから、付き合いのある人に紹介してもらうなどして、こうした金融機関を開拓していくことも重要です。
ちなみに、1棟目に「新築物件・金利1%・20年」というような買い方をする方もいますが、これは手残りの最大化という面からすると悪手です。なぜかというと、2年目以降に税金がとられてしまうから。新築だと低金利は実現できるのですが、減価償却が小さいため、所得税の圧縮につながらないケースも多いのです。
新築がダメだと言っているわけではありません。税金の知識がないまま買ってしまうのがダメなのです。雪玉の芯ができて、「あとは転がすだけ」というときに新築物件を組み入れる、などの戦略は間違っていないと思います。要は順番の問題で、投資序盤では「手元の金融資産をいかに厚くするか」が最大のテーマなので、そのためには先述の3本の柱すべてを使った方が早いと思います。
2棟目以降、融資不可なのは「儲かっていない」から
―これまでの経験から、規模拡大に失敗してしまう方というのはどのような方でしょうか。
これまで話してきたことでもありますが、やはり規模拡大のことを念頭に置かずに、1棟目の物件単体で「良い物件を買えた!」と思ってしまっている人ですね。立地が良い、金利が安いなど「良い」と思うポイントはそれぞれですが、結局キャッシュが貯まるかどうかをきちんと見られていない人は多いです。
―1棟目は買えても、それ以降融資が出ないと悩む人もいます。
金融機関からすれば、属性が良ければ1棟目は何でもOKだと思って出しているケースはあるでしょう。その上で2棟目、3棟目の融資承認が下りない人は、簡単に言えば「あなたの会社は借金の割に儲かっていませんね」と金融機関から言われているだけなんです。つまり、1棟目の物件選びに失敗してしまっているということです。
そして、なぜ物件選びを失敗したかと言えば、不動産会社に言われるがまま、「不動産会社が売りたい物件」を買ってしまったからです。
知識のないまま、高利回りだからというだけでがけ地や旗竿地の物件を買ってしまっている、というケースもそうかもしれません。こうした物件は土地の評価が出ないので、2棟目以降の融資はかなり厳しくなってきます。
―知識不足、そして戦略をしっかり描けていないことが原因ということですね。
そう思います。不動産会社の営業マンも、自分が投資用物件を所有しているわけではなく、税金や融資の引き方など、知識を全く持っていない人も多く存在します。こうした人から正しい知識を得られず買ってしまって、失敗しているという人もいるでしょう。
やはり、きちんと自分自身で不動産投資について学ぶことは非常に重要です。その上で、きちんとノウハウを持った不動産会社をパートナーとして選び、二人三脚で「買い続けられる」不動産投資を進めていっていただければと思います。
不動産投資家が暴露する「不動産会社・売買・金融機関」の裏側
生き馬の目を抜く不動産投資家たちが、不動産会社、不動産売買、金融機関の真実を赤裸々に明かした。特集『不動産投資 売りどき・買いどき』は、7月26日(月)から8月7日(土)まで全11回で連載。不動産投資家の目と実績を通じて投資と融資の環境をつまびらかにして、不動産の「売りどき」「買いどき」を追究する。
#1 7月26日(月)配信
住友不動産販売が物件取引で新体制、「キックバック壊滅」か【不動産投資家座談会1】
住友不動産販売が「物件情報紹介システム」を7月にスタートした。これにより各センターで物件を卸すのをやめ、本部に卸機能を集約する。実はこれ、キックバックを壊滅させるものだとささやかれている。
#2 7月27日(火)配信
オープンハウスが不動産売買で勝てる理由と投資家目線の付き合い方【不動産投資家座談会2】
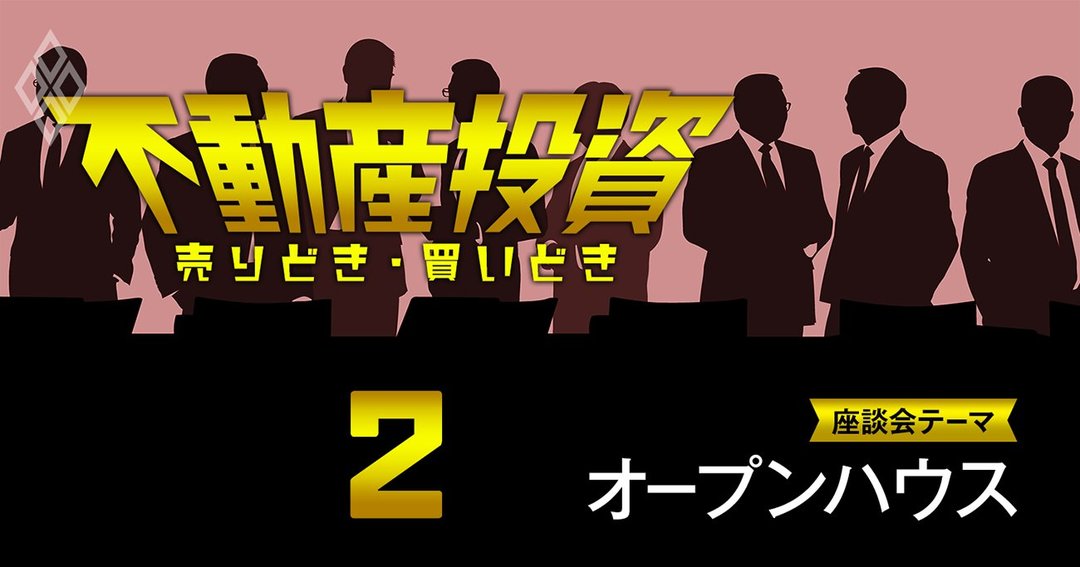 Photo:PIXTA
Photo:PIXTAオープンハウスは一戸建てやマンションを建てて販売するだけではない。不動産売買で稼ぐ事業があり、ここでも強さを誇る。競り勝てる理由を明らかにするとともに、不動産投資家がオープンハウスとうまく付き合う手法に迫る。
>>7月27日(火)配信
#3 7月28日(水)配信
資産100億円の不動産投資家が「金融機関を勝手格付け」、資金調達で頼れるのは?
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA不動産投資の資金調達で頼れる金融機関はどこなのか。個人の専業不動産投資家でトップクラスの保有資産を誇る玉川陽介氏が金融機関を格付け。併せて不動産投資家に実施したアンケートから今後の融資が期待できる金融機関を明らかにした。
>>7月28日(水)配信
#4 7月29日(木)配信
スルガ銀行、不動産投資向け融資「路線変更」の全貌と評判【不動産投資家座談会3】
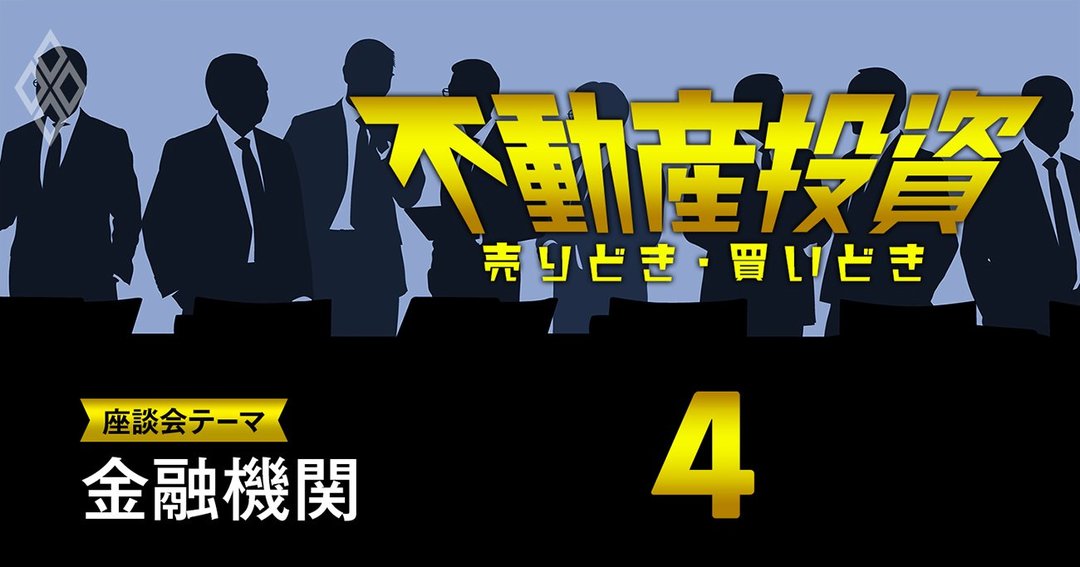 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA不正融資問題で揺れに揺れたスルガ銀行は不動産投資向け融資のターゲットをシフトさせている。その実態を知る「メガ大家」たちが同行の路線変更の全貌、そして「初級サラリーマン投資家」の資金調達の現実を克明に語った。
>>7月29日(木)配信
#5 7月30日(金)配信
アジア富裕層への不動産販売で「ファミマと信義房屋不動産」が頼られる理由【不動産投資家座談会4】
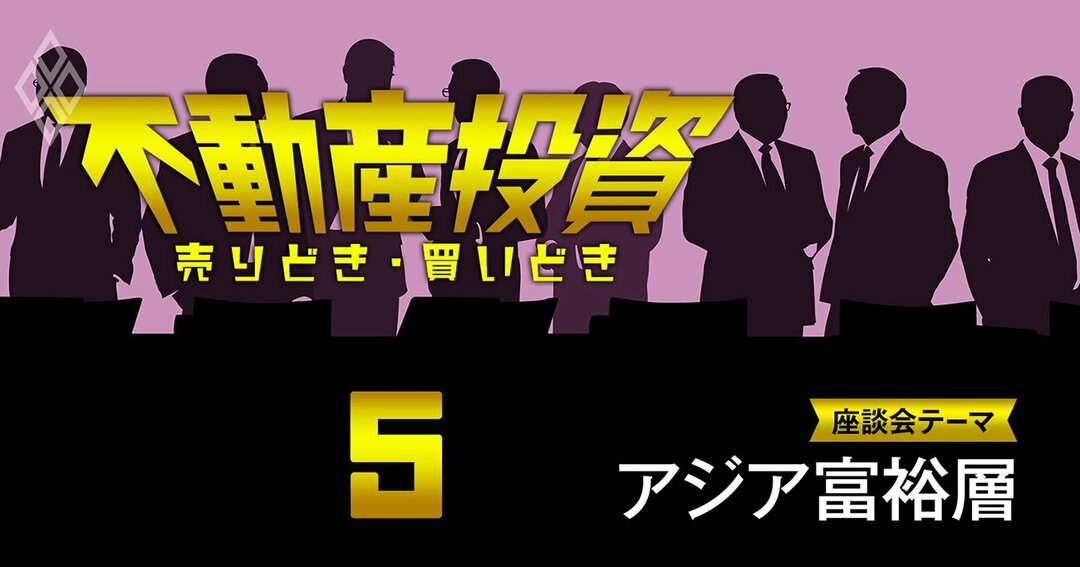 Photo:PIXTA
Photo:PIXTAアジアの富裕層が欲しがる不動産のストライクゾーンは、当たり前の人気エリアや物件とはちょっと異なる。エリア、物件の種類、売買ルートのいずれも一癖ある。
>>7月30日(金)配信
#6 8月2日(月)配信
不動産売買「真の活況度」を暴露!大阪ミナミ、軽井沢、千葉&神奈川の奥地…【不動産投資家座談会5】
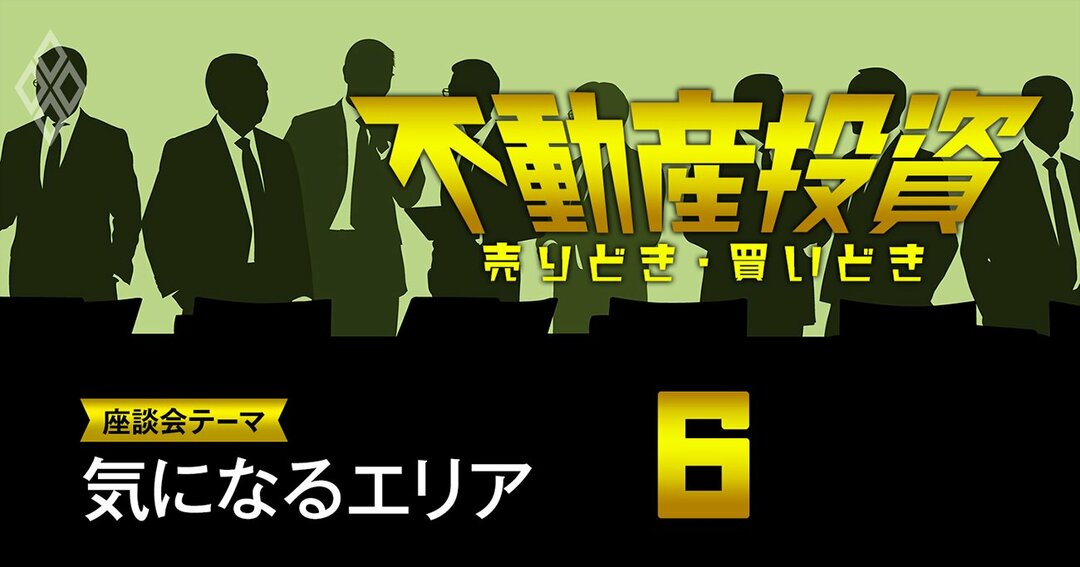 Photo:PIXTA
Photo:PIXTAコロナ禍でにぎわいが消えた大阪・ミナミ、人が流れてきた軽井沢、そして千葉や神奈川の奥地。注目を集めたエリアの不動産売買は活況なのか。不動産投資家たちが各エリアの本当の姿を明かした。
>>8月2日(月)配信
#7 8月3日(火)配信
住宅の火災保険料を値上がりさせた「悪意の真犯人」の正体【不動産投資家座談会6】
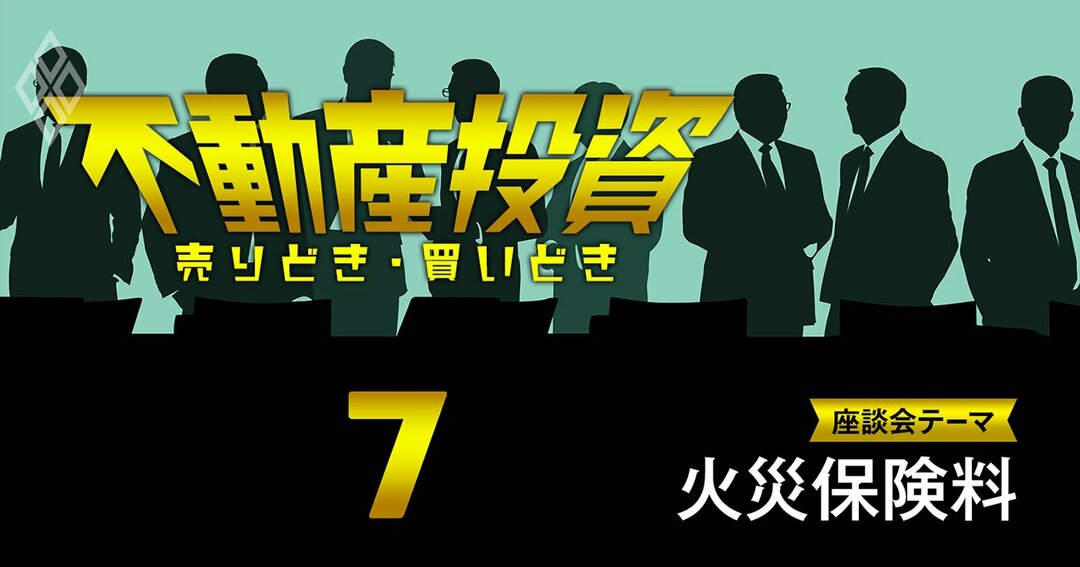 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA台風や豪雨の多発で保険会社の保険金支払いが膨らみ、火災保険料が4月から値上げされた。自然災害が相手ではやむなしではあるが、それとは別に保険金支払いを悪意で膨らます存在がいた。
>>8月3日(火)配信
#8 8月4日(水)配信
不動産投資家へ独自調査!「五輪・コロナ・米国利上げ」影響度予想の意外な結果
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA不動産投資家を対象にした独自アンケートで、直近の投資状況や実績、今後の投資環境について問うた。「ポスト五輪・ポストコロナ・米国利上げ」の影響をどうみているのか。そしてどんな投資戦略を描いているのか。
>>8月4日(水)配信
#9 8月5日(木)配信
不動産投資家が米国利上げよりも今恐れる「危機」の正体【不動産投資家座談会7】
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA米国の量的緩和縮小による利上げを懸念するより先に現実化しかねない、不動産投資家に差し迫る危機とは?不動産投資家たちが、今後の不動産投資を語る。
>>8月5日(木)配信
#10 8月6日(金)配信
不動産クラウドファンディング超絶人気の裏に「危うさ」、真っ当業者の選び方は?
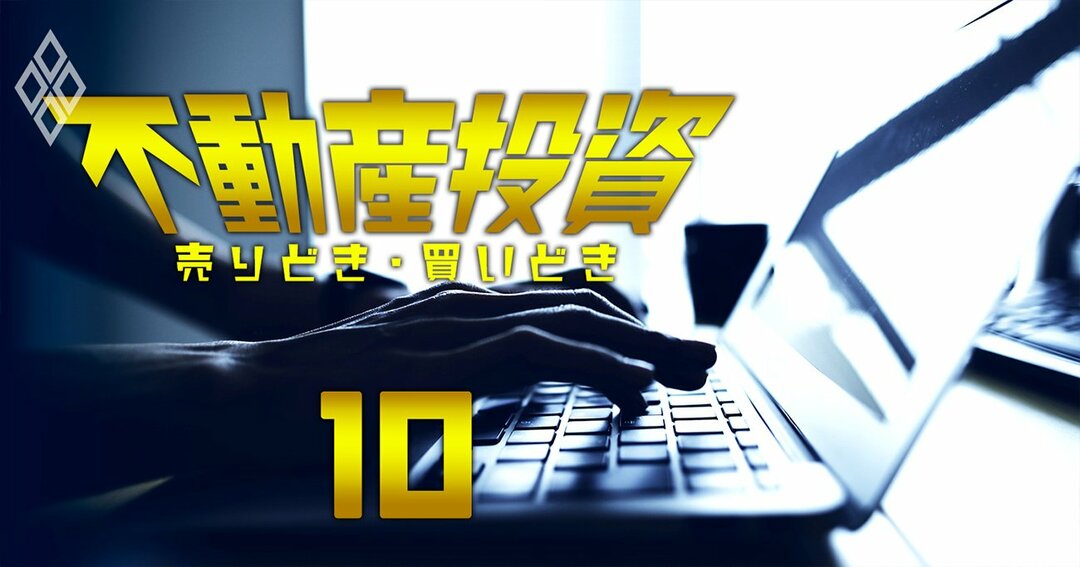 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA募集開始をするとあっという間に枠が埋まる。不動産クラウドファンディングが人気を博している。しかし、業者の不祥事が頻発する危うい世界でもある。参入がどんどん増えていく中で、まっとうな業者を見極める「選択眼」を指南する。
>>8月6日(金)配信
#11 8月7日(土)配信
不動産投資「悪徳業者の手口」、本当はダメな住宅ローン利用が今もまかり通る理由
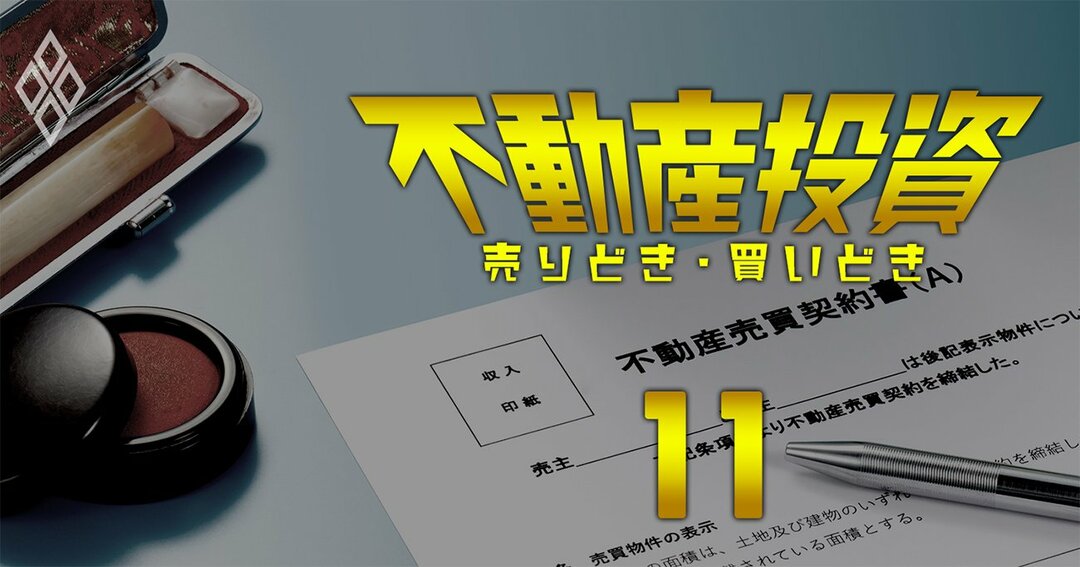 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA不動産投資に対する不正融資は大きな社会問題になった。にもかかわらず、不動産投資には使えないはずの住宅ローンの利用を提案するような悪質業者はいまだに存在する。その悪質なる手口に迫る。
>>8月7日(土)配信
Key Visual by Noriyo Shinoda
不動産クラファン「FUNDROP」、第1号を募集開始へ 1万円から不動産投資
想定利回りは7%で、賃料保証および買取保証も付帯。出資単位は1口1万円で、10口から30口の間で購入できる。募集期間は8月2日から27日まで。運用期間は9月1日から2022年2月28日まで。分配予定日は2022年3月31日を予定しており、募集は先着順となっている。
同社が運営する「FUNDROP」は、不動産取引関連サービスのデジタル化によって、個人等の中長期的な投資促進につなげることを目標として開設。不動産の小口化として、投資家は1万円から投資可能とし、最短5分でスマートフォンから申請ができる利便性の高さもポイントとして挙げている。
また、景気に左右されにくい居住用賃貸住宅(1棟レジデンス・アパートメント)を中心に運用し、より安定した収益の確保を目指すとしている。優先劣後方式を取り入れることにより、投資家の元本および配当の安全性を高める仕組みも導入している。優先劣後方式とは、投資家を優先出資者、ファンドの発売元を劣後出資者とし、元本の償還および配当の支払いを優先出資者に対するものから先に行うことにより、優先出資者の元本および配当金の安全性を高める方式。
今回発売される第1号ファンドでは、優先出資80%、劣後出資20%としている。万が一、賃料収入の減少や不動産価格の下落が起こった場合でも、優先劣後方式を導入していることにより、減少・下落が20%以内であれば、投資家への元本および配当金への影響はないとしている。
不動産クラウドファンディングとは、主にインターネットを通じて投資家から出資を募り、発売元の出資と合わせて不動産を運用(賃貸・売買)し、得られた利益の一部を投資家に分配する仕組み。
通常の現物不動産投資では、1回当たりの投資資金が大きくなるが、不動産クラウドファンディングでは1口1万円からと小口化されており、現物不動産投資を経験する前でも利用しやすい側面がある。(記事:大野 翠
こんにちは。子供の夏休みシーズンですね!共働き親で悩ましいのが、子どもの長期休みのスケジューリングです。
「 学童に行かない 」と言う小3息子のスケジュール調整( 習い事やキャンプ、短期講習で埋める作戦 )をしていると、仕事より複雑な業務( 問い合わせ、予約、見学、申込書類、振り込み等 )を遂行している気分になります。
■ 物件が買えない時期は勉強と情報収集を
さて、久しぶりに物件購入の兆しが見えてきました。条件はほぼ整っているのですが、今回は規模と金額が大きいため、現在、金融機関の役員承認待ちです。決まりましたら、またここでもご報告したいと考えています。
最近は、地銀の融資状況が厳しく( 例えば、3億円の物件( 金利1%、35年 )を打診したところ、私の法人背景では6,000万円頭金が必要との返事でした )、小規模不動産投資家には辛い。ということで、新たな金融機関の開拓も行っています。
今は「 中古物件は高いし、ウッドショックで(?)新築も建築費が高騰しているし、融資状況も悪いし 」という状況です。ここ数年で不動産投資を開始した、経験の浅い方ほど悩ましい情勢なのではないでしょうか( 私もです )
物件を買えない時期や出会えない時期は、不動産投資をしていると必ずあります( ありますよね?)。私も買えない時は「 勉強の時期 」と思い、よくスマホのアプリを活用して勉強( 検索、シュミレーションなど )していました。
有名大家さんたちは、「 夜な夜な、家族が寝静まったらPCを立ち上げて深夜に物件検索していた 」「 毎日検索していたら割安物件が分かるようになってきた 」と、会社員時代から多くの物件を見て目を肥やし、自分に適した物件を積み上げて独立していかれました。
しかし、日中に多くの時間を不動産投資に割くことが難しく、家に帰れば子供の世話や家事も待っており、なかなか「 夜中にもくもく 」とはいかない。子供と一緒に寝落ちなんてこともしょっちゅうだった私は、自ずと「 日中のスキマ時間 」を活用した効率的な情報収集や業務を行うようになりました。
■ 私が不動産活動に使っているスマホアプリ
私が活用していたのは、スマホのアプリです。スキマ時間( ランチタイム、移動時間、子供の習い事送迎待ちなど )を見つけては、アプリで作業( 物件探し、シミュレーション、問い合わせ、終始計算、宅建の勉強まで!)。
PCより精度が劣っても、下調べには有効でした。企業側のDX化、IT化も進み、現在は様々な不動産投資に活用できるアプリがあります。今日は私が使っているものや使い方をご紹介してみます。
まず、私はスマホの画面に不動産アプリを一つの枠に入れて置いています( 私はiPhone )

「 物件が欲しくて、でも買えない 」。そんな時は、日常業務の合間に、スキマ時間ができたら迷わずここを押して、収益物件を見たり、収支計算しているものを呼び出して再計算したりしていました。
例えば、物件探しで築古戸建を探すなら、このニフティ不動産の土地検索がおすすめ。土地を指定して、古家ありにチェックをつけて探すと、いわゆる「 築古戸建 」が見つかります( 広島で不動産投資をされている、ちゃんカジさんに教えてもらいました )。気になるものは保存しておいて、見比べたりすることもできます。
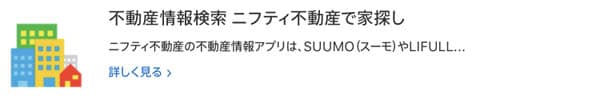

アプリのストアで「 不動産投資 」と検索すると色んな物件検索アプリが出てきます。とりあえず好みのものをダウンロードして、使い勝手や出てくる物件情報を見比べて、調べやすいものを選び、日中はアプリ、夜はPCサイトなど使い分けて探します。
良さそうな物件があり、利回りや収支計算をするという時も、スキマ時間にざっとアプリでやってしまいます。不動産投資の収益計算ツール、これはメモを残しておけるので、過去に試算した物件も見られます。
2年前に「 おお、これ良いかも!」と思ったけど買わなかった物件の数字を今見ると、「 計算が甘いな 」「 出口がないじゃないか 」と感じたりします。( 成長の証 )
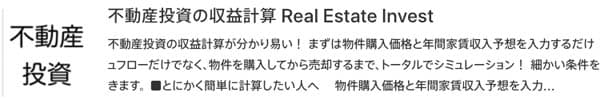

また、物件を見ていると地価情報を知りたい!( 土地総合情報システムはスマホで死ぬほど見にくい )となる時がありますよね?ざっくりで良ければ、下記のアプリ地価マップで地価を見ることができます。こうやって下調べしておくと、いざPCに向かう時は「 知りたいこと、検討したいこと 」が分かっているので、効率よく問い合わせや計算ができます。
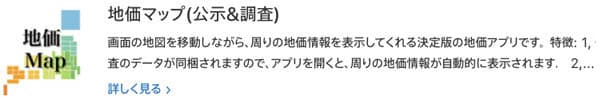

最近は、お願いしている管理会社さんがWealthParkというアプリの導入を始めたので、新築物件はこのアプリで賃貸管理しています。これも便利です。
私のような兼業大家はエクセルファイルで管理更新するのも、結構時間が取られるので、入金明細や情報をアプリで一元管理できるのはありがたいですよね。しかも、このアプリはPCでも閲覧できて、ファイルを落とせるので便利です。
- 毎月の入金、経費一覧がひと目で分かる
- 入居者情報、空室管理が蓄積情報として残る
- レントロールがすぐにダウンロードできる( 地味にありがたい、銀行さんに見せる資料 )
( 先月、退去があったので埋めなければ!と焦ります )

余談ですが、最近は、Twitterで「 宅建士 」「 簿記3級 」を受験する方の投稿を多く見ます。この勉強も、スキマ時間にアプリ活用で合格に近づきます!私もFP2、3級はアプリで取得したようなものなので( スキマ時間学習 )おすすめの勉強法です。( 下記のアプリは実際にいくつか落とした中で、個人的に使いやすいと思ったものです )
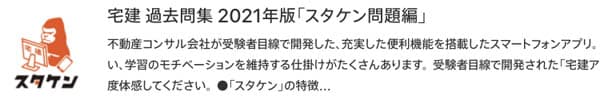
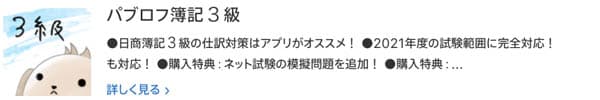
スキマ時間にアプリで得た情報を、帰宅後にPCで見るなら、スマホとPCの一括管理( Mac、Windows、iOS、Android ) で同期できるNotion( これもアプリ )が使いやすいです。
テーブル( 表計算・データベース )、カレンダー、ToDoリスト、ギャラリーなど、いくつも作成できるのですが、メモ帳機能だけでも十分。集めた情報をアプリ上のNotionにコピペして貼っておく、夜にPCでNotionを開くと、集めた情報が全て揃っており、すぐに作業できます。

検討した物件のURL、結果、自己評価( 土地がいまいち、利回り、出口が見えないなど )を書いて貯めていくだけでも、のちの財産になります。
■ 「 欲しい物件 」が見つかった時に役に立つ
情報収集や勉強が本筋になると本末転倒ですが、スキマ時間を使ってコツコツやっておくと、必ずや自分の不動産知識量を増やしてくれる、欲しい物件が出た時の判断材料になるなど、効果はチリツモですが感じています。
「 時間がない、融資が厳しい、欲しい物件に出会えない 」。そんな壁にぶつかった時は、スキマ時間を有効活用して「 情報収集、シミュレーション力磨き、資格取得 」など、未来に繋がる「 点打ち行動 」を楽しく頑張りましょう。私も頑張ります。
海外不動産投資で利回りと値上がり益を狙えるのはどの国?統計で比較
海外各国の利回り比較
Global Property Guideによると、東南アジアの新興国およびアメリカの利回りは以下の表のとおりです。
| 国 | 都市 | 利回り |
|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 2.66% |
| アメリカ | ニューヨーク | 2.91% |
| カンボジア | プノンペン | 5.33% |
| フィリピン | マニラ | 6.13% |
| タイ | バンコク | 5.13% |
| マレーシア | クアラルンプール | 3.72% |
※参照:Global Property Guide(2021年6月参照時点)
日本やアメリカといった先進国の大都市では、東南アジアを中心とした新興国の都市よりも利回りが低くなっていることがわかります。東京もニューヨークも物価が世界トップクラスに高い都市であり、不動産価格も高いことが原因です。
新興国では、首都であっても先進国の大都市と比較すると物件価格が安いため、利回りは先進国よりも高めに推移しています。なお、東南アジアの新興国で比較すると、フィリピンの首都マニラは利回りが高い状態です。その一方で、マレーシアの首都クアラルンプールはマニラやプノンペンといった都市よりも利回りが低くなっています。
マレーシアは2025年までに先進国入りを目指すなど、すでに中進国と言えるまでに発展している状況です。他の新興国よりも経済発展が進んでいるため、マレーシアでは不動産を含む物価が周辺国よりも高くなっています。物件価格の高さが利回りにも反映されているものと考えられます。
海外各国の物件価格上昇率比較
つづいて、海外各国の物件価格上昇率を比較します。利回りがインカムゲインを測る指標となるのに対して、物件価格の上昇率は、キャピタルゲインを狙える国を判断するために有効な指標です。海外各国の5年間物件価格上昇率は以下の表のようになっています。
| 国 | 都市 | 5年間の物件価格上昇率 |
|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 23.52% |
| アメリカ | ニューヨーク | 42.20% |
| カンボジア | プノンペン | データなし |
| フィリピン | マニラ | データなし |
| タイ | バンコク | 17.71% |
| マレーシア | クアラルンプール | 17.40% |
※参照:Global Property Guide(2021年6月参照時点)
過去5年間における物件価格の上昇率は、日本やアメリカなど先進国のほうが高くなっているのが特徴的です。こちらのデータは2021年5月に更新されているため、2017年前後からの上昇率となっています。先進国のほうが価格上昇率が高いのは、2021年時点ではすでにコロナウイルス感染症拡大の影響が現れたデータとなっている点が原因です。
コロナウイルス感染症拡大によって、世界各国では政策金利が引き下げられています。アメリカは特に引き下げ幅が顕著であり、政策金利の引き下げによって住宅ローン金利が大幅に下がりました。住宅ローン金利の引き下げはアメリカ全土で住宅需要を喚起したため、アメリカにおける2020年の対前年比住宅価格上昇率は過去最高レベルに達しています。
その一方で、東南アジアを中心とした新興国では、労働者の失業などを背景として、低所得者向けの住宅取得支援政策が推進されました。結果的に低価格の住宅供給が活発となったため、国全体の住宅価格上昇率はそれほど上がっていません。
海外各国のリスク比較
先進国と新興国とではどちらのほうが低リスクと言えるのか、コロナウイルス感染症が拡大した2020年以降の値動きや、2008年のリーマンショック前後の値動きから推察します。
有事の先進国と新興国とでリスクを比較
コロナウイルス感染症が世界中で拡大した2020年初頭からの値動きを見る限りでは、もともとの平均所得が高く、中流層も多い先進国のほうが有事の際にチャンスがあるとも考えられます。また、先進国は新興国と比較すると人口増加率や経済成長率が低いため、国としての成長力よりも、住宅ローン金利のほうが不動産価格へ影響すると言えます。
その一方で、新興国では有事の際に低所得者向けの政策が推進される上に、外資が本国へ引き上げてしまうことも不動産市場に大きく影響するものです。コロナウイルス感染症拡大を経て不動産価格が伸び悩んでいる新興国では、外資の影響も出たと考えられます。実際に、リーマンショックが起きた2008年9月にも世界各国で景気が悪化しました。企業向け融資などお金の流れが止まったリーマンショックの際は、世界各国で不動産価格も下落しています。
しかし、例えばアメリカのハワイでは、リーマンショックの際も不動産価格の下落幅が軽微で済んだほか、短期間でリーマン前の水準まで回復しました。ブランド力が強い海外の大都市では、有事の際のリスクも小さく抑えられると言えます。なお、こちらの記事でも海外不動産投資のリスクを詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
まとめ
海外各国で不動産投資の利回りを比較すると、全体的に先進国の大都市では低めに推移している一方、新興国では比較的高めです。先進国と新興国とでは、物件価格の違いが利回りの違いとなって現れているものと考えられます。経済規模が大きい先進国では、全般的に不動産価格も高めです。
しかし、2021年以前の5年間において住宅価格の上昇率を比較すると、新興国よりも東京やニューヨークなど先進国の大都市のほうが高くなっています。
また、コロナウイルス感染症拡大の経済対策についてはどの国でも低金利政策が採用されていますが、住宅ローン金利が下がった結果として価格が上がっているのは先進国です。新興国では横ばいもしくは一旦上がった後下がっている国も多く、安定性は先進国の方が高いと言えます。新興国での投資は特に、長期的な目線を持った判断も必要です。
税理士目線で考える/投資するなら新築or中古?
1.一般的な新築と中古の違い
よく言われるのが、「新築は建築費に多くの利益が乗っかっているため利回りが低い。購入した後、すぐに価格が落ちる。」などと言われます。
中古物件の魅力は、利回りの高さかと思います。
新築の利回りと中古の利回りで3~4%以上、中古の利回りが高いのであれば、中古物件に投資したほうがよいでしょう。
しかし、今の市場からすると(特に都心部)は、新築の利回りと中古の利回りでは大きな差がないのが現状です。
利回りに大きな差がない場合には、どう判断するべきか悩ましいところです。
2.新築物件のメリット・デメリット
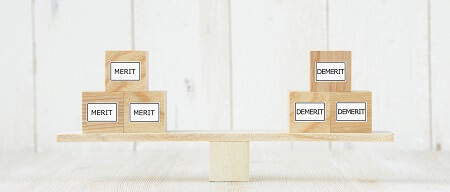
(1)保有期間中
新築物件は、利回りは低いことがデメリットですが、大規模修繕などの大きな支出がないことがメリットになります。
新築プレミアムとして、相場家賃よりも上乗せされた家賃設定されていることが多いため、将来の家賃の値下がりをデメリットにあげる方もいらっしゃいます。
しかし、将来の相場家賃は購入前に調べることができます。
相場家賃に引き直した事業計画を作成して、購入するかどうかを決めれば、デメリットではなくなると考えます。
(2)売却時
私が考える新築物件の最大のメリットは、売却時期を長いスパンで検討できることです。
15年保有していた場合でも、築15年です。
充分に売却できる築年数ではないでしょうか。
売却価格は、地価(市場価格)に大きく左右されます。
景気が良ければ、地価は上がる傾向にあり、景気が悪くなれば、地価は下がる傾向にあります。
売却しようと思ったときに、たまたま好景気であればよいですが、不景気が長く続く状況であれば、売却しようにも売却できないことになってしまうのです。
売却の検討期間を長くとれるということは、いい時期を見て売却できるということになるので、売却して損が出にくいと言えるのです。
3.中古物件のメリット、デメリット

(1)保有期間中
中古物件は、利回りが高いことがメリットです。
購入してすぐにキャッシュフローが貯まるのは大きな魅力です。
しかし、修繕費などの支出が突発的にあることを覚悟しなければなりません。
中古物件を購入してすぐに雨漏りが発覚して、修繕費がかかったという話はよく聞きます。
RCマンションであれば、修繕費は高くなる傾向にあります。
私もお恥ずかしながら、購入したRCマンションで、購入して2ヵ月後に店舗用のエアコン(埋め込み式のエアコン)が壊れたとのことで200万円の支出を強いられました。
いかに安く購入しても、大きな修繕費が出てしまっては意味がありません。
中古物件を購入するときには、大規模修繕をいつしたか、設備をいつ交換したか、など調べられることを徹底的に調べて、購入後の支出を予測しておくべきです。
中古物件のメリットを最大に享受するためには、将来の支出の予測が不可欠なのです。
(2)売却時
中古物件の売却は、新築物件の逆です。
売却時期を長いスパンで検討できないことがデメリットです。
例えば、築25年で購入した場合、10年経つと築35年になります。
築35年の物件を売りに出して、購入する人がいるかどうかになるのです。
これは融資が大きくかかわってきます。
購入者はたいてい金融機関から融資を受けます。
融資を受ける場合の融資期間は、最大で「法定耐用年数-経過年数」の年数になります。
木造なら22年、鉄骨造なら鉄骨の厚みによって19年、27年、34年。
RCなら47年。
木造で築35年なら、融資期間がとれず融資されることが難しくなります。
まったく融資を受けられないということはないですが、一部の銀行やノンバンクに限定されてしまいます。
RCで築35年なら、融資期間は最大で12年です。
12年では月々の返済が苦しく、融資で購入するには現実的ではありません。
現金購入される方、頭金を相当額入れられる方でないと購入できないのです。
購入者が限定されるということは、マーケットの価格としては下がる傾向にあります。
そうならないためには、築年数が購入者にとって融資が受けられる年数のうちに売却しなければならないのです。
売却の検討期間が短ければ、景気を見ながらなど、悠長なことを言っていられません。
売り急いで、損をしてしまうリスクもあるのです。
3.まとめ
メリット・デメリットを踏まえて私が出す結論は、初心者であれば新築物件をおすすめします。
中古物件は儲かる可能性ありますが、将来の支出を予測できるほどの物件の目利きができないと難しいです。
まずは新築物件で賃貸経営を学び、物件の目利きがある程度できてから中古物件にいくのがよいのではないでしょうか。
不動産投資で儲けたいという気持ちはわかりますが、いかに損をしないということを考えるかが生き残る術だと考えます。
画像提供:ピクスタ
少額から不動産投資ができる「REIT」を初心者向けに解説
REITとは、投資の対象が不動産である投資信託だ。間接的ながらも少額の資金で不動産投資が始められる。「不動産投資に興味があるが、多額のローンを借り入れるのに抵抗がある」という人は、REITへの投資を検討してみよう。
本記事では、REITの仕組みや現物の不動産投資との違い、注意点、投資方法などを解説する。
REIT(不動産投資信託、リート)とは?
REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trust(不動産投資信託)の略称であり、法律上は投資信託の一種とされる。REIT市場は、日本だけではなく世界各国にある。日本のREITは「J-REIT」と呼ばれている。
REITは、投資家から集めた資金をもとにオフィスビルや商業施設、マンションなどに投資し、賃料収入や売却益が得られた場合、出資額に応じて投資家に分配する仕組みだ。

投資家から資金を預かった不動産投資法人は、投資家に対して投資証券を発行する。投資物件の選定や資産の管理などは、不動産投資法人が行うのではなく、業務ごとに「運用会社」「資産保管会社」「事務受託会社」に委託される。
運用会社は、不動産投資法人に代わって投資する不動産の選定や管理を行う。賃貸経営の戦略や不動産の修繕計画などを決定するのも運用会社の役割だ。
資産保管会社は、保有する不動産の資産管理を行う会社であり、一般的に信託銀行が担当する。
事務受託会社は、会計や納税に関する事務を行っており、それぞれの業務ごとに専門の会社が選ばれる。
REITの投資対象となる不動産
REITの投資対象は、オフィスビルや商業施設、物流倉庫などだ。J-REITの投資対象には「オフィス」「商業施設」「住宅」「ホテル」「物流施設」「ヘルスケア(高齢者向け住宅・有料老人ホーム)」などがある。
J-REITが運用する不動産の中で、資産規模の約半分を占めるのがオフィスビルであり、次に住宅、商業施設が続いている。
投資対象によって景気に対する感度が異なる。たとえばオフィスビルは、景気の動向によって賃料収入や空室率が変動しやすいといわれている。
デパートやショッピングセンターなどの商業施設は、郊外に立地している場合はテナントとの契約が長期である場合が多く、景気に左右されにくく安定している。一方で都市型の場合は契約期間が短い場合が多く、景気の影響を受けやすくなっている。
住宅(アパート・マンション)は、景気が悪化しても需要が著しく低下する可能性は低いといわれている。これは、住まいが人々の暮らしに必要不可欠だからだ。
REITに投資をする際は、投資対象となる不動産の種類や特徴を把握したうえで銘柄を選ぶことが大切である。
REITの種類
REITは、いくつの用途に投資するかで以下の3種類に分類できる。
・特化型
・複合型
・総合型
特化型は、オフィスビル特化型や住居特化型、商業施設特化型など、単一用途不動産を投資対象とするREITである。用途の観点からは分散投資にはならず、複合型や総合型よりも値動きが大きい。
「商業施設」と「住宅」など、投資対象となる不動産の用途が2種類であるREITを複合型REITという。用途が3種類以上であるREITは総合型REITだ。複合型と総合型は合わせて複数用途型REITとも呼ばれ、複数用途型REITは特化型よりも分散投資の効果が期待できる。
現物の不動産投資とJ-REITの違い
現物の不動産投資とJ-REITの違いをまとめると、以下の通りだ。
| 不動産投資 | J-REIT | |
投資対象 | ・マンション ・アパート ・戸建て住宅 | ・オフィスビル |
投資金額 | 数百万〜数億円と高額 | 数万〜数十万円と少額 |
収益源 | ・家賃収入や礼金など ・売却益 | ・分配金 |
物件の選定・取得・管理 | 投資家自身が行う (専門家への委託も可能) | 専門家が担当 |
流動性 | 低い | 高い |
税金 | 家賃収入:総合課税 売却益:分離課税 | 分離課税(20.315%) |
※実際には上記に当てはまらない場合がある
投資対象
現物の不動産投資は、マンションやアパート、戸建て住宅などに投資をする。またマンションに投資する場合、1室を区分所有する場合もあれば、1棟まるごとに投資する場合もある。
REITは、マンションやアパートなどの住居に限らず、オフィスビルや商業施設、物流倉庫など、個人では取得が難しい不動産も投資対象となる。

投資金額
現物の不動産投資を始める場合、物件を取得するために数百万〜数億円の資金が必要となるため、不動産投資ローンを借りるのが一般的だ。不動産投資ローンを借り入れることでレバレッジ効果が働き、少ない自己資金で高い投資効果が得られる。ただし1件あたりの投資金額が高いため、分散投資は困難だ。
J-REITは、不動産投資ローンは利用できないが、数万〜数十万円と少額の資金で不動産投資が始められる。容易に分散投資できる点も、J-REITのメリットだ。
収益源
現物の不動産投資は、入居者が支払う家賃や礼金などが収益源となる。また不動産を購入したときよりも高い値段で売却して利益を得ることも可能だ。
J-REITの場合、投資対象となる不動産から得られた賃料収入や売却益をもとにした分配金が収益源となる。現物の不動産投資と同様に、売却による利益も狙える。
なおJ-REITは、利益のほとんどが投資家へ分配されるといわれている。これは利益の90%超を投資家に分配すれば、不動産投資法人に法人税が課せられない仕組みがあるためだ。日本取引所グループの資料によると、2021年5月時点の予想年間分配金利回りは3.44%であり、東証一部有配会社平均利回の1.86%を上回っている。一般的に、J-REITは株式よりも利回りが高い傾向にある。
物件の選定・取得・運営
現物の不動産投資では、投資家自らが投資する物件を選定したうえで取得するのが一般的だ。物件の管理は、オーナーである投資家自身が行うこともあれば、不動産管理会社に委託する場合もある。
J-REITにおいて投資対象となる不動産を選定するのは、不動産投資法人が業務委託する専門家である。投資物件の取得や管理も、専門家が行うため投資家自身が行う必要はない。
流動性
現物の不動産投資では物件を換金する場合、不動産を売りに出して買主を探さなければならない。加えて売却時には、仲介手数料や印紙税などの諸費用を支払う必要がある。よって現物の不動産投資は、売却に手間や時間がかかるといえる。
一方でJ-REITは、証券会社にて売り注文を出し買い手が見つかれば、簡単に売却が可能であるため、流動性は高いといえる。売却時のコストは、証券会社に対して支払う売買手数料のみだ。
税金
不動産投資の家賃収入は、総合課税の対象である。年間の家賃収入から必要経費を差し引いた金額である「不動産所得」が、給与所得や事業所得など他の所得と合算されて、所得税や住民税が計算される。 投資物件の売却益(譲渡所得)に対する所得税や住民税は、他の所得は合算されずに、物件の所有期間に応じた税率をかけて計算される。
J-REITの場合、分配金と売却益のどちらも分離課税の対象である。他の所得とは分けたうえで、REITの運用益に対して20.315%(復興特別税含む)の税金が課せられる。

REITに投資するときの注意点
REITに投資をする際は、以下の2点に注意が必要だ。
- 価格や収益が変動する
- 上場廃止のリスクがある
価格や収益が変動する
REITは、元本保証のない金融商品であるため、投資対象である不動産の運用状況によって価格や分配金が変動する。不動産市況の悪化による家賃の下落や、テナントの退去、賃貸料の未納などが発生すると、REITの価格や分配金が低下する恐れがある。
またREITは、土地や建物など実物を投資対象としているため、自然災害をはじめとした偶発的な事象による滅失や劣化などの影響も受ける。
他にも不動産投資法人が金融機関から融資を受けている場合、金利の変動による返済額の増減によって、REITの価格や収益が変動することがある。
上場廃止のリスクがある
不動産投資法人が倒産し、投資法人としての登録が取り消しとなった場合、REITは上場廃止となって証券取引所での売買ができなくなる。
倒産によって法人の清算が行われると、借入先の金融機関をはじめとした債権者へ弁済されたあとの残余財産が、投資家に分配される。そのため投資法人が倒産した場合、投資金額の全部または一部を回収できない恐れがある。これは現物の不動産投資にはないREITのリスクである。
REITの購入方法
REITを購入する方法は、以下の3点だ。
- 個別銘柄を購入する
- REITファンドを購入する
- ETFを購入する
個別銘柄を購入する
REITは、証券会社で個別に購入が可能だ。購入金額は、1口あたりの価格×購入口数で決まる。個別株式は100株単位でなければ購入できないが、REITは1口から購入できる。
なお個別銘柄を購入できるのは、基本的に国内のREIT(J-REIT)のみであり、世界各国のREITは個別に購入できない。国外のREITに投資するには、REITファンドかETFを購入する必要がある。
REITファンドを購入する
複数のREITに分散投資する投資信託を、REITファンドという。REITファンドも証券会社や銀行で口座を開くことで取引できる。
投資信託は、1000〜10000円程度から購入できるため、個別銘柄のREITよりもさらに少ない資金で投資が始められる。毎月一定額の投資信託を買い付ける積立投資も可能だ。また海外のREITを投資対象としている銘柄も選択できる。
ただしREITファンドは、保有期間中に信託報酬を支払う必要があるため、コストが個別銘柄よりも割高だ。
ETFを購入する
ETFとは、「Exchange Traded Fund(上場投資信託)」の略称である。証券取引所に上場しているため、投資信託と同じ仕組みを持ちながら、個別株式のようにタイムリーな取引が可能だ。ETFが購入できるのは証券会社のみである。
「東証REIT指数」を構成する銘柄に投資をするETFを購入すると、少額で東京証券取引所に上場するREIT全銘柄に分散投資できる。
ETFは、証券会社を通じて取引できる。なおETFの保有期間中は、信託報酬を支払う必要がある。

不動産投資家がFP資格の取得を目指すことの意義、2級資格の学習内容と試験とは?
コロナ禍の中、在宅業務で生じた空き時間などを資格取得の学習に充てる人も多いと言われている。
FP(ファイナンシャルプランナー)資格は、家計不安や資産運用のニーズが高まっていることもあり、年々受験者数が増加している人気の資格である。
不動産投資家が、FP(ファイナンシャルプランナー)資格の学習や資格取得を目指すことは、どのような意義があるだろうか。FPの資格の概要と、2級資格の学習内容・試験内容を概説し、不動産投資にどのような効用をもたらすかを考える。
FP(ファイナンシャルプランナー)とは
FP(ファイナンシャルプランナー)とは、長期的な人生のイベントや目標を実現することができるように、経済的な側面からサポートする専門家のことである。顧客の現状の収入や資産・負債などを分析して、長期的な資金計画を立て、貯蓄計画、保険・投資対策などの総合的な資産設計もおこなう。
家計に関わる総合的なお金の問題の相談窓口となっており、住宅ローンや教育ローンの相談、資産運用方法の相談、保険の選び方、相続や贈与の相談など、業務は多岐にわたる。資金計画や資産設計の立案、各種相談業務に対応するには、そのベースとして、ローンや金融商品、保険、年金、税金、不動産に関する幅広い知識が求められる。
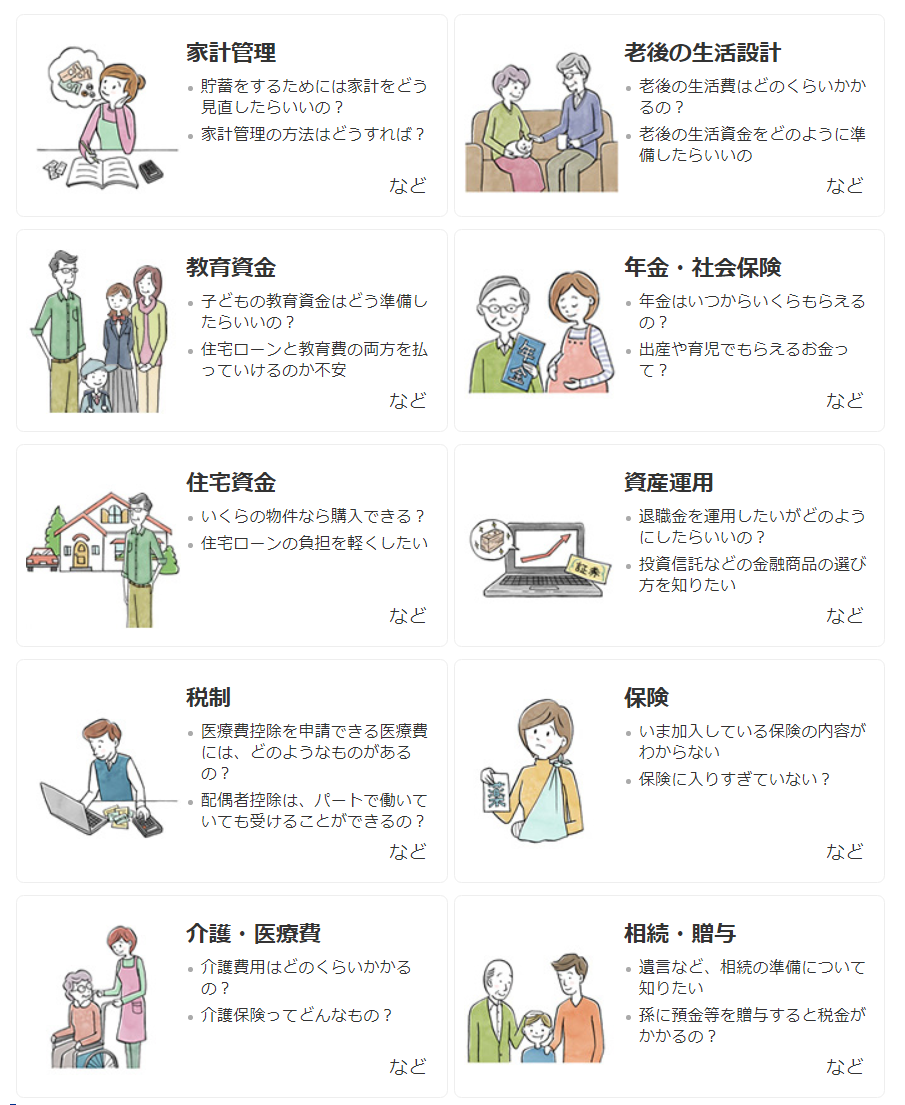
FP資格の概要と
2級の位置づけ
FP資格は国家検定である「ファイナンシャル・プランニング技能士」が3級から1級まである。試験の実施は、日本FP協会と金融財政事情研究会(以下、きんざい)がおこなっている。
日本FP協会は、2級技能士合格者に対し研修をおこなってAFP資格を認定し、さらに試験等を実施して上級のCFP資格の認定をおこなっている。2020年9月現在、AFP認定者は約16万人、CFP認定者は2.3万人となっている。
「ファイナンシャル・プランニング技能士」の3級、2級の試験は、1月、5月、9月の年3回実施されている。いずれも、学科と実技の2つの試験がある。
学科試験は、専門知識を問うのに対し、実技試験は、資産設計提案業務などの実務における知識の活用能力を問うものといえる。日本FP協会ときんざいがおこなう試験は、実技試験の内容が異なる。
日本FP協会は、資産設計提案業務についてであるのに対し、きんざいは、個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務について問われる。
独立系のFPは、CFPやAFPに登録しているケースが多いといえる。これらの登録には、2級技能士の取得が最低条件となることから、2級技能士はFPの登竜門といえるだろう。
2級技能士の学習内容、
試験内容、難易度は?
それでは、2級技能士の試験内容、資格取得のための学習内容はどのようになっているのだろうか。
学科試験の範囲は、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継、となっている。ライフプランニングと資金計画では、ライフプランニングの方法や住宅・教育ローン、公的社会保険について学ぶ。
リスク管理は、生命保険と損害保険の種類や仕組み、税務が主な内容となる。金融資産運用は、債券、株式、投資信託、外貨などの金融商品の種類や仕組みなどが内容となる。
タックスプランニングでは、所得税、住民税、法人税、消費税の仕組み、計算方法などを学ぶ。不動産分野では、不動産に関連する法制度、税務、不動産投資が主な内容となっている。相続・事業承継では、相続に関する法制度、相続・贈与の税務、財産評価、事業承継対策などを学習する。
試験では、学科試験が4肢択一が40問、実技試験では、択一と記述の混合問題が40問出題される。実技試験の記述問題は、キャッシュフロー表やバランスシートの数値、所得税額や金利と運用年数を下にした運用額など、計算によって回答させるものが多い。
合格率は約40%~50%程度と高く、過去問研究などをしてしっかりと対策をおこなえば、合格は十分可能だろう。ただし、合格の得点ラインは全体の6割となっており、問題の難易度はけっして易しいとはいえない。
会計事務所勤務経験、税理士試験受験経験が10年程度ある筆者は、本年5月の2級技能士試験に挑戦した。大手通信教育のテキストを利用して約1カ月、延べ80時間程度学習し、ギリギリのラインで合格した。
税金分野の問題は、細かい知識を問う問題が多く、会計事務所の勤務経験があっても高得点は難しいという印象であった。特に、金融商品や生命保険の種類、仕組みを問う問題には学習段階から苦戦し、試験結果もよくなかった。
不動産投資家がFP資格を目指すことの意義
不動産投資家にとって、FP資格を目指して学習し、資格を取得することはどのような意義があるだろうか。
FP資格の学習では、不動産投資や不動産に関連する法制度についての知識が得られるから、それらが実際の物件購入に役立つことは疑いがない。その他にも、FP資格を学習することには大きな意義があるといえる。
FPのメイン業務であるライフプランニングでは、ライフプランに合わせた資金計画を策定する。その際には、経過年数ごとの収入支出を一覧表にして、年間収支と金融資産を見積っていく「キャッシュフロー表」を作成する。
この「キャッシュフロー表」の作成方法は、不動産賃貸業でも同様である。家賃収入と、管理費、修繕費、ローン返済などの支出を一覧表にして、年間収支とキャッシュ残高の推移を見積る。
FPの学習をすることで、「キャッシュフロー表」の作成をすることができるようになれば、物件購入前の資金計画が容易になり、不動産投資の失敗を防ぐことにもつながる。

不動産投資では、物件購入の判断基準の一つとして「利回り」が非常に重要である。
「利回り」を、物件が安いか高いかという観点から利用しがちであるが、「利回り」の本当の重要性は、資金運用の目標値の設定という観点にあるといえるだろう。
FPのライフプランニングでは、資金計画を立てる際のツールとして様々な係数を用いる。最も分かりやすいのが、一定期間複利で運用して言った場合、いくらになっているかを示す終価係数である。
次に利用価値のあるのは、現価係数だろう。現価係数は、一定期間後に一定金額を得るには、いくらの元本があればよいかを示す。たとえば、年利10%の場合の現価係数表と元利合計10,000,000円を目標値とした場合の必要な元金は、以下のようになる。
| 期間 | 現価係数 | 元金 |
| 1年 | 0.909 | 9,090,000円 |
| 2年 | 0.826 | 8,260,000円 |
| 3年 | 0.751 | 7,510,000円 |
| 4年 | 0.683 | 6,830,000円 |
| 5年 | 0.621 | 6,210,000円 |
| 6年 | 0.564 | 5,640,000円 |
| 7年 | 0.513 | 5,130,000円 |
| 8年 | 0.467 | 4,670,000円 |
| 9年 | 0.424 | 4,240,000円 |
| 10年 | 0.386 | 3,860,000円 |
| 11年 | 0.350 | 3,500,000円 |
| 12年 | 0.319 | 3,190,000円 |
| 13年 | 0.290 | 2,900,000円 |
| 14年 | 0.263 | 2,630,000円 |
| 15年 | 0.239 | 2,390,000円 |
| 16年 | 0.218 | 2,180,000円 |
| 17年 | 0.198 | 1,980,000円 |
| 18年 | 0.180 | 1,800,000円 |
| 19年 | 0.164 | 1,640,000円 |
| 20年 | 0.149 | 1,490,000円 |
現価係数表を用いると、たとえば利回り10%(経費を考慮しない)の物件を運用して20年後に1千万円の手元資金を得たい場合、149万円を投資すればよいことがわかる。
このように、FPの学習は、不動産投資の物件選びの際、資金運用という視点が重要であることに気付かせてくれるといえるだろう。
また、FP資格を取得すれば、対外的な信用も増すだろう。物件購入の際、物件の「キャッシュフロー表」を自分でシミュレーションして作成し、金融機関に持参すれば、好条件での融資獲得に向けてのアピールにもなりうるだろう。
取材・文 佐藤永一郎
ハーバード式ファイナンスで使われる
資産運用の未来予想図、
プロ・フォルマを活用する
どんな時代でも生き残れる不動産投資家になるための極意とは何か? 不動産投資で利益をあげ続けるためには、基本となる知識やノウハウを学ぶ必要があります。ハーバード大学デザイン大学院で最先端の知識を学び、それに自身の体験から得たノウハウをミックスして体系化した『ハーバード式不動産投資術』(上田真路著、ダイヤモンド社)が発売されました。本連載では、世界のどこでも通用する、遍的で再現性のあるナレッジである不動産投資術について、同書の中から抜粋してそのエッセンスをわかりやすくお届けします。良い不動産をデザインするとは、どういうことか? 驚異のリターンを実現するファイナンスの極意とは? 不動産投資のリスクをどうコントロールしたらいいのか? などについて、実際の事例(ケース・スタディ)を踏まえてそのメカニズムを解き明かしていきます。不動産投資を始めたいと思っている人、すでに始めている人、さらに上を目指したい人必読です。好評連載のバックナンバーはこちらからどうぞ。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stockハーバード式不動産ファイナンスで使われているプロ・フォルマ
このように複利の利率が上がれば、指数関数的にリターンが上がるということがわかると思う。
そして、この複利を5年間の期間の間に実現してくれる投資の始まりと終わりの映画を「5年間での資産運用成績/内部収益率(IRR)120%」という。
IRRを算出するにはエクセルやGoogleスプレッドシートなどが、最終的に必要になるが概念さえ掴んでしまえば、それほど難しいものではない。
そして、数字に拒否反応がある方やエクセルに不慣れな方も安心してほしい。
今回、必要なプロ・フォルマを描いたエクセルはすべて公開し、ダウンロード可能とする。ご自身で組み上げる必要はない。どんどん活用してもらって構わない。
ダウンロード教材共通 https://www.kurofune-dh.com/contact
ちなみに投資期間3年のIRRが100%超えという成績は非常に優秀な、世界でもトップクラスの不動産ファンドマネジャーが10件に1件叩き出す数字であることを参考にしてもらいたい。
では、実際にハーバード式不動産ファイナンスで使われているプロ・フォルマを見てみよう。
エクセルで組まれたプロ・フォルマの全体像に圧倒されてしまうかもしれないが、注釈でプロ・フォルマの各エリアが何を示しているか簡単に示しておく。今の時点ではざっくりとイメージを掴んでもらうだけで十分だ。
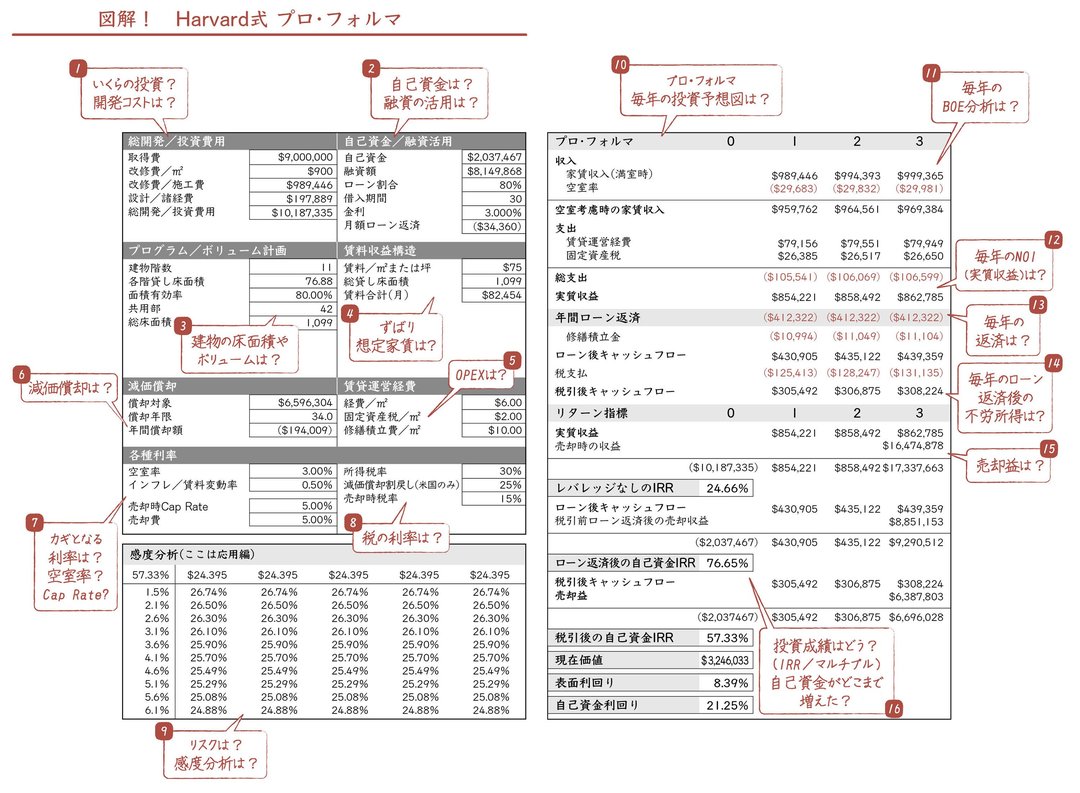
拡大画像表示
ローン後キャッシュフロー(CFAF)が
投資期間に毎年プラスになっているか?
ここでのポイントは2つだ。
まずはしっかりとローン後キャッシュフロー(CFAF)が投資期間に毎年プラスになること。
そして、特に最後の出口(売却)時には、実質収益(NOI)をしっかりと高水準で安定させることだ。もちろん、満室稼働で平均を少しでも超えた家賃収入で賃貸付けできている状態という意味だ。
次の購入者の期待利回りであるCap Rateで割り戻すと売却価格が想定できるが、高水準で安定したNOIが実現できていれば、必然と売却価格も高くなる。
例えば、あなたの物件の購入希望者の期待利回り(Cap Rate)が5%だとして、実質収益(NOI)が100万円下がれば、5%で割り戻して2000万円値引きされて価値付けされてしまう。
逆もしかりで、安定して相場より100万円高い家賃が取れていれば、2000万円上乗せした金額での売却も可能だ。
建築家・不動産投資家
KUROFUNE Design Holdings Inc. 代表取締役CEO
ハーバード大学デザイン大学院で不動産投資と建築デザインを学び、投資理論とデザインの力を融合させたユニークな不動産投資を行う。
鹿島建設入社4年目に不動産投資を開始。数々の不動産投資セミナーに足を運び、不動産関連書籍を数十冊読破。そんな中で出会ったメガ大家集団をメンターに持ち、指導を仰ぎながら不動産投資をスタートする。最初に行った東京・神楽坂での新築マンション開発では超狭小地に苦労し、辛酸を舐めつつも独自の不動産投資スタイルを確立する。現在5棟の超優良物件を保有。保有物件の中では投資額が4年間のうちに26倍になったものもある。
1982年高知県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科、同大学院卒業後に鹿島建設入社。
大学院卒業時にリゾートホテル開発プロジェクトにより早稲田大学小野梓芸術賞を受賞。
同社では国内外で建築設計や大規模な都市開発業務に従事。鹿島建設社長賞、グッドデザイン賞、SDレビュー賞などを受賞。2016年、ハーバード大学デザイン大学院(GSD)へフルブライト留学。2018年、GSD不動産デザイン学科を卒業、外資系不動産ファンドでの投資業務を経験した後、KUROFUNE Design Holdings Inc.(デザイン事務所兼不動産ファンド会社)を創業し独立。現在はハーバード学生寮生活で得た原体験をもとに、住まいと学びを融合させた国際学生寮「U Share」を開発運営する。また、慶應義塾大学SFC特任講師、早稲田大学特任講師として「不動産デザイン」について教えている。初の著書に『ハーバード式不動産投資術 資産26倍を可能にする世界最高峰のノウハウ』(ダイヤモンド社)がある。
タイ不動産投資はどのエリアが低リスク?エリアごとの特徴を解説!
観光先としても有名なタイは、日本人からの海外不動産投資先としても強い人気があります。タイと言えば首都のバンコクを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
しかし、タイにはバンコク以外にも不動産投資の対象となり得るエリアがあります。また、ミクロの視点では、バンコクの中でもメリットやリスクなど特徴が異なるため要注意です。タイ不動産投資で投資対象となり得るエリアにつて、その特徴を解説します。
首都バンコク
タイの首都バンコクは、タイ不動産投資で選べるエリアの中でも最も中心的な選択肢です。しかし、バンコクの中でもエリアによってメリットやリスクなどの特徴が異なる点に要注意です。バンコクの特徴をエリア別に解説します。
中心部:アソーク・プロンポン
タイの首都バンコクには、MRTと呼ばれる地下鉄とBTSと呼ばれる地上鉄道が整備されています。アソークはMRTとBTSとの接続駅として機能しており、バンコクの中心とも言えるエリアです。駅周辺には大型のショッピングモールが立ち並んでおり、地元のタイ人に加えて観光客も多く集まっています。また、アソークに隣接するプロンポンはバンコクの日本人街として知られるエリアです。
駅周辺には日本語の看板を出している飲食店も多く、周辺にはバンコクの日本人駐在員などが多く居住しています。プロンポンにも、駅前にエンポリアムという大規模ショッピングモールが建っています。タイのビジネスパーソンや観光客など、タイの中でも最も人が集まるエリアと言って過言ではありません。
タイは東南アジアの新興国に分類されるものの、バンコクの中心部では物件価格もそれなりに高くなっています。富裕層や外国人駐在員など属性高めの入居者を見込める一方で、物件価格が高いことから想定利回りは低めです。投資を検討するのであれば、収支のシミュレーションには注意を要します。
中心部:シーロム
シーロムはアソークやプロンポンから見て南側に位置するエリアです。ルンピニ公園という大きな公園があり、周辺には諸外国の大使館などがあります。
また、シーロムはバンコクの中でもビジネス街の色合いが強いエリアです。周辺には多くの海外企業が事務所を設置しています。大使館や海外企業が集まっているために、属性の高い外国人が集まるエリアです。
なお、シーロム駅の周辺にも日本料理店など日本人向けの店舗が軒を連ねています。シーロムもまた、プロンポンなどと同様に現地で飲食店などを経営する日本人が多いエリアです。
中心部:プラカノン・オンヌット
プラカノンやオンヌットは、バンコク中心部の東側に位置するエリアです。BTSスクンビット線の沿線に位置しており、アソークやプロンポンなどと比較すると閑静なエリアと言えます。
鉄道沿線の道路から路地に入っていくと、オフィスビルよりはコンドミニアムなどの集合住宅が多く立ち並んでいます。中心部と比較するとオフィスビルや商業施設は少ないものの、プラカノンやオンヌットは、都市の中心部へ通勤する人も多く住んでいるエリアです。
バンコクでは朝夕の交通渋滞が常態化しているため、通勤に鉄道を利用する人も少なくありません。プラカノンやオンヌットなどのエリアでは、駅までの近さなど利便性が入居者の有無を左右します。なお、自宅から駅までの往復にバイクタクシーを利用する人も多いため、バイクタクシーのプールを意識してエリア選定すると、空室リスクの軽減が可能です。
外縁部:サムローン
サムローンはプラカノンやオンヌットよりもさらに東側のエリアです。サムローン周辺のエリアでは、オフィスよりも自動車メーカーの工場などが多くなります。どちらかというと、外国人のオフィスワーカーよりは、地元タイ人のブルーワーカーなどが多く住んでいるエリアです。
バンコクの中心部と比較すると物件価格も安く、投資しやすい物件が多いエリアと言えます。しかし、その一方で、低価格帯の物件では募集家賃も下がるため、キャッシュフローが出づらい物件も多くなる点に要注意です。
そのほか、バンコク中心部では賃貸管理を委託できる日系不動産会社も複数ありますが、サムローンを含む外縁部では、営業エリアに含めていない不動産会社も多くなります。外縁部の物件に投資する場合は、入居者募集の委託先に困る可能性があるため、あらかじめ賃貸管理会社を確認することが重要です。
シラチャ
シラチャはバンコクから見て南東に位置しており、バンコクとパタヤとの間にある都市です。港湾都市として発展しており、多くの日系メーカーが海外拠点を設けています。現地へ進出している日系企業は、例えばトヨタ紡績の関連会社や三菱電機などです。
現地には日本人向けの飲食店が多く、日本料理を出している居酒屋なども多数見受けられます。夜には工場に勤務する日本人の駐在員で席が埋まるお店もあるほどです。アパマンショップのフランチャイズも現地で店舗展開しており、日本人駐在員向けの賃貸物件も少なくありません。
このため、シラチャでは日本人駐在員の入居を狙った投資が可能になります。ただし、日系メーカーの業績次第では企業が撤退してしまうこともあり得るため、日本人の入居有無は景気次第な点に要注意です。タイまたは日本で景気が悪化すると、空室発生のリスクが出てきます。
また、日本人を意識した物件には、高層コンドミニアムなど現地人から見て高級物件と言えるものも少なくありません。現地のタイ人は入居者としてなかなか見込めないため、要注意です。
パタヤ
パタヤは日本人のみならず、外国人にも人気のあるリゾートエリアです。マレーシアやシンガポールなど周辺諸国から2~3時間程度で行けるため、海外から観光客が集まってきます。
パタヤでは、リゾートエリアの特性を活かして物件のホテル運用も可能です。観光客向けに短期賃貸を繰り返せば、通常の賃貸運用を続けるよりも大きな利益を狙える可能性があります。その一方で、パタヤには、観光業やリゾート産業以外に目立った産業がない点はリスクです。
歓楽街やゴルフリゾートなどが産業の中心となっているパタヤでは、外交人観光客がいなくなると経済的な打撃を受けます。世界的な不況時やコロナなどによるパンデミックが起きた時などは、外国人観光客も減少するため、物件をホテル運用する場合は特に打撃を受けやすいものです。
パタヤの不動産に投資するのであれば、収益の柱としてではなく、分散投資先の1つとするにとどめてリスクヘッジを図るのが安全と言えます。
まとめ
タイ不動産投資では、経済的な影響が軽微に済む点において、首都バンコクが最も低リスクな投資先です。しかし、バンコクの中でも、中心部と外縁部とでは想定される入居者が異なるため、各エリアの特徴把握が重要になります。
シラチャやパタヤといった地方エリアで物件を選ぶ場合は、分散投資先の1つとして物件を選ぶなど、リスク分散の必要性がある点に要注意です。収益の安定性が外国人観光客や海外駐在員の動向などに左右されるため、状況次第では他の物件による穴埋めが必要になります。
マカオ大手不動産開発会社の日本法人、累計投資額が約200億円に…東京都心部中心
30歳でリタイア、「フルレバ戸建て投資家」の融資戦略とは《楽待新聞》
前回の記事では、不動産投資をはじめたきっかけや、青年時代のエピソードなどを紹介した。今回は投資手法について詳しく紹介していく。
○大津さんの実績
・投資物件:総投資 戸建31戸、現保有 25戸(※うち1戸は転貸物件)
・開始時期:2015年11月
・投資総額:1億825億円(物件価格 7195万円、リフォーム代など 3630万円)
・満室家賃収入:1854万円
・満室想定利回り:21%
・残債:8283万円
・平均調達金利:2.23%
・年間キャッシュフロー:1124万円
・返済比率:39.3%
・平均借入期間:16.5年
・手元資金:2500万円
※不動産賃貸業のみ(別事業は含まない)
※平均借入期間=残債÷年間元金返済額
■社会的信用がなく、現金で不動産投資をスタート
ボロ戸建て投資に特化し、6年間で年間CF1000万円以上までに到達した大津さん。どのような投資手法で拡大していったのだろうか。
不動産投資をはじめたいと思うようになったのは24歳。当初は早期リタイアをするため、拡大スピードを高められる一棟物件を探していた。しかし、当時は社会人2年目でまだ銀行から信用を得られず、融資を受けることはできなかった。
そこで、仕方なくそれまで貯めていた現金500万円を使って、不動産投資をはじめた。
○初めて購入した物件の収支
不動産価格…215万円
リフォーム費用…205万円
家賃収入(月)…5万3000円
表面利回り…15.1%
初めて購入した物件は215万円のボロ戸建て。リフォーム後、客付けを大津市内の不動産業者に頼んだところ、2週間ほどで入居が決まった。この物件は、約6年保有し350万円の家賃収入があり、その後470万円で売却したそうだ。この1棟目について大津さんは「もう少し安く購入しても良い物件だったかなと思いますが、スタートを切ることができたので、上出来な数字かなと思います」と振り返る。
■利回りは「15%あればいい」
ボロ戸建て投資の魅力の1つは高利回りであることだろう。ボロ戸建て投資を行う投資家の中には、状態が悪い物件を破格の安値で購入し、DIYを行って費用を抑えることで、1年間で投資額を回収する投資家もいる。
しかし、大津さんの利回りの購入基準は15%以上。ボロ戸建て投資家は20%以上を狙う人が多いが、なぜこの利回りを基準にしているのだろうか。
理由は主に2つある。
1つ目は、立地にこだわっているからだ。所有している物件のほとんどは、滋賀県の県庁所在地で県内で最も人口が集まっている(約34万人)大津市の主要部付近。滋賀県内では賃貸需要が高いエリアのため、販売価格は多少高くなるが、入居者募集が楽になるだろうと考えていたそうだ。
2つ目は、リフォームを業者に依頼しているからだ。業者に依頼すれば、DIYよりも多くの費用が発生する。物件一覧表を見ると、実際に1件あたり100万~400万円のリフォーム費用が発生している。
費用が発生することによって利回りは下がってしまうが、サラリーマンである自身が平日に働いている間に、リフォームを進めることができる。コストを支払い、物件を早く賃貸募集できる状態にすることで、入居者募集の機会を早く生み出しているのだ。
さらに、リフォームの効率を高めるために、こんな工夫もしている。
通常、リフォーム時には外壁や内装、水回りなど、さまざまな職人が担当の箇所の修繕を請け負う。しかし、大津さんのやり方は少し違う。
「最初は別々の職人にそれぞれ依頼していたんですが、流れや連携の仕方を知らず手配が上手くいかなくて、非常に効率が悪くなってしまいました。そこで、特定の工事だけでなく複数の工事を行える1人の職人さんに絞って、仕事を依頼することにしました」。そうすることによって、リフォームの効率が格段に上がったと振り返る。
「手間がかかるリフォームを業者さんに依頼することで効率よく、物件を収益化させることができました」
■「4.9%」の鉄骨渡り
リフォーム業者との効率的な連携などによって、6年間でボロ戸建てを31戸購入してきた大津さん。これまで銀行から融資を受けて購入してきた。中には金利4.9%で借りたケースも。高金利の融資を受けることはリスクが高く、敬遠する投資家も少なくないが、なぜこのような手法を取るのだろうか。
大津さんは「儲かる物件を買えるチャンスを逃したくないからです」と話す。
2戸目に購入したボロ戸建ては、1戸目のすぐ近く。賃料相場が5万5000円のエリアで販売価格が320万円。物件もリフォーム費用100万円程度で済み、利回りは16%くらいになると予想した。
また、1戸目の物件が近く管理がしやすいという理由から「絶対に買いたい」と思ったと振り返る。しかし、1戸目でほとんど自己資金を使ってしまったために、借り入れを行うしか選択肢がなかった。
何とか購入する方法がないかと考えた末、ある銀行が出していた「不動産担保ローン」を見つけた。このローンは、不動産を担保にすることでお金を借りることができるのだが、なんと金利は4.9%。
一般的な投資用不動産向け融資の金利が1~3%程度であることを考えると、かなり高い金利だ。
それでも「『金利が高いから無理』と考える投資家は多いのですが、私は儲かるとわかっている物件なら金利が高くても購入します」と大津さん。高金利で借り入れるリスクよりも、儲かるとわかっている物件を逃してしまうリスクの方が高いと考えているという。
結局2戸目は、不動産担保ローンを使って320万円で購入。リフォーム費用は当初の想定に近い110万円だった。家賃は相場通りの5万5000円。この物件は数年間保有したのちに550万円で売却した。
■銀行の信用を獲得する3つの方法
高金利のローンも活用しながら、自身の購入基準に合った物件を購入してきた。しかし、信用棄損となり融資に支障が出てしまった経験はないのだろうか。
「今のところ、『これ以上融資をすることはできません』と言われたことは無いです。継続的に融資を受けるために、健全な賃貸経営を行えていることをアピールしています」と大津さん。金融機関に健全な賃貸経営をアピールするため、主に3つのことを行っているという。
1.常に高い入居率を保つ
これまでの入居率は95~100%で推移しており、現在は26戸中1室のみが空室。できる限り満室経営に近づけ、銀行から「この人にお金を貸しても、きちんと返済してくれそうだ」と評価してもらうことが重要だと話す。
また、大津さんは入居率を高めるために、敷金礼金といった初期費用を抑えている。「家賃を下げる方法もありますが、私は初期費用を抑えた方が効果が高いと思っています。長期的な視点でコストを抑えたいというよりも、目先の費用を工面するのに苦労している人の方が多いからです」
2.返済比率を50~60%程度にする
大津さんが買い進めているボロ戸建の場合、築年数が法定耐用年数を超過している。そのため銀行の融資期間が伸びず、10年程度になってしまうことが多い。また、リフォーム費用も含めた融資を打診するため、オーバーローンを受けていることも。
このような買い方を続けていると、返済比率が高くなってしまう。「銀行からすると、返済比率が高ければリスクが高い経営状況だと判断され、融資を控えようと思われてしまいます。そうならないために現金購入も組み合わせて、返済比率を抑える工夫をしています」。
基本的には現金を使わず、融資を受けて購入していく考えだが、大津さんは返済比率が60%を超えないよう、必要に応じて現金で購入する。これまで現金で購入したのは4件だ。
3.無担保物件を複数所有しておく
現金購入した物件を4戸、無担保で借り入れた物件を2戸所有しており、仮に物件の評価が出ず融資額が伸びなかった場合、共同担保を用意できる点もアピールしている。「銀行からすれば、融資額分の担保を確保できれば、仮に返済が滞ってしまったとしても債権を回収することができます。銀行から『共同担保を出してほしい』と要望を受けた場合も、対応できるように備えています」
そもそも、融資を打診する物件は、物件価格よりも積算評価の方が高いものを選んでいる。経営の健全性をアピールすることはもちろんのこと、常に相場価格よりも安い物件を探すことで、融資を受けることができているという。
■不動産会社と関係構築をするための方法
続いて、物件の購入方法について話を聞いた。不動産会社から良い物件情報を紹介してもらうにはどうしたら良いのだろうか。
不動産投資をはじめたばかりの頃は、「属性も低くコネクションもありませんでした」と話す大津さん。待っているだけでは良い物件情報を得ることはできないと思い、大津市にある不動産会社50社に何度も飛び込みをしたという。
「飛び込みは一度で終えるのではなく、何度も行くことが大切です。不動産会社さんは多くのお客さんの対応をしているので、すぐに忘れられてしまいます。何度も顔を出せば、いずれ顔を覚えてもらえますし、そうなれば物件情報が入ったときに声をかけてくれるかもしれません」
大津さん自身も、飛び込みをしたことで顔を覚えてもらい、まだ市場に出ていない物件情報を紹介してもらって購入したことがあるそうだ。
そのような地道な努力で物件を積み重ねてきたことも、短期間で拡大することができた要因の1つだという。
学生時代から「いつか会社経営者になりたい」と考えていた大津さん。不動産投資を行ったのは、その夢をかなえるためだ。24歳から不動産投資をはじめて土台を作りをしてきた。30歳になった現在は、勤めていた企業を退職し、大家業に加え新たに不動産業を始めた。
今後は滋賀県の物件を中心に購入し、ボロ戸建以外の物件も扱っていく考えだ。また、住宅ローンの借り入れが難しい外国人向けに「譲渡型賃貸」という新しいサービスにも挑戦していくそうだ。
◇
最後にこれから不動産投資をはじめていきたいと考えている人に、こんなアドバイスを送ってくれた。
「サラリーマン投資家の中には、小遣い程度の収入を得られればよい、という人もいるかもしれません。しかし、入居者や不動産会社、銀行からは経営者として見られています。そのことを意識しながら覚悟を持ってやってほしい」と思いを寄せる。
現在、不動産会社として不動産投資家と接するようになった大津さんだが、成功する大家と失敗する大家には、ある違いがあると話す。
「自身の事業に責任を持っていない人ほど、『買えない』と嘆いているように思います。確かに、現在は物件価格が高騰しているし、融資も厳しい状況です。しかし、そのような市況の中でも購入できている人は購入しています」
では、自身の事業に責任を持っている人はどのような人なのだろうか。「内見したその場で、即決できる人だと思います。事業に責任を持っていれば、自身の購入基準が決まっています。そのため『いくらであれば購入する』とその場で判断できるんです」
しかし、経験値が浅い初心者にとって、いくらで家賃が付くのか、売却するとしたらいくらになるのかなど、分からないことが多く即決するのは難しいこと。初心者が即決するためにはどのようにしたら良いのだろうか。
大津さんは「とにかく準備をすること」と話す。「内見をする前に、あらかじめあらゆる不動産ポータルサイトで周辺の売買価格の相場や賃貸相場を調査することや、ネットで地図を見て周辺環境を調査しておくことが大切です。確かに即決するためにはリフォーム費用をパッと頭に浮かべられるくらいの経験値が必要なこともありますが、事前準備で解決できることもあります」
目の前に訪れたチャンスをつかむために、日々の勉強を欠かさないようにしてほしいとエールを送った。
物流不動産投資のメリット・デメリットは?主な投資方法・手順も紹介
1.物流不動産投資とは
物流不動産投資とは、商品などを保管する場所として利用される倉庫・物流センターなどの物流施設に対して投資をすることをいいます。
コロナ禍において対面のサービスに規制が掛かるなか、年々インターネット通販による物流の重要性は増していると言えます。インターネットを介した小売り市場(EC市場)では、販売用の商品を保管したり、スムーズに出荷したりすることが重要となります。
特に、高速道路の出入口に近い好立地に、免振や耐震、業務効率向上のための設備を備え、環境にも配慮している先進的な賃貸型大型物流施設に対する需要も増加傾向にあります。物流不動産投資はこのような物流施設に対して投資を行い、賃料収入を得ることを目的としています。
2.物流不動産の特徴
物流不動産とは、先進的な大型倉庫を活用したビジネスモデルです。いくつかの企業が集まり、お互いの役割を決めたうえで、それぞれがWin-Winとなるような仕組みを構築しています。
ディベロッパーは投資家から資金を募って近代的な大型物流倉庫を建設もしくは取得します。その施設において、3PL企業(3rd Party Logistics)が商品の調達、荷揃え、出荷、配送などの物流サービスをワンストップで提供します。
多くの企業で物流業務がアウトソーシング(外注)されており、EC市場に参入している企業は物流業務をサービスとして受けます。
新しい物流施設ではオペレーションの可視化や商品と情報の一体化、リードタイムの縮小などが可能となり、業務効率のアップとコストダウンを期待できます。
このように、建設・取得した大型物流施設を貸したり、施設での物流サービスを提供したりすることで利益を狙うのが、物流不動産のビジネス形態となります。
3.物流不動産投資のメリット
物流不動産への投資には下記のメリットがあります。
- 物流不動産市場の成長が期待できる
- 物流施設の更新需要が期待できる
- 収入が見込みやすい
3-1.物流不動産市場の成長が期待できる
新型コロナウィルスの影響により、さまざまな業界が打撃を受けています。そのなかで、市場規模・売上ともに拡大を見せるのがEC市場(イーコマース)です。
スマートフォンの普及によって、Amazonや楽天といったEC市場は拡大し続けています。また、新型コロナウィルスにより「買い物に出掛けづらい状況」ができたことから、より多くの方がインターネット通販を利用するようになっています。
日本のEC市場の市場規模は2019年時点で約19兆円であり、ここ10年で約2.5倍に拡大している状況です。また、物販に限った場合でも市場規模は約10兆円です。
一方で、モノの移動を伴う物販系のEC化率は約7%で、今後はさらに上昇すると見込まれています。EC市場の拡大やEC化率の上昇に伴い、物流施設に対する需要はさらに高まり、物流不動産市場の成長が期待できると考えられます。
3-2.物流施設の更新需要が期待できる
物流不動産への投資に欠かせないのが、在庫管理や仕分けなどを行う「先進的物流施設」です。先進的物流施設が日本に導入されたのは2002年頃で、これ以降、物流施設を賃貸するというスタイルが定着することになります。
一方で、耐震基準を満たさない旧耐震基準(1981年6月以前の耐震基準)の倉庫も存在しています。仮に耐震化・免振化されていたとしても、建設から40年以上経過していることになります。
現在の物流施設に求められる設備を備えていないケースもあり、老朽化による更新需要が今まで以上に発生する可能性があります。施設そのものの建替え需要があるということも、物流不動産のメリットと言えます。
3-3.収入が見込みやすい
通常の物件(住宅・オフィス・テナントなど)と比較して、物流施設は規模が大きく、契約期間も長くなる傾向にあります。この背景には、倉庫を利用するのは大規模な法人であること、エリアの制限があること、競合する物件が少ないことなどが要因として挙げられます。
また、施設を拠点としてビジネスが展開されるため、他の業種と比較してテナントの入れ替えが少ないという特徴があります。そのため、物流不動産は収入が見込みやすく、他の不動産物件への投資と比べて低リスクな運用が期待できます。
4.物流不動産投資のデメリット
一方で、物流不動産への投資には下記のデメリットがあります。
- 個人による投資が難しい
- テナントが退去する可能性がある
4-1.個人による投資が難しい
物流施設は小さいもので数億円から数十億円、大きな施設なら数百億円規模となります。そのため、個人投資家が1人で投資しようとしても、資金的にかなり厳しいと言えるでしょう。
ただし、個人投資家でも物流不動産に投資できる方法がいくつかあります。詳細は「物流不動産への投資方法」にて詳しく解説していきます。
4-2.テナントが退去する可能性がある
物流施設は他の業種と比較してテナントの入れ替えが少ないというのは、前述した通りです。しかし、テナントが永遠に入居を続けるわけではないため、賃料収入が途絶えてしまう可能性があります。
物流施設のネガティブな特徴として、差別化が難しいということが挙げられます。仮に、近隣に最新設備を備えた物流施設ができた場合、テナントが流れてしまう可能性があり、代替テナントをすぐに見つけるのも難しくなってきます。
また、物流施設は「物流における利便性」にフォーカスしているため、その土地自体の価値が高くなく、他の用途への変更にも適さないケースがあります。
需要が多く一定の利益が見込めるとはいえ、盤石というわけではないことを理解しておきましょう。
5.物流不動産への投資方法
前述したように、個人投資家が1人で物流施設への投資や、物流施設による資産運用を行うのは難しいといえます。数億円から数百億円という規模の資金的な問題があり、なおかつテナントとの信頼関係も構築する必要があるためです。
一方で、下記の方法なら個人でも容易に物流不動産に投資することができます。それぞれ詳しく見て行きましょう。
- 物流施設に特化したクラウドファンディングへの投資
- 物流施設に投資を行うREITへの投資
5-1.物流施設に特化したクラウドファンディングへの投資
近年、クラウドファンディングによって不動産に投資できるサービスが増加しています。
なかでも、物流施設に特化したクラウドファンディングサービスを提供している「CRE Funding」を利用すれば、個人でも物流不動産に投資することができます。
CRE Funding
CRE Fundingは物流不動産への投資ができる不動産投資型クラウドファンディングサービスです。2社が運営に携わっており、案件を組成しているのは、東証一部上場企業である株式会社シーアールイーです。
株式会社シーアールイーは、主にCRE Funding上で運営される案件の組成を行い、サイト上で募集を行っています。東証一部上場企業が直接運営に携わっているソーシャルレンディングサイトは、このCRE Fundingだけです。CREグループでは、物流施設をメインとした不動産管理・実物不動産投資・不動産私募ファンド運用などを手掛けており、過去の運用実績も豊富です。
一方、運営会社のFUEL株式会社がファンド組成の審査や運用中のモニタリングを行い、透明性の高い投資環境と幅広い投資期間を提供しています。1口1万円から投資可能で、3ヶ月~12ヶ月程度の短期的な運用期間であることから、物流不動産への気軽な投資が可能となっています。
5-2.CRE Fundingの利用手順
CRE Fundingへの投資は下記の手順にて行います。
- 会員登録
- 口座開設
- ファンドへの投資
会員登録
CRE Fundingの会員登録ページから会員登録を行います。[無料で登録する]ボタンからメールアドレスを登録しましょう。登録したメールアドレスに確認メールが届きますので、記載されたURLをクリックして登録完了です。
口座開設
次に、口座開設の申請を行います。申請者の氏名や住所、出金用の振込先などの入力、本人確認書類、マイナンバーカード画像のアップロードを行いましょう。
運営会社が内容を確認し次第、登録住所へ「ウェルカムレター」(簡易書留郵便)が送付されます。ハガキを受け取った時点で口座開設が完了します。
ファンドへの投資
口座開設完了後は投資口座への入金を行い、投資したいファンドを選定して申し込みます。投資ができれば、運用期間中のスケジュールに沿って分配や償還が実施されます。
5-3. 物流施設に投資を行うREITへの投資
物流施設に投資を行うREIT(上場投資信託)への投資によって、物流不動産投資が可能です。物流施設への投資に特化、または物流施設を含む不動産に投資するREIT銘柄は下記の通りです。
- 東海道リート投資法人(2989)
- 大和ハウスリート投資法人(8984)
- 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)
- 東急リアル・エステート投資法人(8957)
- オリックス不動産投資法人(8954)
- 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(3493)
- CREロジスティクスファンド投資法人(3487)
- 三菱地所物流リート投資法人(3481)
- 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)
- スターアジア不動産投資法人(3468)
- ラサールロジポート投資法人(3466)
- 野村不動産マスターファンド投資法人(3462)
- 日本プロロジスリート投資法人(3283)
- GLP投資法人(3281)
- 産業ファンド投資法人(3249)
- SOSiLA物流リート投資法人(2979)
(2021年7月時点)
REITは1口から投資可能で、基準価額が最低投資額となります。2021年7月7日現在では、1口6万円程度から60万円程度で投資できます。
5-4.REITの利用手順
REITへの投資は下記の手順で行います。
- REIT取引を行う証券会社を選ぶ
- 証券口座を開設する
- 入金して投資をする
REIT取引を行う証券会社を選ぶ
REITへの投資を行うために、証券会社を選びます。REITは株式のように売買されている(上場投資信託)ため、基本的にどの証券会社を選んでも取引可能です。そのため、取引手数料の安さや情報量の多さ、普段利用している銀行口座との連携などを考えて償還会社を選びましょう。
三井住友銀行と連携できる「SMBC日興証券」や、住信SBIネット銀行と連携できる「SBI証券」などのネット証券であれば、PCやスマホから簡単に取引を行うことができるうえ、取引手数料も割安になっています。下記の記事でネット銀行と連携できるネット証券会社5社をまとめていますので、まだ口座を開設されていない方は併せてご参考下さい。
【関連記事】ネット証券とネット銀行を連携するメリットは?ネット証券会社5社を比較
証券口座を開設する
証券会社を選んだら口座開設の手続きを行います。氏名や住所などの情報の記載と本人確認書類・マイナンバーカードの提出(画像のアップロード)などが必要になります。
申込みを終えたあと、自宅にハガキが送付されてきます。その内容に沿ってコード入力やマイページログインなどを行うことで口座開設が完了します。
入金して投資をする
開設した証券口座に投資資金を入金します。後は、投資したいREITを選択して購入すればREITへの投資が可能です。
【関連記事】REIT(リート)投資のメリット・デメリットは?配当の仕組みや注意点も
【関連記事】REIT(リート)の始め方は?初心者でも分かる投資手順や銘柄選びを解説
まとめ
今回は物流不動産投資の概要やメリット・デメリット、実際の投資方法などについて紹介しました。物販のEC化が進む日本において、物流施設への需要は増加傾向にあり、投資対象として注目する方も少なくありません。
物流施設に特化したクラウドファンディングやREITなどへ投資することで、個人では難しかった物流不動産への投資が可能です。興味のある方は、まずは物流不動産投資の運用の仕組みなど情報収集など行い、検討してみましょう。
ワクチン接種ツアーも「メディカルツーリズム」の一種
現在、新型コロナのワクチン接種を完了した人数が断トツに多いのはアメリカです。アメリカでは、鉄道駅やスーパーマーケット、ドラッグストアといった人々が日常的に利用する施設を接種会場にしているほか、車を降りずに受けられる「ドライブスルー接種」なども取り入れられています。
このようにワクチン接種活動が急ピッチで進められた結果、集団免疫効果が見えはじめたため、海外からの観光客受け入れも再開されました。それに伴い、外国人観光客を対象にした「ワクチン接種ツアー」も企画され、申込者が殺到しているようです。このワクチン接種ツアーもまた、「メディカルツーリズム」の一種といえます。
これまでのメディカルツーリズムはアメリカなどの先進国が主流でしたが、医療費が高額すぎるため一般外国人は治療を受けることができませんでした。しかし近年、劇的に医療技術が向上したアジア諸国において、適正な医療費で外国人患者を受け入れる取り組みがはじまったのです。
日本人医師も参入…アジア諸国のメディカルツーリズム
●シンガポール
シンガポールでは国家ぐるみでメディカルツーリズムを推奨しています。医師不足の解消と高度な医療水準維持のため、外国で取得された医師免許(条件付き)を認めるかたちで、世界各国から優秀な外国人医師を招致しています。ここ数年は日本人医師の数も増えており、日本人医師が常駐するクリニックもいくつかあります。
シンガポールの私立病院では、各専門医は病院内の施設をテナントとして借り受けてクリニックを開業するシステムを取っています。看護師などの医療スタッフは医師が直接雇用しており、運営や診療方針もすべてその医師に委ねられています。つまりこれらの専門医は独立した開業医なのです。
●マレーシア
マレーシアにおけるメディカルツーリズムの魅力は、高い医療技術を比較的安価な治療費で受けられる点にあります。病院を含めたインフラ整備はアジア諸国の中でもトップレベルで、大きな私立病院であれば設備も十分に整っており、外国人も安心して受診できます。加えて、海外旅行傷害保険に加入していればキャッシュレスで受診できます。ほとんどの医師は英語を話し、中には日本人スタッフや日本語での診療が可能な医師が勤務している私立病院もあります。
●インドネシア
インドネシアでは、私立病院であれば近代的な施設も整っており、医師をはじめ医療スタッフに日本人がいるなどメディカルツーリズムの拠点として安心感があります。しかし医療体制の地域格差が大きく、ケガ(交通事故、マリンスポーツ、登山)、熱中症、脱水症、経口感染症(下痢、肝炎など)、デング熱、皮膚疾患など、さらに致命的な感染症である狂犬病には十分に対応できない病院もあります。大都市の医師数は増加していますが、地方・郡部ではまだまだ医師不足の状態です。一般に国公立病院は混雑しており、外国人の利用は慣れないと難しいでしょう。
●タイ
首都・バンコクにある私立病院の医療水準はかなり高く、日本の病院と比較しても遜色はないといえます。それらの病院では、日本の医学部を卒業した医師、あるいは日本の病院で研修経験のある医師または看護師などが勤務しています。また日本語通訳(日本人またはタイ人)が勤務し、専用窓口を設けるなど、日本人受診者の便宜を図っています。
しかし、私立病院では診察料・治療費などは各々の病院が独自に定めており、全般に日本と比べて安価とはいえません。支払い時のトラブルを避けるためにも、事前に料金などを確認するか、または海外旅行傷害保険などの保険が適用されるか確認することが必要です。
不動産投資は「グローバルな視野」を得る方法の1つ
最近のスポーツ・科学・美術といった分野での日本人のグローバルな活躍は目を見張るものがありますが、一方で、日本人医師が世界で活躍しているという話はあまり聞きません。その間に成長著しいアジアの国々は、積極的に世界展開を図り、日本との差を縮めています。その施策の一つが、外国人が最先端医療を受けることができるメディカルツーリズムなのです。
流暢な英語を話しアメリカなどの最先端医療を学んだ医師が、現地の安い人件費や医療費を活用し、英語圏の患者を治療する。このシステムが近年大当たりし、シンガポールやタイでは国際的病院評価認証機関(JCI)の認証を受けた医療機関の数が、日本をはるかに上回っています。日本の医師がグローバルに活躍するのは、夢のまた夢なのでしょうか?
日本はかつて製造業で世界を席巻しました。医療分野でもそれは可能なはずです。そのためには、一人でも多くの日本人医師が、世界の医療の良いところも悪いところも実際に見て歩くことが必要です。
海外不動産投資は、医療に関するグローバルな視野を持つきっかけとなってくれます。今はまだ気軽に海外へ出かけることはできませんが、この状況が永遠に続くわけではありません。世界で活躍できる医師を目指すならば、未来の自分を描く材料として、海外不動産投資に取り組んでみるのはいかがでしょうか。
大山 一也
プノンペンで不動産投資、メリット・デメリットは?人口推移も検証
1.プノンペンの不動産に投資するメリット
プノンペンの不動産に投資する主なメリットは、若年人口の多さから空室率の低い投資を期待できることと、2次運用による資産分散が可能となることなどです。
1-1.生産年齢人口が多いため空室率の低い運用を期待できる
カンボジア政府の統計によると、カンボジアの首都であるプノンペンには、2019年時点でカンボジアの全人口のうち約14%が集まっています。
また、CIAの統計によると、カンボジアの年齢中央値は2020年の予測値で26.4歳と比較的若いものです。年齢中央値を他の国と比較すると、以下の表のようになります。
東南アジアの年齢中央値の比較
| 国 | 年齢中央値 |
|---|---|
| カンボジア | 26.4歳 |
| マレーシア | 29.2歳 |
| タイ | 39.0歳 |
| ベトナム | 31.9歳 |
※参照:CIA「The World Factbook」
カンボジアの年齢別人口ピラミッド
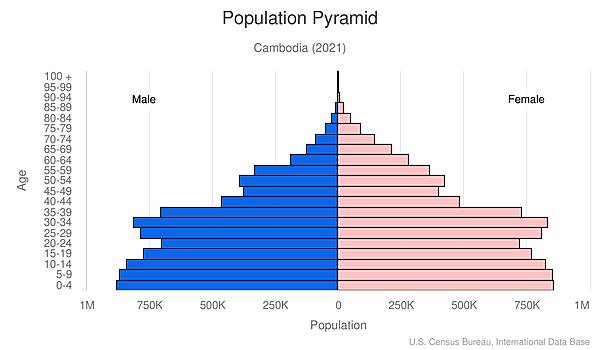
※引用:The World Factbook「Cambodia Details」
カンボジアの年齢別人口を見ると、最も多いのは20代後半〜30代前半の年齢層です。この年齢層は働き始めて間もないため、賃貸の家に住む人も多くなります。プノンペンはカンボジア経済の中心地であることからも、働き盛りの人が多いプノンペンで不動産投資を行うメリットは大きいと言えるでしょう。
1-2.比較的高利回りの投資ができる
プノンペンは東南アジアの中で比較しても大きな経済成長を続けている都市です。しかし、物件価格はまだそれほど上がっておらず、他国と比較して高利回りの投資を期待できます。東南アジアにおける都市別の利回りは以下の表のとおりです。
| 都市 | 利回り |
|---|---|
| プノンペン | 5.33% |
| クアラルンプール | 3.72% |
| バンコク | 5.13% |
| ホーチミン | 4.33% |
※参照:Global Property Guide「Rental Yields」
プノンペンの不動産投資では、人口増加によるキャピタルゲインと安価な物件価格によるインカムゲインとをバランスよく狙える点にメリットがあります。
1-3.為替リスクが低い
カンボジアでは自国通貨であるリエルのほかに、USドルが流通しています。家賃収入もUSドルで得られるため、カンボジア不動産投資では、新興国でありながら為替リスクを抑制可能です。
東南アジアの新興国では自国通貨しか流通していないことが多く、この場合、値動きの激しい新興国通貨の為替リスクを背負うことになります。一方、アメリカの法定通貨であるUSドルは先進国の通貨と比較して低リスクな通貨です。
プノンペンの不動産投資では、安価で利回りの高い投資をしながら、為替リスクの低いUSドルで資産形成できます。また、USドル建ての資産形成は資産分散の観点でも有効です。
1-4.外国人も米ドルの銀行口座を開設しやすい
海外不動産投資では、投資先の国での銀行口座開設も解決すべき課題の1つとなります。現地で定期的な収入がない場合は、外国人による口座開設ができないエリアも少なくありません。
しかし、プノンペンの金融機関では、現地非居住の日本人でも米ドルの銀行口座を開設しやすいメリットがあります。また、経済成長が著しいカンボジアの金融機関では、定期預金などの利率も高水準です。
不動産投資で得た米ドル建ての家賃収入を、定期預金口座への預け入れなどによって2次運用すれば、さらなる資産形成も可能となります。外国人による口座開設のハードルが低く、資産の2次運用も可能な点は、プノンペンの不動産に投資する大きなメリットです。
2.プノンペンの不動産投資で要注意のデメリットやリスク
プノンペンの不動産投資では、新築のコンドミニアムが主な選択肢となることから、竣工リスクに要注意です。
2-1.竣工リスクに要注意
カンボジアでは外国人による土地の保有が認められていません。プノンペンの不動産投資では、コンドミニアムが主な選択肢となります。また、カンボジアでは中古不動産の市場整備が道半ばとなっているため、日本人が購入できるのは新築コンドミニアムが中心的です。
プノンペンで日本人が購入できる新築コンドミニアムは、プレビルドと呼ばれる完成前の物件が多く、物件が完成しない「竣工リスク」に注意を要します。
竣工リスクとは、売主の資金不足などによって物件の建設工事が中止された結果、物件の引き渡しを受けられないリスクのことです。工事が中止されてしまうと、支払い済みの資金も返還されない可能性があります。
プノンペンの不動産投資で竣工リスクを見極めるためには、実績が豊富な不動産エージェントを介したり、日系デベロッパーが開発に入っている物件を選ぶことなどが重要です。
2-2.空室リスクのケアが必要
カンボジアは経済成長が著しく、首都のプノンペンはカンボジア経済の中心地ですが、現地人の所得はまだそれほど高くありません。その一方で、外国人が購入できる物件は現地人から見ると高級物件が多く含まれてます。
価格が高い高級物件で利回りを確保するためには、家賃も高水準に設定する必要があります。2021年時点、高水準の家賃を支払えるのは、外国人駐在員か現地の富裕層に限られてくる点に要注意です。
プノンペンで物件を選ぶ際には、入居者の候補となる人が現地にどの程度いるか確認することが重要になります。なお、カンボジアの在留邦人数は少なく、海外駐在員は中国人の割合が多くなっています。
2-3.外国人が購入できるのはコンドミニアムのみ
すでに解説したとおり、カンボジアでは外国人による土地の保有が認められていないため、カンボジア不動産投資で購入対象となるのはコンドミニアムのみです。
また、カンボジアでは人口増加率が高いことなどから、キャピタルゲインを狙えます。しかし、将来的に物件を売却して利益を得るためには、適切なメンテナンスの継続が重要です。
集合住宅となるコンドミニアムでは、共用部の管理を管理組合が請け負います。このため、購入する物件では管理組合が組織されるのか、管理組合から建物管理などを受託する管理会社はどのような会社なのか、事前の確認が重要です。
3.プノンペンの人口推移について
プノンペンでは10年間で約20%人口が増加しているほか、人口密度も上昇しているため、コンドミニアム投資に適した環境が整ってきていると言えます。カンボジア政府が発表している統計によると、プノンペンの人口および平均人口増加率は以下の表のとおりです。
プノンペンの人口
- 2008年:1,501,725人
- 2019年:2,129,371人
※2019年の人口は推計
プノンペンの平均人口増加率
- 1998年〜2008年:2.8%
- 2008年〜2019年:3.2%
※参照:カンボジア政府統計「Provisional Population Census 2019」
プノンペンの人口は2008年〜2019年の間に約62万8,000人増えているほか、2008年以降の平均人口増加率は、直近の10年平均を上回っています。政府の統計からは、プノンペンでは人口増加の勢いが増している様子が伺えます。
また、1㎢あたりの人口についても、2008年の2,212人から2019年には3,136人まで上昇しており、プノンペンでは人口密度も上昇中です。人口密度が高いエリアでは集合住宅の入居率が高くなるため、プノンペンはコンドミニアム投資に向いていると言えます。
まとめ
プノンペンの不動産投資では、人口および人口密度の上昇や若年人口の多さから、キャピタルゲインを狙えます。また、米ドル建ての資産形成が可能となる点も、プノンペン不動産投資の大きなメリットです。
しかし、竣工リスクや空室リスクには注意を要します。プノンペンで物件を選ぶ際には、入念な下調べと信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
不動産投資とインフレ率の関連性は?不動産価格や金利の推移との比較も
1.2015年以降のインフレ率推移
2015年以降のインフレ率推移を検証します。2020年以降は特に新型コロナウイルスの影響が見られます。日本銀行が発表している資料を参照すると、2015年以降のインフレ率推移は以下グラフの通りです。
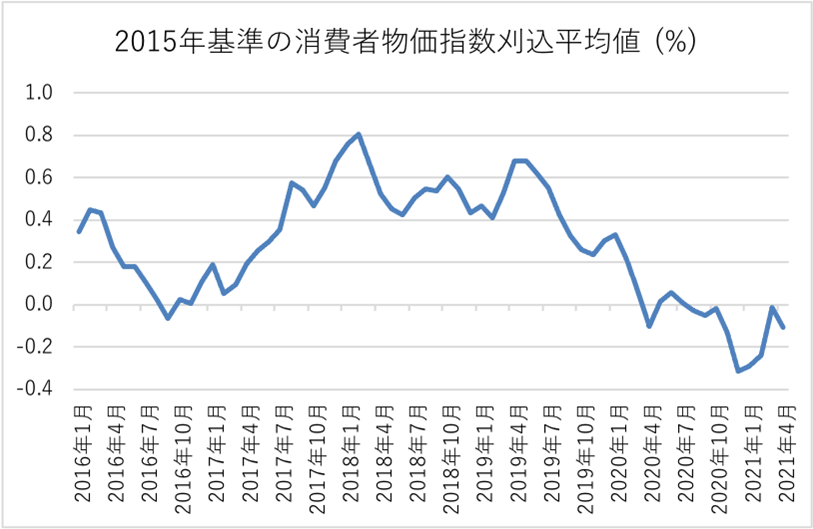 ※参照:日本銀行「分析データ>基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
※参照:日本銀行「分析データ>基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
直近5年間でインフレ率が最高だったのは2018年1月〜2月の時期で、それぞれのインフレ率は対前年比0.8%でした。この時期にインフレ率が上がった原因の1つは、アメリカにあると考えられます。
想定される主要な原因は、トランプ政権によるアメリカの法人税減税に対する期待から、アメリカの株価が史上最高値を更新したことです。
アメリカの株価上昇は日本の株価にも浮揚効果をもたらし、株価の上昇が景気の改善を促した結果、日本でもインフレ率が上昇したものと考えられます。
日本における2015年以降のインフレ率は、周期的な上下動を繰り返しているようにも見えます。しかし、2020年以降の下がり幅は、2016年の下がり幅よりも大きくなっている点が特徴的です。特に、2020年末にかけては対前年比で-0.3%まで下がっており、直近5年間では最低となっています。
なお、失業者数などと照合して見ると、2020年10月の失業率と完全失業者数は過去5年間で最高に近い数値まで上昇した時期です。新型コロナウイルスの影響によって景気が悪化したため、インフレ率が下がったとも考えられます。(※参照:総務省統計局「労働力調査 長期時系列データ」)
2021年3月のインフレ率は対前年比で0%まで持ち直しましたが、4月には再び-0.1%に下がっています。今後の推移も、新型コロナウイルスの影響を大きく受けると考えられます。
2.2015年以降の長期金利推移
つづいて長期金利の目安となる10年国債の推移を検証します。直近5年間の推移では、特に低下している時期が2つありました。日本銀行が発表している資料によると、10年国債の利率は以下グラフのように推移しています。
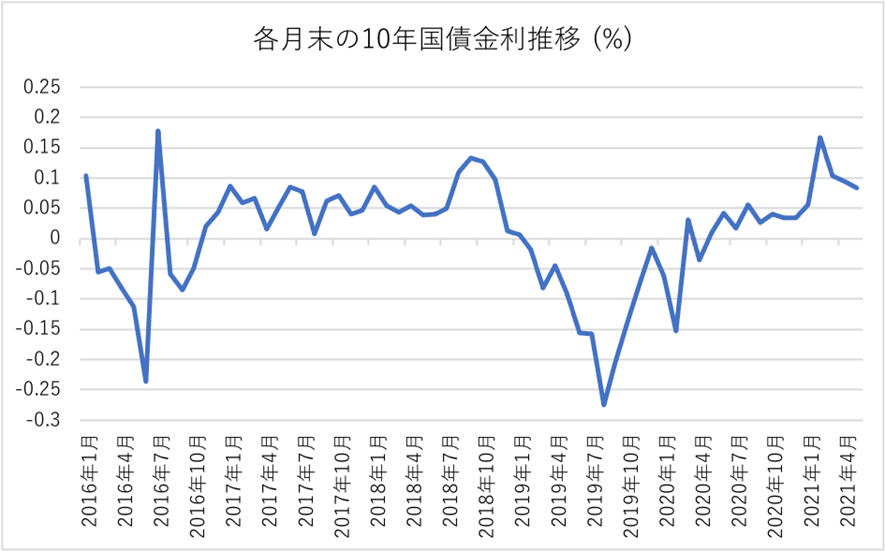 ※参照:財務省「国債金利情報」
※参照:財務省「国債金利情報」
2016年以降の約5年間において長期金利が最高に到達したのは2016年7月で、金利は0.178%でした。なお、2021年2月にも0.168%に達しており、直近5年間で2番目の高金利となっています。
反対に長期金利が最低値を記録したのは2019年8月で、金利は-0.275%でした。2番目に低かったのは2016年6月で、金利は-0.237%です。
新型コロナウイルスの感染拡大と長期金利の関連性を鑑みると、日本で最初に感染者が確認されたのは2020年1月で、翌月の2月には長期金利が下がっています。しかし、それ以降は上昇基調にあり、2020年5月以降は0%を下回った月がありません。
なお、日本銀行は「利上げは当面先になる」との見解を示しており、2021年時点では低金利政策が今後も継続される見通しです。
長期金利とインフレ率の推移を照合すると、インフレ率はコロナの感染が拡大してから低下気味ですが、2020年下半期以降の長期金利は直近5年間で比較的高めに推移しています。
10年国債の利回りは「期待インフレ率と期待される経済成長率」に左右される側面もあり、金利の推移からは「経済の回復期待が大きい」とも考えられます。
また、長期金利が2016年11月以降プラスで推移している一方、インフレ率も2017年の春以降上昇したことを鑑みると、長期金利の後を追う形でインフレ率も上がっていると考えられます。
3.投資用物件の価格推移
投資用区分マンションと一棟アパートの価格推移を検証します。それぞれ違った値動きをしている点が特徴的です。
3-1.投資用区分マンションの価格推移
不動産投資と収益物件の情報サイト健美家が発表している「マンスリーレポート2021年4月期」によると、2015年以降、約1,600万円を上限として上下動を繰り返している様子が伺えます。しかし、長期的には約1,300万円〜1,600万円の間で横ばいと言える状況です。
物件価格が上がったタイミングを見ると、2019年2月と2021年4月に物件価格が上がっています。2019年2月は長期金利の下がり始めに近い時期であり、不動産投資ローンの金利も下がったものと考えられます。
また、インフレ率の推移と照合すると2019年初頭は比較的インフレ率が高めに推移していた時期です。インフレ率が高く金利が低い時期は、投資用区分マンションの価格も上がりやすいと言えます。
なお、2021年4月はインフレ率が低い時期ではありますが、長期金利は直前の時期よりも少し下がった時期です。投資用区分マンションの価格推移は、金利に敏感に反応するとも考えられます。
3-2.一棟アパートの価格推移
一棟アパートの価格推移をみていきましょう。区分マンションと比較すると、一棟アパートの価格は上下動が多い点が特徴的です。
不動産投資と収益物件の情報サイト健美家の「マンスリーレポート2021年4月期」を参照し、2015年からの推移で見ると、一棟アパートは2016年から2017年にかけて上昇基調で推移しました。2017年に入って以降の価格推移は比較的横ばいです。約6,200万円〜7,000万円の間を上下動しています。
インフレ率および長期金利の推移と一棟アパートの価格推移とを照合すると、物件価格が上がった時期とインフレ率が上がった時期とは概ね一致しています。その一方で、インフレ率は2020年以降低下していますが、一棟アパートの価格は下がっていません。
なお、2019年に長期金利が低下している一方でアパートの価格は変動していないことから、長期金利の低下は区分マンションと比較してアパートの価格に影響しなかったと言えます。
まとめ
インフレ率・長期金利と投資用不動産の価格推移を照合すると、どちらも区分マンションや一棟アパートなど不動産価格に影響を与えている様子が伺えます。ただし、物件種別の比較では、区分マンション価格の方が双方の指標に敏感に反応してきた背景があります。
一棟アパートについては、低金利がすでに長期間続いていることや物件規模の大きさから、インフレ率の影響が大きいと考えられます。直近5年間で見ると、2021年時点のインフレ率は低めに推移しているため、今後の価格推移には注意を要します。
借金があっても、不動産投資は始められる?
情けないことに、諸事情で620万円の借金があります。カードローンで、3社からの借入です。「まずは借金の返済をしなさい」が正解なのかもしれませんが、少しでも早く不動産投資を始めたいと思っております。
下記のような属性ですが、融資がおりる可能性ありますでしょうか。
・年収1090万円
・借金620万円(カードローン)
・資産300万円
・勤続年数5年
・独身
・子供1人
・賃貸 7.5万円/月
お知恵をお貸し頂ければ、幸いです。宜しくお願い致します。
■回答者:帆足太一@収益専門 さん(不動産投資家)
過去の経験からになりますが、資産よりも多いカードローンがある場合は、厳しいと考えた方が良いと思います。
可能性だけでいえば、追加のカードローンや有担保ローンで数百万円から1000万円くらいの融資などであれば可能性はゼロではありません。
しかしながら、プロパー融資だったり1棟ものの融資を行う場合、カードローンがある時点で「お金に困っている人」というレッテルが貼られてしまいますから、そういう規模拡大していく融資は難しいということになります。
やるなら数百万円の物件をダメもとで公庫や多目的ローンでやるということになるのですが、ご年収も高いですから、せめて借金と同額の資産を築いてからのスタートを推奨します。
不動産投資の楽待
50万円からはじめられる少額不動産投資!賃貸型宿泊施設経営「一室ホテルリース」スタート
宿泊施設における企画・設計・デザイン・運営・管理をワンストップで提供する合同会社Nowhereが、不動産投資初心者向けに少額からはじめられる賃貸型宿泊施設運営「一室ホテルリース」のサービスを開始した。

■一室ホテルリースのメリット
不動産投資を新しく始めたい!でも、通常のマンション投資やホテル投資のように何千万、何億も投資できるわけではないし、今は忙しくて不動産投資の勉強やマーケットリサーチもできないから自分には無理だ!と思っている人のための「一室ホテルリース」。
コンセプトは、「投資知識がなくても気軽にスタートができる」「少額からはじめられる」「副業ではじめられる」の3つ。同社によると、「不動産投資へ踏み出すきっかけになれば」という思いで開始したサービスだという。
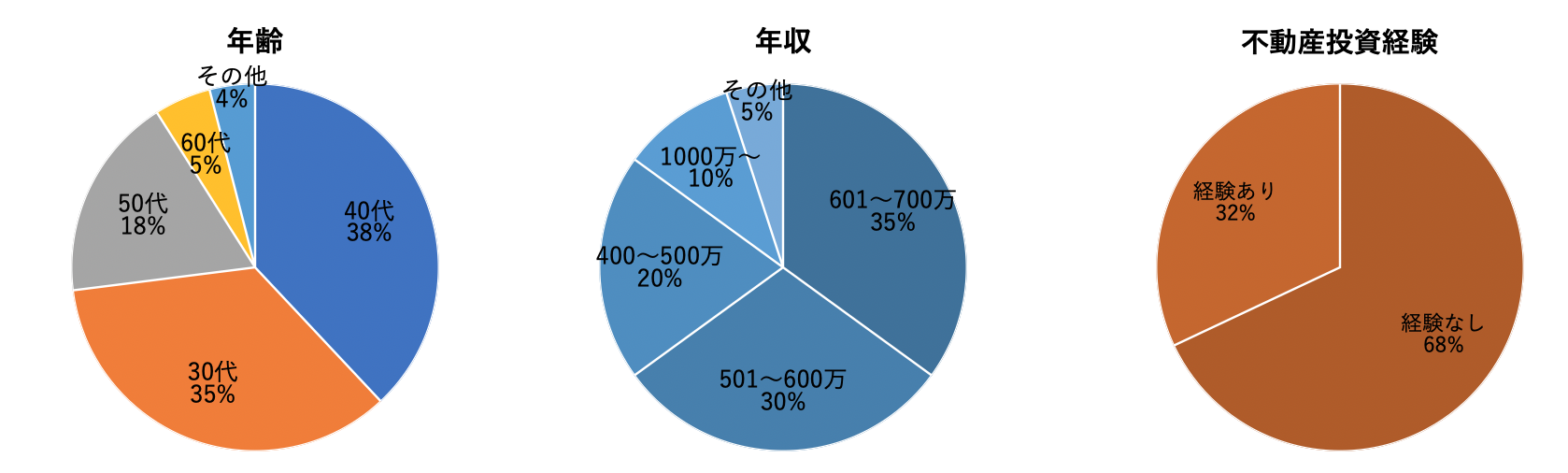
■一室ホテルリースのサービス概要
「一室ホテルリース」は、空室マンションの1室、空き戸建ての1室(棟)、空き別荘の1室(棟)を賃貸し、国内外の一般観光客が利用できる宿泊施設として運用する「賃貸型宿泊施設運用(経営)」となる。
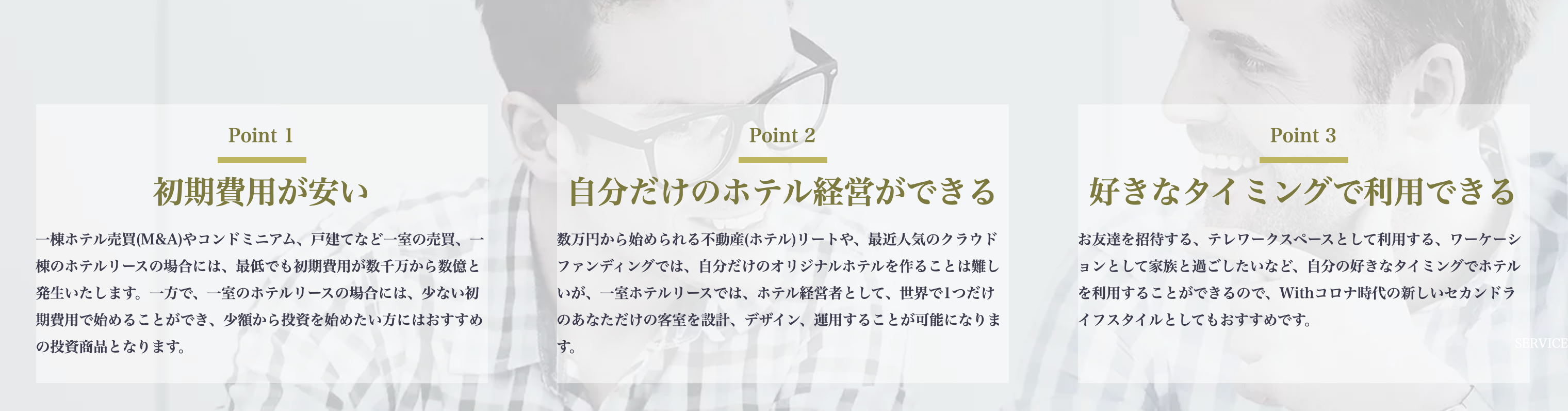
建築リフォームを担当する一級建築士、空間デザインを担当するインテリアデザイナー、PL/BSなど資金調整調達を担当するキャピタルデザイナー、申請関係を担当する申請アドバイザー(行政書士)、宿泊運営を担当するホテルマンやレベニューマネージャー、建物管理を行うファシリティーデザイナー、リスク対策を担当するリスクマネージャー(元警察)など多種多様な専門集団が集結し、宿泊施設経営に関わる、不動産探しから申請・企画・設計・デザイン・運営・管理の各事業領域を横断したトータル的なサービスを一気通貫。
不動産投資における初期投資費用の削減と、投資収益性の向上の実現を目指すという。

健美家編集部
中所得サラリーマンの不動産投資の進め方<2021年版投資展開図>
サラリーマンを卒業して半年が経過した。
卒業した後に何をしたいか??
ワシは学生の頃追いかけていた『 夢 』に再挑戦するべく舞台に出演する。
ゆくゆくは『 Vシネマ 』に俳優として出演したいと思っている。
いよいよ7月22日に開演。ワシは7/22~26の計10公演に出演する。もし良ければ舞台を観に来て欲しい。40過ぎたおじさんが、本気で取り組んでいる。役作りの為に、髪もなくした。
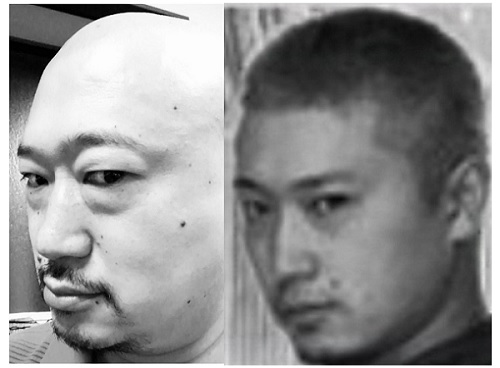
若い頃と比べて見た目は大分変ったが、情熱は衰えていない( 笑 )
さて、後輩夫婦から、自宅購入の相談を受けた。
旦那( 年収550万 )と奥様( 年収420万 )の夫婦。
気に入った家は23区内駅5分で価格は7,000万OVERだ。
金利0.775%、期間35年で月の返済は19万程になる。
まだ収益物件を持っていない後輩夫妻は、ニコニコしながらマイホームについての夢を語る。優しく、かつ正直に思うところを示したが、( ワシに相談しないでくれ~ )という心の声までは届いたかは分からない。
いつの順番に自宅を購入するか?
どの価格帯の物件を購入するか?
それによって、生きやすさが大きく変わる。
サラリーマンの『 夢 』の一つであるマイホーム購入には悩みは尽きない。
■ 中所得サラリーマン投資家の2021年版投資展開図
前回、ここ数年間で融資の状況が変わってきたという話を書いた。
最近、今まで聞いたことの無い銀行名がチラホラ出てきている。
「 サラリーマンの『 一棟目=初手 』に限り融資します 」というジャンルでは、今までオリックス銀行の独壇場だったが、ここに徳島大正銀行が名乗りを上げてきた。
以前、研究生が千葉県市原市の価格4,000万、利回り13%後半のアパートを買いたいと、ノンバンクであるトラストとセゾンに融資を打診したのじゃが、それぞれ4割融資( 1,600万 )と6割融資( 2,400万 )で回答が来て断念したことがあった。
なかなか厳しい時代だと思っていたのじゃが、この物件が売れたという。調べてみると、購入を決めたのは徳島大正銀行を使った初手のサラリーマンで、頭金500万~600万で融資が通ったと聞いた。
数年前と違い、『 初手 』の入り方は非常に大事になってきている。
庶民の味方だったトラストの4000万を超える融資が渋くなってきていることが大きな要因。
また、『 初手 』( 1棟目 )しか使えない金融機関の存在もある。
もちろん、手金が多くあれば、融資も前向きに検討してもらえるが、初期のころは現金の回復がなかなか追いつかない。
いかに効率的に『 一手 』を進めるかは、融資が厳しめの時代に突入した今、最も考えるべきことじゃと思う。
■住宅ローンがない人で一棟目を買いたい人の投資戦略
今回、住宅ローンをまだ組んでおらず、不動産投資をこれから始める人の投資の進め方をワシなりに考えてみた。
オリックス銀行( ※夫婦所得合算 )
徳島大正銀行( ※一都三県在住者 )
<二手目>( 購入金額目安はサラリーマン年収相当 )
現金戸建て購入
<三手目>( 4,000万以内 )
三井住友トラスト
<四手目>
住宅ローンで賃貸併用住宅
一手目しか使えない銀行があることを念頭に、「 融資が厳しくなってきた時代 」を乗り越えるために、1億円以内の借入で三手目までを指すことを目指すことが重要じゃと思う。(※基本的に中所得サラリーマンに対して書いているのでご了承願いたい )
一手目のオリックス銀行は年収700万、徳島大正銀行も同等の年収の基本的な融資基準バーが存在するが、オリックスは夫婦合算が認められる場合がある等、審査を完全に断られることは少なくなってきた。
昨年の今頃は個人の年収バーがきつく、断られる人が多かった印象なので、少し緩和しているように感じられるが、この状態もいつまで続くかは分からない。
オリックスは物件の地域と築年数で金利と融資年数が決まる。本人の年収がバーに足りなくても、奥様の年収を合算して審査してもらえることがある。
「 基本は40年-築年数 」で、地域により10年間の融資期間の延長が可能なようだ。築年数が若めだと利回り自体が10%前後のことが多いが、収支が合えば購入を検討できる物件もある。
徳島大正銀行は、一都三県在住で更に年収というバーもあるが、物件の地域はオリックス銀行より融通が利くので、比較的高利回りな物件を狙うことができる。
オリックスで融資を組むなら返済比率5割強、徳島大正銀行の場合は返済比率5割以下に抑えられるようなら是非とも利用を検討したい。
まとめると、一手目として3,000万~5,000万の融資を組んで、二手目に現金で戸建てを購入して全体の返済比率を調整。( もちろん、16号線の内側で道路付けが良く、再建築可能な物件が望ましい )。
二手目まで進んだら現金をある程度回復する期間へ。
三手目は、戸建てを共同担保に入れて、三井住友トラストを利用。4,000万以内の購入したい物件を見つけたら融資審査に。物件・地域により求められる『頭金』の金額が変わるので、持ち込んで審査をしてもらうことで感覚を掴もう。
結果、ここまで進んだとしても中所得サラリーマンでは借入金額が1億を超えることはない。総返済比率50%以下で借り入れになるはずなので、購入した物件の半数が空室になっても持ち出しはほぼ出ない。
そして、ここがポイントじゃが、これだけ借入していても、住宅ローンは組める。逆に、住宅ローンを組んだ後では使えない銀行もあるので、先に使える金融機関を利用しておくことは、持たざる者にとっては指しておきたい一手となる。
前述の後輩夫妻が、三手目まで指した上で7,000万円OVERの物件を自宅として購入するなら、返済の不安や将来の展望は幾分明るくなる。どうせ組むならここまでやってからならどうか? と、アドバイスしたいが、一般の人にはこの考え方は理解されない。
ま、読んでいる人は不動産投資に興味がある人じゃと思うので、無理目の住宅ローンで大きい金額を組むより、それにちょっとプラスするくらいの借入で、不労所得を手に入れて欲しいと強く思う。
ワシ自体はもう投了気味( 笑 )なので、新規に始める人に相談されたらという前提じゃが、2021年に始めたい中所得サラリーマンに相談されたら、今書いたようなことを教えると思うんじゃ。
ワシなりに調べた内容じゃが、他にも手は存在するはず。人によってもタイミングによっても異なってくる。頭だけでなく足も使い、常に情報を収集することが大事なんじゃ。そしていい情報があれば、ぜひワシにも教えてほしい。
■ サラ卒したワシが役者として出演する舞台 「 うどん 」のご案内
さて、そんなチャレンジとして、サラ卒したワシが、夢を取り戻すために役者として出演する舞台( KENプロデュース第33回公演『 うどん 』 )が、シアターシャイン劇場( JR阿佐ヶ谷駅or丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅 )で7/22~26、7/27~8/1に前後半のWキャスト×2で公演する。
ワシは、前半の7/22~26にシングルキャストで出演する。( 10公演 )
コロナの影響で、1公演の客席を40名に縮小した状態での公演。最後にワシ扱いのチケット予約フォームを貼っておくので、興味がある方は是非観に来て欲しい。
身に来ていただいた方の特典として、チケットの半券を大事に持っていてもらえたら、いずれ優先的なイベントを開催したいと思う( 笑 )
コロナ禍で不動産投資ローンの審査は厳しくなった?金融機関が懸念すること
コロナ禍において飲食店が相次いで閉店に追い込まれる中、不動産経営の環境は非常に厳しくなっています。そのため、金融機関も不動産投資ローンの融資審査を以前よりも厳しい目線で行う可能性があります。コロナ禍においても不動産投資ローンの審査に通過するためには金融機関が「融資をおこなっても安心」だと判断できる物件をよく選んで投資をすることが非常に重要です。
コロナ禍における不動産経営のリスクと、融資審査に通過するためのポイントについて詳しく解説していきます。
コロナ禍の不動産投資の4つのリスク

コロナ禍において、不動産投資環境には変化が生じています。
次の4つのリスクが上昇したことによって、以前よりも厳しい目線で審査されるケースも多いでしょう。
・家賃相場の下落
・空室率の上昇
・地価の下落による担保割れ
・不景気による家賃の滞納
これら4つのリスクは商業用不動産で特に上昇していると言われています。
コロナ禍における不動産経営の4つのリスクについて詳しく見ていきましょう。
家賃相場の下落
景気の悪化や人口の減少、地域の共有過多などによって周辺地域の家賃相場が下がると、入居者確保のために投資物件の家賃を引き下げざるを得なくなります。
コロナによって飲食店をはじめとする店舗が相次いで閉店していることから、商業物件はかなりの空きが出始めています。
空き物件が増えると受給バランスのために当然家賃は下がってきます。
今後、コロナ禍による不景気が飲食店を中心として、物件の空きがさらに増えていけば家賃が下落し、不動産投資における収益を確保することが難しくなるリスクがあります。
空室率の上昇
コロナ禍によって景気が悪化すれば、投資物件の空室率が上昇する懸念があります。
居住用賃貸物件は景気の悪化によってすぐに空きが出ることはありませんが、商業物件に関してはすでに空きがかなり出ています。
当然ながら物件に空きが出れば家賃収入の確保ができないので、家賃収入よりも借入金の返済の方が大きくなってしまい、借金返済が不可能になる可能性があります。
今投資をしても、コロナ禍による不景気が深刻化していけば、現状の家賃収入を維持することが難しくなるということは十分に考慮しておくべきでしょう。
地価の下落による担保割れ
新型コロナウイルスの影響で不動産市況が悪化すれば、不動産価格も下落します。
現に、海外の中にはコロナウイルスの影響で不動産価格が下落している国も出始めています。
不動産価格が下落すると、銀行の担保評価額も下落します。
担保評価額を融資残高が下回ることを「担保割れ」と言いますが、担保割れになると万が一の場合に銀行は融資残高全額を回収することができません。
担保割れの物件に対する融資は銀行にとってリスクが高いので、担保割れの融資に対しては金利を引き上げることがあります。
今後、不動産価格が下落していくと担保割れになり、不動産投資ローンの金利が引き上がってしまうリスクに注意しなければなりません。
不景気による家賃の滞納
居住用の賃貸物件は商業用物件と比較してコロナ禍の影響は小さいですが、居住用の不動産には入居者の家賃の滞納リスクがあります。
コロナによって仕事を失った人、収入が減ってしまった人は多数存在するので、入居者の中には家賃を支払うことができない人がいるかもしれません。
家賃を滞納されたとしても、借入金の返済はやってくるので場合によっては借入金の返済が不可能になる可能性もあります。
居住用住宅に投資している人も、入居者の家賃の支払いには注意しましょう。
コロナ禍でも不動産投資ローンの審査に通過するには
商業用不動産中心として、不動産投資環境は以前よりも厳しさが増しており、その分金融機関の融資審査のハードルが高くなっています。
金融機関の審査にスムーズに通過するためには次の4つのポイントを抑えて借入申込を行いましょう。
・自己資金を3割程度用意する
・築浅物件に投資する
・実質利回りの高い物件に投資する
・取引履歴のある金融機関へ申し込む
不動産投資ローンの審査にスムーズに通過するために抑えるべき4つのポイントについて詳しく解説していきます。
自己資金を3割程度用意する
自己資金を総額の3割程度用意すれば審査に通過できる可能性はかなり高くなります。
自己資金分だけ担保評価額に余裕ができるので、自己資金が多い物件へのローンは金融機関にとって有利な融資になるためです。
例えば、3,000万円の物件購入のために1,000万円の自己資金を用意し、2,000万円借りた場合には金融機関は2,000万円の融資に対して3,000万円の担保を取得したことになります。
これだけ担保に余裕があれば、万が一の時も融資金を回収できる可能性が高いので、金融機関にとってはリスクの低い融資だということができます。
スムーズに審査に通過するためには、投資総額の3割程度の資金を手元に用意してから申し込みをしましょう。
築浅物件に投資する
できる限り築浅の物件に投資した方がよいでしょう。
築浅の物件は高い家賃を長期間継続させることができ、空室率も低めに持続させることができます。
古い物件の方が売買価格は安いので購入当初は利回りが高くお得に感じますが、家賃が下がるのが早く空室率も高くなりがちです。
コロナ禍のような不景気時には特にそのような傾向が強くなるでしょう。
また、築浅物件の方が担保評価額が高いので銀行が融資しやすくなるメリットもあります。
実質利回りの高い物件に投資する
当然ながら実質利回りの高い物件の方が審査に通りやすくなります。
例えば、3,000万円の投資に対して実質利回り3%であれば年間90万円の収益ですが、実質利回り5%の物件なら150万円の収益です。
高収益物件の方が返済できる可能性が高くなるので、銀行も安心して融資を実行することができます。
不景気においても、収益力のある物件に対して銀行は「融資をしたい」と考えています。
できる限り利回りの高い物件へ投資を行いましょう。
取引履歴のある金融機関へ申し込む
不景気時の不動産投資ローンの申し込みは、これまで取引のある金融機関へ申し込みましょう。
不景気時の不動産投資ローンは銀行にとってリスクの高い融資の1つだと言われています。
景気が悪い時には、不動産価格の下落や家賃収入の減少によって投資そのものが失敗するリスクが高くなるためです。
ただでさえリスクの大きな投資資金をこれまで1度も取引をしたことがない人に融資をすることは金融機関にとって大きなリスクになります。
これまで不動産投資ローンを利用しており、問題なく返済することができている人であれば、金融機関から一定の信頼を得ることができているので、審査に通過できる可能性があります。
コロナ禍のような不景気のときこそ、信頼関係構築できている金融機関へ相談しましょう。
また、不景気時にも融資を受ける金融機関を確保するためにも、日頃から金融機関との信頼関係の構築に努めることは大切です。
不景気時には投資のチャンス|優良物件を探し確実に審査に通過しよう
コロナ禍によって、商業用不動産中心として確かに不動産投資のリスクは高まっています。
しかし、収益力の高い物件への投資で、自己資金を用意し、信頼関係が構築されている金融機関へ相談することで審査に通過できる可能性はあります。
コロナ禍のような不景気時こそ、優良物件を安価で購入できるチャンスでもあるので、割安な物件を探してみるとよいでしょう。
(提供:Incomepress )

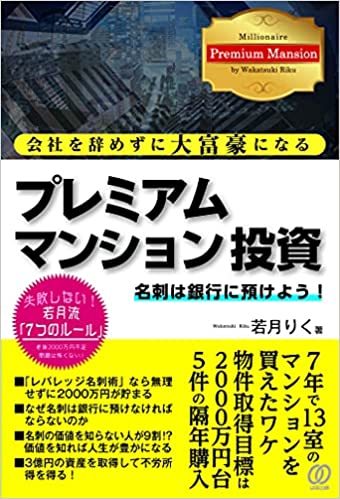
 COZUCHI
COZUCHI CREAL
CREAL TSON FUNDING(ティーソンファンディング)
TSON FUNDING(ティーソンファンディング)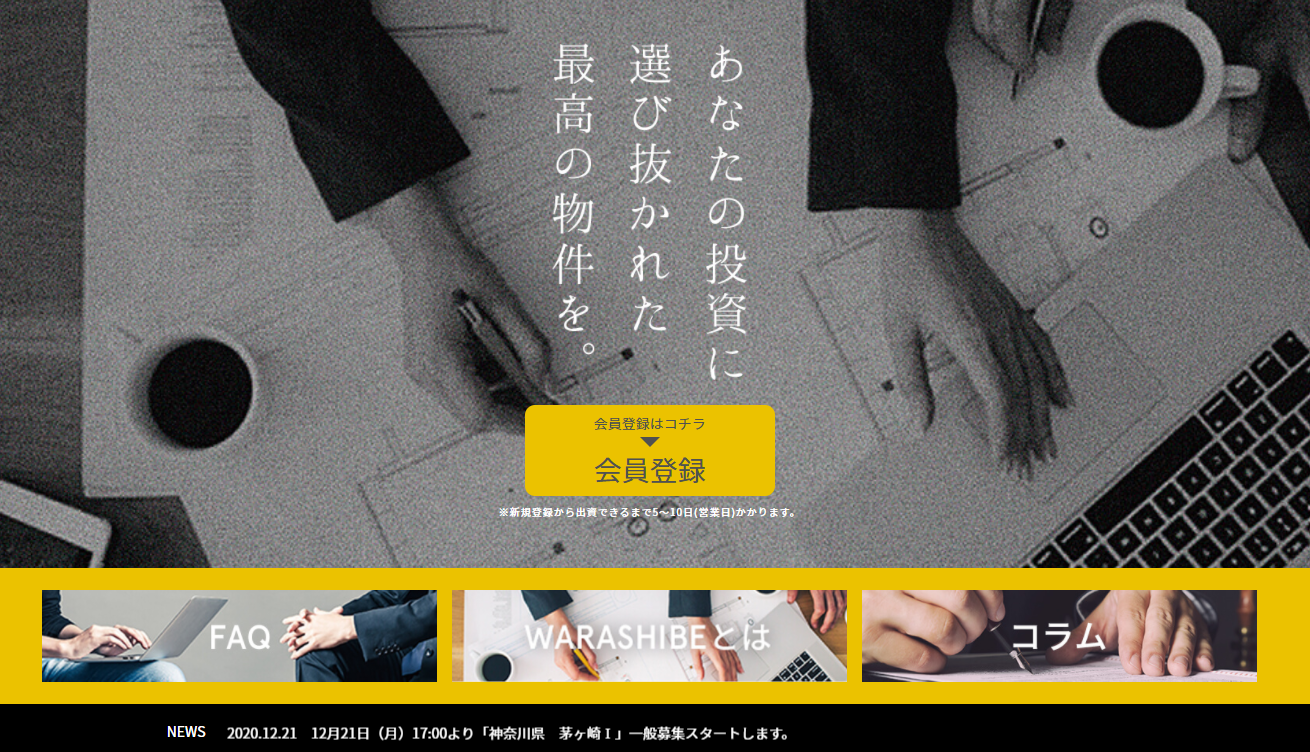 WARASHIBE
WARASHIBE Rimple
Rimple SBI証券
SBI証券 楽天証券
楽天証券 税理士ドットコム
税理士ドットコム 信長ファンディング
信長ファンディング




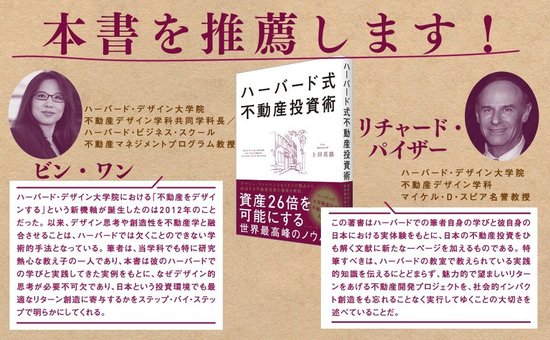

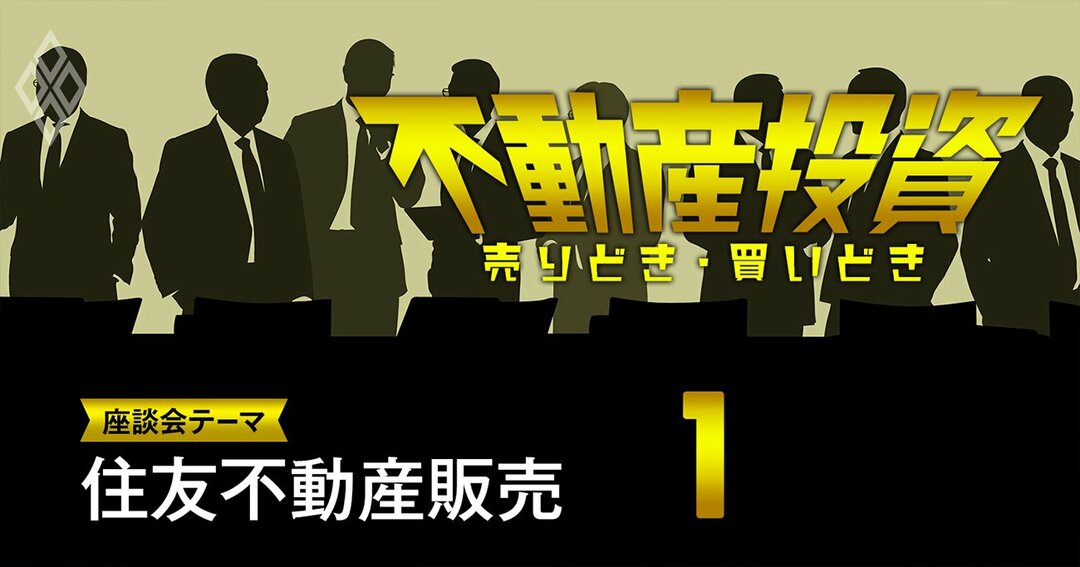


 CRE Funding
CRE Funding
コメント
コメントを投稿