自己資金ゼロで不動産投資…「フルローン」のリスクとは?
フルローンなら高額物件の購入も可能だが…
現金買いの築古投資を始める前に。資本主義のルールや仕組みは誰も教えてくれない
こんにちは!セミナーやなどでお医者さんや大学院を卒業された方から相談される高卒製造業のふんどし王子です! 不思議な感じですが「 ふんどしにできるなら、自分にもできそう!」と思ってもらえれば幸いです(笑)
さて、最近は築古戸建投資が流行っています。今日のコラムでは、それについて自分なりの考えを書こうと思います。
■ 現金買いの築古戸建投資を始める前に
最初に考えなければいけないのは、戸建て投資も「 不動産投資 」である以上、手元資金を効率良く増やすためにはどうすればよいか? を意識することが重要だということです。
200万円の戸建てを利回り20%で購入するのは素晴らしいことですが、年間40万円の家賃では投下した資本( お金 )を回収するのに5年掛かってしまいます。
この投資したお金が一年でいくら戻ってくるかという指標をCash-On-Cash Return( キャッシュ・オン・キャッシュ リターン )、略してCCRと言います。
200万円の投資で家賃40万円の場合は、「 40万円÷200万円=0.2 」で、現金の戻り率( CCR )は20%となります。
次に、レバレッジ( 借金によるテコの原理 )を使った場合を想定します。200万円の頭金を入れて、物件価格2,000万円の利回り15%のアパートを購入したと仮定します。
すると、毎月の家賃収入25万円に対し、毎月の返済額は約11万円で、キャッシュフローは月14万円。年間にすると「 14万円×12ケ月で168万円 」が入ってきます。
200万円の投資額に対してCCRは「 168万円÷200万円=0.84 」となり、現金の戻り率( CCR )は84%となります。
※計算を簡単にするためいろいろな税金や費用を省いています
使ったお金は同じ200万円ですが、回収のスピードの違いは一目瞭然。レバレッジを使った後者の場合は、1年強の収益で、また似たようなスペックの物件を購入できるようになります。
さらに同等の物件を購入できた時は、CFが「 168万円×2棟で年間336万円 」となり、200万円を作るのに1年もかかりません。次の物件を買えるまでのスピードは、こうしてどんどん速まります。
■ 色々な選択肢を知り、そこから最適解を選んでいこう
現金で買った築古戸建てを稼働させ、家賃収入だけで次の物件を購入しようと思った場合、利回り20%でも5年程度かかるところ、レバレッジを利かせることにより、時間を前倒して次々と投資を行えるようになるということが、おわかりいただけたでしょうか?
「 当然のことを言うな! 」と思われる方も多いでしょうが、これから始める方の中には、知らない方もいます。築古戸建投資が人気ですが、不動産投資の醍醐味であるレバレッジ( 借金 )と複利の力を活用しないのはもったいないと思い書かせて頂きました。
「 だけど、融資が厳しいでしょ? 」と思った方もいるかもしれません。しかし、現在でも、地銀と日本政策金融公庫の協調融資を使いアパートを購入されたサラリーマンの方もいらっしゃいますし、本人の属性を活用して、1,500万円程度の融資を受けている方もいらっしゃいます。
まずは、融資を活用できないか検討してみて、ダメだった場合に戸建投資を考えても良いと思います。もちろん、すべての手法に一長一短があり、「 経験値や安全性 」など、数字には見えない部分もあります。
上手にやれば、すべて正解ですし、間違った考えや手法であれば、すべて失敗する可能性はあります。色々な選択肢を勉強して、その中から最適解を選んでいくのが良いと思います。
■ 築古戸建投資にマイホームを絡めるというやり方も
初心者で賃貸暮らしをしており、これから築古戸建投資を始めるという方は、築古戸建を自宅として活用することを考えてみると、選択肢が広がると思います。
その時にうまくいくコツですが、再生が終わった物件を購入するのではなく、残置物がモリモリであったり、外壁がはげているなど、「 伸びしろ 」がある物件を探すのがいいと思います。
世の中には「 土地建物+リフォーム工事 」を1本にまとめた住宅ローンがあります。フラット35にもリフォーム一体型の商品がありますね。
参照:https://www.flat35.com/loan/reform/conditions.html
そして、相見積りを取りながら、安いリフォーム業者を探して再生すればいいのです。全国の投資家さんの築古再生を見ていると、ビックリするくらいキレイでおしゃれにしています。
また、築古を仕入れて再生して再販している業者は、300万円~500万円の利益を乗せていると聞きます。それらを「 応用 」して、自宅を含み益のある資産として保有するのです。
築古戸建に住みながら再生し、含み益のある資産として保有することで得られるスキルとして、以下のようなものがあります。
身銭を切る事により、経験値は爆発的に増えます。また、住宅エコポイントを活用すれば最大60万ポイントがあたります。
参照:https://www.jisedai-points.jp/
当たったポイントでリフォームを行い、築古の問題である断熱性を高めることができれば素敵です。交換商品を見ているとパソコンなど高額なものもあり、活用できそうです。
地方では300万円以下で家が購入出来ることは珍しいことではありません。そこに300~500万円のリフォームをすれば、外も中もピカピカになります。
知り合いの投資家にも、築40年の家に35年ローンが通った方がいます。収益不動産では耐用年数がネックになりますが、住宅ローンは給料収入が基準となるため、担保評価の影響は少なめです。
その結果、田舎の市街化調整区域に大きな家が建ちます( 笑 )。※ある程度は土地建物の担保評価も関係あります
また、リフォーム費用を含めて仮に700万円を35年返済の金利1%の住宅ローンで購入した場合、月々の返済は2万円以下です。つまり、賃貸に住むより購入する方が月々の支払が安くなる逆転現象が起こります。
自分で住みながら不具合を直して、物件の強みと弱みを理解しながら、アウトレットなどを回ってお洒落なインテリアの勉強もしても良いかもしれません。マンション販売の現場にあるようなステージングのつもりで頑張りましょう。
出口ですが、しばらく住んで飽きてきたら、980万円など、利益が出る値段で売りに出します。これをワタクシは「 自宅の商品化 」と呼んでいます。自宅を楽しみつくした後に、利益まで残すのです( 笑 )
条件を満たす必要がありますが、自宅の売却益は3,000万円まで税金が掛かりません。
参照:国税庁HP
ヤドカリ投資は、賃貸だけではなく、所有して売却することで、キャピタルゲインも狙えるのです。自宅再生+貯金で種銭を作るのは難しいことではありません。築古戸建の活用として頭の片隅に置いて頂ければと思います。
補足すると、都会の方は1,500万円~2,000万円などと単位を大きくして、戸建て以外にマンションも視野に入れて考えるのも良いのではないでしょうか。
人によっては、自宅は「 夢 」なのに、投資だとか利益だとか言うのはけしからん! と思われるかもしれません。しかし、不動産を購入するという行為は、個人の資産におけるポートフォリオに不動産資産として計上されることになります。
無意識でも、立派な投資行為です。売却する際に債務を消せない場合や、担保となっている不動産の資産価値が低い場合は、債務超過状態です。住宅ローンを抱える多くの方が、債務超過になっていると思います。
また、マイホームにお金をかけすぎると、資産のポートフォリオにおける不動産の割合が突出し、現金などの流動資産が少なくなりがちです。これは不測の事態に弱い状態と言えます。一度自分の資産と負債を棚卸しして分析してみると良いと思います。
■ 資本主義のルールや仕組みは誰も教えてくれない
日本は資本主義なので、資本主義のルールを知らなくても勝手に適用されています。そして「 そんなの知らなかったんだもん! 」と言って通用するのは子供だけです。自分で気づき、知識を獲得していくしかありません。
税金、社会保障、様々な制度をすべて理解することは不可能です。しかし、「 知らなければ損をする 」「 誰も教えてくれない 」ということは意識して生活することが大事です。
多くの制度の恩恵を受けたり、活用する場合は「 自己申告制 」だということです。遺族年金や障がい者年金を受け取れる資格があるのに、受け取っていない場合があります。
以前、ポールさんのYouTubeチャンネルで障がい者年金の話を紹介したところ、それを見た方が「 自分も適応されるんじゃない? 」と申請し、5年前まで遡り200万円程度受け取れたとのことです!
本来は10年前から受け取れたところ、5年以前は時効となり、権利が消滅していたそうです。もったいないことをしたと言っていましたが、今後受け取れる額を考えると大きな違いになるととても感謝されました。
この方はわざわざワタクシのセミナーに参加してくださって、直接感謝を伝えてくれたので嬉しかったです。極端な例でしたが、単純なミスで取りこぼしていることは多くあります。知識を身に着けて資本主義社会を攻略していきましょう!
それでは次回、またお会いしましょう。
■ セミナーのお知らせ
2020年のセミナーもドンドン決まっています。お会いできることを楽しみにしています。
2月15日( 土 )に札幌で、加藤ひろゆきさんと初コラボをさせていただきます。( 残席僅かとなったため、増席しました )
⇒詳細・お申込み
3月7日( 土 )に鹿児島セミナーを開催させて頂きます!
⇒詳細:お申込み
3月20日( 金 )には岐阜にセミナーでうかがいます!
⇒詳細:お申込み

皆様とお会いできることを楽しみにしています。
さて、最近は築古戸建投資が流行っています。今日のコラムでは、それについて自分なりの考えを書こうと思います。
■ 現金買いの築古戸建投資を始める前に
最初に考えなければいけないのは、戸建て投資も「 不動産投資 」である以上、手元資金を効率良く増やすためにはどうすればよいか? を意識することが重要だということです。
200万円の戸建てを利回り20%で購入するのは素晴らしいことですが、年間40万円の家賃では投下した資本( お金 )を回収するのに5年掛かってしまいます。
この投資したお金が一年でいくら戻ってくるかという指標をCash-On-Cash Return( キャッシュ・オン・キャッシュ リターン )、略してCCRと言います。
200万円の投資で家賃40万円の場合は、「 40万円÷200万円=0.2 」で、現金の戻り率( CCR )は20%となります。
次に、レバレッジ( 借金によるテコの原理 )を使った場合を想定します。200万円の頭金を入れて、物件価格2,000万円の利回り15%のアパートを購入したと仮定します。
物件金額:2,000万円
頭 金:200万円
融 資 額:1,800万円
金 利:1.5%(元利均等返済)
返済期間:15年
頭 金:200万円
融 資 額:1,800万円
金 利:1.5%(元利均等返済)
返済期間:15年
すると、毎月の家賃収入25万円に対し、毎月の返済額は約11万円で、キャッシュフローは月14万円。年間にすると「 14万円×12ケ月で168万円 」が入ってきます。
200万円の投資額に対してCCRは「 168万円÷200万円=0.84 」となり、現金の戻り率( CCR )は84%となります。
※計算を簡単にするためいろいろな税金や費用を省いています
使ったお金は同じ200万円ですが、回収のスピードの違いは一目瞭然。レバレッジを使った後者の場合は、1年強の収益で、また似たようなスペックの物件を購入できるようになります。
さらに同等の物件を購入できた時は、CFが「 168万円×2棟で年間336万円 」となり、200万円を作るのに1年もかかりません。次の物件を買えるまでのスピードは、こうしてどんどん速まります。
■ 色々な選択肢を知り、そこから最適解を選んでいこう
現金で買った築古戸建てを稼働させ、家賃収入だけで次の物件を購入しようと思った場合、利回り20%でも5年程度かかるところ、レバレッジを利かせることにより、時間を前倒して次々と投資を行えるようになるということが、おわかりいただけたでしょうか?
「 当然のことを言うな! 」と思われる方も多いでしょうが、これから始める方の中には、知らない方もいます。築古戸建投資が人気ですが、不動産投資の醍醐味であるレバレッジ( 借金 )と複利の力を活用しないのはもったいないと思い書かせて頂きました。
「 だけど、融資が厳しいでしょ? 」と思った方もいるかもしれません。しかし、現在でも、地銀と日本政策金融公庫の協調融資を使いアパートを購入されたサラリーマンの方もいらっしゃいますし、本人の属性を活用して、1,500万円程度の融資を受けている方もいらっしゃいます。
まずは、融資を活用できないか検討してみて、ダメだった場合に戸建投資を考えても良いと思います。もちろん、すべての手法に一長一短があり、「 経験値や安全性 」など、数字には見えない部分もあります。
上手にやれば、すべて正解ですし、間違った考えや手法であれば、すべて失敗する可能性はあります。色々な選択肢を勉強して、その中から最適解を選んでいくのが良いと思います。
■ 築古戸建投資にマイホームを絡めるというやり方も
初心者で賃貸暮らしをしており、これから築古戸建投資を始めるという方は、築古戸建を自宅として活用することを考えてみると、選択肢が広がると思います。
その時にうまくいくコツですが、再生が終わった物件を購入するのではなく、残置物がモリモリであったり、外壁がはげているなど、「 伸びしろ 」がある物件を探すのがいいと思います。
世の中には「 土地建物+リフォーム工事 」を1本にまとめた住宅ローンがあります。フラット35にもリフォーム一体型の商品がありますね。
参照:https://www.flat35.com/loan/reform/conditions.html
そして、相見積りを取りながら、安いリフォーム業者を探して再生すればいいのです。全国の投資家さんの築古再生を見ていると、ビックリするくらいキレイでおしゃれにしています。
また、築古を仕入れて再生して再販している業者は、300万円~500万円の利益を乗せていると聞きます。それらを「 応用 」して、自宅を含み益のある資産として保有するのです。
築古戸建に住みながら再生し、含み益のある資産として保有することで得られるスキルとして、以下のようなものがあります。
・業者による見積もりの違いがわかる
・外壁、窓、クロスなどのリフォーム単価がわかる
・確定申告による住宅ローン控除の仕組みがわかる
・不動産の購入する際の雑務全てを経験できる
・外壁、窓、クロスなどのリフォーム単価がわかる
・確定申告による住宅ローン控除の仕組みがわかる
・不動産の購入する際の雑務全てを経験できる
身銭を切る事により、経験値は爆発的に増えます。また、住宅エコポイントを活用すれば最大60万ポイントがあたります。
参照:https://www.jisedai-points.jp/
当たったポイントでリフォームを行い、築古の問題である断熱性を高めることができれば素敵です。交換商品を見ているとパソコンなど高額なものもあり、活用できそうです。
地方では300万円以下で家が購入出来ることは珍しいことではありません。そこに300~500万円のリフォームをすれば、外も中もピカピカになります。
知り合いの投資家にも、築40年の家に35年ローンが通った方がいます。収益不動産では耐用年数がネックになりますが、住宅ローンは給料収入が基準となるため、担保評価の影響は少なめです。
その結果、田舎の市街化調整区域に大きな家が建ちます( 笑 )。※ある程度は土地建物の担保評価も関係あります
また、リフォーム費用を含めて仮に700万円を35年返済の金利1%の住宅ローンで購入した場合、月々の返済は2万円以下です。つまり、賃貸に住むより購入する方が月々の支払が安くなる逆転現象が起こります。
自分で住みながら不具合を直して、物件の強みと弱みを理解しながら、アウトレットなどを回ってお洒落なインテリアの勉強もしても良いかもしれません。マンション販売の現場にあるようなステージングのつもりで頑張りましょう。
出口ですが、しばらく住んで飽きてきたら、980万円など、利益が出る値段で売りに出します。これをワタクシは「 自宅の商品化 」と呼んでいます。自宅を楽しみつくした後に、利益まで残すのです( 笑 )
条件を満たす必要がありますが、自宅の売却益は3,000万円まで税金が掛かりません。
参照:国税庁HP
ヤドカリ投資は、賃貸だけではなく、所有して売却することで、キャピタルゲインも狙えるのです。自宅再生+貯金で種銭を作るのは難しいことではありません。築古戸建の活用として頭の片隅に置いて頂ければと思います。
補足すると、都会の方は1,500万円~2,000万円などと単位を大きくして、戸建て以外にマンションも視野に入れて考えるのも良いのではないでしょうか。
人によっては、自宅は「 夢 」なのに、投資だとか利益だとか言うのはけしからん! と思われるかもしれません。しかし、不動産を購入するという行為は、個人の資産におけるポートフォリオに不動産資産として計上されることになります。
無意識でも、立派な投資行為です。売却する際に債務を消せない場合や、担保となっている不動産の資産価値が低い場合は、債務超過状態です。住宅ローンを抱える多くの方が、債務超過になっていると思います。
また、マイホームにお金をかけすぎると、資産のポートフォリオにおける不動産の割合が突出し、現金などの流動資産が少なくなりがちです。これは不測の事態に弱い状態と言えます。一度自分の資産と負債を棚卸しして分析してみると良いと思います。
■ 資本主義のルールや仕組みは誰も教えてくれない
日本は資本主義なので、資本主義のルールを知らなくても勝手に適用されています。そして「 そんなの知らなかったんだもん! 」と言って通用するのは子供だけです。自分で気づき、知識を獲得していくしかありません。
税金、社会保障、様々な制度をすべて理解することは不可能です。しかし、「 知らなければ損をする 」「 誰も教えてくれない 」ということは意識して生活することが大事です。
多くの制度の恩恵を受けたり、活用する場合は「 自己申告制 」だということです。遺族年金や障がい者年金を受け取れる資格があるのに、受け取っていない場合があります。
以前、ポールさんのYouTubeチャンネルで障がい者年金の話を紹介したところ、それを見た方が「 自分も適応されるんじゃない? 」と申請し、5年前まで遡り200万円程度受け取れたとのことです!
本来は10年前から受け取れたところ、5年以前は時効となり、権利が消滅していたそうです。もったいないことをしたと言っていましたが、今後受け取れる額を考えると大きな違いになるととても感謝されました。
この方はわざわざワタクシのセミナーに参加してくださって、直接感謝を伝えてくれたので嬉しかったです。極端な例でしたが、単純なミスで取りこぼしていることは多くあります。知識を身に着けて資本主義社会を攻略していきましょう!
それでは次回、またお会いしましょう。
■ セミナーのお知らせ
2020年のセミナーもドンドン決まっています。お会いできることを楽しみにしています。
2月15日( 土 )に札幌で、加藤ひろゆきさんと初コラボをさせていただきます。( 残席僅かとなったため、増席しました )
⇒詳細・お申込み
3月7日( 土 )に鹿児島セミナーを開催させて頂きます!
⇒詳細:お申込み
3月20日( 金 )には岐阜にセミナーでうかがいます!
⇒詳細:お申込み

皆様とお会いできることを楽しみにしています。
目的が大事!不動産投資のキャッシュフローはマイナスになってもいい
不動産投資におけるキャッシュフローについては、「プラスになることが最低条件」と「マイナスになる時期があっても構わない」という2つの考え方があります。一般的には前者を支持する人が多いようですが、優劣をつけることはできません。なぜなら、何を目的として不動産投資に取り組むかによってキャッシュフローについての考え方は変わるからです。
キャッシュフローは何によって構成される?

(画像=FrameRatio/Shutterstock.com)
現金が主体の家計や小さな商店では「いくら儲かったか」は「いくらお金が増えたか」で決まります。このように「キャッシュフロー=利益」と考えるのは一般的と言えるでしょう。
しかし企業経営や投資ではこの考え方は必ずしも当てはまりません。利益は現金のやり取りだけではなく、お金の貸し借りによる「信用経済」によっても生み出されるからです。
ここで、他人資本であるローンを活用した場合の不動産投資において、キャッシュフローを構成する要素を見てみましょう。
・収入(キャッシュフローを増やす)
家賃収入、礼金など
家賃収入、礼金など
・経費(キャッシュフローを減らす)
固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金、管理会社への委託管理料、退去時のリフォーム代、保険料、仲介手数料、入居者募集時の広告費、ローン返済の金利部分などの経費
固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金、管理会社への委託管理料、退去時のリフォーム代、保険料、仲介手数料、入居者募集時の広告費、ローン返済の金利部分などの経費
・その他(キャッシュフローを減らす、かつ経費にならない)
ローン返済の元本部分、所得税(法人税)・住民税
ローン返済の元本部分、所得税(法人税)・住民税
この中で、キャッシュフローに与える影響が最も大きい要素はどれでしょうか。
答えはローンの元本部分です。支払いの初期においては返済に占める利息の割合が多いため一時的に経費が多くなりますが、構成割合が常に大きいのはやはり元本です。そもそも金利は、元本がなければ発生しません。
例えば、毎月の家賃収入が9万円、経費が1万3,000円、ローンの返済が8万2,000円の新築マンションを保有している場合の収支では、月に5,000円の「持ち出し」が発生しています。8万2,000円のローン返済の影響が大きいことが見て取れるでしょう。
ローン返済や経費はムダ金か?
先ほど、キャッシュフローを構成する要素を「収入」「経費」「その他」に分け、ローンの元本が最もキャッシュフローに影響すると述べました。では、ローンの返済や経費は払うだけムダなお金でしょうか。
一つの考え方として、経費はその時だけのために使うものであり、支払い過ぎると「ムダ金」になってしまうと考えられます。しかし元本返済部分は不動産を買うためにローン期間中継続的に支払うお金です。ある時期にキャッシュフローがマイナスになったからといって、ムダ金にはなったとは言えません。
ローンの返済が終われば、通常キャッシュフローはプラスになります。例えば月5,000円のマイナスが30年続くと合計180万円の赤字ですが、完済後の家賃が5万円、経費が2万5,000円だとすると、6年間で元が取れます。後は持ち続けた分だけ累計の利益が増えていきます。
中古物件はキャッシュフローがプラスになりやすいのですが、ローン完済後に保有できる期間が短くなりやすいことには注意が必要です。特に木造アパートなどで長期のローンを組んでしまうと、完済前に取り壊しや大規模な修繕が発生し、最終的な利益がプラスにならないこともあり得ます。
新築の鉄骨鉄筋コンクリートのマンションなどは、30年ローンを組んだとしても完済後10~20年は利用できる可能性が高いでしょう。
必ずしも次のように分類できるわけではありませんが、中古物件をターゲットにプラスのキャッシュフローを条件とする不動産投資家は、現在の(あるいは近い将来の)お金のやりくりに着目していると言えます。新築物件を中心に、一時期のキャッシュフローがマイナスになることを許容する人は、ローン支払いが終わった後まで見据えて長期の資産形成を目的にしていることが多いです。
キャッシュフローの考え方は目的次第
現在のキャッシュフローと将来のキャッシュフローのどちらを重視するかは、何を目的に不動産投資をするのかによって変わるのです。あるいは、手に入れたキャッシュフローを最終的に何に使うのかによって変わるとも言えます。
新築マンションなどに投資する「マイナスのキャッシュフロー許容派(長期のキャッシュフローを重視する人)」は、老後資金を確保する目的の人がほとんどでしょう。一方、中古物件を中心に投資する「現在のキャッシュフロー重視派」は、獲得したキャッシュフローを次の物件を買うために使います。
長期的な資産形成を目的とした場合は一時的なマイナスのキャッシュフローは許容範囲ですが、物件の売買を繰り返して積極的に資産を形成しようする場合は、目先のキャッシュフローがプラスになることは必須と言えるでしょう。
一時的なキャッシュフローはマイナスでも長期的な資産形成ができればいい
不動産投資は最終的には「保有期間中の利益(あるいは損失)」と「売却した時の利益(損失)」の合算で判断する必要があります。
立地のよい都心の新築マンションは築年から10年経過しても、売却価格が下がらないケースもあります。その間、入居者さんからの家賃収入でローンの残高は減少しています。
例えば、新築時に3,000万円で購入した新築マンションが10年後にも3,000万円で売却できたとして、ローンの残債が2,300万円に減少していたとしたら700万円の利益が残ります。
例えば、新築時に3,000万円で購入した新築マンションが10年後にも3,000万円で売却できたとして、ローンの残債が2,300万円に減少していたとしたら700万円の利益が残ります。
10年間、毎月5,000円の持ち出しがあったとしても5,000×12ヵ月×10年=10年間で60万円の持ち出しです。仮に700万円の売却益があれば、トータルでプラスとなります。
逆に言えば、2,360万円より高く売却できれば、プラスの投資になります。このように10年後のリセール価格が購入価格に比べて減価しにくのは、①都心部、②新築(築浅)の2点が揃った時に実現しやすいと言えます。
逆に言えば、2,360万円より高く売却できれば、プラスの投資になります。このように10年後のリセール価格が購入価格に比べて減価しにくのは、①都心部、②新築(築浅)の2点が揃った時に実現しやすいと言えます。
同じく購入後、10年保有してリセールすることを中古マンションで考えた場合はどうでしょうか。例えば築15年の中古マンションを購入し、10年保有、その間、月1万円のキャッシュフローがあったとします。1万円×12ヵ月×10年=120万円。
ただし、10年後に売却する時は築25年です。次の購入者を考えた時、築25年の中古マンションを購入するケースでは35年ローンは組めないかもしれません。その場合、売却価格はより低下する可能性があります。
不動産投資は家賃収入で利益を得ることも一つの方法ですが、入居者からの家賃収入でローン残高を減少させ、売却価格とローン残債の差額の利益を得ることが非常に手堅い資産形成の方法の一つといえるでしょう。
その時に重要なのは「リセール価格が落ちにくい物件」を購入する事ということを覚えておきましょう。(提供:Incomepress )
その時に重要なのは「リセール価格が落ちにくい物件」を購入する事ということを覚えておきましょう。(提供:Incomepress )
小田急不動産、投資家向けに木造賃貸住宅開発
小田急不動産(東京都渋谷区)は1月27日、大型木造賃貸住宅である「ビューテラス白鳥」(神奈川県川崎市、11戸)を2019年11月に完成させたことを発表した。投資家へ売却を見込んでいる。
同物件は小田急多摩線栗平駅から徒歩8分の立地。敷地面積は1000.01m2。木造3階建てで延床面積は879.67m2。間取りは車庫付き3LDKが7戸、3LDKが3戸、2LDKが1戸で、専有面積は48.85~74.09 m2。月賃料は管理費込みで10万~14万4000円。建築は小田急沿線で主に木造住宅を建築しているグループ会社の小田急ハウジングが手がけた。
小田急不動産は小田急沿線を中心に分譲マンションや戸建てを中心に事業を展開してきたが、新たな部署を立ち上げ、賃貸住宅やオフィスビル、物流施設、ホテルといった投資用不動産の開発事業を開始。その第1弾物件が「ビューテラス白鳥」で、同物件は2~3年後に投資家に売却する予定。小田急不動産では今後も投資物件の開発を進める方針で、木造賃貸住宅についても継続的に事業化を推進し、小田急沿線を中心とした投資家に訴求する。

大ブーム!「アジア新興国」への「不動産投資」で注意すべきこと
事前にここまで調べておこう
マレーシア、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナム、香港、シンガポール……。昨今、アジア新興国への不動産投資について意見を求められることが多くなりました。
 Photo by iStock
Photo by iStock
ここで私が考える、新興国の不動産投資に対するリスク、注意点についてお伝えしたいと思います。
まずは、いわゆるカントリーリスクです。とくに共産圏において、将来的に不動産投資に関する法規制や税制が大きく変わる可能性があります。
党の指導者や政権が変わることで、私たち外国人が不利になるような規制が起こりうることも、あらかじめ想定しておくべきだと思います。
そもそも共産圏には、外国人名義で土地を買うことができない、借地しか買えないなどの規制があります。
次に税制上のリスクです。これも政権が変わることで外国人に対する税制なども大きく変わるリスクがあるということです。
ところで、新興国の不動産を保有しようとする方は、インカムゲインというより、将来的な大きな値上がりを期待していると思います。
日本では、1950年代、60年代に土地を買っていれば、数十年後には数十倍の値段になりました。新興国においても日本で起こったような、高度経済成長にともなう地価の上昇を想定しているのではないでしょうか。
そのとき考慮しなくてはならないのが、建物の維持管理費用と、保有にかかる税金(日本で言う固定資産税)です。また、将来の売却時にかかる譲渡益課税についても、事前に調べておくことが必要です。
1万円から始められる都心の中古マンションに特化した不動産投資型クラウドファンディング「RENOSY ASSET クラウドファンディング」キャピタル重視型第14号案件の募集を開始
不動産テック総合ブランド「RENOSY(リノシー)」を運営する株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ](本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:樋口 龍、証券コード:3491、以下「当社」)は、1万円から始められる都心の中古マンションに特化したクラウドファンディングサービス「RENOSY ASSET(リノシー アセット) クラウドファンディング」キャピタル重視型(※1)第14号ファンドを組成し、本日1月27日(月)15時よりサービスサイトにて出資の募集を開始いたします。
なお応募期間は、2月4日(火)正午までで、厳正なる抽選をもって出資を確定いたします。抽選結果は、2月5日(水)にご登録いただいたメールアドレスへ通知いたします。
サービスサイト:https://www.renosy.com/funding
なお応募期間は、2月4日(火)正午までで、厳正なる抽選をもって出資を確定いたします。抽選結果は、2月5日(水)にご登録いただいたメールアドレスへ通知いたします。
サービスサイト:https://www.renosy.com/funding
 <「RENOSY ASSET(リノシー アセット)クラウドファンディング キャピタル重視型 第14号ファンド」>
<「RENOSY ASSET(リノシー アセット)クラウドファンディング キャピタル重視型 第14号ファンド」>運用物件:シンシア護国寺ステーションプラザ
所在地:東京都文京区
竣工月:2001年7月
出資総額:1,560万円
募集総額:1,404万円
募集口数:1,404口
募集期間:2020年1月27日(月)15時〜2月4日(火)正午
運用期間:3ヶ月(※物件の運用状況によっては、運用期間満了予定日前に終了する場合があります。)
予定分配率:年利4%(税引前)(※投資に係るリスク等につきましては、出資頂くに際してご案内があります。)
申込手数料:なし
途中解約:可能(※但し、利益分配金は計算期間末日の出資者に支払われます。)
解約手数料:なし
◆ 「RENOSY ASSET(リノシー アセット) クラウドファンディング」 概要
リアル×テクノロジーで最先端の不動産投資を提供する「RENOSY ASSET(リノシー アセット)」が提供する、都心の中古マンションに特化した不動産投資型クラウドファンディングサービスです。1⼝1万円で、お⼀⼈様1⼝〜100⼝の範囲で出資の応募が可能です。「専門的な知識が必要」、「まとまった資金が必要」などのイメージを持つ人が少なくない投資において、少額でも参加可能で、専門的な知識を必要としない投資の選択肢を提供しています。
特徴として、当社が提供する不動産投資サービス「RENOSY ASSET マンション投資(※2)」に用いるAI技術と同様の技術を活用し、当社のクラウドファンディング専門チーム(※3)がクラウドファンディングに適した物件を厳選してファンドを組成しております。
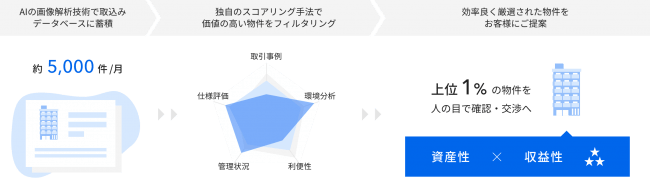 <「RENOSY ASSET(リノシー アセット) マンション投資」におけるAI活用について>
<「RENOSY ASSET(リノシー アセット) マンション投資」におけるAI活用について>また「RENOSY ASSET クラウドファンディング」は、2018年8月に東京都で第一号として小規模不動産特定共同事業の認可を受けてサービスを提供開始し、現在までに累計で17億円(※4)を超える出資の応募をいただいています。20代〜40代を中心に、投資経験自体が初めての方にも多くご利用をいただいており、より多くの方々に不動産を通じた資産運用の機会を提供しています。
 <「RENOSY ASSET (リノシー アセット)クラウドファンディング」イメージ>
<「RENOSY ASSET (リノシー アセット)クラウドファンディング」イメージ>◆ ファンディングの流れ
「RENOSY(リノシー)」に会員登録後、マイページから出資者情報を登録し、本人確認手続が完了したら成立前書面のご確認・ファンドへの出資の応募が可能となります。その後、厳正なる抽選の上、出資を確定させていただき、契約・入金手続を経てファンドの運用を開始いたします。運用期間終了後、財産管理報告書をお送りするとともに、償還日にご登録頂いた口座に分配金をお振込みいたします。

(※1)キャピタル重視型ファンドとは、入居者からの賃料収入によるインカムゲイン(運用益)のほか、物件の売却から得られるキャピタルゲイン(売却益)の2つの配当を受け取れる仕組みです。運用期間中の賃料収入と運用終了時の売却益を運用期間終了後に出資者に分配金として還元いたします。
(※2)「RENOSY ASSET マンション投資」サービスサイト:https://www.renosy.com/asset/mansion
(※3)不動産コンサルティングマスター、不動産証券化協会認定マスター、社内弁護士、公認会計士、仕入れ・売却担当、システムエンジニアで構成されるチーム
(※4)2020年1月27日時点
◆ GAテクノロジーズ 会社概要
社名:株式会社GA technologies
代表者:代表取締役社長 CEO 樋口 龍
URL:https://www.ga-tech.co.jp/
本社:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立:2013年3月
資本金:11億6102万3130円(2019年11月末日時点)
事業内容:
・不動産テック総合ブランド「RENOSY」の運営
・「BEST BASHO(ベスト場所)」や「BLUEPRINT by RENOSY」などのAIやRPAを活⽤した研究開発
・中古マンションのリノベーション設計施⼯
再開発目白押しで資産価値アップが期待。「札幌」がこれからの不動産投資に美味しい理由とは?
北海道最大の都市はいまも人口増
札幌の不動産は投資妙味あり!
札幌の不動産は投資妙味あり!
不動産投資に成否を握る、立地選び。皆さん苦心しているだろうが、今回は「人口」「開発」「資産価値」の観点で、北海道・札幌のポテンシャルを探ってみたところ、とても魅力的だとわかった。
日本では少子高齢化が本格的に進展した結果、多くの都市では人口減少が始まっているのはご存じの通り。人が減れば街の発展は行き詰まり、おのずと衰退していくばかり。
こういったエリアに収益物件を持っていると稼働率は徐々に悪くなり、資産価値も下がっていくかもしれない。入居者は入らず売ろうにも売れない……不動産投資の入り口から出口への流れが濁ってしまうわけだ。もし衰退しそうなエリアに物件を持っているなら、はやくに手を打っておきたい。
他方、東京や横浜を始めとする首都圏、東日本なら仙台、東海以西なら名古屋、大阪、広島、九州なら福岡、那覇空港の第2滑走路開通を控えリゾートホテルの建設などに沸く沖縄など一部エリアの人口は増加~横ばい~微減の状況で、大手デベロッパーの再開発プロジェクトは、これらの地域に集中。賃貸需要もまだあるので、不動産投資家もおのずと注目している。
とはいえ、首都圏の物件は価格が高く、なかなか手が出ない。では、程よい投資でリターンが期待でき、エリアの発展による資産価値増が狙えるのは、いったいどこだろうか。そのひとつが北海道最大の都市、札幌だ。

健美家では1月21日、2019年の不動産投資レポートを取り上げた。これによると、北海道は不動産妙味が高いとわかる。
■全国の利回り・価格(登録)
区分マンション:7.37%/1566万円
一棟アパート:8.88%/6501万円
一棟マンション:8.35%/1億5161万円
区分マンション:7.37%/1566万円
一棟アパート:8.88%/6501万円
一棟マンション:8.35%/1億5161万円
■首都圏と北海道の利回り・価格(登録)
▼首都圏
区分マンション:6.59%/1889万円
一棟アパート:8.45%/6956万円
一棟マンション:7.63%/1億7446万円
▼首都圏
区分マンション:6.59%/1889万円
一棟アパート:8.45%/6956万円
一棟マンション:7.63%/1億7446万円
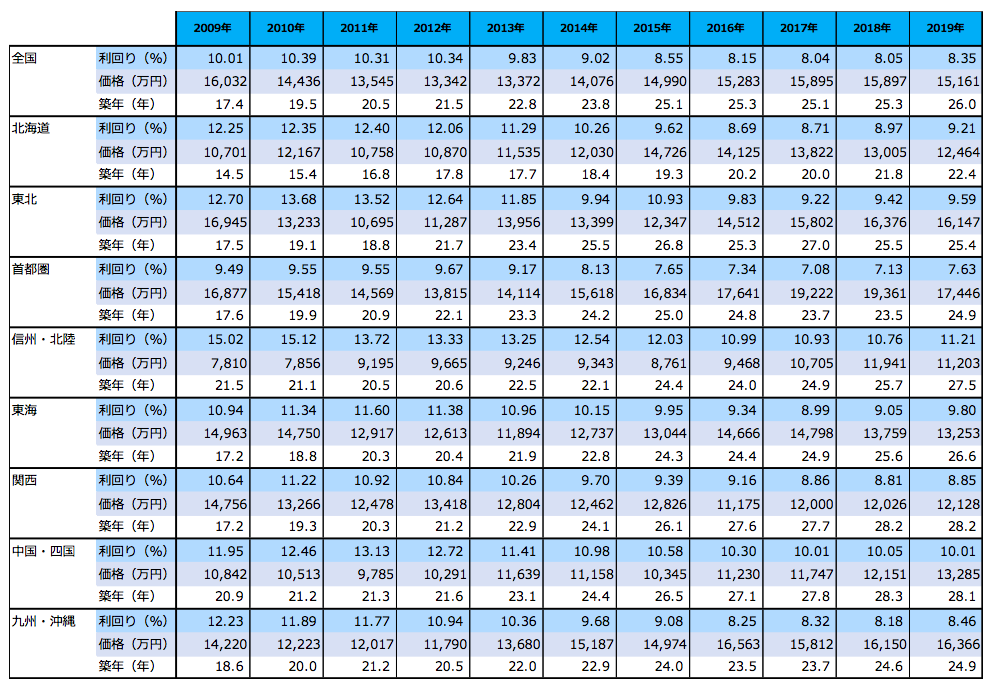
出典:健美家 収益物件 市場動向 年間レポート2019年
北海道は全国平均・首都圏に比べて物件価格が低い分、収益性は高くなるわけだ。ただ、東北や東海、関西、中国・四国は数字上のパフォーマンスは北海道より高い。
とはいえ、エリアポテンシャルを考えると、優位性は北海道、とりわけ最大の都市である札幌に軍配が上がる。背景あるのは、人口増や活発な開発、それに伴う資産価値アップが期待でき、有利に不動産投資を進められるからだ。
まずは、人口。同市は2000年に人口182万人だったのが、現在は190万人を超える規模に拡大。ビジネスや歓楽の中心地ということもあり道内から人が集まり続け、当面はこれだけの人口規模を維持する見通しだ。昨年は東京オリンピックのマラソン競技が開催されることで話題になったが、2030年には札幌冬季オリンピック・パラリンピックの誘致を進めていて、同年には北海道新幹線札幌延伸も控えている。
こういった動きに伴い札幌市は2022年度までの中期計画「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2019」の素案を昨秋に発表。ここでは、22年度に北海道外からの年観光客数を626万人(18年度)から800万人、インバウンドを272万人(同)から350万人に増やす目標を掲げている。そのための都市インフラの充実を目的に、22年度から始まる地下鉄南北線さっぽろ駅の改良工事に13億円を投入。真駒内行き専用ホームを新設して混雑を緩和する。また、標識の多言語化や無料Wi-Fiの整備にも50億円を投じるという。
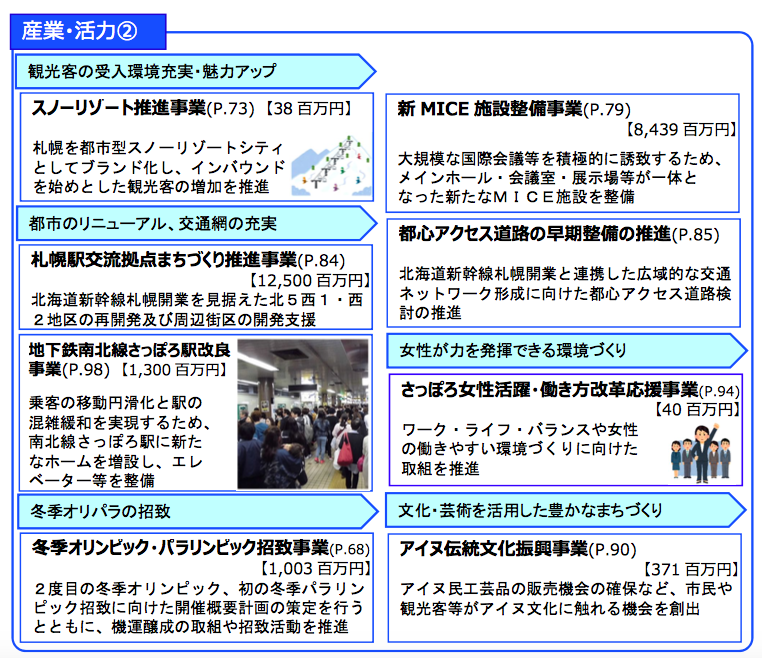
出典:札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2019(案)まとめより
再開発も目白押しだ。昨年12月の『健美家ニュース』でもお伝えしたが、札幌市とJR北海道などJR北海道グループ4社は、札幌駅に隣接する地区を開発する「札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発準備組合」を設立。ホテルやオフィス、商業施設からなる超高層ビルの開発を計画し、2029年秋の全体竣工及び供用開始を目指している。
他にも、ヨドバシカメラホールディングスは2019年11月、今後3年以内を目処に札幌に複合商業施設をオープンすると公表。西武百貨店札幌店跡地を中心とした場所に超高層ビルの建設を構想している。「札幌駅北口8・1地区第一種市街地再開発事業」や「南2条西3丁目西地区第一種市街地再開発事業」も進行中だ。「北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業」では、札幌駅の隣、JR函館本線の苗穂駅に駅直結のツインタワー分譲マンションが建つ。こういった再整備により、同市中心部はますます発展し、人口集中に拍車がかかる可能性は高い。

行政や民間による開発が多く、ますます利便性が高まりそうな札幌。これからが楽しみだ。町が発展する中で、中心部だけではなく周辺の資産価値もアップしていくに違いない。
例えば、札幌の公示地価は2000年代に入り一時落ち込み13年には9万4799円/㎡になったが、19年には13万円7418円/㎡まで回復し、6年連続で上昇。先述した健美家のレポートでも北海道の区分・一棟マンション、一棟アパートの価格は右肩上がりを描いている。
首都圏などに比べて物件価格は安く、他の地方都市に比べると人口増や発展は顕著。不動産投資のリスクとリターンのバランスが取りやすいのが札幌だ。すでに物件を持っている人はその恩恵に預かっているだろうし、これから買う人も心強いだろう。いずれにしても、札幌の進化はとどまることはない。収益物件オーナーにとって注目エリアのひとつなので、今後も注視したいところだ。
もちろん、札幌以外にも有望なエリアはあるに違いない。リサーチする際は、人口や再開発など、将来の発展を尺度にすればいいだろう。
健美家編集部(協力:大正谷成晴)
価格高騰を背景に広がる少額不動産投資。月額1万円などクラウド立ち上げ相次ぐ
個人の不動産投資家の中には、投資リテラシーが不足している人はまだまだ多い。特に投資初心にその傾向は強い。不動産事業者から電話営業などで投資マンションなどのリスクを余り意識しないまま購入している人もよく見受ける。
個々の投資家はさまざま。資産の状況であったり、ライフプランであったり。それによってワンルームを買うのがいいのか、1棟マンションを買うのがいいのか。そもそも買わないのがいいのか。これは個々でそれぞれ違うはず。そうしたことを考えずに単になんとなく儲かるとか、不労所得になるとかで買わされている。そんな投資初心者がいきなり実物物件を購入するのにも勇気がいる。
そんな中、個人が投資しやすい不動産の小口化商品が相次いでいる。投資初心者にとどまらず、不動産価格の高騰で実物不動産に投資しづらくなった個人マネーもそこに向かう。オフィスビルやマンションを区分ごとに販売したり、古民家や空き家の再生・収益化に向けてクラウドファンディングで小口投資を募る。
このような不動産投資スタイルを提案する動きは活発になっている。クラウンドファンディングで1万円や10万円などの少額で不動産投資が可能なプラットフォームが増えた。提供する側は、小口投資のため不動産を購入するときのような多額の借り入れに頼る必要がなく、建物管理の負担もかからないとPRする。

中古ワンルームマンションの販売を手掛けるパートナーズ(東京都品川区)は、昨年12月にインターネット上で完結するクラウドファンディングサービスに新たに参入し、港区高輪のワンルームマンション1区分を第1号ファンド「PARTNERS Funding」として組成・運用を始めた。1口1万円から投資できるもので、投資家保護の観点から出資総額の3割程度を同社が負担しているのが特徴だ。中古物件が毎年積み上がる中で、立地を厳選して小口化商品に仕立てる。今後もファンドを組成し、毎月5本のハイペースで小口化商品向けのファンドを立ち上げる予定だ。利回りは5~8%を目安に運用する。運用期間は短めで数カ月の設定。同社では、将来の年金不安に悩む個人向けにアピールしたいという。
空き家再生のエンジョイワークス(鎌倉市)では、築古の古民家や使われなくなった蔵などを対象に出資を募り、その資金をもとに収益物件化してそこから生まれるキャッシュフローを投資家に分配する。
廃墟となった工場は、これは、廃墟工場の元の持ち主から買い取る資金1200万円を60人超の投資から集めてシェアリングできるアトリエに再生した。さまざま物件が対象となるが、その想定利回りは定期預金や国債の金利よりも高い年利3~8%ほどとなっている。運用期間は3~4年とロングスパンで設定。余剰資金の振り向け先の受け皿ともなっている。同社では、出資者の提案や意見などを取り組みながら稼働率を上げていく手法が投資家の間では人気だという。
中古再生事業のインテリックス(東京都渋谷区)は、不動産特定共同事業法に基づく不動産投資型クラウドファンディングサービスの草分け的な存在だが、直近では1月30日から「ファンド2号(すみ蛍おぼろ)口」の募集申し込みの受付を開始する。全国各地で空き家・空き店舗が増えていることを受けてそれらを収益化するのが狙い。今回の募集は京町家を対象に行うもので3100万円を集める。最低投資額は10万円。約18カ月運用する想定利回りは4.0%を見込んでいる。
個人の所得環境の改善が不動産価格の上昇に追いつかない中で、実物直接投資とは違う新たな投資手法で個人マネーを呼び込む動きが広がりを見せている。
健美家編集部
2020年は対日不動産投資への関心増大、グローバル投資意向調査
ANREV(アジア非上場不動産投資家協会)、INREV(欧州非上場不動産投資家協会)、PREA(米国年金不動産投資協会)が1月22日に発表した「2020年グローバル投資意向調査」によると、東京はグローバル機関投資家の選ぶ不動産投資先として3位にランキングされ、回答者の56.1%がアジア太平洋地域で20年に選好する投資先都市のひとつとして東京を挙げた。日本の都市としてトップで、グローバル機関投資家がそれぞれ選好したシドニー(65.9%)とメルボルン(58.5%)に迫った。一方、欧州(83.3%)と北米(80%)の投資家も不動産資金の投下先として東京を選好、このグループでは東京が不動産投資先都市として第1位となった。
大阪は東京に次ぐ人気で、20年アジア太平洋地域で選好する不動産投資先として機関投資家の46.3%が挙げ、19年の第7位から第4位へと順位を上げた。北米の投資家は80%が大阪を選好投資先に選んで東京と首位を分け、欧州の投資家は75%が大阪を選び、シドニーと同水準の2位となった。
都市とセクターの組み合わせでは、ランキング上位10都市の中に5つの日本の都市が登場、アジア太平洋地域の投資家が注視している。日本国内の組み合わせとしては東京のレジデンスが最も人気があり、機関投資家の41.5%がアジア太平洋地域で選好する組み合わせと回答した。その他、アジア太平洋地域の選好不動産投資先としてアジアのトップ10に入った日本の都市とセクターの組み合わせでは「東京・商業および物流」、「東京・オフィス」、「大阪・レジデンス」「大阪・オフィス」が挙がった。
結果について、ANREVは「多くの投資家がアジア太平洋地域において依然ポートフォリオを構築中で多様化を進めており、日本がグローバル投資家から引き続き高い関心を集めているということを示している」と指摘。大阪の上昇は「東京の不動産市場に限らず日本の他の都市へ拡大したいという投資家の意欲をよく表している」とコメントした。
老後のための資産形成…いま「不動産投資」が推されるワケ
そもそも「老後2,000万円問題」とは?
そもそも老後2,000万円問題とはなんでしょう? 簡単に言ってしまえば、我々の老後生活費用として、年金だけだと不足しており、その不足金額が「2,000万円」だと言われています。
金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が2019年6月に公表した「高齢社会における資産形成・管理」報告書で、
・人生100年時代を迎え老後を安心して暮らしていくには、公的年金だけでは月額で5万円不足するため、公的年金以外に老後、2,000万円を貯蓄から取り崩すことが必要
・そのため、長期的なライフプランを検討し、具体的なシミュレーションを行うことが重要
・「現役期であれば長期・積立・分散投資による資産形成の検討を」行うことが重要
とされました。なお、金融庁の報告書によると老後2,000万円は以下の前提のもと算出されています。
・夫65歳、妻60歳の時点で夫婦ともに無職
・30年後(夫95歳、妻90歳)まで夫婦ともに健在
・その間の家計収支がずっと毎月5.5万円の赤字※
※総務省「家計調査」(2017年)における高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)
上記条件をもとに計算すると、
月5.5万円 × 12か月 × 30年 = 1,980万円
約2,000万円が不足という計算になります。しかし、なぜ上記の数字で計算されているのか、違和感を覚えた方もいるでしょう。上記の試算は平均の数字で算出しており、実際に老後にかかる費用は人によって様々です。
どの様な老後生活を過ごしたいか、という「目的」を前提とすると、その方の年齢や家族構成、社会保障の加入状況など細かな条件が異なる事で金額は変わり、一概に「この金額が必要」とは言い切れません。
とはいえ、多くの方が豊かな「セカンドライフ」を過ごしたいと考えるでしょう。そのための「老後資金」はどの様に作っていくべきでしょうか?
年金の不足分は、どう作ればいいのか?
老後資金の作り方は様々です。日本人の多くはリスクを負うことを嫌い、最もリスクが低い貯金をされている方がほとんどだと思います。もちろん万が一に備えて貯金して現金を持つことは重要ですが、マイナス金利の今の日本では、貯金ではお金をほとんど増やすことができないのは明白なことです。
貯金の他に「資産運用」すること、つまり「お金に働いてもらう仕組みを作る」必要があるのです。
仮に30歳の方が、定年(60歳想定)までに5,000万円の資産を形成するには、
5,000万円÷30年÷12か月=約13.8万円
毎月約14万円の預金をすれば可能です。しかし、毎月14万円の貯金をすることは、なかなかハードルが高いのではないでしょうか。
一方、資産運用をする場合は、たとえば利回り3%の商品であれば、上記同様、30年で約5,000万円の資産を形成するには、月8.6万円で可能となります。
月積立8.6万円×3%(年複利)×30年=約5,011万円
仮に上記毎月の14万円を年複利3%の商品で運用すると、約8,100万円の資産が作れます。
月積立14万円×3%(年複利)×30年=約8,160万円
つまり、資産運用をしている方と、していない方では大きな差が開くのです。

老後、お金の心配をしないように…
不動産投資が「老後のため」に適している理由とは?
資産運用商品として、株、FX、外貨預金など様々な方法がありますが、筆者のおすすめは不動産投資です。
その理由は大きく3つあります。1つ目は、不動産投資は他人資本で投資ができる商品だからです。 自身の属性を活かして、銀行から融資を受けて不動産を購入することができます。そこに第3者に賃貸を出すことによって、月々家賃収入を得ることができ、その家賃を銀行へ返済をする仕組みのため、少ない自己資金で将来の資産を構築することができます。
2つ目は、長期保有を前提としたローン完済後の「家賃収入」です。 一般的には不動産ローンの期間は大抵35年となっており、ローンを完済すると同時に、毎月の家賃収入が老後の年金代わりとして入ってきます。 たとえば、家賃が70,000円の物件を所有している場合は、年間で約75万円の年金にプラスで収入が得られます。
3つ目は、不動産はインフレ(物価上昇)に強いという事です。 インフレになった時に、円の価値は下がりますが、物価が上がるにつれて不動産や金(ゴールド)などの現物資産は連動して上がって行くため、資産の目減りや円の価値が下がるリスクに対策として合理的です。銀行に預金していても、物価上昇には連動しないため、単純にお金の価値が下がり、資産の目減りと待つだけです。 不動産投資はそういった、インフレリスクに対するリスク分散としての役割も果たせるでしょう。
「老後の年金問題」については、結論としては「その方によって異なる」と考えています。その不透明な必要資金をつくりだすには、特定の金融商品だけに偏ることなく、お互いの「性質」をしっかりと見極めたうえで、有効な対策を取って行けると良いでしょう。ポイントは、麻生大臣も言っていた「長期、分散、積立」です。そして「不動産投資」はあくまで1つの手段です。多角的な視野で資産形成を進めましょう。
2020年は更に対日不動産投資への関心が増大―投資意向調査
2020年1月22日、東京 – ANREV、INREVおよびPREAの発表した2020年グローバル投資意向調査によると、東京はグローバル機関投資家の選ぶ不動産投資先として3位にランキングされ、回答者の56.1%がアジア太平洋地域で2020年に選好する投資先都市のひとつとして東京を挙げた。日本の都市としてトップであり、グローバル機関投資家の65.9%と58.5%がそれぞれ選好したシドニーとメルボルンに迫る結果である。
一方、欧州と北米の投資家は、それぞれ83.3%、80.0%が不動産資金の投下先として東京を選好し、このグループでは東京が不動産投資先都市として第一位に選ばれた。
また大阪は、2020年アジア太平洋地域で選好する不動産投資先として機関投資家の46.3%が挙げ、2019年第7位から2020年第4位と飛躍的に順位を上げた。また、北米の投資家は80.0%が同都市を選好投資先に選んだ結果、大阪は東京と首位を分け、また欧州の投資家は75.0%が大阪を選びシドニーと同等2位となった。「その他の国内都市」は機関不動産投資家の19.5%が選好し、アジア太平洋地域の第10位に選ばれた。
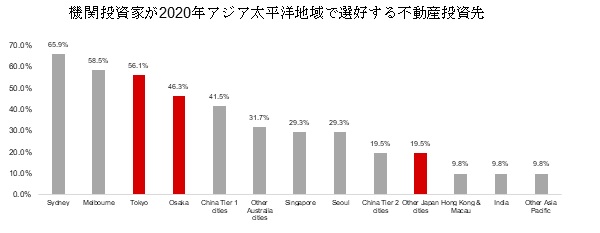
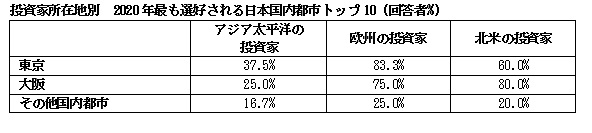 都市とセクターの組み合わせでは、ランキング上位10都市の中に5つの日本の都市が登場し、アジア太平洋地域の投資家が注視している様子が顕著に表れた。日本国内の組み合わせとしては東京のレジデンスが最も人気があり、機関投資家の41.5%がアジア太平洋地域で選好する組み合わせであると回答した。その他、2020年アジア太平洋地域の選好不動産投資先としてアジアトップ10に入った日本の都市・セクターの組み合わせには、東京・商業および物流、東京・オフィス、大阪・レジデンス、大阪・オフィスが挙がった。
都市とセクターの組み合わせでは、ランキング上位10都市の中に5つの日本の都市が登場し、アジア太平洋地域の投資家が注視している様子が顕著に表れた。日本国内の組み合わせとしては東京のレジデンスが最も人気があり、機関投資家の41.5%がアジア太平洋地域で選好する組み合わせであると回答した。その他、2020年アジア太平洋地域の選好不動産投資先としてアジアトップ10に入った日本の都市・セクターの組み合わせには、東京・商業および物流、東京・オフィス、大阪・レジデンス、大阪・オフィスが挙がった。
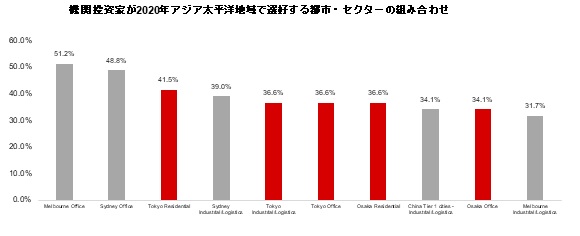 ANREVリサーチおよびプロフェッショナルスタンダード担当ダイレクターのエメリー・デュルネは、「今年の調査で日本が上位にランクインしたことは、多くの投資家がアジア太平洋地域において依然ポートフォリオを構築中で多様化を進めており、日本がグローバル投資家から引き続き高い関心を集めているということを示しています。大阪の上昇は、東京の不動産市場に限らず日本の他の都市へ拡大したいという投資家の意欲をよく表しています」と話す。
ANREVリサーチおよびプロフェッショナルスタンダード担当ダイレクターのエメリー・デュルネは、「今年の調査で日本が上位にランクインしたことは、多くの投資家がアジア太平洋地域において依然ポートフォリオを構築中で多様化を進めており、日本がグローバル投資家から引き続き高い関心を集めているということを示しています。大阪の上昇は、東京の不動産市場に限らず日本の他の都市へ拡大したいという投資家の意欲をよく表しています」と話す。
グローバル全体の結果
グローバル全体では、機関投資家が引き続きアジア太平洋地域におけるバリューアデッド型投資が、同地域内で最も高いリスク調整後パフォーマンス予想を提供すると考えている (44.3% - 昨年と同じ)。しかし、アジア太平洋地域の投資家は、同地域について依然コア型を選好し(47.8%)、北米の投資家の43.8%はオポチュニティ型、欧州の投資家の50%はバリューアデッド型を志向している。
グローバルの不動産は平均で機関投資家のポートフォリオの10.4%を占めており、目標配分値は11.4%でこの資産クラスに対する安定的な関心が継続することを示しており、引き続きこの割合は上昇すると予想される。さらに、63%以上の機関投資家が、今後2年間で自社ポートフォリオにおける不動産の割合は上昇すると予想している。
これらの結果から、低金利・低収益が続く環境のもと、投資家が依然資本活用と高リターン達成のために新たな方法を模索していることがうかがえる。また、2019年には平均で不動産AUM総額の12%以上がオポチュニティ型戦略に投資されており前年比でほぼ50%の上昇、投資家は引き続き一定のトレンドに沿って行動している。
2020年、世界規模で不動産投資に向けられる資金の31.9%がアジア太平洋地域に注入される見込みであり、これは2019年に比較して19.6%の大幅増。この大部分 (83.5%) はアジア太平洋地域の投資家に由来しており。昨年の調査の回答から52.4%増と大幅に拡大している。
アジア太平洋不動産市場への投資経路としては、調査回答した投資家の58.3%以上が非上場ファンドを通じた投資配分の拡大を予定しており、引き続き同経路が最も選好される同地域への投資ルートとなっている。
– 以上 –
注意事項
2020年投資意向調査について
投資意向調査は、2020年不動産投資業界で予想される傾向について分析し、非上場不動産ファンドに焦点を当てて以後2年間の投資方針を調査するものです。
本調査はINREV、ANREVおよびPREAの合同プロジェクトであり、全世界をカバーするグローバルな視点を提供しています。調査結果は毎年1月に発表されます。
今回の調査は、140社(投資機関125社およびファンズオブファンズ運用機関15社)の回答に基づいており、そのうち投資機関89社とファンド12社はアジア太平洋地域で既に投資を行っているか、今後投資を希望しています。
ANREVについて
ANREVは、香港を拠点とする非営利団体、アジア非上場不動産投資家協会の略称です。機関投資家を筆頭とするANREVメンバーは、非上場不動産マーケット情報の透明性とアクセスの向上、専門性とベストプラクティスの推進及び知識の共有・普及に注力しています。その他メンバーにはファンドマネージャー、投資銀行、弁護士事務所やアドバイザリーが含まれ、アジアの非上場不動産投資ファンドにかかる諸問題への助言を提供し、その活動を支援しています。
ANREV は欧州INREV の姉妹団体であり、アジア太平洋および北米全域において、リサーチ、ベストプラクティスの領域に関し多くの関連組織と提携し、グローバルな情報を提供しています。http://www.anrev.org
INREVについて
INREV(欧州非上場不動産投資家協会)は、拡大する非上場不動産ビークル業界の投資家その他市場参加者のためのフォーラムとして2003年5月に設立されました。本協会は総額2兆8千億ユーロの産業を代表しその声となる役割を果たし、INREVメンバー企業は欧州の実体経済に景気対策として3,850億ユーロを注入しています。
INREV は447の会員から成り立ち、そのなかには機関投資家大手84社と、不動産ファンド運用会社大手50社のうち40社、その他欧州その他の地域にわたる銀行や顧問会社などが含まれています。
非営利団体として、非上場ビークルの透明性・アクセス性の向上、専門性とベストプラクティスの促進、知識の共有などに注力しており、オランダ・アムステルダムを拠点としています。
PREAについて
1979年に設立された米国年金不動産投資協会 (PREA) は、国際不動産機関投資家業界の非営利業界団体です。現在PREAは米国、カナダ、欧州およびアジアに700社以上の法人会員を有しています。同協会の会員には、公共・法人年金基金、寄付基金、財団、タフト・ハートリー基金、保険会社、投資顧問会社、REIT、デベロッパー、不動産運用会社、業界サービスプロバイダーなどが含まれます。http://www.prea.org
一方、欧州と北米の投資家は、それぞれ83.3%、80.0%が不動産資金の投下先として東京を選好し、このグループでは東京が不動産投資先都市として第一位に選ばれた。
また大阪は、2020年アジア太平洋地域で選好する不動産投資先として機関投資家の46.3%が挙げ、2019年第7位から2020年第4位と飛躍的に順位を上げた。また、北米の投資家は80.0%が同都市を選好投資先に選んだ結果、大阪は東京と首位を分け、また欧州の投資家は75.0%が大阪を選びシドニーと同等2位となった。「その他の国内都市」は機関不動産投資家の19.5%が選好し、アジア太平洋地域の第10位に選ばれた。
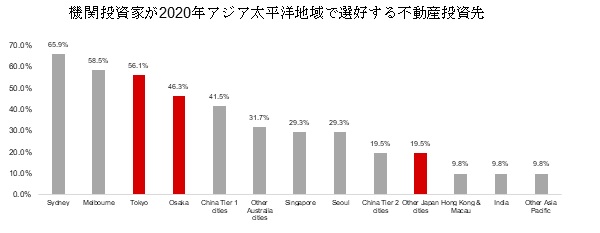
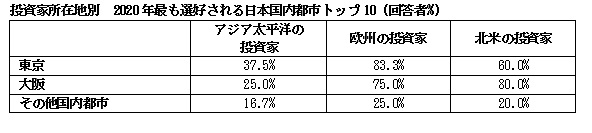
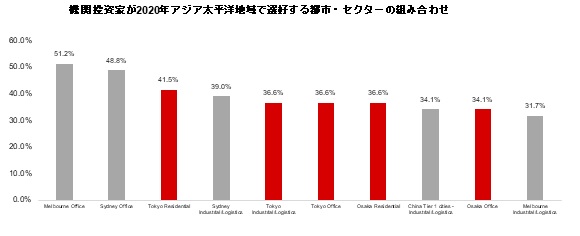
グローバル全体の結果
グローバル全体では、機関投資家が引き続きアジア太平洋地域におけるバリューアデッド型投資が、同地域内で最も高いリスク調整後パフォーマンス予想を提供すると考えている (44.3% - 昨年と同じ)。しかし、アジア太平洋地域の投資家は、同地域について依然コア型を選好し(47.8%)、北米の投資家の43.8%はオポチュニティ型、欧州の投資家の50%はバリューアデッド型を志向している。
グローバルの不動産は平均で機関投資家のポートフォリオの10.4%を占めており、目標配分値は11.4%でこの資産クラスに対する安定的な関心が継続することを示しており、引き続きこの割合は上昇すると予想される。さらに、63%以上の機関投資家が、今後2年間で自社ポートフォリオにおける不動産の割合は上昇すると予想している。
これらの結果から、低金利・低収益が続く環境のもと、投資家が依然資本活用と高リターン達成のために新たな方法を模索していることがうかがえる。また、2019年には平均で不動産AUM総額の12%以上がオポチュニティ型戦略に投資されており前年比でほぼ50%の上昇、投資家は引き続き一定のトレンドに沿って行動している。
2020年、世界規模で不動産投資に向けられる資金の31.9%がアジア太平洋地域に注入される見込みであり、これは2019年に比較して19.6%の大幅増。この大部分 (83.5%) はアジア太平洋地域の投資家に由来しており。昨年の調査の回答から52.4%増と大幅に拡大している。
アジア太平洋不動産市場への投資経路としては、調査回答した投資家の58.3%以上が非上場ファンドを通じた投資配分の拡大を予定しており、引き続き同経路が最も選好される同地域への投資ルートとなっている。
– 以上 –
注意事項
2020年投資意向調査について
投資意向調査は、2020年不動産投資業界で予想される傾向について分析し、非上場不動産ファンドに焦点を当てて以後2年間の投資方針を調査するものです。
本調査はINREV、ANREVおよびPREAの合同プロジェクトであり、全世界をカバーするグローバルな視点を提供しています。調査結果は毎年1月に発表されます。
今回の調査は、140社(投資機関125社およびファンズオブファンズ運用機関15社)の回答に基づいており、そのうち投資機関89社とファンド12社はアジア太平洋地域で既に投資を行っているか、今後投資を希望しています。
ANREVについて
ANREVは、香港を拠点とする非営利団体、アジア非上場不動産投資家協会の略称です。機関投資家を筆頭とするANREVメンバーは、非上場不動産マーケット情報の透明性とアクセスの向上、専門性とベストプラクティスの推進及び知識の共有・普及に注力しています。その他メンバーにはファンドマネージャー、投資銀行、弁護士事務所やアドバイザリーが含まれ、アジアの非上場不動産投資ファンドにかかる諸問題への助言を提供し、その活動を支援しています。
ANREV は欧州INREV の姉妹団体であり、アジア太平洋および北米全域において、リサーチ、ベストプラクティスの領域に関し多くの関連組織と提携し、グローバルな情報を提供しています。http://www.anrev.org
INREVについて
INREV(欧州非上場不動産投資家協会)は、拡大する非上場不動産ビークル業界の投資家その他市場参加者のためのフォーラムとして2003年5月に設立されました。本協会は総額2兆8千億ユーロの産業を代表しその声となる役割を果たし、INREVメンバー企業は欧州の実体経済に景気対策として3,850億ユーロを注入しています。
INREV は447の会員から成り立ち、そのなかには機関投資家大手84社と、不動産ファンド運用会社大手50社のうち40社、その他欧州その他の地域にわたる銀行や顧問会社などが含まれています。
非営利団体として、非上場ビークルの透明性・アクセス性の向上、専門性とベストプラクティスの促進、知識の共有などに注力しており、オランダ・アムステルダムを拠点としています。
PREAについて
1979年に設立された米国年金不動産投資協会 (PREA) は、国際不動産機関投資家業界の非営利業界団体です。現在PREAは米国、カナダ、欧州およびアジアに700社以上の法人会員を有しています。同協会の会員には、公共・法人年金基金、寄付基金、財団、タフト・ハートリー基金、保険会社、投資顧問会社、REIT、デベロッパー、不動産運用会社、業界サービスプロバイダーなどが含まれます。http://www.prea.org
不動産投資は未来にも過去にも行ける「タイムマシン」
ネット上で「借金の本質とはタイムマシンである」という投稿を見つけました。お金を借りることによって、将来手に入るものを今手に入れられる。お金を使って未来に行くことができると言うわけです。
私が実践している銀行からの借入を使った国内不動産投資は、まさにこの未来に行けるタイムマシンです。
現金を投資信託などでコツコツと積み立てて、ある程度の金額が貯まってから不動産を購入しようとすると、積立している間に時間が経ってしまいます。
お金を借りることによって、将来手に入る不動産を、今すぐに手に入れることが出来ます。
その不動産を使って家賃を稼ぎながら、借りたお金をその中から返済すればよいのです。
お金を貯めて現金で不動産を買うよりも、その方がスピード感があり効率的です。
このように、国内の不動産は未来に行けるタイムマシンですが、一方で、新興国の不動産は、未来ではなく過去に行けるタイムマシンです。
カンボジア(写真)、ベトナムといったアジアの新興国に行くと、日本の昭和の風情が残っています。経済成長し「明日は今日より良くなる」と上を向いて歩いている明るい人たちがたくさんいます。日本の高度経済成長を思い出させます。
このような新興国の不動産投資は、数十年前の日本で不動産を購入するのと同じです。タイムマシンで過去に戻ることができるという訳です。
もし、数十年前の東京に戻れたら、銀座や六本木の一等地の不動産を買いまくると思います。
それと同じように、東南アジアの新興国であれば、中心都市の一等地の不動産を今でも1000万円程度で購入することができるのです。
このように不動産は、国内でお金を借りることによって未来に、新興国で投資することで過去にタイムスリップすることができます。
今週末は資産運用EXPOで、そして来週月曜日は名古屋での講演があります。タイムマシンの使い方を説明したいと思います。
■ 毎週金曜日夕方に配信している無料のメールマガジン「資産デザイン研究所メール」。メールアドレスとお名前を登録するだけで、お金の不安を解消するための具体的な方法をご紹介します。
■ 「初めての人のための99%成功する不動産投資」、シリーズ累計30万部を超えた「初めての人のための資産運用ガイド」など、今までに出版された書籍の一覧はこちらから。
※内藤忍、及び株式会社資産デザイン研究所、株式会社資産デザイン・ソリューションズは、国内外の不動産、実物資産のご紹介、資産配分などの投資アドバイスは行いますが、金融商品の個別銘柄の勧誘・推奨などの投資助言行為は一切行っておりません。また、投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。
※このブログは「内藤忍の公式ブログ」2020年1月22日の記事から転載したものです。オリジナル原稿を読みたい方は内藤忍の公式ブログをご覧ください。不動産投資VS株式投資。メリット・デメリット、資産形成どちらが有利か。
2020年の株式市場は波乱の幕開けだった。米国がイランの軍司令官を暗殺し、その報復としてイラクに駐屯する米軍にイランが十数発のミサイルを撃ち込んだ。1月8日の日経平均は600円以上の下げ幅を見せて、昨年末の株高に伴う2020年への期待に冷水を浴びせた。
その後は、米イランの双方の応酬の本質を見て戦争を望んでいない、との判断が広がり株式市場は落ち着きを見せている。
このように株式投資には、企業業績の良しあしだけでなく、経済環境に直結するような外的要因により大きく変動する。政治・経済が安定していても、世界のどこかで起こった紛争・戦争で一気に儲けが吹っ飛ぶ世界でもある。儲けが吹き飛ぶだけでなく大きく元本割れに陥り資産が毀損する。
一方で金融資産を2倍、3倍に増やすことができる魅力もある。住宅・不動産の総合専門紙を発行する週刊住宅タイムズで編集長の中野淳氏は、「奇をてらった投資を勧めるわけではないが、株価の急伸で思わぬ利益を手にすることもある。知り合いの個人投資家は、過去に不動産ファンドや不動産の流動化を主力とする新興不動産会社の株の急伸により投下資金を短期に3倍ほどに膨らませた。3カ月ほどで1株1万円台の株価が8万円台まで上がった例もある」と話す。
株価の形成には様々な思惑が絡み合っている。施工不良問題で揺れているレオパレス21の株価が昨年12月末に上昇していた背景には、大株主である著名投資家が現経営陣の総退陣を求める臨時株主総会の提案をしていたことが影響している。
もちろん、株式投資は、経済環境や企業業績などを見て地道に投資するのが王道だ。長谷工コーポレーションの株価を見ると、2011年10月6日の安値220円から、足もとでは1400円台になっている。
リーマン・ショック後は50円ほどにまで沈んでいた。先見の明のある投資家は今ごろ一定水準以上の金融資産を築き上げていることになる。
そうした中で不動産投資と株式投資の魅力やリスクを探ってみる。年金だけに頼れない多くの国民にとって資産形成は老後を豊かに生き延びるために欠かせなくなってきた。
不動産投資では、アパートやマンションを購入して入居者からの賃料を収入として得るケースが一般的だ。保有する棟数や戸数が多くて満室稼働ならばホクホク顔となるが、一転空室が増えると収益物件を購入するために銀行から借り入れた資金の返済に窮することになる。
ただ、株式投資と比較した際の魅力について、多くの不動産投資家は、「不動産が紙くずになることはない」ということを口にする。景気の悪化や海外発のリスクが顕在化しても入居者がいる限り安定した収入が期待できるためだ。「たとえ巨大地震が発生して建物が倒壊したとしても土地は残る」とも強調する。
小さな不動産会社を経営する70代の男性は、「景気悪化に対する耐用力だけにとどまらない。好景気により物価が上昇した場合には不動産がインフレヘッジにもなる」と指摘する。
人口の本格減少が始まり、賃貸住宅市場に冬の時代が訪れる……。そう指摘する専門家は少なくないが、不動産投資に特化する富士企画(東京都新宿区)の新川義忠社長は、「それは物件や大家しだい。新築でなくても、都心部でなくても満室稼働にしている賃貸オーナーは多い。例えば、千葉や埼玉、群馬、栃木、茨城であっても90%稼働はめずしくはない。築20年、30年でも地域に相応した賃料を徴収することも可能である」と強調する。
不動産ではレバレッジ投資ができることも強みだ。2~3割の頭金を入れて銀行から多額の融資を引き出して収益物件を購入できる。
ただ、不動産のデメリットとしては流動性の低さが挙げられる。つまり、おカネがいざ必要になって物件を売って現金化したくても思うようなスピード感で換金できない。売れずにそのまま換金できない恐れもある。
その流動性の点では株式投資のほうが間違いなく格段に優れている。不動産取引よりも売買の透明性が高い、という信頼性の面でも株式投資に軍配が上がる。不動産投資は資金力のあるなしに大きく左右される部分が大きいが、株投資は少額で始められる手軽さも売りとなっている。
今年の株式市場の見通しについて、RIA JAPANおカネ学株式会社の代表で日経CNBC「朝エクスプレス」のコメンテーターである安東隆司氏は、「足もとで将来が計りづらい状況になっている。米中貿易摩擦や中東問題、英国のブレグジット問題などの国際情勢、世界規模で予想できない自然災害や地震発生の懸念もある。だが、今年の米国市場では11月3日の米大統領選挙に向けて景気を維持して株価を上げる方向だろう。株式市場は底堅く成長する1年が基本シナリオだが、10%程度の下落基調もサブシナリオとしてあり得る」と話す。また、資産運用の方法としてインデックスに投資するパッシブ型が拡大していると強調する。
パッシブ型投資の資産運用額は認知度を高めて国内投資信託市場で50兆円を上回っており、その商品数は膨大だが、「積み立てNISAやイデコ、確定拠出など非課税制度を一般サラリーマン世帯は活用してほしい」とアドバイスする。
日本株の世界の時価総額に占める割合は7~8%に過ぎないが、日本人投資家は日本株中心に資金を振り向けているとも指摘。世界の投資家のグローバル投資とは違う日本の投資はガラパゴス化しているとポートフォリオの改善余地を提案している。
不動産投資と株式投資。それぞれにメリットとデメリットが併存する。双方の専門家の見方を聞くと、将来安心して生活するために老後の転ばぬ先の杖として、不動産投資にすべきか、株式投資にすべきかと悩みもするものの、どちらかへとバイアスをかける必要はない。
金融・不動産の双方を組み込んでもいい。年齢や家族構成、収入など様々だ。年金や医療費など社会保障費が削られていく中で、これまで投資とは縁遠かった人も投資家脳を育てていくことが必要な時代になっている。
健美家編集部
不動産投資物件の現地確認のポイント
不動産投資を始めようと考えたとき、「何から始めればいいの?」という疑問を持つ方もたくさんいるのではないでしょうか。ここで大切なのは、「現地を自分の目で確かめる」ということです。そうはいっても、実際に購入検討中の物件を確認するにあたって注意すべきポイントは意外と分からないものです。そこで、今回は投資物件の現地確認を行う際、確実に押さえておきたいポイントをおさらいしていきます。
■購入する物件は現地で必ず確認を

(画像=SOU EXAM編集部)
記事を読まれている方の中には、これから不動産投資を始めていこうと考えている方や、あるいはすでに数棟の投資用物件を保有している方もいるかもしれません。不動産会社から数多くの投資物件の提案を受けている方にとって、「いかに自分の資産を効果的に運用するのか」という部分は外せない事項でしょう。
また、利回りや築年数、入居率などの情報には特段興味を惹かれているのではないでしょうか。しかし、ここで忘れてはならないポイントがあります。それは、これから購入しようとしている不動産は、不労所得を生み出してくれる有形の資産であると同時に、「実際に人が住み、日常生活を送るための住居」であるという点です。
したがって、「人が住むのに適した環境なのかどうか」という点を確認するためにも、実際の物件はもちろん、物件周辺の状況も、「自らの足で歩いて」チェックする必要があるといえます。
3つの確認ポイント
それでは、購入検討中の物件を実際に確認するにあたって、どのような点に気を付ければいいのでしょうか?今回は、3つのポイントをご紹介したいと思います。
●駅からの距離や周辺環境
賃貸マンションを借りる人の多くは、通勤や通学で駅を利用するケースが多いと考えられます。特に都内に勤務先や学校がある場合、「駅からの徒歩分数」は非常に重要です。購入予定の物件の「最寄り駅は何駅で、何線が通っているのか」といった情報を事前にリサーチしておくのはもちろん、現地確認の際には、実際に駅から物件までの道のりを歩いてみましょう。
上り坂が多かったり信号が多かったりすると、資料上の徒歩分数よりも駅までの距離が遠くに感じてしまうこともあります。そのため、物件の周辺環境も注意して観察しておくことが必要です。駅と物件の道中にコンビニやスーパーなどがあれば生活利便性が高いといえます。また、ファミリー層向けの物件では、周辺に公園や商業施設などがあれば、物件としての魅力も増すでしょう。
●建物に欠陥はないか
物件の質自体が疑われるような場合は、賃貸物件を探している人にとっても入居をためらわせる原因の一つになります。その最たる例が、クラックやタイルのはがれ落ちなどです。クラックと呼ばれる、コンクリートやモルタルに発生する亀裂が随所にみられる物件では、部屋内への雨水の侵入が懸念されますし、建物の強度を低下させる原因の一つにもなります。タイルがはがれ落ちているような場合も同様です。
●共用部は魅力的か
住む人の目に「共用部は魅力的に映るのかどうか」という点も重要です。デザイン性に優れたマンションの共用部は人々のあこがれの的になります。また、宅配ボックスやオートロックなど、生活利便性を高める機能がたくさん取り入れられたマンションは、人々に選ばれやすい傾向です。
現地確認は「入居者にとって魅力的か」という視点を大事に
不動産投資を検討するにあたって現地確認をしっかりと行うことは、不動産会社から提供される資料からだけでは読み解けない多くの情報を入手することにつながります。紹介したポイントを抑えつつ、「入居者にとって魅力的な物件かどうか」という視点を失わないように現地確認を行いましょう。(提供:ユニバーサルトラスト)
不動産の売却で利益は出せる?売却後に後悔しない7つのポイント
不動産を希望価格で売却するためには、不動産の管理状態や売却のタイミングが重要な要素になってきます。また、不動産単体の査定評価だけでなく立地なども価格には影響してきます。その他に、どのような点に注意して売却すれば、より多くの売却益を得ることができるのでしょうか。
この記事では、不動産を売却して利益を出すために考慮しておきたい大切なポイントを、7つご紹介します。
目次
- 不動産売却の戦略は購入時から検討することが大切
1-1.物件の立地は入居者が部屋を決める際の重要項目
1-2.購入した物件の家賃設定は慎重に行う - 不動産の運用中は管理状態にも注意する
- 不動産売却の流れを知り、戦略を立てる
3-1.不動産売却の一般的な流れ
3-2.不動産の売出価格と売却価格の違い - 空室を埋めて入居率を高めておく
4-1.物件の家賃を周辺相場と合わせて空室を埋める
4-2.物件の周辺環境から入居者のターゲットを絞る - 金融機関の状況に合わせて売却活動を進める
5-1.金融機関の融資額から売却価格を設定する
5-2.不動産ローンの残債と売却益を試算する - 売却のタイミングを逃さないために目標額を設定する
- 売却を依頼する不動産会社の選び方
7-1.不動産売却だけでなく、仲介実績が多い不動産会社を選ぶ
7-2.不動産一括査定サイトを利用する - まとめ
1.不動産売却の戦略は購入時から検討することが大切
不動産売却で売却益(キャピタルゲイン)を狙うには、購入時の物件選びが重要です。不動産の購入時にはどのような点がポイントになってくるのでしょうか。確認してみましょう。
1-1.物件の立地は入居者が部屋を決める際の重要項目
不動産の立地は入居者が部屋を選ぶ際にどれくらい重要視されているのでしょうか。以下の表はリクルート住まいカンパニーが発表した資料から引用したものです。こちらの表では賃貸契約した人が部屋を探す際に、決め手にした項目とやむを得ずあきらめた項目を確認するこができます。
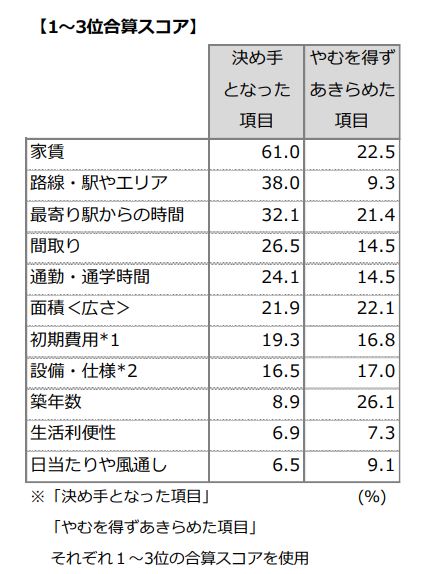 *リクルート住まいカンパニープレスリリース「2018年度 賃貸契約者動向調査」から引用
*リクルート住まいカンパニープレスリリース「2018年度 賃貸契約者動向調査」から引用
調査結果から家賃に次いで、路線や駅からの距離、通勤時間などの立地が部屋を決める際の重要な項目だということが確認できます。特に「路線・駅やエリア」は部屋を決める際に重要視されていることが分かります。
このような入居者の希望は物件の入居率に影響を与えます。立地条件は購入後には変更できないポイントなので、購入前に慎重に検討する必要があります。
1-2.購入した物件の家賃設定は慎重に行う
収益物件の売却では、家賃収入が売却の際の査定価格に影響します。家賃が査定価格に影響する理由について見てみましょう。
査定価格を机上で査定する場合、計算方法には原価法、取引事例比較法、収益還元法の3種類があります。投資用の不動産の場合は一般的に収益還元法が用いられます。下記は収益還元法の計算式です。
物件価格=(年間家賃収入‐経費)÷還元利回り(周辺相場から設定)
収益還元法を使って物件価格を算出する場合は、家賃収入が多く、周辺の還元利回り相場が高いほど物件価格も比例して高く査定されることが確認できます。
このように家賃は売却の際の査定価格に影響します。家賃は入居率のバランスをとりながら、慎重に設定する必要があります。
2.不動産の運用中は管理状態にも注意する
不動産の売却を考える上では、管理状態にも注意しなければいけません。不動産の管理が入居率に影響を与えるためです。特にマンション投資の場合には、所有する部屋だけでなく、物件全体の管理にも目を配るのが良いでしょう。
マンション投資の場合、室内の管理だけでなくマンション全体の管理状態も入居率に影響してきます。エントランスやポスト周辺が汚れていたり、損壊していたりすれば、入居率が下がる可能性が高くなります。入居率が下がれば収益が下がり、物件の売出価格も低く査定されることが多くなります。
このように、物件管理は所有する部屋だけでなく、物件全体の管理に目を配ることが入居率を保つために重要です。
3.不動産売却の流れを知り、戦略を立てる
不動産売却の際はどのような流れになるのかを確認してみましょう。
3-1.不動産売却の一般的な流れ
不動産売却は、一般的に下記の流れで行います。
- 不動産会社に査定依頼
- 物件の売出価格を設定
- 媒介契約の締結(売り出し開始)
- 買主からの問い合わせ
- 売却価格や引き渡し日、その他条件の調整
- 売買契約
- 引き渡し
上記の不動産売却の流れからわかる通り、不動産の査定依頼をした後にも様々な手続きや判断が必要になります。スムーズな売却活動を行うために、全体の流れを把握しておくことも重要です。
3-2.不動産の売出価格と売却価格の違い
不動産の売出価格は、物件の査定査定金額をもとに設定されます。不動産の売却では、この売出価格と実際の売却価格に大きな差が出ることがあります。買主側からの指値(減額)交渉により、売出価格から減額されるケースがあるためです。
希望価格で不動産を売却するためには売出価格と売却価格の違いを理解し、売出価格を現実的な売却額から少し高めに設定するなど、指値交渉に備えておくことが大切です。
4.空室を埋めて入居率を高めておく
投資物件の入居率を高い水準で保っておくことは、売却時の査定でも重要な指標です。空室を埋めるために、どのような点に注意すべきか確認しましょう。
4-1.物件の家賃を周辺相場と合わせて空室を埋める
空室が多い場合、家賃の高さが空室の原因になっていることがあります。同条件の物件と比べて相場より家賃が高ければ、入居率の低下につながります。そのため、家賃相場は必ず確認するようにしましょう。
また、相場より家賃が低すぎると収益性が下がり、物件の査定価格が低くなります。入居率と家賃設定はバランスを取りながら検討することが大切です。
4-2.物件の周辺環境から入居者のターゲットを絞る
空室になる要因として入居者のターゲットが絞れていない、ということも考えられます。例えば、周辺に大学などがないのに学生向けの内装やデザインになっていたり、大学が多い地域で社会人向けの内装にしている、という場合は、入居率が悪くなる可能性があるでしょう。
以下の図は、リクルート住まいカンパニーがプレスリリースした資料から引用したものです。こちらの調査では、一人暮らしの性別や年齢、職業によって今後住み替える場合に、6畳+バストイレ一緒と6畳+シャワーブース+トイレのタイプではどちらが好まれているかを確認することができます。
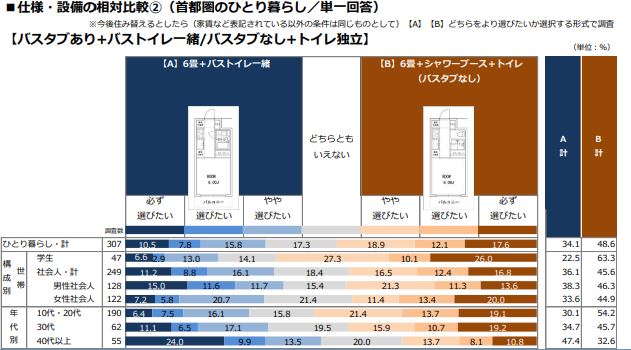 *リクルート住まいカンパニープレスリリース「2018年度 賃貸契約者動向調査」から引用
*リクルート住まいカンパニープレスリリース「2018年度 賃貸契約者動向調査」から引用
こちらの表から単身者の年代別を見ると10代、20代ではバスタブがなくても、シャワーブースとトイレが別になっているタイプを必ず選びたいという層が19.1%あるのに対し、40代以上は10.8%に減少。逆にバストイレ一緒でバスタブがあるタイプを選ぶ人が24.0%と、40歳代では最も多い割合を占めていることがわかります。
このように、年齢や性別によって選びたい物件のタイプが異なることが確認できます。空室を減らすには、周辺環境を調査し、入居者のターゲットを絞り込んで内装を考えたり、募集をしたりすることが重要になってきます。
5.金融機関の状況に合わせて売却活動を進める
物件の価格と買主の準備できる資金が相違すると、売却が長期化してしまう可能性が高まります。物件の価格や融資額について、どのように判断すれば良いのかを見てみましょう。
5-1.金融機関の融資額から売却価格を設定する
不動産を購入する買主は、金融機関の融資を受けるのが一般的です。そのため、不動産を1,800万円で売却したいと思っても、金融機関の評価により1,000万円が融資上限となった場合、買主は融資以外に800万円以上の資金を準備することになります。
このように売りに出す価格と金融機関の融資する金額が大きく異なると、買主が資金を準備できず、物件の売却は長期化する傾向にあります。計画的に売却を進めるために、売却予定の不動産が金融機関でどのような評価をされるのかを確認しておくことが大切です。
5-2.不動産ローンの残債と売却益を試算する
金融機関の抵当に入っている不動産を売却するには、売却時にローンの残債を完済しなければいけません。そのため、売却する価格から残債を完済できるかどうか、仲介手数料や税金などを支払えるか、試算しながら物件の希望売却価格を設定することが大切です。
6.売却のタイミングを逃さないために目標額を設定する
売却のタイミングを逃さないためには、利益の目標額を決めて、その金額に達したら売却を実行するという決断も必要になります。不動産の売却には買主側の融資状況によって2~3ヶ月の期間がかかることがあるうえ、金融機関の融資条件が変更されるなど、売却が途中で崩れてしまう可能性もあります。このような売却期間の長期化を避けるために、売却の目標額を定めておき、できるだけ素早い売却の決断をすることも大切です。
7.売却を依頼する不動産会社の選び方
不動産売却の際は仲介する不動産会社の選び方も重要です。どのような点に注意して不動産会社を選べば良いのかを見てみましょう。
7-1.不動産売却だけでなく、仲介実績が多い不動産会社を選ぶ
不動産会社の中には、仲介手数料だけでなく買取再販による売却益をメインにした会社があります。不動産の買取は早く現金化できるというメリットがありますが、不動産会社の利益が入るため、仲介よりも売却価格が下がってしまうデメリットがあります。
できるだけ高く不動産を売却し、利益を得るためには不動産仲介をメインとした会社を選ぶ方が良いでしょう。不動産会社を選ぶ際は、仲介実績を確認したり、複数社の担当者と話をしたりして判断するようにしましょう。
7-2.不動産一括査定サイトを利用する
複数の不動産会社に手軽に査定を依頼する方法として、不動産一括査定サイトを利用するという方法を検討するのも良いでしょう。複数の会社とやり取りを進めながら、効率的に信用できる不動産会社を探すことが可能です。
主な不動産一括サイト
| サイト名 | 運営会社 | 特徴 |
|---|---|---|
| すまいValue | 不動産仲介大手6社による共同運営 | 査定は業界をリードする6社のみ。全国870店舗。利用者の96.7%が「トラブルなく安心・安全に取引できた」と回答 |
| リガイド(RE-Guide) | 株式会社ウェイブダッシュ | 登録会社数700社、最大10社から査定を受け取れる。収益物件情報を掲載する姉妹サイトも運営、他サイトと比べて投資用マンションや投資用アパートの売却に強みあり |
| HOME4U | 株式会社NTTデータ スマートソーシング | 全国900社から6社まで依頼可能。独自審査で悪徳会社を排除 |
まとめ
不動産を売却する際に、利益を出すための7つのポイントについて解説しました。不動産の売却益得るためには売却の時点だけではなく、購入時や運用時、賃借人の募集時など、それぞれの段階で対策を講じることが大切です。
また、自分自身で対策することに加えて、信用できる不動産会社と協力することも重要になります。自身の運用フェーズに合わせて、後悔しない不動産売却を目指しましょう。
また、自分自身で対策することに加えて、信用できる不動産会社と協力することも重要になります。自身の運用フェーズに合わせて、後悔しない不動産売却を目指しましょう。
医師特化型で投資運用をサポート『東京不動産投資』
東京不動産投資株式会社は、医師専門の、投資用不動産を活用した
節税・資産形成マネジメント会社である。
専任の不動産コンサルタントが医師だからこそ活用できる投資を手厚くサポート。税務、法律相談の各専門家も配し、多忙でお時間の限られている医師の皆様が安心してご相談できる体制を万全に整えている。
入居者様の募集から賃貸管理の事務手続き、ルームクリーニングなどメンテナンスも行っているので、医師の皆様にご負担なく、ノーストレスで運用していただける。
取り扱い物件は、東京都心、五区エリアに限定し、資産価値が下がりにくい物件を精査して紹介している。
ご興味ある方は、ぜひ一度ご相談を!
迫る「2022年問題」…不動産投資を「簡単」とは言えないワケ
2022年以降、「生産緑地」が宅地転用され大量放出
「生産緑地の2022年問題」が賃貸市場に大きな打撃をもたらすといわれています。
生産緑地とは都市部に残る緑地を守る目的で1970年代に制定された生産緑地法に基づいて、市町村から指定を受けた農地のことです。この指定を受けることにより、農地所有者は税制面での優遇措置を受けることが可能となりました。しかし、1992年に、東京、大阪、名古屋の三大都市圏を対象とした生産緑地法改正が行われます。この改正の結果、生産緑地の指定を受けられるのは、30年以上営農継続の意志のある場合に、つまりは農業を続ける場合に限られることになったのです。
その背景には不動産バブルによる地価高騰がありました。国は、生産緑地法の改正によって「都市部の農地への課税強化→宅地の供給増加→地価抑制」という効果を狙ったのです。
現在、全国には約1万3000ヘクタールの生産緑地が存在します。このうち、約8割は1992年の改正生産緑地法に基づいて指定されたものです。したがって、それから30年たった2022年以降は「農業を続けなければならない」というしばりがなくなり、所定の手続きを経れば指定を解除することができます。つまりは、宅地として利用することが可能になるわけです。
そこで、2022年を迎えた暁には、現在、生産緑地に指定されている大量の農地が不動産業者によって買い取られ、建売住宅や賃貸アパートなどに形を変え一斉に放出されることが予想されています。このような想定のもとで、「賃貸市場はますます厳しくなる」と囁かれているのです。

賃貸市場はますます厳しくなる
すでに東京西部エリアも「フリーレント」が当たり前に
「不動産は一にも二にも立地がすべて」といわれています。立地条件が悪ければ、不動産事業で安定的な収益を確保することが難しくなります。
人口の減少、生産緑地の指定解除による住宅用地の大量供給――賃貸経営にとっては楽観を許されない将来が待ち受けている中で、「どの場所に物件を持つのか」という立地の重要性はこの先、さらに増してくることになるでしょう。
現時点でも、入居者を安定的に確保できている物件は都市部の駅から徒歩10分圏内のアパート、マンションに限られているといっても過言ではありません。それ以外の物件に関しては、一定期間、賃料を無料にするフリーレントを実施するなど、オーナーが空き部屋を埋めるために四苦八苦しています。
例えば、2017年10月21日付日本経済新聞では、借り手を確保できず、フリーレントを行っているオーナーの状況を以下のように伝えています。
【入居者様募集――。JR栃木駅から徒歩30分。空き地や山々に囲まれたある地域には、アパートの入居者を募るノボリや看板がわずか数百メートルの範囲に8つも立っていた。今夏に完成した新築の物件は20部屋弱のうち、9割ほどは埋まっていない。不動産店に問い合わせると「今ならキャンペーンで2年間は賃料を毎月5千円下げる」という。
物件を大手不動産サイトで検索すると、「フリーレント」のサービスを付けると書いてある。不動産業界は空室が埋まらない場合、1~3カ月の無料貸しをしたうえで契約に結びつけることがある。栃木では千件以上の物件がフリーレントに出ている。地元の主婦は「昔は兼業農家が多く、誰も土地を売らなかった。今は農業をしないし、相続対策でアパートが増えた」と話す。】
この記事では、栃木県の小山市のケースが取りあげられていますが、東京でも都心から離れた八王子市やあきる野市のような西部エリアのアパートなどでは、入居者募集広告でフリーレントが当たり前のようにうたわれています。駅から遠く賃貸の坪単価が4千円、3千円という条件の悪い場所では、6カ月間、賃料が無料という例さえ見られます。
借主確保のため「AD名目」の支払いが発生!?
また、借主を確保するために「AD」の名目で仲介業者に法定の報酬以外の手数料を支払うこともあります。
ADとは宣伝広告料のことです。
オーナーが仲介業者に支払う不動産仲介の報酬は宅地建物取引業法(宅建業法)で定められており、その額よりも1円でも高い場合には違法となり処罰の対象になります。具体的には、アパート、マンション等の居住用の建物であれば、貸主、借主それぞれから賃料の半分ずつしかもらうことはできません。なお、依頼者の承諾がある場合は、いずれか一方から賃料の1カ月分以内を受けとることができます。ただし、この場合も貸主、借主から受ける報酬の合計額は賃料の1カ月分以内でなければならないというルールがあります。
このように、報酬に関しては法律で厳しい規制が課されていますが、一方で、「宣伝広告を行ってほしい」などオーナーからの特別な依頼に基づく費用については受けとることが認められています。
そこで、ADという形で特別な手数料を付けることで、仲介業者のモチベーションを刺激してより積極的な営業活動を促し入居者獲得につなげることが業界では常態化しています。
ADの額は「100%」であれば賃料1カ月分、「200%」であれば賃料2カ月分というようにパーセンテージで示されます。築年数が古いなど入居者を確保しづらい物件ほど、ADの額は高くなっていきます。多くは100%ですが、200%、300%のケースも見られます(先日、「400%」の例も目にしました。ここまで高いものはさすがに私も初めてでした)。
このように、現在の厳しい賃貸市場の状況の中で、空室を避けるためには、フリーレントやADの活用など、何らかの工夫や努力を行うことが必要になっています。
さらに、入居者を確保するためには、借り手のニーズを積極的に取り込む努力も求められます。エアコンはもちろん、インターネット設備を用意するのは当たり前となっていますし、それにプラスアルファしたサービスを打ち出すことが必要です。その結果として、賃貸経営のために要するコストはどんどん増えていくことになるでしょう。
必要経費を考慮しない「表面利回り」
コストの話と関連して注意を促しておきたいのは「利回り」の問題です。利回りとは、投資資金に対する収益の割合であり、投資した物件からどれだけの利益を得られるのかを予測する指標として用いられています。アパートやマンションを購入するときには、「このアパートは年間7%の利回りで回ります」などというように業者の側から利回りが示されるはずです。
そして、この業者から示される利回りは「表面利回り」とよばれており、通常、以下のように年間の賃料収入の総額を物件価格で割り出した計算式で求められているはずです。
利回り=年間の賃料収入の総額÷物件価格×100
例えば、2億円の物件で1年間に1400万円の賃料収入が得られる場合には、「1400万円÷2億円=0.7」から利回りは7%になります。
この利回りの数字を見ると、「7%もあるのか、結構いいなあ」と思うかもしれません。しかし、このような賃料収入だけを分子とした利回りの計算方法には実は「落とし穴」があります。それは、賃貸経営に必要となる経費が一切考慮されていないことです。
アパートやマンションは建てたときのイニシャルコストだけではなく、運用している間のランニングコスト(維持費等)も必要となります。具体的には、固定資産税・都市計画税、保険、修繕費等の費用があげられます。また、右で述べたADの費用やエアコン、インターネット設備等のコストも含まれることになるでしょう(さらに、最終的には建物を解体することになるでしょうから、その解体費用も考慮に入れておくことが必要となります)。
利回りを求める場合には、本来、それらの諸費用も含めなければならないはずです。つまり、利回りを正しく求めようとするのなら、年間の賃料収入から維持費等を引いた額を物件価格で割り出すべきなのです。その場合、計算式は以下のような形になるでしょう。
利回り=(年間の賃料収入の総額マイナス年間の維持費等)÷物件価格×100
例えば、上記のアパートの例で維持費等が年間で400万円かかるのであれば、「(1400万円マイナス400万円)÷2億円=0.5」から利回りは5%になります。
このように経費を入れて利回りを考えると、思ったほど利回りがよくないことに気づくことがあるかもしれません。
「日本初のタワマン」が建てられた、超・意外な街とは?
「日本初のタワマン」は、いつ、どこにできた?
何かと話題になることの多い「タワーマンション」だが、その呼称に法的な基準はなく、階数による定義もない。しかし建築基準法や消防法で、31m、60mと、建物の高さで基準が異なり、このうち高さ60m以上の建物が超高層建築物とする考え方が広まっていることから、高さ60m以上、階数にすると20階以上のマンションをタワーマンションと呼ぶことが多いようだ。
このタワーマンションだが、高層階からの眺望やハイスペックな施設・サービスによって近年人気となったが、一方で、昨年の台風被害により、災害時の危うさがクローズアップされている。
メリット、デメリットを顧みて、それを良しとするかどうかは、選ぶ人の価値観によるものだが、ところで、日本で初めてタワーマンションは、いつ、どこにできたか、ご存じだろうか。
諸説あるが、まず1971年に東京都港区三田にできた「三田綱町パークマンション」。しかし高さ52m、19階建てのツインタワーであることから、「タワマン」ではなく「高層マンション」の先駆けとして語られることが多い。前述のタワーマンションの定義による、日本第1号のタワーマンションが誕生したのは、埼玉県さいたま市。旧与野市に1976年に誕生した「与野ハウス」である。高さ66m、21階建て、総戸数463戸の大規模マンションだ。
最寄り駅でいうと、JR埼京線「北与野」駅。昨今は東京都心の再開発地区や臨海部に建てられることの多いタワーマンションだが、黎明期である1970年代は状況が異なる。当時は、日照権や敷地面積確保などの課題により、都心部にタワーマンションを建てるにはハードルが高かった。「与野ハウス」ができた当時、周辺にある建物といえば、戸建てや数階建てのアパートくらいで、隣駅のさいたま新都心の高層ビル群もなかった。
1997年、建築基準法の改正で共用部分が容積率算出上の延床面積に算入されなくなったことや日影規制の緩和などにより、人口集積地域にもタワーマンションの建設が可能になった。今日では、駅前の再開発といえば、まずはタワーマンションというくらい、いたるところで建てられている。地域のランドマークになりやすいことからも、今後も都心ばかりでなく、郊外でもタワーマンションは増えていくだろう。
そんなタワーマンション第1号が誕生した、さいたま市中央区、旧与野市は、どのような街で、どのような可能性を秘めたエリアなのか、不動産投資の観点で見ていこう。

北与野駅前
新都心の街開きで、開発の中心は「北与野」へ
与野市は、2001年、大宮市と浦和市と合併し、さいたま市が誕生するまで、埼玉県南部に存在していた市だ。旧与野市の市域は、現在、さいたま市中央区となっている。
収穫が不安定で租税を賦課できない土地である「余野」から転訛したとか、ヨは「ものの間」のことで「台地と台地の間の野」という地名から転じたなど、与野の由来には諸説あるが、与野が歴史に初めて表れたのは1314年と意外に古い。平安時代後期に浄土教の宗派である融通念仏宗をおこした良忍の事績などを描いた絵巻物『融通念佛縁起絵巻』に、「与野郷」という記述が登場する。室町時代には市場が開かれ、江戸時代には甲州街道と奥州街道を結ぶ脇往還(五街道以外の主要な街道)の町場として栄えた。当時の地誌『新編武蔵風土記稿』には、与野の戸数を304、浦和を208、大宮を200余りと記している。
しかし明治時代に高崎線、東北線が開通し、1912年に「与野」駅が開設されると、商業の中心は、市が開かれていた本町通り周辺から東部地区に移っていった(ちなみに「与野」駅は現さいたま市浦和区北部にあたる旧木崎村と旧与野町の境に設置され、住所は“与野”ではない)。
1958年には、単独で市制を施行し、県下20番目の市となり、1985年、埼京線の開通により、市内に「北与野」駅、「与野本町」駅、「南与野」駅の3駅が新設された。
「北与野」駅は、2000年に街開きとなったさいたま新都心の西側にあたり、「さいたま新都心」駅とは、ペデストリアンデッキ「北与野デッキ」でつながっている。また駅周辺では高層マンションの建設が進み、駅利用者も増加傾向にある。「与野本町」は江戸時代に賑わった与野宿に近い駅であり、さいたま市中央区役所が置かれたり、「彩の国さいたま芸術劇場」が建設されたりと、行政・公共施設の集積が見られる。「南与野」は埼玉大学に向かうバス便により、3駅のなかで乗降客は一番多いが、駅周辺には商業の集積はなく、空き地も目立つ。まだまだ発展途上といった雰囲気である。
旧与野市埼京線沿い3駅…ポテンシャルが高い駅は?
不動産投資の観点で与野を見ていこう。まずは、地域の人口と世帯構成(図表1)だが、さいたま市中央区の人口は10万人強で、埼京線3駅周辺には1万人前後が居住する。また1世帯当たりの人数は、2人強とファミリー層と単身者層が混在するエリアである。3駅周辺に限ると、人口構造の目立った差異は見られない。
続いて、中古マンションの次に中古マンションの平均取引価格(図表2)と、その種類(図表3)を見ていこう。さいたま市中央区の平均取引価格は3239万円で、3部屋以上のファミリー物件が8割を超える。また駅周辺に限ると、さいたま新都心の第2の玄関口としても機能する「北与野」は、平均取引価格、平米単価ともに、中央区平均を上回った。新都心に近いという利便性から、プレミアム感が出ていると推測される。
一方で、「与野本町」「南与野」の取引物件数は少なく、今回の分析では、2駅周辺の物件を足しても、「北与野」周辺の物件数を下回った。3駅いずれかのエリアで不動産投資を考えるのなら、まずは「北与野」が選択肢になるだろう。
今後の不動産投資の可能性はどうか。将来の人口増加の予測から見てみよう。黄色~橙で10%以上、緑~黄緑0~10%の人口増加率を表し、青系色で人口減少を表す将来人口推移のメッシュ分析(図表4)では、3駅周辺では現状維持から微増と予想。特に「北与野」周辺は、ほか2駅よりも高い人口増加が見込まれている。
さいたま市中央区の借家率は45%で、ファミリー物件の取引が活発なエリアだ。埼京線沿い3駅に限ると、今後も安定的な人口増加も見込める。家族層のニーズをつかむことで、長期的に安定した不動産経営が実現するエリアだといえるだろう。
浸水、洪水、地震…与野周辺の災害リスクは?
日本で初めてのタワーマンションが誕生した与野。タワーマンションといえば、昨今は、災害でクローズアップされたが、与野周辺の災害リスクはどうなっているのだろうか。ハザードマップを確認してみよう。
浸水(内水)のハザードマップを見てみると、南北に流れる鴻沼川、高沼用水路沿いを中心に、50センチ以上の浸水域が点在する。また洪水のハザードマップを見てみると、注意すべきは鴻沼川。1998年の台風5号では流域で多くの浸水被害をもたらした。このとき旧与野市では災害救助法が適用されている。
また地震のリスクはどうだろう。まず国立研究開発法人防災科学技術研究所の「J-SHIS地震ハザードステーション」で地盤を見てみると、さいたま市中央区一は、火山灰質の粘土であるローム台地に分類され、比較的安定したエリアだといえる。
しかし、表層地盤増幅率(地表面近くに堆積した地層の地震時の揺れの大きさを数値化したもので、1.6以上は地盤が弱く揺れやすい、2.0以上は特に揺れやすいと評価される)を見てみると、多くが1.6~1.8と、揺れやすい地域という結果に。そのなかでも、「与野本町」の南西、上峰あたりは1.55~1.59と、エリアのなかでは揺れにくい地盤であることがわかった。
地震の被害は、揺れによる建物被害だけではない。不動産投資家であれば、地盤の液状化はしっかりと想定しておきたい。さいたま市の地震の防災マップを見てみると、鴻沼川流域は、液状化の危険が高いとされている地域。物件選びの際には、心得ておこう。
不動産投資を有利にする「ローン借り換え」のポイント
借り換えで高額の利益の可能性も…ただし注意点あり
金利面で今より好条件のローンを見つけて、借り換えを行いたいと思ったことはありませんか? 実際に不動産投資をしている人が、ローンの借り換えを行ったことによって500万円、1000万円といった高額の利益を出すケースも珍しくありません。
だからと言って、安易に好条件の金融機関に飛びついてしまうのも考えもの。ローンの借り換えはメリットも多いものの、タイミングを間違えると逆に負担が増えてしまうこともありえます。
そこで今回は、不動産投資を行っている人のために、ローン借り換えで生じるメリット、それから借り換えを行うベストな時期はいつなのかということ、最後に借り換えのデメリットについてご紹介します。
不動産投資ローンを借り換えるメリット
不動産投資をしていると発生するさまざまな費用の中でも、特にローン返済における金利負担は大きいものです。この金利がある一定以上に大きい場合は収益を著しく下げてしまうようなこともありますし、逆にこの負担を賢く減らしていけば収益を大幅に上げることもできます。
ローンの借り換えを行うべきかどうかという判断を的確に行うためにも、メリットについてしっかりと整理しておきましょう。
●メリットその1――利回り率を上げられる
不動産投資成功の鍵は、いかに利回りを向上させられるかです。特に収益を下げてしまう原因は諸経費の中のローン返済の金利。返済額をうまく減らすことができれば収益が当然上がるわけで、実際うまく借り換えを行いながら、新しく別の不動産投資を進めていく人もいます。
●メリットその2――強気の交渉が可能
ローンの借り換えは必ず行わなければいけないものではなく、条件が合わなければやめればいいわけです。つまり借り換えのときは、新しくローンを組んでもらう会社に対して、立場が少し上になるということがいえます。
例えばある条件を提示して、その条件が満たされなければ借り換えは行いませんということを強く主張することもできます。かなり有利な立場から交渉を進めていくことができるようになり、その分借り換え後の条件を良くできる可能性も高くなるわけです。
●メリットその3――返済方法も変えられる
例えば毎月の金利の支払いが高すぎることが不満な場合、借り換えを行えば、返済期間を長くしてその金利を下げる、といった新しい条件提示をすることができるようになります。実質的に返済する金額があまり変わらなかったような場合でも、その時々の状況に応じて返済方法について見直しができ、融通をつけることもできるのです。
最適な借り換えのタイミング「3つの見極めどころ」
確かに借り換えを行うことによって、返済額を抑えることや、総支払額を下げることも不可能ではありませんが、その際に重要になってくるのが「タイミング」。そのタイミングを見極めるうえでのポイントを3つご紹介します。
①金利が低いとき
もちろんせっかく借り換えを行うのですから、総支払額を下げなければ意味がありません。金利が低いタイミングで借り換えを行うことがなにより重要です。特に日銀がマイナス金利政策をとった場合は、ローン金利もそれに従って下がる傾向がありますので、そのような社会的な流れも見極めることが必要になります。
②固定金利期間が終了するとき
例えば固定金利でローンを利用していた場合は、その金利が変動金利よりも高めに設定されている傾向があります。だからその期間がちょうど終わったときに変動金利に変更すると、かなり高い確率で利益が得られます。ただしこの場合、変動金利は将来的に金利が上がってしまうリスクもあることを注意しましょう。
③健康状態が良好なとき
「団体信用生命保険」への加入とローンの加入がセットになっていることがよくあります。団体生命保険とは、ローン返済中に死亡したり高度の障害で働けなくなってしまったりしたときに、残りの返済額を肩代わりしてもらえる制度です。当然、加入するには健康状態の告知が必要になります。そのため健康状態が良好な状態でないときには加入できず、ローンが組めなくなることもあります。
借り換えで生じる「2つのデメリット」
最後に借り換えを行うべきなのかどうかということをしっかり理解しておくためにも、その借り換えで生じてしまうデメリットもよく理解しておきましょう。
●デメリットその1――違約金や手数料がかかる
まずはもともとローンを組んでいた金融機関に対して高額の違約金がかかってしまう可能性があることです。また、手数料や諸経費が余計に発生してしまい、逆に負担が増えてしまう場合もあります。
●デメリットその2――金利交渉をした方がよい場合も
現在融資をしてもらっている金融機関に金利交渉をすることも不可能ではありません。借り換えでかかる手数料や手間を考えると、金利に納得ができないのであれば、現在利用しているローン会社に金利交渉を持ちかけてみることも検討してみましょう。
今回は、不動産投資でローンの借り換えをするメリットと、最適なタイミングを見極めるポイントをご紹介しました。
確かに借り換えには、手数料などの諸経費、さらにそれ相応に手間もかかります。しかし適切にタイミングを見極めて借り換えができれば、返済額が大幅に減る可能性も出てきます。メリットが大きくなるのか、それともデメリットが大きくなるのかを慎重に検討することが重要です。
不動産投資をするなら知っておきたい!「路線価」の基礎知識
路線価で物件の「適正価格」の根拠がわかる
不動産投資において路線価を参考にして投資エリアを選定することは基本中の基本とされています。しかしこれから不動産投資を検討するという場合は、路線価といわれてもピンとこない人もいるのではないでしょうか。実際、路線価が掲載された地図を見ても意味が分からないかもしれません。
そもそも路線価とは何なのでしょうか? 不動産では、公示価格や固定資産税評価額など目的に応じて同じ土地に対して、さまざまな価格がありあります。路線価はそのなかの一つで相続税の計算に利用されることが一般的です。毎年1月1日を評価時点として、その年の7月に国税庁が公表しており、だれでも閲覧することができます。道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を1,000円単位で表示しています。
固定資産税評価額の更新は3年に一度です。それ以外は毎年の更新なので路線価は最新の実態を反映していることになります。
不動産投資においては、土地と建物の価格を正確に算出するために路線価を読み解く必要があります。なぜなら路線価から割り出した価格と実勢価格(不動産の時価で、取引が成立する価格)や不動産会社が査定した価格(売主との相談で決めた売り出し価格)の間にギャップがあることが多いからです。不動産の売買は相対取引で売主と買主の間で決定されます。
売主からすると少しでも高く売りたいでしょうし、仲介する不動産会社も売買手数料に関わるので、できるだけ高く売りたいと考えるのが一般的です。良心的な不動産会社であればいいのですが、こちらの知識や情報が不足している場合は足元をみられて、だまされてしまうかもしれません。投資は自己責任ですから、自分でも価格を算出しておくことは重要です。
提示された金額や利回りの根拠を聞き取り、先方の回答次第で誠実な相手かどうかを見極められるぐらいに自ら情報収集をしておいたほうがよいでしょう。

路線価で穴場の不動産が見つかる!?
路線価の「見方」と「地価の算出方法」
路線価は地図上の道路すべてに数字とアルファベットで示されています。たとえば数字が「250」とあれば、1,000円単位ですので1平方メートルあたり25万円です。アルファベットは借地権の割合でAからGに行くにつれて減少します。路線価は公示地価の8割と設定されているため、たとえば「250」の土地200平方メートルの価格は、25万円×200平方メートル÷0.8=6,250万円となります。
土地の実勢価格は公示価格よりも10~20%高いという仕組みになっているので、実際の価格は7,000万円前後になるとみてよいでしょう。また建物の価格については、構造(鉄骨造り、木造など)に応じた標準的な建築単価を国土交通省のウェブサイトなどで調べ、延べ床面積をかけると新築価格が算出可能です。そこから、築年数と耐用年数に応じて減価償却することで判明します。
路線価が高い=国が認めた資産価値の高いエリア
不動産投資で最も大切なことは、物件の立地です。路線価が高いということは、資産価値の高いエリアだと国が認めていることにほかなりません。不動産投資では金融機関でローンを組んで資金調達すること多くなりますが、路線価が高いエリアの物件であれば金融機関の担保評価が高く、ローン額や条件において有利です。
ただし、いくら路線価が高いエリアがいいといっても銀座のような一等地にある物件は高くて投資用の資金が不足する可能性もあります。このように商業エリアで住居用の賃貸物件に投資したいと思っている場合は投資対象が見つからないかもしれません。そのため以下のような内容を明確にしておくことが重要です。
●住宅なのか
●商業施設なのか
●マンションなのか
●アパートなのか
●単身者用なのか
●ファミリー用なのか
●自分が購入したい物件がどのようなものなのか
また過去数年分の路線価を調査して「価格が上昇しているのか」「下落しているのか」を確かめるようにしましょう。需要が高ければ路線価は上がり人気がなければ路線価は下がるはずです。将来の出口戦略を考えると資産価値が目減りしにくいエリアの物件は有利になります。このように不動産投資において路線価の活用は非常に重要です。
なお土地の形状や接道条件などで不動産の評価額は変化するため、路線価の高いエリアであれば、なんでもいいというわけではありません。路線価の見方だけでなく、いずれはこうした知識も身につけておけば収益性の高い物件を探し出すことができるようになるでしょう。
「限界マンション」が抱える負のスパイラルとは
他人ごとではない神戸のマンション事情
神戸市が公表した資料によると、神戸市内にある全住宅約82万戸のうち半数以上の約51万戸がマンションなどの共同住宅、そのうち約20万戸が分譲マンションとのことで、一戸建ての約27万戸に迫ってきています。
ただ、分譲マンションが増えてきたのはここ最近の話ではなく、マンション建設が本格化した昭和後期くらいから継続的に増えており、そのことが今回取り上げる課題でもあるのです。
神戸の分譲マンションの約3割は築35年以上
30年以上にわたって継続的に分譲マンションが増え続けたことで今問題となっているのが「分譲マンションの老朽化」です。
資料によれば神戸の分譲マンションの約30%は築35年以上が経過しており、さらに今から5年後には43%にまで増えることがわかっています。
分譲マンションは一戸建てが老朽化する場合とは違い、分譲マンションであるがゆえに避けられない問題や課題があるのです。
築古分譲マンションが直面する3つの問題とは
神戸市が設置した「マンション管理支援制度検討会」では、築古分譲マンションの抱える課題として、主に次の3つの点について解決に向けての検討が行われました。
分譲マンションの抱える課題は全国的に同じなので、神戸市の例を参考に課題を分析していきましょう。
課題1:分譲マンションの老朽化問題

築年数が古くなってきているマンションの一番の課題は、「建物自体の物理的な老朽化」です。分譲マンションの多くは鉄筋コンクリート造で、法定耐用年数でいうと47年とされていますが、それはあくまで目安に過ぎません。
神戸市の資料を参考に考えると、次のような課題があります。
- 建物全体の汚れ
- 鉄部塗装の劣化、サビつき
- コンクリート部分の亀裂、鉄筋の露出
- 給排水設備の劣化
- 機械式駐車場の劣化
居住環境を良好な状態で47年以上維持するためには、定期的な修繕が必要不可欠ですが、既存の分譲マンションの多くで十分な修繕が行われていないことが発覚しているようなのです。
課題2:管理組合の財政難

分譲マンションの維持管理において重要な要素となるのが「管理組合の財政」です。
1人の所有者が建物全体を所有管理している一戸建てとは違い、分譲マンションについては各戸の所有者の集合体である「管理組合」が建物の維持管理を行います。
わかりやすくいうと、管理組合とはマンションの住民で組織する「町内会」のようなもので、町内会費にあたる修繕積立金を毎月各戸から徴収しているのです。
本来、修繕積立金は建物の老朽化具合に応じて適宜増額していく必要があるのですが、管理組合が適切に機能せず、十分な修繕積立金が貯蓄されないまま築年数が古くなってしまっているマンションが増えています。
そうなると、課題1の「分譲マンションの老朽化」を改善するために大規模修繕を実施しようとしても、修繕積立金残高が足りないという財政難のせいで、必要な修繕ができないまま建物がどんどん古くなって住環境が悪化してしまうのです。
課題3:居住者の高齢化

分譲マンションの築年数が古くなるということは、必然的に居住者の高齢化率も高くなります。
居住者が高齢化すると管理組合の役員のなり手がいなくなり、十分な議論ができなくなるという問題が発生するのです。
特に若い世代がいない分譲マンションの場合、10年、20年先を見据えた長期修繕計画を立てる意欲が失われ、その場しのぎの対応になりがちなので、ますますマンションの老朽化が進んでしまいます。
神戸市の資料によれば、所有者同士のつながりが薄くなり、所有者名簿もないため総会を招集することが難しい分譲マンションもあるようです。
マンションの老朽化を回避したくても、十分な修繕積立金がないため工事ができない。何とか対策を検討したくても、管理組合が高齢化していてその気力もない。
これら3つの課題はある意味1つの大きな課題であり、現代の分譲マンションが抱えている負のスパイラル、そしてこの状態に陥っているマンションのことを、俗に「限界マンション」というそうです。
次回は、マンションの中でも最も問題視されている「タワーマンション」にスポットをあてて課題を解説したいと思います。
一度の失敗で大きなダメージ。不動産投資で失敗を招く原因とは
世に出回る不動産投資に関する情報は、不動産投資のプラス面や成功事例を伝えるものがほとんど。しかし、投資である以上、失敗する可能性があることを忘れてはいけません。不動産投資の失敗の原因を把握し、失敗を避ける方法を考えてみましょう。
不動産投資における失敗とは?

(画像=Lumen Photos/Shutterstock.com)
そもそも、不動産投資における「失敗」とは、どういう状態を指すのでしょうか。投資の目的にはいろいろありますが、成功の指標のひとつはトータルで利益を得ることであり、その対極に「失敗」があります。つまり、不動産投資における失敗とは、「トータルで損を出すること」と言えます。
ただし不動産投資では、物件を運用している間はトータルの損益がなかなか見えてきません。物件を売却した時に、「売却価格-残債-それまでの不動産所得」という計算によってトータルの損益が確定するからです。
物件を売却後に計算してみたらトータルで損をしていた、ということもあり得ます。物件によっては、売りたいと思った時に買い手が見つからず売却できない可能性もあります。
一方で、売却しないで、長期保有して家賃を受け取り続けることで、トータルでプラスにすることもできます。また、物件からの表面的なキャッシュフローは多少のマイナスであっても、節税効果や保険効果も加味して考えればプラス効果がある、ということもあります。個人のファイナンス全体を考慮して、長期のスパンで見て損得を判断する必要があります。
甘い収支計画にご用心
では、不動産投資で失敗してしまう原因は何でしょうか。最大の原因は、投資を始める前に立てた収支計画の甘さでしょう。不動産会社から提供される物件情報に書かれた家賃収入や利回り、運用時の諸経費などの数値は、あくまでもその時点の想定であり、将来にわたって約束されたものではありません。
人口推移や周辺の家賃相場、経済状況など、さまざまな要因によってそれらの数値は変化します。楽観的・希望的観測のもとに収支計画を立ててしまうと、将来状況の変化があった時に泣きを見ることになります。
収支計画を立てる時は、リスクを加味し、手堅くシミュレーションを行う必要があります。トータルで利益が出ると判断できないなら、その物件への投資をあきらめるべきでしょう。
不動産投資は自己責任で
不動産投資は、物件探しや契約、資金調達、管理運営、修繕、売却などがあるため、他人の力を借りなければできない投資です。とはいえ、パートナーが常に正しい提案をしてくれるとは限りません。そのため、適切な提案をしてくれるパートナーを見つけ、最終的な判断をしっかりと自分で行う必要があります。
物件購入段階なら、収支計画の精度に問題はないか、物件は借り手がつきそうか、融資・返済条件に無理はないか、契約書に内容に問題はないかなど、投資の成否を左右する根幹の部分については、自分でチェックし、判断するようにしましょう。
慎重すぎると買い逃すことも
慎重になりすぎて物件を買えないことも、「機会損失=失敗」と言えるでしょう。不動産投資を成功に導くポイントの一つが、「早く始めること」です。早く始めることで、早期に収益を得られるようになり、それを次の投資に回せるようになるからです。
投資をスタートすればローンの返済は進みます。ローンの返済が終われば、そこから先は利益だけが積み上がっていきます。その意味でも、いち早く始めるべきです。投資を始めれば、経験と実績が蓄積され、経営判断力が磨かれます。
失敗を避けるポイントは会社選び
不動産投資で失敗する原因をいくつか挙げてきましたが、失敗を避けるための最大のポイントは、パートナーとして信頼できる不動産会社を選ぶことです。
顧客の資産とその運用の全体を俯瞰し、物件購入から賃貸管理、売却まできめ細やかな提案をしてくれる不動産会社を選べば、それだけで不動産投資は成功したようなものです。ぜひ、長期的な視点でサポートしてくれる誠実なパートナーを見つけてください。(提供:Dear Reicious Online)
不動産投資ローンの上手な活用方法『金利タイプ別の選び方と返済方法』
各種の不動産投資ローンには3つの金利タイプがあります。1つ目は、市場の金利動向に応じて金利と返済額が変わる「変動金利型」。2つ目は2年、3年、5年……10年といったように一定期間、金利が固定している「固定期間選択型」です。そして3つ目が当初の金利が完済まで変わらない「全期間固定金利型」となります。不動産投資では全期間固定金利型のローンは少なく、変動金利型と固定期間選択型が多いのが特徴です。本稿ではこれらの選び方と返済方法について説明します。
今後の金利の見通しを推測する

(写真=Solis Images/Shutterstock.com)
不動産投資ローンを選ぶ際、どの金利タイプを選べば効率的に返済できるかは市場動向によって変わります。変動金利型は市場の金利動向が変動する場合、それに沿って適用金利が変わりますが、返済額の見直しは5年に1度です。変動金利型の場合、金利が低めに設定されている上、当初の5年間の返済額は確定しているので、返済計画を立てやすいという面があります。
一方の固定期間選択型は、期間の短い場合は変動金利型並みの低い金利が多く、10年固定など固定期間の長いタイプはやや高めの金利設定となる傾向があります。
これらの条件から、今後の市場動向を推測して、この先も当分は低金利が続くと予想されるのであれば、「変動金利型」か、もしくは「固定期間選択型」の中でも、2年もしくは3年といったような短期間で金利の低いタイプを活用することが効率的です。逆に遠からず市場の金利が上がるという予想であれば、返済額を10年間フィックスできる10年固定を利用することが効率的であると言えるでしょう。
返済計画に頼らず、返済期間は自分で設定する
不動産投資ローンを検討する場合、金融機関のウェブサイトでは借入額や年収などに応じて資金計画をシミュレーションできますので、それを利用するとよいでしょう。しかしそれはあくまでも返済における一例に過ぎません。不動産会社や金融機関が立ててくれる返済計画は、物件を買ってもらいたいという狙いがありますから、返済可能な最長期間で計算した方法が提示されることが一般的だといえます。
不動産投資用ローンの場合、最長返済期間は30年としているところが多いようです。しかし、実際の返済の場合、30年以下ならば1年単位で選択できることがほとんどです。返済期間を短くすれば、毎月の返済額は増えますが期間が短い分、完済までの総額は少なくなります。もちろん負担額が大きくなる分、万が一空室で家賃収入を見込めない場合に生じるリスクも高くなります。このため、年収や賃料収入などとの関係をチェックした上で、余裕のある範囲を探りながら適正な返済期間を見定めたいところです。
返済期間を短くすれば、200万円以上の節約になることも
同じ金利でも返済期間が短くなるほど、一回あたりの返済額は大きくなります。下記表にある通り、金利2.0%で30年返済ならば毎月7万3,923円の返済額で済みますが、25年返済にすると8年4,770円に、20年返済にすると10万1,176円となる計算です。
これは家賃収入が6万円の物件なら、30年返済だと1万4,000円ほどの持ち出しですが、20年返済だと4万円ちょっとの持ち出しになるということでもあります。平均的な年収で考えると、その返済額が苦しいかどうかが漠然と推測できることでしょう。
返済期間が短いと、それだけ完済までの総支払額は少なくなります。仮に、完済まで金利が変わらないとすれば、30年返済だと総返済額は7万3923円×12か月×30年で約2,661万円ですが、20年返済だと10万1176円×12か月×20年で約2,428万円に減少します。年収に余裕があって早めに返済できるのであれば、返済期間を短くすれば差し引きで233万円もトクできるという結果になります。
| 金利 | 15年返済 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 11万9,698円 | 9万1,978円 | 7万5,374円 | 6万4,327円 |
| 2.0% | 12万8,701円 | 10万1,176円 | 8万4,770円 | 7万3,923円 |
| 3.0% | 13万8,176円 | 11万919円 | 9万4,842円 | 8万4,320円 |
返済期間を短縮すれば老後に備える安心感も
現在35歳の人であれば、30年返済だと完済できるは64歳です。しかし20年での返済計画を立てた場合、完済となるのは54歳です。55歳からローン返済がなくなり、不動産投資用物件から得られる賃料収入を老後の備えに回すことができるようになります。不動産投資は長期的な視点で臨むというのも、一つの投資方法です。老後について考えた場合、返済期間を短縮するという方法も戦略に取り入れてみてはいかがでしょうか。(提供:Incomepress )
マンション投資で大失敗する5つの理由とは?具体的な対策も解説
「マンション投資に興味はあるけど、失敗したくない…」そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかしその反面、不動産投資の知識のないままにマンション投資に手を出し、大失敗してしまうケースも存在します。
この記事では、マンション投資で大失敗してしまわないように、失敗の主な5つの理由と、具体的な対策について解説しています。
目次
- マンション投資で大失敗する5つの理由とは
1-1.投資マンションの空室が長引いて収支が悪化する
1-2.マンションの周辺環境が変化し、入居率や家賃に悪影響が生じる
1-3.マンションの修繕が多く発生しキャッシュフローを圧迫する
1-4.高い返済比率で不動産ローンの融資を受けてしまう
1-5.マンション購入時の金額が高すぎる - マンション投資で大失敗しないための具体的な対策
2-1.キャッシュフローに余裕のある投資マンションを選ぶ
2-2.マンション周辺の人口推移や住環境を確認する
2-3.マンション購入後の修繕がどれくらい発生しそうかを確認する
2-4.不動産ローンの金利が高いなら「借り換え」を検討する
2-5.マンション購入前に収支をシミュレーションする - まとめ
1.マンション投資で大失敗する5つの理由とは
マンション投資で失敗してしまう要因の多くに、購入前のリスク把握が足りていなかった、というケースがあります。マンションを購入するメリットはもちろん、どのような失敗要因があるのかもしっかり把握しておくことが大切です。
主な失敗要因として、下記の5つの理由が挙げられます。
マイナス金利政策で融資金利が歴史的な低水準となり、マンション投資ローンも借りやすくなったことから、これまで投資に興味の無かった層にまで広く認知されるようになりました。
マイナス金利政策で融資金利が歴史的な低水準となり、マンション投資ローンも借りやすくなったことから、これまで投資に興味の無かった層にまで広く認知されるようになりました。
- 空室が長引いて収支が悪化する
- 周辺環境が変化し、入居率や家賃に悪影響が生じる
- 修繕が多く発生しキャッシュフローを圧迫する
- 高い返済比率で融資を受けてしまう
- 購入時の金額が高すぎる
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1.投資マンションの空室が長引いて収支が悪化する
1室の区分マンション投資は、複数室ある1棟アパート・マンションの投資と異なり、入居者が退去し、次の入居者が決まるまでの間は家賃収入が0円になってしまいます。
一方、家賃収入がない月でも、借入金の返済義務は生じます。もし、入居者が数ヶ月以上にわたって見つからず、想定より空室期間が長引いてしまうようであれば、家賃の見直しやリノベーションなどの対策が必要になり、家賃収入の低下やリフォーム費の増加につながります。
1-2.マンションの周辺環境が変化し、入居率や家賃に悪影響が生じる
マンションの入居需要が特定の周辺環境に依存するものだった場合、環境の変化によって入居率が一気に低下してしまう可能性があります。例えば、近隣の学校が移転や廃校になってしまう、大手企業の支店・工場が移転する、ショッピングモールが閉鎖されるなど、投資物件によってその要因は様々です。
入居中の満足度については内装リフォームなどでもある程度の向上を図ることができますが、周辺環境の変化をコントロールすることはできません。このように入居率を維持しているのが特定の周辺環境によるものだった場合、個人投資家が対策できることは非常に限られてしまいます。
1-3.マンションの修繕が多く発生しキャッシュフローを圧迫する
マンション投資では屋上防水、外壁塗装、給排水管の取り替えなどの大がかりな修繕が発生します。このような修繕の回数が購入時の想定よりも多いと、キャッシュフローを圧迫することに繋がります。
通常、大規模修繕に備え、修繕積立金を毎月定額で管理組合から徴収されます。しかし、一部の中古マンションでは大規模修繕に向けた修繕積立金が徴収されていない物件もあり、その場合は自分自身で修繕費を積み立てておくなどの対策が必要です。
修繕の際には工事の規模によっては20万~50万円ほどの一時金を支払う必要があるでしょう。大規模修繕ではマンション投資で得られる1~2年間分のキャッシュを失うことになるため、事前に修繕費を想定しておかなければ失敗する可能性が高まってしまいます。
1-4.高い返済比率で不動産ローンの融資を受けてしまう
返済比率とは、月の家賃収入に対する返済金の割合のことです。
返済比率=「毎月返済額」÷「満室時の毎月の家賃収入」
この返済比率は毎月のキャッシュフローに直結しており、返済比率が低ければ低いほど投資の安全度は高まります。逆に、高金利で融資を受ける、融資年数が短い、という場合には毎月の返済額が大きくなるために返済比率が高くなってしまい、毎月の手残り金が少なくなってしまいます。
仮に、返済比率が60%を超える状態の場合は投資額に対し手残り金が少ないため、突発的な修繕対応や空室時の持ち出しに耐えにくくなる危険な状態であると言えるでしょう。むやみに融資を受けてしまい、この返済比率を無視してしまうと、現金がショートして投資を損切りせざるを得ない状況にもなりかねません。
1-5.マンション購入時の金額が高すぎる
マンションの購入価格が相場よりも高すぎる、というのもマンション投資で失敗してしまう理由の一つです。
融資を受けて購入した物件の価格が相場より高いほど、毎月の返済金にキャッシュフローは圧迫されます。また、いざ売却しようと考えた際に残債も多く残っていることになります。残債よりも売却時の価格が低いか同程度の場合には「お金を払って資産を手放す」という状況にもなりかねません。
家賃の下落や金利の上昇によりキャッシュフローの悪くなった物件を手放したいと考えても、残債と物件価格の差額を返済できる現金資産がなければ損切りが出来ない、ということも考えられます。
2.マンション投資で大失敗しないための具体的な対策
ここまでマンション投資で大失敗してしまう理由を挙げてきましたが、このような状況に陥らないためにはどのような対策が必要なのでしょうか。以下では、失敗例それぞれの対策を見ていきましょう。
- キャッシュフローに余裕のある物件を選ぶ
- 地域の人口推移や周辺環境を確認する
- どれくらい修繕が発生しそうかを確認する<
- 金利が高いなら「借り換え」を検討する
- マンション購入前に収支をシミュレーションする
2-1.キャッシュフローに余裕のある投資マンションを選ぶ
マンション投資では購入前に想定していた入居率を下回ってしまうリスクがあります。そのようなリスクを考慮し、想定より1~2ヶ月長く空室期間が続いても年間キャッシュフローがマイナスにならない物件を選ぶなどの対策をとっておきましょう。
不動産販売会社が提出している入居率のデータは、あくまでも想定値です。安定稼働を担保するものではない点に注意しながら、自分自身でも投資後のシミュレーションを行い、慎重に投資物件を選ぶようにしましょう。
2-2.マンション周辺の人口推移や住環境を確認する
人口が減少し続けている郊外の物件や、特定の周辺環境に依存した物件は現在の入居率を保てない可能性があります。該当地域の人口推移を調べ、マンション全体でどのような属性の入居者が多いのかを調べておくと良いでしょう。
日本全体は少子化により人口減少が予想されていますが、『総務省統計局 都市部への人口集中、大都市等の増加について』によると、特に東京都市圏では転入超過(転出者より転入者が多い状況)が続いており、今後も賃貸需要が高いと予想されます。
このような将来的な人口増加による賃貸需要の高い地域に絞り、周辺環境を考慮した物件を選ぶことが大切です。
2-3.マンション購入後の修繕がどれくらい発生しそうかを確認する
マンションを購入する際は、将来的にどれくらいの修繕が発生し、どれくらいの支出になるかを計算した上で利益が出るかどうかを考える必要があります。
新築マンションであればマンション管理会社の修繕計画をあらかじめ確認しておくと良いでしょう。また、もし古い中古マンションで修繕計画などが無かった場合には、過去の修繕履歴や前オーナーが支払った積立金を確認しておきます。あらかじめ発生する修繕費を想定しておくことで、月々のキャッシュフローからどれだけ積み立ておくべきかを予測することができます。
ただし、修繕計画がなく、過去の修繕履歴や前オーナーの積立金も無い、という状況でどれだけの修繕費が発生するかわからない場合には、投資対象から外してしまうのが無難でしょう。
2-4.不動産ローンの金利が高いなら「借り換え」を検討する
変動金利でローンを借りて、金利上昇によってキャッシュフローが苦しくなってしまった際には、ローンの借り換えも検討してみましょう。
この時、おそらく他の金融機関の金利も上がっているので借り換えは容易ではありませんが、「投資物件が安定したキャッシュフローを生み出している」「返済金が順調に減っており、まだ与信がある」という状況であれば、金融機関からの信用も上がり、物件購入時の金利より下げられる可能性があります。
他行への借り換え審査では、物件購入時と同じく投資家の属性と物件の総合評価がなされます。キャッシュフローを意識しておくことで、金利上昇のリスクに備えておきましょう。
2-5.マンション購入前に収支をシミュレーションする
投資マンションとして物件が高すぎないかどうか、購入前に今後の収支をシミュレーションして確認しましょう。マンション販売元の不動産会社が収支シミュレーションを作成してくれるケースもありますが、リスク管理が甘い数値計画になっていることもあります。
シミュレーションを行う際には家賃収入から経費、空室率、ローン返済金などを差し引き、賃貸需要の低下による家賃下落や、修繕積立金なども考慮しておきます。また物件をいつまで所有し続けるのか、いついくらで売却をするのかなど、出口戦略も購入前に検討しておくことが大切です。
収支シミュレーションを作成したうえで購入価格が高いと判断される物件であれば、物件価格の交渉を行うか、次の投資機会を待ち、購入を見送るのも重要な判断です。
まとめ
マンション投資で大失敗する5つの理由と具体的な対策を解説しました。これまでに挙げた失敗理由に共通しているのは、購入前の判断が甘かったということです。マンション投資で購入後に出来る対策は限られており、購入前にどれだけリスクに向き合えるかが重要になります。
一方で、マンション投資は長期的な定期収入を期待できる投資方法でもあります。この記事でご紹介した失敗要因を考慮し、ぜひマンション投資の検討を進めてみて下さい。
今年の不動産投資戦略と最も大切な2つの原則
皆さま、新年明けましておめでとうございます。赤井誠です。
令和としての初めてのお正月、皆様どうお過ごしだったでしょうか。私は、初孫とともに過ごした初体験の記念すべきお正月となりました。今年も一年よろしくお願いいたします。
今年は様々な不動産会社も6日より営業を開始しているようですが、私は4日からのんびりとですが活動を開始しました。あまり飲んでばかりいても身体に良くないので、少しづつ動いた方が調子がいいようです。
私自身は、本当にお正月以外は何もしないで過ごすことがなく、何かしらの活動をしています。そのため、お正月の間はいろいろ今後のことなどを考えて過ごしましたので、今年最初のコラムはこの話をしたいと思います。
■ 今年も最重要と考えていること
私自身は、とにかく、昨年末より台風被害でやらざるを得なくなった仕事が膨大にあり、それが大きな試練になっています。
ただ、この対応をやることによって、自分自身の知識・経験レベルはどんどん上がっていて、結果として自分の能力や経験値が向上し、一回りレベルアップした自分になったと実感しています。
どんなに物件やお金を持っていたとしても、何か大きなトラブルがあればすべて失うこともあります。しかし、自分自身の持つ知識・経験と言ったものは誰にも奪われることのない最大の資産です。
この資産があれば、たとえ何かがあってすべてを失ったとしても絶対に復活できます。人生の様々な事に対して興味を持ち、いろいろ自分自身でやっていくことで自分の知識や経験値を進化されることを今年も第一に考えていきたいと思います。
■ 今年の不動産に対する取り組み
ここ数年間に発生した不動産業界の不正の数々が公になるにつれて、銀行融資はどんどん厳しくなり、特に昨年の年末からはさらに厳しくなってきています。
都銀においてはこの秋から、物件価格の30%程度の頭金と諸経費も求められるように変わってきています。もちろん、資産背景の良い方は今でももっと有利な条件で融資を得ることができますが、全体的には本当に厳しくなってきました。
これから始めたいと思っている人にはまだまだ厳しい融資状況が続く気がします。ただ、もちろん、一部の銀行さんのようにいまでも融資を従来通りに行っている銀行はありますが、どうしても金利が高い傾向にあります。
一時に比べると物件の値段は下がってはいるものの、高金利の融資を使う場合はより高利回りの物件を購入しないと間違いなくやっていけない状況になります。
とにかく購入したいばかりに、不正手段で無理な融資を引き、厳しい状況に追い込まれているここ数年のハリボテ大家になってしまわないように自分自身を自制していかなくてはなりません。
ただ現在、一部の地方や利便性の悪い場所では随分と利回りが上がってきています。ここ何年も見ることがなかった利回り15%以上の築古アパートや鉄骨マンションなどもちょくちょく見つけるようになりました。
さらに、新築アパートも昨年までは8%を超えるものはほとんどありませんでしたが、最近は8%を超えて9%近いものも見つけられるようになりました。それだけ、需要と供給の関係が崩れてきているのだと思います。
ただ、都心部立地の良いところの物件は相変わらず利回りは低く、それでも売買が成立しています。今年は特にオリンピックもあることから、より一層、海外の投資家の日本の不動産に対する興味が上がるように思います。
というのも、私自信は投資対象と考えている国々には必ず長期で滞在しますが、予想以上の良い地域もあれば、予想以下の地域もあります。実際に目で見て体験することで、その地域の良い点・悪い点が見えてきます。
そういう意味では、今年は多くの外国人が日本に興味を持ち、訪れる人が多くなりますので、興味をさらに持つ外国人の投資家やその観光客を期待した日本の投資家が物件を購入するようになります。
ニセコのように日本人が見捨てていた場所も外国人からみると価値のある地域というものもあり、これからは都心部の手堅い場所と、外国人が意外に興味を持っている場所などは思わぬ値上がりが期待できるかもしれません。
海外に行ったときは、その地域の日本旅行向けパンフレットやインフルエンサーと呼ばれるSNSでの旅好きな人の注目している場所などはチェックしておく必要があると思います。
私自身もインバウンドに対する活動は開始していますが、今そのような地域でも本当に膨大なホテルが建設されています。
今年はオリンピックもあり、必ずもうかると思います。ただその後、これらがすべて稼働していてもやっていけるかどうかという問題は残ります。
個人的にはもうすでにそれなりの資産を築いているので、以下の事を意識してやっていきたいと思っています。
①銀行の信用を毀損しない物件の取得・新築
②一般賃貸に転用可能な宿泊物件の稼働
■ 今から始めるとしたら
もし、私が資金がない状態でやるとしたらどうするか。今は自分自身はそういう状態ではないのですが、息子たちにいろいろ教える中でいろいろ考えることが多いです。
今、資金がない人は融資がなかなか受けられません。そのため、どうしても築古のぼろ物件をリフォームして高利回りで貸すということに目が行く人が多いと思います。ただ、注意していただきたいのは、耐用年数の過ぎた物件を銀行は全く評価しないということです。
私も築古のフルリノベーションした高利回り物件を所有していますが、これらを都銀さんなどに共同担保として提供しようとしても、全く担保として見てもらえません。そのため、最初は銀行からの借金はさけ、親から借りたりすることも大事だと思います。
親から借りることをバカにする人もいるかもしれませんが、自分自身の信用がなければ、親だって貸しません。親からの借り入れは銀行からすれば、負債にはなりませんので、こういう物件でインカムを積み上げていく方法もあるでしょう。
もし金融機関から借りてスタートするならば、ある程度収益を稼いだのちは売却して現金資産に変えていきながら、銀行から見た自分の財務状況を向上させつつ、資金を貯めていくことになると思います。
時代とともに様々な変化が起き、それに対応する投資法が生まれ、ブームになったりしていますが、いつの時代も結局は銀行からきちんと評価されるような資産形成を時間をかけて作り上げていくことが不動産投資の王道だと思います。
最後になりますが、今年度も自分の感じたこと考えたことをコラムでお話ししていきたいと思います。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
令和としての初めてのお正月、皆様どうお過ごしだったでしょうか。私は、初孫とともに過ごした初体験の記念すべきお正月となりました。今年も一年よろしくお願いいたします。
今年は様々な不動産会社も6日より営業を開始しているようですが、私は4日からのんびりとですが活動を開始しました。あまり飲んでばかりいても身体に良くないので、少しづつ動いた方が調子がいいようです。
私自身は、本当にお正月以外は何もしないで過ごすことがなく、何かしらの活動をしています。そのため、お正月の間はいろいろ今後のことなどを考えて過ごしましたので、今年最初のコラムはこの話をしたいと思います。
■ 今年も最重要と考えていること
私自身は、とにかく、昨年末より台風被害でやらざるを得なくなった仕事が膨大にあり、それが大きな試練になっています。
ただ、この対応をやることによって、自分自身の知識・経験レベルはどんどん上がっていて、結果として自分の能力や経験値が向上し、一回りレベルアップした自分になったと実感しています。
どんなに物件やお金を持っていたとしても、何か大きなトラブルがあればすべて失うこともあります。しかし、自分自身の持つ知識・経験と言ったものは誰にも奪われることのない最大の資産です。
この資産があれば、たとえ何かがあってすべてを失ったとしても絶対に復活できます。人生の様々な事に対して興味を持ち、いろいろ自分自身でやっていくことで自分の知識や経験値を進化されることを今年も第一に考えていきたいと思います。
■ 今年の不動産に対する取り組み
ここ数年間に発生した不動産業界の不正の数々が公になるにつれて、銀行融資はどんどん厳しくなり、特に昨年の年末からはさらに厳しくなってきています。
都銀においてはこの秋から、物件価格の30%程度の頭金と諸経費も求められるように変わってきています。もちろん、資産背景の良い方は今でももっと有利な条件で融資を得ることができますが、全体的には本当に厳しくなってきました。
これから始めたいと思っている人にはまだまだ厳しい融資状況が続く気がします。ただ、もちろん、一部の銀行さんのようにいまでも融資を従来通りに行っている銀行はありますが、どうしても金利が高い傾向にあります。
一時に比べると物件の値段は下がってはいるものの、高金利の融資を使う場合はより高利回りの物件を購入しないと間違いなくやっていけない状況になります。
とにかく購入したいばかりに、不正手段で無理な融資を引き、厳しい状況に追い込まれているここ数年のハリボテ大家になってしまわないように自分自身を自制していかなくてはなりません。
ただ現在、一部の地方や利便性の悪い場所では随分と利回りが上がってきています。ここ何年も見ることがなかった利回り15%以上の築古アパートや鉄骨マンションなどもちょくちょく見つけるようになりました。
さらに、新築アパートも昨年までは8%を超えるものはほとんどありませんでしたが、最近は8%を超えて9%近いものも見つけられるようになりました。それだけ、需要と供給の関係が崩れてきているのだと思います。
ただ、都心部立地の良いところの物件は相変わらず利回りは低く、それでも売買が成立しています。今年は特にオリンピックもあることから、より一層、海外の投資家の日本の不動産に対する興味が上がるように思います。
というのも、私自信は投資対象と考えている国々には必ず長期で滞在しますが、予想以上の良い地域もあれば、予想以下の地域もあります。実際に目で見て体験することで、その地域の良い点・悪い点が見えてきます。
そういう意味では、今年は多くの外国人が日本に興味を持ち、訪れる人が多くなりますので、興味をさらに持つ外国人の投資家やその観光客を期待した日本の投資家が物件を購入するようになります。
ニセコのように日本人が見捨てていた場所も外国人からみると価値のある地域というものもあり、これからは都心部の手堅い場所と、外国人が意外に興味を持っている場所などは思わぬ値上がりが期待できるかもしれません。
海外に行ったときは、その地域の日本旅行向けパンフレットやインフルエンサーと呼ばれるSNSでの旅好きな人の注目している場所などはチェックしておく必要があると思います。
私自身もインバウンドに対する活動は開始していますが、今そのような地域でも本当に膨大なホテルが建設されています。
今年はオリンピックもあり、必ずもうかると思います。ただその後、これらがすべて稼働していてもやっていけるかどうかという問題は残ります。
個人的にはもうすでにそれなりの資産を築いているので、以下の事を意識してやっていきたいと思っています。
①銀行の信用を毀損しない物件の取得・新築
②一般賃貸に転用可能な宿泊物件の稼働
■ 今から始めるとしたら
もし、私が資金がない状態でやるとしたらどうするか。今は自分自身はそういう状態ではないのですが、息子たちにいろいろ教える中でいろいろ考えることが多いです。
今、資金がない人は融資がなかなか受けられません。そのため、どうしても築古のぼろ物件をリフォームして高利回りで貸すということに目が行く人が多いと思います。ただ、注意していただきたいのは、耐用年数の過ぎた物件を銀行は全く評価しないということです。
私も築古のフルリノベーションした高利回り物件を所有していますが、これらを都銀さんなどに共同担保として提供しようとしても、全く担保として見てもらえません。そのため、最初は銀行からの借金はさけ、親から借りたりすることも大事だと思います。
親から借りることをバカにする人もいるかもしれませんが、自分自身の信用がなければ、親だって貸しません。親からの借り入れは銀行からすれば、負債にはなりませんので、こういう物件でインカムを積み上げていく方法もあるでしょう。
もし金融機関から借りてスタートするならば、ある程度収益を稼いだのちは売却して現金資産に変えていきながら、銀行から見た自分の財務状況を向上させつつ、資金を貯めていくことになると思います。
時代とともに様々な変化が起き、それに対応する投資法が生まれ、ブームになったりしていますが、いつの時代も結局は銀行からきちんと評価されるような資産形成を時間をかけて作り上げていくことが不動産投資の王道だと思います。
最後になりますが、今年度も自分の感じたこと考えたことをコラムでお話ししていきたいと思います。少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
コンテナハウス/トレーラーハウス投資との違いは?
コンテナハウス投資でかかる3つの初期費用
コンテナハウス投資を始める際には、大きく分けて次の3つの初期費用が必要になります。
コンテナハウス投資を始める際には、大きく分けて次の3つの初期費用が必要になります。
コンテナハウスを設置する土地購入費用
まずは、コンテナハウスを設置する「土地」を仕入れる必要があります。
コンテナハウス投資のメリットの1つが固定資産税の節税対策であることを考えると、基本的には自身が所有している更地で始めるのが理想ですが、土地仕入から始めることも可能です。
土地購入費用については購入する場所によって大きく異なります。
コンテナハウス投資の場合は、前回のコラム でも触れたとおりコンテナを設置するための大型クレーンなどの搬入経路が必須となるため、東京都心の住宅街などはあまり向いていません。
コンテナハウスのおしゃれな外観などの特徴を活かすことを考えた場合、郊外や沖縄などのリゾート地の方がおすすめです。

まずは、コンテナハウスを設置する「土地」を仕入れる必要があります。
コンテナハウス投資のメリットの1つが固定資産税の節税対策であることを考えると、基本的には自身が所有している更地で始めるのが理想ですが、土地仕入から始めることも可能です。
土地購入費用については購入する場所によって大きく異なります。
コンテナハウス投資の場合は、前回のコラム でも触れたとおりコンテナを設置するための大型クレーンなどの搬入経路が必須となるため、東京都心の住宅街などはあまり向いていません。
コンテナハウスのおしゃれな外観などの特徴を活かすことを考えた場合、郊外や沖縄などのリゾート地の方がおすすめです。

コンテナハウス本体費用の相場
コンテナハウスは建築基準法に適合する規格のものを新規で製作してもらう必要があるため、中古コンテナでトランクルーム投資をするよりはコストが割高になります。
コンテナハウスの相場は、コンテナの大きさに応じて概ね以下のような価格が相場です。
12フィート(5帖程度):50~60万円
20フィート(9帖程度):80~90万円
40フィート(18帖程度):150~160万円
これらはあくまでコンテナ本体の製作費用なので、運送費用については別途必要です。
金額についてはコンテナの戸数や運送経路、運送距離、運送方法などによって異なりますので予め業者に確認したほうがよいでしょう。
コンテナハウスは建築基準法に適合する規格のものを新規で製作してもらう必要があるため、中古コンテナでトランクルーム投資をするよりはコストが割高になります。
コンテナハウスの相場は、コンテナの大きさに応じて概ね以下のような価格が相場です。
12フィート(5帖程度):50~60万円
20フィート(9帖程度):80~90万円
40フィート(18帖程度):150~160万円
20フィート(9帖程度):80~90万円
40フィート(18帖程度):150~160万円
これらはあくまでコンテナ本体の製作費用なので、運送費用については別途必要です。
金額についてはコンテナの戸数や運送経路、運送距離、運送方法などによって異なりますので予め業者に確認したほうがよいでしょう。
金額についてはコンテナの戸数や運送経路、運送距離、運送方法などによって異なりますので予め業者に確認したほうがよいでしょう。
コンテナハウスの設置費用
コンテナを住居として設置するためには、ただ置くだけでなく電気、ガス、水道などのライフラインや空調設備などの工事も必要になります。
また、現場での組み立て作業費なども考えると本体費用のほかに500万円前後は予算を確保しておく必要があるでしょう。
海外では低コストであることから比較的メジャーなコンテナハウスですが、日本では地震大国ということもあり厳しい建築基準法に適合する仕様のコンテナが必要になるため、コストパフォーマンスとしてはそこまで格安とはいかないのが実情のようです。
ただ、木造よりも少し高い金額で丈夫な建物が建てられると考えれば、投資対象として一定の魅力はあるでしょう。
コンテナを住居として設置するためには、ただ置くだけでなく電気、ガス、水道などのライフラインや空調設備などの工事も必要になります。
また、現場での組み立て作業費なども考えると本体費用のほかに500万円前後は予算を確保しておく必要があるでしょう。
海外では低コストであることから比較的メジャーなコンテナハウスですが、日本では地震大国ということもあり厳しい建築基準法に適合する仕様のコンテナが必要になるため、コストパフォーマンスとしてはそこまで格安とはいかないのが実情のようです。
ただ、木造よりも少し高い金額で丈夫な建物が建てられると考えれば、投資対象として一定の魅力はあるでしょう。
トレーラーハウス投資との違いについて
コンテナハウス投資を検討する際のもう1つの選択肢として比較されることが多いのが「トレーラーハウス投資」です。
トレーラーハウスとは車で移動できる車両型の小さな家のことで、最近ではトレーラーハウスで賃貸経営している投資家の方もいます。
では、コンテナとトレーラーハウスを投資として比べてみた場合、どのような違いがあるのでしょうか。
コンテナハウス投資を検討する際のもう1つの選択肢として比較されることが多いのが「トレーラーハウス投資」です。
トレーラーハウスとは車で移動できる車両型の小さな家のことで、最近ではトレーラーハウスで賃貸経営している投資家の方もいます。
では、コンテナとトレーラーハウスを投資として比べてみた場合、どのような違いがあるのでしょうか。
トレーラーハウスは固定資産税が不要

最も大きな違いは固定資産税です。
コンテナハウスについては土地に定着する「建築物」とみなされるため、固定資産として固定資産税が課税されます。
一方で、トレーラーハウスについては建築物ではなく「車両」という位置づけなので、固定資産税については課税されません。
ただし、車両なので自動車税が課税されるほか、車検がない大型特殊自動車については、自動車税は非課税ですが償却資産税の対象となります。

最も大きな違いは固定資産税です。
コンテナハウスについては土地に定着する「建築物」とみなされるため、固定資産として固定資産税が課税されます。
コンテナハウスについては土地に定着する「建築物」とみなされるため、固定資産として固定資産税が課税されます。
一方で、トレーラーハウスについては建築物ではなく「車両」という位置づけなので、固定資産税については課税されません。
ただし、車両なので自動車税が課税されるほか、車検がない大型特殊自動車については、自動車税は非課税ですが償却資産税の対象となります。
トレーラーハウスの登記について
基本的にトレーラーハウスは車両なので登記はできませんが、土地に定着する建築物とみなされる条件を満たせば、不動産登記することも可能です。
ただ、不動産登記をするとトレーラーハウスでも固定資産税が課税されます。
また、トレーラーハウスを設置するためには行政機関の許可や届出が必要になることもありますので、設置予定地を管轄する市区町村に確認したほうがよいでしょう。
基本的にトレーラーハウスは車両なので登記はできませんが、土地に定着する建築物とみなされる条件を満たせば、不動産登記することも可能です。
ただ、不動産登記をするとトレーラーハウスでも固定資産税が課税されます。
また、トレーラーハウスを設置するためには行政機関の許可や届出が必要になることもありますので、設置予定地を管轄する市区町村に確認したほうがよいでしょう。
また、トレーラーハウスを設置するためには行政機関の許可や届出が必要になることもありますので、設置予定地を管轄する市区町村に確認したほうがよいでしょう。
トレーラーハウスの相場
トレーラーハウスの価格は車両の大きさやグレードなどによって異なりますが、安いものであれば200万円台からあり、高いものになると1,000万円程度のものもあります。
投資として考えた場合は、普通賃貸借として2年契約で貸し出すのは難しいため、感覚的にはリゾートなどで旅行者に宿泊してもらう感じの民泊投資になるでしょう。
低金利でローンを組むことは難しいので、リゾート地で更地を所有している場合などでなければ、コンテナハウス投資よりもハイリスクかもしれません。
トレーラーハウスの価格は車両の大きさやグレードなどによって異なりますが、安いものであれば200万円台からあり、高いものになると1,000万円程度のものもあります。
投資として考えた場合は、普通賃貸借として2年契約で貸し出すのは難しいため、感覚的にはリゾートなどで旅行者に宿泊してもらう感じの民泊投資になるでしょう。
低金利でローンを組むことは難しいので、リゾート地で更地を所有している場合などでなければ、コンテナハウス投資よりもハイリスクかもしれません。
まとめ
今回は全3回にわたってコンテナハウス投資を中心に解説してきました。
現在の日本においてはまだそこまで認知されていませんが、コンテナハウスの性能やデザイン性は年々向上しているそうなので、今後木造や鉄骨、RCとともに第4の選択肢となる日が来るかもしれません。
近隣物件との差別化を重要視したい方については、コンテナハウス投資を検討してみてはいかがでしょうか。
今回は全3回にわたってコンテナハウス投資を中心に解説してきました。
現在の日本においてはまだそこまで認知されていませんが、コンテナハウスの性能やデザイン性は年々向上しているそうなので、今後木造や鉄骨、RCとともに第4の選択肢となる日が来るかもしれません。
近隣物件との差別化を重要視したい方については、コンテナハウス投資を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産投資で賃貸を続けるべきか売却すべきかを判断するためのコツ
資産運用には、株式投資や投資信託など数多くの手段がありますが、その中で不動産投資を行っている方も多くいます。不動産投資は、入居者がいる限り安定した家賃収入が得られるのが1つの魅力ですが、築年数経過とともに修繕が必要になる、入居率が低下するといった可能性があるため、いつまでも安定した家賃収入が得られるとは限りません。
そのため、運用を行っていく中で、賃貸を続けるべきか売却すべきかの判断が必要になります。この記事では、不動産投資で賃貸を続けるべきか売却すべきか判断するためのコツを紹介します。
1 不動産投資では出口戦略を考える必要がある
不動産投資は、自己資金が少ない場合でも融資条件を満たしていれば金融機関から融資を受けて始めることが可能です。また、入居者がつけば月々安定した家賃収入が期待できるため、資産運用の手段として不動産投資を選んでいる方も多くいます。
株式投資やFXなどは値動きが激しく、利益が得られるかは不確実ですが、不動産投資は入居者がいる限りは安定した家賃収入が確保できます。しかし、逆に空室であれば家賃収入が入らず、借入金の返済や経費の支払いなど支出のみが生じてしまうほか、築年数の経過とともに修繕費が増えて利回りが下がってくるため、どこかのタイミングで出口戦略を考えなければなりません。
不動産投資における出口戦略とは、一言でいえば「運用を手じまいすること」であり、主に所有している不動産を売却することを指します。出口戦略を考える際には、主に以下の3つの判断方法が挙げられます。
- 賃貸を続ける
- 売却して現金化する
- 物件を建て直して新たに賃貸を始める
物件を建て直して新たに賃貸を始めるのは費用が大きくなるため、修繕を繰り返しつつ賃貸を続ける、売却して現金化する、のどちらかを選ぶのが一般的です。
2 賃貸を続けるべきか売却すべきかを判断するコツ
賃貸を続けるべきか売却すべきかを判断するコツとして、以下の6つのポイントを確認しておくことが挙げられます。
- 想定していた利益が得られない場合
- キャピタルゲインが期待できる場合
- 売却価格が返済残高を上回る場合
- 大きな修繕が発生する前
- 満室になっている場合
- まとまったお金が必要な場合
それぞれのコツについて詳しく見ていきましょう。
2-1 想定していた利益が得られない場合
不動産投資を行う際は、物件の利回りを考慮しながら投資する物件を取得します。しかし、必ず想定通りの利回りが得られるとは限りません。物件を取得したものの、想定していた利回りを確保できず運用が思わしくない場合には、賃貸を続けるべきか売却すべきかを判断する1つのタイミングと言えます。
賃貸を続けていく中で家賃収入を上げ必要経費を抑えることができれば、そのうち想定していた実質利回り(経費を考慮した利回り)に達する可能性もあるかもしれません。しかし、想定していた利回りに達するまでは、不動産投資を始める際に契約した融資の返済が大きな負担になりかねません。そのため、賃貸を続けることが正しい選択とは必ずしも言えません。
想定していた利益が得られない場合には、無理に賃貸を続けようとするのではなく、早期に売却した方が将来的な損失を小さく抑えられる可能性があると言えます。
2-2 キャピタルゲインが期待できる場合
資産運用で得られる利益は、キャピタルゲインとインカムゲインの2つに分類されます。キャピタルゲインとは、資産価値の上昇により生じる売却益のことです。インカムゲインとは、不動産投資や債券などの資産を保有し続けることによって安定的・継続的に得られる利益のことです。
不動産投資は、安定的・継続的に得られるインカムゲイン(家賃収入)を主な目的としていますが、不動産価格も変動が生じることからキャピタルゲインを狙うことも可能です。
2008年にアメリカの投資銀行であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが破綻した「リーマンショック」後、不動産価格は下落していましたが、2013年からは回復基調です。国土交通省が公表した平成31年の地価公示価格によると、三大都市圏に限らず地方圏でも住宅地価格が上昇に転じています。そのため、物件価格が低い頃に不動産投資を始めた人の場合、現在売却すればキャピタルゲインが得られる可能性もあるでしょう。
しかし、不動産市場に影響を与えるような事態がいつ発生するかは誰にも分かりません。そのため、売却でキャピタルゲインが期待できる場合には、賃貸を続けることから売却に戦略を切り替えることも1つの選択肢と言えるでしょう。
2-3 売却価格が返済残高を上回る場合
投資用の不動産を取得した際の価格よりも売却価格の方が上回っている場合には、売却を判断する1つの良いタイミングが来ていると言えます。しかし、売却価格が融資の返済残高を上回る場合も、売却を判断する1つの選択肢が現れたと言えます。
不動産投資では、得られた家賃収入から融資の返済を行っていきます。ある程度の返済が終了すると、物件の売却価格が融資の返済残高を上回るようになります。
このタイミングで不動産を売却すれば、手じまい後にはほぼ確実に現金が手元に残ることになります。不動産投資を行っているものの、思ったような収益が出ていない場合には、このタイミングで売却を判断するのも良いでしょう。
2-4 大きな修繕が発生する前
新築物件で不動産投資を始めた場合でも、ある程度の築年数が経過すると、少しずつ修繕が必要になります。修繕を行うと支出が増えることから、利回りは低くなります。家賃収入が発生していても、融資の返済を考えた場合に利益をきちんと確保できなくなる可能性もあるため、そうなる際には賃貸を続けるべきか考えなければなりません。
例えば、マンションでは各設備の耐用年数に合わせて修繕が行われます。特に25~30年に1回、各設備の耐用年数が合わさるため、膨大な修繕費用が発生します。マンションの区分所有者はこうした修繕に備え、修繕積立金として毎月ある程度の修繕費用を積み立てるのですが、修繕費用によってはそれだけで足りるとは限りません。
25~30年に1回行われる大規模修繕工事が近づいてくると、修繕費用の上乗せにより支出が増えるケースも多いため、大きな修繕が発生する前に売却を判断するのも方法の1つと言えるでしょう。
2-5 満室になっている場合
「満室になっている場合は、家賃収入が十分にあるからむしろ賃貸を続けた方が良いのでは?」と考える方も多いかもしれませんが、反対に空室が目立つと買い手の需要が低くなるため、満室時は物件の売却を判断する1つのタイミングとも言えます。
投資用不動産の売却価格は、通常の不動産の売却価格と同様に、築年数の経過による影響を受けます。しかし、築年数より「利回りが高いか、低いか」ということの方が重要なことも多くあります。利回りが高い物件であれば、築年数が経過していてもある程度需要が期待できますが、利回りが低くかつ築年数が経過している物件は一般的に需要が低くなります。
そのため、満室になっている状況では、賃貸を続けたいという思いが強いかもしれませんが、絶好の売り時を逃す可能性もあるため、よく考えることが重要と言えるでしょう。
2-6 まとまったお金が必要な場合
子供が大学に進学する、家を購入する、車を買い替えるといったようにライフイベントにはまとまったお金が必要になる場合があります。このような場合には、投資用不動産を担保に金融機関からお金を借りるという方法もありますが、不動産を売却してまとまったお金を手に入れるということも1つの方法と言えます。
ただし、焦って不動産を売却した場合には、必要以上に安く売却してしまうことになる可能性もあるので注意が必要です。そのため、まとまったお金が必要になることが事前に分かっている場合には、そこに向けて売却計画を立てておくことも重要と言えるでしょう。
3 まとめ
不動産投資を行っている方の中には、賃貸を続けるべきか売却すべきかで悩んでいる方も多いと思います。安定した家賃収入を得られている場合、まだ売却を検討する必要はないと考えている方もいるかもしれませんが、入居率が低くなったり、築年数が経過したりするとスムーズに買い手を見つけられなくなる可能性もあるので注意が必要です。
不動産をうまく売却できるタイミングは限られています。例えば、想定していた利益が得られない時、キャピタルゲインが期待できる時、売却価格が返済残高を上回る時などです。いつまでも安定的・継続的に家賃収入を得られるとは限らないため、タイミングを見ながら売却を含む出口戦略を常に検討しておくことが重要と言えるでしょう。
どうする?不動産投資ローンの団体信用生命保険
住宅ローンを組む際、団体信用生命保険(団信)への加入が必須と言われた人は多いのではないでしょうか。多くの不動産投資ローンでは任意加入となるため、メリットやデメリットを知っておく必要があります。不動産投資を検討している人は参考にしてください。
任意?必須?加入した場合のコストは

(写真=Pachai Leknettip/Shutterstock.com)
初めに団信について解説しておくと、ローンを支払う人が亡くなったり、高度障害を負ったりして今後の支払いが困難になったときに、残りの債務が免除されるというものです。遺族は負債のない不動産が手に入ります。賃料収入を生む資産を残すことができるわけです。
不動産投資ローンで団信が必須となるケースは、住宅ローンに比べて多くありません。特にオーダーメイドのローンであるプロパーローンの場合は、加入したくてもできないこともあります。「加入は任意」と言われると、迷ってしまうのではないでしょうか。保険は未来に備えるものなので、今の時点では判断しづらいという性質もあります。
加入を必須とする場合、保険料はローン金利に含まれるのが一般的です。そうでない場合は金利に保険料分を上乗せします。加入した場合のコストは2019年10月現在、ローン残高に対して0.3%前後です。仮に2,500万円のローンを組んだ場合、最初の月は6,250円となります。
加入することでトータルの保険料が削減できることも
団信の保険金は直接遺族に支払われるわけではありません。この点が一般的な生命保険とは大きく異なるところです。しかし加入することで、他の保険の代わりになることがあります。生命保険の保険料は一人当たり1.5万円~2万円が平均ですが、月6,250円の団信に加入することで、削減できる可能性があるのです。
不動産投資ローンでは、団信を使うような事態になったとき、家族に残るのはマンションなどの収益不動産です。家族はこのマンションから発生する賃料を生活費の足しにできますし、売却して現金に変えることもできます。
例えば、自分が亡くなったときのため、配偶者を受取人にした1,000万円の終身保険に入っているとします。払込みが65歳までに終わる契約で、保険料は毎月2万円ほどかかります。一方、2,500万円の団信付きローンを組んで買い、20年後に所有者が亡くなったとします。建物の価値が半減したとすると、1,250万円分の資産を残すことができたことになります。終身保険よりもはるかに低い保険料で、より手厚い保障ができるのです。
終身保険との大きな違いは加入期間です。団信はローンを完済すれば契約が終了します。保険自体はいわゆる「掛け捨て」ですが、完済した時点で収入を生む資産を手に入れられるので、実質的に貯蓄型生命保険と同じ効果があります。
相続対策の場合は一考の余地あり
団信に加入するかどうかを検討する際には、相続税も考慮に入れる必要があります。相続対策で不動産投資を始める場合には、加入しないほうが良い場合が多いのです。
相続対策の不動産購入の仕組みを簡単に説明します。相続税は、現金預金や不動産、株式などの資産を、被相続人が亡くなったときの時価で集計し、さらにローンなどの負債を差し引いた「純資産」に対してかかります。遺産相続の際の不動産評価額は実勢価格の7割から8割で計算されますが、賃貸に出していることでさらに評価額が下がり、5分の1程度まで評価を下げられます。これによりローンとの差額分、相続税を圧縮できるというものです。
例えば、ローン残高が1,000万円、不動産の時価が800万円の場合、不動産を買うことによって200万円分の財産が圧縮され、その分の相続税が減ります。しかし団信に入っていると負債の1,000万円がなくなるため、不動産の時価である800万円分に対して相続税がかかります。
相続税には基礎控除があり、3,000万円+600万円×法定相続人までは無税です。団信に加入するかどうかを考える際には、資産全体を見て、相続税がかかるかどうかを計算してみる必要があります。
不動産投資ローンで団体信用生命保険をつけるかどうかは資産全体を考慮して決める
団体信用生命保険の保険料はローン残高に対して年間0.3%程度です。保険料に対して保障が手厚く、加入することで他の生命保険が不要になる場合があります。ただし相続税対策としてはつけないほうが良い場合もあります。不動産投資の目的や、資産の状況を考えて加入を検討してください。(提供:Dear Reicious Online)
不動産投資の失敗で「ローン返済が不能」…破産を防ぐ手段は?
ローンが返済不能に…何が差し押さえられる?
今回は、ローンが返済不能になったあとの手続きについて見てみます。返済が1回でも滞ると、銀行などの金融機関は事故の可能性を考えます。事故とは「信用事故」のことで、返済の遅延を1つの事故として記録し、事故が重なると貸しているお金を全額返済を求められます。ちなみに、信用に関する情報は金融機関全体で共有されます。いわゆるブラックリストと呼ばれるもので、ある銀行で返済を遅延すると、その情報が別の銀行でも共有され、融資審査などに影響します。
さて、返済日に入金がなかったと確認された場合、金融機関はどうなっているのか知るためにオーナーに連絡します。状況を確認し、返済不能だとわかれば、マニュアルに沿って債権回収の手続きに進みます。具体的には、裁判によって債権を確定し、担保になっている物件などを差し押さえ、換金可能な資産を押さえます。
ただし、金融機関は差し押さえのプロではありませんので、差し押さえなどに向けて進んでいく流れは緩やかです。返済が滞ってすぐに差し押さえとなるわけではなく、だいたい1年を超えたころから、ようやく物件の差し押さえの手続きが進んでいくようなイメージです。また、差し押さえの実務などについても、金融機関ではなく、金融機関が債権回収を行う債権回収会社などに依頼するケースがほとんどです。
差し押さえた物件は、最終的には競売で換金します。
ただし、競売にかけると相場よりも安い値段になるため、通常は少しでも高く買ってくれる業者を探し、売却しようと取り組みます。これを任意売却といいます。ローン残高が2億円、物件の時価が1.5億円、競売に出すと1億円になる場合に、1.6億円で買ってくれる業者がいれば、金融機関は6000万円ほど損失を減らすことができるわけです。
物件の処理方法が決まったら、次に返済不能となったオーナーの資産などを強制執行します。強制執行の対象となるのは、本人名義の預金や不動産などです。当人名義のものに限られますので、オーナーの配偶者の預金などは強制執行の対象にはなりません。
また、サラリーマン大家の場合は本業で稼いでいる給料が対象になりますが、差し押さえらえるのは手取り金額の25%までで、残りの金額(手取り金額の75%)が33万円を超えた場合は、超過分も対象になります。
テレビドラマなどを見ていると、強制執行の担当者が家に上がり込み、家電や家具などを次々と差し押さえていくようなシーンが出てきます。しかし、実際には家電や家具は換価価値がなく、差し押さえられないケースがほとんどです。
つまり、預金、不動産、給料の差し押さえが済んだところで「これ以上お金になるものがない」と判断され、それ以上は深追いされないのです。この状態を、法律用語で「執行不能」と言います。執行不能になると「執行不能調書」が発行され、一連の差し押さえ業務は終わります。
意外に感じるかもしれませんが、仮に大きな負債が残っていたとしても、手元にあるものを差し出せば、それで終わりです。不動産などがなくなり、給料が減ることはありますが、普通に生活することは十分可能でしょう。破産しても債務者の権利は守られるため、あとは金融機関の手続きに任せて、その様子を見守るだけでもとくに問題はありません。
破産すれば官報に掲載、名前や住所も公表されるが…
強制執行は債務者となったオーナーが自己破産した時の手続きの1つです。破産はイメージが悪いですし、信用事故としてブラックリストにも乗りますのでなるべく知られたくないと思う人も多いことでしょう。
しかし、それは避けられません。破産は官報に掲載され、名前や住所も公表されるからです。逆に言えば、官報を見ない人にはほとんど知られる可能性がないということです。金融機関に勤めている人なら官報を見るかもしれませんが、それ以外の業界で働いている人が官報を見るケースは極めて稀だと思います。
また、仮に勤め先に破産したことが知られたとしても、それが理由でクビになったりすることはありません。実際、破産してから企業の取締役になった人もいますし、銀行員の中に破産した人もいます。
破産から5年間はクレジットカードが作れず、10年間はローンが組めませんので、その点では苦労があるかもしれません。しかし、日常生活の面から見れば特にハンディキャップを負うわけではなく、苦労もしないでしょう。それでも巷で破産が「犯罪」のように扱われるのは、金融機関にとって、そのほうが都合が良いからです。融資を受ける側が破産を恐れてくれれば、真面目に返そうと思いますし、破産を避けるためにあらゆる努力をしてくれます。つまり、破産は本当は怖くないことなのですが、怖いと思わせておくほうが良い人がいるため、怖くないという事実が広まらないということです。
「破産に至らない」ためのいくつかの手段とは
自己破産や、破産に伴う差し押さえや強制執行と関連して、もう1つ押さえておきたいことがあります。それは、破産に至らないようにするための手段がいくつかあるということです。本記事の最後に、その方法と流れを簡単に列記します。
●リスケジュール(リスケ)
リスケは、融資元である金融機関と交渉し、返済のタイミングや返済計画そのものを見直すことです。リスケをすることにより、債務者としては無理のない返済計画になり、破産を避けられる可能性が高まります。金融機関側も、債務者に破産されると損失が大きくなるケースがほとんどですので、債務者から金融機関にリスケをお願いするだけでなく、金融機関から債務者にリスケを提案することもあります。
●任意整理
任意整理は、減免を狙う場合や担保に入っている不動産の処理を行う際に取る手段です。任意整理には元本を減らしたり利息を減らすといった方法があり、リスケのように返済期間を調整するだけでなく、負債額や担保などの調整も含みます。「返済不能になったので仕方がない」という前提で、現時点でできることを考え、債務者であるオーナーと債権者である金融機関がそれぞれ譲歩し、お互いが納得できる和解の方法を見つけます。
●特定調停
任意整理は債権者と債務者の話し合いによって行うものですので、法律には縛られません。ただし、お金が絡む交渉ごとですので、うまくまとまらないこともあります。そのような時の仲介役となるのが特定調停です。任意整理の交渉はどこで行っても構いませんが、特定調停は簡易裁判所で行い、裁判官または調停委員が仲介役として同席します。
●民事再生
交渉がまとまらない場合は、民事再生です。民事再生は、破産と一緒にまとめて法的整理とも呼びます。任意整理が関係者の意思で解決していく方法であるのに対して、法的整理は法律と裁判所が加わり、法的に債権を大幅に減らすといった措置をとります。
特定調停における裁判所の役目が「債権を減らしてはいかがですか」という仲介や提案である一方、法的整理では法の執行人として交渉成立に関わります。
●破産
ここまでの方法を試し、どれもうまくいかなかった場合は、最終的に自己破産です。自己破産すると、債務返済の義務がなくなります。民事再生は、再生計画にのっとって負債を返済していきますが、破産した場合はその必要がありません。手持ちの資産は裁判所によって管理され、破産手続の費用となり、残った分は債権者に分配されます。自己破産を申告し、公的な第三者が「この申立人は債務を返済できない状態です」と確認すれば、破産手続きは終わりです。
前述の通り、クレジットカードを作ったりローンを組んだりする際のハンディキャップはありますが、それ以外の点では特に不自由はなく、経済的、精神的な重荷をリセットし、再出発することができます。
知識なしで始めるのは危険!キャッシュレスと不動産の落とし穴
不動産投資に必要なのは「若さ・健康・勇気」
2019年終盤の今、投資物件はズバリ「売り時」
2019年はズバリ「売り時」である可能性が高い
売り時、買い時に関する記事の多くは、最終的な結論が中途半端になりがちなので、今回はあえてはっきりとお伝えしていきたいと思います。
ズバリ、2019年の今は東京の物件に不動産投資をしている人にとってズバリ「売り時」です。
「東京」とエリアを限定したのは、地域によっては万博が決まった大阪のように、これから伸びる可能性があるエリアも多いので東京としています。
今現在、東京の不動産価格は2013年に東京オリンピックが決まって以降、成約価格も含め上昇していましたが、オリンピック本番を来年に控えた今、正直なところ今以上に上昇する理由がなく頭打ちの状況です。
2018年頃からそろそろ価格が天井を迎えると業界内で囁かれ始めていましたが、「かぼちゃの馬車」に端を発した「スルガ銀行不正融資問題」によって事態は急展開しました。
ローン審査の引き締めで相場は上がりようがない状況に
 スルガ銀行の不正融資問題によって、金融庁が他の金融機関に対しても不動産投資からみのローン審査について大きく踏み込んできており、シンプルにいうと融資が通りにくくなっているのです。
以前であれば、頭金なしのフルローンでも審査がおりていた案件でも、想定していた金額までの融資が引っ張ることができなくなってきています。
いくら不動産投資ブームと言われていても、金融機関が融資してくれなければ投資することができません。
スルガ銀行の不正融資問題によって、金融庁が他の金融機関に対しても不動産投資からみのローン審査について大きく踏み込んできており、シンプルにいうと融資が通りにくくなっているのです。
以前であれば、頭金なしのフルローンでも審査がおりていた案件でも、想定していた金額までの融資が引っ張ることができなくなってきています。
いくら不動産投資ブームと言われていても、金融機関が融資してくれなければ投資することができません。
審査のハードルが上がったり、融資してもらえる金額が下がったりすれば、都内の不動産価格はジリ貧の状況に陥るでしょう。
審査のハードルが上がったり、融資してもらえる金額が下がったりすれば、都内の不動産価格はジリ貧の状況に陥るでしょう。
買主層の年収が下がっているらしい…
不動産投資セミナーを積極的に開催している不動産会社からは、以前に比べてセミナーに来る人の年収が下がっていると聞きます。
以前は800万円〜1,000万円程度の年収のある人が多かったらしいのですが、最近は一般的なサラリーマンである400〜500万円程度の人に顧客層が変化してきているそうです。
年金に対する不安から、サラリーマンが不動産投資に興味を持ち始めたのはよいことですが、年収が低い人はローンを組める金額も低くなります。
加えて、スルガ銀行の一件でローン審査は厳しい状況です。
これまでのような3〜4%前後の利回りでは中古物件が売れなくなるため、必然的に不動産価格は値下がりすることになると考えられます。
これらの理由に加えて、来年はオリンピック本番なのでそれまでに売り抜けようという心理が働く可能性も高いです。
ここ数年以内に売却を検討している方については、待つことで今よりも価格が上昇するとは考え難いため、売却に踏み切ったほうが良いかもしれません。
加えて、スルガ銀行の一件でローン審査は厳しい状況です。
買い時はもう少し後に来るはず
ここまでお読みいただければ、少なくとも今以上の上昇は考え難いことがわかると思います。ということは、今現在買うということは割高になる可能性が高いということです。
今後地価が上昇するイベントや計画が多い大阪、沖縄、北海道とは違い、東京については好材料がすべて出尽くしている感があり、ピークが過ぎ去ろうとしている状況にあります。
であれば、どうしても今年中に転職したいような方でなければ、第2回で解説 したように、もう少し様子を見た方が賢明です。
次の買い時にはキャッシュが武器になる
 今が買い時ではないとして、仮に東京オリンピックが終わった後、東京の相場が下がり始めた場合、不動産投資家にとって必要になってくるのが「キャッシュ」です。
不動産価格が今の高騰した状態から落ち着いてくれば、一般的な年収のサラリーマンでも買いやすくなるでしょう。
今が買い時ではないとして、仮に東京オリンピックが終わった後、東京の相場が下がり始めた場合、不動産投資家にとって必要になってくるのが「キャッシュ」です。
不動産価格が今の高騰した状態から落ち着いてくれば、一般的な年収のサラリーマンでも買いやすくなるでしょう。
ただ、その時もおそらくはローンの審査は厳しいままである可能性が考えられます。
安くなってきたから買いたい、と思ったとしても頭金にできるキャッシュが手元にないとローン審査が通らず買いたくても買えない状態に陥る可能性も考えられるのです。
よって、価格がまだ高騰している今のうちにキャッシュを貯蓄して準備しておき、来年以降下がり始めたタイミングで頭金にして投資するのが一番理想的ではないでしょうか。
ただ、その時もおそらくはローンの審査は厳しいままである可能性が考えられます。
不動産投資で後悔しないために重要なこととは
最終回となる今回は、今後の動向についてかなり突っ込んだ見解を述べさせてもらいました。
ただ、不動産投資において最も重要なことは、売り時、買い時の判断を他人の意見やネットの記事だけに依存するのではなく、それらの情報をすべて踏まえた上で、自分自身の持てる知識と経験で熟慮して結論を出すことです。
不動産投資に失敗する人は「〇〇を信じたのに失敗した」という言葉をよく口にしますが、それは信じているのではなく、自分で考える、検討する、分析するという労力を面倒で放棄しているだけなのです。
不動産投資は高額な投資だからこそ、後悔しないよう、本記事も含めあらゆる情報をもとに自分自身で熟慮した上で、売り時買い時について判断することをおすすめします。
唯一の人口自然増加県、沖縄。投資でもアツイ?
沖縄県がアツイ理由について語る上で外せないのが、人口増加です。
人口減少が著しい日本において、沖縄県については20年以上にわたって人口が増加し続けている極めて貴重な地域なのです。
人口減少が著しい日本において、沖縄県については20年以上にわたって人口が増加し続けている極めて貴重な地域なのです。
沖縄県の出生率は日本一
人口増加という点では東京についても同じことがいえますが、実は東京と沖縄では増加の意味合いが大きく異なります。
東京の人口増加は、ほかの道府県からの流入が主な要因ですが、沖縄県については自力の出生率で人口が増加している、全国で唯一、日本人自然増加をしている県なのです。
 沖縄県の人口千人あたりの出生率は、43年連続で1位であり、さらにいうと死亡率については15年連続で全国最下位と、必然的に人口が増加する状況が出来上がっています。
また、一人の女性が生涯に出産する子供の人数を推定する「合計特殊出生率」についても、32年連続で全国1位であり、まさに人口が増加する要素が満載なのです。
このことから、沖縄の人口増加傾向は外的要因の影響を受けにくく、今後も人口が増え続けることが予想されるため、不動産の投資先としてはこれ以上ない好材料といえるでしょう。
沖縄県の人口千人あたりの出生率は、43年連続で1位であり、さらにいうと死亡率については15年連続で全国最下位と、必然的に人口が増加する状況が出来上がっています。
また、一人の女性が生涯に出産する子供の人数を推定する「合計特殊出生率」についても、32年連続で全国1位であり、まさに人口が増加する要素が満載なのです。
このことから、沖縄の人口増加傾向は外的要因の影響を受けにくく、今後も人口が増え続けることが予想されるため、不動産の投資先としてはこれ以上ない好材料といえるでしょう。
100人に1人は外国人
沖縄県の人口を考える際に、もうひとつ覚えておきたいのが外国人の占める割合です。
沖縄県に暮らしている外国人は、沖縄県全体の人口のおよそ1%、つまり100人に1人は外国人が住んでいるということです。
沖縄県は外国人観光客を受け入れるために、外国人労働者が増えており、この度改正された入管法の影響でよりビザが発給されやすくなったことで、さらにこの割合は増加していく可能性があります。
外国人は日本人のように住まいを買うことが簡単ではないため、マイホームを賃貸する可能性が高く、沖縄全体の賃貸需要の底上げになると考えられるでしょう。
沖縄県に暮らしている外国人は、沖縄県全体の人口のおよそ1%、つまり100人に1人は外国人が住んでいるということです。
沖縄VS北海道 不動産投資するならどっち?
さて、沖縄が不動産投資先として明るい展望があることはお分かりいただけたかと思いますが、実は同じような地域として「北海道」が以前から注目を集めています。
そこでここでは、沖縄と北海道について、不動産投資先として考えた場合の違いについて比較してみました。
不動産投資の経費は、沖縄の方が断然おトク
不動産投資で高い利回りを維持するためには、「経費」を抑えることがとても重要です。
北海道はご存知の通り日本有数の寒冷地のため、除雪費用や凍結対策費用がとても高く、不動産投資による利益を圧迫するといわれています。
一方、沖縄については1年を通じて雪が降ることがないため、余分な経費がかからず、実質利回りを高く維持することが可能です。
北海道はご存知の通り日本有数の寒冷地のため、除雪費用や凍結対策費用がとても高く、不動産投資による利益を圧迫するといわれています。
沖縄県は広告費(AD)もタダ
空室を埋めるための手段として、不動産会社に「広告費(AD)」を出すという習慣が全国的にありますが、実は沖縄については広告費の習慣がほとんどありません。
競争が激しい東京では、広告費を家賃の2ヵ月分も出すようなケースもありますが、沖縄ではそのような経費がかからないというメリットがあります。
物件価格は沖縄の方が高め
 北海道と沖縄の決定的な違いは、面積の広さです。
地図で見ても分かる通り、北海道の面積は1,121平方キロであるのに対し、沖縄県は40平方キロと28倍も違うことから、土地価格の指標となる公示地価についても、沖縄の方が割高となります。
例えば、北海道札幌市の2019年平均公示地価が「13万7,418円/㎡」であるのに対し、沖縄県那覇市は「22万6,678円/㎡」と割高なのです。
もちろん場所によって違いはありますが、北海道よりも沖縄の方が、物件価格が高くなる可能性が高いでしょう。
このように、北海道と沖縄県では、不動産投資における特徴に違いがあることがお分かりいただけたでしょうか。
ちなみに、本州に住んでいる不動産投資家からすると、北海道での不動産投資は気候的な面から思わぬ出費を覚悟しなければなりませんが、沖縄県での不動産投資は本州の感覚とそこまで大きくは違わないため、比較的やりやすいと言えるかもしれません。
北海道と沖縄の決定的な違いは、面積の広さです。
地図で見ても分かる通り、北海道の面積は1,121平方キロであるのに対し、沖縄県は40平方キロと28倍も違うことから、土地価格の指標となる公示地価についても、沖縄の方が割高となります。
例えば、北海道札幌市の2019年平均公示地価が「13万7,418円/㎡」であるのに対し、沖縄県那覇市は「22万6,678円/㎡」と割高なのです。
もちろん場所によって違いはありますが、北海道よりも沖縄の方が、物件価格が高くなる可能性が高いでしょう。
このように、北海道と沖縄県では、不動産投資における特徴に違いがあることがお分かりいただけたでしょうか。
ちなみに、本州に住んでいる不動産投資家からすると、北海道での不動産投資は気候的な面から思わぬ出費を覚悟しなければなりませんが、沖縄県での不動産投資は本州の感覚とそこまで大きくは違わないため、比較的やりやすいと言えるかもしれません。
沖縄不動産投資、買うなら早めがおすすめ
今回は沖縄県がアツい視線を集める理由と、不動産投資先としての展望について解説してきました。
クルーズ船の増加や那覇空港滑走路増設など、プラス材料が多い沖縄ですが、すでに不動産価格が高騰し始めているため、不動産投資をするならあまり迷っている時間はありません。
先ほども触れましたが、沖縄県は北海道とは違い面積が狭いため、今後、物件の希少価値が出て、さらに物件価格が高騰する可能性があります。
とくに那覇市や浦添市の物件については、東京都の都心3区(港区、中央区、千代田区)のように、今後価格がどんどん釣り上がる可能性が考えられますので、投資を検討しているなら、早めに動き出すことをおすすめします。
「待つ」だけではなく「攻める」選択肢!空室が発生したらどうする?
資産形成の手段としてマンション経営は有力な選択肢です。しかし、例えば借り主が退去してしばらく新しい入居者が決まらなければ、家賃収入でローンを返済することができなくなります。このような失敗をイメージしてしまい、マンション経営に踏み切れない人もいるのではないでしょうか。こういう空室の状況では、入居希望者をただ待つだけではなく積極的に動くことが大切です。
投資用マンションを居住用として売る

(写真=PlusONE/Shutterstock.com)
いきなり思い切った選択肢と感じるかもしれませんが投資家ではなく住みたい人に売るのです。この方法のよいところは、比較的高値で売れる可能性があること。基本的に不動産投資家は投資に対する利益を追求するため、購入価格に厳しくなりがちです。周辺の家賃相場や地域の利回りを調べ、損をしにくい価格でなければ買わないのが基本姿勢です。
居住者がいないのをいいことに内見して修繕の必要性を指摘し、価格交渉してくるかもしれません。現況が空室なのであれば、なおさら安く見られるでしょう。一方自分が住むマンションを探している人は、一般的にそこまで価格にシビアではない人も多いでしょう。立地や内装が気に入れば、相場と比べて高い物件を即決するケースもあります。居住環境や居住空間には「プライスレス」な部分があるのです。
一般的に居住用として売ることに適しているのはファミリー向けマンションですが、ワンルームマンションにもチャンスはあります。これからは少子高齢化や未婚率上昇の影響により、購入を検討する人が増えてくるでしょう。

(写真=PlusONE/Shutterstock.com)
投資用マンションをリノベーションする
リノベーションとは、内装を一新して付加価値をつけることです。現状維持を前提とするリフォームと比べると「攻め」の物件管理といえます。どれも同じに見える、ありふれたマンションと差別化を図り、収益性を高めます。特に築20年以上経ち、今まで大規模な改修をしていない部屋はリノベーションのチャンスです。
システムキッチンや給湯器、エアコンなど、定期的な交換が必要な設備の更新も行い、利便性も同時に高めることができます。給排水管からの水漏れなどを防ぐ効果もあります。ポイントとしては、新築物件をライバル視しないことです。築年数が経っていることを逆手に取り、個性的な風合いの内装を取り入れることをおすすめします。
レトロモダンなライフスタイルを好む人などから一定の人気を得られるはずです。人びとの心をつかめれば、空室を早く終わらせるだけでなく家賃月額を上げられることでしょう。
投資用マンションに自分で住む
自分で住むという選択肢もあります。自分の持ち家ですから家賃を払う必要がありません。 住居費が月1万~2万円の管理費・修繕積立金のみになることで生活費はかなり楽になるでしょう。浮いたお金を貯金して、また新しい物件を買うという「攻め」に転じるのも方法の一つといえます。この方法による効果が最も高い時期は、ローンを払い終わった後です。
購入から日が浅く、まだ返済がたっぷり残っている場合はおすすめできません。なぜなら不動産投資ローンよりも金利が低い住宅ローンを使ったほうが得だからです。考え方を変えると投資用のマンションを買うということは、自分が住める場所を確保できるということでもあります。入居者がいるときには家賃収入があり、いないときには居住空間になるのです。
もし何らかの理由で家を出ざるを得なくなっても住む場所に困ることはないでしょう。高齢になると修繕費がかさむうえに不便な郊外の自宅を売り、駅近の賃貸マンションに引っ越す人は少なくありません。老後に住む場所または収入をもたらす投資マンションは心強い存在です。
空室は必ずしも脅威ではない
マンション経営にとって空室はリスクですが、考え方によってはチャンスでもあります。売却やリノベーションなどで収益アップを図るという「攻め」に転じることができるのです。必要以上に恐怖を感じてチャンスを逃すのはもったいないことです。(提供:アセットONLINE)
不動産投資の空室リスクを回避するための7つの方法
不動産投資には、天災リスクや金利上昇リスク、家賃滞納リスクなどのリスクがあります。ここでは、不動産投資で最も重要な「空室リスク」を回避する方法を解説します。

空室リスクの回避策:立地や管理会社を厳選、サブリース・空室補償の利用など

(写真=3DPhoto/Shutterstock.com)
なぜ、空室リスクが最も重要なのでしょうか。
建物を所有していても入居者がいなければ、家賃収入は0円です。それどころか、毎月ローンの返済があるため、持ち出しになってしまいます。したがって、空室リスクはできる限り回避しなければなりません。
以下に挙げる7つの方法を実行すると、空室リスクを回避しやすくなります。

(写真=3DPhoto/Shutterstock.com)
空室リスクを回避する方法1:都心部×人気駅×駅近にこだわる
不動産投資のセオリーは、好立地の収益物件を選ぶことです。特に学生や単身ビジネスパーソンが対象のワンルームマンションは、「都心部×人気駅×駅近」にこだわる必要があります。このうち1つでも欠けると、空室リスクは高まります。
しかし、好立地の重要性を理解していながら、妥協してしまうケースもあります。「物件価格が破格だった」「営業マンに押し切られた」といった理由で、妥協することのないように気をつけましょう。
空室リスクを回避する方法2:サブリースを利用する
空室リスクをヘッジする方法には、サブリースの利用もあります。これは、サブリース会社(管理会社や不動産会社がサービス提供することもある)と賃貸契約を結ぶものです。サブリース会社が入居者に転貸するため、空室が発生してもオーナーには毎月賃料が入ります。
オーナーにメリットのある仕組みですが、サブリース賃料は満室賃料の80~90%程度に設定されるのが一般的です。空室は回避できるものの、賃料が減る分低利回りになります。
空室リスクを回避する方法3:空室補償を利用する
補償額を満室賃料の80~90%程度に設定し、それを下回った場合に差額を給付金として受け取る仕組みです。一定の賃料を確保できる点はサブリースと同じですが、設定額を上回った分の賃料や敷金・礼金もオーナーの収入になる点が異なります。
サブリースや空室補償の内容は会社によって異なるため、個々のサービスをよく比較して検討すべきでしょう。
空室リスクを回避する方法4:入居率の高い管理会社を選ぶ
入居者も満足度を高めて安定経営をするには、入居者募集やクレーム対応を担う管理会社の対応力も重要です。管理会社の能力は、管理物件数と平均入居率(稼働率)に表れることが多いです。これらをチェックするとともに、サービスの方針もヒアリングしてみましょう。こちらも、複数の管理会社をよく比較した上で契約すべきです。
管理委託手数料は賃料の4~10%が相場ですが、「手数料が安い」という理由だけで選ぶのは危険です。
空室リスクを回避する方法5:再開発エリアを選ぶ
安定経営を実現するためには、現時点だけでなく、将来の空室リスクも想定しておく必要があります。現在大型の再開発が進行中、あるいは計画中であれば、今後エリアの価値が高まって賃貸ニーズも高まる可能性が高いです。
再開発の規模や内容、その波及効果などをチェックした上で、エリアを選定するといいでしょう。
空室リスクを回避する方法6:現地調査をする
立地環境は物件広告やGoogleマップでも確認できますが、やはり現地調査をするのがベストです。紙やネットでは気づかなかったマイナス材料に気づくかもしれないからです。たとえば、周辺に競合物件が集中していて空室が多かったり、嫌悪施設があったりするケースがあります。
空室リスクを回避する方法7:入居率の高いデベロッパー物件を選ぶ
デベロッパーが売主である直販の場合は、過去に施工したマンションの入居状況をヒアリングしてみるといいでしょう。過去の開発物件の稼働状況が良好な場合は、入居者に支持にされる物件を提供するデベロッパーである可能性が高いです。
注意点:「サブリース・空室補償=空室リスクゼロ」ではない
「サブリース」や「空室補償」を利用すれば、空室リスクがゼロになると考えている人がいますが、管理会社や補償会社が破綻すれば、賃料や給付金の貸し倒れが発生します。よって、信用できるパートナーを選ぶことが何よりも重要です。
以上、空室リスクを回避する7つの方法をお伝えしました。
事前に想定されるリスクを潰しておくことが不動産投資の成功に繋がりますので、ぜひ実践してみてください。(提供:Incomepress )
事前に想定されるリスクを潰しておくことが不動産投資の成功に繋がりますので、ぜひ実践してみてください。(提供:Incomepress )
不動産の未来を読み解く!開発・流通・投資の行く末は?
「衣・食・住」という、私たちの生活を支える基本3要素。そのうち、日本経済の発展にも深く関わってきた“住(不動産)”の動向は、景気の趨勢を示すバロメーターの役割を果たしてきたこともあり、指標として注視している人も多いことでしょう。加えて、不動産は中長期的な開発計画がベースになっていることもあり、今後の日本経済や社会情勢がどのように変化していくのかを予想するのにも役立ちます。
とくに、今後の動向として注目されているのが、2020年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」です。東京都内をはじめとして、五輪関連の工事が急ピッチで進められていることに加えて、五輪後も見越した“レガシィ”としての不動産開発にも力が入れられています。これから先、日本の不動産市場はどのように推移していくのでしょうか。過去の分析をふまえつつ、未来を読み解いていきましょう。
トレンドと不動産関連の大きな動き

(画像=Thampapon/Shutterstock.com)
ここ数年、ニュースでも取り上げられている不動産関連のトピックには、いくつかのキーワードがあります。たとえば、少子高齢化にともなう人口減少や、地方からの人材流出、空き家・空き地等の有休不動産活用などがその代表例ですが、その他にも、人生100年時代、働き方改革、女性・高齢者・外国人人材の活用、環境問題など、多種多様な話題が不動産市場の動向に直接的・間接的に関係しています。
そういったマクロ・ミクロの動きを注視しているだけでも、不動産関連のトレンドが見えてくるものです。重要なのは、未来を読み解く視点をもち、幅広い情報収集を重ねていくこと。その際のポイントは、特定の物事が市況に与える影響と、その因果論理を見通すことでしょう。ひとつひとつの出来事やムーブメントが、1年後、5年後、10年後にどうつながっていくのか。それが、予測の精度を高めます。

(画像=Thampapon/Shutterstock.com)
今後の不動産市場を読み解く
たとえば、国土交通省が開催している「社会資本整備審議会産業分科会不動産部会」では、各界の有識者が参加し、社会経済の変化をふまえた幅広い議論が行われています。特筆すべきなのは、不動産業の持続的な発展を図るために、10年程度先を見越した指針を設けていること。同会が作成している資料「新・不動産業ビジョン2030(仮称)」から、ポイントを絞ってその内容を紹介しましょう。
不動産「開発・分譲」について
不動産の開発・分譲に関しては、いわゆる「ストック型社会」への進展を見越し、良質な不動産を市場に供給することが重要とされています。具体的な内容としては、耐震性、省エネ性、ユニバーサルデザイン等に優れた不動産であることに加えて、老朽化した不動産の「たたみ方」まで含めた活用や、ホテル、MICE施設、物流施設、さらにはサテライトオフィス・シェアオフィスなどの活用も、新たなニーズとして注目されています。
不動産「流通」について
不動産の流通に関しては、不動産取引の透明性・安全性・信頼性を高めていくことに加えて、消費者や地域の多様なニーズに対応するためのコンサルティング能力向上についても言及されています。そのためには、設計士や建築士、金融機関などの幅広い関係者が相互にネットワークを構築し、よりきめ細かい需要に応えていくことが求められます。また、空き家問題の拡大をふまえ、より地域性を重視した不動産の提案も必要となりそうです。
不動産「投資・運用」について
不動産の投資に関しては、リート等の市場が資産規模30兆円を超えて拡大していくと期待されています。将来的には、米国に比肩する規模の上場リート市場を構成することを視野に、発展を続けていくと見込まれます。加えて、多様化する不動産投資業界の実情をふまえ、不動産投資リテラシーの向上や環境整備など、個人と業者双方への対応が求められます。フィンテックやAIの活用など、投資助言サービスの普及もその一翼を担うかもしれません。
不動産は過去と現在でみる
安全性と安定性が求められる不動産は、中長期的な視点で投資していくことが求められます。そしてそのための指標となるのは、現在だけでなく、過去と未来をふまえた、起こりうる変化や数値データなどです。完璧に未来を予測することはできませんが、過去と現在から未来を見通すことは可能です。そういった幅広い視点こそ、より堅実な投資につながるヒントをもたらしてくれることでしょう。(提供:YANUSY)
世界の不動産投資会社が日本に熱い視線を注いでいる!超低金利だからこそ不動産投資のメリットは大きい
世界の投資マネーが日本、特に東京や大阪などの大都市の不動産に対して熱い眼差しを注いでいます。今後も大規模な投資が相次ぎ、東京や大阪の不動産の資産価値への期待がますます高まりそうです。
イギリスのASIは高齢者向け住宅などで1,000億円の投資

(画像=takkun/Shutterstock.com)
海外の投資機関の日本への投資熱が高まっています。主なものだけみても、イギリスの運用大手のアバディーン・スタンダード・インベストメント(ASI)は、日本向け投資の専門部署を設けて、積極的な投資を目指しています。
ASIはイギリス最大であり、ヨーロッパでも第2位の運用会社で、世界中で幅広く投資を行っています。もともとは株式運用で知られる投資会社ですが、近年では不動産投資も活発で、その不動産関連の運用資産は、全世界で約6兆円にも達しているといわれています。
ASIでは、アジアの主要都市への関心を高めており、なかでも経済、社会が安定している日本の大都市への投資に積極的です。同社のホームページでは、日本市場を次のように取り上げています。
「(日本の住宅の)市場価格は2008年から10年間で15%と比較的緩やかな上昇にとどまっています。しかしながら日本では物件の供給戸数増加のため低層住宅から高層タワー型住宅へのシフトが促進されており、ユニークな市場といえるでしょう」
そのユニークな市場に対する投資の第1弾として、2019年中に高齢者向け住宅への投資をスタートさせる計画といわれます。既存の物件の取得だけではなく、新規の開発にも取り組む意向といわれ、最大では1,000億円程度の投資を見込んでいるようです。

(画像=takkun/Shutterstock.com)
「(日本の住宅の)市場価格は2008年から10年間で15%と比較的緩やかな上昇にとどまっています。しかしながら日本では物件の供給戸数増加のため低層住宅から高層タワー型住宅へのシフトが促進されており、ユニークな市場といえるでしょう」
アメリカのKKRは再開発などの大型案件に取り組む
また、アメリカ・ニューヨークに本部を置く投資会社、コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)は、2005年からアジアでの事業を開始し、現在ではプライベート・エクイティ分野では有数の投資会社に成長しています。
そのKKRは不動産ファンドなどから不動産投資、開発の専門家をスカウト、不動産分野への本格参入の準備を進めています。これまでも不動産の売買などを手がけてきましたが、今後は再開発などによって不動産の価値を高めた上で売却して利益を挙げることも目指すようです。KKRの最大のメリットは資金が潤沢であること。1,000億円単位の大型案件への投資も可能であり、日本の不動産市場に大きなインパクトを与えそうです。
これまでにも、ノルウェーの政府年金基金が東京都港区で1,300億円の複数ビルを購入、香港とフランスの投資会社が共同で1,000億円を投じて物流施設を取得、シンガポールの投資会社が東京都新宿区のオフィスビルを取得など積極的な投資が行われてきましたが、今後はさらに拍車がかかりそうな情勢です。
超低金利の日本は投資先として魅力に満ちている
海外の投資会社や投資ファンドなどが日本の不動産市場に強い関心を示している背景には、日本銀行のマイナス金利政策にともなう超低金利が背景にあるといわれます。低い金利で資金を調達してオフィスや住宅などの不動産に投資すれば、十分な利益をあげることができます。
日本、なかでも最も注目度が高いのは東京です。不動産投資による利回りは都心部で3%~4%前後ですが、2%台のロンドン、1%台のニュヨークに比べれば、まだまだ魅力に富んでいます。それも、世界の成長エンジンといわれるアジアのなかでも政治的、経済的に極めて安定しており、安心して大規模な投資を行うことができます。
実際、日本不動産研究所が行っている『第45回不動産投資家調査(2019年4月現在)』)によると、今後の日本の不動産市場を取り巻く環境においては、グラフにあるように海外からの投資の増大が最も期待されています。
海外からの熱視線を浴びる日本、なかでも東京の不動産の魅力がますます高まりそうです。(提供:YANUSY)
賃貸不動産の相続……やるなら換価分割?代償分割?
不動産投資家が亡くなった場合、問題になるのが賃貸不動産の相続です。相続する現預金が少ない場合、特に重大な問題となりかねませんが、一体どのように対処したらよいのでしょうか。今回は、賃貸不動産の相続の問題と対処法について解説します。
不動産投資家が増加した今、課題は「相続」

(写真=LookerStudio/Shutterstock.com)
日本経済の停滞や年金問題の深刻化とともに不動産投資を行う人が増えました。今後、課題になるのは「賃貸不動産の相続」です。土地神話が信じられていた時代なら尊ばれた賃貸不動産の相続ですが、今は重大な問題の一つになりつつあります。なぜなら相続財産が不動産ばかりで現預金が少ないとトラブルの元となるからです。
被相続人が不動産投資を積極的に行ってきた場合、相続財産のほとんどが不動産で現預金はわずかというケースも珍しくありません。しかし相続税の納付は原則金銭によることとされています。しかも被相続人の死亡から10ヵ月以内という短期間に納税しなくてはなりません。さらに不動産は現預金や有価証券に比べて分割の難しい財産です。
相続人が複数人いる場合、不動産は遺産分割協議において現預金のように平等に分けることが難しいため相続人同士の争いの原因になりかねません。家賃という果実を生む賃貸不動産はなおさら争いの対象となります。これらを踏まえたうえで賃貸不動産の相続を念頭に置いておくことが必要です。

(写真=LookerStudio/Shutterstock.com)
現預金が少ないときの対処法
相続財産のほとんどが不動産で現預金が少ない場合は、トラブルを避けるための手段として「換価分割」「代償分割」のいずれかが検討されることがよくあります。それぞれの内容は次の通りです。
換価分割
換価分割とは、不動産など現物として遺された財産を売却して現金にし、その現金を相続人間で分ける方法を指します。分割しにくい現物の財産が分割しやすい現金に変わるため、相続人間の不公平が小さくなりやすい方法です。相続人の誰もが現物財産を受け継ぎたくないときなどに用いられます。
代償分割
代償分割とは、相続人の内の1人に不動産などの現物の財産を承継させ、承継した相続人が他の相続人に対して金銭を支払うことで遺産分割を行う方法です。承継した相続人に現預金の余裕がある場合や被相続人と同じく不動産投資に積極的である場合に活用の価値があります。換価分割も代償分割も遺産分割に現金をあえて登場させることで納税トラブルも遺産分割トラブルも小さくする効果があるのです。
いずれを選んでもよいのですが、相続した不動産の実勢価格が取得価額よりも高く、節税をしたいのなら代償分割を選んだほうがよいでしょう。
節税したいなら「代償分割」を選ぶべき理由
節税したいのならなぜ代償分割を選ぶべきなのでしょうか。なぜなら換価分割は相続税だけでなく所得税も納付しなくてはならない可能性があるからです。換価分割は現物財産自体を売却し、金銭に換えます。このとき売却益つまり譲渡所得が発生したら所得税と住民税を申告・納付しなくてはなりません。このときの譲渡所得と税額の計算は次のように行います。
譲渡所得の計算
譲渡所得の金額=売却代金-(取得費+譲渡費用)
所得税・住民税の計算
税率は不動産の保有期間によって次のように分かれます。
【所有期間が5年以下の場合(短期譲渡)】
譲渡所得の金額×39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
【所有期間が5年超の場合(長期譲渡)】
譲渡所得の金額×20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※どちらも復興所得税を含む
例えば相続人AとBで不動産(取得費と譲渡費用あわせて3,000万円)を相続し、5,000万円で売却した場合、AとBはそれぞれの譲渡所得は(5,000万円-3,000万円)×2分の1=1,000万円となります。この1,000万円に課される所得税・住民税を申告・納付することが必要です。相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産を売却した場合、納付済の相続税の一部を譲渡所得計算上の取得費に加算することができます。
ただ「所得税・住民税を支払わなくてはならない」「売却に際し手数料や手間が別途かかる」といったことなどを考えると換価分割は熟慮が必要だといえるでしょう。
譲渡所得の金額×39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
譲渡所得の金額×20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※どちらも復興所得税を含む
共有はできれば避けよう
現預金が少ない場合の不動産の相続方法には、もう一つ「共有」という方法があります。相続人で一つの不動産を共有し、ともに管理していくのですが、これはあまりおすすめできません。なぜなら改装や契約など一つ一つの法律行為に共有者全員の同意が必要であるうえ、共有者の子どもや孫に持ち分が承継された後、トラブルの元となりやすいからです。
賃貸不動産は自宅と異なり収益や経費が発生するだけでなく、さまざまな法律行為が求められます。どのような相続を選択するにせよ慎重になったほうがよいでしょう。(提供:YANUSY)
不動産賃貸管理…「自主・集金代行・サブリース」どれを選ぶ?
不動産の「賃貸管理」は、大きく3種類
不動産投資をするうえで、賃貸管理にはどういった種類があるのか知っていますか? 不動産管理には、「自主管理」「集金代行管理」「サブリース管理(借上げ保証・家賃保証など)」と、大きく3種類あります。
自主管理は不動産賃貸管理会社の力を借りず、自らの力で入居者を募集し、家賃回収や問い合わせ、退去時の対応などを含めて、自ら行うことです。メリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。
【自主管理のメリット】
・定期的なコストがかからないため、家賃を丸々もらえる
・自分で入居者を決めることが出来る
・使途不明の請求等が来ない
・リフォーム会社等含め、全て自分で決定できる
【自主管理のデメリット】
・入居募集活動をしなければならない
・時間と労力を費やす
・入居者から直接クレームを受ける場合がある
・空室のリスクがある(ネットなどで大々的に賃貸募集ができない場合は特に注意)
集金代行管理は、ほとんどの不動産投資家が契約するスタイルです。その多くが家賃の3~5%を集金代行費用と称して、入居者の募集から、管理中の家賃集金代行、退去時の立会いなどを賃貸管理会社が投資家に代わって行います。メリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。
【集金代行管理のメリット】
・家賃の〇%という、双方WIN WINな関係で、家賃が高くするメリットが双方にあるため、家賃を高く設定した際にも、協力的な可能性も高い
・募集作業、集金作業、入居者からのクレーム対応、退去時の立会いなど全て代行してくれる
・賃貸管理会社などによっては滞納保証や、家賃保証に切替えることができるオプションもある
・礼金や更新料を貰えるケースがある
【集金代行管理のデメリット】
・空室になっても賃貸管理会社が失うものが小さい為、あまり募集に力を入れない賃貸管理会社も多く存在する
・自分では入居者を選べない
・リフォーム費用を含め、請求してくる業者任せの為、請求額に応じるしかないことも多い
・毎月の手数料がかかる(3~5%税別)
サブリース管理は、賃貸管理会社が部屋をオーナーから借上げ第三者に又貸しすることをいいます。会社によって呼び方は違う場合や、明確な定義が存在しないことが多く、各会社がオリジナリティを出せるものです。
逆をいえば、各社定義が違うものが多く、しっかり見極める必要があります。サブリース契約を破棄した会社がニュースになり、社会問題に発展したこともあるので、選択する際には注意が必要です。メリットとデメリットは、それぞれ以下の通りです。
【サブリースのメリット】
・オーナーと賃貸会社とで契約しているため、空室や家賃滞納を気にしないで済む
・入居中の管理や対応は一切関与しない為、ストレスに感じない
・長期的なサブリース契約の場合は安定収入が見込める
【サブリースのデメリット】
・賃貸管理会社の契約内容次第では、解約されてしまう可能性もある
・手数料が集金代行に比べると高い(設定家賃の10%~20%程度)
・契約次第では免責期間や、解約に要する期間が異なる為、融通が利かない可能性がある
・礼金や更新料等を受け取ることができない

管理の方法で収益に差が…

管理の方法で収益に差が…
不動産の管理方法の「選択基準」は?
不動産の管理方法には、3つの種類があります。どのように選択すればいいのか、判断基準を見ていきましょう。
まず自主管理の絶対条件として、募集を自身で行わないといけないので、最初から入居者がいる状態で、なおかつ緊急時に駆け付けられるように自宅付近であることが望ましいです。清掃管理なども含めて、近所であるほうが、管理をする上で便利だからです。
また入居者とのトラブルを避ける意味でも、自身の不動産知識があることも大きな条件になります。親せきや友人に貸す場合などは自主管理を選択される方も多いです。
他人に貸す以上、入退去時の専門的な対応方法など含めて、自主管理の場合は注意が必要です。また一棟オーナーであれば、立地や建物の構造によっては空室部分を旅館業申請して、旅館業として展開することもできます。こちらは旅館業をメインに扱っている専門家とのタッグが望ましいといえますが、空室対策としても注目されています。
物件が自宅周辺になく、信用できる賃貸管理会社で集金代行を活用するといいでしょう。すでに賃貸中の物件に投資する場合には、そのまま管理形態を継承する可能性もあります。
また、都市部の人気エリアは適正な家賃設定である限り、借手は付きやすいということもあるため、集金代行が適しています。ただし、常に空室のリスクが付きまとうので、頻繁に入居者が入れ替わるワンルームタイプの単身者向けマンションではなく、入替えの頻度が少ないファミリーマンション物件の賃貸管理に向いているともいえます。
サブリース管理は集金代行管理と比べると、取扱いの手数料は上がります。その分収入面では劣るところもありますが、それ以外のメリットで見るとサブリース管理は優秀ではあります。特に戸数が多いマンション・アパートは複数空室になった際に、相場より少し家賃を低めに設定しないと、借手が付きにくくなる傾向があります。
またワンルームマンションの入居者は単身者で、学生は卒業、社会人は転勤や結婚を機に退去するなど、入退去のサイクルが早く、空室になる機会が多いので、ワンルームタイプの場合はサブリース管理がおすすめです。
また、中古物件でも「現況空室」となっている物件の場合は、いつ借手が付くかはわからない不安が付きまといます。購入時に空室の場合は、サブリース管理契約をおすすめします。
さらに長期的運用で考えている方の場合は、どんなに好立地であっても、永久に空室が起こらないということはないことから、サブリース管理も一考するといいでしょう。
石田ゆり子は「3軒7億円」爆買い!「不動産王」芸能人荒稼ぎ実態

石田ゆり子

不動産投資セミナーの個別相談で聞いておきたい4つの成功ポイント
不動産投資セミナーは本や資料などの情報と違い、直接実際に不動産投資をしている人や専門家の話を聞くことができたり、具体的な運用方法を学んだりできる点でメリットが大きいと言えます。
また、多くのセミナーでは個別相談の時間があり、専門家に個別に話ができる機会を設けています。個別相談では大勢の人前では聞けないことが確認できたり、専門的なことをプロに直接質問したりすることができますので、積極的に利用したい機会です。
この記事では不動産投資セミナーに参加する際に準備しておきたいことや、個別相談の効率的な使い方についてご紹介します。
目次
- 不動産投資セミナーの流れ
- 不動産投資セミナーのテーマ事例
- 個別相談を使うメリット4つ
3-1.疑問をその場で解決できる
3-2.大勢の人の前では聞きにくいことが聞ける
3-3.不動産投資に関する具体的な相談ができる
3-4.専門家とのつながりができる
- 不動産投資セミナーに参加する前に準備しておきたいこと
4-1.自分の希望をはっきりさせてセミナーに参加する
4-2.どの状態まで話を進めるかを決めておくことが大事
4-3.セミナー主催会社のことを事前に調べておく
- 個別相談で聞いておきたいこと4つ
5-1.セミナーで分からなかったことや初歩的な質問
5-2.節税やローンなど専門的な内容
5-3.初期費用や物件のあるエリアなど投資に必要な内容
5-4.利用を検討する管理会社の概要
- 個別相談をセミナー以外でも行っている不動産会社
- まとめ
3-1.疑問をその場で解決できる
3-2.大勢の人の前では聞きにくいことが聞ける
3-3.不動産投資に関する具体的な相談ができる
3-4.専門家とのつながりができる
4-1.自分の希望をはっきりさせてセミナーに参加する
4-2.どの状態まで話を進めるかを決めておくことが大事
4-3.セミナー主催会社のことを事前に調べておく
5-1.セミナーで分からなかったことや初歩的な質問
5-2.節税やローンなど専門的な内容
5-3.初期費用や物件のあるエリアなど投資に必要な内容
5-4.利用を検討する管理会社の概要
1.不動産投資セミナーの流れ
不動産投資セミナーは一般的に2部制か3部制になっています。2部制では1部でその日のトピックとなるテーマで専門家が講話を行います。1部のテーマがそのセミナーのメインの講話となりますので、参加する前に自分の投資スタイルや、不動産投資に求めているものと大きく違っていないかどうかを確認することが大切です。
1部の講話が終わったら、2部が個別相談になります。個別相談は任意参加になることがほとんどですので、参加意思がなければ参加する必要はありません。3部制の場合は、1部と2部が専門家の講話で、3部が個別相談になります。
基本的にはこのような流れで、2部制でも3部制でも個別相談の時間が取ってありますので、この時間を有効的に使うようにしましょう。
2.不動産投資セミナーのテーマ事例
不動産投資セミナーのテーマにはどのようなものがあるのでしょうか。参考にマンション投資の会社が実施しているセミナーのテーマを見てみましょう。(2019年10月時点)
湘建
- 大人が知りたい資産運用のキホン
- リスクが嫌いな人の資産運用のはじめ方
- 女性司会者が楽しく伝える「失敗した投資」
グローバル・リンク・マネジメント
- 日本一わかりやすい投資不動産セミナー/FP無料相談特典付き
- 0からはじめる不動産投資セミナー/FP無料相談特典付き
- 不動産投資を決断する前に知っておくべき5つのコト
- 年収1000万円以上が分岐点!ゼロから始める【節税×資産形成】
プロパティエージェント
- 0から始める不動産投資セミナー
リズム
- マーケティングで成功を勝ち取る!戦略セミナー
- ベテラン投資家に学ぶ基礎知識!実践セミナー
FJネクスト
- 不動産投資の真実!あなたは本質が見えていますか?
このように、セミナーではそれぞれテーマが決まっていますので、「参加したけど自分には合わなかった」ということが無いように、自分が必要とするテーマを探して参加することが大切です。
3.個別相談を使うメリット
では、セミナー後に個別相談をした場合、どのようなメリットがあるのかを見てみましょう。
3-1.疑問をその場で解決できる
1部や2部で専門家の話を聞いた際に疑問が生じた場合、個別相談で質問することができ、そこで解決できることが考えられます。本を買って読んだり、資料を取りよせただけでは、疑問が生じた場合でも解決するのに時間がかかったりすることがありますので、セミナーに参加した場合は個別相談を有効活用するようにしましょう。
3-2.大勢の人の前では聞きにくいことが聞ける
講話の際に質問を受け付けてくれても、初歩的な内容やお金に関することなどは、みんなの前では恥ずかしいという気持ちが先に立ち、質問しにくいことも考えられます。個別相談では担当者と専門家(税理士や会計士、FPなど)の2人で聞いてくれたり、専門家1人だけだったりすることもありますので、大勢の人の前では聞きにくいことでも聞きやすくなるでしょう。
3-3.不動産投資に関する具体的な相談ができる
そろそろ不動産投資を始めようかと思っている時など、どのような運用になるかといった質問は、時間がかかりそうなので相談しにくいものです。しかし、個別相談ではそういった話もすることができます。
詳細は別の機会に時間を取ってする形にはなったとしても、こちらの希望を不動産会社に伝えたり、投資にあたって準備するものを聞けたりしますので、先に話を進めることができます。
3-4.専門家とのつながりができる
一度個別相談をしていれば、後で何かあった時にもその人に相談ができる可能性があります。普段は専門家と知り合う機会はあまりありませんので、このような機会を利用して相談していれば、その後機会があった際にも話ができたり、内容によっては気軽に相談に乗ってくれたりする可能性もあります。
個別相談を通して知り合いになっておくことは、専門家のネットワークを広げることにもつながりますので、積極的に利用するようにしましょう。
4.不動産投資セミナーに参加する前に準備しておきたいこと
せっかくセミナーに参加しても、質問が的外れだったり、聞きたいことが聞けなかったりすると、質疑応答や個別相談の時間を損してしまいますので、セミナーに参加する前には十分な準備をしておくことが大切です。何を準備しておけば良いのかを見てみましょう。
4-1.自分の希望をはっきりさせてセミナーに参加する
セミナーを開催している会社によって取り扱っている物件のあるエリアが違っていたり、紹介してもらえる金融機関が限られたりします。そのため、自分の希望をはっきりさせてセミナーを探すことが大切です。例えば投資をする目的や、投資対象は中古なのか新築なのかといったこと、また初期費用はいくらくらい用意できるかといったことです。
そのような質問事項を事前にまとめることで、参加すべきセミナーが絞られてきますし、参加した際に積極的に質問もできるようになります。
セミナーを開催している会社によって取り扱っている物件のあるエリアが違っていたり、紹介してもらえる金融機関が限られたりします。そのため、自分の希望をはっきりさせてセミナーを探すことが大切です。例えば投資をする目的や、投資対象は中古なのか新築なのかといったこと、また初期費用はいくらくらい用意できるかといったことです。
4-2.どの状態まで話を進めるかを決めておくことが大事
セミナーに参加する際は、そのセミナーでどの段階まで話を進めたいのかを考えておきましょう。他のセミナーと合わせて勉強目的で参加するのか、融資の金利相場や注目エリアや物件価格などの情報収集をしたいのか、あるいはそのセミナーで良い物件があれば購入の話に進み、不動産投資を始めてみたいのか、といった意思決定に関することです。
話をどこまで進めるかによって、個別相談で話す内容もある程度範囲が決まってくるので、どの状況まで進展させたいのかを考えてセミナーに参加するようにしましょう。
4-3.セミナー主催会社のことを事前に調べておく
セミナーを開催している会社のことは十分に調べておくことが大切です。上場しているか、物件の管理は自社で行っているかどうかなどを知ることで、自分がセミナーに参加してメリットがあるのかどうかが見えてきます。
具体的に不動産の購入を考えている場合、セミナーの内容や主催会社のスタンスが自分の求めている投資スタイルと合っていなければ、セミナーに参加しても話を前に進めることは難しくなります。そのようなことがないように、セミナーを行っている会社のことはきちんと調べるようにしましょう。
5.個別相談で聞いておきたいこと4つ
個別相談のメリットを有効活用できるように、現場ではどのようなことを聞けば良いのでしょうか。個別相談の際に聞いておいた方が良いことについて見てみましょう。
5-1.セミナーで分からなかったことや初歩的な質問
個別相談では大勢の前では聞けないようなことも聞けるメリットがあります。個別に相談できる場ですので、初歩的な質問や疑問に思っていても恥ずかしくて大勢の前では聞けない、といったことでも漏れなく聞いて解決できるようにしましょう。
5-2.節税やローンなど専門的な内容
個別相談はセミナーに講師として登壇した専門家が担当として相談を受ける場合がありますので、その際はその分野の専門的な質問をすることができます。その際は遠慮せずに踏み込んだ質問をして問題を解決するようにしましょう。
5-3.初期費用や物件のあるエリアなど投資に必要な内容
個別相談の担当者が不動産会社の営業マンの場合は、その会社が行っている不動産投資の内容に精通していますので、取引についての詳細な質問をするといいでしょう。
投資する物件のタイプやエリアによって必要資金が違ってきますので、取り扱っている物件が新築なのか中古なのかといったことや、対象エリアなどを個別相談の際に確認しておくようにしましょう。
セミナーや個別相談の中で気に入った物件の紹介があれば購入して投資を始めても良いという場合は、取り扱い物件の価格や初期費用の額、提携金融機関なども聞いておくようにしましょう。
5-4.利用する管理会社の概要
不動産会社によって自社で管理業務をしている場合と、自社では管理を行わず委託している場合があります。管理会社によっては管理物件の入居率が99%を超えていたりすることもあり、委託する管理会社によって運用状態は変わります。そのため、物件を購入する際は委託する管理会社はどこになるかを聞いておくようにしましょう。
6.個別相談をセミナー以外でも行っている不動産会社
個別相談はセミナーだけで行われているわけではありません。仕事の都合などでセミナーに参加できない人のために、ある程度希望の日時に合わせて個別相談の時間を取ってくれる会社があります。以下に個別相談を行っているFJネクストの相談会概要を記載しておきます。
株式会社FJネクストが行う個別相談会
- 50分のFJ個別相談会
※決まった日時ではセミナーに参加するのがむずかしい方。
※前日までの予約制になります。
- 10:00~20:00の50分間
※決まった日時ではセミナーに参加するのがむずかしい方。
※前日までの予約制になります。
まとめ
不動産投資セミナーに参加した際に個別相談をうまく使う方法と、セミナーに参加する前に準備しておきたいことについてご紹介しました。セミナーでは基本的に個別相談の時間が取ってあります。個別相談では専門家とも個別に話ができますので、目的に応じて参加して効率的に使いたいものです。
個別相談では2~3人程度と少人数で行われますので、大勢の人の前では聞けないことが聞けたり、時間がかかりそうな相談もしたりすることができます。また、相談をすることで専門家との接点ができますので、ゆくゆく何かあった時に相談に乗ってくれる人を作れる可能性も広がります。
個別相談をする際は、時間が無駄にならないように、相談する内容を前もって準備しておくことが大切です。不動産投資を成功させるためにも個別相談を有効に活用するようにしましょう。
何故か潰れない「町の不動産屋さん」、ついに破滅の危機迫る
オリンピックも近づき業界は活発化しているものの…
不動産市場は現在、活況にあるといってよいでしょう。国土交通省が毎月発表している「不動産市場動向マンスリーレポート」[図表1][図表2]や土地代データの「日本全国の地価推移グラフ」[図表3]によると、確かに前年よりは落ち着いてきた感はありますが、それでも不動産市場全体は2013年から緩やかに右肩上がりの傾向にあります。
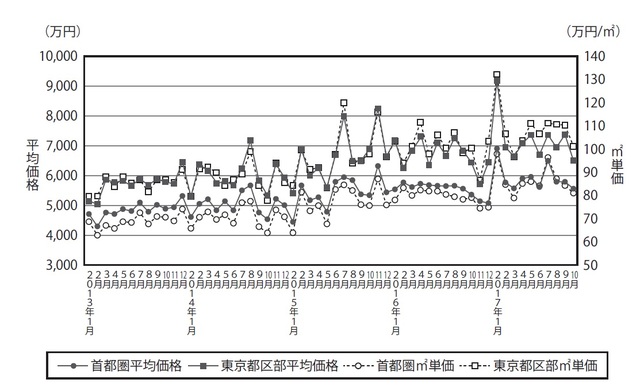
[図表1]〈新築マンション:首都圏・東京都区部〉平均価格と㎡単価の推移 出所:不動産経済研究所「不動産経済調査月報」、「全国マンション市場動向」
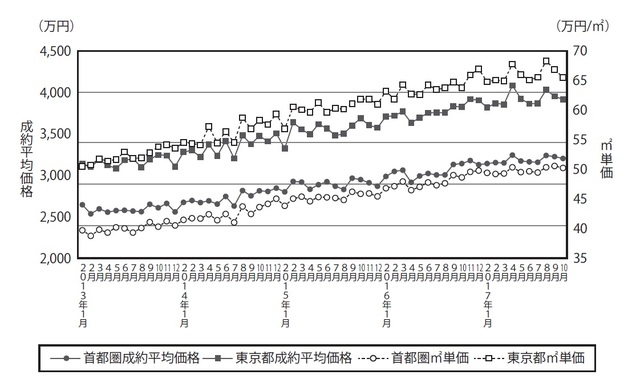
[図表2]〈中古マンション:首都圏・東京都〉成約平均価格と㎡単価の推移出所:(公財)東日本不動産流通機構「マーケットウオッチ」
これはおそらく、安倍晋三内閣による「アベノミクス」効果などが影響し、住宅ローンの金利も低下したうえ、中国を中心とした海外からの不動産投資が増えてきたことなどによるものだと推測できます。
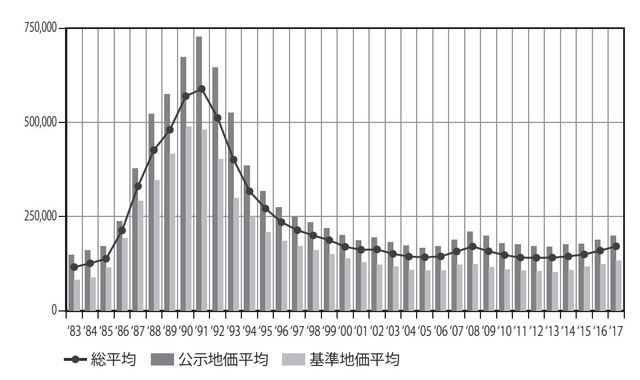
[図表3]土地代データ「日本全国の地価推移グラフ」
中国富裕層の「爆買い」が一旦収まり、高騰しすぎた価格は適正価格へと下がってきたものの、今なお新築マンションは続々と建設されています。2020年の東京オリンピックを控え、インフラやホテルの整備などで地価が上昇していることも一因でしょう。
また特に東京を中心とした首都圏の中古マンションの人気は依然衰えず、不動産市場の底上げに貢献しています。住宅ローンが低金利のうちに住宅を購入する、または相続税対策や自己年金創出のためにマンションやアパートなどの不動産を購入するという人が増えているからだと思われます。特に都心の物件やターミナル駅周辺の物件の売買は堅調で、しばらくは安定した資産として投資対象になっていくでしょう。
その一方で、2016年度の不動産仲介業の倒産は前年度を上回っており、そのうちの7割は負債5000万円未満の小規模企業であるという事実もあります。
不動産市場が好況だとはいっても、オリンピック関連施設や大規模商業施設や高層マンションなど大型事業の建設はごくひと握りの大手一流ゼネコンに集中しているのが現状です。同様に、不動産売買や賃貸の分野も名の知れた大手にかすめ取られ、中小不動産業はほとんど恩恵を受けていません。その結果がこの倒産数から読み取れます。
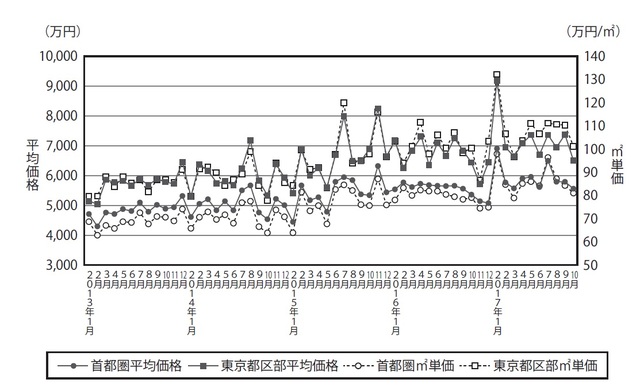
[図表1]〈新築マンション:首都圏・東京都区部〉平均価格と㎡単価の推移 出所:不動産経済研究所「不動産経済調査月報」、「全国マンション市場動向」
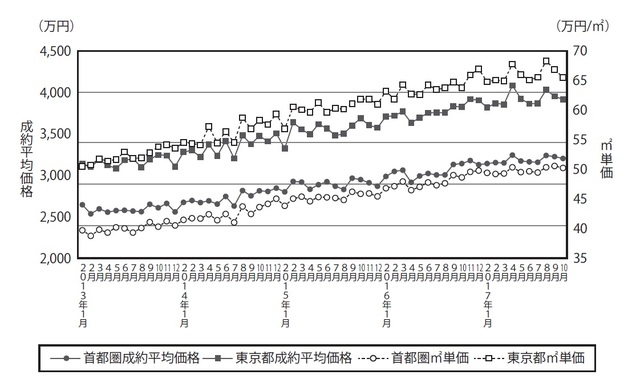
[図表2]〈中古マンション:首都圏・東京都〉成約平均価格と㎡単価の推移出所:(公財)東日本不動産流通機構「マーケットウオッチ」
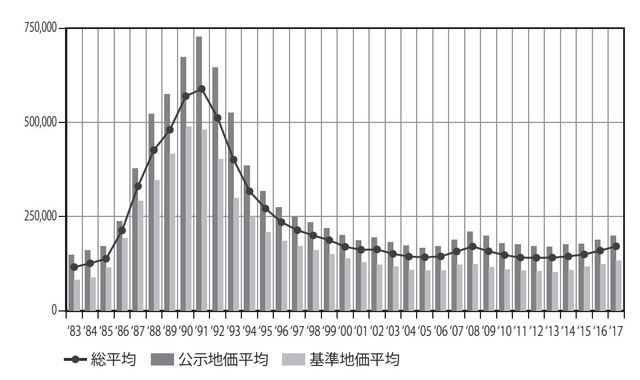
[図表3]土地代データ「日本全国の地価推移グラフ」
大企業の「絨毯爆撃」に立ち向かう手段はない
建設部門はさておき、不動産売買や賃貸などの仲介業で、なぜ中小企業が破綻していくのか。それには当然とも思える理由があります。
やはり圧倒的に不利なのは、企業の持つネームバリューやイメージの差です。大手の中には旧財閥系や電鉄の冠がついているところもあり、テレビCMや広告などで目立っています。全国規模で事業展開しているため支店数や社員数、資金力など企業規模がそもそも異なります。すでに名前を知られているということは、売る側、買う側、貸す側、借りる側にとって存在感や安心感があり、とても大きなアドバンテージとなります。
また不動産情報の提供にはインターネットが駆使され、昨今の住居探しのスタイルが大きく変化したことも影響しています。たとえばひと昔前、大学進学や就職で上京した若者たちは、自分の住みたい場所、学校や勤務地に通うのに都合のいい場所の見当をつけ、その駅に降り立って駅前の不動産屋に飛び込むというスタイルが主流でした。後にアパマン関連の情報誌が台頭しますが、それでも実際に管理する不動産屋に連絡し、部屋を見て決めていました。
ところが、近年ではパソコンやスマートフォンなどから住居を検索し、場合によっては実際に行かなくても写真や動画などで部屋を選ぶことができるまでになっています。
不動産は通常の場合、指定流通機構に情報を登録しなければならず、数あるウェブサイトも駅前の不動産屋も、一部の例外を除いて同じ情報を共有しているので、どこからアプローチしても同じデータが出てきます。
ただ、これだけインターネットが進化した時代になると、せっかくの休日にわざわざ出かけて何となく住まいを探すより、自宅からインターネット経由で情報を数件に絞り込んで、ピンポイントで探すほうが圧倒的に便利で楽なことは間違いありません。
そうなると、ユーザーが検索しやすいウェブサイトを作ることができる技術や資金力を持ち、大量の情報提供ができる大手不動産業者のほうが有利なことは明らかです。大手不動産業者が有名なポータルサイトや通信事業者と提携してしまえば、町の不動産屋は出る幕ではありません。
一方、管理オーナー、つまり大家さんの側としても、従来のように地元の不動産屋にお願いすることが減っています。それは、不動産売買や賃貸系の大手企業が、知名度と機動力を駆使して、まるで「絨毯爆撃」のように、ある一帯に住む大家さんや不動産を売りたいと考えている潜在的なオーナーたちの掘り起こしと取り込みに入っていくからです。まったくその土地に縁もゆかりもない企業ですが、名前が知られているために大家さん側も「ここなら大丈夫そう」と安心し、お願いすることになります。
大手企業の取り込み方も優れており、たとえば仲介手数料を半額にする、広域な情報提供が可能なことをアピールする、何かしらの特典を付ける、といった方法で多くの大家さんを囲い込んでいきます。そもそも資金力があり、扱う件数も多いとなれば、多少のサービスはいくらでも可能です。
またアパートを経営している大家さんがもっとも恐れるのは、空室ができることです。大家さんが高齢の場合、年金だけでは足りずに家賃収入を当てにしている方は実際に大勢います。若い大家さんの場合は、家賃収入の一部を建築ローンの返済に利用している例が多々あります。こんなケースで一部屋でも空きができると、収入が不足することになり、自身の生活に支障をきたしかねません。
一方、個人で経営していると宣伝ができず住人の確保が難しくなります。さらに住人の管理以外にも、アパートの補修や清掃など大変な手間がかかり、その労力だけで参ってしまうこともあります。
こうした大家さんに対して「情報提供はウェブでいくらでも可能です」「うちが清掃や管理もすべて代行します」などと大手不動産業者が歩み寄ってくれば、空室も埋めてくれる可能性が高く、管理全般を任せることができます。多少の手数料を取られても、自分の手を離れて自動的に収入が入ってくるのであれば、こんなに楽なことはありません。
大手は管理しているアパートやマンション、戸建住宅などに修理やリフォームが必要になれば、大家さんに連絡して修理や建て替えなどを勧めることもあります。建物がきれいになれば、またそこで資産価値がアップし、空室ができても少し高い家賃で入居させることができます。やがて建物が古くなって人が入りにくくなったり、大家さんが亡くなって資産を分与する形になったりしたときに、その土地・建物を買い取って別の買い手に転売すればいいのです。
この手法は中小不動産屋でも同様に行っていることではありますが、大手が積極的に大家さんに働きかけ、面倒見の良さをアピールすれば大家さん側もそのまま任せてしまおうと考えるのは当然です。言い換えれば、町の不動産屋はこのような積極的な営業努力をあまりしてこなかったということにもなります。
このような形で、大手は強大な総合力を使って無縁の地域に入り、大家さんたちの懐に入り込んでいくのです。もちろんそれは悪いことではありません。むしろ大手なりのしっかりとした営業努力です。大手不動産業者の機動力には、通常の街場の不動産屋がどうあがいても歯が立ちません。
大手の機動力と粘り強さを理解するうえでわかりやすいのは、表参道ヒルズや虎ノ門ヒルズなどを手掛けた森ビル株式会社の事業です。森ビルは東京のど真ん中、大勢の人が集まる地域にマンションや事務所が入った複合型商業施設を建てることで知られています。そのプロジェクトのひとつひとつが、気の遠くなるような作業の積み重ねの上に成り立っています。
「さほど動かなくても食べていける」に甘んじていた
東京都心は、戦後の焼け野原から復興した土地柄、どこの誰が土地の所有権を持っているのか容易にはわかりません。法律上、どんな小さなスペースでも、その所有者をきちんと見つけ出さなければ土地を取得できないため、何年もかけて果てしない追跡調査と交渉を試み、小さな地面を買い集めてひとつの巨大な土地を確保するのです。
地域一帯の避難所となる防災設備を整えれば、建設の際に国からの補助金も得られます。このように砂浜から粒を集めてひとつにまとめるような作業は、いくら土地勘のある住民でも簡単にはできません。それをやり遂げてしまうのが森ビルという会社です。
こうした機動力と粘りは、町の不動産屋にはありません。人づて、業界づてに「あそこの土地が売りに出そうだよ」という話を聞いて、良さそうなら「じゃあ、引き受けるか」と土地を買い、アパートにしたり、そのまま販売したりする「受け身」の仕事が主となります。私の会社も、以前はそんなタイプの不動産屋であったことを否定はしません。
また町の不動産屋の悪いところは、さほど動かなくても食べていけるだけの利益が出てしまうという点です。管理しているのがかなり古ぼけたアパートでも、人が入ればそこそこの収益になってしまいます。空室があってもほかの何部屋かが借りられていれば、仲介手数料という収益が入ってくるわけです。どんなに古い建物で空室があっても、たまに空き部屋に人が入ってくれれば、収益が増えるので願ったり叶ったりです。
このように積極的な働きかけを行わなくても、町の不動産屋はとりあえず収入を得られるので、駅前などでじっとしていてもさほど困らず暮らしていけることになるのです。これが「町の不動産屋」の実態です。
そんな競争も何もない地域に強大な力を持った大手不動産業者が乗り込んできて、見る見る間に、本当は商売になったであろう不動産を奪われてしまい、最終的にその一帯は大手が扱う物件ばかりに偏ってしまうのです。町の不動産屋はどんどん追いやられ、手持ちの物件もいつの間にか失い、気がつけば負債だけを背負って倒産する。これが、中小不動産業者が生き残れない現代の業界事情です。
賃貸経営に活用しよう!保険申請における保険代理店の重要性
保険は物件購入時に検討して決める人が多い傾向です。また、その際に検討するのは保険代理店ではなく保険の補償内容と費用という人が多いのではないでしょうか。なかには特定の保険代理店がすでに決まっているという人もいるかもしれません。
しかし保険金請求の手続きをしてみたり、保険代理店の切り替えをしたりすると「どこの保険代理店で保険を入会するか」が保険の補償内容や費用と同じぐらい重要なことがわかります。特に1棟を所有している人は保険金請求の機会が比較的多い傾向のため、なおさら重要です。そこで今回は不動産投資における保険代理店の選定の重要性について解説します。
保険金請求に協力的な代理店は少ない

(写真=Joyseulay/Shutterstock.com)
保険金はなかなかもらえないものというイメージを持っている人も多いかもしれませんが、補償内容に含まれる被害に遭って必要な請求を行えば保険金は下ります。しかし保険金請求に協力的な保険代理店は少ない傾向という一面もあります。なぜなら保険代理店として保険加入者に支払っている保険金の金額が大きくなればなるほど、損害率の数値が上がり保険会社から保険代理店への手数料が減少するからです。
保険代理店は自分たちがもらえる手数料が少なくなるのを避けたいため、「保険金請求を積極的に行いたくない」という実情もあります。その結果、保険金請求に協力的でない保険代理店も出てきてしまうといえるでしょう。ただし台風15号のような甚大な被害を及ぼした災害によって起こった被害の保険金請求は損害率の計算に含まれないなど、保険代理店としての手数料が少なくならないように保険金申請をすることも可能です。
こういった隙間を理解して自分たちの手数料は下げずに、保険金請求に協力的に動いてくれる保険代理店も存在します。もちろん、手数料に関係なく保険金請求に協力的な保険代理店がいることも事実です。そのため保険代理店を選ぶ際に不動産投資家は、このような保険代理店と付き合っていくことが望ましいでしょう。

(写真=Joyseulay/Shutterstock.com)
請求のやり方により保険金認可の判断が変わる
保険金の請求自体はそこまで難しくありません。保険会社の事故受付センターに連絡を行うと自分の住所に保険金請求書が郵送されます。保険金請求書が届いたら請求書に振込先口座情報など必要事項を記載し、被害箇所の写真および被害箇所を修復するための工事見積書を同封して保険会社に送付するだけです。
流れは簡単なのですが「添付する写真」「見積書の記載方法」などは一工夫したほうがよりスムーズに保険金が支払われます。ある保険請求コンサルタントによると、あまり詳細に伝えないほうが良いというのが一般的見解です。保険会社は、被害とは関係ない経年劣化による被害に対しては保険金を支払いません。そのため見積書の内容を詳細にすることによって、本当に災害により被害にあったにもかかわらず、経年劣化として判断され、その部分だけ保険が下りないという可能性もありえるのです。
保険会社が「どのような考えを基にどのような判断をしてくるのか」については、保険金請求をする機会が少ない不動産投資家より、日常的に保険金請求をしている保険代理店のほうが熟知しています。したがって請求書の記載方法や添付写真の選択を間違えるだけで保険が下りない結果になる可能性があるのであれば、保険金請求は保険代理店に相談したり任せたりすることも方法の一つです。
保険会社より保険代理店で選ぶべき
実際に保険請求をしたことがないと保険は保険会社や補償内容が重要だと思い込んでいる人も少なくありません。しかし実務上は保険代理店のサービスの良し悪しやノウハウを十分に調べ、活用することが重要です。もちろん、万事の際、保険金を出し渋るような保険会社は論外ですし補償内容も大切な項目になります。しかしどんなに保険会社や補償内容が充実していても、保険金請求をするとき効果的かつスムーズに保険でカバーできないのであれば結果的に損する可能性も否めません。
契約時に保険金請求について協力的に行う姿勢を見せる保険代理店も多いですが、本当に協力的かどうかは実際に保険金請求をしてみないことには判断が難しくなります。そのため口コミや不動産投資家の仲間がいれば人づてに良い保険代理店を探していく方法がおすすめです。物件購入時に1から探している時間はないと思うので、購入前に信頼できる保険代理店と関係を構築しておくよう心がけましょう。(提供:YANUSY)
東京都心と郊外のマンション投資、どちらが得?メリット・デメリットを比較
マンション投資をする際に、都心と郊外どちらのエリアで投資しようかと迷われる方もいるでしょう。都心は賃貸需要が高く長期的に収益が発生する可能性が高いものの、価格帯は高くなります。
逆に郊外は価格帯が低く始めやすいのですが、数十年後の入居率がどれくらいあるのかが気になります。マンション投資をするならどちらが得なのでしょうか。
この記事では東京都心と郊外でマンション投資をする際の、メリットとデメリットを確認した上で目的にあった投資方法をご紹介します。
目次
- 東京都心でマンション投資をするメリット
1-1.職住近接で賃貸ニーズが高まっている
1-2.転入者数が多い
1-3.資産性が高い
- 東京都心でマンション投資をする際に考えられるデメリット
2-1.価格が高く利回りが悪い
2-2.固定資産税などが高くなる
- 郊外でマンション投資をするメリット
3-1.物件価格帯が低い
3-2.郊外は利回りが高い
- 郊外でマンション投資をする際のデメリット
4-1.将来的な賃貸ニーズの不安がある
4-2.出口戦略の不安
- 目的別のマンション投資法
5-1.キャッシュを多くストックしたい場合
5-2.高い価格で売却したい場合
5-3.老後に年金代わりの収入を得たい場合
5-4.運用を手放しでしたい
- まとめ
1-1.職住近接で賃貸ニーズが高まっている
1-2.転入者数が多い
1-3.資産性が高い
2-1.価格が高く利回りが悪い
2-2.固定資産税などが高くなる
3-1.物件価格帯が低い
3-2.郊外は利回りが高い
4-1.将来的な賃貸ニーズの不安がある
4-2.出口戦略の不安
5-1.キャッシュを多くストックしたい場合
5-2.高い価格で売却したい場合
5-3.老後に年金代わりの収入を得たい場合
5-4.運用を手放しでしたい
1.東京都心でマンション投資をするメリット
東京都心でマンション投資をする場合、どのような点がメリットになるのかを見てみましょう。
1-1.職住近接で賃貸ニーズが高まっている
近年は国が職住近接の施策を推進していたこともあり、都心の会社の近くに住みたいという社会人が増え、都心回帰の状態にあります。企業やそこに勤めている人が多ければ、近隣に住んでいる人が多くなる傾向にあります。
では東京都心の事業所数や従業員数は、全国市町村の中ではどれくらいの位置にあるのでしょうか。以下の表は平成28年における全国の事業所数と、従業員が多く在籍している市町村のランキングです。
こちらの表から東京都23区は、事業所数で2位の大阪市と比較して約35万件も多いことが確認できます。従業員数も最も多く、2位の大阪市と比較して530万人以上の差があることが確認できます。このことから東京都心は職住近接に伴い、非常に賃貸ニーズが高いことが考えられます。
1-2.転入者数が多い
上記のように東京都心に住みたいという社会人が増えていることが想定できますが、他の都市との関係はどのようになっているのでしょうか。以下のグラフは、2018年中の都道府県別転入者超過数を表したものです。
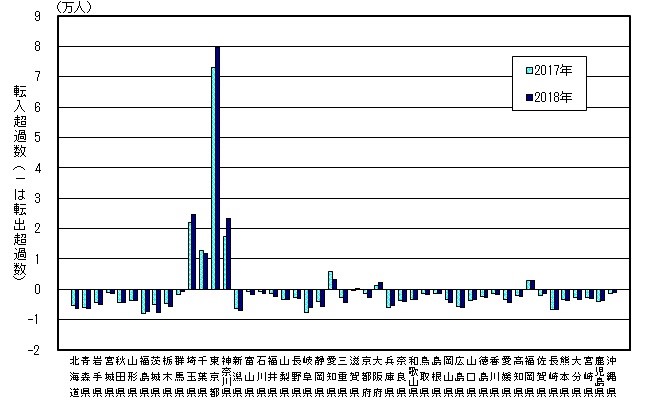 *総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用
こちらのグラフから東京都が2017年、2018年ともに都道府県の中で最も転入超過数が多いことが確認できます。また多くの都道府県では転出人口の方が多いことから、そのような都市から東京などに転入しているということが想定できます。
また、以下の表では各市町村の転入超過数が確認できます。
*総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用
こちらのグラフから東京都が2017年、2018年ともに都道府県の中で最も転入超過数が多いことが確認できます。また多くの都道府県では転出人口の方が多いことから、そのような都市から東京などに転入しているということが想定できます。
また、以下の表では各市町村の転入超過数が確認できます。
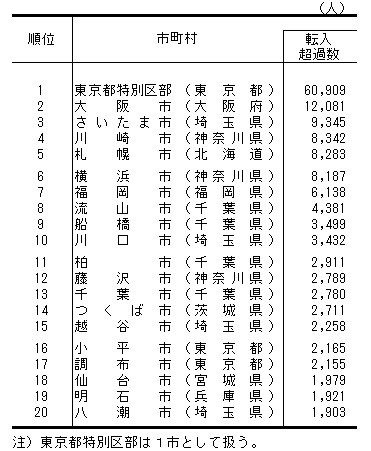 *総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用
こちらの表から、東京都区部が全国の市町村の中で最も転入超過数が多いことが確認できます。このように、東京都の中でも都心(23区)は事業所数や従業員数が多い上に、転入者も全国で最も多いため、人口や人の動きの面から見てマンション投資をする上での賃貸条件が良いことが想定できます。
*総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用
こちらの表から、東京都区部が全国の市町村の中で最も転入超過数が多いことが確認できます。このように、東京都の中でも都心(23区)は事業所数や従業員数が多い上に、転入者も全国で最も多いため、人口や人の動きの面から見てマンション投資をする上での賃貸条件が良いことが想定できます。
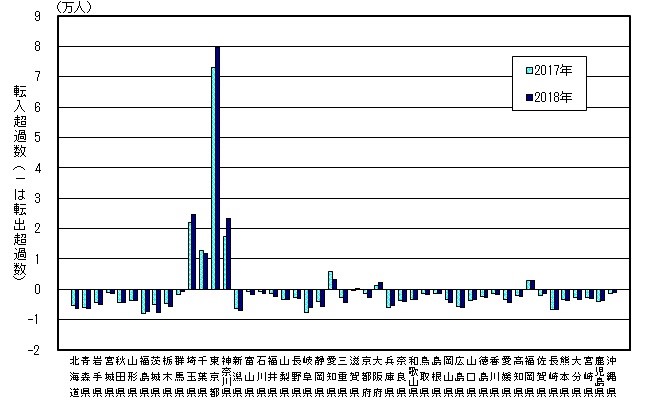 *総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用
*総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用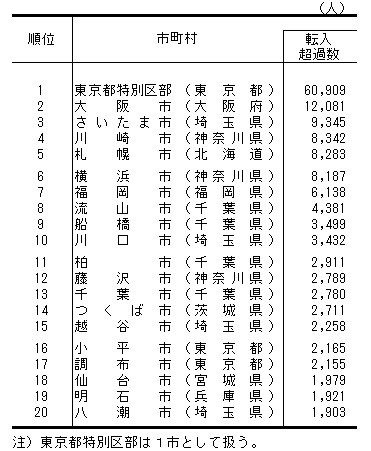 *総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用
*総務省発表「住民基本台帳人口移動報告平成30年(2018年)結果」から引用1-3.資産性が高い
上記のように、東京都心には転入者増加の状況や事業所が集中していることから高い賃貸ニーズが期待できます。賃貸ニーズが高ければそれだけ収益を得られる期待があるため、資産性が高く維持できる可能性も高くなります。そのため売却する際の評価も高くなることが考えられます。
都心のマンションは郊外のマンションと比較して賃貸ニーズが高く、その影響で物件の資産性も高くなるメリットがあると言えます。
2.東京都心でマンション投資をする際に考えられるデメリット
都心は人口が多く、賃貸ニーズの面でメリットがありますが、逆にデメリットはどのような点になるのでしょうか。確認してみましょう。
2-1.価格が高く利回りが悪い
都心のマンションは資産価値が高いぶん、価格帯も高くなります。そのため利回りが低く、運用においてキャッシュがストックされるスピードが遅くなります。
キャッシュのストックが少ない場合、空室リスクや家賃滞納リスクへの対応が難しくなる場合もあります。月々のキャッシュフローを良くするにはローンの頭金を多く入れたり、繰上返済をしたりするなどの工夫が必要になってきます。
2-2.固定資産税などが高くなる
都心の物件は価格帯が高いだけでなく、固定資産税や都市計画税も高くなるので注意が必要です。マンション投資の収支が悪く、毎月手元に残る資金が少ない場合、固定資産税を支払ったことで手元資金が少なくなったり、無くなったりすることも考えられます。
そうならないためには、日頃から将来発生する経費をあらかじめ把握した上で、収支を良くする工夫が必要になります。資金計画を慎重に検討して取り組むことが大切だと言えます。
3.郊外でマンション投資をするメリット
では次に、郊外でマンション投資をする場合にはどのような点がメリットになるのかを見てみましょう。
3-1.物件価格帯が低い
郊外は都心と比較して物件価格が低い傾向にあります。以下は2019年7月~9月期における一都三県の主要都市別区分マンションの平均価格です。
エリア 平均価格 東京23区 2,164万円 川崎市 1,352万円 東京市部 1,281万円 埼玉主要都市 1,254万円 横浜市 1,164万円 千葉主要都市 1,102万円
*不動産投資と収益物件の情報サイト健美家「四半期レポート2019年7月~9月期」の資料をもとに筆者作成
こちらの表から東京市部の区分マンションの平均価格は1,281万円で、東京23区の2,164万円の約2分の1の価格帯であることが確認できます。また同様に、その他郊外エリアの物件価格はいずれも東京23区に比べて大幅に低い価格帯となっています。
| エリア | 平均価格 |
|---|---|
| 東京23区 | 2,164万円 |
| 川崎市 | 1,352万円 |
| 東京市部 | 1,281万円 |
| 埼玉主要都市 | 1,254万円 |
| 横浜市 | 1,164万円 |
| 千葉主要都市 | 1,102万円 |
3-2.郊外は利回りが高い
郊外は都心と比較してマンションの価格帯が低いことが確認できました。次に利回りを確認してみましょう。
エリア 平均利回り 千葉主要都市 10.27% 埼玉主要都市 8.19% 東京市部 8.08% 横浜市 8.03% 川崎市 7.32% 東京23区 5.80%
*不動産投資と収益物件の情報サイト健美家「四半期レポート2019年7月~9月期」の資料をもとに筆者作成
こちらの表から、東京23区の平均利回り5.80%という数値に比べ、その他地域のほうが総じて利回りが高い傾向にあることが確認できます。
例えば2,000万円の物件を満室で運用できた場合、利回り8.08%と5.80%では年間の収益がどれくらい違うか試算してみましょう。試算した結果は以下のようになります。
利回り 年間収入 8.08% 161万6,000円 5.8% 116万円
同じ価格の物件の場合、23区と東京市部における満室時の年間家賃収入は、東京市部の方が約45万円も多いことが確認できます。1ヵ月当たり3万8,000円も差があり、とても大きな違いになることが考えられます。
このことから、郊外でのマンション投資は都心と比較して低予算でスタートでき、満室を実現・維持できれば高い利回りとなり、キャッシュもストックしやすいことが考えられます。投資額を抑えて、効率的に運用できる可能性があるという点が大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、マンション投資は物件個別に条件が異なり、利回りもこの通りになるとは限りませんので、個別に収支をシミュレーションして取り組むようにしましょう。
| エリア | 平均利回り |
|---|---|
| 千葉主要都市 | 10.27% |
| 埼玉主要都市 | 8.19% |
| 東京市部 | 8.08% |
| 横浜市 | 8.03% |
| 川崎市 | 7.32% |
| 東京23区 | 5.80% |
| 利回り | 年間収入 |
|---|---|
| 8.08% | 161万6,000円 |
| 5.8% | 116万円 |
4.郊外でマンション投資をする際のデメリット
郊外でマンション投資をする場合、価格帯が低く利回りが良いため、キャッシュフローを活かした運用がしやすいことが考えられますが、逆にデメリットはどのような点になるのか確認してみましょう。
4-1.将来的な賃貸ニーズの不安がある
都心のマンション投資のメリットで見たように、都心に転入者が集中しているぶん、郊外に行くほど賃貸ニーズの面では不安があると言えます。そのため、郊外でも賃貸ニーズが高いエリアを探して投資を考える必要があります。
4-2.出口戦略の不安
郊外のマンションを購入し運用する場合、出口戦略に不安が残ることが考えられます。賃貸ニーズが低い物件は収益が見込みづらく、また築年数が経過すればさらに賃貸ニーズは下落すると考えられるため、郊外には購入時から値崩れしやすいマンションが多い傾向にあるからです。
また、郊外は将来にわたって賃貸ニーズが低下していくリスクが高いエリアも多いため、なるべく賃貸ニーズが落ちないであろうエリアの物件を選んだり、早めに出口戦略を立てて行動したりすることが必要だと言えます。
5.目的別のマンション投資法
都心と郊外ではマンションの価格や利回り、賃貸ニーズ面で違いがあることが確認できました。このような特徴を活かすためにはどのような形で投資をすれば良いのでしょうか。投資を行う目的別に、どちらのエリアでマンション投資をしたらメリットが大きいのかを考えてみましょう。
5-1.キャッシュを多くストックしたい場合
キャッシュを多くストックするには、収支が良いことが条件になります。満室時の利回りを試算した際に、キャッシュは郊外マンションの方がストックしやすい傾向にあることが確認できました。
ただし、都心のマンションでも工夫の仕方によってはキャッシュを多くストックすることも可能です。例えば頭金を多く入れたり、借り換えや繰上返済をしたりしてローンの返済負担を減らすという方法です。ただし、それらを行うと先に出ていく資金が多くなりますので、都心と郊外ではどちらがメリットは大きくなるのかは、自己資金も考慮しながら物件単位で慎重にシミュレーションして取り組むことが大切です。
5-2.高い価格で売却したい場合
高い価格で売却したい場合は、都心のマンションの方がメリットはあると考えられます。都心は上記で確認したように人口が多く、長期的に見ても賃貸ニーズが高いことが考えられます。賃貸ニーズが高い物件は収益が多く、売却時の査定価格も高くなります。売却をより良い条件で行いたい場合は、都心のマンションの方がメリットの方が大きいと言えるでしょう。
5-3.老後に年金代わりの収入を得たい場合
今後、老後の生活費は自分で作っていかなければならず、年金だけでは足りないとも言われています。マンション投資を検討している方の中にも、老後の年金作りを意識する方は多いのではないでしょうか。
不動産投資では、ローンを完済したあとの家賃収入はほとんどそのまま自分の蓄えにすることができます。そのため老後に少しでも多く収入を得たいということであれば、家賃が高めの都心のマンションの方がメリットは大きくなるでしょう。
しかし、都心のマンションは価格帯が高く、運用時の収支が悪い可能性も高くなります。収支を良くするには、繰り上げ返済の必要経費などの投資が必要になりますので、あらかじめそのリスクは考えておく必要があります。
一方、郊外のマンションでも月数万円の家賃収入は見込めますので、老後に必要な金額によっては、低予算でスタートできる郊外のマンションでもメリットはあると考えられます。
5-4.運用を手放しでしたい
マンション投資は、管理会社に管理業務を委託することで、ほぼ手放しで運用できる点が魅力の一つです。都心・郊外問わず、管理業務を委託することは可能です。ただ、管理会社の管理体制によって以後の入居率や管理状態が違ってきますので、管理会社を選択する際は、実績などをよく見て委託するようにしましょう。
まとめ
マンション投資をする際、都心と郊外ではどちらがメリットが大きいのかを見てみました。都心と郊外では賃貸ニーズや価格帯、利回りに違いはありますが、必ずしもどちらか一方が良いというわけではないと言えます。
マンション投資にかけられる時間や費用、目的などの違いによって、都心と郊外のマンションのどちらに投資するかを検討することが大切です。マンション投資に取り組む際は、候補物件の収支を慎重にシミュレーションした上で判断するようにしましょう。
お金持ちになる人の「生活習慣」3つの鉄則
■お金持ちほどお金を大事に使う生活を送っている
お金の相談を受けていると、一代で大きな資産を築かれた人にお目にかかることがあります。
皆さん、そこに至る歴史はそれぞれですが、物事の考え方やおっしゃることには、いくつかの共通点があると思います。お金持ちの考え方、ぜひ真似してみたいですよね。
資産を築くためには収入が多いに越したことはないのですが、それだけでは十分ではありません。
なぜなら、多くの人は収入が上がればそれにともなって支出も増えてしまい、結局、資産は増やせないからです。ウラを返せば、収入が増えても生活水準を一定にキープすれば、自然と資産は積みあがります。
■習慣1:支出のコントロールが上手
事実、お金持ちになる人の多くは、支出のコントロールが上手く、無駄遣いが少ないのが特徴です。
「格安スマホに変えたらずいぶんお安くなりました」とおっしゃったのは、老人ホームを経営する80歳の女性です。
一生で使い切れないほどの資産があっても、雑誌や本は買わずに図書館を利用されている人はいくらでもいますし、ふるさと納税などのようなおトクな制度は早くから積極的に取り入れている人も目立ちます。
単純に節約志向が強いだけなのかというと、そういうわけではありません。女性からよくお聞きするのが、「気に入った洋服は高くても買って、長く愛用しています」とのお言葉です。
「安物買いの銭失い」ということわざがありますが、その真逆で、買い物を安いからという理由ではなく必要かどうかで判断しているわけですね。
無駄な支出は抑え、本当に必要なものにお金を使う暮らしぶりに、お金を大事にするお金持ちの思考がうかがえます。
■習慣2:取るべきリスクを取って、避けるべきリスクを避ける
大きな資産形成に欠かせないのが、投資で増やすという考え方でしょう。不動産投資や株式投資など、スタイルは人によって異なりますが、資産形成の核として若いころから続けてきた手法をお持ちです。
「株式投資は、かれこれ50年のキャリアです」
そう話してくれたのは、75歳になる男性のAさんです。株式投資に興味を持ったのは小学校のころ、お父様をはじめ周りの人が話しているのを聞いたのがきっかけだったそうです。
実際に自分で始めたのは20歳を過ぎてからだそうですが、それでも投資歴は50年のベテランです。始めたばかりのころは失敗もよくあったそうですが、長年続けていくうちに、徐々に利益を出すことが増えてきたのだとか。
都内にマンションとアパートをあわせて6つ所有されていらっしゃるBさん(70歳/女性)もお母様の代から、不動産投資をされてきたそうです。ご自分なりの利回りの計算式があるので、「その条件に合わなければ見送るようにしています」とのことでした。
■習慣3:経験の中でつかんだ成功セオリーを持っている
AさんやBさんに共通なのが、経験の中でつかんだ成功セオリーを持っていることです。
こうした方々に金融商品をご紹介させていただくことがありますが、皆さんすばやく決断されるのには驚かされます。長年の投資経験を積まれてきたからこそ、自分なりの判断基準があって、考え方に合う、合わないがすぐに決められるのだと思います。
「まだ早いとは思ったのですが、いずれ今の家では段差もあって住みづらくなるだろうから、高齢者用のマンションを買いました」
「ご主人が病気になったのをきっかけに、万が一の相続で引っ越すことも考えて、自宅を売ったらどの程度の値段になるか調べました」
これらは、いずれも資産家の方からお聞きした話です。
自分に将来どんなリスクがあるかを考え、回避するために先回りして行動が起こせるのも、お金持ちの人に共通の特徴です。とるべきリスクをとって避けるべきリスクは避ける、その繰り返しが、資産を守り育てるのだと感じます。
教えてくれたのは……新屋 真摘さん
大手生命保険会社を経て、「正しいマネーセンスを身につけて、お金に振り回されない人生を送ってもらうお手伝いがしたい」という想いからファイナンシャルプランナーを目指す。2005年、独立系FP会社の立ち上げから参画。2014年、資産運用のアドバイスに強みを持つFP法人ガイアに入社。現役世代の資産形成から退職金の運用まで、バランスの良い提案を行う。
(文:All About 編集部)
お金の相談を受けていると、一代で大きな資産を築かれた人にお目にかかることがあります。
皆さん、そこに至る歴史はそれぞれですが、物事の考え方やおっしゃることには、いくつかの共通点があると思います。お金持ちの考え方、ぜひ真似してみたいですよね。
資産を築くためには収入が多いに越したことはないのですが、それだけでは十分ではありません。
なぜなら、多くの人は収入が上がればそれにともなって支出も増えてしまい、結局、資産は増やせないからです。ウラを返せば、収入が増えても生活水準を一定にキープすれば、自然と資産は積みあがります。
■習慣1:支出のコントロールが上手
事実、お金持ちになる人の多くは、支出のコントロールが上手く、無駄遣いが少ないのが特徴です。
「格安スマホに変えたらずいぶんお安くなりました」とおっしゃったのは、老人ホームを経営する80歳の女性です。
一生で使い切れないほどの資産があっても、雑誌や本は買わずに図書館を利用されている人はいくらでもいますし、ふるさと納税などのようなおトクな制度は早くから積極的に取り入れている人も目立ちます。
単純に節約志向が強いだけなのかというと、そういうわけではありません。女性からよくお聞きするのが、「気に入った洋服は高くても買って、長く愛用しています」とのお言葉です。
「安物買いの銭失い」ということわざがありますが、その真逆で、買い物を安いからという理由ではなく必要かどうかで判断しているわけですね。
無駄な支出は抑え、本当に必要なものにお金を使う暮らしぶりに、お金を大事にするお金持ちの思考がうかがえます。
■習慣2:取るべきリスクを取って、避けるべきリスクを避ける
大きな資産形成に欠かせないのが、投資で増やすという考え方でしょう。不動産投資や株式投資など、スタイルは人によって異なりますが、資産形成の核として若いころから続けてきた手法をお持ちです。
「株式投資は、かれこれ50年のキャリアです」
そう話してくれたのは、75歳になる男性のAさんです。株式投資に興味を持ったのは小学校のころ、お父様をはじめ周りの人が話しているのを聞いたのがきっかけだったそうです。
実際に自分で始めたのは20歳を過ぎてからだそうですが、それでも投資歴は50年のベテランです。始めたばかりのころは失敗もよくあったそうですが、長年続けていくうちに、徐々に利益を出すことが増えてきたのだとか。
都内にマンションとアパートをあわせて6つ所有されていらっしゃるBさん(70歳/女性)もお母様の代から、不動産投資をされてきたそうです。ご自分なりの利回りの計算式があるので、「その条件に合わなければ見送るようにしています」とのことでした。
■習慣3:経験の中でつかんだ成功セオリーを持っている
AさんやBさんに共通なのが、経験の中でつかんだ成功セオリーを持っていることです。
こうした方々に金融商品をご紹介させていただくことがありますが、皆さんすばやく決断されるのには驚かされます。長年の投資経験を積まれてきたからこそ、自分なりの判断基準があって、考え方に合う、合わないがすぐに決められるのだと思います。
「まだ早いとは思ったのですが、いずれ今の家では段差もあって住みづらくなるだろうから、高齢者用のマンションを買いました」
「ご主人が病気になったのをきっかけに、万が一の相続で引っ越すことも考えて、自宅を売ったらどの程度の値段になるか調べました」
これらは、いずれも資産家の方からお聞きした話です。
自分に将来どんなリスクがあるかを考え、回避するために先回りして行動が起こせるのも、お金持ちの人に共通の特徴です。とるべきリスクをとって避けるべきリスクは避ける、その繰り返しが、資産を守り育てるのだと感じます。
教えてくれたのは……新屋 真摘さん
大手生命保険会社を経て、「正しいマネーセンスを身につけて、お金に振り回されない人生を送ってもらうお手伝いがしたい」という想いからファイナンシャルプランナーを目指す。2005年、独立系FP会社の立ち上げから参画。2014年、資産運用のアドバイスに強みを持つFP法人ガイアに入社。現役世代の資産形成から退職金の運用まで、バランスの良い提案を行う。
(文:All About 編集部)
にほんブログ村
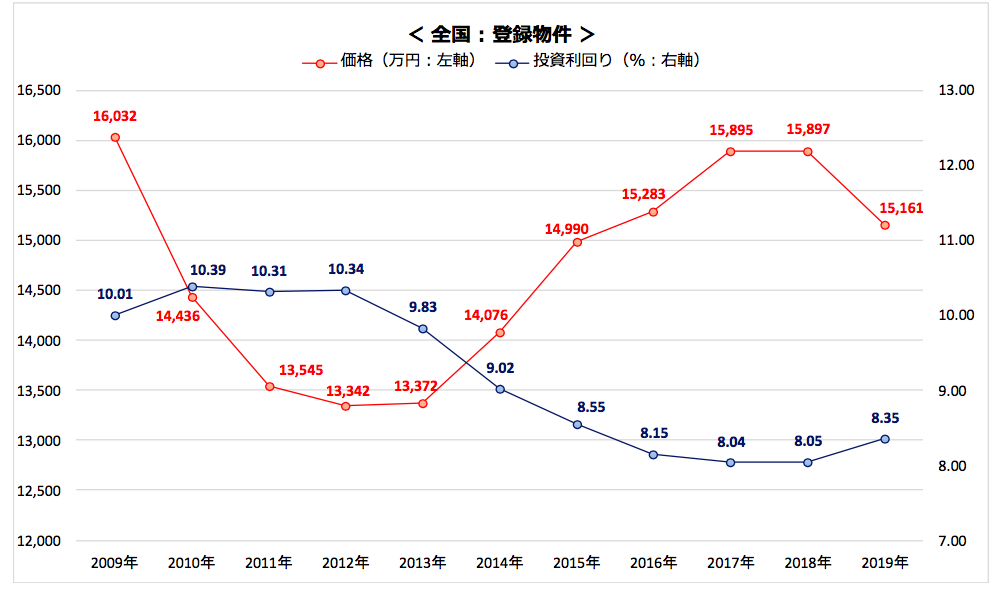



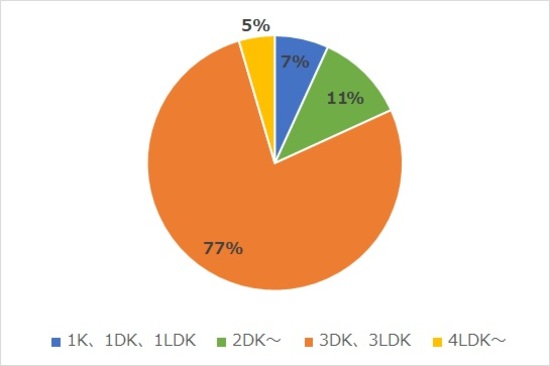
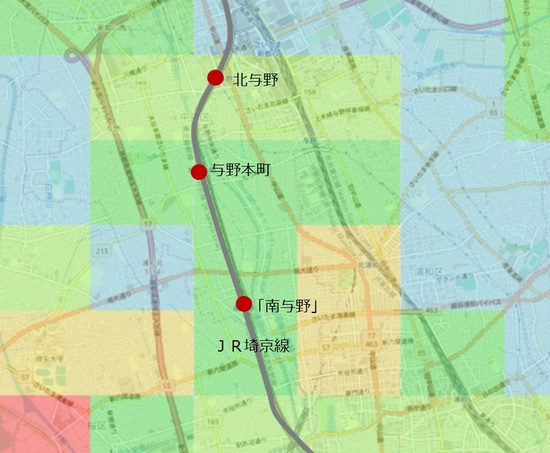

 *総務省発表「
*総務省発表「
コメント
コメントを投稿