不動産投資で知っておきたい減価償却
不動産投資を始めると給与収入以外の所得が発生するため、確定申告を行う必要があります。確定申告の際に減価償却費という言葉を初めて聞く方もいるかもしれません。減価償却費は、不動産投資においては非常に重要な経費であり、減価償却費がないと多額の税金が発生する可能性があります。今回は、この減価償却費の仕組みや節税効果について解説します。
減価償却費の仕組みと計算方法

(画像=ユニバーサルトラスト編集部)
まず、減価償却費の基本的な概念から解説します。減価償却費は、購入した建物の価値が経年により減価していく金額を費用として計上するものです。実態の経年劣化のスピードと税務上の耐用年数は異なりますが、構造別の経済的耐用年数は以下のように定められています。
・構造別の経済的耐用年数
RC造:47年
重量鉄骨造:34年
軽量鉄骨造:19年
木造:22年
RC造:47年
重量鉄骨造:34年
軽量鉄骨造:19年
木造:22年
例えば、新築のRC造のマンションを購入した場合、1年あたりの減価償却費は、建物価格×1年÷47年(耐用年数)となります。また、新築の場合は、耐用年数を基に減価償却費を算定しますが、中古物件の耐用年数は以下の数式で求めることが可能です。
・本来の耐用年数-(経過年数×0.8)=中古物件の耐用年数
1つ例を出すと、築20年のRC造中古物件を購入した場合の耐用年数は、以下の通り求められることになります。
・47年-(20年×0.8)=31年
また、建物は減価償却費を計上することができますが、土地は時間の経過による価値の減少がないという税務上・会計上の考え方により、土地に対しての減価償却費はありませんのでご注意ください。したがって、物件総額が4億円だとすると建物価格が2億円の場合と、2億円の場合ではその後、経費計上できる減価償却費の金額は異なります。
減価償却償却費は節税のポイント
次に、減価償却費と節税についてです。購入した建物の金額については、上記の通り、税務上一定期間損金として費用計上することができます。つまり、実際のキャッシュアウトを伴っていないのに、損金算入することで、利益を圧縮する効果があり、減価償却費は節税効果があると捉えられています。ただし、減価償却費は多ければ多いほど良いということではありません。
確かに、1年間ごとの減価償却費を増やすことは、その年の税金を減らすことにつながるという意味で節税効果があります。しかし、減価償却費を多くとるということは、その分税務上の建物価格が減少していくスピードが早くなるということです。売却時には売却価格から簿価を引き、その差額に対し譲渡所得税が発生します。
つまり、物件保有中に多くの減価償却を引き、簿価が低くなればなるほど、売却価格との差額が大きくなる傾向があるのです。そのため、将来売却する際に計上される売却益も大きくなり、将来の売却時に支払う税金が多くなる場合もあります。また、将来的に銀行からの借り入れを増やし、事業規模を拡大していきたい場合もあるでしょう。
その場合は、減価償却費を多く計上していることによって、毎年赤字になっていると金融機関に対する印象が悪くなる可能性があります。融資の条件が悪くなったり、融資承認がとりにくくなったりすることもあるため注意が必要です。したがって、減価償却費は将来的な出口戦略や規模拡大のスピードなどを考慮して、金額を決めたほうがよいでしょう。
減価償却費はいったん耐用年数を決めてしまうと、そこから変更することは難しいです。そのため、初期設定時は専門家からアドバイスをもらいながら決定していくのがよいでしょう。(提供:ユニバーサルトラスト)
不動産投資の「やりすぎ節税」が引き起こす4つのリスク
不動産投資の目的が「節税」だけだと危険?
不動産投資の魅力として真っ先に思いつくのは、「家賃収入」です。もうひとつの大きな魅力が、「節税」。不動産投資で得た所得は、経費で課税所得を下げられますし、サラリーマンの方であれば、本業の利益と投資の損失を相殺し、所得税の還付が可能です。所得税が減額されれば、当然住民税も減ります。
ただし、節税だけが目的の不動産投資は、ノーリスクではありません。税金対策としての不動産投資に関して、具体的な節税内容を理解し、注意点をまとめました。
投資の経費で課税所得が下げられるから、節税になる
サラリーマンが本業の方は、医療費控除などの特別な事情がない限り、確定申告は必要ないもの。普段は税金も天引きですから、課税所得を下げられると聞いてもピンとこないかもしれません。不動産投資で課税されるのは「不動産所得」で、「総収入金額−必要経費」で求められます。ここで認められる必要経費とは、以下のようなものです。
●固定資産税
●不動産取得税
●損害保険料
●減価償却費
●修繕費
●管理会社への管理委託費
●ローン金利
これら以外にも、次のような費用も必要経費にできます。
●物件を見に行ったときの交通費
●不動産投資セミナー参加費
●税金に関する本の書籍代
ただし、交通費や書籍代の頻度・金額が多すぎると、税務署のチェックが入りますから注意が必要です。また、私用や自宅に関わること、ローン返済の元本部分は経費にはなりません。必要経費計上で所得を下げれば課税対象額が減額され、所得税が減るという仕組みです。
所得税の還付や住民税の減税が実現
不動産所得に必要経費を計上し、所得税を減らす流れはご理解いただけましたか。次に、所得税還付・住民税減額に関して説明しましょう。
所得税還付の流れ
本業の給与所得のうち、課税対象額が600万円だとします。不動産所得が100万円の場合、所得税の課税対象額は合計で700万円。同じように給与所得が600万円でも、不動産所得が100万円の赤字だった場合、課税対象額は600万円+(-100万円)=500万円となります。給与所得の所得税は毎月天引きされていますから、所得が減った分の所得税が還付されるのです。
不動産投資なら損益通算OK
このような、所得で生じた損失と他の所得で生じた利益の相殺は、損益通算と呼ばれます。不動産所得は、給与所得との損益通算ができるのです。同じ投資でも、株式投資の場合、給与所得との損益通算は認められていません。ただし、損益通算は確定申告をしないと適用されませんので、必ず申告してください。
住民税も減税
住民税には道府県民税と市町村民税があり、都道府県民税が4%、市町村民税が6%、合計10%です。さらに、住民税は、大半を占める「所得割」と「均等割」に分かれます。所得割は所得によって課税額が決まり、前年1月から12月までの所得によって計算されます。したがって計算のベースの所得が減ると、住民税も減るわけです。
なお、住民税の均等割は所得による変動はなく一律課税で、自治体によって差はありますが、標準税額は都道府県民税が5,000円、市町村民税が3,500円程度です。
節税目的だけの不動産投資は避けたほうがよい
不動産投資が節税になる仕組み、ご理解いただけましたか? 注意していただきたいのは、節税だけが目的の不動産投資はノーリスクではないことです。節税に焦点を当てすぎた場合のリスクを解説します。
リスク①キャッシュフローの悪化
損益通算の場合、不動産投資の節税は不動産投資の赤字が前提です。利益が大きい場合、経費計上しても節税には限界があります。節税効果を得るために収益を抑えてしまったら、「投資で利益を獲得」という本来の不動産投資の目的からも離れてしまいます。
リスク②金融機関の信用低下
不動産投資を進めるときは、多くの方が不動産投資ローンを利用します。金融機関との関係はとても大切です。赤字経営になってしまうと、金融機関の印象が悪くなります。所有物件を増やそうとしても、不動産投資ローンの際の審査が通りにくくなるでしょう。
リスク③物価や金利変動のリスクに弱くなる
不動産投資を赤字にして節税した場合、経営はギリギリです。家賃を下げざるを得ない状況になったり、金利が上昇してしまったりする可能性はゼロではありません。そのような状況に直面すると、収益が一気に悪化、節税どころではなくなります。
リスク④耐用年数の問題
不動産投資による節税は、金額の大きい減価償却費の経費計上がカギです。耐用年数が終了すると減価償却はできなくなります。それにより不動産所得が黒字化し、税金が一気に上昇する場合があるでしょう。
不動産投資で節税は可能だが、バランスが大切
不動産投資で節税は可能です。経費計上で所得金額を減額すれば、所得税はかなり圧縮できます。給与所得のある方であれば、赤字の不動産所得を給与の黒字と相殺し、所得税還付を受け住民税を減らすことも可能です。
ただし、節税を目的に赤字を出し続けてしまうと、キャッシュフローが悪化してリスクに弱くなります。金融機関の印象も悪くなるでしょう。不動産投資の際には、節税だけだはなくキャッシュフローのバランスを考慮し、「やりすぎ」ないようにするのがおすすめです。
2020年の不動産投資…「2013年以前の物件」が狙い目なワケ
なぜ「不動産価格」は高騰しているのか?
2020年の東京オリンピック開催決定が決まったのは、遡ること6年前の2013年9月です。そのころの日本は、第2次安倍政権が発足したてで、「三本の矢」「アベノミクス」などの政策効果で、日本経済が上向きに転じようとしている時期でした。
東京にオリンピックが決定したことにより、今まで以上に世界から注目される東京。オリンピック施設の建設による、建築費、人件費等の高騰などで、不動産価格が上昇し始めました。
このグラフからわかることがあります。
・2013年以降、不動産価格指数が全国的に高騰していること
・特にマンション価格指数が著しく高騰していること
このようにマンション価格が高騰している理由はいくつかありますが、鉄やコンクリートなどの資材の価格上昇、また職長クラスの職人の不足などが、オリンピック開催決定を引き金に起きたことで、マンションが価格高騰しています。
価格高騰のもう一つの理由が、史上最低金利といわれる「マイナス金利政策」により、住宅ローン利率が、過去に例を見ない低金利となり、住宅購入ラッシュが起きているということがあります。その結果2016年にはバブル期以来の不動産融資額を更新しました。
超低金利時代に不動産を買ったほうが良い理由とは?
マイナス金利政策を打ち出した理由は、住宅ローンを組みやすくするためだけに行われたのではありません。
中央銀行(日銀)が名目金利をゼロ以下に設定し、貸出金利を下げることで、企業への事業融資も金利が下がり、産業も盛んになることで多くの経済効果をもたらし、お金の流通も良くなり、好景気に転じさせるといった狙いがあります。
もちろん住宅ローン金利が下がることで、住宅購入者が増えて、結果として大きな買い物をする訳ですから、大きな経済効果が生まれます。
このように景気向上を促すための利率下げが、不動産業界にも影響し、「家は賃貸で借りるより、買った方がお得」な時代が来たのです。さらにローン支払い金額が下がったことにより、同じ年収でも、以前よりも多くの融資を受けられるようになったことで、買える物件の価格帯の限界が広がりました。
上記の表から、貸出金利が低いだけで借り入れ可能年収が下がっていることがわかります。逆にいうと年収の高い方は、もっと大きな住宅ローンを組むことが可能になりました。
仮に貸出金利が0.457%だったとしたら、年収の約11.3倍もの借り入れが可能ということです。マイナス金利政策前は年収の約10倍の借入限度だったことを考えると、不動産価格が10%くらい高騰しても、買えてしまうということなのです。
ではなぜ、この超低金利時代に不動産を買った方が良いのかというと、仮に不動産価格が5,500万円に上がっていたとしても、金利が0.475%であれば、支払い利息の合計額は42万円ほどしか上昇しないため、金利が2.975%で5,000万円の住宅ローンを組むよりも利息だけで計算すると2,500万円もお得になります。
この2,500万円の差は、不動産価格が相当上昇しても埋まらない計算になりますので、過去に例を見ないこの超低金利時代に不動産を買った方がお得といえます。
これはマイホームのみならず、不動産投資にも同じことがいえるので、金利という観点からみても今が買い時といえるのではないでしょうか。
というのも、好景気が続くと金利は上昇していきますので、「いまは景気がいいな~」と思うような時代になってからでは遅いのです。そしてこの金利低下が皆さんのローンの融資枠を増やしたことで、不動産価格の上昇にも繋がっているのです。
早くスタートすれば、早く収入源にできる
周りに不動産投資をやっている人がいた場合、その方から話を聞いてみても、それだけで不動産投資の善し悪しは決められないのではないでしょうか。
というのも、自分とその方とでは年齢や年収、家族構成や考え方も違うことが多く、その方と同じようにやることはできない可能性もあるからです。
また不動産投資は縁です。同じ条件の物件はほぼ存在しません。
さらに年齢によっては組めるローンの年数も変わり、定年も人によって異なります。通常住宅ローンの完済年齢は79歳(一部金融機関は84歳)と設定されていますが、30歳の方と50歳の方とでは組めるローン年数が異なります。
そして組めるローン年数次第で、毎月の支払額も変わるため、家賃が一定の不動産投資においては、ローン支払額によって月々の収支が変わってきてしまうということです(図表3参照)。
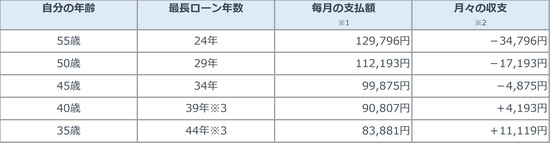
[図表3]【家賃95,000円、価格3,000万円の投資物件を、満額融資利用で買った場合の比較※1 貸出金利1.9%で計算した場合
※2 修繕積立金が管理費や賃貸管理費等は含まず
※3 一部金融機関では45年ローンまで可能な場合があります
※完済年齢は79歳の場合を仮定
※2 修繕積立金が管理費や賃貸管理費等は含まず
※3 一部金融機関では45年ローンまで可能な場合があります
※完済年齢は79歳の場合を仮定
このように不動産投資は始める年齢が早ければ早いほど、同じ物件を購入する場合でも収支に大きな差が出てきます。
当然ですが年齢は年々上がりますので、組めるローン年数が減っていく可能性があるので、不動産投資を検討するなら、景気や時期を考察するよりも、自身の引退までの年齢を考え、早く始めるに越したことはありません。
つまり、スタートが早ければ、完済時期も早まり、早く収入源に変えていけるのです。
オリンピック開催決定前の「中古物件」を狙う
冒頭のグラフから分かるように、マンション価格は2013年の東京オリンピック開催決定してから、わかりやすいほど上昇しています。
新築マンションの価格が前述の理由で上昇すると、それにつられて中古マンション価格も上昇していきます。結果としてマンション価格全体が上昇しているのです。
今新築を買うのも、価格高騰が始まった2013年築以降の中古物件を買うのも、価格が高騰しているのでもったいないともいえますが、2013年より前の中古マンションなら、価格高騰の影響を受けていないケースが多く、かつ、今から始める方は現在の超低金利の恩恵も受けられるため、大変お買い得な状態にあります。
建築技術や、設備なども年々向上はしていますが、2013年以前でも風呂トイレ別の中古マンションであれば投資用としては十分ともいえます。
特に1Kタイプのようなコンパクトマンションは、ハイグレードなタワマンとは違い、ここ十数年同じような設備なので、違いをほとんど感じないのではないでしょうか。
前回のコラム『 今さら訊けない 「 バランスシート 」の意味。なにそれ美味しいの? と思った大家さんへ 』で、資産について触れました。
今回は、銀行が資産の内容について、どう捉えているか、不動産賃貸業以外への投資や事業への取り組みについて、どう考えているかを解説していきます。
■ 銀行が最も重視するのは「 収益性 」
銀行は融資をする際に、融資先の収益性、債務償還能力、安全性などを重視します。収益性とは、儲ける力のことです。これが最も重視されます。
債務償還能力は、借入金を返済する能力。キャッシュフローで推し量ります。そして、安全性は前回説明したバランスシートの純資産による変事抵抗力や事業の安定性です。
不動産賃貸業は、他の事業に比べて安定していて、銀行にとって長期の事業計画が読みやすいのが特徴です。また、担保での融資保全率が高く貸倒リスクが低い。だからこそ、超長期の返済期間で比較的低金利で貸してもらえるのです。
それなのに、他の事業を手掛けて、もし経営がうまくいかなかった場合、そちらの事業に不動産賃貸業で得た本来は融資の返済に充てるべき資金を回されてしまうことを銀行は懸念します。
元々、アパートローンは地主向けで、その後サラリーマンに門戸を開きました。しかし、一般事業オーナー経営者への間口は狭いままです。逆を言えば、一般事業を手掛けると、不動産融資への間口が狭くなるといえます。
また、設備投資でなく、運用としての投資について、銀行は保守的です。銀行は事業資金を貸しますが、投資資金は貸さない傾向にあるのです。
昔から貸さなかったのではなく、バブルの時までは結構貸していました。その後のバブル崩壊でかなりの痛い目を見たため、方針を変えたということです。
一時は株式投資資金のみならず、不動産投資資金ももってのほかという時代がありました。バブル崩壊時は地価が下がり続け、不動産融資が焦げ付き、多くの銀行が破綻したり、救済合併されたりしましたから、仕方のないことです。
現在、当時の大変さを現場で見ていた行員が銀行の中枢を支えており、そのトラウマは消えていません。そのため、令和になってからもこの融資方針は大きく変わらないと考えられます。
■ 様々な投資法に対する銀行の考え方
ここから、各投資手法の例をあげて解説します。
1、海外不動産投資
国内と海外の不動産投資は、全くの別物です。不動産に対する財産権への考え方が、国によって異なることもあります。個人投資家が投資する規模の物件の評価は、自行で融資していない場合、収益還元法でなく積算法で評価することが一般的です。
その点、海外の物件は評価が難しくなります。たいていの銀行は海外の不動産を評価・査定するスキル・ノウハウを有しません。保守主義の観点から、評価できないものは、0円と査定されることもあります。
特にプレビルドで竣工が予定より遅れている場合は、その傾向が強くなります。銀行から融資を受けて国内不動産投資を進めていく場合、海外物件は自己資本が充実するまで手掛けないほうが良いかもしれません。
2、太陽光発電投資
土地を取得・賃借して、設備を置いて、その稼働により収益を得るという点で、不動産賃貸業と類似点が多い投資です。天候での発電量変動はありますが、固定価格で買取られるので、一定期間は収益も安定しています。
設備は税法通り減価償却していれば、簿価評価でバランスシートを毀損することは少ないでしょう。ただし、買取価格は下落傾向にあるので、新規の投資は事業計画を綿密に精査したほうが良いでしょう。
3、ホテル・旅館業
民泊から高じて、ホテル・旅館業に進出される大家さんが増えています。カテゴリーは不動産賃貸業に近く、自己査定上でも超長期融資が受けやすいといえます。
銀行も事業計画が良ければ、融資します。収益性も通常のアパート・マンション賃貸より良いことが多いです。やりようによっては、ありでしょう。注意点ですが、ホテル・旅館業は、装置産業というよりは、サービス業のカテゴリーになります。
人のマネジメントが重要で、経営者の資質が問われます。建物を作って、運営はプロに任せるならば、不動産賃貸業として融資は通りやすくなります。一方、運営を自分でやる場合は、規模によりますが実績や経営スキルの証明が必要なこともあります。
ホテル・旅館業は、バブル崩壊時は構造不況業種でした。現在はインバウンド需要もあり盛り上がっていますが、新築が多く、需給バランスが崩れることに懸念する銀行も増えてきました。
個人投資家が手掛ける規模ならば、将来、共同住宅に転用できる構造・間取りにするのがベターといえます。そうすることで、融資審査の際にも銀行を説得しやすくなるでしょう。
4、コインランドリー経営
開業は、不動産投資に比べて少額の資金でできるため、参入障壁が低い事業です。事業計画を立てた時は採算が取れそうでも、近くに新規に出店され、赤字に転落することも想定されます。銀行から見ると、一般事業になりますので、おすすめはしません。
5、再建築不可物件投資
建築基準法上の再建築不可の物件は、銀行の評価が0円になります。利回りは高い傾向にありますが、融資を引いて規模を拡大する方針の場合、やめておいたほうが良いでしょう。
■ 高収益を狙えるものなら、あえて注力する道も
今回、事例にあげたそれぞれの投資手法は、儲からないとか悪いとかいうことではありません。あくまで、純資産・自己資本の充実していない方が、融資を受けて国内不動産投資をしたい場合は、やめておいたほうが良いということです。
逆に純資産の少ない方は融資を使って不動産賃貸業を拡大しにくい昨今、上記にあげた投資手法の中で、高収益を狙えるものがあれば、それに特化・注力するのも手でしょう。
今回は、銀行が資産の内容について、どう捉えているか、不動産賃貸業以外への投資や事業への取り組みについて、どう考えているかを解説していきます。
■ 銀行が最も重視するのは「 収益性 」
銀行は融資をする際に、融資先の収益性、債務償還能力、安全性などを重視します。収益性とは、儲ける力のことです。これが最も重視されます。
債務償還能力は、借入金を返済する能力。キャッシュフローで推し量ります。そして、安全性は前回説明したバランスシートの純資産による変事抵抗力や事業の安定性です。
不動産賃貸業は、他の事業に比べて安定していて、銀行にとって長期の事業計画が読みやすいのが特徴です。また、担保での融資保全率が高く貸倒リスクが低い。だからこそ、超長期の返済期間で比較的低金利で貸してもらえるのです。
それなのに、他の事業を手掛けて、もし経営がうまくいかなかった場合、そちらの事業に不動産賃貸業で得た本来は融資の返済に充てるべき資金を回されてしまうことを銀行は懸念します。
元々、アパートローンは地主向けで、その後サラリーマンに門戸を開きました。しかし、一般事業オーナー経営者への間口は狭いままです。逆を言えば、一般事業を手掛けると、不動産融資への間口が狭くなるといえます。
また、設備投資でなく、運用としての投資について、銀行は保守的です。銀行は事業資金を貸しますが、投資資金は貸さない傾向にあるのです。
昔から貸さなかったのではなく、バブルの時までは結構貸していました。その後のバブル崩壊でかなりの痛い目を見たため、方針を変えたということです。
一時は株式投資資金のみならず、不動産投資資金ももってのほかという時代がありました。バブル崩壊時は地価が下がり続け、不動産融資が焦げ付き、多くの銀行が破綻したり、救済合併されたりしましたから、仕方のないことです。
現在、当時の大変さを現場で見ていた行員が銀行の中枢を支えており、そのトラウマは消えていません。そのため、令和になってからもこの融資方針は大きく変わらないと考えられます。
■ 様々な投資法に対する銀行の考え方
ここから、各投資手法の例をあげて解説します。
1、海外不動産投資
国内と海外の不動産投資は、全くの別物です。不動産に対する財産権への考え方が、国によって異なることもあります。個人投資家が投資する規模の物件の評価は、自行で融資していない場合、収益還元法でなく積算法で評価することが一般的です。
その点、海外の物件は評価が難しくなります。たいていの銀行は海外の不動産を評価・査定するスキル・ノウハウを有しません。保守主義の観点から、評価できないものは、0円と査定されることもあります。
特にプレビルドで竣工が予定より遅れている場合は、その傾向が強くなります。銀行から融資を受けて国内不動産投資を進めていく場合、海外物件は自己資本が充実するまで手掛けないほうが良いかもしれません。
2、太陽光発電投資
土地を取得・賃借して、設備を置いて、その稼働により収益を得るという点で、不動産賃貸業と類似点が多い投資です。天候での発電量変動はありますが、固定価格で買取られるので、一定期間は収益も安定しています。
設備は税法通り減価償却していれば、簿価評価でバランスシートを毀損することは少ないでしょう。ただし、買取価格は下落傾向にあるので、新規の投資は事業計画を綿密に精査したほうが良いでしょう。
3、ホテル・旅館業
民泊から高じて、ホテル・旅館業に進出される大家さんが増えています。カテゴリーは不動産賃貸業に近く、自己査定上でも超長期融資が受けやすいといえます。
銀行も事業計画が良ければ、融資します。収益性も通常のアパート・マンション賃貸より良いことが多いです。やりようによっては、ありでしょう。注意点ですが、ホテル・旅館業は、装置産業というよりは、サービス業のカテゴリーになります。
人のマネジメントが重要で、経営者の資質が問われます。建物を作って、運営はプロに任せるならば、不動産賃貸業として融資は通りやすくなります。一方、運営を自分でやる場合は、規模によりますが実績や経営スキルの証明が必要なこともあります。
ホテル・旅館業は、バブル崩壊時は構造不況業種でした。現在はインバウンド需要もあり盛り上がっていますが、新築が多く、需給バランスが崩れることに懸念する銀行も増えてきました。
個人投資家が手掛ける規模ならば、将来、共同住宅に転用できる構造・間取りにするのがベターといえます。そうすることで、融資審査の際にも銀行を説得しやすくなるでしょう。
4、コインランドリー経営
開業は、不動産投資に比べて少額の資金でできるため、参入障壁が低い事業です。事業計画を立てた時は採算が取れそうでも、近くに新規に出店され、赤字に転落することも想定されます。銀行から見ると、一般事業になりますので、おすすめはしません。
5、再建築不可物件投資
建築基準法上の再建築不可の物件は、銀行の評価が0円になります。利回りは高い傾向にありますが、融資を引いて規模を拡大する方針の場合、やめておいたほうが良いでしょう。
■ 高収益を狙えるものなら、あえて注力する道も
今回、事例にあげたそれぞれの投資手法は、儲からないとか悪いとかいうことではありません。あくまで、純資産・自己資本の充実していない方が、融資を受けて国内不動産投資をしたい場合は、やめておいたほうが良いということです。
逆に純資産の少ない方は融資を使って不動産賃貸業を拡大しにくい昨今、上記にあげた投資手法の中で、高収益を狙えるものがあれば、それに特化・注力するのも手でしょう。
なぜ相続対策で不動産を買うなら「都心物件」にすべきなのか?
相続税評価額が相対的に低いため、相続対策として有利
相続対策は、昔から必ずと言っていいほど不動産を駆使して行われます。理由としては、同じ金額の資産でも、現金よりも不動産の方が相続評価額を抑えることができるからです。
現金も不動産も、相続税評価額は原則として「時価」です。現金は、1,000万円なら1,000万円が時価なので、その金額がそのまま相続税評価額となります。
一方で、不動産も時価が相続税評価額となりますが、厳密に時価を把握するのであれば不動産をすべて相続時に売却して時価を知る必要が生じます。
しかしながら、時価を知るために全部の不動産を売却することは非現実的なため、行う必要はありません。不動産に関しては、相続税評価額を計算する簡易なルールが設けられており、そのルールで求められた価額を時価として良いということになっています。
その計算のルールに用いられるのが、土地については相続税路線価、建物については固定資産税評価額となります。
土地の相続税路線価については、土地の時価の80%程度の金額で価格が設定されています。また、建物の固定資産税評価額も、新築当初は請負工事金額の50%程度であり、かなり安いといえます。
そのため、たとえば単純に5,000万円の現金だけを持っているAさんと、時価が5,000万円の土地を持っているBさんでは、相続税はAさんのほうが高くなります。
相続税評価額をみてみると、Aさんは現金なので5,000万円であるのに対し、Bさんは土地なので4,000万円(時価の80%)です。
AさんもBさんも相続人がそれぞれ「配偶者と子ども2人」だとすると、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×法定相続人3人)となります。
すると、Aさんの相続人には5,000万円から4,800万円を控除して残った200万円に対し相続税が発生します。
それに対して、Bさんの相続人には、控除額が課税価格より多いため、相続税は発生しないことになります。
AさんもBさんも資産の時価総額は5,000万円なのに、現金か不動産かの違いによって、相続税の金額や、発生の有無まで異なってしまうのです。このように不動産は相続税評価額が現金より低いため、相続対策として有利な資産になります。
「賃貸物件」なら、より評価額が下がり現金も得られる
不動産は、土地については相続税路線価、建物については固定資産税評価額を用いて相続税評価額を決定します。相続税路線価や固定資産税評価額は、時価よりも安いため、そのままでも現金を持つよりは相続対策となっています。
ただし、同じ不動産でも賃貸物件になるとさらに評価額が下がることになります。賃貸物件は、入居者が入っていると、所有者が自分ですぐに利用することはできません。相続税評価では、「自分で使っている不動産」よりも「他人に貸している不動産」のほうが、権利の制約があることから価値が劣るという考え方をします。
そのため、自宅よりもアパートや賃貸マンションのように、他人に貸している不動産の方が評価額は下がるのが基本的な仕組みです。
まず、建物については他人に貸すと「借家権割合による評価減」の適用を受けます。借家権割合による評価減は、一律30%の減額となります。固定資産税評価額が5,000万円の建物なら、相続税評価額が3,500万円(=5,000万円×70%)と計算されます。
次に、土地については「貸家建付地評価減」の適用を受けます。貸家建付地は少々複雑な計算をしますが、以下の式で計算されます。
貸家建付地の価格=路線価評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
借家権割合は全国一律で30%です。借地権割合はエリアによって30%~90%の数値が指定されています。たとえば、借地権割合が70%の土地だと、貸家建付地としての土地の評価額は以下のようになります。
貸家建付地=路線価評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)
=路線価評価額 ×(1-70%×30%)
=路線価評価額 ×(1-21%)
=路線価評価額 × 79%
上記の例では、貸家建付地は路線価評価額よりもさらに21%も評価が下がることになります。このように不動産の中でも賃貸物件となると、建物も土地も評価額が下がる仕組みとなっています。
そして賃貸物件は家賃収入という現金も生み出します。評価を下げるだけでなく、現金も生み出すというメリットがあることから、賃貸物件を保有することは優れた相続対策となるのです。
相続財産を減らし、ある程度の現金を残せる「借入金」
不動産投資は現金を賃貸物件に換えることになるため、相続対策として有効です。不動産投資では、借入金を用いることが多いですが、借入金も相続対策として効果があります。
借入金を使うと「相続財産を減らせる」ことや、「現金を残せる」という2つのメリットがあります。借入金は、マイナスの財産なので、借入金があると相続財産を減らすことができます。しかも、借入金はマイナスの現金なので、相続税評価額は相続時の借入残高がそのまま減額されます。
たとえば、相続税評価額が3,000万円の賃貸不動産を持っていたとします。そして、相続時の借入残高が2,500万円だとします。
すると、相続税評価額は3,000万円から2,500万円を控除した500万円になります。借入金があることで、相続税評価額そのものを小さくすることができるのです。
また、借入金は被相続人に現金を残すという効果もあります。不動産投資を全て手持ちの自己資金で行ってしまうと、被相続人の財産から現金を多く減らしてしまいます。
不動産は節税効果をもたらしますが、現金を減らし過ぎることには注意が必要です。相続税は現金納付が原則です。相続財産が不動産だけだと、相続人に納税する現金が足りず、結局のところ相続時に不動産を手放さなくてはいけなくなる恐れがあります。
相続対策では不動産を引き継いだ相続人が、納税時に困ることがないよう納税資金も相続できるようにしておくことが理想です。
よって、相続対策では現金をすべて不動産に換えてしまうのではなく、借入金を使いながら、ある程度現金も残しておくことが重要となります。
流動性が高く、需要も底堅い「都心物件」がおすすめ
相続対策で不動産投資をするなら、都心物件がおすすめとなります。理由としては、都心物件は流動性が高く、賃貸需要も底堅いからです。
相続人が複数人いる場合、それぞれの相続人の事情が異なっていることがあります。たとえば、長男は不動産が欲しいと思っていても、次男の家では子どもが私立の医学部に行ったため現金が欲しいと思っているというような場合です。
このようなとき、引き継ぐ不動産がすぐに売却できれば、理想的です。たとえば、相続分に見合った不動産を相続人分購入しておき、相続人それぞれに分け与えることを考えます。ただし、不動産は通常売却するまでに時間がかかりやすく、換金できるまでの時間が比較的長い商材でもあります。相続対策として不動産投資を検討するならば、相続人の事情に合わせて保有や売却がしやすい、流動性の高い物件を選択することが重要となります。
資産家による不動産投資の実態、資産家は本当に有利なのか
不動産投資はサラリーマンなど、多くの人に門戸が開かれていますが、かつてはそうではありませんでした。いわゆる資産家と呼ばれる人たちが取り組むものであり、「先祖代々の土地などがなければ縁がないもの」というのは、多くの人が抱いてきたイメージではないでしょうか。しかしその状況が変わりサラリーマン大家と呼ばれる人たちが続々と誕生しています。
それでもなお資産家のほうが圧倒的に有利という声が絶えません。果たしてそれは本当なのでしょうか。既存の土地を持たない人が続々と不動産投資に参入する時代において古参投資家たちの不動産投資とはどう違うのでしょうか。そこで本記事では不動産投資と資産家の関係について考察してみます。
本来、不動産投資は資産家の専売特許だった

(画像=voyata/Shutterstock.com)
アパートやマンション、駐車場経営というと「先祖代々の土地がある人の商売」という概念があります。しかもこれは多くの人が定着しているイメージであり、現代でもそういった考えを持っている人は少なくありません。不動産投資を始めるのに欠かせない土地や建物といった収益不動産は、文字通り資産家だけが持っている専売特許でした。そのため収益不動産を持っていない人が新たに購入して経営を始めたとしても成功できるだけのノウハウがなかったのです。
不動産投資の門戸が開かれて「サラリーマン大家」が急増
しかし今では、不動産投資に関する情報やノウハウが確立され、投資家向けの新たなサービスが登場し、その状況が大きく変わっています。既存の不動産を持っていない人が新たに物件購入をして、そこから不動産投資を始めても十分成功できる環境が構築されているのです。これにはインターネットによる情報流通の発展や金融機関による個人投資家向け融資商品の拡充によって、個人投資家が必ずしも決定的に不利な状況ではなくなったことが大きく関わっています。
その結果、安定的な収入や社会的な信用というサラリーマン特有の強みを活かして銀行融資を利用し、不動産経営を始めるサラリーマン大家が急増したのです。
今や資産家と「サラリーマン大家」に違いはない?
資産家以外にも門戸が開かれ、投資家にとって選択の余地が広がったことは喜ばしいことです。それでは、「資産家とサラリーマン大家との間には一切差はないのか」というと、そんなことはありません。資産家には既存の不動産という武器があります。購入しなくても相続などによって取得した不動産があるため、この点においては依然として圧倒的に有利です。
土地があるのであれば建物を建てる費用だけでアパートやマンションの経営を始められます。資産を保有する人は銀行からの評価が高いため融資を利用する際にも有利な条件を引き出しやすいでしょう。投資コストが少なくて済む分、不動産投資の利回りとキャッシュフローは好転します。一方で今どきの不動産投資ではサラリーマン大家が有利になる部分もあるのです。
なぜなら立地条件など物件選びの自由度が高いからです。相続などで土地を受け継いだ資産家の場合、不動産投資はあくまでも「既存の不動産をどのように活用するか」という視点であり、立地を容易に変えることができないケースもあります。一方既存の不動産がない人は集客力の高い魅力的な物件を選ぶことから始められるため、資産家が所有している物件よりも競争力の高い物件を選ぶことも可能です。
成功のカギは不動産の価値を見分ける力
不動産投資は地域によって物件同士の競争が激しくなっているため、「空いている土地があるから賃貸経営でも始めてみよう」というだけでは投資として成立しないケースも少なくありません。既存の不動産という武器があるとはいえ、「対象の不動産(立地を含む)がどれだけの競争力を持っているか」によって本当に有利なのかが決まる時代になっているということです。
現代は資産の有無ではなく中身や価値、収益力が問われているといえます。そんな時代において不動産投資の成否を分けるのは、情報収集力やその情報を的確に分析し、投資に反映する能力であるといえるのかもしれません。(提供:アセットONLINE)
50代でも不動産投資はできる?知っておきたいメリットと注意点を解説
50代になると、仕事上ではある程度目標を達成し、そろそろ老後の準備をしようかという人も増えてくるかと思います。昔と違って退職金だけでは老後の生活が不安視される時代ですので、資産形成は自分でなんとかしようという方も多いでしょう。
資産形成の一つの選択肢として不動産投資があります。不動産投資はシミュレーション通りに運用できれば安定した投資です。しかし、定年までに残された時間が少なくなった中、どのように取り組めば良いのでしょうか。
この記事では50代の方が不動産投資を始める際のメリットと注意点をご紹介します。
- 50代で不動産投資を始めるメリット
1-1.不動産投資に使える資金を捻出しやすい
1-2.30代・40代よりも不動産投資に時間を使いやすい
1-3.老後に必要な資金をイメージしやすい - 50代から不動産投資を始める際に注意しておくこと
2-1.限られた融資期間内でもキャッシュフローのある物件を選ぶ
2-2.金利上昇リスクに備えて繰上返済を検討する
2-3.不動産ローン完済後の資金計画を立てておく - まとめ
1.50代で不動産投資を始めるメリット
50代からでは資産形成や貯蓄を始めるのには遅い、と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、投資で資産形成をするには決して条件が悪いというわけではありません。50代で不動産投資を始めるメリットについて見てみましょう。
1-1.不動産投資に使える資金を捻出しやすい
総務省「家計調査報告(貯蓄・負債編)2018年平均結果(二人以上の世帯)」によると、50代は年代別に見ると最も収入の多い年代のため、投資に使える資金がある程度貯めやすい年代であると言えます。また、定年の時期が迫っていますので、退職金の使い方を具体的に考える時期でもあるでしょう。50代から始める不動産投資では、これまでの貯蓄や毎月の家計の黒字収支、いずれ受け取ることができる退職金などを有効に活用した投資の仕方ができるという点で取り組みやすいことが考えられます。
1-2.30代・40代よりも不動産投資に時間を使いやすい
50代になると本業が安定し、子育てにかける労力も減っているでしょう。これにより空いた時間を不動産投資の勉強やセミナーへの参加など有効活用できるというメリットがあります。
時間に余裕があれば、慎重に不動産会社や物件を比較検討して選ぶことができます。限られた資金の投資先をじっくりと検討しやすいのも、暮らしが安定した50代から投資を開始する際のメリットと言えるでしょう。
1-3.老後に必要な資金をイメージしやすい
50代は定年退職までの期間が差し迫っているため、投資の具体的な目標を立てやすい状況にあると言えます。老後に必要な資金はいくらなのか、購入した物件をいずれ売却するのか、居住用として利用するのか、相続するのかなど、よりイメージの湧きやすい環境で不動産投資の出口戦略を検討することができるでしょう。
不動産投資を始めて検討する方にとって、現在の状況から将来をイメージしやすい点はメリットであると言えます。
2.50代から不動産投資を成功させるために注意しておくこと
ここまで、50代から不動産投資を始めるメリットを解説してきました。しかし一方で、30代や40代と比較すると融資年数などの条件が悪くなってしまうなど懸念点もあります。
次に、具体的にどのような点に注意しながら不動産投資に取り組めばよいのかを考えてみましょう。
2-1.限られた融資期間内でもキャッシュフローのある物件を選ぶ
50代で不動産投資をスタートする場合、定年退職までは10~15年前後の期間しかありませんので、長期の融資を受けられない可能性が高まります。不動産投資の最終完済年齢は75歳とも言われており、30年などの長期ローンを想定した物件を購入することは難しくなります。また、融資年数が短すぎると月々のキャッシュフローを圧迫してしまう点にも注意が必要です。
月々の返済がネックにならないように、ローンの返済期間が短い場合でも資金の持ち出しを避けられるキャッシュフローの潤沢な物件を選ぶことが大切です。
月々の返済がネックにならないように、ローンの返済期間が短い場合でも資金の持ち出しを避けられるキャッシュフローの潤沢な物件を選ぶことが大切です。
2-2.金利上昇リスクに備えて繰上返済を検討する
退職金に余裕があるようであれば、受け取った後の繰上返済を検討してみましょう。繰上返済をすることで月々の返済額を減らせたり、返済期間の短縮によって完済の時期が早くなるメリットがあります。
ローンの金利が上昇すると月々のキャッシュフローを圧迫し、投資効果が悪化してしまいます。このような事態に備え、退職金などで繰上返済することを検討しておきましょう。
2-3.不動産ローンの完済後の資金計画を立てておく
定年退職後にローンを完済してキャッシュフローが良化したとしても、経年劣化した物件の修繕費、家賃下落、入居率の低下など、不動産投資における様々なリスクは軽減するわけではありません。このようなリスクに備え、キャッシュフローの貯蓄や修繕計画の立案をしておくことが重要になります。
ローンの完済後はキャッシュフローを潤沢に生み出せるタイミングでもあります。いざという時の資金がなくならないように、完済後の賃貸経営や資金に関する計画をすることが大切です。
まとめ
50代から不動産投資を始める際のメリットと注意点についてご紹介しました。
50代は今までより収入も安定し、子供の教育も一旦落ち着く年代でもあります。老後の具体的な課題が見えやすい50代だからこそ、30~40代の方とは違った手法の投資も可能です。貯蓄や退職金を有効活用して、計画的に資産形成するようにしましょう。
50代は今までより収入も安定し、子供の教育も一旦落ち着く年代でもあります。老後の具体的な課題が見えやすい50代だからこそ、30~40代の方とは違った手法の投資も可能です。貯蓄や退職金を有効活用して、計画的に資産形成するようにしましょう。
新築物件投資で知っておきたい、新築プレミアムとは?
不動産投資に取り組む場合、区分マンションや1棟マンション、戸建てなど様々な投資対象と種類がありますが、1つの大きな「括り」として新築と中古の違いがあります。その中で、新築物件投資には避けて通ることのできない「新築プレミアム」という概念があります。新築プレミアムは物件購入のコストと考えることができ、これを考慮しないことには収支を見誤ってしまう可能性すらあるでしょう。そのため「言葉を聞いたことがある程度」「言葉自体を初めて聞いた」という人は、ぜひこの機会に新築プレミアムを理解しておきましょう。
新築プレミアムとは?平均的な相場とは?

(画像=Roman Babakin/Shutterstock.com)
新築プレミアムのプレミアムとは、直訳すると「上乗せ金」のような意味合いです。つまり新築プレミアムとは、新築物件だけに上乗せされ価格決定に影響を与えるお金といえます。一般的に新築プレミアムは、物件価格の1~3割程度というのが相場です。例えば5,000万円の新築物件で最大の3割の新築プレミアムだった場合は、1,500万円程度が上乗せになるため、決して看過できないレベルといえるでしょう。
新築プレミアムがある理由
なぜ新築プレミアムという概念および価格差があるのでしょうか。そこには、私たち日本人の価値観が深く関わっています。日本人は伝統的にどんなものでも新品であることに、とりわけ高い価値を見出す傾向があります。これは不動産に準ずる高額商品の車でも同様で新車と中古車はそれぞれにまったく別の市場で流通しています。そのため「新車は高く、中古車は安い」というのが常識です。
不動産や車が一度でも誰かの所有物になると、「手垢がついた」という表現もあるように、すでに新品の価値はないと見なされます。これは、たとえ1ヵ月程度しか所有していなくても関係ありません。そのため、一度中古市場で流通したものが2番目、3番目のオーナーへとわたっていく際には、新品によるプレミアム価格が反映されていない相場通りの価格が適用されます。
これだけを見ると新築プレミアムは購入者にとって不利な価格決定プロセスであるように感じるかもしれませんが、新築物件には入居者にとっても特別な価値があるため、家賃を高めに設定できるというメリットもあるのです。
新築プレミアムを考慮した不動産投資のあるべき姿
それでは新築物件投資を始めるにあたって新築プレミアムを意識したうえで投資を成功へ導くには、どうしたほうがよいのでしょうか。新築プレミアムはデメリットと見なす場合が多いです。しかし新築物件にはそれ以外のデメリットがあまりなく、むしろメリットが多いことにも着目するべきでしょう。
そのメリットをうまく活かし新築プレミアムを克服できる不動産投資の形を作れば「トータルで成功する」という考え方です。少々家賃が高くても誰も入居したことがない新築物件に住みたい人はたくさんいます。「購入価格の上昇分を高めの家賃設定でカバー」「新築が持つ空室リスクの低さを味方につけて利回りを確保する」などのスタンスで取り組めば、新築物件のメリットを最大化できるでしょう。
また新築物件は融資がつきやすいため、属性の高い人であれば新築であることを活かして、より有利な条件を引き出すことも視野に入ります。さらにこれは見えにくいポイントですが、新築物件は「その時点で最新の設備が使用されている」「耐震性能の高さによる地震リスクの低さ」なども大きなメリットといえるでしょう。
中古物件は購入価格こそ抑えられるかもしれませんが、メンテナンスや大規模改修など購入後のコストがかさむ可能性は十分にあります。新築物件投資には例に挙げたように多くのメリットもあるため、新築プレミアムの分をカバーできる余地は十分にあるのです。それをいかに味方につけるかが、新築プレミアムを考慮した不動産投資のあるべき姿といえるでしょう。(提供:アセットONLINE)
即行動せよ!私が28歳、貯金ゼロ、年収300万円から自己資金を貯めた方法
2020/1/4 掲載
サラリーマン大家の斉藤です。今回は私が不動産投資を志し、物件を買うために実践したことを発表します。特に20代、30代で、ゼロから不動産投資を始めようという人向けの内容です。
どうやってゼロから初期の物件を手に入れたか? この点に絞って説明していきます。ゼロから1( イチ )を作るのが最も難しいとされます。特に自己資金を稼ぐのが最もハードルが高いと言えましょう。
25歳で正社員となり、1年で転職、2社目がブラック労働の投資用不動産販売会社で、ここも1年で転職。3社目となる会社に就職した時、私の貯金はゼロでした。
むしろ親から50万円も借金をしている状態というマイナスからのスタートでした。( 妻と結婚したことで、親からの借金は免除してもらいました・泣。ありがたい )
その後、結婚して自宅としてJR高田馬場駅徒歩7分の1LDK( 45㎡ )マンションを住宅ローンで購入( 諸費用含め全額借入 )。

JR高田馬場徒歩7分の区分所有、当初は自己使用していた
この状態から、私の不動産投資はスタートしました。
当時( 2007年末~2008年 )は1,000万円以下で実質利回り10%という物件がたくさんありました。芦沢晃さんのようなサラリーマン投資家を目指していたので、このタイプの物件を買うことを目標にしました。
1件目は自宅ですので、実質的に「 初 」となる投資用物件( 2号物件 )を買ったのは2008年9月。自己資金は250万円で、510万円のローンを妻名義で組んで買えました。

2号物件、都営三田線「 白山 」駅730万円
2007年~2008年9月と、2年弱で自己資金250万円を貯めました。さすがにローンは妻に借りてもらいましたが、自己資金部分は私が妻に貸付しました。( その後、私の妻への債権は時効で消滅 )。
妻に借金をしてもらえた理由は3つあります。
毎月家賃が入り、返済は家賃から行われ、管理費修繕積立金を払っても、毎月3万円残る。さらに私が5万円入金し続けるので、毎月8万円ずつ妻の口座には貯金ができていく状態になりました。
今回のコラムのポイントはココです。年収300万円時代のわたしの手取は確か18万円前後でした。ここからまず自宅の住宅ローン、管理費等の合計額11万円を払います。7万円で生活しなければいけません。
7万円ではまともな生活が出来ません。携帯電話と水光熱費を払ったら、もう残りは4万円程、ボーナス( 1カ月、年2回 )で何とか赤字を免れるだけで、貯金などできようはずがありません。
どうしたかと言えば、そう「 副業 」です。私は友人の会社の総務・経理業務を受注して、毎月15万円を得ていたのです。
今でこそ、世の中は副業解禁ムードですが、当時( 2007年頃 )はまだまだ副業をしている人は少ない時代でした。副業をやっている人がいても、コッソリやっていた状態でしたね。
私も有給休暇を取得したり、平日早く仕事を切り上げたり、土日に友人の会社に出勤したりしてコッソリやっておりました。
オマケにこの15万円は業務委託契約で支払われていたので、源泉徴収や社会保険料が控除されることなく、まるまる残りました。この15万円が、2号物件の頭金となったのです。
本業の手取り給与に近い額の報酬を貰えると、肉体・精神は疲労しますが、お金はしっかりと手元に残ります。この収入、まさに血と汗と涙の結晶を、不動産投資の頭金のために貯蓄したのです。
さて、副業で確実に稼ぐために必要なことは何でしょうか? それは「 本業で体力・精神力を失わないこと 」です。
日本人は真面目なので、勤務先の業務に全身全霊をかけて取り組む人が多いと思います。私もしばらくはそんなサラリーマンでした。しかし、これではいけません。
勤め先は無理をして頑張って成果を出す勤め人が大好きです! 給料は増えないのに、成果が青天井なのですから、儲かって仕方がありません。口では「 無理するな 」と言っていても、黙ってサービス残業して成果を出してくれると、「 ありがたい 」のです。
でも、本業で毎日残業をして、休日出勤をしていたら、副業に時間を使うことはできません。
本業で100%満足な額の給与( つまり、生活費をカバーした上に投資資金まで貯蓄できる額の給与 )を得られているなら別ですが、そうでなければ雇用契約で約束した以上の労働をしてはいけません。
私の場合には「 債権回収 」という業種柄、督促行為は夜20時以降禁止です。早朝深夜の訪問もダメ。弁護士が関与したら債務者に直接接触してはいけない。など、業法上の厳しい制限がありました。
そして借金取り( 回収担当者 )は「 営業 」する必要がありません。遅くまで残業して督促してはいけないので、早く帰ることが出来ました。( それでも「 付き合い残業 」がありましたが )
ポイントは、「 いくらでも働いて欲しい 」勤め先からの攻撃を守らなければいけないということ。自分のために働く( =副業 )、体力・精神力を温存しなければいけないのです。

このような状況です。中身の労働力を食べられてしまったらサラリーマンの副業はオシマイです。特に「 低賃金 」なのに「 厳しい労働環境・労働条件 」というダブルパンチを喰らってしまっては、再起不能となります。冗談ではなく、「 人生 」が再起不能となります。
資産形成ができず、生活を維持するだけで精いっぱいなまま、歳だけとって、ふと、気が付いたら、無資産老人になって勤め先から追い出されるだけです。
同僚に迷惑がかかろうが、何だろうが、ブラック労働の会社を即退職して、常識的な労働環境の会社に転職です。自分の人生を最優先に考えるべきです。
私がそうしたように、ブラック企業退職後の転職先は生活費がカバーできて、労働力が温存できる環境であればOKです。資産形成は副業でやればよいのです。
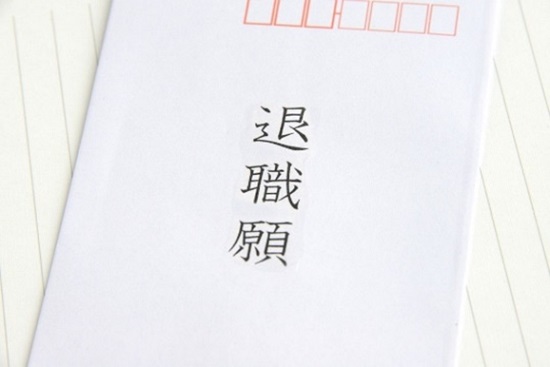
副業ができる企業で働いている人は、「 即行動 」。人は誰も「 今日が一番若い 」のですから、今すぐ始めるべきです。明日でもありません、今です。
1件目の不動産を買うために必要な金額を決め、そのためには副業を何カ月続ければ良いかを計算します。私の場合には2件目の投資物件の250万円( 頭金 )まで毎月10万円貯金、25カ月計画でスタート。結果的には計画を前倒して2年弱で到達しました。
極端な話、友人と起業しなかったのであれば、自宅周辺のファミリーレストランでアルバイトでもしていたと思います。土日だけでも時給1,000円×8時間×週2回( 月8回 )=64,000円です。

3年頑張ったら200万円にもなります。20代や30代前半であれば平日の深夜でもいいでしょう。ド根性です!
私はこのように、ダブルワークによって投資資金を貯めました。こんな無理をしている人は私の勤め先にはいませんでした。勤め先の同僚は私と似たような安い給与なのに、休日に趣味の野球をしたり、ゴルフに行ったり、平日も連れだって飲みに行っていました。
恐らく彼らは、今も似たような生活をしているでしょうし、収益不動産は1件も所有していないでしょう。資産もなく、給料だけで生活を維持しているであろうことは想像できます。
確かに、それでも当面の生活はできるし、家族には普通の暮らしをさせることもできる。だからほとんどの人は「 やらない 」のです。私の話を聞いてうらやましいと思ったとしても、行動に移す人はわずかです。
平均的な努力しかせずに、平均以上の成果を望むのは『 愚か 』なことです。現状に不満があるのであれば、まず平均的であることをやめなければいけません。
是非、今すぐ、一歩踏み出しましょう。私のような不器用な努力の仕方でも3年もすれば見える世界が変わってきました。皆さんが始めるのはいつでしょう?
( 終 )
どうやってゼロから初期の物件を手に入れたか? この点に絞って説明していきます。ゼロから1( イチ )を作るのが最も難しいとされます。特に自己資金を稼ぐのが最もハードルが高いと言えましょう。
転職2回で貯金ゼロ、で年収300万円の会社へ就職
25歳で正社員となり、1年で転職、2社目がブラック労働の投資用不動産販売会社で、ここも1年で転職。3社目となる会社に就職した時、私の貯金はゼロでした。
むしろ親から50万円も借金をしている状態というマイナスからのスタートでした。( 妻と結婚したことで、親からの借金は免除してもらいました・泣。ありがたい )
その後、結婚して自宅としてJR高田馬場駅徒歩7分の1LDK( 45㎡ )マンションを住宅ローンで購入( 諸費用含め全額借入 )。

JR高田馬場徒歩7分の区分所有、当初は自己使用していた
この状態から、私の不動産投資はスタートしました。
1件目の投資物件( 都心・中古区分・実質利回り10%、1,000万円以下 )
当時( 2007年末~2008年 )は1,000万円以下で実質利回り10%という物件がたくさんありました。芦沢晃さんのようなサラリーマン投資家を目指していたので、このタイプの物件を買うことを目標にしました。
1件目は自宅ですので、実質的に「 初 」となる投資用物件( 2号物件 )を買ったのは2008年9月。自己資金は250万円で、510万円のローンを妻名義で組んで買えました。

2号物件、都営三田線「 白山 」駅730万円
2007年~2008年9月と、2年弱で自己資金250万円を貯めました。さすがにローンは妻に借りてもらいましたが、自己資金部分は私が妻に貸付しました。( その後、私の妻への債権は時効で消滅 )。
妻に借金をしてもらえた理由は3つあります。
①自己資金250万円を実質的に私が出したのですが、所有権は100%妻
②家賃の入金口座は妻で、全額妻の管理下に
③別途毎月5万円を私がその口座に入金して万全を期す
②家賃の入金口座は妻で、全額妻の管理下に
③別途毎月5万円を私がその口座に入金して万全を期す
毎月家賃が入り、返済は家賃から行われ、管理費修繕積立金を払っても、毎月3万円残る。さらに私が5万円入金し続けるので、毎月8万円ずつ妻の口座には貯金ができていく状態になりました。
年収300万円で、どうやって2年弱で250万円貯めたのか?
今回のコラムのポイントはココです。年収300万円時代のわたしの手取は確か18万円前後でした。ここからまず自宅の住宅ローン、管理費等の合計額11万円を払います。7万円で生活しなければいけません。
7万円ではまともな生活が出来ません。携帯電話と水光熱費を払ったら、もう残りは4万円程、ボーナス( 1カ月、年2回 )で何とか赤字を免れるだけで、貯金などできようはずがありません。
どうしたかと言えば、そう「 副業 」です。私は友人の会社の総務・経理業務を受注して、毎月15万円を得ていたのです。
今でこそ、世の中は副業解禁ムードですが、当時( 2007年頃 )はまだまだ副業をしている人は少ない時代でした。副業をやっている人がいても、コッソリやっていた状態でしたね。
私も有給休暇を取得したり、平日早く仕事を切り上げたり、土日に友人の会社に出勤したりしてコッソリやっておりました。
オマケにこの15万円は業務委託契約で支払われていたので、源泉徴収や社会保険料が控除されることなく、まるまる残りました。この15万円が、2号物件の頭金となったのです。
本業の手取り給与に近い額の報酬を貰えると、肉体・精神は疲労しますが、お金はしっかりと手元に残ります。この収入、まさに血と汗と涙の結晶を、不動産投資の頭金のために貯蓄したのです。
副業をするために必要なこと
さて、副業で確実に稼ぐために必要なことは何でしょうか? それは「 本業で体力・精神力を失わないこと 」です。
日本人は真面目なので、勤務先の業務に全身全霊をかけて取り組む人が多いと思います。私もしばらくはそんなサラリーマンでした。しかし、これではいけません。
勤め先は無理をして頑張って成果を出す勤め人が大好きです! 給料は増えないのに、成果が青天井なのですから、儲かって仕方がありません。口では「 無理するな 」と言っていても、黙ってサービス残業して成果を出してくれると、「 ありがたい 」のです。
でも、本業で毎日残業をして、休日出勤をしていたら、副業に時間を使うことはできません。
本業で100%満足な額の給与( つまり、生活費をカバーした上に投資資金まで貯蓄できる額の給与 )を得られているなら別ですが、そうでなければ雇用契約で約束した以上の労働をしてはいけません。
私の場合には「 債権回収 」という業種柄、督促行為は夜20時以降禁止です。早朝深夜の訪問もダメ。弁護士が関与したら債務者に直接接触してはいけない。など、業法上の厳しい制限がありました。
そして借金取り( 回収担当者 )は「 営業 」する必要がありません。遅くまで残業して督促してはいけないので、早く帰ることが出来ました。( それでも「 付き合い残業 」がありましたが )
ポイントは、「 いくらでも働いて欲しい 」勤め先からの攻撃を守らなければいけないということ。自分のために働く( =副業 )、体力・精神力を温存しなければいけないのです。

このような状況です。中身の労働力を食べられてしまったらサラリーマンの副業はオシマイです。特に「 低賃金 」なのに「 厳しい労働環境・労働条件 」というダブルパンチを喰らってしまっては、再起不能となります。冗談ではなく、「 人生 」が再起不能となります。
資産形成ができず、生活を維持するだけで精いっぱいなまま、歳だけとって、ふと、気が付いたら、無資産老人になって勤め先から追い出されるだけです。
ブラック企業に身を置いている人は即退職
同僚に迷惑がかかろうが、何だろうが、ブラック労働の会社を即退職して、常識的な労働環境の会社に転職です。自分の人生を最優先に考えるべきです。
私がそうしたように、ブラック企業退職後の転職先は生活費がカバーできて、労働力が温存できる環境であればOKです。資産形成は副業でやればよいのです。
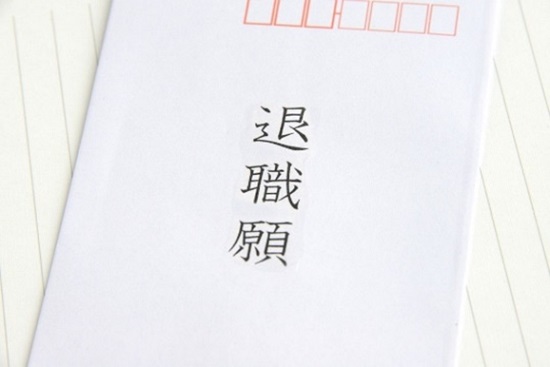
副業ができる状況なら即行動
副業ができる企業で働いている人は、「 即行動 」。人は誰も「 今日が一番若い 」のですから、今すぐ始めるべきです。明日でもありません、今です。
1件目の不動産を買うために必要な金額を決め、そのためには副業を何カ月続ければ良いかを計算します。私の場合には2件目の投資物件の250万円( 頭金 )まで毎月10万円貯金、25カ月計画でスタート。結果的には計画を前倒して2年弱で到達しました。
極端な話、友人と起業しなかったのであれば、自宅周辺のファミリーレストランでアルバイトでもしていたと思います。土日だけでも時給1,000円×8時間×週2回( 月8回 )=64,000円です。

3年頑張ったら200万円にもなります。20代や30代前半であれば平日の深夜でもいいでしょう。ド根性です!
結局やらない人が9割
私はこのように、ダブルワークによって投資資金を貯めました。こんな無理をしている人は私の勤め先にはいませんでした。勤め先の同僚は私と似たような安い給与なのに、休日に趣味の野球をしたり、ゴルフに行ったり、平日も連れだって飲みに行っていました。
恐らく彼らは、今も似たような生活をしているでしょうし、収益不動産は1件も所有していないでしょう。資産もなく、給料だけで生活を維持しているであろうことは想像できます。
確かに、それでも当面の生活はできるし、家族には普通の暮らしをさせることもできる。だからほとんどの人は「 やらない 」のです。私の話を聞いてうらやましいと思ったとしても、行動に移す人はわずかです。
平均的な努力しかせずに、平均以上の成果を望むのは『 愚か 』なことです。現状に不満があるのであれば、まず平均的であることをやめなければいけません。
是非、今すぐ、一歩踏み出しましょう。私のような不器用な努力の仕方でも3年もすれば見える世界が変わってきました。皆さんが始めるのはいつでしょう?
( 終 )
不動産投資家が知っておくべき「利回り利回り」の計算方法
「表面利回り」と「実質利回り」を知る
不動産投資の広告などで、「利回り10%」といった表示を見かけることがあります。通常、これは家賃収入を物件価額で割った数値で表示されていますが、これを「表面利回り」といいます。
たとえば、毎年1000万円の家賃収入が得られる1億円の物件であれば、表面利回りは10%となります。しかし、実際には管理費や修繕費、税金といった支出が生じます。不動産投資では、これらの経費を差し引いた実際の運用利回り=実質利回りを知ることが大切です。
表面利回りと実質利回りの、基本的な計算式は以下の通りです。
表面利回り=年間家賃収入÷不動産価格
実質利回り=(年間家賃収入-諸経費-空室損益)÷(不動産価格-購入時諸費用)
たとえば、毎年1000万円の家賃収入が得られる1億円の物件であれば、表面利回りは10%となります。しかし、実際には管理費や修繕費、税金といった支出が生じます。不動産投資では、これらの経費を差し引いた実際の運用利回り=実質利回りを知ることが大切です。
表面利回りと実質利回りの、基本的な計算式は以下の通りです。
表面利回り=年間家賃収入÷不動産価格
実質利回り=(年間家賃収入-諸経費-空室損益)÷(不動産価格-購入時諸費用)
営業にかかわる収益をあらわす「NOI」
実質利回りを計算するためには、家賃収入から維持管理費などの諸経費を差し引いた純営業収益がどれくらいになるのかがわからないといけません。純営業収益のことを英語で、「Net Operating Income」といい、略して「NOI」と呼ばれます。その計算式は以下の通りです。
NOI(純収益)=総賃料収入-諸経費
諸経費には固定資産税や修繕費、保険料などが該当します。ただし、融資を受けている場合の支払い金利や減価償却費は除きます。細かい話ですが、支払い金利は資金調達にかんする費用であり、営業にかんする費用ではないため、NOIには入れません。
また、「減価償却」とは、減価償却資産(建物など)の使用または時間の経過で減る部分について、その減耗部分を一定の方法で費用計上する会計手続きのことです。その費用は減価償却費として、会計上費用となりますが、キャッシュの動きがともなわないため、キャッシュフローを計算するためのNOIからは除くのです。
NOI(純収益)=総賃料収入-諸経費
諸経費には固定資産税や修繕費、保険料などが該当します。ただし、融資を受けている場合の支払い金利や減価償却費は除きます。細かい話ですが、支払い金利は資金調達にかんする費用であり、営業にかんする費用ではないため、NOIには入れません。
また、「減価償却」とは、減価償却資産(建物など)の使用または時間の経過で減る部分について、その減耗部分を一定の方法で費用計上する会計手続きのことです。その費用は減価償却費として、会計上費用となりますが、キャッシュの動きがともなわないため、キャッシュフローを計算するためのNOIからは除くのです。
将来の収益率を見るための「キャップレート」とは : https://lifeplan-navi.com/column/5218/
不動産投資家が知っておくべき「利回り」の計算方法|LIFE PLAN navi(ライフプランナビ) : https://lifeplan-navi.com/column/5218/
ライフプランnaviとは、充実した人生を送るための手助けとなる、ライフプランに関する情報を発信しているウェブサイトです。
人はそれぞれ、自分の生き方を持っているはずです。家族との時間を大切にする方もいれば、仕事や趣味に生きる方もいるでしょう。
そういった現在の生き方が定まっていても将来設計や退職後といった将来の生き方は定まっておらず、漠然とした不安を抱えている人は多いのではないでしょうか?
ライフプランnaviでは将来お金に困らないように、若い内からでもできるライフプランニングに役立つ情報を発信しております。
人はそれぞれ、自分の生き方を持っているはずです。家族との時間を大切にする方もいれば、仕事や趣味に生きる方もいるでしょう。
そういった現在の生き方が定まっていても将来設計や退職後といった将来の生き方は定まっておらず、漠然とした不安を抱えている人は多いのではないでしょうか?
ライフプランnaviでは将来お金に困らないように、若い内からでもできるライフプランニングに役立つ情報を発信しております。
ライフプランnavi : https://lifeplan-navi.com/
不動産投資の狙い目…「再開発エリア物件」の魅力とは?
再開発による地価高騰・人口増で賃貸ニーズもアップ!
再開発は、敷地の細分化・建物の老朽化や密集化が顕著なエリアに対し、敷地の統合、大規模複合施設の建設などを行う計画です。都市再開発法に基づき地方公共団体が計画・施工、多くの民間企業や団体と協力して長期間に渡って進められます。
公園など公共施設の充実も図られ、合理的な都市空間を形成。再開発が行われたエリアは、街が整備され住みやすくなり、景観も向上し魅力が増します。このような再開発エリアが、不動産投資対象として優れているのはどのような点でしょうか。
●不動産価格上昇
さまざまな施設が充実し街全体が活性化すれば、当然、不動産価格は上昇し賃貸物件の家賃の上昇が期待できます。
●人口増
商業施設・オフィスが増えると、エリアに人が集まります。エリアとしての魅力が増せば、当然居住者も増えるでしょう。
●賃貸需要アップ
施設の充実で集客力のある地域になり、景観の良い街になれば、街のブランド化が進みます。居住希望者も増加、賃貸の需要もアップするはずです。
要注目は「都心・臨海・ターミナル駅」エリア
例として、東京の再開発エリアを確認してみましょう。
●現在も将来も進む都心の再開発
東京都心ではいくつもの再開発が進行中です。オリンピック以降、投資不動産の利益確定売りが始まり、不動産マーケットは冷え込むという見解があります。しかし、都心の再開発は東京オリンピック終了後も予定されており、再開発による賃貸需要がストップすることはないでしょう。
【現在進行中の代表的な都内再開発計画】
春日・後楽園駅前地区市街地再開発
中野二丁目地区第一種市街地再開発
【オリンピック終了後の代表的な東京再開発計画】
2022年 新宿 TOKYU MILANO 再開発・竣工
2023年 渋谷駅桜丘口地区再開発・竣工
2023年 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発・竣工
2024年 東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発・竣工
●臨海エリアには引き続き注目
市場移転問題で注目された「豊洲エリア」、東京オリンピックに向けた準備が進む「晴海エリア」を含む湾岸エリアは、引き続き注目エリアでしょう。晴海エリアは、オリンピック終了後に選手用宿泊施設が住居・店舗などに再整備される予定です。居住者が増えるため、保育所・小中学校・老人ホームも整備され、人口が約1万2,000人になると予想されている大規模な再開発となります。
●ターミナル駅周辺・虎ノ門周辺
新宿・渋谷・品川・池袋など、ターミナル駅周辺エリア、虎ノ門・麻布台周辺の都心でも、大規模な再開発が進んでいます。もともとにぎわっているエリアですが、商業施設・オフィス、公共施設、複合施設ビルなどが整備されることで、より利便性の高い街になり、ブランド化が進むでしょう。
再開発エリアの物件を購入する際の注意点とは?
再開発エリアの魅力、お分かりいただけましたか。では、このエリアの物件購入の際は、どのような点に注意が必要なのかお伝えします。
●資産価値上昇は未確定
再開発エリアは、すべての不動産の価値が上がるわけではありません。
●計画の変更もありうる
また、予定通りに再開発が進まず、計画の一部が変更される可能性もゼロではありません。その場合、再開発されても不動産価値は上がらないかもしれません。値上がりを見込んで取得した物件が、取得金額よりも価値が下がるリスクもあります。
●タイミングも大切
再開発が順調に進みブランド化が成功した地域であっても、取得時に既に大きく値上がり済みで、それ以上の価格上昇・賃料アップを期待できないケースもあります。再開発が進行中のエリアで物件を購入したい場合、再開発情報は公開されているので、資料を熟読し、数年後をしっかりイメージしてみましょう。最新情報にも注意します。
また、上記のエリアはどこも物件価格が高いところばかりです。予算的に最寄り駅が厳しければ、隣の駅から近い物件も検討してみましょう。魅力的な街のそばであれば、入居希望者の心配をする必要はないはずです。
計画の変更も…慎重な判断が必要
再開発エリアは、大規模な投資で街が住みやすくなり、エリアとしてブランド化が進みます。当然賃貸需要に関して非常に期待できるマーケットです。このエリアで不動産を所有すれば、空室リスクは大きくはないでしょうし、値上がり具合によっては売却益を狙っていくこともできるかもしれません。
ただし、開発計画は数年単位。資産価値の上昇は約束されたものではありませんし、計画そのものの変更もありえます。購入時の価格が最高で、その後停滞する場合もあるでしょう。物件購入の際は、公開されている情報をしっかり収集したうえで最新情報にアンテナを張り、十分検討して判断しましょう。
格安物件でも、こうすれば勝負できる!?<100万円からの不動産投資>
不動産投資で大事なのは、やっぱりキャッシュフロー。増やす方法は?
不動産投資の指標にはいくつかありますが、なかでも重視すべきはキャッシュフローでしょう。キャッシュフローがなければ、何のために投資をしているのかわからなくなってしまいます。キャッシュフローの定義やその重要性、増やすための手段について知っておきましょう。
不動産投資におけるキャッシュフローとは?

(画像=garagestock/Shutterstock.com)
広義の意味での「キャッシュフロー」は、キャッシュイン(収入)からキャッシュアウト(支出)を差し引いた残りの金額を指していたり、あるいは事業活動におけるお金の出入りそのもののことを指したりします。
不動産投資において使われる「キャッシュフロー」について明確な定義があるわけではありませんが、一定の期間に残ったお金のことを指していることが多いといえます。具体的な計算方法は人それぞれですが、簡易的なキャッシュフローの計算式は次のようなものです。
家賃収入-ローン返済-経費=キャッシュフロー
ただしこの場合、ローン返済額のうち経費にできない元金の部分を考慮しているものの、税金が考慮されていません。そこでもっと厳密に、
税引き後利益+減価償却費-返済元金=キャッシュフロー
と計算してキャッシュフローを求める人もいます。金融機関が融資審査のために決算書を見る際には、後者の計算式に当てはめてキャッシュフローを算出すると言われています。ただ、この方式でキャッシュフローを割り出すには、まず税金の計算をする必要があるのでかなり手間がかかります。
そこで、賃貸経営の大まかな現状を知りたい時や、購入を検討している物件の収益力を見る時には、最初の簡易的な計算式でキャッシュフローを計算すればいいでしょう。
この時、経費をいくらに設定するかは難しいところです。単に不動産管理会社へ支払う管理委託費だけなら家賃収入の5%程度ですが、退去に伴う原状回復費や、突発的な修繕費、将来の大規模修繕工事に備えた積み立てなども考慮する必要があります。空室期間に家賃収入が入ってこない分のマイナスも含めて、おおむね30%の経費がかかると考えておくと、手堅い計算になります。(もちろん空室期間についての想定は築年数や間取りの競争力、エリアでの空室率などを考慮し上下させる必要があります。)
なぜキャッシュフローが大事なのか?
なぜキャッシュフローが大事なのかといえば、それはお金がいくら残るかを表す指標だからです。利回りが高い物件を買ったとしても、あるいは好条件で融資を引き出せたとしても、最後に残るお金が少なければ、何のために投資をしているのかわかりません。
反対にキャッシュが十分に残る状態なら、選択肢の幅が広がります。貯まったキャッシュで次の物件を購入することもできますし、物件の価値を上げるために修繕することもできます。不動産賃貸経営を安定的に行うためにも、キャッシュフローがきちんと残る状態をつくることが大事なのです。
キャッシュフローを増やす鍵は融資にあり
キャッシュフローを増やすにはどうすればいいのか。そのポイントの一つは利回りにあります。購入額に対して家賃収入が多い、つまり利回りの高い物件であれば、それだけ多くのキャッシュフローを期待できます。ただし、単に利回りが高いだけではリスクの高い物件の可能性もあるので注意が必要です。
そこでもう一つのポイントとなるのが、ローン返済額です。ローン返済額が少なければ少ないほど、キャッシュフローが増えるからです。ローンの返済額は、借入金額、金利、借入期間によって決まってきます。借入金額は少なく、金利は低く、借入期間は長い方が、ローン返済額を抑えることができます。
最終的なキャッシュフローが最重要指標
ただし、キャッシュフローだけを重視してとにかく長期のローンを組んでしまうと、元金がなかなか減らず、返済が終わるまで長期にわたって金利上昇や空室リスクにさらされるというデメリットもあります。あくまで長期的な目線でリスクを織り込んだ計画を立てることが重要です。
一時的に収支のバランスが悪化したとしても、結局は「最終的なキャッシュフロー」が不動産投資における一つの重要な指標になります。物件保有中はキャッシュフローがプラスで推移し、残債の減少額と将来的な売却までを含めてトータルで収支を見て、最終的にいくらの利益が得られたかで、不動産投資の成否が決まるのです。(提供:オーナーズ倶楽部)
相続税対策には生命保険加入より「不動産投資」が有利なワケ
ネックは「貯蓄効果の低さ」…早期解約で大きな損失も
終身保険は、死亡保障をカバーすることを主たる目的とし、被保険者が死亡したときに、決められた受取人が死亡保険金を受け取ることになる生命保険である。これには満期が設定されておらず、保障が一生涯続く契約となっている。被保険者がいつ死亡しても、契約に定められた金額の死亡保険金を受け取ることができるのだ。
終身保険の保険料の払込み方法には、終身払いと有期払いがある。「終身払い」は、存命中はずっと保険料を払い込み続ける方法である。
「有期払い」は、60歳まで、65歳、20年間など、払込みの期間を定める方法である。1回で保険料を全額しはらうとすれば、「一時払い」となる。これらは、終身払いよりも払込み回数が少なくなるため、保険料額は当然に割高になる。
終身保険は途中で解約することができる。ただし、その返戻金の金額は、保障額、加入年齢や保険料の払い込み期間によって変わる。そのため、保険料の支払いが終わらないうちに解約すると、解約返戻金は、支払った保険料の累計額を下回ることになり、損失が発生する(一時払いでも同様である)。
よって、終身保険は、資産運用を目的とするものではなく、あくまでも一生涯の死亡保障を目的とする商品である。
終身保険のメリットは、若い人たちにとって家族を守る死亡保障として機能すること、老後は解約返戻金を老後資金として活用することができることである。
また、死亡保険金には相続税の非課税枠(=500万円✕法定相続人の数)があるため、相続税対策の効果がある。
さらに、相続時に支払われることになる死亡保険金は、受取人の固有の財産となるため、個人財産の分割を事前に本人が生前に決めることができる。終身保険には、遺産分割争いを防ぐ効果があり、相続対策(相続税対策ではない)として有効な手法だとされている。
しかし、終身保険のデメリットは、解約返戻金が支払った保険料を大きく下回ることである。設定される運用利回りは低く、早期に解約すると大きな損失が発生する。これではお金を貯蓄する効果が乏しい。
払込み期間中の死亡を想定する加入者は「ほぼいない」
筆者は、生命保険セールスを目的としたセミナー講師を担当する機会が多くあり、「終身保険は相続対策に効果的だ」「遺産分割の争いを防ぐために、終身保険に加入すべきだ」と言い続けてきた。
しかし、本当にそうなのだろうか?
自分で主張しておきながら、今さら疑問を呈すのもおかしな話だが、顧客利益を最優先すべきだという職業倫理を守るため、立ち止まって冷静に考えてみたい。
気になるのは、終身保険の効果は、相続対策のメリットよりも、相続税対策のデメリットのほうが大きいことだ。
確かに、終身保険遺産分割争いを防ぐ効果があり、相続対策(相続税対策ではない)として有効な手法となる。しかし、終身保険も金融商品であり、一定の非課税枠を控除した後の相続税評価は額面100%である。投資信託と変わらない。
「いやいや、〈貯蓄は三角、保険は四角※〉でしょう」とおっしゃる読者もいるかもしれない。確かに、払込み期間中に死亡すると、払込んだ保険料を大きく超える死亡保険金を受け取ることができる。死亡保障があるため、保険は「四角」だ。
※ 貯蓄はお金を少しずつ積み立てていくため、時間とともに貯蓄残高は右肩上がりになるが(三角形)、生命保険は時間の経過とに係なく、加入した時から受け取れる金額(保障額)が一定である(四角形)との意味。
「四角」という生命保険に特有の機能もメリットと考えるべきだ。死亡保障プラス遺産分割対策において有効であれば、生命保険を活用する価値があるのではないか。
しかし、保険料の払込み期間中に死亡することを想定する加入者は、ほとんどいないと思われる。それを想定した加入者がいたとしても、想定外に長生きするケースがほとんどであろう。結局は、保険料を全額支払うはめになるのだ(一時払いであれば明確だ)。結果として、貯蓄と比較して「四角」の部分の優位性を発揮するケースは、現実にはほとんどないはずだ。
そうすると、終身保険は「三角」の貯蓄に対する優位性はない。金融商品の一種として考えることができよう。そうすると、最終的な利回りが大きいかどうかが問題だ。
終身保険は高コストであるため、予定利回りは低く設定されている。外国株式のインデックス型ファンドなど、期待利回りの高い投資信託と比較した場合、終身保険は利回りが低い分だけ不利な金融商品となっている。これで加入する意味はあるのだろうか。
定石は「自宅を継がない子どもには生命保険」だが…
簡単な事例を考えてみよう。相続人は長男と次男の2人、母親の財産は自宅不動産2億円と現金7,000万円だけである。自宅は長男が取得し、現金は次男が取得する。遺産の分け方が不公平になる。

これは遺産分割が問題となる典型的なケースだ。この問題について、自宅不動産を継がない次男を受取人とする生命保険に加入しておくことが、最も効果的な相続対策だとされている。
この事例を分析しよう。
自宅不動産を共有にすれば公平に遺産分割できるかもしれないが、そのような厄介な相続は回避して、長男が単独で取得する。長男は母親と同居しており、居住を継続するので、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地330㎡まで▲80%、ここでの想定は▲1億2,000万円)を適用することができる。
それでも長男は、納税資金として約1,000万円が必要である。幸いにも死亡保険金500万円(非課税枠の範囲内)を受け取ることができるが、それでも600万円が不足している。
一方、次男は現金を取得する。さすがに長男に分ける現金をゼロとするのはかわいそうであるため(納税資金が足らないから)、600万円だけは我慢して長男に分けてやろう。すると、次男の取得する現金は6,400万円だ。
長男が取得する自宅不動産2億円とのバランスにおいて、次男が不公平だと言い出すかもしれないが、自宅不動産を共有しないと決めた以上、やむを得ない。そこはグッとこらえて我慢することにしよう。
しかし、この金額では、次男の遺留分である6,750万円(=2億7,000万円÷2人÷2)を下回るため、問題が生じる。
[PR] 本稿執筆者によるセミナーを2020年1月21日(火)に2本一挙に開催!/東京(幻冬舎)
★【緊急開催】富裕層のための「税制改正大綱」ポイント解説
★財産2億円以上の方のためのタイプ別(企業オーナー、地主・不動産オーナー、金融資産家)「相続生前対策」の円滑な進め方
★【緊急開催】富裕層のための「税制改正大綱」ポイント解説
★財産2億円以上の方のためのタイプ別(企業オーナー、地主・不動産オーナー、金融資産家)「相続生前対策」の円滑な進め方
次男が取得する財産6,400万円 < 遺留分6,750万円
このような遺産分割には問題がある。この問題を解決するには、次男に取得させる財産を増やさなければいけない。これがポイントなので、忘れないでほしい。
解決策 次男に取得させる財産を増やすこと!
生命保険で遺留分の侵害が解消されればOKなのか?
そこに、「相続専門」と称する生命保険セールスマンが提案に来たとしよう。筆者である私が同席しているかもしれない。「遺産分割争いの唯一の解決策は生命保険です!」と提案されることだろう。
生命保険セールスマンからの提案は、現金6,000万円を支払って、一時払い終身保険に加入し、それを次男に確実に相続させようというものだ。
ただし、長男を受取人にして、相続時に長男から次男へ6,000万円の代償金を支払う遺産分割を予定する。この点、「次男を受取人にすべきではないか?」と考える読者もいるかもしれないが、その説明はここでは省略させていただく。
次男が受け取る相続財産額は変わらないが、遺留分の侵害が解消される(次男にとっては不本意だが)。生命保険の6,000万円が遺留分の算定基礎から消えて、遺留分が5,250万円(=2億1,000万円÷2人÷2)に減少するからだ。
次男が取得する財産6,400万円 > 遺留分5,250万円
生命保険によって遺留分を侵害する状況は解消された。一見して、素晴らしい提案のように見える。
果たしてこれが正解なのだろうか。
不動産投資なら、相続税・遺産分割の双方に効果あり
生命保険セールスマンが提案に来る前に、たまたま投資用マンションのセールスマンが提案に来たとしよう。筆者である私が同席している可能性は低い。「投資用マンションは相続税対策になりますよ!」と提案されることだろう。
ここでのポイントは「相続対策」ではなく「相続税の対策」であるということだ。すなわち、不動産投資を行えば、財産評価が引下げられ、相続税負担が軽減されるという節税効果だ。遺産分割のことは考えていない。
投資用マンションのセールスマンからの提案は、現金のうち6,000万円を支払って、投資用の区分所有マンションを購入せよというものだ。これによって、財産評価が3,900万円(圧縮率▲65%)だけ引下げられ、相続税対策になるという。
不動産が増えると遺産分割が心配になる。不動産の購入では生命保険のように相続人を指定する効果がないため、母親には公正証書遺言を書いてもらおう。
不動産投資の効果で明らかなのは、相続税負担が減少することだ。財産評価の引下げによって、相続税合計額は1,840万円から980万円まで減少する。節税効果の総額は860万円だ。
一般的な相続税の教科書には、ここまでしか説明されていない。この事例では、今まで明らかにされていない副次的な効果を解説しよう。
相続税合計額が減少するということは、長男の相続税負担も減少するということだ。この事例では約1,000万円だった長男の相続税額が約730万円まで減少している。
そうすると、長男は、節税できた分だけ自分の取り分を減らし、それを次男に多く分けてあげることが可能となる。ここでは、長男の取得する現金を350万円減らして、次男に同額を増やしてやろう。
これにより、次男が受け取る相続財産額は350万円増えるため、多少なりとも遺産分割の不公平さ(バランス)は改善される。
一方で、不動産が相続財産となる場合、生命保険のように遺留分の算定基礎から除外されることがないので、ここでは次男の遺留分が侵害されないかどうかが心配になる。しかし、現金を次男へ多めに取得させてやることによって、遺留分の侵害は防ぐことができる。
次男の相続税負担も同様に減少する。この事例では約780万円だった次男の相続税額は約250万円まで減少している。
結果として、次男が取得する財産は、約6,100万円から約7,000万円になり、大きく増加した。この効果は、①長男の現金を減らして次男を増やしたこと(350万円)と、②次男の相続税負担が減少したこと(約530万円)の合計額である。
この事例で最初に掲げたポイントを再掲しよう。
解決策 次男に取得させる財産を増やすこと!
どうやら不動産投資によっても、当初の問題は解決できたようだ。遺産分割の問題である。もちろん相続税負担の軽減は実現されている。つまり、不動産投資は、相続税対策だけでなく、遺産分割対策にも効果的ということだ。
よって結論はこうだ。遺産分割に生命保険が最適だというわけではない。不動産投資のほうが優れている。生命保険の優れた商品だというのは誤解だった。
不動産投資の遺産分割への有効性は「汎用的」なもの
読者には、「この事例に限った話で、計算結果は偶然ではないか」と思われる方がいるかもしれない。場合によっては、生命保険のほうが効果的だという結果が出るケースは、多分に存在するだろう。
しかし、ほとんどのケースにおいてこの計算ロジックが通用する。つまり、不動産投資は遺産分割にも有効なのかもしれない。今のところ筆者は、この効果は汎用的なものであると考えている。
なぜ不動産投資のほうが生命保険よりも優れているのか。これは相続対策の有効性を判定するタイミングが異なるからだろう。
相続税負担の軽減は「相続税評価額」で決めるものであり、まさに相続時点における資産の形態によって算出される。一方の遺産分割の公平さは「時価」で決めるものであり、相続直後に資産を売却することによっても調整することが可能である。先に相続税評価の問題があって、後で時価の問題がやってくる。
結局のところ、相続というイベントを通過する瞬間の財産評価が最大の課題なのではないか。相続税額は修正できないが、遺産分割や納税資金は何とでもなる。
とすれば、相続財産として持つべきものは不動産であろう。遺産分割の公平さは時価で決めればよい。相続税評価を引下げた結果として納税資金が足りなくなったのであれば、相続した後に不動産を売却すればよい。
筆者が相続税申告で応対するお客様の半数近くは、相続直後に不動産を売却している(納税資金が足りず、実家を売るのだが)。
もちろん、不動産は嫌いだ、生命保険は安心だという方は多いはずだ。確かに、不動産価格は下落する傾向にあるし、地震も心配だろう。生命保険であれば、保険金は100%約束され安全だといっても過言ではない。節税効果のために不安になるよりも、元本保全で精神的に安心して過ごすことが優先されるべきだ――。
さて、読者はどのようにお考えだろうか? 生命保険セールスマンの方々からの反論を期待したい。
岸田 康雄
事業承継コンサルティング株式会社 代表取締役
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
頭金ゼロ円で始めるマンション投資、メリット・デメリットは?投資法も解説
不動産を購入する際は、一般的に不動産価格の一部を頭金として入れて、残りの額はローンを借りることで支払います。しかし、場合によっては物件価格の100%の額のローンが組め、頭金ゼロ円で不動産投資をスタートできることがあります。
その場合は初期費用があまりかからないというメリットがある反面、借入総額が増え毎月の返済額も大きくなるというデメリットもあります。この記事では、頭金ゼロ円でマンション投資をした際の運用方法や、将来の売却の仕方について解説いたします。
目次
- 頭金ゼロ円でマンション投資をする際のメリット
1-1.初期費用を抑えることができる
1-2.現金が手元に残る - 頭金ゼロ円の場合に考えられるデメリット
2-1.毎月のローンの返済額が多くなる
2-2.リスク対応に余裕がなくなる可能性がある
2-3.売却益が少なくなる可能性がある - 頭金ゼロ円でマンション投資をする際に注意すること
3-1.月々の収支を改善しながら運用する
3-2.家賃相場や価格相場は常に把握しておく - 頭金ゼロ円の物件を売却する際の注意点
4-1.出口戦略は早めに立てておく - まとめ
1.頭金ゼロ円でマンション投資をする際のメリット
頭金ゼロ円でマンション投資をする際にはどのようなメリットがあるのでしょうか。確認してみましょう。
1-1.初期費用を抑えることができる
頭金がゼロであれば、その分マンション購入時にかかる初期費用を抑えることができます。初期費用には頭金以外に、仲介手数料や金融機関の事務手数料、保証料などが含まれます。その他にも色々あるため、どのような費用があるのかを以下の表で見てみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介してくれた不動産会社に支払う手数料 |
| 売買契約の印紙税 | 売買契約書に貼る収入印紙 |
| 金融機関の事務手数料 | ローンを組む際に発生する金融機関の手数料 |
| ローン保証料 | 保証会社へ支払う保証料 |
| ローン契約の印紙税 | 金融機関と締結する契約書に貼る収入印紙 |
| 火災保険料 | 火災保険の保険料 |
| 団体信用生命保険料 | 契約者死亡時にローンの残債を完済する保険 |
| 登記費用 | 登記時の登録免許税と司法書士報酬 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際にかかる税金 |
| 固定資産税(精算金) | 不動産を所有していると毎年かかる税金。不動産購入時には期間に応じて按分精算する |
| 都市計画税(精算金) | 毎年発生する都市計画に関する税金 |
| 管理費・修繕積立金 | マンションの管理組合に支払う管理費・共用部修繕の積立費 |
マンションの購入時にはこれだけの費用がかかります。不動産取得税などは購入時から数ヵ月遅れて支払うことになりますが、必ず発生する費用になりますので忘れないようにしましょう。
例えばマンション価格が2,000万円で、90%の割合しかローンが組めなかった場合は、上記の費用以外に頭金を200万円支払わなければいけません。頭金ゼロで始める場合はその費用はかかりません。頭金があるかないかの違いで、初期段階で準備しなければいけないお金の額は大きく異なります。
1-2.現金が手元に残る
また頭金がかからなかった分、現金が手元に残るということも言えます。手元に残る現金が多ければ、空室時のローンの返済や、突発的な修理の費用に使える資金が多くなりますので、それだけ余裕を持って運用をすることができるようになります。
2.頭金ゼロ円の場合に考えられるデメリット
では次に、頭金ゼロ円でマンション投資をする際のデメリットについて見てみましょう。
2-1.毎月のローンの返済額が多くなる
頭金がゼロ円の場合、それだけ毎月のローンの返済額が大きくなります。そのため、頭金を支払った場合と比較して、家賃収入と支出との差があまり無く、収支が悪化することがデメリットになります。
仮に2,000万円の物件を購入する際に、頭金を1割支払った場合とゼロ円の場合では、毎月の返済額がいくらくらい違うのかを試算してみましょう。金利2%、返済期間35年の条件でローンを組んだとします。
| 物件価格 | 頭金 | ローン価格 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 200万円 | 1,800万円 | 5万9,627円 |
| 2,000万円 | 0円 | 2,000万円 | 6万6,252円 |
*金利2%、返済期間35年
この場合では、月々の返済額は頭金を入れた方が約7,000円低くなります。それだけ頭金を入れた方が毎月の収支に余裕が出るということが確認できます。
2-2.リスク対応に余裕がなくなる可能性がある
上記の通り、頭金を入れないぶん収支は悪くなりますので、その分キャッシュのストックされるスピードも遅くなります。これにより空室になったり設備が壊れて修理費用が必要になったりした場合に、資金の余裕がない状態に陥る可能性が上がると考えられます。そのため、頭金ゼロで投資を始める場合は、ローンの返済遅延リスクなどに注意して運用することが求められます。
2-3.売却益が少なくなる可能性がある
毎月のローンの返済を続けていけば、一定の割合で残債は減っていきます。同じようにマンション(建物)の評価額も下落しますが、築年数に応じた平均物件価格は途中で横ばいに近くなるため、時間の経過とともに物件価格の下落よりも残債の減少の方が大きくなる傾向にあります。
そのため、ケースによっては売却をした際にローンの残債よりも高い価格で売却できる時期があり、その時点で売却できれば手元に残る収益が大きくなります。
頭金ゼロでスタートした場合は、頭金を入れた場合と比較して元のローン価格が大きいため、残債が物件の評価額を下回りにくくなります。そのため売却によって得られる収益は頭金を入れた時より少なくなる可能性が高くなります。
3.頭金ゼロ円でマンション投資をする際に注意すること
頭金ゼロ円でマンション投資をスタートするには、メリットもあればデメリットもあります。できるだけメリットを多く得られるようにするには、どのような点に注意すれば良いのかを見てみましょう。
3-1.月々の収支を改善しながら運用する
頭金ゼロ円の場合は頭金を入れた場合と比較して、月々の収支が悪くなることが大きなデメリットになります。そのため、頭金ゼロ円でマンション投資をする場合は、月々の収支を改善しながら運用できるように心掛けることが大切です。収支を改善するには一部繰上返済や借り換えをすることが効果的です。それぞれを詳しく見てみましょう。
一部繰上返済をする場合
残債の一部を繰上返済することで、月々の収支を改善することができます。では、どの時期にいくらくらい繰上返済すれば良いのでしょうか。
仮に2,000万円の物件を購入した場合の繰上返済を試算してみましょう。金利2%、返済期間35年で組み、15年後に200万円繰上返済をしたとします。その場合、月々の返済額がいくらになるのかを見てみましょう。
| 月々の返済額 | 15年後の残債 | 200万円繰上返済した場合の残債 | 15年経過後からの毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 6万6,252円 | 1,309万6,418円 | 1,109万6,418円 | 5万6,134円 |
*繰上返済のタイミングによっては、16年目以降の月々の返済額はこの通りではありません
頭金を200万円入れた場合の月々の返済額が5万9,627円でしたので、途中でも200万円を準備できた段階で同じ額を繰上返済すれば、ほぼ同じ返済額になったり、頭金を入れた場合の返済額を下回ったりすることが確認できます。
このようにマンション投資を始める段階で初期費用をかけなかったとしても、途中で繰上返済することで、頭金を入れた場合と同じような収支に改善できます。
しかし、頭金を入れた場合は、スタート時から頭金ゼロの場合より多くのキャッシュが得られますので、その差額分は収益力の違いがあることを押さえておくことが大切です。
借り換えをした場合
次は、15年後に金利が1%低いローンに借り換えができたと仮定した場合、月々の返済額はいくらくらい変わるのかを試算してみましょう。
| 15年後の残債 | 借り換え後の毎月の返済額 |
|---|---|
| 1,309万6,418円 | 6万229円 |
*タイミングや条件により実際の返済額は変わります
借り換えをした場合も、頭金を入れた場合と同様に返済額を下げる効果があることが確認できます。この場合は、借り換えにも費用がかかることを押さえておくことと、状況によっては低い金利に借り換えができない可能性があることも頭に入れておくことが大切です。借り換えを検討する際は、早めに金融機関に相談すると良いでしょう。
3-2.家賃相場や価格相場は常に把握しておく
売却をする際は物件価格だけでなくローンの残債も収益に関係してきます。また、頭金を入れた場合と頭金ゼロの場合では、ローン価格が違う分、残債の額も異なります。そのため、その時点の想定売却価格と残債はつどチェックしておくことが大切です。さらに、家賃も売却する際の査定に影響してきますので、家賃相場も一緒に確認するようにしましょう。
4.頭金ゼロ円の物件を売却する際の注意点
賃貸マンションの運用においては繰上返済や借り換えを積極的に行い、収支の改善を図ることが大切です。では売却を視野に入れた場合はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
4-1.出口戦略は早めに立てておく
頭金がゼロ円の場合、頭金を入れた場合と比較して収支が悪くなることには触れました。普段の収支の改善を意識しながら運用をしなければいけませんので、計画的に資金管理を行う必要があります。そのためには出口戦略を早めに立てた方が長期的な資金管理がしやすくなります。
売却できそうな価格と残債の減り具合から、いつぐらいに売却するのが良いのか、リノベーションはする必要があるか、家賃の減額と売却のタイミングをどう取るか、といった点から、できるだけ早めに、不動産会社とも相談しつつ出口戦略を立てて取り組むようにしましょう。
まとめ
頭金ゼロ円でマンション投資をする際に注意する点について解説しました。頭金ゼロ円でマンション投資をする場合は、初期投資を抑えられるぶんキャッシュを有効にストックすることができる一方、ローン金額が大きくなるため、毎月の収支が悪化することが考えられます。
投資効率を上げるためには、できるだけ収支を改善しながら売却まで運用を続け、最終的なキャッシュをプラスにすることが大切です。そのためには出口戦略をできるだけ早く立てて、しっかり資金管理をしながら運用に取り組むようにしましょう。
高額な買い物をしたとき、分割して費用にするのが「減価償却」
減価償却とは、「設備投資で支出した金額を、その資産が使用できる期間で按分し費用計上する会計上の処理」のことです。とはいえ、これだけではなんのことかわからないですね。
もう少しかみ砕いて説明すると、「お金を出して手に入れた資産を〈その資産は、このくらいの期間なら利用できるだろう〉と法律で定められている年数で、分割して費用として計上すること」です。
事業の利益は、
利益=売上-費用
で計算されます。売上が100万円で費用が20万円なら、利益は80万円です。
長期間使用できて、しかもその使用期間中、ずっと売上を生み出すために役に立つ高額な設備を、買った時点でその代金全額を費用とするのはおかしい、と会計では考えます。長く使えて売上も生むのだから、経費にする分も、その期間に合わせて分割しよう、というのが、減価償却の考え方なのです。
たとえば、マンション一室を3000万円で購入して不動産投資を始めた場合で考えましょう。設備投資額は、マンション購入にかかった3000万円です。
もし仮に、1年目にこの3000万円の全額を経費として費用計上したら、仮に年120万円(月10万円)の家賃収入があっても、大赤字ということになります(話を簡単にするため、他の費用はないものと仮定します)。ちなみに、赤字なのでこの事業にかかわる税金はゼロです。
次に、2年目以降は、年120万円の家賃(=売上)で、費用はゼロですから、利益は120万円になります。税金はこの120万円に対して課税されます。
このように、同じ家賃収入(売上)を得ているのに、利益も、利益をもとにして計算される税金も大きく異なってきます。これでは安定した経営はできないし、課税上も不公平が生じる、ということで考え出されたのが減価償却という仕組みです。
この場合、新築マンションの法律上の使用期間(法定耐用年数)は47年なので、
3000万円÷47年=約64万円
を、毎年分割払いで費用として計上していくことになります。
すると、
1年目…家賃120万円-費用64万円=56万円の利益(56万円に対する課税)
2年目…家賃120万円-費用64万円=56万円の利益(56万円に対する課税)
:
と、毎年均等な利益と課税額が計上されます。これなら、経営が安定します。この仕組みのことを「減価償却」、減価償却によって計上される費用のことを「減価償却費」といいます。
もう少しかみ砕いて説明すると、「お金を出して手に入れた資産を〈その資産は、このくらいの期間なら利用できるだろう〉と法律で定められている年数で、分割して費用として計上すること」です。
事業の利益は、
利益=売上-費用
で計算されます。売上が100万円で費用が20万円なら、利益は80万円です。
長期間使用できて、しかもその使用期間中、ずっと売上を生み出すために役に立つ高額な設備を、買った時点でその代金全額を費用とするのはおかしい、と会計では考えます。長く使えて売上も生むのだから、経費にする分も、その期間に合わせて分割しよう、というのが、減価償却の考え方なのです。
たとえば、マンション一室を3000万円で購入して不動産投資を始めた場合で考えましょう。設備投資額は、マンション購入にかかった3000万円です。
もし仮に、1年目にこの3000万円の全額を経費として費用計上したら、仮に年120万円(月10万円)の家賃収入があっても、大赤字ということになります(話を簡単にするため、他の費用はないものと仮定します)。ちなみに、赤字なのでこの事業にかかわる税金はゼロです。
次に、2年目以降は、年120万円の家賃(=売上)で、費用はゼロですから、利益は120万円になります。税金はこの120万円に対して課税されます。
このように、同じ家賃収入(売上)を得ているのに、利益も、利益をもとにして計算される税金も大きく異なってきます。これでは安定した経営はできないし、課税上も不公平が生じる、ということで考え出されたのが減価償却という仕組みです。
この場合、新築マンションの法律上の使用期間(法定耐用年数)は47年なので、
3000万円÷47年=約64万円
を、毎年分割払いで費用として計上していくことになります。
すると、
1年目…家賃120万円-費用64万円=56万円の利益(56万円に対する課税)
2年目…家賃120万円-費用64万円=56万円の利益(56万円に対する課税)
:
と、毎年均等な利益と課税額が計上されます。これなら、経営が安定します。この仕組みのことを「減価償却」、減価償却によって計上される費用のことを「減価償却費」といいます。
記事詳細はこちら : https://lifeplan-navi.com/column/5241/
不動産投資家が知っておくべき「減価償却」の仕組み|LIFE PLAN navi(ライフプランナビ) : https://lifeplan-navi.com/column/5241/
ライフプランnaviとは、充実した人生を送るための手助けとなる、ライフプランに関する情報を発信しているウェブサイトです。
人はそれぞれ、自分の生き方を持っているはずです。家族との時間を大切にする方もいれば、仕事や趣味に生きる方もいるでしょう。
そういった現在の生き方が定まっていても将来設計や退職後といった将来の生き方は定まっておらず、漠然とした不安を抱えている人は多いのではないでしょうか?
ライフプランnaviでは将来お金に困らないように、若い内からでもできるライフプランニングに役立つ情報を発信しております。
人はそれぞれ、自分の生き方を持っているはずです。家族との時間を大切にする方もいれば、仕事や趣味に生きる方もいるでしょう。
そういった現在の生き方が定まっていても将来設計や退職後といった将来の生き方は定まっておらず、漠然とした不安を抱えている人は多いのではないでしょうか?
ライフプランnaviでは将来お金に困らないように、若い内からでもできるライフプランニングに役立つ情報を発信しております。
ライフプランnavi : https://lifeplan-navi.com/
どこが有望?東京都内のマンション投資、転入者数や利回りからエリアを分析
マンション投資の成果には立地がとても大きく影響します。特にマンション価格が上がりきったという意見も聞かれる現時点からマンション投資をするには、特に立地は慎重に検討すべきポイントと言えるでしょう。では、どういった視点からエリアを選択すれば良いのでしょうか。
この記事では、2020年以降でも投資先として見込めそうな東京都近隣エリアを、利回りや転入者数などをもとに考えてみたいと思います。
目次
- 東京都心は賃貸ニーズが高く長期投資に向いている?
1-1.東京都は転入者が多い
1-2.職住近接の時代になった
1-3.都心のワンルームは今後もニーズがある? - 東京都心でのマンション投資法
2-1.物件価格との関係
2-2.常に収支を良くする工夫をする - 利回りを考えるなら都心から外れたエリア
3-1.都心に30分以内で移動できる場所
3-2.駅から徒歩10分圏内は外さない
3-3.複数の路線が通っているエリアを選ぶ - 東京23区内で2020年以降も期待できるエリア
4-1.転入者数を優先する場合に注意すること
4-2.23区内で利回り上昇率を優先するなら - 23区外で2020年以降も期待できるエリア
- まとめ
1.東京都心は賃貸ニーズが高く長期投資に向いている?
マンション投資の効率を上げる要因の一つが立地です。特に東京都心では賃貸ニーズが高く、長期的に効率の良い運用ができる確率が高い傾向にあります。
1-1.東京都は転入者が多い
東京都は他の都市と比較して転入者数が多い都市です。以下の図は都道府県別の転入者数を表したものです。
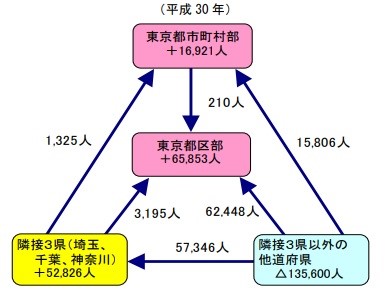 *東京都総務局統計部作成資料から引用
*東京都総務局統計部作成資料から引用
東京都隣接3県以外の他道府県では13万人以上が転出しています。逆に東京都や隣接3県は転入者超になっています。特に東京都区部が6万5,000人超と転入者数が最も多いことが確認できます。このような点から、東京都区部は賃貸ニーズが高いことが考えられ、賃貸経営に向いていると言えるでしょう。
1-2.職住近接の時代になった
近年、国が職住近接の施策を進めてきましたが、上記の転入者数の増減から、その施策は成功していることが予想されます。会社の近くに住んで、通勤時間を減らし仕事に集中したいと考える人や、平日でも自分の趣味や習い事をしたいという人が増えているのです。
また、企業が多く在籍する23区内では街の再開発が進み、ショッピングモールや病院、スーパーなどが建ち並び、都心でも快適に生活ができる環境が整っています。このような都市の変化も都心の賃貸ニーズを押し上げていると言っていいでしょう。
1-3.都心のワンルームは今後もニーズがある?
ワンルームマンションは単身者向けに造られていますので、家族層の世帯割合が多ければニーズは低くなることが考えられます。人口が集中している都心の世帯の家族構成はどのようになっているのかを確認してみましょう。
こちらのグラフは1995年から2060年までの東京都の家族構成とその予測を表したものです。
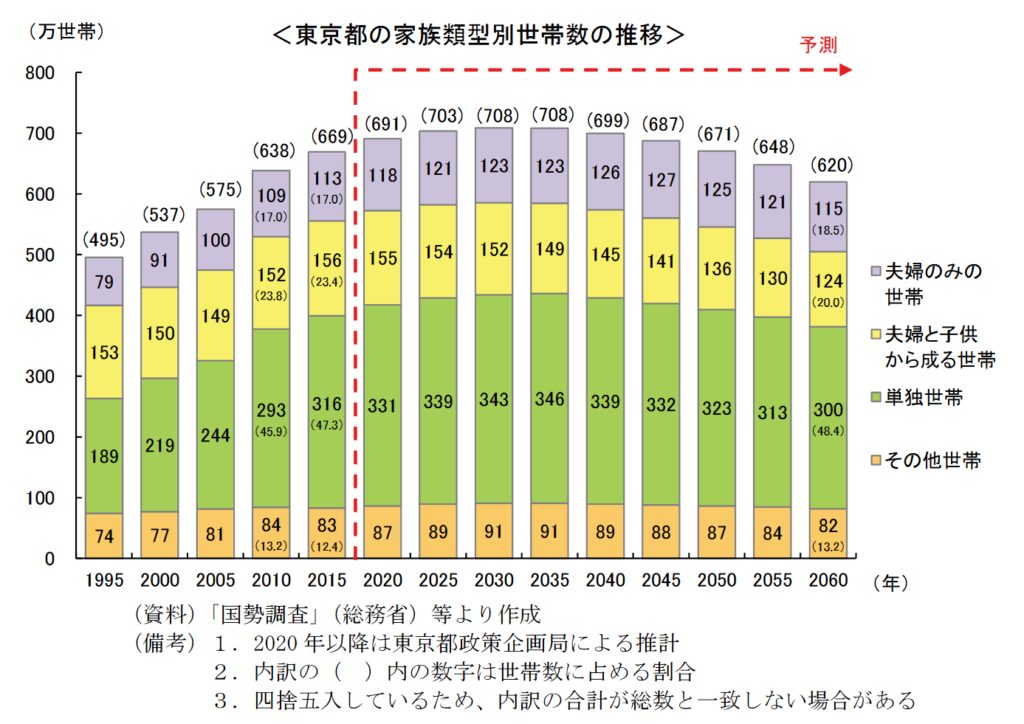 *東京都政策企画課作成「2060年までの東京の人口推計」から引用
*東京都政策企画課作成「2060年までの東京の人口推計」から引用
2015年時点で単独世帯が全体の47.3%と、世帯構成の中で最も多い割合を占めています。その後も全体の世帯数が減少する中、単独世帯は大きな減少がなく、2060年時点では全体の48.4%を占めることが予測されています。このグラフの通りになれば、ワンルームは2060年時点でも賃貸ニーズが高いことが考えられます。
これは予測ですので必ずこのようになるというわけではありませんが、都心の世帯構成はこのような傾向があるということを知っておきましょう。
2.東京都心でのマンション投資法
将来的にも賃貸ニーズが高いことが予想される東京都心では、マンション投資の際にどのような点に注意して取り組めば良いのでしょうか。
2-1.物件価格との関係
都心は郊外と比較して土地の価格が高いので、物件価格が高い傾向にあります。以下は地域別の土地坪単価一覧表です。
23区内の土地坪単価
| 千代田区 | 766.7万円 |
| 中央区 | 552.9万円 |
| 港区 | 549万円 |
| 新宿区 | 317.3万円 |
| 文京区 | 340万円 |
| 台東区 | 294.5万円 |
| 墨田区 | 220.5万円 |
23区外の土地坪単価
| 八王子市 | 53.2万円 |
| 立川市 | 76.3万円 |
| 武蔵野市 | 196.3万円 |
| 三鷹市 | 167.7万円 |
| 青梅市 | 41.6万円 |
| 府中市 | 108.6万円 |
| 昭島市 | 68.3万円 |
*不動産情報サイトSUUMO作成「地域別の坪単価一覧」をもとに一部抜粋し筆者が作成(2019年7月調査)
表を見ると、千代田区が坪単価766.7万円で、八王子市の53.2万円と比較して10倍以上の差があります。その他のエリアを見ても都心部は土地の価格が高く、23区外の方が低いことがわかります。
物件価格には土地の仕入れ代金なども含まれますので、23区内の物件価格の方が比較的高くなります。そのため都心でマンション投資をする際は、郊外の物件に投資するより利回りが悪い傾向が強くなります。これによってキャッシュフローが蓄積されにくいというデメリットがあることを前提に運用に取り組むことが大切です。
2-2.常に収支を良くする工夫をする
都心の物件は価格帯が高いため、毎月の収支が郊外の物件に比べるとあまり良くない傾向にあります。そのため、突発的な修理が発生したり、空室期間が長引いたりした場合にストックしたキャッシュフローが無くなることも考えられます。
そのような状況を防止するためにも、常に収支を良くする工夫をすることが大切です。例えばローンの一部繰上返済や、借り換えなどの方法があります。これらには月々の返済額を減らす効果がありますので、高い額のローンを組んだ場合などは検討するようにしましょう。ただし、いずれも費用が発生するため、実際にコストメリットがどれくらいあるかを計算してから取り組みましょう。
3.利回りを考えるなら都心から外れたエリア
都心の物件は利回りが良くないことには触れましたが、実際に23区内と区外の利回りはどれくらい差があるのでしょうか。以下の表は東京市部、横浜市、川崎市、東京23区の平均利回りをまとめたものです。
| エリア | 利回り |
|---|---|
| 東京市部 | 9.35% |
| 横浜市 | 8.22% |
| 川崎市 | 7.52% |
| 東京23区 | 5.87% |
*不動産投資と収益物件の情報サイト健美家作成「年間レポート 2018年」から抜粋し筆者作成
この表から東京市部と23区内の利回りには大きな差があることが確認できます。しかし、利回りが良いだけでマンション投資の成功確率が上がるとは限りません。
3-1.都心に30分以内で移動できる場所
利回りを追求しながらも、賃貸ニーズの高い物件をつかむ一つの目安として、都心に30分以内で移動できる駅から選択する方法があります。30分以内の移動距離であれば、それほど負担に感じることは無いでしょうし、23区内に住んでいても会社まで30分くらいはかかる駅もあります。
都心から離れたエリアでも特急や急行が停まる駅であれば、職住近接を希望する人も選択肢として考える可能性が高くなるでしょう。
3-2.駅から徒歩10分圏内は人気が高い
都心から30分以内で移動できたとしても、駅から徒歩で時間がかかる場所になると、長期の投資を考えた場合にはネックになり得ることが考えられます。将来的に物件が古くなったとしても、駅近の立地であれば高い賃貸ニーズが見込める可能性が高くなります。駅から徒歩10分以内という条件は、賃貸ニーズが高い物件を見つけるための有効な指標になります。
3-3.複数の路線が通っているエリアを選ぶ
単身者が物件を決める際には、通勤や通学に便利な場所を選ぶ傾向があります。不動産情報サイトSUUMOが単身者と夫婦世帯にとった「家を探すときに重視する項目」のアンケート結果によれば、家を探すときに重視する項目としては家賃以外に、路線・駅やエリア、最寄駅からの時間、通勤通学時間などが大きな比重を占めていることが確認できます。
このことから複数の路線が通っていたり、優等列車が停車したりする駅が最寄りの立地であれば、通勤や通学に便利なため賃貸ニーズが高くなることが考えられます。都心ではなくても、通っている路線などをチェックすることで投資効率が上がる可能性が高まります。
4.東京都23区内で2020年以降も期待できるエリア
23区内と23区外の物件について、利回りなどを確認しました。では実際に転入者数や、利回りをもとにマンション投資におすすめのエリアを考えてみましょう。
4-1.転入者数を優先する場合に注意すること
東京都心には転入者数が多いことには触れました。以下は23区内で2017年と2018年に転入者数が多かった上位5区のデータです。
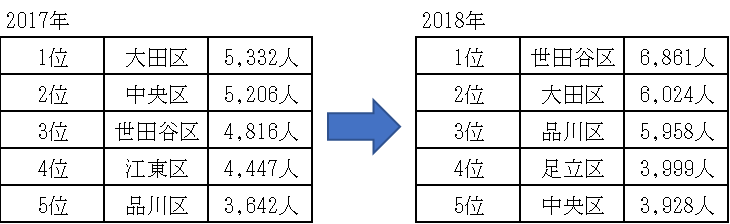 *総務省「住民基本台帳に基づく2017年、2018年の人口移動報告」から抜粋して作成
*総務省「住民基本台帳に基づく2017年、2018年の人口移動報告」から抜粋して作成
この表から分かるように、ランキングは毎年入れ替わりますので、単年の情報だけでエリアを選ぶと、その年だけ特殊な事情によって転入者が増えただけだった、という可能性もあります。
その反面、大田区や世田谷区、品川区などのように、毎年のようにランクインする区もありますので、そのような区であれば将来的にも賃貸ニーズが高い可能性があります。このようなデータをもとにエリアを選ぶ場合は、単年だけでなく複数年の推移を確認するようにしましょう。
4-2.23区内で利回り上昇率を優先するなら
23区内は利回りが良くない傾向にあることには触れました。上記で紹介した表では23区の平均利回りは5.87%でしたが、細かく見るともう少し高いエリアもあります。
以下の表は不動産投資と収益物件の情報サイト健美家が作成した2018年の東京23区利回りランキングの抜粋で、利回りの上昇率が高いエリア順に記載しています。
| 順位 | 区名 | 上昇率 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 1位 | 練馬区 | 0.26% | 7.57% |
| 2位 | 中野区 | 0.26% | 6.39% |
| 3位 | 杉並区 | 0.21% | 6.33% |
| 4位 | 練馬区 | 0.17% | 6.15% |
| 5位 | 大田区 | 0.16% | 6.13% |
*不動産投資と収益物件の情報サイト健美家作成「東京23区賃貸マンション利回りランキング」をもとに筆者作成
こちらの表から練馬区は2017年から0.26%上昇し7.57%もあることが確認できます。7.57%というと23区外の物件に近い利回りですので、23区内でも利回りを追求したい場合はこういったエリアから選ぶと良いでしょう。この場合も毎年利回りは変化しますので、複数年の推移を見てエリアを選ぶようにしましょう。
5.23区外で2020年以降も期待できるエリア
次に23区外でマンション投資におすすめのエリアを考えてみましょう。以下の表は総務省が作成した2018年の「住民基本台帳人口移動報告」から引用したものです。
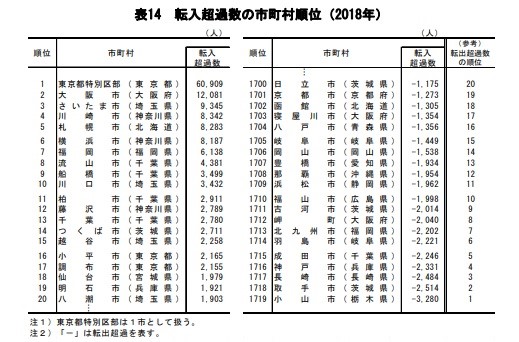 *総務省作成「住民基本台帳人口移動報告2018年」から引用
*総務省作成「住民基本台帳人口移動報告2018年」から引用
こちらの表から東京近隣の23区以外の都市では、さいたま市や川崎市、横浜市などの転入者数が多いことが確認できます。ただし転入者数を参考にエリアを選ぶ際も、ランキングは毎年変わりますので、数年分の推移を確認した上で検討することが大切です。
まとめ
2020年以降に向けてマンション投資をしたいエリアについて、転入者数や住みたい街などのデータからご紹介しました。
マンション投資には立地やエリアが大きく影響してきます。投資効率の良いエリアかどうかを判断する一つの材料として、継続して人口が集中していたり、住みたい街ランキングなどにランクインしたりする街を選択する方法があります。
しかし、データによっては何か特殊な要因でその時だけ人気が上昇している可能性もありますので、複数年の推移を確認したり、できるだけ多くの情報から選択したりするようにしましょう。
武蔵小杉は時代遅れ?高給取りの医師が狙う「タワマン」3選
都心の一等地にはオンボロマンションが鎮座している
我が国でマンションブームが始まったのは1960年代。1964年に開催された東京オリンピックも拍車となり、都心の一等地と呼ばれる場所で、分譲マンションの開発が次々と始まりました。
今ではヴィンテージマンションと呼ばれる「ホーマット」「ドムス」シリーズなど、専有面積100㎡を優に超える贅沢な間取りプランで、大使館や外資系企業に勤務する外国人駐在員向けのブランドマンションが、赤坂、青山、六本木など都内屈指の一等地に建ち始めます。これらはいわゆる「億ション」。一般市民には到底手が届きませんでした。
1980年代に入ると、日本人のライフスタイルに沿った庶民派マンションが建ち始めます。広尾、高輪、品川、麹町など、いにしえの「江戸お屋敷町」を舞台にマンションブームは沸騰し続けます。
バブル経済時代は、とうとう10億円超マンションまで登場、都心は億ションで埋め尽くされました。そして1990年代以降、開発の舞台は郊外へと広がっていきます。
現在、都心の一等地に建っている物件のほとんどは、1970年代~80年代竣工のヴィンテージマンションです。これらは現在の建築基準法による耐震基準を充たしておらず、加えて配管設備等の老朽化も進んでいるため、管理組合が中心となって建替え協議が進められています。
協議の内容は、昭和のマンション開発では想像もできなかったであろうランドプラン。たとえば、建物をタワー化して周囲の敷地内に緑豊かな公園や遊歩道を設ける、共用部にカフェや保育園を増設するなど、時代に即した企画案が盛り込まれています。
2010~2020年代は、築40年を超えるオンボロ・ヴィンテージマンションがタワーマンションに生まれ変わる一大ピーク。魅力的なランドプランのある物件が続々と誕生しています。
武蔵小杉でみる「郊外型タワーマンション」
前述の通り、1990年代以降のマンション開発は、郊外のベッドタウンへ移行します。不動産の立地に対する評価も少しずつ変わり、中央線沿線の吉祥寺・三鷹、京王線の千歳烏山・調布、小田急線沿線の経堂・成城、東急線沿線の自由が丘・用賀などが「準都心」の位置づけに昇格します。
そして2000年代、開発の手はさらに千葉、埼玉、神奈川へと広がります。郊外型タワーマンション開発の代表格となる場所が、神奈川県川崎市の「武蔵小杉」駅。以前は東急東横線とJR南武線の2路線のみでしたが、そこにJR横須賀線が乗り入れて3路線利用可能に。
JR横須賀線利用で「品川」駅へ2駅10分という、都心駅のような高い交通利便性を備える街となり、それからは劇的に不動産投資・実需ともに人気が高まっていきます。
しかし、周辺街並みとの不調和、新旧住民同士の関わり合いの稀薄さ、そして台風19号被害への対応など、竣工してから発覚した諸問題への取り組みが大きな課題となってきました。
もちろん、これらの街並み、人、環境への取り組みは、昭和のマンション開発においても高い壁であったことは事実です。それらの課題を乗り越えて、今あるヴィンテージマンションは生き残ってきたのですから、一概に「悪い」と評価できるものではありません。

マンション選びのポイント「アクセス・眺望・静寂」
不動産関連雑誌には、ときどき「都心5区」という言葉が出てきます。これはズバリ、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区を指しています。
「この5つの区域内ならば、不動産投資をしても失敗しない」といわれますが、接面道路状況や土地の形状、用途地域の違いなどもあり、一概にそういえないケースもたくさんあります。
徒歩5分圏内に駅があるか、駅への道のりはフラットか、高台立地なら眺望は良いか、夜景はきれいか、学校や公園はあるか、救急対応可能な総合病院はあるか……など、都心5区に立地していても、これらの諸条件がそろう物件はなかなか見つかりません。ネットで下調べをし、現地に足を運んで情報を集めながら、多くの物件を吟味するのは大変な作業です。
そこでてっとり早く、ベテラン投資家である超一流医師たちから、今注目する「真に価値のある」都心のタワーマンションについて取材しました。
◆投資上級者の医師が選ぶ、今注目のタワーマンションはこれだ
中央区【THE TOKYO TOWERS(ザ・トウキョウタワーズ)】
「THE TOKYO TOWERS」は、勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業によって2008年に誕生した、地上58階建・総戸数2794戸のタワーマンションです。新築分譲時、TVCMに大俳優リチャード・ギアを起用したことでも有名です。
都営大江戸線「勝どき」駅へ徒歩5分のほか、銀座エリアも2km圏に捉えます。上層階住戸の窓辺からは、お台場から汐留、銀座、丸ノ内、日本橋方面の眺望を望むことができます。
建物内には、シアタールーム、パーティールーム、ゲストルームなどがあり、外出予定のない休日など、友人を招いて楽しむことができます。そのほか、小さな子どもがいるファミリーのために保育園も併設しています。近隣には聖路加国際病院をはじめ4ヵ所の総合病院があるので、家族の急な発熱やケガをした時も安心です。
現在、坪単価400~500万円程度で取り引きされています。
新宿区【ファーストリアルタワー新宿】
「ファーストリアルタワー新宿」は、2006年に誕生した、地下2階・地上32階建、総戸数370戸のタワーマンションです。都営大江戸線「新宿西口」駅へ徒歩4分、西武新宿線「西武新宿」駅へ徒歩5分のほか、JR「新宿」駅へも徒歩8分と、3駅8路線が利用できる交通利便性が大きな魅力です。
ショッピング施設やレストランなどのエンターテイメント施設がひしめく新宿の商業エリア内に位置しているので、刺激的で洗練されたシティライフが楽しめるマンションです。
間取りは、都心で働く多忙なビジネスマンをターゲットとしたワンルームタイプが中心。エントランスに指紋認証オートロックを採用、共用部にサウナ付き大浴場や最上階のスカイラウンジを備えるなど、共用設備も充実しています。
現在、坪単価400~500万円程度で取り引きされています。
港区【GC白金(グレイスコート白金)】
「GC白金」は、2006年に誕生した、地上5階建、総戸数58戸の低層マンションです。東京メトロ日比谷線「広尾」駅、南北線「白金高輪」駅、都営三田線「白金高輪」駅の3駅3路線が利用できる利便性豊かな地にあります。暮らしの舞台はセレブの街・白金、そして広尾。
いずれも徒歩圏にあるので、気軽に出かけられます。また、すぐそばの北里通りには、古民家風のおしゃれなカフェやバー、雑貨店が並び、いつも近隣の北里大学へ通う若者たちでにぎわっています。身近な街の散策も楽しめるエリアです。
建物外観は、白を基調とした清潔感のあるデザイン。エントランスにはオートロック、ホテルライクな内廊下、共用部各所に防犯カメラ、各戸の玄関ドアにディンプルキー採用のダブルロックなど、セキュリティ設備も充実した洗練のレジデンスです。
間取りプランは30㎡台~40㎡台の1R・1LDKが中心で、月額賃料15万円~18万円で賃貸されています。
秋葉 侑輝
東京不動産投資株式会社 代表取締役
3億円もの追徴課税⁉「王道の節税」を税務署が問題視した理由
合法手段を否定し追加徴税した、国税の「後出し」権限
近年最も驚かされた相続税の税務調査のひとつに、賃貸不動産を使った相続税の王道中の王道の節税が国税から否認された事例があります。
相続税の節税として、低く評価される賃貸不動産を借金で購入することが挙げられます。例えば、1億円借金してその1億円で投資用マンションを購入した場合、相続税の計算で控除できる借金は1億円ですが、相続財産として課税される投資用マンションは、8000万円程度で評価されます。このスキームはどの節税本にも書いてある王道中の王道です。
このような、だれもがやっている節税を国税がけしからんとし、その国税の指導を東京地裁が合法としたのがこの事例で、日本経済新聞などでも特集され、大きなニュースとなりました。
この節税は王道中の王道ですから本来は合法ですが、このような合法的なものでも、安易な節税につながるものであれば、課税できるという権限が国税にはあります。この権限が、総則6項と言われるものです。
相続税の対象になる相続財産の評価は、国税が独自に決めた財産評価基本通達というルールによって評価されることになっています。この総則6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と規定されています。
要約すると、安直な節税をして評価を下げるなど、「著しく不適当」な事情があれば、自分たちが決めたルールを無視して、独自に評価して問題ないというものです。となると、ルールを後日変えることができる訳ですから、いわば後出しじゃんけんなのです。
こんな後出しじゃんけんにより、追加で税金を納めさせられるのはたまったものではありません。しかし、困ったことに、この国税の権限について、裁判所も問題ないと判断するのがほとんどです。
となれば、「著しく不適当」とは何を意味するか問題になりますが、従来言われていたのは、余命宣告をされているような方が、直前に投資用マンションを購入するようなケースです。普通に考えて、余命宣告を受けるような方が、回収に時間がかかる不動産投資はしないはずで、となると相続税を少なくするためだけに、合理性のない取引を行っていると判断できるからです。
とりわけ、相続の直前に賃貸不動産を買って、相続の直後に売却するようなケースについては、相続税のメリットだけを狙っていると見ることができますので、「著しく不適当」と判断されることが極めて多いため注意が必要です。

本来ならば、購入時期は「著しく不適当」に該当しない
話を戻しますが、この税務調査の事例は、相続開始の直前ではなく、相続が開始する2、3年前に賃貸不動産を購入したものなのです。相続までにこのくらいのタイムラグがあれば、安易な相続税の節税と見るのは無理があります。
中には、相続直前に買っていなくても、相続が開始してすぐ(この事例では9ヵ月後)に売却したのがよくない、と指摘される専門家がいます。相続税の納税のために、早いタイミングで売らざるを得ないことはありますから、売却のタイミングは本来大きな問題ではありません。このため、従来の傾向や本来の取扱いからすれば、「著しく不適当」とまでは言えないと考えられます。
原因は「課税の公平性に問題あり」と思わせる証拠
ところで、この事例で、東京地裁は国税を勝たせていますが、その理由として大きくふたつの事情があると考えられています。
1. 賃貸不動産の購入だけでなく、小規模宅地の特例などその他の節税スキームを駆使した結果、相続人の納税額がゼロであったこと
2. 銀行の融資の稟議書に、節税目的で賃貸不動産を購入する目的があることが明記されていたこと
裁判所の判決は、裁判官の心証で決まることが多いですが、上記のような事情があると、行き過ぎた節税をしており、課税の公平から問題があるから国税が正しい、と判断する可能性が大きいと言えます。加えて、国税としても、このような露骨な証拠があると課税しやすいです。合法だから、だれもがやっているから、という理屈だけでは、国税に通用しないでしょう。
以上を踏まえた場合、上記1のような露骨すぎる節税は差し控えた方がいいということになりそうです。税法で決まっている以上の税額を納める必要はないのですが、総則6項のような横暴な制度がありますので、慎重な対応が必要になるでしょう。
加えて、上記の2に関連してですが、国税対策を考えるうえで、銀行などの金融機関との折衝は要注意です。国税には納税者の取引先を調査する反面調査の権限が認められていますが、金融機関も当然対象になるからです。金融機関は後日のトラブルなどに備えて、しっかりと記録を残す組織ですので、国税が事実確認をするのに、最も適した機関です。実際のところ、金融機関を調査されて自分に不利な証拠をつかまれた、という調査事例も多いですから、金融機関に提出する書類や、金融機関との打ち合わせの内容などにも注意する必要があります。
いずれにしても、最終的には税務署との折衝で課税が決まるので、税務調査で国税としっかりと交渉することが重要になります。税務調査と聞くと怖い思いをされる方も多いと思いますが、税務調査を乗り切るためのテクニックはいろいろありますので、こちらも勉強しておくべきでしょう。
セブンセンスグループ
井本 壮一郎
セブンセンス税理士法人
代表パートナー・税理士
松嶋 洋
元国税調査官・税理士
不動産投資の利回りを理解して優良物件を見極める方法
「不動産投資で利回りという言葉をよく聞くけれど、どういうこと?」
「利回りはどうやって計算されているの?」
「利回りは投資判断にどう関わってくるのか?」
「利回りはどうやって計算されているの?」
「利回りは投資判断にどう関わってくるのか?」
当記事では、
・不動産投資の利回りがどのように計算されているのか
・利回りを知ることでどのように投資判断に活用できるのか
これらを踏まえ、目安となる利回り情報を交えて実践的な解説をします。利回りが理解できれば適切な投資判断ができるようになり、その分、不動産投資に失敗するリスクも低くなります。
・不動産投資の利回りがどのように計算されているのか
・利回りを知ることでどのように投資判断に活用できるのか
これらを踏まえ、目安となる利回り情報を交えて実践的な解説をします。利回りが理解できれば適切な投資判断ができるようになり、その分、不動産投資に失敗するリスクも低くなります。
読み終わった時には不動産投資と利回りについての実践的な知識が身につくことでしょう。不動産投資の「失敗」を回避するためにも、ぜひ利回りについての知識をマスターしてください。

(画像=Andrey_Popov/Shutterstock.com)
1.不動産投資の利回りについて必須の知識

(画像=AlexLMX/Shutterstock.com)
不動産投資の目的の一つは利益を得ることです。その利益がどれだけ見込めるかを示す指標として利回りが用いられています。
例えば、1億円の物件で利回りが5%だとしたら、その物件では年間に500万円の家賃収入が発生しているという意味になります。
これはとてもシンプルな例ですが、実際の不動産投資では利回りに対する概念が複数あり、計算方法も使い道によっていくつかの種類があります。
利回りは投資判断をする際にとても重要な指標となります。ここでは利回りの基本から順に解説していきます。
これはとてもシンプルな例ですが、実際の不動産投資では利回りに対する概念が複数あり、計算方法も使い道によっていくつかの種類があります。
利回りは投資判断をする際にとても重要な指標となります。ここでは利回りの基本から順に解説していきます。
1-1.不動産投資の利回りとは何か
不動産投資の利回りとは、「所有している収益物件がどれだけの利益を稼いでくれるのか」を示す指標です。単位は%(パーセント)で、年間ベースで算出されます。利回りが高ければ高いほど「稼ぐ力」が大きいことを示しますが、単純に利回りだけで判断することはできません。
不動産以外の投資についても、同じように利回りの概念があります。年利〇%と表示されているものは、その数値が投資利回りです。他の投資商品ではあまり「利回り」という言葉は用いられませんが、投資金に対するリターンの比率という意味では同じです。
1-2.利回りの計算方法はとてもシンプル
利回りの計算式は、以下の通りです。
年間の賃料収入 ÷ 物件取得費用 × 100 = 不動産投資の利回り
この計算式が意味しているのは、「収益物件が1年でどれだけ稼ぎ、それが取得費用に対してどれだけの水準か」ということです。先ほど単純に利回りだけで収益性を判断することはできないと述べましたが、その理由はこの計算式にあります。
同じ賃料水準だったとしても、分母である物件取得費用が安ければ、利回りは高くなります。よく地方の格安物件などで見られるパターンですが、利回りが20%、30%といったようにとても高い物件があります。しかしこれは物件の売り出し価格が安いため利回りが高くなっているだけで、空室率などは考慮しておりません。収益性が本当に高いかどうかは購入者の運用力に大きく影響されます。
1-3.表面利回りと実質利回りの違い
表面利回りと実質利回りについて、その違いとそれぞれの用途を解説します。
利回りの計算式や具体的な計算例などをご紹介していますが、先述の例はすべて「表面利回り」です。表面利回りは計算式の分子に満室の場合の賃料収入をそのまま反映して計算をします。しかし実際には空室率や物件を維持するコストや税金、ローン返済などを差し引かないことには実態には近づきません。
ではなぜ表面利回りがあるのかというと、その物件の満室想定での家賃収入と物件価格の関係値を統一の基準で一次判断するためです。修繕費や管理費などは購入した後の所有者の判断により変動します。また、ローン支払いについても同じく購入者によって変わってきます。そのため、表面利回りで統一することで比較しやすくなるというメリットがあります。
それに対して実質利回りとは、収益物件を維持するための必要経費と、空室リスクを加味した利回りです。計算をする場合には分子の部分に入る賃料収入から必要経費と想定空室率分を差し引き、それを物件取得費で割ります。
表面利回りと比べると不動産投資の現実に即しているように見えますが、実は実質利回りだけでは投資家の手残り(取り分)が分かりません。そこで必要になるのが、次項のキャッシュフロー計算です。
表面利回りと比べると不動産投資の現実に即しているように見えますが、実は実質利回りだけでは投資家の手残り(取り分)が分かりません。そこで必要になるのが、次項のキャッシュフロー計算です。
1-4.利回りとキャッシュフローの違い
実質利回りは必要経費や空室リスクを加味した指標なので不動産投資の実態に近いのですが、もうひとつ重要な経費が加味されていません。その経費とは、ローン返済です。不動産投資では多くのケースでローンの利用が前提になっているため、ローン返済を差し引かないことには投資家にどれだけの手残りがあるのかが判明しません。この手残りのことをキャッシュフローといいます。投資家が最終的に知るべきなのは、このキャッシュフローです。
1-5.不動産投資の「正確な成績」を知るための指標
表面利回りと実質利回り、そしてキャッシュフロー。これらを理解していただいた上で、さらに不動産投資の成績を正確に知る上で重要な指標を知っていただきましょう。
①返済後利回り
先ほど、投資家は最終的にキャッシュフローを知るべきだと述べました。このキャッシュフローはローン返済分も差し引いた数値なので、投資家の手残りを正確に算出できます。このようにローン返済を加味して、手残りが物件取得費用に対してどれだけあるのかを示す指標のことを返済後利回りといいます。
先ほど、投資家は最終的にキャッシュフローを知るべきだと述べました。このキャッシュフローはローン返済分も差し引いた数値なので、投資家の手残りを正確に算出できます。このようにローン返済を加味して、手残りが物件取得費用に対してどれだけあるのかを示す指標のことを返済後利回りといいます。
②自己資金利回り
ローンという他人資本を利用できるのは、不動産投資の最大と言っても良いメリットです。低利でローンを利用し、手元にできるだけ多くのキャッシュを残すのが不動産投資の本筋です。そこで注目したいのが、自己資金をベースにした利回りです。
ローンという他人資本を利用できるのは、不動産投資の最大と言っても良いメリットです。低利でローンを利用し、手元にできるだけ多くのキャッシュを残すのが不動産投資の本筋です。そこで注目したいのが、自己資金をベースにした利回りです。
計算方法は返済後利回りと同じですが、違うのは分母が自己資金であることです。ローン返済後の手残りを自己資金で割ると、自己資金に対してどれだけ稼げているのかが分かります。
次に解説するCCRと同様、不動産投資の健全性を高め、さらなる投資規模の拡大を目指すのであれば手元に多くのキャッシュを残す必要があります。自己資金利回りは資金をどれだけ効率的に運用しているかを確認する指標です。他の投資商品とも同じ目線で比較することができます。
なお、自己資金利回りはCCR(自己資金回収率)という指標にも使うことができます。例えば自己資金利回りが20%であれば、毎年20%ずつ自己資金を回収できることになり、5年で自己資金を全額回収できます。自己資金利回り(つまりCCR)が高いほど投資した資金を早く回収できるため、投資の健全性が高く次なる投資への可能性も広がると判断できます。
2.利回りを使った不動産の投資判断方法

(画像=Kunal Mehta/Shutterstock.com)
不動産投資で利回りが重視されるのは、その物件の収益性を把握し、比較することができるからです。次に利回りを使って正しい投資判断をする方法について解説します。
2-1.利回りで不動産投資の健全性が分かる
不動産投資の利回りが示すものは、直接的にはその物件でどれだけの利益が得られるのかという未来です。では、どれだけの利益が得られるのかという未来を知るのは何のためかというと、その物件を購入した際の不動産投資の健全性を知るためです。
不動産は高額であるがゆえに、失敗(=資産の減少)のダメージが大きくなりがちです。失敗したくないと思う投資家が最も知りたいのは、健全性といえるでしょう。利回りが分かると、その物件を用いて賃貸経営をした時の収支をシミュレーションすることができます。シミュレーション結果が健全であるかどうかが最終的な投資判断につながります。
2-2.データから見る「物件別」表面利回りの傾向
それでは実際に、収益物件ではどれくらいの利回りが見込めるのでしょうか。その目安を投資判断に役立てるため、ここではいくつかのデータを見てみましょう。
1つ目は、物件別の利回りデータです。不動産投資情報サイト「健美家」に掲載された全国の収益物件について、表面利回りの推移をグラフ化したものです。
グラフ内の少し古いですが最新データである2017年7月の時点で、区分マンションが7.69%、一棟マンションが8.10%、一棟アパートが8.95%となっています。この相関関係は目安なので、一棟アパートの利回りが高くなりやすく、その一方で区分マンションは利回りが低くなりやすいという傾向を押さえておいてください。
次に、野村不動産が運営する不動産投資情報サイト「ノムコム・プロ」が発表した、2016年上半期の市場動向です。
こちらのデータで最新となる2016年5月の、地域別表面利回りを見てみましょう。
こちらのデータで最新となる2016年5月の、地域別表面利回りを見てみましょう。
| 一棟アパート | 一棟マンション | 区分マンション | |
|---|---|---|---|
| 東京都心5区 | 5.32% | 4.94% | 4.79% |
| 東京23区以西 | 6% | 5.92% | 5.72% |
| 横浜、川崎 | 7.53% | 6.93% | 6.61% |
これらの数値からは、東京都心5区が最も利回りが低く、次に高いのが23区以西で、横浜川崎がこの中では最も高いという傾向が見て取れます。これも収益物件の利回りによく見られる傾向で、高額物件が多い都心ほど利回りが低くなり、そこから郊外や地方に向かうほど利回りが高くなりやすいというのも、利回りの目安を知る上で押さえておきたいポイントです。
2-3.物件の立地や種別、状態と利回りの相関関係
前項では収益物件の利回りについて2つの傾向があることを解説しました。その傾向を含む、物件の条件と利回りの相関関係についてまとめました。これらはあくまでも全体的な傾向であり、個別の物件についてはそれに当てはまらない場合もあります。
| 条件 | 利回りへの影響 |
|---|---|
| 立地 | 都心に近づくほど利回りが低くなり、郊外になるほど高くなる |
| 物件種別 | 区分マンションは利回りが低くなり、一棟ものは高くなる |
| 築年数 | 新築に近いほど利回りは低く、築年数が古くなるほど高くなる |
| 構造 | RCは利回りが低くなり、木造は高くなる |
これらは表面利回りという指標に見られる傾向であり、実際の不動産投資がこの通りになるわけではありません。いくら表面利回りが高いからといっても入居者がいなければ収益は見込めないわけで、これだけで投資の最終判断するのは早計といえます。
2-4.ローン返済を上乗せして必要な利回りを算出しよう
先ほどご紹介した各種利回りのデータについては、すべて表面利回りで表示されています。重要なのは必要経費などを考慮した実質利回りに、ローン返済を考慮した「利回り」です。
例えばローンの金利が1.5%であった場合、必要な利回りは少なくとも1.5%を上乗せした数値である必要があります。ローン金利が2%であれば2%を上乗せするといった具合に、利用できる不動産投資ローンの金利がどれくらいになるか見極め、その利率を上乗せすることによって実際に必要な利回りの目安が見えてきます。
3.投資判断を間違えないために知っておきたいこと

(画像=Andrey_Popov/Shutterstock.com)
ここまで不動産投資の利回りについてさまざまな角度から解説をしてきました。
この章ではそこから得られた結論として、投資判断を間違えないための利回りを活用するノウハウについて解説したいと思います。
この章ではそこから得られた結論として、投資判断を間違えないための利回りを活用するノウハウについて解説したいと思います。
3-1.物件に表示されている利回りは「表面利回り」である
どんな物件であっても、売り出されている収益物件の情報に表示されているのは、「表面利回り」です。必要経費やローン返済などを差し引いていない、名目的な利回りです。
すでに解説したように、表面利回りはあらゆる利回りの中で最も高い数値になります。しかしそれは一次判断をするための数値です。
物件の実力を知るには、「実質利回り」と「ローン返済」を加味した「返済後利回り」がそれぞれ何%になるのかという情報が必要です。
物件の実力を知るには、「実質利回り」と「ローン返済」を加味した「返済後利回り」がそれぞれ何%になるのかという情報が必要です。
3-2.利回り計算には「現況」と「満室想定」がある
中古の収益物件情報に記載されている家賃収入を見る際には、その金額が「現況」なのか「満室想定」なのかが重要です。
「現況」とは現況賃料収入のことで、中古物件が現在、得られている家賃収入を示しています。現在すでに入居者がいる場合は、その入居者から得られている実際の賃料収入が表示されています。
それに対して「満室想定」賃料収入とは、文字通りその物件が満室になっていることを想定した賃料収入です。もしかすると現在は入居者がいないかも知れませんし、一棟物件の場合は満室ではないかも知れません。その物件がフル稼働して満室経営になっている時には家賃収入がこれだけになりますよ、という数値なので、こちらは想定値です。
区分マンションであっても一棟物件であっても、退去に伴う原状回復の期間もあり、空室ゼロの満室経営は実際には難しいでしょう。その「通常は無い」数値が賃料収入として表示されていることが多いのが実情です。家賃収入が「現況」なのか、「満室想定」なのか、しっかりとチェックする必要があります。また設定している家賃が相場に近しいかも必ずチェックしましょう。
3-3.高利回り=優良物件なのか
不動産投資の利回りは高い方が良いのでしょうか。
必ずしも、「表示されている利回りが高ければ優良物件である」とは言い切れません。
必ずしも、「表示されている利回りが高ければ優良物件である」とは言い切れません。
先ほど解説したように、満室想定の利回りがいくら高くても、その物件に長らく入居者が入っていない状態であれば、それは単なる机上の空論でしかありません。
利回りが20%、30%という高い数値になっている物件は地方や郊外などでよく見かけますが、これらの物件で表面利回りが高くなっているのは、
・物件価格が安い(または安く売られている相応の理由がある)
・満室想定の賃料収入が、入居者が存在していた頃のままになっている
などの理由があります。
・物件価格が安い(または安く売られている相応の理由がある)
・満室想定の賃料収入が、入居者が存在していた頃のままになっている
などの理由があります。
物件の集客力が落ちてくると、売り出し価格も安くなります。しかし集客力があった頃の想定利回りのままになっていれば、利回りの数値だけが高くなっていくのは当然です。
これとは逆に地価の上昇が続いている地域では、賃料収入が変わっていないのに物件価格が高くなっているせいで利回りは低くなります。しかし、むしろこちらのほうが空室リスクの低い物件であるケースもあります。
これらの例から、利回りだけで優良物件かどうかを判断するのは早計だとわかります。
これらの例から、利回りだけで優良物件かどうかを判断するのは早計だとわかります。
それでは利回りの他にどんな部分を精査すれば優良物件であると判断できるのでしょうか。次項で解説します。
3-4.利回りよりも重視したい3つの項目
収益物件選びにおいて、利回りと同様に重視したい3つの項目を紹介します。
① 空室率
新築物件の場合はまだ入居実績がないので空室率を算出することはできませんが、中古物件の場合で表示されている賃料収入が満室想定であれば、空室率を知っておく必要があります。レントロールは必ず確認しましょう。
・直近3年程度の入居実績はどうだったのか
・空室だった時期はどれくらいあるのか
・募集家賃は近隣の同じような物件と比較して高くないか
これらを元に適正家賃と空室率を算出します。それを収支シミュレーションに反映することで、実態に近しいシミュレーションが可能になります。
新築物件の場合はまだ入居実績がないので空室率を算出することはできませんが、中古物件の場合で表示されている賃料収入が満室想定であれば、空室率を知っておく必要があります。レントロールは必ず確認しましょう。
・直近3年程度の入居実績はどうだったのか
・空室だった時期はどれくらいあるのか
・募集家賃は近隣の同じような物件と比較して高くないか
これらを元に適正家賃と空室率を算出します。それを収支シミュレーションに反映することで、実態に近しいシミュレーションが可能になります。
② キャッシュフロー
不動産投資家にとって、最終的に「手残りがいくらになるのか」は重要です。キャッシュフローがプラスになるのか、いくらになるのかを入念にシミュレーションしてから判断をしてください。
不動産投資家にとって、最終的に「手残りがいくらになるのか」は重要です。キャッシュフローがプラスになるのか、いくらになるのかを入念にシミュレーションしてから判断をしてください。
③ 将来需要
不動産投資は物件を買ったら終了ではなく、そこからがスタートです。長期間にわたって物件を所有し続けることになるため、不動産投資の投資判断は「今」だけではなく「将来性」をしっかりとシミュレーションしていくことが重要になります。
不動産投資は物件を買ったら終了ではなく、そこからがスタートです。長期間にわたって物件を所有し続けることになるため、不動産投資の投資判断は「今」だけではなく「将来性」をしっかりとシミュレーションしていくことが重要になります。
「人口流入が見込まれる地域」「今後も地価が下がらない地域」など「立地の良し悪し」で選ぶべきと言われるのはこの理由によります。東京での不動産投資が注目されているのは、その条件に最も合致しているからです。
もちろん東京だけではなく、全国各地に将来性のある地域はあります。おもに都市部に限定されますが、「今後も賃貸需要が衰えないと見込まれる地域かどうか」を入念に精査してください。
3-5.新築が中古より利回りが低くなる理由
当記事でご紹介した物件種別の利回りでは、新築よりも中古のほうが利回りが総じて高いという傾向が見て取れます。これは他のデータや記事などでも同様で、不動産投資において新築よりも中古の方が利回りが高くなるのは一般的として捉えられています。
物件の取得価格は利回り計算の分母になるため、新築の方が分母が大きくなる=利回りは低くなり、中古はその逆に利回りが高くなるのです。
- <参考:新築と中古を利回りだけで比較できない理由>
新築物件は利回りが中古より低くなるのは上記のとおりです。しかし新築物件には利回りだけでは測れないメリットがあります。
例えば、地方の築古アパート(表面利回り20%)と、都心部駅近の新築RC一棟マンション(表面利回り5%)を比較した場合、どちらが将来性があるでしょうか。
・修繕費用等の追加コスト
・残り運用期間
・空室率による実質利回り
・売却時の価格下落率
これらを総合的に見て、投資を判断しなければならないことを念頭におきましょう。
4.まとめ

(画像=Andrey_Popov/Shutterstock.com)
不動産投資の利回りについて、基本から投資判断に活用する方法まで解説してきました。
ここで得た知見を使って物件選びにお役立てください。
この記事が、将来にわたってしっかりと利益を出してくれる優良物件との出会いに役立てられたら幸いです。
この記事が、将来にわたってしっかりと利益を出してくれる優良物件との出会いに役立てられたら幸いです。
不動産投資に失敗するのはどんな人か?
今年もあとわずかとなりましたが、2019年は「老後2000万円問題」が注目をあびたことから、「資産運用」を意識した人も多かった年ではなかったでしょうか。
「資産運用」と一言でいっても、株式や投資信託、不動産投資など様々な種類があります。自分がどの投資に向いているかは、その人がとれるリスク許容度により変わってきます。自分の返済力以上に借金をして不動産投資をはじめてしまうことは無謀ですし、大きなリターンを狙いたい人が投資信託を行うのも違和感を感じます。私は不動産投資ローンのコンサルタントとして、これまで数多くの不動産投資家と接してきました。今回は「サラリーマンが不動産投資で資産運用すること」のメリットとデメリットを、他の投資法と比較しながらお伝えします。

(SvetaZi/gettyimages)
不動産投資は「ミドルリスク・ミドルリターン」
不動産投資と聞くと「巨額のお金が必要」「不動産が暴落して破産する」と、身構えてしまう方も多いかと思いますが、準備・計画性を持って始めれば意外にも「ミドルリスク・ミドルリターン」の投資に分類されます。
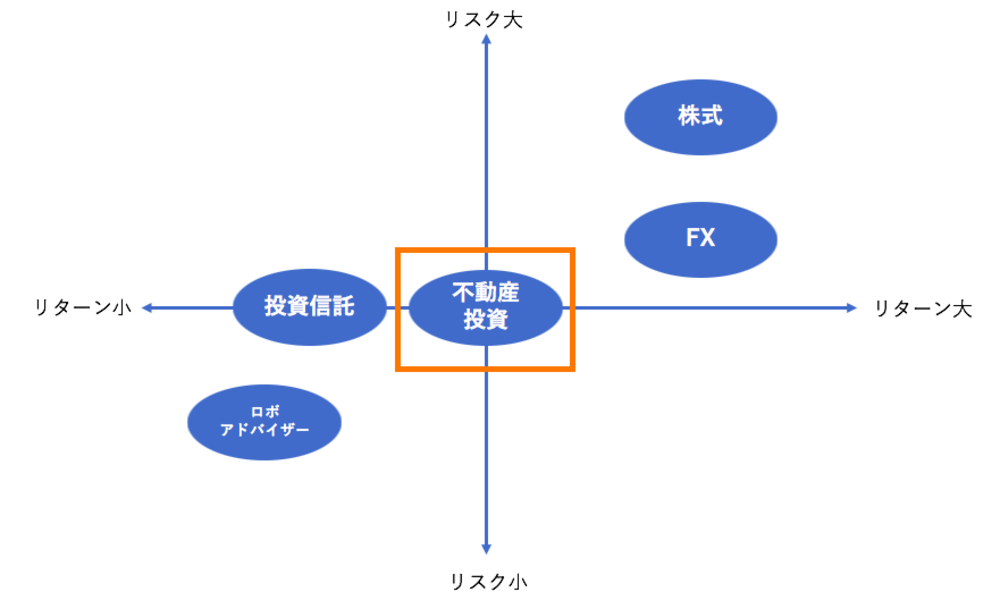
「株式」や「FX」に比べるとリスクは低く、「投資信託」や「ロボアドバイザー」に比べるとリターンは大きくなります。なぜミドルリスク・ミドルリターンになるのか、その答えは「価格変動の傾向」と「収入の安定性」にあります。
株式やFXでは、企業業績や為替相場が予想に反して下落した場合、下手をすると一瞬で大損をしてしまいます。東芝を例にとってみると、2016年11月には1株4289円の高値をつけていた株価が、その翌月には減損損失計上の可能性から2320円まで落ち込む場面がありました。11月の高値で100株購入したとすると単純計算で約43万円が取得にかかったことになり、1カ月後の安値で売ったとすると約23万円でしか売れないことになります。1カ月で20万円のマイナスです。もちろん株価は上下するので回復を待つことにより再度上昇を狙うことはできますが、こればかりは個人の力ではどうしようもできず正確な予測を立てることも難しいでしょう。
一方、不動産投資では不動産自体の価格変動はゆるやかという特徴があります。数十年先を見据えると資産価値が大幅に下落する可能性はありますが、1カ月や1年で買値の半額などの大幅な下落に見舞われることはまずありません。もちろん自然災害など人間では予測できないリスクもありますが、総合的に見ても株式やFXに比べてリスクは低いと言えるでしょう。
また、不動産投資がミドルリターンと言われる所以は「毎月の家賃収入」にあります。株式やFXでの収入は配当金や売却益にあたり、投資先の業績や相場が向上した場合は数十倍ものリターンを得られる可能性があります。しかし、これは決して安定したものではなく、運要素も大きいと言えます。
一方、不動産投資では入居者がいれさえすれば「家賃」という形で毎月収入を得ることができます。株式やFXに比べ、安定した収入を得ることができるのです。加えて、不動産を売却する際には購入時よりも高い値段で売ることにより、売却益を狙うこともできます。投資金額も数千万円単位であることが多いため、売却益も大きく上乗せできる可能性があります。
サラリーマン最大の武器「銀行融資」が使える
その他にも、不動産投資にはある変わった特徴があります。それは「銀行からの融資が受けられる」点です。銀行からお金を借りて自分の資産を拡大できる、他にはない面白い投資法とも言えます。サラリーマンの方であれば、不動産購入資金を全額ローンで賄うフルローンを利用することにより、自己資金は出さずに投資をするということも可能になります。
株式や投資信託などでも、カードローンで借りたお金を元手にすることはできますが、不動産投資ローンと比べると金利が圧倒的に異なってきます。カードローンの場合は、年利8~14%ほどが相場になり、借りられる金額もどんなに属性が良い方でも500万円程度が限界です。
一方、不動産投資ローンの場合は、年利1~4%で年収の約8~10倍を借りることができます。年収600万円のサラリーマンであれば、総額4800~6000万を借りることができる計算になります。自営業の方でも不動産投資ローンを利用することは可能ですが、年利が通常より高くなったり条件が悪くなったりと、どうしてもサラリーマンの方に比べると融資条件は悪くなります。
私がコンサルタントを勤めている「モゲチェック不動産投資」では、主にサラリーマンの方の不動産投資ローンの借り入れ可能額診断、適正金利の推定を行なっています。現在であれば、平均の借り入れ金利は大体2%程度です。ローンを借入れる際の参考にしてみてください。
不動産投資ローンには「生命保険」がついてくる
もう一つ、他の投資法にはない特徴として、ローンを組んだ際に付随される「団体信用生命保険」があります。団体生命信用保険とは、ローン返済中にローン契約者が死亡・高度障害などの返済が困難な状況に陥った場合、残りのローンがすべて免除される制度です(各社により規定があります)。不動産投資ローンを組む場合には、加入しなければならないことが多く、万が一自分に何か起こった場合でも、現物である「不動産」という資産は家族に残ることとなります。不動産投資ローンを組むことで、生命保険の内容をカバーできると考えることができます。
「投資」に確実はない。ミドルリスクでも大ダメージを受ける可能性もある
ここまで不動産投資に関する良い点を中心にご紹介してきましたが、もちろんリスクもあります。不動産投資のリスクは、「売却リスク」「空室リスク」の2つに分けられます。
「売却リスク」とは、物件を売りたい時に希望の値段で売ることができないリスクです。時には買い手が見つからない、売ることさえできないというケースもあります。家賃収入が下がり売却したくてもできず、赤字だけが増えていくということも考えられます。
「空室リスク」は、空室が出てしまった場合に想定よりも低い収入が続くことです。物件の立地や状態次第では入居者が集まらず、結果、家賃回収ができずにローン返済に追われる生活になる可能性があります。不動産投資を始める際には、入居者が集まりやすい立地条件にあるか、家賃や設備は周辺物件に比べて妥当かなどを考えなければなりません。また、空室を出さないためにも定期的なメンテナンスが必要になってきます。
物件購入前に不動産会社が提示してくる物件の表面利回りを安易に信じてしまうと、その後痛い目を見ることもあります。不動産会社の計算する利回りは、購入したばかりの一番良い時期の収入が30年以上続くものとして計算されている場合が多々あります。
業者は「不動産を売ることが仕事」なので、「一番いい状態で保てること」を想定して魅力的な物件に見せてきます。しかし、よほどの目利き力や情報力がない限り「一番いい状態を保つ」ことはまず不可能でしょう。
必ず自分で最悪の場合のシミュレーションを行い、「負動産」になってしまった場合に自身の経済力で耐えられるかを想定することも重要です。不動産投資は長期目線での投資です。必ず「自分がこの不動産を運営している」という自覚を持ち、空室リスクを防ぐ工夫を行わなければいけません。「ほったらかし」ではまず成功しません。
私が出会った「ほったらかし」失敗例
都内の物件を保有する40代のAさん(会社員)は、物件管理や空室対策をすべて管理会社におまかせしていました。オーナーの管理代行を行う管理会社は玉石混淆です。誠心誠意で対応してくれる会社や担当者もいれば、空室が出ても放置、物件の管理状況も把握していない担当者もいます。
Aさんへのヒアリングを進めていくと、Aさんの管理会社は残念ながら後者であることが判明しました。また同時に、Aさん自身もご自身の物件について全く把握をしていない状況でした。空室30%の状況が続き家賃収入が入らず、ただただローン返済のために働く日々。
それを少しでも解消したく、ローン金利が安い金融機関への借り換えをご希望でした。ローンを借りかえるにしても、金融機関の審査では今の入居者状況を確認されます。金融機関も「落ちこぼれ」と判明している物件へのローン貸出はしたくありません。審査に通るため、Aさんから管理会社へ再三抗議をしていただき、管理会社による積極的な入居者付けを要請しました。管理会社への交渉を初めて3カ月、ようやく管理会社が動き出し、7カ月後には空室率10%までにも落ち、無事ローン借り換えも成功しました。
ここでお伝えしたいのは、「もしAさんが事前に物件の状況を把握し、自分で管理会社への催促をし、対策を講じていたとしたら、もっと早く赤字は食い止められた」ということです。もちろん悪い管理会社にあたってしまったという不運もありますが、それを含めてもAさん自身でもっと早い段階で食い止められたはずです。
以上の通り、不動産投資にもリスクはつきものです。ただし、エリアや立地を見定め、築年数や間取りなど長く消費者受けできる物件を見つけ、良い管理状態を保つことで、不動産で「資産運用」していくことは十分可能です。
成功している投資家は「分散投資」をしている
不動産投資は、他の投資法と組み合わせることによりリスク分散をすることが可能です。例えば、「株」「投資信託」「FX」は変動の要素が近いものになり、どれかが下がれば連動して下がるという特徴を持っています。
一方、不動産投資はこの変動要素から切り離されているものなので、市場の影響を受けにくいという面があります。実際に、私が対応してきたお客様でも不動産投資単体でなく株やFXと組み合わせて投資をしている人は7割程度にのぼります。もし余裕があるのであれば、資金を分散させることにより何かあった場合のリスクバランスをとることができます。
投資に「絶対大丈夫」はあり得ません。「この物件に賭ける」ではなく、「長期目線で資産を形成する」という視点で可能な範囲での資産運用をおすすめします。
元グラドル・杉原杏璃が不動産投資を実践中!株の利益でまず買ったのは意外なあの場所だった!?
「株以外にも分散投資を!」と思い立ち、不動産を即購入!
株式投資歴10数年のグラドルとして名高い杉原杏璃さんだが、実は密かに不動産投資にも手を広げているという。
「18年の6月に、中古の1Kマンションを購入しました。リーマンショック前からずっと株式投資を続けてきて、銘柄に関する分散投資はかなり進めてきたつもりです。ただ、資産全体としても株だけに偏らずに分散を心掛けたほうがいいとも考え始め、安定的なインカムを期待できる不動産に投資することにしました」
杉原さんは投資関連のイベントに出演することも多く、そういった催しに出席した不動産投資のプロからもいろいろと話を聞いて刺激を受けていた。その一方で、家賃保証や管理費のことなど、まだ不動産知識に関して知らないことは少なくなかったが、すぐさま購入に至ったそうだ。
「まずは実際にアクションを起こして、その後から勉強をするというのが私の性格で、いつも追い込み型なんです(笑)」
杉原さんが目をつけたのは、大阪の中心的スポットである“キタ”にアクセスしやすい閑静な住宅地にある「7畳・キッチン付き」の物件で、購入額は1500万円弱、表面利回りは5.53%だった。
「上場企業が販売・管理していた物件です。この会社は物件データの解析や管理ツールなどにAIを活用していて、その情報をスマホのアプリで簡単にチェックできます。私が指定した条件をもとにAIが選び出した物件の情報がメールで送られてきて、それをチェックしていたら、すでに入居者がいる物件が見つかりました。最寄りの駅からもわりと近くて築浅(06年竣工)だったので、ほとんど迷うこともなく、あっさりと購入を決めましたね」
「18年の6月に、中古の1Kマンションを購入しました。リーマンショック前からずっと株式投資を続けてきて、銘柄に関する分散投資はかなり進めてきたつもりです。ただ、資産全体としても株だけに偏らずに分散を心掛けたほうがいいとも考え始め、安定的なインカムを期待できる不動産に投資することにしました」
杉原さんは投資関連のイベントに出演することも多く、そういった催しに出席した不動産投資のプロからもいろいろと話を聞いて刺激を受けていた。その一方で、家賃保証や管理費のことなど、まだ不動産知識に関して知らないことは少なくなかったが、すぐさま購入に至ったそうだ。
「まずは実際にアクションを起こして、その後から勉強をするというのが私の性格で、いつも追い込み型なんです(笑)」
杉原さんが目をつけたのは、大阪の中心的スポットである“キタ”にアクセスしやすい閑静な住宅地にある「7畳・キッチン付き」の物件で、購入額は1500万円弱、表面利回りは5.53%だった。
「上場企業が販売・管理していた物件です。この会社は物件データの解析や管理ツールなどにAIを活用していて、その情報をスマホのアプリで簡単にチェックできます。私が指定した条件をもとにAIが選び出した物件の情報がメールで送られてきて、それをチェックしていたら、すでに入居者がいる物件が見つかりました。最寄りの駅からもわりと近くて築浅(06年竣工)だったので、ほとんど迷うこともなく、あっさりと購入を決めましたね」
狙っていたわけではないが、法人借り上げの物件を購入!
その部屋は法人が借り上げていて、その従業員が入居者だった。ただし、最初からそういった物件を狙っていたわけではなく、その事実は買った後で知ったらしい。
「購入後にチェックしていたアプリの情報を改めて確認してみたら、物件概要の欄に法人が借り上げていることが記載されていました。たまたま運よく、好条件の物件に手を出したみたいです。でも、お陰でさっそく、そういった物件に注目するという発想があることを勉強できましたね」
杉原さんは安定的な需要が見込まれる東京でも物件を探していたが、最終的に大阪を選んだのは、今後の盛り上がりを期待できる気がしたからだ。
「東京はオリンピック開催後に不動産市況などがどうなるかがちょっと気掛かりでした。その点、大阪では25年に万博(日本国際博覧会)が開催される予定だし、カジノの計画(大阪RFP=夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業の仮称で検討されている統合型リゾート施設)も進められているので、むしろこれからに期待をもてそう。それに、私は広島出身で距離的に近い大阪のほうが馴染み深くてある程度の土地勘も働きましたし、東京よりも物件価格が安いですから。道頓堀には中国人をはじめとするインバウンドが押し寄せていますし、自分が不動産で勝負するなら大阪だと思いました」
杉原さんは現地でその物件を自分の目でチェックしていないし、内見もしていないそうだ。現状では入居者がいても先々で空室リスクが顕在化する可能性があることは理解していたが、特に躊躇することはなかったという。
「大阪方面でのお仕事も多いので、もしも借り手が見つからなくなったら、自分でホテル代わりに使えばいいやと思っていました。今、大阪ではホテル不足が深刻ですから。とにかく、あれこれ悩んでいたら、なかなかも始められませんから。すべてが自己責任の株とは違って、不明点や悩みなどが生じたら、販売・管理を行っている不動産屋さんに相談できるという点では気が楽でした」キャッシュで一括購入したことは少々後悔
「購入後にチェックしていたアプリの情報を改めて確認してみたら、物件概要の欄に法人が借り上げていることが記載されていました。たまたま運よく、好条件の物件に手を出したみたいです。でも、お陰でさっそく、そういった物件に注目するという発想があることを勉強できましたね」
杉原さんは安定的な需要が見込まれる東京でも物件を探していたが、最終的に大阪を選んだのは、今後の盛り上がりを期待できる気がしたからだ。
「東京はオリンピック開催後に不動産市況などがどうなるかがちょっと気掛かりでした。その点、大阪では25年に万博(日本国際博覧会)が開催される予定だし、カジノの計画(大阪RFP=夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業の仮称で検討されている統合型リゾート施設)も進められているので、むしろこれからに期待をもてそう。それに、私は広島出身で距離的に近い大阪のほうが馴染み深くてある程度の土地勘も働きましたし、東京よりも物件価格が安いですから。道頓堀には中国人をはじめとするインバウンドが押し寄せていますし、自分が不動産で勝負するなら大阪だと思いました」
杉原さんは現地でその物件を自分の目でチェックしていないし、内見もしていないそうだ。現状では入居者がいても先々で空室リスクが顕在化する可能性があることは理解していたが、特に躊躇することはなかったという。
「大阪方面でのお仕事も多いので、もしも借り手が見つからなくなったら、自分でホテル代わりに使えばいいやと思っていました。今、大阪ではホテル不足が深刻ですから。とにかく、あれこれ悩んでいたら、なかなかも始められませんから。すべてが自己責任の株とは違って、不明点や悩みなどが生じたら、販売・管理を行っている不動産屋さんに相談できるという点では気が楽でした」キャッシュで一括購入したことは少々後悔
初期投資はかさむものの、入居者の間で人気の高い新築物件については、最初から視野に入れていなかったと杉原さんは語る。
「新築は1年も経つと半値とかまで下がっちゃうので怖いです。私の場合はせいぜい、築5年程度で十分かなと思っています。知り合いのテレビマンには新築投資の達人がいて、駅直結とかの人気分譲物件の抽選に毎月手当たり次第に応募しています。つねに自分で住む前提で買っているのですが、あまりに人気が高くて利益が出るのですぐに売却し、また新たな物件に応募するというパターンを繰り返しているようです」
ワンルームや1Kのような単身者向けのマンションを選択したことが自分にとって本当に正解だったのか、本当は区分所有ではなく、アパートでもいいから1棟買いしたほうがよかったのかなど、不動産投資に関する勉強を始めたばかりの杉原さんの胸中には、様々な迷いや疑問もある。
「とにかく、自分が住んでも大丈夫だと思うものを選びました。それ以外の選び方をまだ私は理解できていないわけです。購入してからまだ1年少々しか経ってないので、節税対策やその効果のこともよくわかっていません」
それでもまずは買ってみたことをまったく後悔していないが、唯一、早計だったと痛感していることがあるという。
「キャッシュで一括購入してしまったことはちょっと失敗でしたね。家賃が毎月入ってくるのはうれしいのですが、単に購入に充てたお金が戻ってくるような感覚で、ローンを組んだほうが投資効率もよかったと悔やんでいます。実はローンでの購入も提案されたのですが、私は人生において一度も借金で何かを買ったことがなかったので、そのときには眼中にありませんでした。『ちゃんとお金を貯めて買いなさい』と子どもの頃からしつけられてきたんです(笑)。購入を決めた時点で、『借金とは資産である』という感覚が私の中にまだ備わっていませんでした」
現実に一歩前に踏み出してみたことで、不動産投資のプロが口にしていた言葉の真意を実感できたわけである。また、幸いというか、「類は友を呼ぶ」とでもいうか、杉原さんの周辺は投資家だらけとか。
「私のマネージャーさんは株をやっていますし、メイクさんでも1棟買いで不動産投資に取り組んでいる方もいます。1階に自分たちが住みながら2階から上を賃貸にしていて、リフォームの手配も自分で工務店を見つけて指図するほどです。こうして身近に実践している人がいると、怖いものではないと思えるから心強いですね」
(構成/大西洋平 写真/和田佳久 後半に続く)
「新築は1年も経つと半値とかまで下がっちゃうので怖いです。私の場合はせいぜい、築5年程度で十分かなと思っています。知り合いのテレビマンには新築投資の達人がいて、駅直結とかの人気分譲物件の抽選に毎月手当たり次第に応募しています。つねに自分で住む前提で買っているのですが、あまりに人気が高くて利益が出るのですぐに売却し、また新たな物件に応募するというパターンを繰り返しているようです」
ワンルームや1Kのような単身者向けのマンションを選択したことが自分にとって本当に正解だったのか、本当は区分所有ではなく、アパートでもいいから1棟買いしたほうがよかったのかなど、不動産投資に関する勉強を始めたばかりの杉原さんの胸中には、様々な迷いや疑問もある。
「とにかく、自分が住んでも大丈夫だと思うものを選びました。それ以外の選び方をまだ私は理解できていないわけです。購入してからまだ1年少々しか経ってないので、節税対策やその効果のこともよくわかっていません」
それでもまずは買ってみたことをまったく後悔していないが、唯一、早計だったと痛感していることがあるという。
「キャッシュで一括購入してしまったことはちょっと失敗でしたね。家賃が毎月入ってくるのはうれしいのですが、単に購入に充てたお金が戻ってくるような感覚で、ローンを組んだほうが投資効率もよかったと悔やんでいます。実はローンでの購入も提案されたのですが、私は人生において一度も借金で何かを買ったことがなかったので、そのときには眼中にありませんでした。『ちゃんとお金を貯めて買いなさい』と子どもの頃からしつけられてきたんです(笑)。購入を決めた時点で、『借金とは資産である』という感覚が私の中にまだ備わっていませんでした」
現実に一歩前に踏み出してみたことで、不動産投資のプロが口にしていた言葉の真意を実感できたわけである。また、幸いというか、「類は友を呼ぶ」とでもいうか、杉原さんの周辺は投資家だらけとか。
「私のマネージャーさんは株をやっていますし、メイクさんでも1棟買いで不動産投資に取り組んでいる方もいます。1階に自分たちが住みながら2階から上を賃貸にしていて、リフォームの手配も自分で工務店を見つけて指図するほどです。こうして身近に実践している人がいると、怖いものではないと思えるから心強いですね」
(構成/大西洋平 写真/和田佳久 後半に続く)
再建築不可物件投資がアツいと言われる理由、なぜ訳あり物件なのに魅力的なのか
投資目的で格安の不動産物件を探していると、「再建築不可」という注意書きを見つけることがあります。再建築不可とは文字通り、そこにある建物を取り壊して建物を新築することも、すでに更地になっている場合でも新たに建物を建てられない土地のことです。
いわゆる「訳あり物件」なのですが、この再建築不可物件に熱い視線を注いでいる不動産投資家は少なくありません。
再建築ができないのに、なぜ多くの不動産投資家が再建築不可物件に注目するのでしょうか。再建築不可物件に投資するメリットや、その一方で知っておくべきデメリットやリスク、再建築不可物件投資における主な成功パターンについて解説したいと思います。
再建築不可物件とは?

(画像=beeboys/Shutterstock.com)
再建築不可物件とは、そこに建物を新築できない不動産物件のことです。再建築不可になっている理由は、接道義務という要件を満たしていないからです。
接道義務は建築基準法に規定されているもので、その土地が面している道路の幅や道路に接する長さなどが定められています。以下のいずれかに該当する土地は、再建築不可となります。
・建築基準法上の道路に2メートル以上接していない
・接している道路が建築基準法上の道路要件を満たしていない
・そもそも道路に接していない
・接している道路が建築基準法上の道路要件を満たしていない
・そもそも道路に接していない
「建築基準法上の道路」とは、原則として幅が4メートル以上ある公道を指します。
この要件を満たしていない土地は災害時などに避難路を確保しにくく、また消防車や救急車などが入れないため救助が困難であるという理由で、再建築不可となっているのです。
再建築不可物件投資のメリット
再建築不可物件に投資するメリットは、以下のとおりです。
・物件価格が総じて安い
・古い家を好む人には魅力的な物件がある
・周辺も再建築不可である可能性が高く、街並みや景観が保持される可能性が高い
・古い家を好む人には魅力的な物件がある
・周辺も再建築不可である可能性が高く、街並みや景観が保持される可能性が高い
物件価格が安いことに注目しがちですが、それ以外にも再建築不可であるがゆえのメリットもあるのです。
再建築不可物件投資のデメリット、リスク
再建築不可物件に投資するデメリットやリスクについても挙げておきましょう。
・再建築不可なので既存の建物が使用不能になっても建て替えられない
・更地にしても活用法が限られる
・災害など不可抗力で建物が損傷しても建て替えられない
・更地にしても活用法が限られる
・災害など不可抗力で建物が損傷しても建て替えられない
特に、所有者の事情や意向に関係なく建物を失う可能性があることに留意しておくべきでしょう。
再建築不可物件投資で考えられる4つの成功パターン
再建築不可物件投資での成功パターンは、主に4つあります。
①安く仕入れてキャッシュフローを多めに確保する
②隣地を購入して接道義務を満たす
③隣地オーナーに有利な条件で売却する
④更地にして駐車場、資材置き場として活用する
②隣地を購入して接道義務を満たす
③隣地オーナーに有利な条件で売却する
④更地にして駐車場、資材置き場として活用する
①は再建築不可のまま賃貸経営をするという考え方です。既存の建物がまだ使えるのであれば、リノベーションによって再生してもいいですし、古い建物を好む人に入居してもらうことも考えられます。
②と③については、どちらも目的は同じです。隣地オーナーが土地を手放そうとしているのであれば、購入して接道義務を満たし、新築できるようにすることができます。隣地オーナーが接道義務を果たす目的でその土地を買いたいと言ってきた場合は、特別な価値を持つ土地だけに有利な価格で売却できる可能性があります。
④は建物を新築しない活用法ですが、再建築不可になっているだけあって接している道路が細い、あるいは接道幅が狭いといった問題がつきまとうため、車の出入りが問題なくできるかどうかを調査する必要があります。
再建築不可物件は価格的には有利だが、不動産投資に慣れた上級者向け
再建築不可であることは大きな制約なので、その分物件価格は安くなります。また、再建築不可なので建物が新しくないため、建物の築年数が古いと価格はさらに下がります。
しかし、再建築不可であっても建物がまだ十分使える場合や、将来再建築不可でなくなる可能性がある物件など、条件によってはお値打ちなものもあるため、再建築不可物件に注目している不動産投資家もいます。
再建築不可物件は、さまざまな状況や条件を鑑みて購入する必要があります。難しい分野と言えますが、魅力的な物件があればプロに相談しつつ、購入するかどうか熟考するとよいでしょう。 (提供:アセットONLINE)
【不動産投資本】バビロンの大富豪に学ぶ「お金」と「幸せ」の黄金法則
本書『漫画バビロン 大富豪の教え』は約100年前に書かれた世界的ベストセラー『バビロンの大富豪』(ジョージ・S・クレイソン著)に現代風のアレンジを加え、マンガ化したもの。
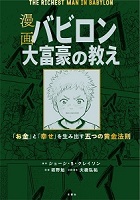 必死で働いても苦しい生活から抜けだせずにいる主人公が、師匠の教えに従い富と幸運を手に入れる物語を通じ、読者に「お金持ちになる基本法則」を伝授する内容だ。
必死で働いても苦しい生活から抜けだせずにいる主人公が、師匠の教えに従い富と幸運を手に入れる物語を通じ、読者に「お金持ちになる基本法則」を伝授する内容だ。
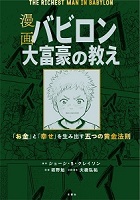 必死で働いても苦しい生活から抜けだせずにいる主人公が、師匠の教えに従い富と幸運を手に入れる物語を通じ、読者に「お金持ちになる基本法則」を伝授する内容だ。
必死で働いても苦しい生活から抜けだせずにいる主人公が、師匠の教えに従い富と幸運を手に入れる物語を通じ、読者に「お金持ちになる基本法則」を伝授する内容だ。
その根幹ともいえるのが、バビロン一の大富豪アルカドが説く「5つの黄金法則」。種銭を作る方法、小さなお金を大きく育てる方法、そしてお金を守る方法と、資産を増やすために「やらなければいけないこと」、「やってはダメなこと」を教えくれる。
法則は言葉として見ればシンプルであるが、鋭い。お金を稼ぎたいと願い、実際に行動した読者にこそ、深く付き刺さるはずだ。
例えば、確実に増やすから出資しろという相手にお金を渡して無一文になったり、必死で働いて得たお金をビジネスパートナーに使い込まれたりと、主人公は多くの人々が経験する様々な金銭トラブルを経験する。
そうして、失敗したときはいつも、バビロンの大富豪の示した「5つの黄金法則」から外れていたことに気づくのだ。この主人公に自分の失敗を重ね、「もっと早く、黄金法則を知りたかった」と感じる読者も多いだろう。
この他にも、「お金を奪われないコツ」「お金に愛されるコツ」等が豊富なその内容は、初心者よりもむしろ、ある程度の資産を築いた人、例えば不動産投資で一定の成果を上げ、さらに上のステージを目指す人たちに、より響く内容かもしれない。
また、登場人物は、「金持ちの家に生まれたにもかかわらず、お金へのだらしなさから奴隷になった者」「金持ちの家に生まれ、生きる楽しみや働くことの意味がわからない者」「一度は奴隷の身分に落ちたものの、お金に関する考え方を変えて再び自由を得た者」など様々。
決して、貧乏から右肩上がりを目指す人ばかりではない。そうした「一度はお金を手にした者」が反面教師として、読者に伝えてくれるものも大きい。
バビロンの大富豪は、主人公の少年に「お金持ち」の定義を尋ね、「お金をたくさん持っている人!」と答えた少年にこう告げた。「お金をたくさん持っているのがお金持ちなのではない。お金持ちというのは、お金の増やし方を知っている人だ」。
本書が100年もの間、版を重ね、いまなお注目されているのは、本書が時代や国を問わない金言に満ちているからだろう。
450ページを超える大作だが、ほとんどがマンガで、子供でも読める。ちなみに、原作はロバート・キヨサキ著『金持ち父さん貧乏父さん』でも、おすすめの書籍として紹介されている。
人生には、「どちらの道を選ぶべきか」「この人を信じていいのか」等、迷う場面が何度も訪れる。そんな時、本書が北極星のように、自分の今いる場所、そして進むべき道を示してくれるかもしれない。
不動産投資を続ける為に理解しておきたい税金とは?
不動産投資をする上で、必ず関わってくる項目として税金があります。
税金と一言でいっても、不動産を取得する際、不動産を保有している期間、不動産を売却する際など、様々な場面で異なる税金が関係してきます。
不動産投資をする事によって、節税に繋がる事もありますし、きちんと理解しておかなくてはならないといえるでしょう。
今回は、不動産投資を検討するにあたって、理解しておくべき税金について解説していきます。
不動産投資において理解しておきたい3つの税金とは?

(画像=FrameRatio/Shutterstock.com)
不動産に関わる税金は数多くありますが、今回は3つに絞ってお伝えしていきます。
固定資産税、所得税、相続税について、それぞれ細かく確認していきます。
固定資産税、所得税、相続税について、それぞれ細かく確認していきます。
毎年課税される固定資産税とは?
不動産を保有しているという事は、資産を保有しているという事になります。その為、固定資産税は不動産を保有している期間は、毎年課税される税金になります。
入居者のいる、いないとは関係なく発生しますし、毎年の収支が赤字であったとしても、きっちり既定の固定資産税が課税されます。その為、家賃が減少したり、空室期間が続いてしまったりすると、その分、負担が大きくなりますので、固定資産税に関しては購入前にきちんと計算した上で支払い計画をたてる必要があります。
所得によって税率が大きく変わる所得税とは?
不動産投資によって所得が増えるほど、気になってくるのが所得税になります。個人で不動産投資を行っている場合、個人の収入、つまり所得に対して所得税が課せられます。
日本の所得税は、所得によって5%から、最大で45%の税率が課せられるという事もあり、いくらの所得に対して、どれだけの税金が必要かはきちんと把握しておく必要があります。
逆に不動産投資によって赤字が計上された場合や、経費が多くかかる場合などは、税金も減る事になりますので、詳しく理解できているかによって、納める税金が変わるという事になりますから、きちんと勉強しておく税金の1つと言えるでしょう。
将来を見据えて理解しておくべき相続税とは?
現金を相続するよりも、不動産として保有しておいた方が相続税が低くなるという事を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
相続税はすべての財産から基礎控除額を引いて、相続税率をかける事で算出されます。その為、現金であれば、そのまま相続税の計算をする必要がありますが、土地や建物として資産を保有する事によって相続税が下がる場合があります。
例えば、建物の場合、固定資産税の評価額が基準になりますので、建築費用に比べて割安になる場合が多いです。また、賃貸として利用している場合、さらに控除されます。
これだけでも、現金で保有しているより、不動産として保有しておく方がメリットといえるでしょう。
自分自身が相続対策で不動産を保有するつもりがなかったとしても、不動産を買いたい、売りたい理由に、相続が関係してくるケースも多いです。
その為、不動産投資をするにあたって、理解しておきたい税金といえるでしょう。
不動産投資をするなら、税金とはうまく付き合っていこう
税金と聞くと、ネガティブなイメージを持つ方も多いかもしれませんが、きちんと理解していく事で節税できる部分もありますし、きちんと納税していく。つまり、利益をあげていくことで、銀行融資に有利になる事もあります。
大切なのは、税金だからと毛嫌いせずに、理解して、支払うべきものは支払い、支払う必要がない部分に関してはきちんと対策をたてる。
税金とうまく付き合っていく事によって、不動産投資において、より大きな成果を得られるできるでしょう。(提供:YANUSY)
他の収益物件にはない、新築ワンルームマンション経営ならではの5つのメリットは?
ひと口に不動産投資といっても「新築アパート一棟もの」「中古区分マンション」「中古戸建て」「商業ビル」などさまざまなスタイルがあります。そのなかでも新築ワンルームマンション経営にはどんなメリットがあるのでしょうか。本記事では新築ワンルームマンション経営ならではの5つのメリットについて解説します。
1新築ワンルームマンションは客付けがしやすい

(写真=Solis Images/Shutterstock.com)
新築ワンルームマンション経営の大きなメリットは何といっても「客付けがしやすいこと」です。日本では古くから「新築信仰」が根強い一面があります。たしかに新しい建物や設備で生活をスタートするのは誰にとっても気持ちのいいものです。建築の技術は日々進化しているのでセキュリティや防音、耐震性などの性能面も中古物件よりも新築のほうが向上しているというメリットもあるでしょう。
そのため部屋を探している人のなかには、新築に限定して探している人もかなりいます。新築ワンルームマンションでは、建物が完成する数カ月前から入居者の募集を開始することもあり、すぐに契約が決まってしまうことも少なくありません。また新築時の入居者が数年後に退去した場合も、まだ築浅物件として高い人気を維持できる点もオーナーにとっては魅力です。

(写真=Solis Images/Shutterstock.com)
2設備が新しいため、しばらくは大きな修繕がない
不動産投資における大きなコストの一つが修繕費です。区分マンションの場合は、共用部の修繕費は管理組合に納める修繕積立金によってまかなわれます。しかし専有部の修繕費はそれぞれの区分所有者持ちです。専有部の修繕費としては、退去時の原状回復費用や設備が故障した際の修理費などが想定され中古物件の場合はこれらの修繕費がかさみます。
特にキッチンやお風呂、給湯器などの設備が壊れたりリフォームしたりすれば、費用負担は10万~200万円程度です。新築物件であれば完成から数年は老朽化の心配をする必要はありません。退去が発生したときの原状回復もフローリングの張り替えなど多額の費用がかかる工事は発生しにくいため、場合によってはクリーニングだけで次に人に貸せることもあります。
3建物としての寿命が長い
設備だけでなく建物の寿命が長いことも新築マンションのメリットの一つです。RC造の建物の法定耐用年数は47年ですが、これは使える期間が47年ということではありません。法定耐用年数は税法上減価償却の計算をするうえで使用する年数のため、実際は法定耐用年数よりも長期にわたって利用できることが一般的です。
コンクリートの寿命は100年以上という説もあります。実際にどれくらいの期間使えるかは、新築後のメンテナンス次第です。区分マンションの場合は管理組合が主体となって定期的な大規模修繕工事を行いますが、これをスケジュール通りにきちんと実施すれば長い寿命を確保できます。
4金融機関の融資が通りやすい
客付けがしやすくしばらくは大きな修繕が発生しにくいため、収益物件のなかでも手堅い運営ができるのが新築ワンルームマンションの特徴です。また投資額も比較的低い傾向でリスクが限定されているため、金融機関からの評価も高く融資審査に比較的通りやすいというメリットがあります。場合によっては自己資金を投入しないフルローンを組むことも可能です。
借入期間は金融機関によって異なりますが一般的には35年、なかには最大45年の長期ローンを組める場合もあります。ローンは短期よりも長期で組んだほうが毎月の返済負担は少なくできることがメリットです。返済負担が少なければ、手元キャッシュフローが良化して資金繰りは改善することが期待できるでしょう。
ただし同じ金利の場合、長期になればなるほど総支払額はアップしてしまうことは念頭に置いておく必要があります。
5いざとなったら売りやすい
区分所有ワンルームマンションは他の収益物件と比べても人気の投資スタイルなので市場において活発な取引が行われています。したがって「売却したい」となったときも比較的早く現金化することが可能です。この流動性の高さもメリットの一つです。ただし流動性は高くても購入時の価格を大きく割り込む可能性があるため、フルローンで資金調達している場合は売却時の残債を下回る可能性があります。
新築ワンルームマンションのメリットを押さえて将来の戦略を描こう
新築ワンルームマンションにはさまざまなメリットがあります。そのため長期にわたる戦略を描きやすいというのが大きな特徴です。不動産投資の未経験者が第一歩を踏み出すにはリスクが低めのスタイルといえるのではないでしょうか。メリットだけでなくデメリットも踏まえたうえで新築ワンルームマンション経営を検討してみましょう。(提供:Dear Reicious Online)
より堅実な投資を!不動産投資はアパートよりマンションがオススメの理由
年金をはじめとする社会保障制度への不信感が高まるにつれて、日本においても、「自分のことは自分で守る」という意識が高まっています。事実、若いうちから投資をはじめる人が増えており、各金融機関においても、そうした人々を対象とした金融商品やサービスを拡充。さらには金融リテラシーを高めるための書籍や講座、セミナーなども展開されています。
そのうち、安定資産の形成に寄与する投資手法として注目されているのが、不動産投資です。不動産投資は、中長期的な資産形成を行うのに最適であり、かつ、特殊な技能が求められることもありません。そのため、会社員の方を中心に積極的に取り組む人が増えています。では、より堅実な投資を実現するために、どのような点に注意しておけばいいのでしょうか。
不動産投資における「マンション」と「アパート」

(写真=Song_about_summer/Shutterstock.com)
不動産投資において最大のポイントとなるのは、融資に伴うローン返済と、ローン返済の原資となる家賃収入のバランスです。すぐに売却を考えている場合を除き、多くの不動産投資は入居者から得られる家賃収入がベースとなります。そのため、いかに安定的に入居者を獲得できるかが、不動産投資全体の成否を左右することにつながります。
その点において、あらかじめ検討しておきたいのが「マンション」と「アパート」の違いです。どちらも投資物件として活用されてきた過去があるものの、とくにこれからは、マンションを中心に投資を検討したほうがいいかもしれません。事実、空いた土地にアパートを建てるといった手法は、地方の過疎化や少子化によって、採算が合わなくなりつつあります。
投資対象としてのマンションの優位性とは

(写真=yampi/Shutterstock.com)
集合住宅への投資という意味で似通っているマンションとアパートの違いについて、あらためて確認しておきましょう。とくに重要なのは、すでに述べているようなアパートが直面している厳しい現状です。加えて、マクロおよびミクロの視点から、マンションに投資することがどのような優位性をもたらすのか、それぞれのポイントを押さえておきましょう。
厳しいアパート経営の現状
日本経済を俯瞰すると、少子化に伴う人口減少は避けられない状況にあり、それに付随する形で地方の過疎化が進んでいます。そのことは、戸建て住宅を中心に広がっている「空き家問題」にも表れており、集合住宅としてのアパート需要にも影響が生じているのが実情です。事実、アパートを建てて経営する投資スキームは、採算性からも厳しい状況が続いています。
資産としての価値の推移
では、資産価値の推移としてはどうでしょうか。経年劣化が伴うアパートの資産価値は、その大半が土地値によって左右されます。ただ、入居者を安定的に獲得できる好立地の物件は限られており、人口が減少している実情をふまえると、中長期的な資産価値の維持も難しいと考えられます。その点においても、これからのアパート経営は厳しいのです。
マンションならより安定的な資産形成ができる
一方でマンションなら、管理組合が主導する修繕積立金の積立や大規模修繕など、将来を見越した価値の維持が計画されています。管理会社による適切な管理運営によって、入居者を獲得することも可能です。資産価値という点で考えても、マンションの価値は緩やかに下落する傾向にあり、また流動性が高いことから、柔軟な資金計画を立てることもできます。
長い目で投資適格性を判断しよう
このように集合住宅を活用した不動産投資は、大きくマンションへの投資とアパートへの投資に分かれます。これまではアパート(木造)に投資する投資家も多かったのですが、今後の不動産市場を見るにつけ、マンションのほうがより堅実的な投資を実現できる可能性があると言えるかもしれません。それぞれの特徴をふまえ、慎重に判断していきましょう。(提供:Braight Lab)
不動産投資の節税メリットに欠かせない「減価償却・耐用年数・損益通算」をわかりやすく
不動産投資をはじめるには、「税金の基本を理解していること」がマストです。そのために外せない3つのキーワードが「減価償却・耐用年数・損益通算」。これらについてはネット上で数多くの解説がされていますが、難しい内容がほとんどです。ここではわかりやすさを重視して解説していきます。
「減価償却」の理解度で不動産投資の見え方は大きく変わる

(写真=Nata-Lia/Shutterstock.com)
まずは「減価償却」についてです。これはすべての不動産投資家に欠かせない知識ですが、特に新築マンションを経営する人にとって重要です。新築マンションの場合、毎月の収支(賃料-運営コスト)がマイナスになるケースがあります。特に東京都心の好立地の新築マンションをローン中心で買う場合は、赤字経営になるケースが多いでしょう。
そのため減価償却を理解していないと「赤字経営なのに不動産投資をする意味あるの?」といったことになりかねません。逆に減価償却をしっかりと理解していると、「毎月の収支は赤字だけどメリットはある」といった180度違う見方ができます。
「減価償却」とは、高額な資産の出費を毎年少しずつ経費にするルール
減価償却とは、高額な資産を購入したときに毎年少しずつ経費化していくことです。例えば会社で社用車を買ったときで考えてみましょう。もし減価償却という仕組みがなかったら、社用車を数年に渡り使用するにもかかわらず、買った年にまとめて経費にすることになります。たくさん利益が出た年(法人であればその期)に社用車を買ったのであれば、社用車の経費で利益を圧縮できその分、税金が安くなるため大きなメリットです。
しかし利益が少ない年や赤字の年に購入した場合、まとめて費用として計上すると「社用車を買ったせいで赤字に転落」「赤字額が増加」ということになりかねません。こういったアンバランスなことが起きないよう、資産が使える期間の目安に合わせて毎年少しずつ経費化していく必要があるのです。
「耐用年数」とは、それぞれの資産が使える期間の目安
この資産が使える期間の目安は「耐用年数」と呼ばれ、耐用年数はそれぞれの資産によって国税庁が細かく設定しています。例えば不動産であればマンションでよく使われる鉄筋コンクリートの建物の耐用年数は47年、アパートや戸建てなどで採用される木造の建物は22年です。(※)このほかレンガ造、金属造など建物構造で耐用年数は変わってきます。
※いずれも建物の用途が住宅(賃貸経営も含む)の場合
ちなみに土地は減価償却(経費化)できません。なぜなら土地は10年使おうが、100年使おうが傷まないからです。また先ほど挙げた鉄筋コンクリート47年、木造22年という耐用年数は建物に限ったもので、建物内の住宅設備は期間が異なります。例えば照明を含む電気設備、給排水設備、ガス設備などの耐用年数は15年です。
「損益通算」は給与所得と不動産所得を相殺してよいルール
不動産投資をすると減価償却があるので、毎年確定申告時に経費として計上することになります。利益がたくさん出たときに減価償却を行えば利益が圧縮されるため、所得税などが少なくなります。またギリギリ黒字であれば減価償却で赤字になり所得税がかかりません。さらにもともと赤字であれば、当然ながら赤字幅が大きくなります。
損益通算は、ビジネスパーソンが不動産投資をする場合、確定申告では給与所得と不動産所得を相殺してよいというルールです。先の例をあてはめれば、黒字になった場合は所得税も増えますが、黒字分は減価償却で減った分に限定されます。赤字の場合は、その分給与所得が圧縮でき、所得税が減るため、還付金として戻ってくるのが魅力です。
ただし損益通算があるからといって赤字額を膨らませすぎると、節税額を実際の出費が大きく上回ることもあります。そうならないよう節税効果とキャッシュフローをバランスよくコントロールしながら不動産投資をすることが大切です。(提供:アセットONLINE)
東京の不動産投資…「都心」か「郊外」か、どちらにすべきか?
都心と郊外の「境目」はどこにあるのか?
東京をはじめとする首都圏は、不動産投資の対象エリアとして高い注目を集めています。しかし、ひとくちに東京といっても、23区内もあれば、東京都西部の三鷹や立川などの郊外もあります。また、首都圏といった場合、定義はさまざまですが、埼玉県のさいたま市大宮区や神奈川県の横浜市を含む場合もあり、かなり広域にわたることもあります。
結局、不動産投資ではどの対象エリアに投資するかが決め手になりますが、その際、大きく分けて都心と郊外のどちらのエリアにある物件を選ぶのかが重要になります。
そもそも都心とは「大都会の中心部」で、郊外は「都市に隣接した地域」という意味ですが、その境界が厳密に引かれているわけではありません。いわゆる都心6区と呼ばれるのは、千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区・文京区です。
しかし、荻窪がある杉並区や、二子玉川がある世田谷区を「郊外だ」と言われても、なかなかピンとこない人が多いのではないでしょうか。不動産投資の対象エリアとしては、「23区」と「それ以外」というような分け方が合理的かもしれません。
マンションと戸建てのどちらが多く供給されているかによって地域の特性が変わり、マンション中心のエリアを「都心」、戸建て中心のエリアを「郊外」と分ける場合もあります。
ある経済誌の記事によると、皇居を中心に25キロメートル圏内、または都心6区内の主要駅から急行などに乗って30分前後のエリアは、戸建てよりもマンションの供給が盛んで、都心として扱われることが多いエリアだと位置づけていました。

高層ビルが建ち並ぶ、東京の都心部

東京とはいえ、郊外は緑豊かな住宅地も
都心か郊外か…それぞれのメリット&デメリット
都心物件に投資するメリットは、空室率の低さと客付けのしやすさだといえます。不動産市場調査会社のタス株式会社が2019年7月に発表した「賃貸住宅市場レポート」によれば、2019年5月の空室率は23区内が12.92%、市部が14.89%と、都心の空室率の方が低い傾向にあります。ちなみに、主要な首都圏の空室率は、神奈川県が16.40%・埼玉県が16.31%・千葉県が16.76%となっています。
空室の発生は、不動産投資の最大のリスクです。空室が続き、ローンの返済に行き詰まると、場合によっては物件を手放さなければならなくなります。しかも、空室が続く物件は買い手を見つけるのが難しく、購入時よりも大きく値下がりすることが予想されます。
不動産投資では、出口戦略として売却のしやすさも重要です。その点でも、郊外より都心は有利だと言えます。都心物件の場合、不動産価格における土地の割合が大きくなり、都心部は数年から数十年先の売却のタイミングでも、地価は安定的に推移していると予想されます。
東京都が発表している「東京都区市町村別人口の予測」によれば、区部は2015年時点では927万人ですが、2030年には979万人に増加する見込みです。一方、市部は2015年時点では424万人ですが、2030年には415万人に減少する見込みです。
上記のような都心の地価の方が安定する傾向は、今後も続く可能性が高いでしょう。そのため、都心の不動産に対する投資家からの注目度はさらに高まり、購入価格も上がるため、利回りは低くなりがちです。
一方、郊外の物件は価格の安さがメリットであり、客付けに成功すれば、かなりの利回りが見込めます。価格が安いため、ローンも含めて用意できる資金が少ない人でも投資が可能です。資金力のある人は、複数の物件を購入してリスクヘッジしたり、グレードの高い物件を購入したりすることができます。不動産の投資戦略の幅も広がるでしょう。
しかし都心と比較すると、郊外は空室率が高いエリアも多く、将来、売却を希望した際に難航してしまう可能性があります。ただし郊外でも、地域によってかなりの差があります。都心へのアクセスが良い人気のあるエリアは空室率が低い上に客付けがしやすく、人口が増加しています。また近くに大学や大きな工場などがある場合は、郊外でも十分な需要が見込めます。
不動産投資初心者なら、都心の物件が安心だが……
一般的に、都心の物件はローリスク・ローリターン、郊外の物件はハイリスク・ハイリターンという傾向があります。あなたが不動産投資の初心者であれば、都心の物件を選ぶ方が安心かもしれません。
ただし、投資経験が豊富だったり、時間に余裕があったり、また物件のリサーチや自力での修繕などにも十分に時間を注げたりする人は、郊外の物件に投資することも悪くありません。郊外が自身の出身地や勤務先である場合、現在住居を構えていて土地勘がある場合であれば、なおさら成功する可能性は高くなります。こういった諸条件を総合的に判断して、自分に合った投資物件を見つけてみてください。
東京をはじめとする首都圏は、不動産投資の対象エリアとして高い注目を集めています。しかし、ひとくちに東京といっても、23区内もあれば、東京都西部の三鷹や立川などの郊外もあります。また、首都圏といった場合、定義はさまざまですが、埼玉県のさいたま市大宮区や神奈川県の横浜市を含む場合もあり、かなり広域にわたることもあります。
結局、不動産投資ではどの対象エリアに投資するかが決め手になりますが、その際、大きく分けて都心と郊外のどちらのエリアにある物件を選ぶのかが重要になります。
資産形成で不動産投資のメリットをもう一度確認したい
東京五輪で頂点へ…2020年「不動産バブル」は弾けるのか?
どれがいい?ワンルーム投資セミナーを目的別に使い分けるコツ
ワンルームマンションの投資セミナーでは専門家の話を聞くことができる上に、個別に質問をしてアドバイスを受けることができる点で、本やインターネットの情報では得られないメリットがあります。
しかし、自分の投資スタイルと合わないセミナーに参加しても、期待していた情報を得られない可能性がありますので、セミナーを選ぶ際は主催企業の概要やセミナーの内容をきちんと調べた上で参加することが大切です。
今回はワンルーム投資セミナーを開催する不動産会社の様々な特徴を確認した上で、投資目的別にどういったセミナーが合っているかについてご紹介したいと思います。
目次
1.不動産会社によって特徴が異なる
ワンルーム投資とは、ワンルームマンションを購入し賃貸経営をすることを言います。ワンルームは不動産会社から購入しますが、会社によって取り扱う物件が新築か中古なのかといった点や注力するエリアが違い、それぞれ得意とする分野や苦手な分野があります。
セミナーでは主催する不動産会社が自社の得意分野で運用の仕方をレクチャーするケースが多いので、セミナーに参加する際はセミナーのテーマや会社の特徴を知ってから参加することが大切です。
例えば頭金10万円で投資ができるスキームを持つ不動産会社は、初期費用をあまりかけずに投資ができる点を紹介したり、多くの金融機関と提携している会社なら金利の低さやローンを組む際のメリットを訴求したりすることが考えられます。
その場合、頭金を多く入れて借入額を減らしたい方や、借入をせず現金のみで購入したい方は、そのようなセミナーに参加してもメリットを感じない可能性があります。
このようにセミナーを開催している不動産会社の強みや弱みによって、セミナーの内容がそれに合わせた内容になる傾向がありますので、セミナーに参加する際は自分の投資スタイルに合っているかの確認をすることが大切です。
ここでは、不動産会社によって、どのような特徴があるのかを見てみたいと思います。
1-1.新築か中古かでノウハウが違う
新築と中古のどちらを販売しているかで、その不動産会社が持つノウハウは違います。例えば、一般的にワンルーム投資を行う際は金融機関から融資を受けますが、金融機関が融資をする際の金利や返済期間、融資額などが新築と中古では異なります。そのため不動産会社が行う手続きも異なることがある上、うまく融資を引き出すための交渉の仕方も変わります。
また、物件を仕入れる方法に関しても、新築物件の場合は自社で土地の仕入れから販売までを全て行う会社もありますが、中古の場合は仲介での取り扱いが多くなります。
このように、新築と中古では多くの点で不動産会社に必要となるノウハウが違います。両方を取り扱っている会社もありますが、新築と中古のどちらか一方しか取り扱っていない不動産会社もあります。
このようなことから、新築物件を主に取り扱う不動産会社と中古を主に取り扱う不動産会社が行うセミナーの内容には違いが出てくると言えます。
1-2.リノベーションをする場合としない場合がある
同じ中古のワンルーム投資でも、自社でリノベーションをしてから販売する会社と、リノベーションはせずに仲介だけをする会社があります。リノベーションをした場合は、しない場合と比較して価格帯が高くなります。そのため一般的な中古ワンルーム投資と比較すると利回りは低くなります。
一方、リノベーションによって採光が広がったり、最新式の設備や内装になったりするケースもあり、高級感や快適性が増すことで家賃を高く設定できたり、売却の際にも高く売却できたりする可能性があります。
1-3.都心のみで事業展開をする不動産会社
都心には人口が集中し、家賃も高く設定できますので、都心に建設された物件であれば長期的に投資メリットが得られる可能性が高くなります。しかし、都心にはマンションを建てる場所が少なくなっていますし、建設できたとしても新築では物件価格が高くなる可能性もあります。
一方、都心にはすでに建設されている中古物件も数多くありますので、物件価格の面で新築は難しいという場合でも中古物件を狙うことで都心にもマンションを所有しやすくなります。不動産会社の中には都心のみに自社物件を持ち、中古物件を流通させている会社もありますので、都心の物件を購入したい場合はそのような会社が開催するセミナーに参加することで、都心の物件を運用するノウハウを得ることができます。
1-4.金融機関の特約などが違う
不動産会社の中には多くの金融機関と提携し、関係を太くして良い条件を提供できる会社も少なくありません。そのような不動産会社でワンルームを購入する場合、頭金が10万円で済んだり、フルローンが組めたり、他の金融機関より低い金利でローンが組めたりするなどのメリットがあります。
そのような不動産会社の融資上の強みを効果的に利用するためには、セミナーに参加する前に、物件を購入する際に初期費用をかけたくないのか、あるいは頭金を多く支払ってもローン金額を少なくしたいのかといった、自分が準備できる頭金の額や毎月の返済できる額など、目安となる借入条件を決めておく必要があります。
2.投資目的に合わせたワンルーム投資セミナーの選び方
不動産会社によって取り扱っている物件のタイプや、物件があるエリア、金融機関の条件などの特徴があることがわかりました。投資をする目的によって、どのようなセミナーに参加すれば良いのかを見てみましょう。
2-1.長期間保有してキャッシュフローを増やしたい場合
キャッシュフローとはお金の流れのことで、例えば家賃収入から諸経費を支払った後にいくら手元にお金が残るのかを表すような指標です。ワンルームを長期間保有してキャッシュフローを増やすには、なるべく高い家賃で貸す、入居率を維持する、毎月の家賃収入から支払うローンの返済額を抑える、といったことが大切です。
返済額を抑えるには金利を低く、できるだけ長い返済期間でローンを組むことが必要になりますので、低い金利でローンを組んだ実績がある会社や、節税対策の仕方などを積極的に提案する会社が行うセミナーに参加することが一つの方法になります。
中古ワンルームで低金利・長期での融資実績がある不動産会社のセミナー情報
2-3.長期で安定した賃貸運用がしたい
新築ワンルームは中古に比べると利回りが低いのですが、当分の間は入居率が高くなる傾向にあるため、安定した運用が期待できます。入居率の実績を出している不動産会社もあるため、高い実績を持つ会社を選ぶのも有効です。
また中古でも資産価値が落ちにくい物件を探している場合は、リノベーションで投資価値を上げた物件を販売している会社がおすすめです。
入居率が99.5%以上の実績がある不動産会社のセミナー情報
2-4.都心や駅近など立地を最優先する場合
ワンルーム投資の成功には立地が大きく影響してきます。立地が良ければ、多少価格帯が高くて利回りがあまり良くなくても、長期的の資産価値の維持が期待できます。立地にこだわって物件を探したいという方は、都心や、都心ではなくても駅からの距離が近いエリアに建っている物件を中心に販売している不動産会社のセミナーに参加すると良いでしょう。
都心の物件や駅近物件を中心に販売している不動産会社のセミナー情報
2-5.会社の規模や信用などで判断したい場合
初めてワンルーム投資をする方の中には、大手の不動産会社と安心して取引をしたい、と考える方もいるでしょう。上場している不動産会社は豊富な資金力で、土地の仕入れから販売、管理まで幅広く事業を行っています。出口戦略を考える際もワンストップで購入から売却までのサポートをしてくれるため、初めての方にも安心です。
東証1部に上場している不動産会社が行うセミナー情報
まとめ
不動産会社の事業内容の特徴と、会社の特徴を活かしたセミナー情報についてご紹介しました。
不動産会社はそれぞれ独自のサービスを展開しています。ワンルームの投資セミナーでは、その会社の特徴を活かした投資法や、運用の仕方を知ることができます。そのため、セミナーに参加する際は、自分の目的に合ったサービスを展開している不動産会社のセミナーを選ぶことが、よりワンルーム投資への理解を深める方法になります。
セミナーに参加する際は事前に不動産会社の特徴を調べて、できるだけ自分の投資スタイルに合った不動産会社のセミナーに参加するようにしましょう。
不動産投資の家賃下落が怖い! リスクを最小限にとどめるポイント
不動産投資で失敗しないためには、将来の家賃下落を想定して返済計画を立てることが重要です。この家賃下落の予測が甘いままだと、見込んだ家賃収入が得られずに返済負担が大きくなるリスクがあります。そのポイントを解説していきます。
新築時には周辺相場より割高なプレミアム家賃を設定できる

(写真=PavelShynkarou/Shutterstock.com)
一般的な不動産投資では、新築時のプレミアム家賃の期間を経て、築年数が長くなるにつれて家賃が下落していきます。プレミアム家賃とは、新築時のみ、周辺相場よりも高い家賃を設定しても入居者が決まりやすいことを指します。相場よりもどれくらい高い設定にするかは、オーナーや管理会社の方針にもよりますが、「1〜2割程度ではないか」という目安が業界関係者の間では一般的となっています。

(写真=PavelShynkarou/Shutterstock.com)
築年数が1年長くなるごとに、家賃は平均1%下落する

(写真=fizkes/Shutterstock.com)
このプレミアム家賃の期間は、初めに契約した入居者が退去するまで続くことが一般的です。その後、築年数とともに家賃が下落していきます。具体的な家賃の下落率については、総務省が三井住友トラスト基礎研究所をヒアリングしたレポート内で、次のように解説しています。
どの地域においても、借家住宅の経年劣化による家賃の下落率は年率に換算すると1%程度だろうと、市場関係者の間では言われている。
引用:総務省統計局「借家家賃の経年変化」
この年率1%程度の家賃下落を織り込んで返済計画を立てなければ、現実とのギャップが大きくなります。例えば、家賃8万円の設定で、毎年1%前後の家賃下落が続くと、10年後の家賃は7万円台前半まで下がります。

(写真=fizkes/Shutterstock.com)
引用:総務省統計局「借家家賃の経年変化」
賃貸ニーズが好調なエリアでは家賃変動率がプラスになることも
ただし「家賃下落率=年率1%」というのは、あくまで全国的な平均値であり、例外もあります。賃貸ニーズが高いエリアでは、家賃下落率が低い(または下落が起きない、家賃相場が上がる)ケースもありますし、賃貸ニーズが低いエリアでは逆もあり得ます。
賃貸ニーズが高いエリアの例としては、沖縄県の一部地域があります。沖縄県では、リゾート開発が進む地域を中心に、家賃(1R〜1LDK)が次のような上昇傾向にあります。
・那覇新都心:24.7%上昇
・宮古島市:4%上昇
・石垣市:7.6%上昇
出典:おきぎん賃料動向ネットワーク調査(2018年)
※中古家賃44,900円を100%とした場合の変動率
また、2025年の大阪・関西万博やIR(カジノを含む統合リゾート)に沸く大阪では、エリア全体の賃料変動率がプラスで推移しています。
参照:日本不動産研究所「第12回 国際不動産価格賃料指数」(2019年4月現在)
このように賃貸ニーズが好調なエリアに絞り込んで投資をすれば、家賃下落を抑えながら展開していくことも可能になるでしょう。
・宮古島市:4%上昇
・石垣市:7.6%上昇
出典:おきぎん賃料動向ネットワーク調査(2018年)
※中古家賃44,900円を100%とした場合の変動率
参照:日本不動産研究所「第12回 国際不動産価格賃料指数」(2019年4月現在)
法人契約で相場よりも割高な家賃が設定できることも
もう一つの家賃下落に影響を与える要素は、「法人契約」です。社宅として賃貸物件を契約する場合、家賃を払うのは社員個人ではなく会社です。一般的に、個人契約よりも法人契約の方が家賃に甘い傾向にあるといわれています。
そのため、法人契約はプレミアム家賃期間が長く設定できる、あるいは相場よりも高めの家賃設定ができるといったケースも見られます。
特に現在のような人手不足の状況では、求人に目を留めてもらうために賃貸物件への法人ニーズが高まると考えられます。少々家賃が高くても、安定的に賃貸物件を確保したいと考える企業が増えてもおかしくありません。
こういった法人契約の背景を考えると、転勤族が多い地方の大都市や、人手不足が顕著な首都圏での不動産投資には有利な面があります。
不動産投資における「家賃下落リスク」の考え方
ここでお話ししてきたことをまとめると、次のようになります。
・新築時は相場よりも割高なプレミアム家賃を設定しやすい
・プレミアム家賃期間を過ぎると、平均年率1%家賃が下がる
・賃貸ニーズが好調なエリアでは家賃が下がりにくい
・法人契約では高めの家賃を設定しやすい
不動産投資では、家賃下落を返済計画に織り込むと同時に、家賃下落が起きにくいエリアを狙うことがポイントになってきます。(提供:Braight Lab)
・プレミアム家賃期間を過ぎると、平均年率1%家賃が下がる
・賃貸ニーズが好調なエリアでは家賃が下がりにくい
・法人契約では高めの家賃を設定しやすい
テナントがハウス・ハンティングでチェックする意外なポイント
理想のテナント(賃借人)に、長く幸せに住んで欲しい……家主共通の願いではないでしょうか。テナントがハウス・ハウティング(家探し)でチェックしている意外なポイントを把握し、必要に応じて改善することで、優良テナントにめぐり合うチャンスを増やしましょう。
理想的なテナントとは?

(画像=PR Image Factory/Shutterstock.com)
家主にとって理想的なテナントとは、テナントの義務である「賃料支払義務」「原状回復義務」「契約内容遵守義務」をしっかりと守ってくれる人でしょう。つまり期日通りに家賃を納め、物件を良好な状態で保ち、賃貸契約時の契約内容を守れるテナントです。また中長期間借りてくれるテナントは、一定したキャッシュフローをもたらしてくれるだけではありません。
テナント入れ替えの際のメンテナンス回数が少なくてすむというメリットがあります。不動産業者や管理会社にテナントの選択やメンテナンスを任せきりにするのではなく、積極的に参加する姿勢が大切です。
物件の魅力をアピールし、選択肢の幅を広げる
理想的なテナントを見つけるためには、できるだけ多くの入居希望者に物件の魅力をアピールし、選択肢の幅を広げることが必要です。物件を何週間もマーケットに出しているにも関わらず、内見の数が極端に少ないと、入居者の条件を気にする精神的あるいは経済的な余裕もなくなります。場合によっては、家賃の値下げなど家主にとって不利な交渉に応じる必要もでてくるでしょう。
逆に物件をマーケットに出してわずか数日で入居希望者が殺到すると、複数の候補者の中から納得のいく入居者を選ぶ余裕が生まれます。立地や築年数など改善できない点もありますが、改善できる点に惜しみなく投資することで、入居希望者にアピールする物件に生まれ変わるはずです。
ハウス・ハウティング、入居希望者がチェックする7つの隠れポイント
ハウス・ハウティングで入居者がチェックするのは、部屋の作りや間取り、日当たり、交通の便など、目に見える箇所だけではありません。「もし自分がここに住んでいたら」と入居者の立場に立って、住み心地の良い家に作り変えましょう。
1 部屋の匂い
人が生活している限り、部屋には「生活臭」がつくものです。例えば、「前入居者が室内で喫煙していた」「ペットを飼っていた」「換気を怠っていた」などの場合、内見前にプロの業者にハウスクリーニングを依頼するなど、徹底的に不快な臭気を排除しておきましょう。
人が生活している限り、部屋には「生活臭」がつくものです。例えば、「前入居者が室内で喫煙していた」「ペットを飼っていた」「換気を怠っていた」などの場合、内見前にプロの業者にハウスクリーニングを依頼するなど、徹底的に不快な臭気を排除しておきましょう。
2 ドア、窓の立てつけ
ドアや窓の立てつけが悪いと、「家主があまり物件の手入れをしていないのでは」という印象を与えてしまうかもしれません。また開け閉めの際、騒音の原因となります。スムースに開閉できるように建付けをチェックしておくと安心です。
ドアや窓の立てつけが悪いと、「家主があまり物件の手入れをしていないのでは」という印象を与えてしまうかもしれません。また開け閉めの際、騒音の原因となります。スムースに開閉できるように建付けをチェックしておくと安心です。
3 安全性・快適性
インターホンの設置やピッキングされにくいカギに交換するなど、セキュリティーの強化から、シャワーの水圧・温度調整まで、入居者が安全かつ快適に暮らせる環境作りを心掛けましょう。
インターホンの設置やピッキングされにくいカギに交換するなど、セキュリティーの強化から、シャワーの水圧・温度調整まで、入居者が安全かつ快適に暮らせる環境作りを心掛けましょう。
4 遮音性
騒音が気になる地域であれば「二重サッシに交換する」、隣接している部屋の生活音が気になるようであれば、「思い切って壁や床の防音工事に投資する」などを検討することが必要です。
騒音が気になる地域であれば「二重サッシに交換する」、隣接している部屋の生活音が気になるようであれば、「思い切って壁や床の防音工事に投資する」などを検討することが必要です。
5 住宅の傾き
住居の傾きは、頭痛や目まいなど健康被害の原因となります。たった0.3度の傾きでも症状が現れるケースもあるため、ピンポン玉などで傾き具合をチェックしてみましょう。傾きが確認された場合、住宅の基盤工事が必要です。
住居の傾きは、頭痛や目まいなど健康被害の原因となります。たった0.3度の傾きでも症状が現れるケースもあるため、ピンポン玉などで傾き具合をチェックしてみましょう。傾きが確認された場合、住宅の基盤工事が必要です。
6 湿気
水回りだけではなく、押し入れやクローゼット、下駄箱の中などもしっかりとチェックし、湿気を感じる場合は換気対策が必要です。ハウスダストやカビは、入居者の健康に害を及ぼすだけではなく、建物を傷める原因にもなります。
水回りだけではなく、押し入れやクローゼット、下駄箱の中などもしっかりとチェックし、湿気を感じる場合は換気対策が必要です。ハウスダストやカビは、入居者の健康に害を及ぼすだけではなく、建物を傷める原因にもなります。
7 コンセントの数・位置
実際に住んでみないと分からないのがコンセント問題です。電化製品を設置するとき、「数が不足していないか」「使いにくい位置に設置されていないか」について入居者の立場に立って見直してみましょう。増設工事の相場は5,000~3万円ほどです。
入居者に選ばれるために出来ることはいっぱいあります。まずは実施した方が良いと思う項目を一覧に書き出してみましょう。その中から最低限するべきこと、実施した方がよいこと、実施した方がよいけどコストが高いこと、など色分けしてみましょう。
実際に住んでみないと分からないのがコンセント問題です。電化製品を設置するとき、「数が不足していないか」「使いにくい位置に設置されていないか」について入居者の立場に立って見直してみましょう。増設工事の相場は5,000~3万円ほどです。
入居者に選ばれるために出来ることはいっぱいあります。まずは実施した方が良いと思う項目を一覧に書き出してみましょう。その中から最低限するべきこと、実施した方がよいこと、実施した方がよいけどコストが高いこと、など色分けしてみましょう。
そのうえで、問合せ数や内見状況に応じて、実施するべきこと、しないことを精査し、費用対効果のよい賃貸経営を目指しましょう。(提供:YANUSY)「海外不動産投資で節税」はおいしいのか?注意すべき3つのポイント
インターネットで海外の情報が簡単に入ってくるようになったこともあり、海外不動産への投資も人気が高まりつつあります。なかには「海外不動産で節税」を期待する投資家もいるようですが、日本国内への不動産投資とはまた違った注意をすることが必要です。そこで今回は海外の不動産へ投資する場合の3つの注意点について解説します。

「日本はダメだから海外不動産に投資」が増加

(写真=Sasin Paraksa/Shutterstock.com)
日本は、少子高齢化による経済衰退や累積債務超過による財政破綻が懸念されています。そんな日本特有のリスクを避けるため最初から海外不動産に目を向ける人も少なくありません。特にアジアやアメリカの不動産は経済成長や人口動向から人気が高まっている傾向です。海外不動産投資を扱う企業も頻繁に宣伝やセミナーを行っています。
ただ安易に「海外不動産なら安心」とばかりに投資をするのはおすすめできません。むしろ、より慎重になる必要があります。なぜなら海外は言語だけでなく文化や法律、税制などが日本と大きく異なるからです。「日本と事情が異なる」というのは投資のうえでは大きなリスクとなりえます。

(写真=Sasin Paraksa/Shutterstock.com)
「海外不動産で節税」、それホント?見るべき3つのポイント
特に注意したいのが「海外不動産で節税」という海外不動産の投資を促す宣伝文句です。「日本の不動産はダメだけど海外の不動産ならミラクルが起きて節税できる」という印象を持つ人もいることでしょう。この宣伝文句で海外不動産投資に心惹かれたなら、一歩踏み出す前に次の3つのポイントをきちんと吟味することが必要です。
ポイント1:利回りとローン金利
不動産投資においてまず見るべきなのは「利回り」です。多額の投資をして利回りが低ければ不労所得を得るどころか投資額を回収できず、お金を捨てることになります。そのため利回りの数字を意識すべきですが、「海外投資」という一言で冷静さを保てなくなる人も中にはいるでしょう。この利回りでいいかどうかを判断する基準の一つが「ローン金利とのバランス」です。
投資物件の中には、利回りとローン金利の差がほとんどないものもあります。実際に不動産投資を行うと、管理費などが別途かかります。つまりここでいう「海外不動産で投資」の意味は、「収入<必要経費」だから赤字で節税できるに過ぎないわけです。またローン金利もすべてが節税につながるわけではありません。
不動産所得が赤字の場合、土地購入のためのローン金利は損益通算の対象から外れます。思ったほど節税できないケースもあるので注意が必要です。
ポイント2:海外不動産の申告には現地の専門家が必要
海外の賃貸不動産から家賃などの収益が発生すると、多くの場合、不動産の所在地国の法律により不動産所得に税金が課されます。ただし「現地の税法がどうなっているか」は現地の専門家でなければ分かりません。そのため海外不動産に投資をしたら通常は現地の専門家を探し、確定申告などの税務的な処理を依頼しなくてはなりません。
専門家を見つけるまでの過程はもちろんですが、報酬などの経済的コストも加味したうえで海外不動産の投資の妥当性を検討する必要があります。「専門家への報酬で赤字になるから節税」でしかないならば、慎重になったほうがよいかもしれません。
ポイント3:日本でも申告しなくてはならない
海外の賃貸不動産の収益については、不動産の所在地国だけでなく投資家自身の所在地国である日本でも所得税の確定申告を行わなくてはなりません。つまり申告・納税という手間やコストが日本国内での不動産投資の2倍かかるのです。このとき不動産の所在地国と日本とで二重に納税を行っている場合、外国税額控除という制度を用いることで二重課税状態を解消することができます。
ただし控除額に一定の制限があるため、海外で納めた税金のすべてを取り戻せるとは限りません。なお一昔前、「海外不動産への投資はバレない」という都市伝説が信じられていました。今でもこの都市伝説に期待する投資家がいるようですが、伝説に過ぎません。OECD加盟国を中心に租税に関する情報交換制度が整っているため、海外での不動産所得を隠しても日本の税務当局に把握されてしまうのが現実です。
投資の注意点は海外も日本もあまり変わらない
「海外不動産ならメリットがある」といわれると、まるで海外不動産ならば日本の不動産にはない秘策があるかのように感じます。しかし現実には、投資の注意点は海外でも日本でもほとんど変わりません。むしろ不動産の所在地国の事情を正確に調べるのは日本以上に骨が折れることのほうが多いこともあります。
「資金に余裕がありすぎるから失敗してもいい」というくらいの覚悟がある場合は問題ありません。しかし真剣に「不労所得が欲しい」「虎の子の資金を投じる予定」という場合、まずは日本の不動産で小さく始めることから検討したほうがよいかもしれません。(提供:YANUSY)
賃貸不動産を相続するとき最初に注意すべき3つのポイント
賃貸不動産の相続は、自宅の相続よりも注意すべきことが多岐にわたります。なかには誤解や思い込みが先行してしまい、あとで痛い目に遭う場合もあるのです。今回は、賃貸不動産を相続する場合に最初に注意すべき3つのポイントについて解説します。
賃貸不動産の相続は「相続完了まで」がうっかりしやすい

(写真=Sam and Brian/Shutterstock.com)
賃貸不動産の相続の問題というと「不動産の遺産分割をめぐって相続人同士で争いになりやすい」「相続税の申告は10ヵ月以内」というイメージが最初に浮かぶ人も多いかもしれません。それ自体は間違いではないのですが、それだけにとらわれると思わぬミスをしてしまうことになります。なぜなら相続の手続きは遺産分割と相続税の申告だけではないからです。
実際の相続は被相続人の死亡届や葬儀、名義変更などさまざまな作業が伴います。わかりやすい作業だけならよいのですが、なかにはうっかり失念しやすいものもあるため注意が必要です。忘れてしまうと余計なお金がかかったりトラブルのもととなってしまったりしかねません。相続の手続きを完璧に記憶する必要はありませんが、「ここだけは知っておいたほうがよい」という点だけは念頭に置いておくとよいでしょう。

(写真=Sam and Brian/Shutterstock.com)
賃貸不動産の相続で最初に注意すべき3つのポイント
賃貸不動産の相続が実際に発生した場合、最初に注意すべき3つのポイントについて説明します。
ポイント1:複数で相続する場合「遺産分割完了までは『共有状態』」
複数の相続人がいる場合、賃貸不動産は「遺産分割協議で誰がどのように引き継ぐか」が決まるまでは「相続人全員が法定相続分に従って共有している状態」となります。賃貸不動産が複数の相続人の共有下に置かれるということは、次のような手間がかかるということです。
- 賃貸物件の契約や契約解除、リフォームなどについては、共有者全員(管理行為については持ち分の過半数)の合意が必要
- 家賃などの収入や必要経費は法定相続分で按分して計上
- 按分した収入や必要経費について所得税の確定申告を各相続人が行う
争いなどで遺産分割がいつまでたっても決着がつかない場合、この手間が相続人全員にずっとつきまとうことになるわけです。お互い納得のいくように協議を行うことは大事ですが、協議が長引くと相続人全員の生活に支障が出るおそれがあります。
ポイント2:被相続人分の賃貸収入は4ヵ月以内に準確定申告を
被相続人が亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日(相続開始の日)までの間の所得金額と所得税額を計算し準確定申告をすることが必要です。準確定申告は相続開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に所得税の確定申告と納付を行わなくてはなりません。被相続人は生前にこの作業を行えないので、代わりに相続人(包括受遺者を含みます)が行うことになります。
相続税の確定申告は多くの人に認知されている一方、所得税の準確定申告はなかなか意識されません。被相続人の死亡後のさまざまな手続きに取り紛れてうっかりしがちなのが現実です。確定申告に慣れていないと不動産所得の計算にも手間がかかります。期限を過ぎれば延滞税などのペナルティを別途納めなくてはならないので注意が必要です。
ポイント3:不動産は相続の対象でも家賃は相続の対象ではない
賃貸不動産を相続する場合、自宅の相続と違った問題が発生します。それは「家賃などの法定果実が発生する」ということです。そして相続の対象はあくまでも賃貸不動産であり、家賃などの収入は相続の対象ではありません。つまり賃貸不動産を相続したら不動産そのものについては相続税がかかりますが、家賃は別途所得税や住民税がかかるのです。
ポイント1で解説したように遺産分割が完了するまでは相続人全員の共有状態に置かれるため、それぞれの法定相続分に応じて不動産所得の確定申告が必要となります。遺産分割が完了し、誰が賃貸不動産を引き継ぐかが決まった場合は、引き継ぐ人自ら不動産所得の確定申告をしなくてはなりません。また被相続人が不動産所得について青色申告の適用を受けていた場合、その青色申告の効力までが相続されるわけではありません。
賃貸不動産を引き継いだ相続人が青色申告の適用を受けようとするならば、あらためて自分の名前で青色申告の承認申請を行う必要になります。
賃貸不動産を相続する時には、上記で解説した3つのポイント以外にも多くの注意点が存在しますので、専門家への適切な相談が必須です。(提供:YANUSY)
不動産投資でワンルームマンションを選んだときのメリット・デメリット
不動産投資にはさまざまな種類がありますが、中でも人気なのがワンルームマンションです。とはいえ、すべての投資家にワンルームが合うわけではありません。ここでは、客観的な視点でメリット・デメリットを解説します。
ワンルームの5大メリット:少ない投資額、ほったらかし運用、売却がスムーズなど

(写真=sommart sombutwanitkul/Shutterstock.com)

(写真=sommart sombutwanitkul/Shutterstock.com)
ワンルームのメリット1:少ない投資金額と頭金で買える
不動産投資(賃貸経営)というと、富裕層がするものというイメージがあるかもしれません。たしかに、新築のマンションやアパートは1億円以上することもありますが、ワンルームマンションだと都心でも新築や築浅なら数千万円、中古なら数百万円~1千万円台で購入できるものもあります。
しかも物件価格の大半はローンでまかなえるため、実際に必要なキャッシュは、頭金と諸経費だけです。頭金は物件価格の1~2割、場合によっては頭金なしのフルローンも可能です。
ワンルームのメリット2:ほったらかしに近い形で運用できる
管理に手間のかからないこともワンルームマンションの魅力であり、忙しいビジネスパーソンにも向いています。購入後のルーティンワークは、月に1回賃料の入金をチェックすることくらいです。
収益物件を運用していく上で欠かせない業務(入居者のトラブル処理、賃料の督促、退去時の対応など)は、専門の管理会社に委託することで代行してもらえます。
ワンルームのメリット3:運用コストが予想しやすい
不動産投資で失敗するパターンの一つに、収入や資産に見合わない規模の収益物件を購入してしまい、修繕費が予想以上に膨らみ破綻するというものがあります。たとえば、アパートや1棟マンションを経営している場合、数百万円単位の修繕費が突如発生することもあります。
ワンルームマンションであれば、管理費や修繕積立金、中長期的な住宅設備の交換費用などのコストを見積もりやすく、資金計画と実際の差異が生まれにくいというメリットがあります。
ワンルームのメリット4:スムーズに売却しやすい
私的年金を目的に不動産投資を始めた場合でも、何らかの理由で収益物件を売却する必要が生じることもあります。
1棟マンションやアパートなどは高額なので、買い手がなかなか見つからず、値引きをしても売れないケースもあります。ワンルームマンションは価格が手頃なため、価格が適正で立地が良ければ比較的スムーズに売却できるでしょう。
ワンルームのメリット5:選択肢に柔軟性がある
所有する部屋数を増減させることで、経営規模を自由に調節できるのもワンルームマンションのメリットです。
「初めての不動産投資なので、まずは1部屋所有したい」「リターンを大きくしたいので、一度に5部屋購入したい」「一定期間ごとに1部屋ずつ増やしていきたい」など、オーナーの要望(人生設計)に合わせて、好きなタイミングで所有する部屋数を自由に調整できます。
以上が、ワンルームマンションの主なメリットです。今後単身世帯が増えるという予測も、追い風と言えるでしょう。
ワンルームのデメリット:短期的には儲からないこと
デメリットは、「低利回り」という点が挙げられます。特に新築マンションや築浅マンションは、その傾向が見られます。
ワンルームマンションは立地が良いケースが多いため、低利回りになりがちです。東京23区であれば、ワンルームマンションのほとんどが、通勤に便利な路線の駅近にあります。資産価値が高いため、どうしても物件価格が割高になり、利回りが低くなってしまうのです。ただし、立地が良いため、駅から距離のある物件より優位性を持っていると言えるでしょう。
また、経営規模が小さいため、大きなリターンが見込めません。毎月少しずつ残債を減らしながらコツコツ資産形成していくスタイルが基本になります。
このような特徴があるので、ワンルームマンションは「短期で大きく儲けたい人」には向かず、「将来の私的年金代わりにしたい」というビジネスパーソンにマッチすると言えるでしょう。(提供:Incomepress )
商業用不動産投資額、19年1~9月期は前年比2%増
JLLは28日、2019年1~9月期および第3四半期の日本の商業用不動産投資額(速報値)を発表した。
1~9月期は、3兆1,590億円(前年同期比2%増)、第3四半期は9,170億円(同9%増)となった。
プラスマイナス0%であった上半期(1~6月)から第3四半期の増加分が寄与し、1~9月期は前年比増に。不動産価格が高値で推移する中、保有不動産を売却する事業会社や開発物件を私募ファンド等に売却する不動産会社が増加していることが増加の背景にあるとみられる。世界的にも米中貿易摩擦や香港の政治不安などで不透明感が高まる地域がある中で、政治的・経済的安定性に優れた日本に対する注目度は高まっており、日本の不動産取得に意欲的な海外投資家も増加。19年後半に入って、不動産売買はより活発になっており、売買金額は18年比で増加すると見込んでいる。
不動産投資もAIの時代へ!デジタルネイティブ世代台頭で不動産テック浸透か!?
不動産にテクノロジーを取り入れた「不動産テック」。人工知能(AI)を活用して不動産の価格・賃料の将来予測をはじき出すサービスは、とりわけ不動産投資家にとってなくてはならないものになるかもしれない。
大東建託では、2020年度の本格導入に向けて、6月から首都圏の一部エリアを対象に、東京大学空間情報科学研究センター不動産情報科学研究室の清水千弘特任教授と、同社賃貸未来研究所が共同開発した、Alを活用した家賃査定システムを試験的に導入した。
グループで全国約109万戸の管理戸数がある同社では、家賃査定を約1000人のスタッフによる類似物件の情報収集とデータ解析に基づいて行ってきた。この作業をシステムにより自動化することで、スタッフの業務軽減と、顧客や取引先に家賃設定の明確な根拠を示すことが出来るとしている。
同社が蓄積してきた賃貸募集広告データなどを、重回帰分析(一つの目的変数を複数の説明変数で予測)を適用して処理するもので、最寄り駅と住所の整合性、適切な説明変数の選択と説明変数の組み合わせによる変数合成、モデルの分割方法、査定対象類似物件抽出ロジックなどこれまでにないノウハウが組み込まれている。
複数エリアで理論モデルの誤差率中央値5%未満を達成、実装モデルにはチューニングを加え、最寄り駅が存在しないエリアなど全国を査定エリアとして開発されているという。
AI活用で不動産の価格・賃料の将来予測をはじき出す草分け的な存在であるリーウェイズ(東京都渋谷区)では、不動産投資では国内初となる人工知能を活用した将来収益の査定・分析システム「Gate.(ゲート)」の開発・運営を行っている。
インターネット上で得られる不動産に関する信用データを集めるプログラムの開発によりサービスを提供しており、同社では駅ごとの賃料の下落率を分析し、投資を検討している物件が将来どれほどの収益を生み出す資産であるかを説明できるとする。主に使うデータは人口統計、税金、個別の物件状況といったものだ。
不産投資では出口での損益が重要となる。足もとの利回りにとどまらず、来年、再来年、さらには将来の想定売却価格を駅ごとの賃料下落率などからオンライン査定、投資家が全保有期間での収益性に基づいて判断できるようにした。
10年後の家賃相場を予測、現在価値から割り引くことで売却予想価格も算出できる。買い主にとっても生涯の収支に基づいたIRR(内部収益率)で判断できる。売り主は利回り、買い主はIRRを重視するため売り手と買い手の双方のメリットを考えて提供する。
これからの不動産マーケットについて、同社では、インターネットやスマートフォンなどが身近な環境で育ったデジタルネイティブ世代の不動産オーナーが増加し、テクノロジーを活用した新たなコミュニケーションが必要不可欠になると想定している。
そうしたことを受けて、今年に入って同社では業務提携を積極化している。不動産オーナー向けに賃貸経営コスト削減サービスなどを提供するCasa(東京都新宿区)と提携し、リーウェイズの6000万件超の物件データをもとにAI分析機能を生かした不動産評価システム、物件情報提供のプラットフォーム、不動産管理アプリの共同開発を進めている。
静岡銀行とも資本業務提携した。同行向けに新たな不動産評価システムの開発やサービスなどの企画・開発を行う。不動産の将来的な空室率の上昇や賃料の下落などのリスクの可視化、不動産投資におけるパフォーマンスの解析などを通じて不動産投資家の資産形成をサポートする新たなサービスの開発に取り組むという。
静岡銀行が保有する地方の不動産データであったり、審査ノウハウを活用して全国共通の不動産審査プラットフォームの共同開発も行っていく予定だ。
賃貸住宅経営の外部環境は厳しさを増している。いかにして適正賃料を把握し、満室稼働に繋げるか。AIを用いたビッグデータの分析に基づく経営判断が当たり前の時代は、すぐそこまで来ている。
健美家編集部
不動産投資の利回りは何%が理想?平均相場&物件の見分け方をFPが解説!
https://manetasu.jp
不動産投資を始めるにあたって知っておくべき知識の中でも特に重要なのが利回りです。利回りについてなんとなく理解できているという人は多いかもしれませんが、不動産投資で成功するためには「なんとなく」ではいけません。
利回りの考え方や見極め方は、不動産投資の成否を分けるとても重要な知識であるにもかかわらず、十分に理解できていない人が多いように感じます。
そこで本記事では、不動産投資の利回りに関する重要な知識や利回りの相場などについて詳しく解説します。
間違えるとヤバイ、「表面利回り」と「実質利回り」の違いとは

不動産投資の利回りについて解説するにあたり、初心者投資家にまずお伝えしたいのが、表面利回りと実質利回りに関する誤解です。
実は不動産投資に失敗する不動産投資家の多くは、話を細かく聞いていくと元々の原因は表面利回りと実質利回りの誤解によることがよくあります。では、表面利回りと実質利回りは具体的に何が違うのでしょうか。
表面利回りは収益物件の大まかな指標表面利回りとは、物件価格に対してどの程度の家賃収益があるのかを示す指標のことです。例えば、物件価格2,000万円、年間家賃収入80万円の場合、表面利回りは次のようになります。
- 80万円÷2,000万円×100=4%
よって表面利回りは4%です。表面利回りは主に他の物件と比較する際活用できます。
不動産投資における資産運用と頭金の関係性とは
資産運用とは、平たく言えば「お金に働いてもらい新たなお金を生み出してもらうこと」です。不動産投資はさまざまな資産運用の中の一つの手段です。
フルローンという言葉を耳にしたことがないでしょうか。自分のお金をまったく使わず、不動産投資に必要な物件を購入するために利用できるローンです。フルローンを使えば金融機関から借りたお金だけで不動産を購入でき、家賃収入とローン返済額の差額が自分の手元に残る仕組みです。自己資金を一切使わず資産運用の手段が取れる可能性があることは、不動産投資の一つの特徴です。
「頭金を不動産価格のどの程度の割合で入れるべきか?」という議論がありますが、フルローンで借り入れができるけれども、あえて頭金を多く入れる場合もあります。頭金を入れることもまた資産運用の一つの方法だといえるでしょう。今回はこの頭金と資産運用の関連性について解説していきます。
頭金の割合を考えることは資産運用そのものを考えることと同義

(画像=smolaw/Shutterstock.com)
例えば1,000万円の現預金が手元にあるとします。その現金を普通預金として金融機関に預けていても現代はマイナス金利という状況のため、ほぼ受取利息は発生しません。一方、その1,000万円を1億円の不動産購入の頭金に使用した場合、どうなるでしょうか?
頭金を入れた場合、フルローンのケースと比較して総支払額が減少することが大きな特徴です。総支払額の減少は支払利息の減少を意味することから、「支払利息の軽減=キャッシュフローの増加」となります。資産運用というと受取利息を多くするイメージを持っている人も多いかもしれませんが、支払利息を少なくすることも資産運用の一つです。そのため普通預金に入れておくだけの余剰資金があれば、不動産購入の頭金として使用して支払利息を軽減させることも一つの資産運用の手段であることは頭に入れておきましょう。
しかし、場合によっては頭金を入れることがデメリットになることもあるためバランスをとりながら適正な頭金の割合を決めていくことが賢明です。頭金を入れることのメリットとデメリットについて次の章で解説します。

(画像=smolaw/Shutterstock.com)
頭金を多く入れることのメリット
頭金を入れる代表的なメリットはフルローンよりも総支払額が軽減されることです。また精神的にも経営的にも頭金を多く入れたほうが健全といえます。例えば毎月の平均家賃収入が50万円かつフルローンでの毎月のローン返済額が25万円だった場合に頭金を入れたらどのようになるでしょうか。もし1,000万円の頭金を入れることによりローン返済額が18万円まで減額した場合は総支払額が圧縮されるだけでなく毎月7万円のキャッシュフローが増加することになります。
不動産投資は毎月のキャッシュフローがプラスであれば自己破産することはありません。そういった意味で頭金を入れることによって毎月のキャッシュフローが改善し、経営的も精神的にも安定するというのも大きなメリットです。
頭金を多く入れることのデメリット
頭金を多く入れることによるデメリットは大きく分けると2つあります。
1つ目は頭金を多く入れることによって、手元キャッシュが少なくなり急な出費に耐えられなくなる可能性がでてくるということです。特に1棟を所有している人は大規模修繕など定期的に大きな出費があることに加えて物件の共用部で突発的な出費が発生する可能性もあります。保有キャッシュが少なく、修繕すべき設備を修繕できないことで、入居者の解約が増え経営が厳しくなりかねません。この部分は一定の現預金水準は保つというルールを決めておけば防ぐことは可能です。
2つ目のデメリットは、保有キャッシュが少ないと不動産投資の規模拡大のペースが遅くなってしまうということです。融資申請の際、必ず保有キャッシュの額(現預金)を金融機関に通知する必要があることがその理由です。手元キャッシュの金額が大きければ大きいほど健全性が高いとみなされ、金融機関からの評価は高くなります。手元キャッシュが少ないと、そもそも融資を受けられないという可能性もあるのです。
頭金を入れる場合は、これらのデメリットを踏まえたうえで余剰資金全額を遊ばせておかないよう、バランスを見極め効率的な資産運用をしていく意識を持つようにしましょう。(提供:YANUSY)
ソフトバンク「孫正義」社長、ITの次は不動産投資に注力
インテリックスが不動産投資型クラウドファンディング「X-Crowd」開始
東証1部上場企業で中古マンション再生流通事業などを手掛ける株式会社インテリックスが10月7日、不動産投資型クラウドファンディングサービス「X-Crowd(エックスクラウド)」を開始、CF事業に参入した。ポートフォリオ分散に役立つオルタナティブ投資として提案していく。
同サービスでは、投資家は会員登録後に同社との間で匿名組合契約を締結、その後出資金を払い込む。出資金は優先出資部分となり、同社が優先出資者に劣後して償還を受ける「劣後出資」で運用する。
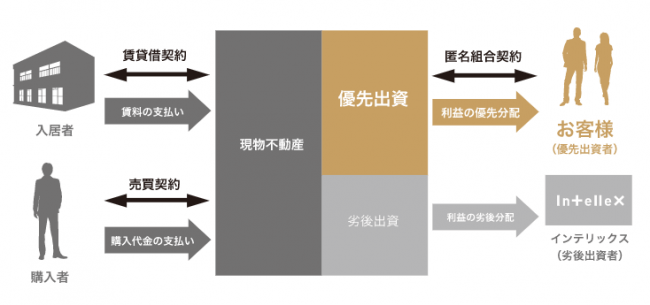 優先出資者は、運用資産からの利益について、劣後出資者よりも優先的に分配を受ける権利が付与される。優先出資者の保全手当てとしては、優先劣後構造による内部信用補完を設けている。対象不動産の価格下落が発生した場合、下落価格が劣後出資者の出資元本の範囲内なら、不動産価格変動による投資家の元本払戻には影響を受けないことになる。
同サービスの提供にあたり、同社は不動産特定共同事業法第2条第4項第1号に基づく電子取扱業務の許可、第2条第4項第2号に基づく電子取扱業務の許可を取得。基本的な手続きをインターネット上で行える投資環境を用意した。これまで中古マンション再生流通事業で培ったファンド対象物件の“目利き力”が強みだ。第1号ファンドは、同社が展開する京町家をリノベーションした宿泊施設を投資対象とし、11月を目途に募集を開始する予定。
優先出資者は、運用資産からの利益について、劣後出資者よりも優先的に分配を受ける権利が付与される。優先出資者の保全手当てとしては、優先劣後構造による内部信用補完を設けている。対象不動産の価格下落が発生した場合、下落価格が劣後出資者の出資元本の範囲内なら、不動産価格変動による投資家の元本払戻には影響を受けないことになる。
同サービスの提供にあたり、同社は不動産特定共同事業法第2条第4項第1号に基づく電子取扱業務の許可、第2条第4項第2号に基づく電子取扱業務の許可を取得。基本的な手続きをインターネット上で行える投資環境を用意した。これまで中古マンション再生流通事業で培ったファンド対象物件の“目利き力”が強みだ。第1号ファンドは、同社が展開する京町家をリノベーションした宿泊施設を投資対象とし、11月を目途に募集を開始する予定。

 また、地方創生に繋がる不動産ファンドも計画しており、より豊かなストック型社会の実現を目指す。自社の不動産投資型ファンドにとどまらず、他社の不動産投資型ファンドも募集する取り組み(プラットフォーム展開)も推進、サービスの拡充を図っていく。
インテリックス社は中古マンション再生流通事業を展開。14年連続で1000戸以上の販売を行い、19年5月末現在、累計販売戸数2万1000戸を達成。首都圏に加えて全国主要都市での事業展開を進めている。10月7日に東京都台東区根岸に地上15階建て・全169室のホテルを建設、2020年1月中旬に開業予定と発表した。また、京阪電鉄不動産株式会社との共同プロジェクト第1号の京町家再生施設が完成し、宿泊施設として11月1日の開業を予定している。
また、地方創生に繋がる不動産ファンドも計画しており、より豊かなストック型社会の実現を目指す。自社の不動産投資型ファンドにとどまらず、他社の不動産投資型ファンドも募集する取り組み(プラットフォーム展開)も推進、サービスの拡充を図っていく。
インテリックス社は中古マンション再生流通事業を展開。14年連続で1000戸以上の販売を行い、19年5月末現在、累計販売戸数2万1000戸を達成。首都圏に加えて全国主要都市での事業展開を進めている。10月7日に東京都台東区根岸に地上15階建て・全169室のホテルを建設、2020年1月中旬に開業予定と発表した。また、京阪電鉄不動産株式会社との共同プロジェクト第1号の京町家再生施設が完成し、宿泊施設として11月1日の開業を予定している。


相続対策としての不動産投資…「落とし穴」はないのか?
昨今の不動産業界の騒動は「事業者本位」が要因⁉
――相続対策に極めて有効な不動産投資ですが、その一方で注意すべきポイントもあるかと思われます。たとえば、対談の冒頭で蜂谷社長が触れていたようにアパートやシェアハウスへの投資を勧める事業者が急増しましたが、その一方で「かぼちゃの馬車騒動」や「レオパレス問題」「スルガ銀行の不適切融資」といったトラブルが相次ぎましたね。
蜂谷 結局のところ、それらの事業者の経営スタンスがもたらした騒動だと私は解釈しています。事業者本位なのか、それとも顧客本位なのかという違いです。一連のトラブルは、いずれも事業者本位のスタンスがもたらしたものだといえるでしょう。
顧客本位に徹していれば、安定的な需要を見込めない場所に、賃貸物件を建設するような提案を行うはずがありません。また、売ったら終わりの姿勢でなければ、施工不良や強引な融資のような問題も発生しないはずです。

税理士法人チェスター代表
税理士
荒巻善宏氏
荒巻 私たちのところへ相談に来られたお客さまの間でも、けっして好立地とはいえない場所に賃貸物件を建ててほとんど空室が埋まらず、所有しているだけで赤字がどんどん増えてしまうような物件を抱えているケースが散見されます。そういった場合は、思い切ってその物件を処分し、もっと都心で空室リスクの低い物件を購入して資産を組み替えることを提案しています。
蜂谷 私はフェイスネットワークを設立する前に金融機関で融資を担当していたのですが、その頃からお客さまと寄り添いながら仕事を進める姿勢を貫いてきました。
顧客本位であるからこそ、再び利用していただけるものだと強く意識しています。現に、当時は他の金融機関のほうが低い金利で借りられるにもかかわらず、あえて私に相談を持ちかけてくれたお客さまもいらっしゃいました。不動産業界においてこうした顧客本位のスタンスで取り組んでいる事業者がどれだけあるのかと問われれば、「その数はかなり限られているかも……」と答えざるをえません。
10月26日(土)無料セミナー開催@東京・千駄ヶ谷
プロが教える『都心一棟マンション』を活用した相続対策の進め方
~相続専門の税理士も特別登壇!~

税理士法人チェスター代表
税理士
荒巻善宏氏
税理士
荒巻善宏氏
プロが教える『都心一棟マンション』を活用した相続対策の進め方
~相続専門の税理士も特別登壇!~
計算上の利回りが高い物件には「相応のリスク」が伴う
――つまり、自分たちの利益のことしか考えていない事業者の話は鵜呑みにしない、という当たり前を出発点として考えるということですね。そのうえで、具体的に不動産投資を検討する際には、どういったことに注意を払うべきなのでしょうか?

株式会社フェイスネットワーク
代表取締役社長
蜂谷二郎氏
蜂谷 節税効果のような不動産投資のメリットだけに目を奪われず、先ほどの話にも出てきた空室リスクや修繕リスク、資産価値の低下リスクといった特有のリスクもきちんと認識しておく必要があります。そのうえで、これらのリスクをできるだけ軽減・回避できるミドルリスク&ミドルリターンの投資を実践するのが基本です。
どうしても高い利回りを追求しがちですが、ローリスクでハイリターンの物件があれば誰もが競って買うはずで、そのようなものはまず存在しません。計算上は利回りが高くても、ハイリスクの(空室が発生しやすい)物件に手を出しているのが現実です。そういった意味でも、物件の“目利き”が重要となってきます。
荒巻 税理士としての観点から注意を促すとしたら、あからさまな節税対策で税務署から目をつけられてしまうのは避けるべきだということが、まず挙げられます。もう一つ、蜂谷社長のお話にも出てきましたが、リスクをきちんと理解したうえで投資を行うのが大前提ということです。さらに挙げるなら、ご子息たちが相続対策や不動産投資の必要性を感じていても、親御さまが難色を示すというケースも少なくなく、家族の足並みが揃いにくいことも注意点かもしれません。
蜂谷 「億単位」のローンを組むことを説明した時点で、そこから先の話にはまったく耳を傾けず、頑なに拒んでしまう親御さまもいらっしゃいます。
荒巻 相続の問題は非常に個別性が高く、各家庭によって最善の解決策は異なってきますし、相続税の節税効果も異なってくるものです。その意味では、単に本を読んだりするだけでは、自分たちに相応しい対策が判明しないのも注意点でしょう。
私たちにも、個別面談でじっくりと話をうかがったうえで、個々のお客さまにとっての最善策を提案することが求められています。耳を貸そうとしない親御さまに対しても、目の前で節税効果を具体的な金額を示しながらていねいに説明すれば、反応が変わってくることが少なくありません。
蜂谷 適切な対策を講じればケタ違いの節税効果を得られますし、空室リスクの低い優良物件を建てることで長く安定的な家賃収入が入ってきますからね。例えばそういった意味では、都心部でのエリア選択はとても重要になってきます。あとで詳しくご説明しますが、当社では「城南三区(世田谷・目黒・渋谷)の新築1棟マンション」に的を絞って物件を手掛けているのもその一環なのです。
荒巻 もう一つ、相続対策としての不動産投資を考える場合には、相談を持ちかける相手をきちんと選んだほうがいいでしょう。相続税の手続きにおいて、不動産の資産価値評価は基礎的な業務に当たります。しかしながら、その評価方法を間違えてしまい、結果的に過払いとなっている(相続税を払いすぎている)ケースが珍しくありません。
裏返せば、相続税の申告を得意としている税理士がそれだけ少ないということを意味しているのでしょう。相続対策の中でも金額的に最も大きいのは不動産で、生前贈与などと違って億単位の規模になるだけに、どういった物件を選ぶのかが極めて重要です。私たちのような相続の専門家とともに、資産価値の高い物件づくりに強い不動産のプロに相談するのが肝心です。

株式会社フェイスネットワーク
代表取締役社長
蜂谷二郎氏
代表取締役社長
蜂谷二郎氏
不動産投資の家賃収入に対してかかる税金はいくら?覚えておきたい不動産所得の計算方法
ワンルームマンション投資や一棟買いなど、いわゆる『不動産投資』などによって、家賃収入を副業として考えている人が増えています。家賃収入にはいったいどのぐらいの税金がかかるのでしょうか?税金の仕組みや計算方法について解説します。
家賃収入を得た場合の処理
収入には税金がかかります。家賃収入を得た場合、どのような税金を納めなければならないのか、またどのような形で税務署に申告するのかを見ていきましょう。
家賃収入は不動産所得
収入から必要経費を引いた金額を『所得』といいます。そしてこの所得には『所得税』がかかり、決められた金額を税金として納めなければなりません。
この所得は、収入の形によって10種類に分類されます。会社からもらう給与は『給与所得』、副業や自営業なら『事業所得』に分類され、それぞれに所得税がかかります。
家賃収入は、所有している不動産によって発生する収入のため『不動産所得』に分類されます。確定申告を行う場合は、この不動産所得として申告しなければなりません。
規模により事業所得で処理も可能
不動産所得は以下の要件を満たしていれば『事業所得』としても申告が可能です。
- 賃貸できる独立した部屋の数が10室以上
- 独立家屋の貸付けが5棟以上
事業所得で申告すると、青色申告特別控除や専従者控除が適用可能になり、不動産所得として申告するよりもはるかに税金を安く抑えられるのです。
家賃収入は正しく申告しよう

給与所得以外の所得が年間20万円を超えた場合、確定申告を行う義務が発生します。
正しく申告しないとペナルティが科せられる可能性があるため、申告は正確に行うようにしましょう。
赤字でも確定申告がおすすめ
前述のように給与以外の所得が20万円を下回った場合は確定申告の必要はありません。しかし、トータルで見ると申告した方がお得です。
不動産所得で赤字になった場合は『損益通算』といって他の所得と合算できます。つまり、事業所得で100万円の黒字、不動産所得で30万円の赤字なら70万円の黒字として確定申告が可能になるのです。
また、青色申告の場合は負債を繰り越して翌年に計上することができます。前年50万円の赤字、今年度が100万年の黒字だとすれば、今年度は50万円の黒字として申告できるのです。赤字は最大3年間の繰り越しができます。
そのため、事業所得で家賃収入を申告する場合でも、赤字を申告した方が税金が節約できるのです。
申告漏れは脱税に
サラリーマンの場合、確定申告は会社が『源泉徴収』と『年末調整』という形で行ってくれます。しかし、会社の知らない収入やフリーランスの場合、そういった手続きは自分で行わなければなりません。
家賃収入も同じです。確定申告を行わない場合、税務署に申告漏れと判断される可能性があります。
そうなると『追徴金』が発生して20%も余計に税金が取られるほか、最悪の場合、脱税として国税局から告発され、犯罪として裁かれる可能性もあるのです。
もっとも脱税と判断されるのは、意図的な申告漏れや帳簿の改ざんといった悪質なケースにのみ適用されるため、まずは漏れのないようにしっかりと申告を行っておきましょう。
不動産所得にかかる税金

不動産所得にかかる税金について、より詳しく解説します。固定資産税や都市計画税といった税金の種類についても見ていきましょう。
所得税と住民税の支払いが必要
不動産所得で支払いが必要なのは次の二つです。
一つはこれまで紹介してきた所得税です。具体的な金額は、国税庁のHPに税率が記載されているため、それを元に計算します。
計算方式は『所得金額×税率-控除額』です。例えば所得が500万円なら、税率は20%、控除額は42万7500円のため、500万×20%-42万7500円=57万2500円となります。
そしてもう一つは『住民税』です。住民税は市町村税と都道府県民税の2種類があり、収入とすんでいる地域によって金額が異なります。
住民税の場合は、前年の所得を参考に決定するという性質があることも覚えておきましょう。
物件の固定資産税・都市計画税も発生
さらに家賃収入には固定資産税と都市計画税も発生します。固定資産税とは、土地や家屋に課せられる税金で、固定資産評価額を元に算出されます。
都市計画税は、都市計画事業などに必要な費用を補填するために徴収される税金です。こちらは固定資産税評価額に制限税率を掛けた値となります。
経費にできる費用
経費にできる費用は、主に次のようなものがあります
- 固定資産税や都市計画税などの税金、収入印紙代など
- 火災保険や地震保険など、不動産にかけた保険料
- 管理会社への業務委託料
- 税理士や司法書士、弁護士への報酬
- 減価償却費
- マンション・アパートなど建物の修繕費
- ローン金利
その他にも、物件を下見に訪れたときの交通費や、税金や不動産の勉強のために購入した書籍代などが経費として計上可能です。
ただし、あまりにも関連性の薄い支払いや高額な費用は、税務署のチェックが入るため注意しましょう。
文/編集部
にほんブログ村



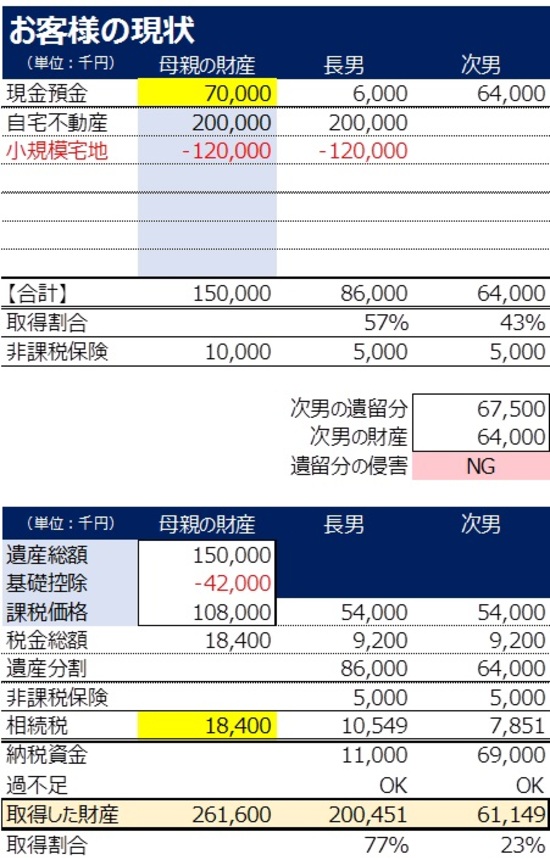
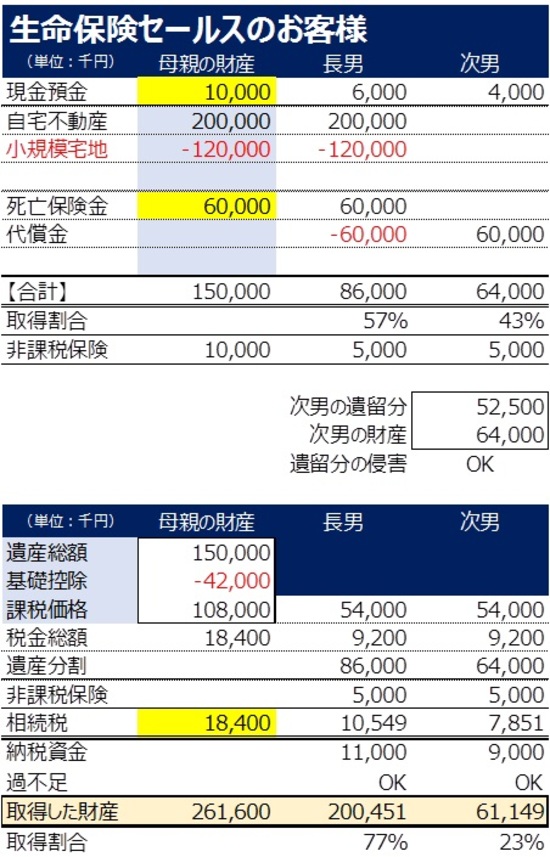
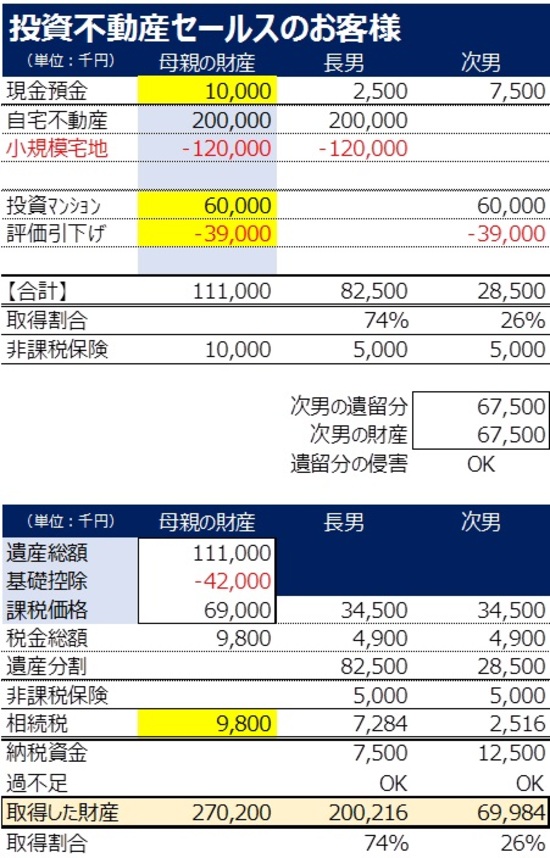





![[図表1]](https://gentosha-go.com/mwimgs/c/e/550/img_ce085d8623861dae7283577703e2ba0751428.jpg)
コメント
コメントを投稿