年間キャッシュフロー2000万円の専業大家が語る「私が区分オーナーチェンジ物件から始めたワケ」
新卒で入行した都銀が肌に合わず
セミリタイアを目指し投資を開始
首都圏在住のきょうへいさんは2014年から不動産投資を始め、その4年後には30歳の若さでサラリーマンを卒業し、現在は区分や戸建て、シェアハウスを計10物件所有する専業大家だ。
他にもシェアハウス100室ほどを転貸したり、法人を立ち上げスタッフを雇用して、保有物件の管理も手掛ける。借入金7500万円に対して、諸経費控除後税引き前のキャッシュフロー(CF)は2000万円と、投資のパフォーマンスは申し分ない。

いまでは専業大家として独立を果たしたきょうへいさんだが、そのきっかけはいまから10年前。大学を卒業して都銀に入行したまではよかったのだが……。
「朝8時から夜8時までの12時間勤務はザラで、とにかくきつかったのです(苦笑)。人間関係や組織風土も合わず、1日でもはやくサラリーマンを辞めてセミリタイアしたいと思うようになりました。手始めにやったのが、投信積み立てです」(きょうへいさん、以下同)
なぜ、投資信託だったのか。銀行員の場合、個別株の取引はインサイダーに該当し、売買をするには届け出が必須。
「上司からハンコをもらえば良いのですが、行内的に株式投資はご法度な雰囲気……。始めると目をつけられるかもしれないと思い、そこまでしてやる気になりませんでした。対して、投資信託は許可不要で、1億円まで積み立てて年利5%なら年500万円儲かり、これだけあればセミリタイアできると思ったのです」
22歳で始め、最初は月々4万円、途中からは月10万円に積立額を増額。3年後に利益確定したところ、300万円ほどの利益を得たという。「ですが、この調子だといつセミリタイアできるのか……。ざっと計算すると40代になっていて、これでは遅すぎます。そこで他の手段を考えたところ、融資を受けることでレバレッジをかけられる不動産投資なら、もっとはやく資産が作れると気づきました」
選んだのは区分マンションの
オーナーチェンジ物件。その理由は?
不動産投資に注目したきょうへいさんは、ネットなどで物件を探し、2014年に神奈川県内で3LDKの区分マンションを910万円で購入。大家デビューを果たした。
「当時で築33年、すでに入居者のいるオーナーチェンジ物件で、家賃は10万3000円。ただし、ここから管理費と修繕積立金を支払うと10万円を切り、実質的な家賃収入は年91万円でした。対して当初の売り出し価格は1200万円で、これだと利回りが10%を切ります。私としては最初の物件は絶対に失敗したくなく、利回りもこれだと不安でした。何とか10%以上にしたく850万円の指値を入れたところ、それは無理でしたが、910万円まで下げていただき、思い切って買いました」
区分マンションなら1棟物件に比べて価格が安く、多額の融資を受けないで済むのもポイント。きょうへいさんは金融機関から870万円を借り、残りは自己負担でまかなったという。ちなみに、オーナーチェンジ物件にしたのは理由がある。
「入居者のいる区分マンションを実需で買う人はいなくて、おのずと投資用物件として捉えられます。すると、住宅ローンは低金利で返済期間が長いので購入層は広がる一方、投資用ローンはそれより金利が高くて返済期間が短くなるので買い手が限られ、その結果、同じ物件でもオーナーチェンジの方が低価格になるケースがあるのです。なので、私は入居者のいる物件を探し、住んでいる間は家賃を受け取り、退去したら実需向けに売れば損をしないと考えました」
最初の投資だからこそ小さく始められる区分マンションを選び、そのなかでも、価格や客づけの面で有利なオーナーチェンジに限定したというのが、きょうへいさんの戦略。
「指値は言うだけならタダです。現金化を急ぐオーナーなら、ある程度は応じるかもしれませんし、まずは試してみました」
という。
この物件は現在も保有していて、毎月の家賃に加えて2年に一度は更新料も手に入る。
「ただし、ついこの間、入居者から『買い取りたい』と申し出があり、来年早々に手放す予定です。これまでの家賃収入と売却代で収益は十分プラスで、手始めの物件としては大成功だと思います」
管理は業者に任せずに自身で行っている。大変では?
「保有物件の規模によりますが、少ないうちは問題ありません。仮に水回りなどのトラブルが起きれば専門の設備業者を探せば良いだけで、私の場合は色んな方と付き合っていくうちに懇意な業者が見つかりました。物件を保有するエリアごとにリスト化しておくと、すぐに対処できます。ただし、最初に買ったこの区分は、一度もトラブルはありません」
区分マンションだけだとCFが少ない……。
次に選んだのが「シェアハウス」だった
幸先の良いスタートを切ったが、始めたから気づかされることもあった。
「神奈川で賃貸ニーズのあるエリアの物件なら、売却時に利益はでると考えましたが、いつ退去するかわかりません。その間に家賃収入は入りますが、ローンを返し終わった後のCFは月2万円ほどで、これだと、セミリタイアはいつになることやら。区分マンション増やしても非効率で、かつ銀行評価が低く融資を受けるにも限界があるとわかり、方針転換を迫られました」
人生を変えるには、区分マンション投資だけでは不十分。そこで、少ない借り入れで高利回り、CFが出る投資対象は何かを突き詰めた結果、たどり着いたのがシェアハウスだったという。
「首都圏でも築古の戸建てなら価格は安く、高い利回りが期待できます。入居者トラブルや頻繁な入れ替わりなど手間はかかりますが、それは引き受けようと思いました。とにかく、低リスクで損をしないことを優先したのです」

シェアハウスの購入・運営の知識はないので、コンサルタントに教えを請い、ノウハウを吸収。
2015年に東京と埼玉で戸建てを1棟ずつ計2棟購入し、シェアハウスとして運用を始めた。そして、これをきっかけにきょうへいさんの不動産投資は加速し、わずか2年後にサラリーマンを卒業することに! そのプロセスは、次回お伝えしよう。
中古マンション投資のメリット・デメリットは?初心者向けの注意点も
1.中古マンション投資の特徴
中古マンション投資とは、中古マンションを購入し、賃貸・売却することで収益を得る投資です。
中古区分マンションでは、同程度のグレードを持つ新築区分マンションに比べると価格の下落が緩やかになる傾向があり、かつ、新築マンションに比べて価格そのものが安くなります。
立地がよく管理状態の良いマンションであれば実需もあり、売却益を狙うことも可能です。戸建投資や一棟物に比べて、建物価格の割合が大きい分、立地や間取りなどの要素から将来的な価格を予測しやすい傾向があります。
2.中古マンション投資のメリットとデメリット
中古マンションの価格は新築マンションに比べると20%から40%程度低いため、投資額を安く抑えることができます。
ただし、建物の担保評価が落ちるため融資も付きにくくなり、頭金(初期投資額)が大きくなる可能性がある点には注意が必要です。また、家賃収入面からは、新築マンションに比べて家賃相場が低くなり、空室リスク、修繕リスクも高くなる点は懸念事項と言えるでしょう。
一方、入居者がすでに入居したまま売買されるオーナーチェンジ物件であることも多く、その場合購入してすぐに賃貸収入が入って来るメリットがあります。
中古マンション投資のメリットとデメリットについて、それぞれ詳しく見て行きましょう。
2-1.中古マンション投資のメリット
中古マンション投資のメリットは主に次のような点になります。
- 新築マンションと比較して安く購入できる
- 新築マンションよりも表面利回りが高い傾向がある
- 家賃収入がすぐに得られるか予想しやすい
- 資産価値の減少が起きにくい/li>
以下で、それぞれの内容を詳しく説明します。
新築マンションと比較して安く購入できる
不動産投資では特に立地が重要になりますが、立地の良い物件は価格が高く、ローンを利用して購入するとキャッシュフローが厳しくなることがあります。
しかし、上中古マンションであれば新築マンションよりも安い価格で購入可能であるため、立地条件の良い物件でもキャッシュフローが好転する可能性が高くなります。
不動産投資において、家賃下落リスク・空室リスクを下げるために、豊富な賃貸需要の期待できる好立地の物件を選ぶことは重要なポイントです。好立地な物件でも選択肢に入れられる可能性が高いことは、中古マンション投資の大きなメリットと言えるでしょう。
新築マンションよりも利回りが高い傾向がある
中古マンション投資では物件価格が安い分、表面利回りが新築マンションと比較すると高めである傾向があります。表面利回りとは、年間賃貸収入に対する購入価格の割合であり、表面利回りが高くなればそれだけ高い収益を得られる可能性のある物件であると言えます。
利回りが低い物件は、不動産投資ローンの返済額や経費を上回ることができず、キャッシュフローがマイナスになるケースも少なくありません。新築物件と比較して空室率が上がる一方で、良好なキャッシュフローを得やすい点は中古マンション投資のメリットとなります。
しかし、不動産投資では表面利回りだけでなく、諸経費を考慮した「実質利回り」も考慮することが大切です。「高利回りだから良い物件」とは限らないため、実際に投資物件を探す際は経費や将来的なリスクも踏まえ総合的に判断するようにしましょう。
家賃収入がすぐに得られるか予想しやすい
中古マンション投資では、オーナーチェンジという形式で、入居者が付いたままの状態で売買されることがあります。このようなケースでは、購入後すぐに家賃収入を得ることができ、入居者を探すのに手間や費用をかけずに済みます。
また、現在空室であっても、過去の賃貸実績があれば家賃収入を予想することができます。
不動産は個別性が高いため、マンションといえども正確な家賃収入を見積もることは困難と言えます。しかし、中古であれば過去の実績に基づき高い精度で家賃収入を推測できるため、キャッシュフロー計画が立てやすく、投資が失敗するリスクも減らすことができます。
資産価値の減少が起きにくい
東日本不動産流通機構REINSの「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2019年)」によると、中古マンションは、築30年を過ぎた頃から平米単価の下落が緩やか、もしくは横ばいとなる傾向にあります。
新築あるいは築浅マンションが資産価値の急落リスクがある一方、中古マンションの資産価値の下落スピードが緩やかであると言えるでしょう。
このような中古マンションの特徴は、賃貸需要の減少が起きにくいエリアの選定や適切なリノベーションなどの市場ニーズに合わせた工夫を施すことによって、売却益も得られる可能性を高めることに繋がります。
2-2.中古マンション投資のデメリット
中古マンション投資のデメリットは、主に次のような点です。
- 不利な条件でのローンになりやすい
- 空室率が高くなるおそれがある
- 購入後に修繕費がかかりやすい
- 売却を見据える必要がある
以下で、詳しく説明していきます。
不利な条件でのローンになりやすい
建物部分の価格が占める割合の大きい区分マンションの場合、金融機関の担保評価が伸びず、ローンの条件が不利になる可能性が高くなります。
自己資金を多く用意する必要があったり、利率や返済期間などの条件が不利になり、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
空室率が高くなるおそれがある
中古マンションは、外観が経年劣化や設備の性能が低いなどの理由で、他の物件よりも入居需要が低くなる傾向があります。このような場合、近隣の同条件のより新しい物件に入居者が流れてしまいます。
あるいは、そもそも賃貸需要が少ない立地である場合、新しいうちは新しさを求めて入居者が付いたとしても、古くなることで賃貸需要の弱さが顕在化することもあります。
このように、中古マンションでは新築に比べて入居需要が落ちることから、空室率が高くなるおそれがあります。
購入後に修繕費がかかりやすい
中古マンション投資では、購入後に修繕費がかかりやすいのも大きなデメリットです。築年数が経過してくると、経年劣化によって修繕を行う箇所や頻度が多くなることが予想されます。
一棟マンションであれば、エレベーターや給排水設備など共用設備の大規模修繕には、多額の費用がかかります。区分マンションであっても、キッチンやユニットバスの修繕、交換はまとまった支出になります。入居需要を維持するためには、新しい設備に交換する必要が生じる可能性もありえます。
売却を見据える必要がある
中古マンション投資では、新築あるいは築浅に比べて賃貸収益を得られる残りの年数が短くなります。
賃貸収益によってキャッシュフローを維持するだけでなく、売却による初期投資額の回収を見込んで、トータルでどれだけの収益が得られるか、という観点から投資計画を立てる必要があるでしょう。
3.中古マンション投資の初心者が気を付けたい注意点
中古マンション投資で初心者が気を付けたい注意点は、物件選びの観点から次のような点となります。
- 好立地で資産価値の高い物件を選ぶ
- 物件の管理状況をチェックする
- 投資計画を十分に練る
3-1.好立地で資産価値の高い中古マンションを選ぶ
中古マンション投資では、築年数が経過しても入居需要を維持するために、物件本来の賃貸需要を支える好立地であることが重要になります。
将来的に人口が激減しないような大都市圏で駅近に立地している物件は比較的低リスクであり、初心者が最初に検討する物件として適していると言えます。
ただし、前述したように好立地な収益物件は利回りが低下する傾向にあり、低リスクである反面、収益性は劣ります。リスクとリターンのバランスをどのように設定するのか、マンション投資でどのような目的を実現させていきたいのか、再度検討してみましょう。
3-2.物件の管理状況をチェックする
購入後の修繕リスクに備え、購入前に物件の管理状況をチェックしましょう。修繕費の積立状況や大規模修繕の履歴などはできる限り把握しておきたいといえます。購入後の大規模修繕は、キャッシュフローを大きく悪化させる可能性があるので注意しましょう。
3-3.投資計画を十分に練る
中古マンション投資では、ローン条件が不利になり、空室リスクや修繕リスクが大きくなります。それらのリスクも考慮し、キャッシュフローや手元資金に余裕を持った投資計画を練りましょう。
また、売却による初期投資額の回収をするのか、保有し続けて相続を視野に入れるのか、長期的な物件の運用についても考慮に入れるとよいでしょう。
このような不動産投資の最終的な運用方法について考慮することを「出口戦略」と言い、最終的な利益を確定する重要なポイントとなります。売却するのであれば売却益のシミュレーションを行い、相続するのであれば相続税の課税額についても調査しておきましょう。
4.好立地の中古マンションを販売する不動産投資会社
最後に、好立地の中古マンションを販売する不動産投資会社を2社ご紹介します。
4-1.プロパティエージェント
プロパティエージェントは、東京23区・横浜エリアに集中したマンション開発・販売により入居率99.47%(2020年10月時点)の実績を有する東証1部上場企業です。扱う物件は新築マンションと中古マンションのハイブリッドとなっています。
好立地にこだわり高い入居率を保っている点はプロパティエージェントの大きな特徴と言え、始めてマンション投資を検討している方にとっても検討しやすい不動産投資会社と言えるでしょう。
中古マンション販売では、資産性・収益性・移動率の3軸から定量的に評価するssスコアリングを用いて、将来にわたって高い資産性を維持できる物件を厳選し仕入れている点もメリットと言えます。
しかし、好条件の立地にこだわっている一方で、物件価格は比較的高く高利回りのリターンを得にくい点はデメリットと言えます。プロパティエージェントでは、初心者向けの「0から始める不動産投資セミナー」を連日開催しているので詳細を確認してみましょう。
まとめ
中古マンション投資は、投資額が少なく、好条件な立地の物件を取得しやすい不動産投資の手段であると言えます。
しかし、新築物件と比較して、空室リスク・修繕リスクなどは高くなるため、購入前に物件の資産性や管理状況を調査し、綿密な資金計画を練ってから余裕を持った投資を行うことが重要です。
また、中古マンション投資は個別性が高く、シミュレーションを行っていても想定通りに進まないリスクのある投資手段です。まずは不動産会社が提供する不動産投資セミナーで情報収集をするなど、実際に投資を始める前に慎重に検討してみましょう。
苦労のわりに魅力がない…日本の不動産投資に未来はないのか?
コロナショックでも、住宅不動産価格に変動なし
2020年3月から4月にかけて、世界の金融市場をコロナショックが襲いました。株式、債券、そして米ドルなどの資産価値が急落したため、これらの資産に集中して投資していた人の中にはパニック的な売りも見られました。
一方、コロナショックの間、そしてその後の5月以降において、日本でもアメリカでも住宅不動産価格にはほとんど変化がありませんでした。不動産にも住宅、オフィス、商業施設などさまざまな種類がありますが、特に賃貸住宅については、短期的な景気の変動や金融市場の変化があっても、需要が大きく変動する(人が家に住まなくなる)ということはありません。
アメリカでは、各州における外出禁止令などの「ステイ・ホーム」の動きの中でオフィスや商業施設の賃貸市場は大きな影響を受けました。しかし住宅の賃貸市場については賃料滞納率こそ一時的に増加したものの、行政からの給付金などの施策もあり、すぐに収束に向かいました。
アメリカの住宅売買市場においても、取引件数こそ前年比で3割ほど減少したものの、成約日数や成約価格にはほとんど影響は見られませんでした。つまり、インカムゲイン・キャピタルゲイン両面において、株式などの資産と比べると極めて安定しているのが住宅系不動産投資の特長、優位性なのです。

そのことを、コロナショックであらためて実感した不動産オーナーは多かったのではないでしょうか。
なぜ、わざわざアメリカの不動産を買うのか?
「なぜ、わざわざアメリカの不動産を買うのか?」
「賃貸不動産に投資をした方がいいというのはわかる。しかし、どうしてわざわざアメリ
カの、それもダラスだの、アトランタだの、行ったこともないようなところの不動産を買
わなければならないんだ?」
そのようにおっしゃる投資家が、まれにいます。
「日本に住んでいるのだから、日本の不動産を買えばいいじゃないか」
これは一見もっともな意見です。では、なぜ日本ではなく、アメリカの不動産なのでしょうか。その理由として「日本での賃貸不動産投資は、苦労の割に魅力がない」ということが挙げられ得ます。これは、不動産会社に勤務する立場からの答えではありません。自分自身の資金で、実際に日本の不動産とアメリカ不動産の両方に投資をした私の経験から得た、正直な実感です。
米国では「中古物件」の価格が上がり続ける
新築不動産は買った瞬間から中古になってしまい、そうなるといきなり平均2割ほど価格が下落すると言われています。新築から中古になると価格が下がること自体は仕方がないかもしれません。
しかし、中古物件価格が、(都心の一部地域などのわずかな例外を除いて)その後上がることが(めったに)ないという事実は、価格が上がり続けているアメリカ不動産を知ってしまった今では、非常にむなしい感じがします。価格が下がっていくか、良くて横ばいのものをひたすら持ち続けるしかないのです。
それでも、入居者がいれば家賃収入は得られて、キャッシュフローは回ります。しかし、余裕を持った自己資金を入れていない場合、残債の大きさを考えると、得られた収入を自由に使ったり、他の投資に回したりすることは怖くてなかなかできません。特に、金融機
関の融資姿勢が厳しくなった2018年からは、アパートは買い手が不足しているため、私が持っているのと同じような築浅中古物件の価格が下落するのではないかと危惧しています。
もちろん今は売るに売れませんし、おそらく物件価格の下がり方の方が残債の減り方より大きいため、いくらキャッシュフローは回っていても、使うことができないのです。最悪、将来の残債割れにあてるために取っておかなければなりません。常にそうやって心配
を抱えているのは、非常にストレスを感じることです。
「日本の不動産投資」は夢がない!?
2018年からは、特に銀行の融資姿勢が厳しくなっている時期だという事情もあります。長期的に見れば金融情勢には波がありますから、将来は融資姿勢が積極化し、そこから物件需要が喚起されて不動産市況が良くなる時期もくるでしょう。
ただ、いつそうなるかは誰にも分かりません。いつか市況が良くなることを信じて、いまは「後始末をどうつけるか」ということを考えているのが、私の日本における不動産投資の状況です。せっかく投資をしているのに、下がり続ける物件の価格と残債割れを気にして、後ろ向きというか、後始末をつけることばかり考えなければならない日本の不動産投資は、やはり夢がないと言わざるを得ません。
株式会社オープンハウス ウェルス・マネジメント事業部
高山吏司氏
不動産会社は大事なパートナー…空室対策で入居者確保の裏ワザ
アパート経営にもビジネスパートナーとの連携が不可欠
賃貸経営にも「組織の力」が必要な時代になった
家主業は、資産運用の有効な一手法であることは間違いないが、決して楽に儲かるというものではない。不動産の売買によるキャピタルゲインを狙う投資ではなく、取得した不動産を、人々に生活の基盤となる住まいとして提供し、入居者の獲得、賃貸管理、法改正への対応、財務管理など、経営戦略を立て遂行し利益を上げる事業だ。
現在、家主業を取り巻く環境は大きく変化し、到底一人の力だけでは太刀打ちできなくなりつつある。そんな中で、安定した家賃収入を得るためには組織の力、すなわち体制づくりが重要になってきた。その体制をつくるためには、ビジネスパートナーである不動産会社やリフォーム会社との連携が必要だ。

家主業自体は、建物を取得し、入居者に貸し、対価として家賃を得るというシンプルな事業だが、家主業を取り巻く賃貸業界は意外に複雑だ。賃貸業界に商品やサービスを提供するために新規で営業をしようとする企業に話を聞くと、営業のやり方は意外と難しいという話を聞く。何がどう複雑なのか、賃貸業界の構造について紹介しよう。
賃貸業は主に3者が関わる。アパート・マンションを所有する家主、入居者募集や賃貸管理を行う不動産会社、そしてそのアパート・マンションを借りて住む入居者だ。3者がそれぞれどのように関係するのかを、第1段階「募集~契約」、第2段階「入居」、第3段階「解約・退去」の3段階に分けて紹介する。
第1段階
募集~契約
入居者の募集は不動産会社が行う。現在、募集方法の主となるインターネットの媒体に物件情報を掲載するのも不動産会社だ。
家主は、不動産会社に物件情報を提供、不動産会社は、部屋の写真を撮影して物件情報を不動産情報ポータルサイト(例えば、「ライフルホームズ」や「SUUMO」など)や自社サイトにアップする。
物件情報を見た入居希望者から問い合わせがあると対応し、「内見」と呼ばれる物件見学に同行する。内見後、入居希望者が気に入れば「申し込み」を受け付け、審査。審査後、不動産会社で「賃貸借契約」を締結する。賃貸借契約の際に「重要事項説明書」を読み上げて内容を確認するのは「宅地建物取引士」と呼ばれる有資格者で、契約を締結後、鍵を渡して入居となる。
なお、募集する際に不動産情報ポータルサイトに掲載する物件情報、すなわち広告の掲載費用はすべて不動産会社が負担する。家主には契約が成立するまでの募集コストは基本的にかからない。
入居者が家賃以外にどんな費用を支払っているか
入居者が契約するのは賃貸借契約だけではない。「家財保険」と、近年は「家賃債務保証」の契約を結ぶケースが多い。
「家財保険」は、入居者が契約期間中に、例えば、地震でテレビが倒れて壊れたり、盗難に入られたりなど入居者自身の家財を補償するだけでなく、「借家人賠償責任保険」も付帯されている。「借家人賠償責任保険」は、家主に対して、原状回復のための修繕費用やその他の賠償責任、水漏れなど居住者同士のトラブルに備える第三者への賠償責任を補償の対象としている。
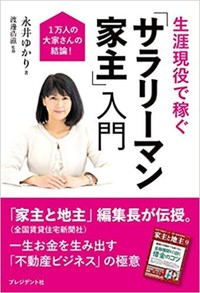
「家賃債務保証」とは、入居者が万が一家賃の滞納をした際に、保証会社が入居者の代わりに家賃を立て替える制度だ。従来は連帯保証人を立てることが難しい人が利用する制度だったが、近年は、不動産会社が入居希望者の審査や滞納督促業務を家賃債務保証会社にアウトソーシングして代理店手数料を得られることもあり、賃貸借契約と併せて入居者に加入してもらうケースが増加している。
この2つの契約には、家主は直接関与せず、不動産会社が、それぞれ保険会社や家賃債務保証会社の代理店として入居者と契約する。ただし、家賃債務保証については、入居者との契約はないが、家賃債務保証会社と家主の間で「家賃債務保証委託契約」を結ぶ。
代理店手数料は、不動産会社にとっても大事な収入源になっている。この2つ以外にも、2018年12月に起きた北海道のアパマンショップ店舗の「ガス爆発」で有名になった消臭剤、浄水器レンタルやカートリッジの販売、24時間緊急駆け付けサービスなどの加入を入居者に促し、代理店収入を得ているケースも少なくない。
家主は、このような付加サービスの契約には直接関与していないとはいえ、自身の所有する賃貸住宅の入居者が、家賃以外にどんな費用を支払っているかは、きちんと把握をしておいた方がいいだろう。
契約時には、家主は入居者からはお金を受け取り、不動産会社にはお金を払うことになる。入居者から受け取るお金は、「敷金」「礼金」「前家賃」「当月家賃」であり、不動産会社に支払うお金は、「仲介手数料」と「広告料」だ。
近年、エリアによっては敷金や礼金をゼロにする物件も増えつつある。これらをゼロにして募集すれば、当然ながら、この収入はない。
一方、支払うお金については、不動産会社によって異なる。家賃1カ月分を仲介手数料として設定する場合が多いが、近年は0.5カ月分のケースもある。
「宅地建物取引業法」には、「貸主と借主それぞれから受け取る仲介手数料は賃料の半月分以内とする。ただし、依頼者の承諾があればどちらか一方から賃料の1カ月分以内を受け取ることができる」との記載がある。つまり、仲介手数料は本来0.5カ月分だが、仲介を依頼する家主や入居者が承認すれば、不動産会社は家賃1カ月分を受け取ることができるということだ。
広告料については、こちらも同じように「宅地建物取引業法」では、基本的に0.5カ月分であるが、家主が承認すれば、1カ月分まで支払うことができる。ただし、近年は「AD」という名のもとで、広告料と同じような扱いの手数料を要求する不動産会社もある。それを逆手にとり「ADを多く払うので入居者を決めてほしい」という家主もいる。
「AD」は業法的に問題があると指摘されるが、現状では空室数が増えている中、家主の入居者獲得対策として用いられるケースも少なくない。
永井ゆかり
「家主と地主」編集長
中古不動産投資のリスクを軽減するには?現地調査や内見のポイントを解説
1.中古不動産投資における現地調査・内見の重要性
不動産投資では、投資家自身が居住しないことや、優良物件は競争相手が多いことなどから、現地調査や内見をせずに机上の書類だけで購入を判断することも少なくありません。
しかし、中古不動産投資では、中古であることのリスクに加え、売主が個人であることが多く、物件について十分な情報が揃っていない場合もあります。
机上の書類で割安の優良物件と判断できたとしても、割安であることの理由がある可能性があります。建物の実際の劣化状況や入居者の属性など、現地で調査をしないと分からない情報も数多くあるため、出来るだけ事前の現地調査を行うことを検討しておきましょう。
2.周辺環境の調査ポイント
中古不動産投資では、経年劣化によって建物の価値が低下しているため、賃貸需要、資産価値の観点から周辺環境をチェックすることがより重要になります。
以下では、周辺環境の調査ポイントとして、交通機関・生活施設へのアクセスといったプラス面と、嫌悪施設の有無・治安状況といったマイナス面に分けて説明します。
2-1.交通機関・生活施設へのアクセス
最寄駅や最寄りのバス停までのアクセスは、販売資料などに記載されていても道路状況によって変化することがあります。可能な距離であれば実際に歩いてみるなど、入居者目線での利便性を検証してみましょう。
また、生活施設・公共施設へのアクセスも重要です。スーパーやコンビニ、ドラッグストア、などの生活施設に近いこともプラスになります。商業店舗は移転する可能性も高いので、学校や銀行、公園など移転しにくい公共施設へのアクセスも調査しておきたいといえます。
賃貸需要の観点からは、工場や大学などの賃貸需要を構成すると考えられる施設があるかどうかもチェックするとよいでしょう。賃貸需要については、地元の賃貸不動産業者に直接ヒアリングするのも有効です。
2-2.嫌悪施設の有無・治安状況
周辺環境にマイナスの影響を与える嫌悪施設がないかどうかも調べておきましょう。例えば、近隣に墓地霊園や火葬場、ゴミ処理場などがあると、環境面からはマイナスとなる可能性があります。
また、治安状況について、近隣に風俗店やスナック、空き家やゴミ屋敷などがあると悪影響が出るおそれがあります。実際に周辺を歩いてみることで、入居者が周辺地域の治安状況についてどのような印象を持つか、肌で感じてみることも大切です。
3.土地の状況の調査ポイント
不動産は経年劣化によって全体の資産価格に占める土地の価格割合が徐々に大きくなる資産です。そのため、その土地が将来的にも売却しやすく資産価値があるかどうか、という観点から、土地の状況を確認することも重要です。
以下では、土地の状況の調査ポイントを、道路状況、土地の形状、境界状況の3つの側面から解説します。
3-1.前面道路の状況
不動産の土地の状況を確認する上で「建築基準法上の道路に2メートル接するという条件を満たしている敷地であるかどうか」、という点は非常に重要なポイントです。これを満たす敷地でない場合、原則的に建物の再建築ができない土地となり、資産価値面から問題のある土地になります。
不動産仲介業者が確認しているポイントですが、旗竿地などでは接道幅が2メートルぎりぎりというケースもあり、自分でも現地を見てしっかりとチェックしておきましょう。
また、敷地が接している道路の幅についても確認しておきたいポイントです。幅員4メートル未満の道路の場合、将来の再建築時に中心線から2メートルの幅を確保できるよう、敷地を道路に提供(セットバック)しなければなりません。
このセットバック部分につき、実質的には敷地面積が狭いことになり、その分の資産価値が落ちるといえます。
さらに、道路の種類が私道であり道路の持分を持っていないなどの場合は、ライフラインを道路から敷地に引き入れる際に、私道所有者に掘削の承諾を得なければならないことがあります。仲介業者を通して登記簿謄本を確認するなど、注意しておきましょう。
3-2.土地の形状
土地の形状も、現地調査で確認したい事項といえます。土地の平面的な形状は、公図などの書類から分かりますが、立体的な形状は現地でないと分からないことがあります。
敷地のなかや隣地との間に高低差があると、建築費が嵩むことがあるので、チェックしたいポイントといえます。
3-3.境界状況
敷地の境界状況も、土地について問題となりやすい事項であるため、現地で調査しておきたいポイントです。境界石の有無を確認し、明確に境界が確定しているか確認しておくことが大切です。
確定測量が行われ、境界標が埋まっている場合は、隣地との間に越境物がないかどうか確認しておきましょう。越境物があると、その取扱いを巡って隣地とトラブルに発展する可能性があります。
確定測量を行わない場合には、隣地との間に境界について紛争がないかどうか、仲介業者を通してヒアリングするなどして確認しておくとよいでしょう。
4.建物の状況の調査ポイント
中古不動産投資では、経年劣化がある建物を購入することになります。そこで、建物の現地調査では、目視で分かる範囲で経年劣化の度合いをチェックします。また、賃貸需要の観点から、入居者目線で建物の全体的な印象を把握することも大切です。
室内については、建物に重大な問題があるかどうか、リフォーム費用がどれぐらいかかるかという観点から調査を行うとよいでしょう。
4-1.外観の状況
建物の経年劣化の度合いについて、基礎や外壁の剥がれ、ひび割れ、タイルの浮き沈み、水染みなどがないかどうかをチェックします。
特に、基礎に大きな剥がれやひび割れがあると、建物の耐震性や強度に問題が生じている可能性もあります。大きな水染みがある場合も、内部に雨水が侵入して劣化が進んでいる可能性があり、注意する必要があるといえます。
このような問題があると、修繕には多額の費用がかかることが予想されます。該当する劣化を発見した場合は、購入前に専門家によるインスペクションを依頼するなどの対策を講じた方がよいでしょう。
賃貸需要の観点から、共用部などを含めた建物外観の清潔感も重要です。共用部やエントランスに入居者の私物やゴミなどがないか、陽当たりは充分か、などをチェックしましょう。
4-2.室内の状況
室内については、まず、雨漏りと床の傾きをチェックしましょう。もしこれらがあると、建物の構造に問題が生じている可能性があり、修繕費用が大きくなることが予想されます。臭気についても、排水設備に問題があるかどうかを知るために、調査したいポイントといえます。
リフォーム費用の観点からは、コストが嵩みやすいシステムキッチンやユニットバスの状態をチェックしましょう。傷みがひどかったり、清潔感に欠けたりするような状態であれば、交換することになり、一部屋につき数十万円のコストがかかることになります。
5.中古不動産を販売する不動産会社の選び方
中古不動産は新築物件と比較して、売主と買主双方にリスクの大きい取引となります。そのため、利回りや家賃相場など机上のデータだけでなく、紹介物件の事前調査を徹底している不動産会社を選ぶことが重要です。
例えば、中古マンション販売を手掛ける「プロパティエージェント」では、資産性・収益性・移動率の3軸から定量的に評価するスコアリングを用いて、将来にわたって高い資産性を維持できる物件を厳選し仕入れています。
また、建物管理事業を備えているため、中古マンション投資のリスクの一つである購入後のコストについても、当該物件の将来にわたり物件の資産性を維持するための必要なコストを見通すことが可能です。
中古不動産投資では、現地調査では見抜けない隠れた欠陥が購入後に見つかることも少なくありません。紹介物件の事前調査を徹底している不動産会社を選ぶなど、販売元の不動産会社選びも慎重に行いましょう。
まとめ
中古不動産投資の現地調査や内見でチェックしたい主なポイントとして、資産価値の観点から、周辺環境の利便性や土地の状況、建物の重大な問題の有無、経年劣化状況、という部分をご紹介しました。
特に、土地の状況について、接道に関する状況は資産価値に大きな影響を与えかねないため、現地調査においても重点をおき、確認しておきましょう。
また、資産価値のみならず、賃貸需要の観点から入居者に与える印象にも配慮することが大切です。建物の状況については、室内のリフォーム費用を見積もることも忘れないようにしましょう。
アメリカ不動産投資…多発する自然災害に、どう備えるべきか?
アメリカの自然災害リスクは地域によって大きく異なる
前回の記事では、アメリカの自然災害リスクについて解説しました。今回は日本に住む私たちがアメリカ不動産投資を行う上で、現地の災害リスクにどう向き合うべきかを解説します。
アメリカは日本の約26倍もの国土を有する広大な国です。西海岸北部のシアトルから東海岸南部のマイアミまでは飛行機で約6時間もかかります。当然、州・地域によって自然災害の影響は大きく異なり、毎年被害を被っている地域もあれば、自然災害とはほぼ無縁の地域もあります。
FEMA(アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)が発表している「自然災害が多い州」ランキングでは、1位はカリフォルニア州、2位テキサス州、3位オクラホマ州。反対に「自然災害が少ない州」は、1位がデラウェア州、2位がロードアイランド州、3位はサウスカロライナ州となっています(※1)。
ちなみにFEMAが1953年から調査している災害発生件数を見てみると、自然災害が最も多いカリフォルニア州の発生件数は255件/年、最も少ないデラウェア州は21件/年であり、単純計算でカリフォルニア州はデラウェア州の12倍も自然災害が発生していることがわかります(※2)。
大きな州では、「都市によっては安全」なことも
とはいえ、自然災害発生上位のカリフォルニア州やテキサス州は面積が大変広いため、州全体で自然災害リスクが高いかというと、そうとも言い切れません。実際、テキサス州北部はトルネード・アレイ(竜巻街道)と呼ばれる地域に含まれますが、テキサス州西側に位置する都市は比較的トルネードの被害が少ないことで知られています。
また、自然災害が多い地域では、リスクに備え、物件自体も進化しています。昨年、カナダの建設会社が発表したハリケーンに強い家には、壁にペットボトル60万本分の再生プラスチックパネルが使用されており、強度はカテゴリー5の強さのハリケーンにも耐えられるほどだといいます(※3)。
数年前のハリケーン「イルマ」による洪水被害が大きかったフロリダ州では、高床式の家やポンプ機能を備えた建物が増加しています。マイアミ都市圏は、ハリケーンに加え、「キングタイド(極端な大潮)」によって地下水が地上にあふれる現象が深刻化しているため、30〜40年後には、嵐に強い高床式のタワーマンションが主流になると考えている建築家もいます(※4)。
こうした都市単位の災害リスクや、物件の耐久性などの詳細な情報はなかなか日本からでは調査しづらいものです。正確な情報を入手するためには、現地事情に詳しいパートナーを見つけるのが得策かもしれません。
リスクヘッジとしての「保険加入」は重要
自然災害は予測できないものです。特に近年は異常気象により、以前は考えられなかった規模の被害が発生するケースも相次いでいます。過去のデータから自然災害の少ない地域、リスクの少ない物件を選んでも、安心とは言い切れません。備えとして、保険への加入は重要と言えるでしょう。
実は、アメリカの一般的な不動産保険(Home Owner’s Insurance)は、必ずしも洪水やハリケーン、地震などの自然災害を全般的にカバーしているわけではありません。
山火事も含めた火災による被害や、雷や風による被害(原因がハリケーンであっても)は対象になる場合が多いようですが、同じハリケーン被害でも洪水は対象にならない場合が多いようです。また、洪水はカバーしていたとしても、下から上がってくる水、浸水などの条件は対象にならないこともあるようです。
自然災害リスクに細かく備えるためには、一般的な不動産保険加入のほかに、洪水保険、ハリケーン保険、地震保険などを個別に検討することも必要だといえます。
しかし、どの保険がどこまでの災害をカバーしているかは、各社で細かな違いがあるため、事前に保障条件をしっかりチェックすることが欠かせません。リサーチが難しいような場合は、例えばオープンハウスでも災害保険を含んだアメリカ不動産の保険プランを提案しているので、日本の不動産投資会社にまずは話を聞いてみるのも、一つの手です。
リスクとリターンのバランスを常に考えることが重要
アメリカ現地の自然災害リスクを考慮しながら物件を選ぶのは、日本人にとっては簡単なことではありません。
重要なのは、投資を行う際に、常にリスクとリターンのバランスを考えること。いくら災害リスクの低い物件でも、そもそもの投資価値が低ければ意味がありませんし、住民数が増え不動産需要が高まっている地域なら、災害リスクが多少高くとも「買い」だとみなせます。
また災害保険に入るのが望ましいといっても、低価格な物件に高額な保険をかけるのは、コスト的に不釣り合いになってしまいます。
自然災害に対する備えとして最も重要なことは、リスクをいたずらに怖がらないこと。そして正確な情報をもとに正しく警戒すること。常にリスクとリターンの両面を天秤にかけながら、的確な判断を下していきましょう。
あえて「事故物件」を見せて…不動産営業マンの恐ろしい手口
「実際には売れなくとも集客力がある」物件とは?
物件には様々な特徴があります。中には、「実際には売れなくとも集客力がある」という物件も存在します。こうした物件は広告向きです。なお、ここでいう広告とは収益不動産専門のポータルサイトに掲載される情報を指します。
たとえば、大きなデメリットを抱えていても利回りが突出して良い物件は、ポータルサイトなどの検索でヒットする可能性が高いという強みを持っています。「ほとんど人が住んでいない」とか「事故物件(自殺や事件があった部屋。賃貸では入居者に、売買では売主に対する告知義務がある。なおこれを告知事項といいます)である」といった重大な欠陥を抱えているにもかかわらずです。
なぜなら告知事項は、紙資料には詳細が記載されるものですが、不動産業界の商慣習上、ポータルサイトでは詳しく触れないのが一般的だからです。不動産会社は、こういった物件を不動産投資家を惹き付けるための集客ツールとして使います。
不動産投資家が検索キーワードとして入力しそうな「地域」や「価格帯」、「物件規模」などに当たりをつけて広告を出していくのです。並べている情報は、その不動産業者と肌が合うかを判断させるために用意しているだけで、本気で売るためのものではありません。
つまり、買い手となる不動産投資家の購買行動を先読みしているわけです。

(画像はイメージです/PIXTA)
広告とは別の物件を紹介するのが、物件営業の基本!?
集客力が最も強い要素となるのが、「利回り」です。ですから多少欠陥を抱えていても利回りが高ければ広告を出し、それをフックに顧客を自社に呼び込みます。そしてそこから、「どのような物件をお探しですか?」と営業を開始するわけです。
利回りの高い物件を入り口として顧客を集め、広告とは別の物件を紹介していく。これが不動産会社における物件営業の基本です。
「未公開情報」として売りに出し、物件の価値を高める
物件を高値で売るためには、情報の出し方も重要です。具体的には物件の情報を未公開にすることで、その希少価値を高めて最高値で売るのです。
物件情報の公開における、基本的な知識を解説しましょう。まず「公開情報」とは、一般的に「レインズ(指定流通機構)」に出ている物件を指します。「レインズ」に出て公開情報となった物件は、取扱不動産会社以外の会社でも売買仲介で取り扱えるようになります。
「未公開情報」はその逆です。「レインズ」に掲載される前の、一般に公開されていない物件を指します。
未公開物件は情報の希少性が高いため、不動産投資家に好まれる傾向があります。また誰もが見られる情報でないことから、ライバルが少ないと考える投資家も多くいます。確かに、いち早く未公開情報を手に入れることができれば、有利に買い進めることができるのは事実です。
また売りにくい物件は、未公開とすることで状況を打破できることもあります。公開情報にすると、何年も売れ残ってしまい、「他の人が手を出さないということは、何か問題がある物件なのだろうか、自分の判断は間違っているのでは」という購入者心理が働きます。前回ご紹介した広告向け物件のように、顧客を集めるためのツールとして活用された挙句、放置される可能性もあります。
情報を未公開にすることで、こういったリスクを回避しつつ、希少価値を高めていくことが可能なのです。
筆者の経営する会社でも、市場に出ていない未公開物件を中心に取り扱っています。基本的に「レインズ」には出しません。売却を検討するお客様には、必ず「市場に出る前に情報をください」とお伝えしています。そのほうが高く売れるということを、長年のキャリアの中で実感しているからです。
多くの不動産投資家は、未公開の物件こそ優良と捉える
実際のところ、未公開だけが良い物件かといえば、そんなことはありません。公開情報の中にも、数は少ないですが良い物件は存在します。
たとえば、地方の不動産会社が地主から相続対策のために購入した、東京の区分マンションの売却を依頼されたケース。「現地の相場や商慣習を知らない自分たちよりは、東京の業者に任せたほうが売りやすいだろう」と考えて情報を公開します。
あるいは賃貸管理の専門会社が、不動産オーナーからアパートの売却を相談されたケース。売買を専門に行っていない会社は、相場を知りません。必然的に値付けを行う力がありませんから、適当な安値で情報を公開することがあります。もしくは相続などを理由に地主が売り急いでいるとなれば、投げ売りに近い、安い価格で情報が公開されることもあります。
こうした場合には、安くて良い物件が「レインズ」に掲載されます。ですから、公開物件の質が悪いとは一概に言い切れません。
ただし多くの不動産投資家は、未公開の物件こそ優良と捉えています。物件を高く売るに当たって、その希少性は大きな強みになります。
過去に殺人事件が…?「危ない物件」を一発で見破る方法
反社が入居していたり、過去に殺人事件があったり…
収益物件は高額な投資商品です。高額であればあるほど、そこには万が一のリスクが内在します。なかでも最も大きなリスクは、物件について「わからない」ということから生まれます。
例えば、反社会的な組織の関係者が入居していたり、そのような事務所が隣接していたり、過去に殺人事件があったり、入居者が架空のもので取得後大部分が一斉に退去してしまったり、とんでもない滞納者がいたり・・・という可能性があるのです。これらは過去に筆者の会社で管理を請け負った物件で実際にあった事例です。

(画像はイメージです/PIXTA)
こうしたことが「わからない」ままで買うことは怖いことです。たとえ購入前に想定利回りや返済計画などを緻密にシミュレーションしたとしても、「わからなかった」大きな盲点が原因となって、予定していた収支計画が根本から狂ってしまうこともあるからです。
中古の収益物件は、原則として購入する際に一部屋一部屋の中まで見ることができません。ですから、物件の入居者や周辺環境までしっかりと情報を持っている不動産会社から買う必要があるのです。重要なのは、物件を紹介してくれる不動産会社と、その物件および売り主との関係です。
売り主から「直接」売却の依頼を受けている会社か?
あなたに物件を紹介してくれる不動産会社が下記図表の①のように、直接売り主から売却の依頼を受けている関係であれば、物件の詳細まで確認できる可能性が高くなります。
さらに業者Aが管理まで請け負っている場合は、物件の内容をほぼ理解していると考えていいでしょう。なぜなら、管理をしているということは、毎月の賃料回収から入居者の対応を行っているので滞納者や入居者の属性を把握できるからです。
逆に②、③の場合は注意が必要です。特に業者Aと業者Bの間に面識や取引関係がない③のような場合は、物件の情報が業者Bに伝わっていないケースが多いのです。なぜならAの立場は売り主がお客様であり、物件を売ることが目的になるので、都合の悪い情報は出さないことがあるからです。
ですから、物件を紹介してくれる会社がどこまで物件のことを理解しているかが重要です。さらにいえば、業者が事実を知っていたとしても買い主に正直に伝えるかどうかは別の問題です。極論すれば、結局のところその会社(担当者)が信頼に値するかという点に行き着きます。繰り返しになりますが、物件選びは会社(人)選びなのです。
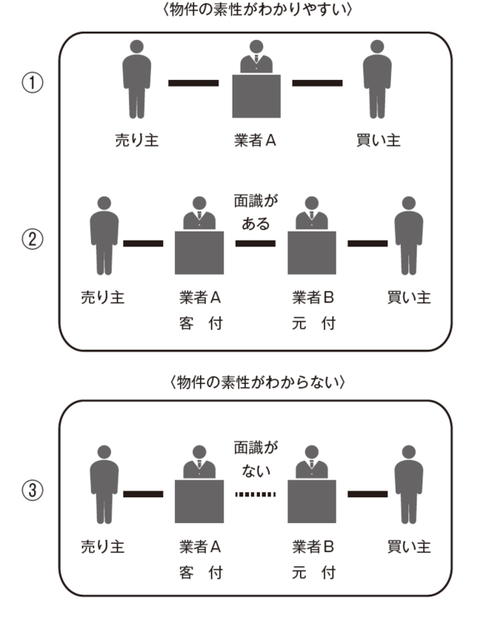
「利益を最大化できるか」が物件選びの基準に
物件を選ぶにあたっては利益最大化という視点を外さないことが基本です。繰り返しになりますが、収益物件の活用における利益は以下のとおりです。
利益=【売却金額-取得金額+収入-支出】
収益物件はあくまでもオーナー社長自身および会社を守るためのツールとして活用すべきものです。そのためには、このツールを用いて利益を最大化する必要があります。
一方で、収益物件は不動産です。不動産を買う際には、新しくてきれいなものが良いとか、おしゃれな建物が良いとか、港区にある物件が良いなどという買い主の主観的な評価も入るものです。しかし、収益物件は自分が住みたいかどうかよりも利益を最大化できるかどうかで判断するものです。このポイントを外してしまうと、成功する物件選びができなくなってしまいます。
「自分が住みたいかどうか」は関係ない
自宅は極論すれば自己満足の世界ですから、いくらお金をかけて自分の好みの場所に好みの建物を建てても何の問題もありません。一方、不動産投資はあくまで採算です。
例えば家賃5万円のアパートを対象としたときに、自分の感覚だけでは絶対に良し悪しはわかりません。自分から見ればボロボロに思えるようなアパートにも一定の需要があることが想像できないのです。
生活レベルに応じて人が求めるものは違います。年収1億円のオーナー社長と学生では生活環境が違うのです。自分が住みたいかどうかではなく、きちんと利益が出るかどうかという基準で物件を選ぶ必要があります。
融資を利用しやすい土地活用の方法は?不動産投資・事業ローンの比較も
1.不動産投資ローンか事業ローンか
土地活用における金融機関の融資は「不動産投資ローン」か「事業ローン」なのかで審査基準が異なります。これらのうち、実物不動産を担保設定できるため、不動産投資ローンの方が審査基準は低い傾向があります。
土地活用では、土地の上に、収益を生み出せる建物や装置などを建築・設置し、事業をおこなって収益を得ます。事業ローンであれば、その事業自体の収益性を審査し、月々の返済原資をその事業収益から充当できるかどうか、を重視して融資審査をおこないます。
これに対して、不動産投資ローンでは不動産賃貸業としての収益性だけでなく、不動産の担保性、個人の属性などを総合考慮して融資がおこなわれます。事業としての収益性も評価対象となりますが、他の評価が良ければ審査に通る可能性を高めることが可能です。
以下、不動産投資ローンと事業ローンの審査基準について比較します。
1-1.不動産投資ローンの審査基準
不動産投資ローンでは、対象不動産の収益性と担保性のほか、融資希望者の属性が審査対象となります。
対象不動産の収益性と担保性については、収益還元法と積算法と言われる評価方法が用いられますが、特に積算法の評価を重視する金融機関が多い傾向があります。
積算法は、不動産を土地と建物に分け、それぞれの現在価格を合計して評価する方法です。土地については路線価、建物については再調達価格を用いて算定します。
収益還元法は、その不動産から生じる家賃や地代などの純収益を将来にわたって予測し、その総和を推計して評価します。
このほか、家賃収入からローン返済できない場合の返済原資として、融資希望者の給与収入や年齢、勤続年数、勤め先企業の業績等の属性が考慮されます。
【関連記事】不動産投資ローンを組むメリット・デメリットは?金利を下げるコツも
1-2.事業ローンの審査基準
事業ローンは、事業の「安全性」、「収益性」、「成長性」などを財務諸表や事業計画書などから測定して審査をおこないます。特に、入口審査としての「安全性」は厳しく審査され、財務諸表を下に返済能力・返済財源、担保力、信用力などを判断します。
「安全性」の審査をクリアすると、事業計画を下に将来の事業の「収益性」や「成長性」を審査し、具体的な融資金額や利息などの融資条件を決めていくという流れになります。
創業融資などの公的支援に沿った融資を除けば、事業ローンは、「安全性」を証明できる実績を上げて、かつ、将来の「収益性」や「成長性」についても合理的な根拠があるようでなければ、審査を通過することは難しい、といえるでしょう。
2.不動産投資ローンが利用可能な土地活用
事業ローンよりも不動産投資ローンの方が融資を受けやすいことが分かりました。そこで、融資を受けやすい土地活用方法として、不動産投資ローンを利用できる2つの土地活用を紹介します。
なお、民泊やコインパーキング、コインランドリー、店舗経営などの土地活用は、不動産投資ローンの枠ではなく、事業ローンの枠での審査となり、融資を利用する難易度は上がるといえます。
2-1.賃貸アパート経営
賃貸需要が見込めるエリアである必要がありますが、賃貸アパート経営であれば、不動産投資ローンを利用して始めることができます。マンション経営の場合、広めの土地であることも条件になります。
路線価が安く担保評価が低い土地であっても、土地活用として賃貸アパート・マンション経営をするのであれば、主な初期投資は建物の建築費用となり、投資コストに対する収益性は高くなる傾向があります。
土地と建物両方を対象として不動産投資ローンを組むことと比較して、不動産投資ローンを組みやすいといえます。
ただし、大規模な賃貸アパートを建築する場合、融資額では足りずに多額の自己資金が必要となるケースもあります。また、融資が下りたとしても、想定した入居率が保てないまま事業自体が失敗してしまうリスクについても慎重に検証することが大切です。
実際に賃貸アパートを建築する前に、該当エリアで賃貸需要が見込めるかどうか調査をすることから始めてみましょう。
例えば、「アイケンジャパン」というアパート経営の不動産会社では、対象エリアを主要駅15分以内、入居者のターゲットはアパート造りの基準を物件選びの目線が厳しい社会人女性に絞って、入居率99%以上(2020年6月時点)の実績を実現しています。このようなアパート経営会社へ事前に相談し、アパート経営に適したエリアかどうか確認しておくことも有効な手段となります。
アイケンジャパンのセミナーに参加をすると、アパート経営成功の秘訣が分かる詳細資料やアパート経営に関する書籍を無料でプレゼントしてもらえますので、まずはアパート経営について学んでから始めたいという方や情報収集だけでもしてみたいという方は検討してみるのもよいでしょう。
【関連記事】アイケンジャパンの評判・口コミ・資料請求
2-2.賃貸戸建経営
賃貸戸建経営も、近年、土地活用の一つとして認知度が高まっており、手ごろな施工プランを用意している建設会社もあります。
賃貸アパート経営より収益性は落ちるものの、初期投資費用を抑えられることから、不動産投資ローンも利用しやすいでしょう。賃貸戸建の供給は少ないことから、家賃も高めに設定しやすく、土地の形状や立地などの条件がうまく揃えば、収益性が高くなることもあります。
【関連記事】賃貸に向いている戸建てとは?判断基準やポイントを投資家が解説
3.事業ローンでも比較的融資を受けやすい土地活用
事業ローンを利用することになり、不動産投資ローンより審査は厳しくなりますが、比較的融資を受けやすいといえるのが、太陽光発電投資です。
太陽光発電投資は、20年は固定価格での買取が保証された売電収入があり、一定期間において定額のキャッシュフローが見込めるため、金融機関から評価される傾向があります。
さらに、土地活用の事業として認知されている手法であることから、金融機関のなかには太陽光発電投資向けのローン商品を用意していることがあります。ローン商品がある金融機関では、太陽光発電投資事業への融資実績があるということになり、比較的融資が受けやすい土地活用方法と言えるでしょう。
ただし、太陽光発電の買取制度の買取価格は下落傾向にある点には注意が必要です。太陽光発電を検討する際は固定買取価格だけを重視するのではなく、設備投資にかかる費用や発電量の予測など、その他の面から多角的に判断することが重要になります。
【関連記事】太陽光発電投資のメリットとデメリットは?2020年以降のFIT制度も解説
太陽光発電だけでなく、その他の土地活用方法と並行して比較したい場合は「HOME4U」の土地活用サービスも利用を検討してみましょう。こちらのサービスでは最大7社まで土地活用の収益プランを比較可能なうえ、自分が選んだ企業以外から連絡がくることは一切ありません。
金融機関の融資評価を優先するのではなく、まずは土地のエリア特性に適した活用方法を検討することは重要です。まずはどのような土地活用方法が適しているのか土地診断を受け、様々な活用方法から適した事業内容を比較検討してみましょう。
【関連記事】HOME4U(土地活用)の評判・口コミ
まとめ
金融機関の融資を利用しやすい土地活用は、不動産投資ローンを利用できる賃貸アパート・マンション経営や、賃貸戸建経営であるといえます。
事業ローンは不動産投資ローンよりも審査基準が厳しいですが、固定買取制度により定期的なキャッシュフローが見込める太陽光発電投資であれば、比較的融資は利用しやすいといえるでしょう。
ただし、金融機関の融資利用を優先して土地に適していない活用方法を検討してしまうと、思わぬ事業リスクを被ることもあります。まずは所有している土地の特性を理解し、適した活用方法を検討することから始めてみましょう。
プロパティアクセス 海外不動産取引総額が63億円を突破!
東京、シンガポール、マレーシア、フィリピンを拠点とし、「世界不動産の流動化で投資家に明るい未来」をビジョンに掲げる、Property Access(プロパティアクセス)株式会社(代表取締役:風戸裕樹)は、2019年6月から開始をしたコンサルティング事業における売買取引総額が63億円(個人投資家への販売総額)を突破しました。集計期間は2019年6月から2020年10月末までの17ヶ月です。
- コンサルティング事業を立ち上げた経緯
最も信頼される海外不動産の取引の場を目指す当社は、2018年3月の創業以後、プラットフォーム構築としてのメディア事業で海外不動産の投資情報を大規模なイベントや自社オンラインメディアを通じて日本の投資家の皆様に提供してまいりました。主催イベントでは過去4回で3000名超の方が来場。紹介した国は、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、キプロス、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、カンボジア、インドネシア、ベトナム、ミャンマーの13カ国に及びます。一方で東南アジア新興国における不透明で不安定な実取引上の課題を解決すべく、2019年6月からフィリピン及びマレーシアにおいて取引に関するコンサルティング事業を開始しています。

- コロナ禍で海外投資取引の増加
資産100億・不動産投資家「17行以上の金融機関と付き合ってわかったこと」
不動産を買うにあたり、大きな壁となるのが資金調達です。金融機関の融資が受けやすくなる方法について、前回前々回に引き続き、資産100億円投資家の玉川陽介さんに聞きました。
ベトナム不動産投資「契約書すら見ない」平和ボケ日本人の驚愕
安易な儲け話に乗っかり、泣きを見る日本人が続出
2020年10月に執筆した、日本人によるベトナムでの不動産投資トラブルの事例を紹介した記事、『ベトナム不動産投資、日本人がやらかした「購入トラブル」の例』の反響が大きかったため、今回も実例をあげ、引き続き注意喚起を行いたいと思います(※プライバシーに配慮し、一部変更している部分があります)。

話が違う!「年利10%で10年運営のはず」と怒るも…
【実例1】現地の日本人の紹介で投資用物件を購入。保証に惹かれたが…
知人からの紹介で会った現地在住の日本人に、リゾート地域のコンドミニアムの購入を勧められる。紹介した知人も購入しているとのことで、「コンドミニアムをホテルとして、年利10%の条件で10年運営する」という保証付きの条件に惹かれ、購入を決意。年2回の支払いで契約した。ところが、購入翌年の支払いはあったものの、2年目以降から支払いが滞ってしまい、交渉するもらちがあかない。
知人からの紹介で会った現地在住の日本人に、リゾート地域のコンドミニアムの購入を勧められる。紹介した知人も購入しているとのことで、「コンドミニアムをホテルとして、年利10%の条件で10年運営する」という保証付きの条件に惹かれ、購入を決意。年2回の支払いで契約した。ところが、購入翌年の支払いはあったものの、2年目以降から支払いが滞ってしまい、交渉するもらちがあかない。
その後の経過と対応
相談を受けた筆者は、最初に購入経緯と契約書を確認しました。すると、購入者本人は「コンドミニアム購入後、ホテルとして運用。賃貸保障あり」との認識だったのですが、実際には「コンドテル契約」でした。コンドテル(Condotel)とは、「ホテル」と「コンドミニアム」を合体させた略語で、部屋を所有するオーナーがホテル運営者に貸し出し、稼働率に応じた一定の利益を得られるしくみのことです。ホテルコンドともいいます。
この契約では、コンドミニアムの使用権は開発会社にあるとされており、運営会社も開発会社の関連会社だと思われます。
相談者に物件を勧めた現地在住の日本人は、開発会社関係のベトナム人ブローカーからの紹介で、販売促進を行っていました。確認時は、ホテルというよりもAirbnb運営でしたが、運営状況が厳しく約束した配当が出せない状態でした。
筆者が契約書の内容を精査したところ、契約書はベトナム語のみで書かれているほか、驚くべきことに、購入者は、販売仲介した日本人ブローカーの通訳者から契約書の内容を聞いただけで契約書を締結していたこともわかりました。ベトナム語で書かれた契約書の内容は、上述したようにコンドテルでの契約締結であり、内容も販売側に有利なものとなっていました。
ちなみにベトナムでは、コンドテルの事業に関して明確な法律はなく、2020年10月現在、合法・非合法が判断できない、いわゆるグレーゾーンの状況にあります。このケースは、法的に対応しても時間と費用だけがかかってしまう、非常にむずかしいものとなっており、いまもなお、回収に向けて対応中です。
継続中の案件であるため、筆者からはいいにくい部分もありますが、ベトナムだけでなく、海外での不動産購入は「日本とは法律も事情も異なる」という点を理解したうえで、なおかつ、実際に投資する前にしっかり現地事情を調べておくというのが、最低限必要なことだと思います。
正直な話、現地在住の日本人のなかにもいい加減な人・悪質な人はたくさんいます。日本人だからといって、頭から信用してかかるのは考えものです。彼らについても「ベトナムで労働ビザ(事業者もしくは社員としての労働許可)を持っているか」「現地での実績はあるか」という点は、最低限の確認事項として調べてください。
いくら親しくても、現地人名義で不動産を買うって…
【実例2】現地人の友人に勧められ「友人名義」で不動産を購入した結果…
現地で知り合ったベトナム人の友人に不動産購入による儲け話を持ち掛けられ、承諾。値上がりしたら転売するつもりで、居住用の住宅を購入した。ところが、購入時期は法改正の前であり、当時は外国人の購入に厳しい制限があった。また、物件自体が外国人の購入できない中古住宅だったこともあり、購入を勧めてきたベトナム人の友人名義で購入することにした。しかしその後、その友人と仲たがいして関係悪化。物件売却を希望するも、名義人である友人が同意しないため、売却できない状況が続いている。
現地で知り合ったベトナム人の友人に不動産購入による儲け話を持ち掛けられ、承諾。値上がりしたら転売するつもりで、居住用の住宅を購入した。ところが、購入時期は法改正の前であり、当時は外国人の購入に厳しい制限があった。また、物件自体が外国人の購入できない中古住宅だったこともあり、購入を勧めてきたベトナム人の友人名義で購入することにした。しかしその後、その友人と仲たがいして関係悪化。物件売却を希望するも、名義人である友人が同意しないため、売却できない状況が続いている。
その後の経過と対応
最初に筆者が行ったのは、契約書、もしくは相談内容についてエビデンスがあるかどうかの確認でした。状況的には、下記の通りとなっていました。
●物件を購入した販売契約書のコピー…アリ
●建物権利書(通称ピンクブック)…ナシ
●海外からの送金表…アリ
●メールでのやり取りの記録…アリ
結論を先に申し上げると、送金したお金は取り戻すことができました。海外からの送金項目について「不動産購入」と記載されていたことと、物件転売による利益を名義人側に譲渡することで双方の調整できたことが、取り戻せた理由です。
従来であれば、お金を取り返すのがむずかしいケースなのですが、日本からの送金表の項目に「不動産購入」と記載された点と、メールも含め具体的なエビデンスがあったことが幸いしました。
この案件と同様のケースの相談は多く、その大半は回収できません。とくにハンドキャリーで現金を持ち込んだ場合は、お金の流れが追跡できないためどうしようもありませんし、そもそもベトナム人名義で購入すること自体が大問題です。
しかし、ベトナム人名義での不動産購入や名義借りのトラブルは、何年も前からひっきりなしに起こっています。
本記事では2つの事例を紹介しましたが、現在も裁判中や提訴を控えた案件もあります。以前も書いたように、おおらかで穏やかなベトナム人にも悪意を持った人はいます。また、同じ日本人だとしても、用心するに越したことはないのです。
どのような状況においても投資は自己責任です。いまも各所で「悪い人たち」が、虎視眈々とおいしそうな獲物を狙っていますよ。
徳嶺 勝信
VINACOMPASS Co., Ltd.
General Director
頭の良さだけではない…医師が「不動産投資に激強」なワケ
収益物件は不動産サイトで探してはいけない…
自分が住む前提でマンションを探すなら、多くの人はまず不動産ポータルサイトを見るでしょう。しかし、収益物件に関してはこの方法はお勧めできません。必ず専門の不動産会社を探していろいろと直接相談するべきです。
確かに現在の物件探しの主流はインターネットです。希望の物件があるエリアにわざわざ行かなくても、建物の様子や価格、利回りなどの情報を簡単に入手できます。
「スーモ」や「ホームズ」「ヤフー不動産」といったメジャーなサイトから、「楽待」「クリスティ」「健美家」など収益物件の専門サイトまで多種多様。日本全国すべての情報が網羅されているように感じます。「これだけの情報があれば、いくらでもお宝物件が見つかりそう」と思ってしまうでしょう。
サイトに表示されているおもな利回りは「表面利回り」
ところがそれが落とし穴です。まず収益物件を探す中で、もっとも気になる利回りからして鵜呑みにはできません。
利回りとは物件価格に対する年間の家賃収入の割合です。たとえば1億円の物件の家賃収入が年間1000万円なら利回りは10%となります。つまり、10年で物件購入価格を回収できるということ。この数値が高ければ高いほど収益性の良い物件ということになります。
ところがサイトに表示されているおもな利回りは「表面利回り」です。これは満室状態の家賃収入から割り出したものです。実際には常に満室にできるわけではありませんし、基準となる家賃もいずれ下げなくてはならない事態になるかもしれません。さらに物件の状態によってはすぐに補修工事が必要になる場合もあります。
本来、利回りというものは、物件やその周辺地域が持つそれぞれの特徴を加味した「実質利回り」を指すべきです。しかし、ほとんどのサイトの情報からはそれを読み解くことはできません。
厳格に決まっている不動産広告の表示ルール
不動産ポータルサイトの情報は極めて少ないものが目立ちます。時間があれば各物件の詳細な情報を確認してみてください。「間取りが分からない」「写真がない」、中には「価格と住所以外の情報がない」といった圧倒的に情報がスカスカの物件が本当にたくさん見つかるはずです。
さらにその情報も正確かどうか分かりません。そこには同業者としては、はずかしながら不動産業者のモラルの問題があります。そもそも不動産表示に関する公正競争規約では、嘘をつかないことはもちろん、消費者が不動産を選ぶ際に表示するべき事項が定められています。
不動産広告には以下の事項についてバラバラな表示とならないように、いろいろな表示基準があります。
●物件の内容・取引条件等に係る表示基準
1 取引態様
2 物件の所在地
3 交通の利便性
4 各種施設までの距離または所要時間
5 団地の規模
6 面積
7 物件の形質
8 写真・絵図
9 設備・施設等
10 生活関連施設
11 価格・賃料
12 住宅ローン等
13 その他の取引条件
●節税効果等の表示基準
●入札及び競り売りの方法による場合の表示基準
たとえば、4「各種施設までの距離または所要時間」の場合の基準は、徒歩時間は1分で80メートルとして表示することになっています。また、不動産広告は「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」によっての誇大広告が禁止されています。
そこで公正競争規約では、次のような用語について表示内容を裏づける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。
特選、厳選
日本一、抜群、当社だけ
完全、完ぺき、絶対
格安、掘出、底値
完売など著しく人気が高く、売行きが良いことを意味する用語
最高、最高級など最上級を意味する用語
皆さんは新聞折り込みの不動産チラシなどで「眺望最高」「日当たりバツグン」といった売り文句を日常的に見ていませんか?残念ながら不動産業界はいまだにこのようないい加減な業者が多いため、広告の信用性も高いとはいえないのです。
サイト情報にまつわる悪質な業者の手口
業者のモラルという意味では、以前私のところへ相談に来た医師でこのような人がいました。
彼は不動産運用に関してすでにかなり勉強しており、インターネットを駆使してある中古物件を見つけました。現状で満室。しかも利回りが周辺の相場よりも若干高く、価格も手が届く範囲だったそうです。直接現地へ行って物件を確認しましたが、特に問題は見当たりません。そこで購入を決意。ローンの審査もすんなり通り、売買契約をします。
ところが数日後、再度現地に行くと衝撃の事実が。2階の1部屋にカーテンがなく、どう見ても入居者がいる気配もないのです。急いで仲介した不動産会社に駆け込み、問いただすと「満室という表示がありましたか? それならサイト運営会社のミスですね」と言われたそうです。
その開き直りぶりから、どう考えてもわざととしか思えません。そこで知り合いの医師の紹介で私のところに相談に来たわけです。結局この契約はさまざまな交渉の末、解除できました。
悪質な不動産業者は、このようなマンガや小説にしか出てこないようなセコい手で何とか成約に結びつけようとします。やはりサイト情報の内容には細心の注意が必要といえるでしょう。
物件だけでなく、街の周辺環境もチェック
不動産ポータルサイトの情報は正確なものがほとんどですが、情報が足りないものや正確性にかけるものもあります。いざ希望に合う物件を見つけたとき、それを買うべきかどうか、どのような基準で判断すべきでしょうか。
まず、その地域の人口動態や産業構造などから「どれだけ高い入居率を維持できるか」を
調べる必要があります。これらはインターネットで検索したり、役所などの公共サービスに問い合わせれば分かるはずです。総務省のウェブサイトには各種の情報が公開されています。
さらにその地域の不動産会社へ行き、周辺の入居率を聞いて回るのも有効です。現地を訪れるなら周辺の環境もチェックしましょう。商業施設や病院など生活に不可欠な施設がどこにあるのか。単身向けならコンビニへの距離、ファミリー向けなら学校への道のりなどを確認。学校への道のりは距離だけでなく車の交通量も見ましょう。また周辺環境としては、葬儀場やお墓などいわゆる嫌悪施設が近くにないかも重要です。
このような周辺環境のチェックは、実際に住む人の気持ちになることが大切です。自分で
も「これは住みやすい街だ」と思えれば合格でしょう。
物件購入の決断には「生の情報」が必要不可欠
物件そのものの目のつけどころは、まず見た目です。見た瞬間にくたびれた印象を持つよ
うであれば、相場よりもよほど家賃を下げるか、リフォームをしないと満室は望めないでしょう。あまりに奇抜なデザインも避けた方が無難です。
さらに基礎にヒビが入っていないか、中に入ったときに傾きを感じないか、妙な湿気はな
いか、などをチェックします。
傾きに関しては水平器やスマートフォンのアプリで測れますし、室内のドアや窓を開け閉
めして引っかかりの有無で確認できます。湿気を感じるようなら雨漏りや水漏れのおそれがあります。内装のきれいさやデザインは比較的安価に改善できますが、構造的な傷みは多額の費用を要します。ここは入念にチェックしたいところです。
不動産ポータルサイトでこのようなリアルな情報を得るのは、ほぼ不可能でしょう。結局物件購入の決断には生の情報が必要なのです。サイトの情報はあくまで相場感をつかむ程度と捉えていた方が無難です。
また多忙な方が生の情報を得るには、パートナーとなる不動産会社と二人三脚でいくのが最短・最善の方法です。
「立地」と「利回り」だけでは黒字経営は困難
物件情報を得たくても、場所を絞り込んでいなければ得ようがありません。医師に限らず一般的に、はじめて収益物件を買おうとする人は、自宅周辺で探そうとします。土地勘があることや常に管理状態を確認したいからでしょう。その気持ちはよく分かります。
しかし、残念ながら理想的な条件が揃った物件はそこかしこにあるわけではありません。自身の土地勘があるようなエリアで物件を探すのはあまりにも範囲が狭すぎます。
収益物件を探すならその範囲は全国、または世界に目を向けるべきです。なぜなら土地選びでもっとも重要なことは、そこに住む人がたくさんいること。つまりたとえ空室になったとしても、すぐに次の入居者が見つかる可能性が高い人口密集地であることです。しかも収益物件の経営は、20年、30年と長期にわたるので、その時点でも人口を維持していることが必須条件になります。
ところが今後の日本は人口が減っていくことが予想されます。国立社会保障・人口問題研究所では、次のような推計を公表しています(2012年1月推計)。
2010年の人口1億2805万7000人を100とする。
2025年の人口は1億2065万9000人で94.2。
2040年の人口は1億727万6000人で83.8。
25年後の人口はおよそ2割減ってしまうのです。しかし、地域によっては減少率が低いところがあります。それは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県です。
東京都は2025年まで現状維持で2040年でも93.5。
神奈川県は2025年まで99.6でほぼ現状維持、2040年でも92.2。
埼玉県は2025年で97.2、2040年でも87.6です。
千葉県は2025年で96.3、2040年でも86.2となっています。
(2010年を100としたときの指数。2013年3月推計。)
これらの都県は、全国平均よりも減少率が低く推計されています。地方で同じように2040年の減少率が低い県を挙げると、愛知県(92.5)、福岡県(86.3)などがあります。
このような数字から一都三県をはじめ大都市圏が、収益物件を経営する上で理想的な立地であるといえます。
とはいえ、これはあくまで一般論。確かに人口が多い場所の物件を買うことは確実な戦略です。収益物件を取り扱う不動産業者のほとんどは、この立地条件にプラスして利回りを売り文句に営業を展開しています。「こんなに交通の便がいいですよ。しかもこれだけ高い利回りがありますよ」。営業トークはこれだけです。
しかし、人口減に突入した昨今、この立地+利回りだけでは黒字経営を維持するのは困難です。この2つの条件にプラスして周辺のライバル物件に対して差別化できる何かが必要なのです。
人口密度と同じくらい「医師密度」が重要に
その何かとはどんなものか?
それは「周辺エリアの医師の数」、そして「コンセプト」です。医師が不動産運用をする際は、人口密度と同時に周辺の医師の数も視野に入れるべきです。
たとえば埼玉県の大宮駅周辺。大宮駅はJR埼京線で新宿へわずか30分の好立地。JR東日本の2013年度乗降客ランキングでは新橋駅に次ぐ8位(1日平均24万5479人)の巨大なターミナルステーションです。ところが大宮駅がある埼玉県は、厚生労働省が発表している「人口10万人対医師数」ではワースト1位なのです。
すなわち日本でもっとも医師が不足している県であり、開業するにはお勧めのエリアといえます。
収益物件を探すというと、人口密度の高いエリアにばかり目が行きがちです。しかし人口が多いエリアほど物件価格も高い。ところが医師であれば、人口密度と同じくらいそのエリアの「医師密度」も重要です。この基準は一般的な不動産価値とは違うので、医師にとっては魅力的な物件を安く購入することも可能になるわけです。そして、将来その物件を医療関係施設として開業すれば、不動産の価値は大きく高まります。

不動産の付加価値…コンセプトとは何か?
不動産運用で収益を上げる秘訣は、安く買ってその後に付加価値をつけることであり、これは鉄則ともいえるでしょう。
その付加価値とはいわゆる「コンセプト」です。たとえ一般的には人気の低いエリアでも、医師ならではのコンセプトがプラスされたとき、その物件は周辺のどの物件よりも収益率の良い存在になります。
たとえば詳細は後ほど説明しますが、シングルマザーの多い土地柄なら託児所を併設した
「シングルマザーシェアハウス」や、高齢者が多い地域ならおじいちゃんやおばあちゃんが日帰りで利用できる「デイサービス付き高齢者住宅」といったオーナーが医師であることを活かしたコンセプトです。
ほかにも、かつて医大生だった頃にどんな賃貸マンションが欲しかったか、今オーナー医師として何かアピールできることはないかを考えて、医大や大きな病院近くの物件を医大生や看護師向けの賃貸住宅にするといったコンセプトもあります。定期的に情報交換会を開催したり、エントランスなどの共用部分に専門書の貸出コーナーを設けるなどで差別化を図るのです。
このように医師ならではのコンセプトを明確に打ち出せれば、多少人口の少ない地方都市でも十分に経営が成り立つはずです。同時にシングルマザーや高齢者がイキイキと生活できるといった地域の活性化にも役に立てるでしょう。
逆にいくら都心に近く、いい立地でもコンセプトがない平凡な物件では選ばれる理由がなく、建物が老朽化するにしたがい、入居者募集が困難になるはずです。
ただし、どんなに画期的なコンセプトでも、過疎地のような人が集まらない土地はおすすめしません。町おこしなどの地域の活性化は行政が動かないと難しいものがあります。やはりある程度の人口規模が下地にあった上でのコンセプトといえます。
海外不動産投資・進出でも「コンセプト」を重視
また、「周辺エリアの医師の数」「コンセプト」という土地選びの視点はなにも国内に限ったことではありません。
現在は人もモノもグローバル化しています。かつては「メイド・イン・ジャパン」がもてはやされましたが、今は「メイド・バイ・ジャパン」に変わっています。
このような流れの中では、海外の物件を購入して現地で医療サービスを提供するという手も十分勝算があります。たとえば定年退職した人の移住先として人気の高いマレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、カナダ、カンボジアなどが狙い目です。
所有している物件からきちんと家賃収入があれば、勤務医として過酷な状況で働かなくても物価の安い海外なら十分暮らせるでしょう。海外で気ままにリゾートライフを送りながら、現地で移住者を対象に開業もけっして夢ではありません。
右も左も分からない海外での開業など現実的ではないと思うかもしれませんが、海外でも経験豊富なエージェントに仲介を依頼すれば問題はありません。実際、私は知り合いの医師と一緒にカンボジアで事業を始めています。
『金持ち父さん〜』が火付け役だった?不動産投資の落とし穴
「表面利回り」は「実質利回り」とは異なる
『金持ち父さん貧乏父さん』は「借金で不動産投資」の火付け役
レバレッジを利かせて資産を増やす——。自己資金が十分になくても借り入れを上手に使って資産を増やす方法が書かれたロバート・キヨサキ氏の著書『金持ち父さん貧乏父さん――アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学』(筑摩書房)の基本的な考え方だ。本書は2000年に日本で出版され、「インカムゲイン(運用して利益を得る)型」不動産投資の火付け役となった。
家主業の前提条件は不動産を所有していること。その不動産をまず買うことから始まるが、その不動産購入資金を金融機関から融資を受けることで、サラリーマンでも資産を増やせる方法として注目を集めたのだ。だが、借金ありきの賃貸経営は、借金のコントロールが財務状況に大きく影響するだけに、正しい知識がないと資金繰りに追われてしまう。

近年は金融機関の融資審査が厳しくなったため、自己資金ゼロではアパートや一棟マンションを買えなくなったが、融資を受けて「かぼちゃの馬車」をはじめ、積算評価が出やすい地方の中古一棟マンションなどを買った人は、今大変な思いで経営していることだろう。自己資金がゼロということは、それだけ毎月の家賃収入から差し引かれる借入返済額が大きいということであり、高い金利で借りていたら、資金繰りが苦しくなるからだ。
少額の元手から投資を始め、不動産を買い進め資産を築いた家主の代表選手といえば、『「お宝不動産」で金持ちになる!——サラリーマンでもできる不動産投資入門』(筑摩書房)の著者の沢孝史さんだろう。
沢さんは、サラリーマン時代に奥さんと2人で貯めた資金で、コンビニエンスストアのFCに加盟し開業するも、売り上げが伸びず、4カ月で閉店するという苦い経験をした。コンビニエンスストア事業の経費として重くのしかかったのが、実は「賃料」だった。そこで、賃料の支払い先であった家主という職業に目を付けた沢さんは、1998年から不動産を取得し始め、現在、総投資額27億円、債務を差し引いた純資産はなんと4億円を保有するまでになった。
不動産による資産形成の成功者である沢さんは、常々「不動産投資には、『利回り』と『不動産価格』という2つの落とし穴がある。そのことに注意して購入する不動産を選ぶべきだ」と話す。
まず、「利回りの落とし穴」とは何か。利回りとは、不動産購入額に対して1年間で得られる収入の比率のこと。5000万円の不動産を購入して、年間家賃収入が500万円なら利回り10%、年間家賃収入が400万円なら利回り8%となる。この利回りは収益不動産の広告に明示されているが、その数字はあくまでも「表面利回り」であり、借入金返済額、管理費、修繕費等の支出や空室率は入っていないため、実質利回りとは異なる。
将来の不動産価格は誰にもわからない
しかし、ビギナーにとっては、その知識はあっても、実際どの程度の利回りを想定して、不動産を購入し、借り入れをすればいいのか見当をつけることは難しいだろう。沢さんは、これまでの自身の経験から、購入するときの実質利回りの目安は「金利+6%」以上を確保することを原則にしているという。目標とする実質利回りの数字が決まれば、逆算して、表面利回りがどのくらいの不動産を購入するのがいいのかがわかる。
例えば、沢さんによると、金利2%、管理費5%、空室率20%とした場合、表面利回りを算出する計算式は、
表面利回り=実質利回り(借入金金利2%+6%)÷{1-(空室率20%+管理費5%)}=8%÷(1-0.25)=10.66%
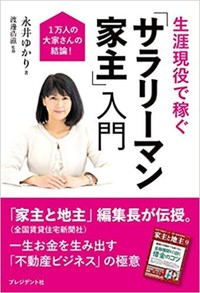
となる。すなわち、表面利回り10.66%以上の物件が購入を検討すべき物件となるというわけだ。
もう一つの「不動産価格の落とし穴」とは、不動産価格の将来は誰にもわからないということだと、沢さんは言う。つまり、できるだけ価値の下がらない不動産を購入することが不動産投資を成功させるということだが、実際、どの程度の価値が残っていれば成功といえるのだろうか。
沢さんは自身の経験から、10年後に「市場価値が購入時の80%、賃貸収入が購入時の90%」の基準を満たしていれば、投資する価値のある不動産として検討対象にするという。実際に、実質利回り「金利+6%」と「市場価値が購入時の80%」でシミュレーションしてみよう。
前提条件は、物件価格1億円、自己資金10%、家賃800万円、金利2%で20年元利均等返済、固定資産税・火災保険は家賃8%、空室率・募集経費・管理費等は家賃15%、修繕費は家賃3%、所得税は20%とする。
この投資は、10年間でどのような結果となったのか。
キャッシュフローの累計額(回収額)は3324万円、不動産価格からキャッシュフローの累計額を差し引いた不足分(未回収額)が6676万円となる。10年後の物件価格を下限80%と設定しているので、8000万円で売れたとする。8000万円から未回収額を差し引けば、1324万円で、自己資金1000万円が10年後に1324万円になったということになる。
「元利均等」か「元金均等」か、それが問題だ
また、この実質利回りを「金利+5.5%」として同じ条件で計算してみると、1000万円の自己資金は1044万円と、44万円しか増やすことができない。さらに「金利+5%」で計算すると、236万円減ってしまう。つまり、確実に資産を増やすためには「金利+6%」未満では厳しいという結果となった。
沢さんがこうした計算式を導き出すことができたのは、サラリーマン時代に損保会社に勤めていた経験が大きいそうだ。交通事故等での示談交渉で使用していた賠償額の計算の中での逸失利益の算定方法が、不動産を購入し賃貸業をする際にも役立ったという。逸失利益の算定は、将来もらう収入を今もらうのであれば、その間の利息は差し引かれるという考え方に基づいて行われるが、これは不動産賃貸業の、将来得られるであろう利益に対し、今いくら投資すれば採算が取れるのかという考え方に通じるものがあると気づいたのだという。
「元利均等」か「元金均等」か、それが問題だ
また、沢さんが着実に不動産を増やせたのは、借り入れのバランスを毎月確認して投資してきたからだ。
「返済の総額だけを見るのではなく、元金と金利のバランスを見ることも重要」と語る沢さんは月々の返済額のうち、金利が元金よりも多いと資金繰りが厳しくなると指摘する。
元金とは実際に借り入れた金額のことで、金利とは借入金に対する利息のことだ。金利には「変動金利」と「固定金利」があり、固定金利に比べて変動金利は市場金利に連動して見直されるため、低く設定されている。固定金利の場合は3年、5年、10年と期間があり(これ以外の期間のケースもある)、低金利で近い将来金利上昇が予測されるとき、また、支出があらかじめ計算できるため、返済計画が立てやすいとの理由から選択されるケースもある。
元金と金利のバランスは、借り入れの返済方法によって大きく異なる。
たいていの人は元利均等を選択する。不動産を購入して初期段階でのキャッシュフローが多いからだ。返済期間の初期段階では、返済額に占める金利の割合が大きいため、税務上の経費が多くなり、税額も少なくなる。一方、元金均等は初期段階においては返済負担が大きいが、元金を早く減らせるため、返済総額は元利均等よりも少なくなる。
以上のことを踏まえて、「元金と金利のバランスを見る」とはどういうことかというと、沢さんは「金利の変化による元金返済割合、毎月返済額に占める金利支払い分の割合を確認する」と話す。このそれぞれの割合を確認して、どちらの返済方式が得策かを判断するのだという。では、それぞれの割合は金利の変化でどのように変わるのかを見てみよう。
結局、借金しての不動産投資は儲かるのか?
例えば、返済期間30年で1億円を借りたケースで比較してみよう。
〈金利2%の場合〉
元利均等では、毎月返済額は36万9000円、そのうち金利の割合は45%。
元金均等では、毎月返済額は44万4000円、そのうち金利の割合は37%。
〈金利4%の場合〉
元利均等では、毎月返済額は47万7000円、そのうち金利の割合は70%。
元金均等では、毎月返済額は61万1000円、そのうち金利の割合は54%。
金利2%と4%を比較すると、金利が高くなるほど元利均等の金利返済割合が大きくなり、当初は元金が減らず返済総額が減りにくくなる。つまり、金融機関の儲けのための返済になってしまっている。
一方、金利が1%の場合を見てみよう。
〈金利1%の場合〉
元利均等では、毎月返済額は32万1000円、そのうち金利の割合は26%。
元金均等では、毎月返済額は36万1000円、そのうち金利の割合は23%。
金利1%で比較すると、元利均等と元金均等の金利返済割合の差が縮まる。この場合は元利均等で次の購入のための自己資金を貯めることを優先した方がよさそうだ。
次の不動産の購入に進むためには、借入総額を減らしながら、キャッシュを貯めることが必要だ。元金均等、元利均等の特性を考えつつ、金利の水準と今後の動向を見ながら判断する必要があるというわけだ。
「実際には金利が高い場合、元金均等だとキャッシュフローがマイナスになるというケースもあるだろう。しかし、そもそもそんな案件は投資に値しないのではないか」というのが沢さんの考えだ。
永井ゆかり
「家主と地主」編集長
長男が隠し通す「父の遺産額」…真実を知った弟が激怒したワケ
「人間関係」「感情の問題」が相続事件の行方を左右
相続事件は、多数の当事者をめぐる複雑な権利関係を扱うものであり、法律的に難しいということもあるのですが、それ以上に重要なことは、各相続人間の人間関係、感情の問題が事件の行方に非常に大きな影響を及ぼすということです。
このため、弁護士の立場としては、依頼者だけでなく、相手方に対しても、その気持ちや想いに対する配慮を怠り対応を誤るようなことがあれば、その後の結果が全く異なってしまうことも多々あります。たとえば、他の相続人からの協力を得られない場合、相続財産の調査や結論に大きな影響を与えてしまいます。
では、どうすれば協力を得られるのか? 正解があるわけではないですが、やはり正攻法としては、相手方とのファーストコンタクトの段階、具体的には最初のお手紙を出す段階から礼節をもって接し、誠実に対応することに尽きるのではないかと考えています。
このように、相続事件では特に初期対応が重要となります。私は、相続事件を専門的に扱う弁護士として、依頼者の想いや心情に寄り添いながらも、初期対応の重要性を忘れることなく、紛争の解決に向けて着実に前進していくという心構えをもって、一つひとつの案件に真摯に向き合っています。
私は、これまでに200件以上の相続事件に携わり問題解決をしてきましたが、それらのうちの紛争案件については、「生前の対策をきちんとしていれば、このような泥沼の紛争にはならなかったのに」と感じるものばかりでした。
昨今、一時の相続ブームは去りましたが、それでも近時の相続法の改正などにより依然として相続問題や「終活」は関心が高く、書店に行けば相続関係の書籍がたくさん並んでいます。
ただ、そのような相続関係の本をみてみると、税理士やファイナンシャルプランナーの方が書いた相続税対策を中心としたもの、あるいは、他の士業や、中には怪しげな自称相続コンサルタント・無資格者が書いた相続手続の解説などに偏ったものが多いと感じました。
そこで私は、これまで私が解決してきた200件以上の実際の事件の一つひとつを丁寧に振り返り、改めて精査・分析してみました。そしてその分析結果をもとに、若干の再構成を加えたオリジナルのストーリーをご紹介することで、
①現在、まさに紛争に巻き込まれている方々には紛争解決の糸口・方法を知っていただきたい。
②ご自分の死後のご家族の紛争を避けたいと考えている方々には、生前に対策をとらないと、残されたご家族が不幸になってしまうおそれがあることを知っていただきたい。
③紛争を未然に防止するために、生前の対策を実行するための一つのきっかけとしていただきたい。
と考え、紛争解決の唯一の士業専門家である弁護士ならではの視点で、相続に関する「紛争の解決」と「紛争の未然防止」に特化した内容の本を書きたいと思うに至りました。ここでは、その一部を紹介します。相続を「争族」にしないために、多くの皆様に本連載を有効活用していただければ幸いです。
父の遺産額を開示しない長男…不信感が募り対立激化
依頼者は50代の男性で、ご夫婦で相談にいらっしゃいました。お話を伺うと、亡くなった父親の相続人は、依頼者と依頼者の母、そして、依頼者の兄の3名でした。
依頼者の兄は、亡くなった父親が所有する土地の上に自宅を建てて住んでいたのですが、遺産のうちの預貯金等の有無及び金額が不明で、しかも、兄から任意に開示されなかったために不信感が募っていました。
このように、相手方が財産を開示しなかったり隠したりすると、不信感を募らせることになってしまいます。
ご相談の結果、当事者間の感情的な対立が激しかったため、当事者同士でこれ以上話し合いをしても解決する見込みはないと判断し、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする方針を立てて正式にご依頼を受けました。
総額5千万円以上…長男の「不自然な引出し」が発覚
調停の申立てをすると、相手方である兄と母にも弁護士が代理人に就き、相手方から預貯金等がようやく、開示されました。
しかし、その預貯金口座の取引履歴をみてみると、被相続人である亡き父の預金口座から数年間にわたり、不自然かつ多額のお金(総額で5000万円以上)が引き出されていました。
そこで、この使途不明金等をめぐり、当方から、相手方の「特別受益」ではないかという主張をすると、今度は相手方からは、亡き父の生前に身の回りの世話をしたなどの理由で「寄与分」の主張をされ、双方で主張の応酬となりました。
また、遺産である不動産の評価額も争いとなり、話し合いでの解決が困難となったため、やむなく調停は不成立となり、審判手続に移行しました(遺産分割調停は、裁判所が話し合いでの解決の見込みがないと判断すると不成立となり、自動的に審判という手続に移行します)。
兄vs弟の審判手続…3つの争点
「審判」という手続は、厳密には「訴訟(裁判)」とは異なります。もっとも、審判も当事者双方が主張・立証をし、最終的に裁判所が証拠に基づいて事実を認定して一定の判断を下すという点で、訴訟(裁判)に似た手続です。審判手続の中では、①不動産の評価額、②特別受益の有無及び金額、③寄与分の有無及び金額の3点が争点になりました。
①不動産の評価額
まず、①の不動産の評価額については、当方からは、知り合いの不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、鑑定評価書を証拠として提出しました。
他方、相手方は不動産会社の価格査定書を提出してきましたので、最終的には双方の金額の中間値を評価額とすることで合意しました。
不動産の評価額が争点になる場合、本件のように不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することの他、双方が不動産会社の価格査定書を提出し、その平均額を評価額とすることで合意することも多いです。
また、不動産会社の査定価格と相続税評価額(路線価)との中間値を評価額とする方法や、相続税評価額(路線価)をそのまま評価額とする方法などもあります。
②特別受益
次に、②特別受益の有無及び金額についてですが、相手方である兄が、遺産である被相続人名義の土地の上に自分名義の建物を建てて長年にわたり住んでいたので、当方が主張したとおり、遺産である土地を長年にわたり無償で利用したことが特別受益にあたると認められました。
この場合、土地を無償で使用したことで得た利益としては、一般的には更地価格の1〜3割程度と評価されることになります。
この他、使途不明金については、当方の粘り強い主張・立証活動により裁判官の説得に成功し、一定の金額については、相手方に対する生前贈与があったものとして特別受益として認めてもらうことができました。
③寄与分
最後に、③寄与分の有無及び金額についてです。相手方は、被相続人を介護したことについて寄与分の主張をしていました。
しかし、寄与分が認められるためには「特別の寄与」であることが必要であり、かつ、そのことにより、被相続人の遺産が維持又は増加したことまで立証しなければならないため、後述するとおり、一般的には非常にハードルが高いです。
本件でも、その立証がなされていないと裁判官に判断され、相手方の寄与分の主張は認められませんでした。
このように3つの争点について、一つずつ粘り強く解決していき、最終的に当事者の納得を得られ、調停成立で事件終了となりました(一度、審判手続に移行しても、話し合いでの解決が可能であれば、いつでも調停手続に戻すことが可能です)。
この事件では、依頼者の言い分をきちんと主張し立証することで、依頼者の感情的な不満を十分に吐き出してもらうとともに、裁判官が審判を出すときの最終的な結論を見据えたうえで、落としどころを粘り強く依頼者に説明したことが事件解決のポイントだったと考えています。
<教訓>
●依頼者の想いや言い分をきちんと聞き出して主張・立証すべし。
●依頼者の言い分を裁判所がどう考えるか、粘り強く依頼者に説明すべし。
安易な「寄与分」の主張は紛争長期化を招くおそれ
■チェックポイント:不動産の評価額
「不動産の評価額」には4種類ありますが、遺産の中に不動産があると、必ずといってよいほど、不動産の評価額が争いとなります。
不動産の評価額には、時価(実勢価格)、公示価格、相続税評価額(路線価)、固定資産(税)評価額という4つの種類があります。
公示価格は、国土交通省が特定の標準地について毎年公示する価格であり、いわゆる正常な価格(自由公開市場で取引が行われるとした場合において、その取引において通常成立すると認められる価格)として算出され、時価(実勢価格)に近いとされています。
相続税評価額(路線価)は、相続税・贈与税の算出の基準となる価格であり、路線価方式・倍率方式のいずれかにより算出されています。この路線価については、公示価格の80%を目処に設定されています。
固定資産(税)評価額は、固定資産税の課税標準額を定める基準となる価格であり、公示価格の70%を目処に設定されています。
遺産分割での不動産の評価は、原則としてその不動産の時価を基準としますが、当事者双方が合意すれば、必ずしも時価を基準とする必要はありません。
この点、不動産の時価は公示価格に近いとされているため、相続税評価額(路線価)を80%で割り戻したり、固定資産(税)評価額を70%で割り戻したりして概算額を算出することもあります。
これまでの経験を踏まえた私の感覚では、土地については、双方が複数の不動産会社の査定書を提出し、その査定価格の平均額を評価額とする方法、不動産会社の査定価格と相続税評価額(路線価)との平均額を評価額とする方法などが多いです(なお、不動産鑑定士に鑑定評価書を依頼することもありますが、相応の費用がかかるため、実務上は不動産会社の無料の査定書を利用することが多いです)。
他方、建物については新築の一戸建てやマンションであれば別ですが、遺産となる建物は通常、かなりの築年数を経ていることが多いので、評価額をゼロとするか、評価額を計上するとしても固定資産(税)評価額を計上することがほとんどです。
■チェックポイント:特別受益
「特別受益」とは、被相続人が特定の相続人に生前贈与等をしていた場合、実質的には遺産の先渡しをしたことになり、そのままでは相続人間で不公平になってしまうので、生前贈与された財産を金額に評価して、その価格を相続財産に加算(「持ち戻し」といいます)して、相続分を算定し、相続人間の公平を図る制度のことをいいます。
特別受益が認められるためには証拠が必要となりますので、相手方に特別受益があることを主張する場合には、それを裏付ける証拠として何があるのかを精査することが必要です。
■チェックポイント:寄与分
「寄与分」とは、相続人の中に、被相続人の財産を維持又は増加させたことについて特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして一応の相続分を算定し、その算定された一応の相続分に寄与分を加えた額をその者の具体的相続分とすることで、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、相続人間の公平を図る制度のことをいいます。
寄与分には次のような類型があります。
①家業従事型:無報酬又はこれに近い状態で、被相続人が経営する自営業に従事する場合
②金銭等出資型:被相続人に対し財産の給付を行う場合
③療養看護型:無報酬又はこれに近い状態で病気療養中の被相続人の療養看護を行なった場合
④扶養型:無報酬又はこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合
⑤財産管理型:無報酬又はこれに近い状態で、被相続人の財産を管理した場合
寄与分を認めてもらうためには非常にハードルが高いので、認められる見込みがないのに安易に主張をすると、いたずらに紛争を長期化させてしまうおそれがあります。このため、寄与分を主張する場合は、それが認められる可能性があるのか、事前の十分な検討が不可欠でしょう。
加藤 剛毅
武蔵野経営法律事務所 代表
弁護士、元さいたま家庭裁判所家事調停官
■チェックポイント:不動産の評価額
「不動産の評価額」には4種類ありますが、遺産の中に不動産があると、必ずといってよいほど、不動産の評価額が争いとなります。
不動産の評価額には、時価(実勢価格)、公示価格、相続税評価額(路線価)、固定資産(税)評価額という4つの種類があります。
公示価格は、国土交通省が特定の標準地について毎年公示する価格であり、いわゆる正常な価格(自由公開市場で取引が行われるとした場合において、その取引において通常成立すると認められる価格)として算出され、時価(実勢価格)に近いとされています。
相続税評価額(路線価)は、相続税・贈与税の算出の基準となる価格であり、路線価方式・倍率方式のいずれかにより算出されています。この路線価については、公示価格の80%を目処に設定されています。
固定資産(税)評価額は、固定資産税の課税標準額を定める基準となる価格であり、公示価格の70%を目処に設定されています。
遺産分割での不動産の評価は、原則としてその不動産の時価を基準としますが、当事者双方が合意すれば、必ずしも時価を基準とする必要はありません。
この点、不動産の時価は公示価格に近いとされているため、相続税評価額(路線価)を80%で割り戻したり、固定資産(税)評価額を70%で割り戻したりして概算額を算出することもあります。
これまでの経験を踏まえた私の感覚では、土地については、双方が複数の不動産会社の査定書を提出し、その査定価格の平均額を評価額とする方法、不動産会社の査定価格と相続税評価額(路線価)との平均額を評価額とする方法などが多いです(なお、不動産鑑定士に鑑定評価書を依頼することもありますが、相応の費用がかかるため、実務上は不動産会社の無料の査定書を利用することが多いです)。
他方、建物については新築の一戸建てやマンションであれば別ですが、遺産となる建物は通常、かなりの築年数を経ていることが多いので、評価額をゼロとするか、評価額を計上するとしても固定資産(税)評価額を計上することがほとんどです。
■チェックポイント:特別受益
「特別受益」とは、被相続人が特定の相続人に生前贈与等をしていた場合、実質的には遺産の先渡しをしたことになり、そのままでは相続人間で不公平になってしまうので、生前贈与された財産を金額に評価して、その価格を相続財産に加算(「持ち戻し」といいます)して、相続分を算定し、相続人間の公平を図る制度のことをいいます。
特別受益が認められるためには証拠が必要となりますので、相手方に特別受益があることを主張する場合には、それを裏付ける証拠として何があるのかを精査することが必要です。
■チェックポイント:寄与分
「寄与分」とは、相続人の中に、被相続人の財産を維持又は増加させたことについて特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして一応の相続分を算定し、その算定された一応の相続分に寄与分を加えた額をその者の具体的相続分とすることで、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、相続人間の公平を図る制度のことをいいます。
寄与分には次のような類型があります。
①家業従事型:無報酬又はこれに近い状態で、被相続人が経営する自営業に従事する場合
②金銭等出資型:被相続人に対し財産の給付を行う場合
③療養看護型:無報酬又はこれに近い状態で病気療養中の被相続人の療養看護を行なった場合
④扶養型:無報酬又はこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合
⑤財産管理型:無報酬又はこれに近い状態で、被相続人の財産を管理した場合
寄与分を認めてもらうためには非常にハードルが高いので、認められる見込みがないのに安易に主張をすると、いたずらに紛争を長期化させてしまうおそれがあります。このため、寄与分を主張する場合は、それが認められる可能性があるのか、事前の十分な検討が不可欠でしょう。
加藤 剛毅
武蔵野経営法律事務所 代表
弁護士、元さいたま家庭裁判所家事調停官
世田谷・家賃56万円の新築アパートが「大失敗でした…」の謎
建築条件や借入金利等に足を引っ張られ…
世田谷新築アパート(新築プロジェクト1)
①購入:2014年3月(土地契約)
②最寄駅:世田谷線三軒茶屋駅徒歩3分
③購入価格:1億1000万円(土地7000万円、建物4000万円)
④部屋数:5部屋
⑤家賃:56万円/月(表面利回り6.1%)
⑥築年数:新築(建物完成2015年2月)
⑦借入金額:1億円
⑧借入期間:35年
⑨借入金利:3.5%(※)⇒1%台に
(※)預金金額により、金利優遇措置あり。
初めて買った新築物件で、若干舞い上がっていた。
以下が、その反省点。
●建築条件付で土地を購入した
建築条件付とは土地を購入する際に、建築業者を指定されていることだ。交渉により、建築条件を外すこともできるが、その場合は土地価格が数%上がることもある。建築条件を外す交渉をすると、土地が購入できなくなる可能性もあったため、売主を刺激することなく、そのまま建築条件付で土地を購入した。結果、建築費はざっくり1割程度高かったような印象を受けた。

●借入金利が高かった
借入金利が3.5%(※預金金額により、金利優遇があり、1%台まで下がる)だった。金利優遇は元本返済後にしか適用されず、土地ローン支払い時は3.5%の金利を支払い続けた。結果、建物が完成して家賃を生み出すまでに、土地の利息だけで200万円近く支払った。金融機関との調整が甘かった。
●家賃収入が想定よりも4万円(7%)も低かった
繁忙期(2月)に完成と、新築プレミアムによる効果で、家賃収入を高く見積もり過ぎた。次の入居募集戦略にもつながるが、もう少し前もって入居募集戦略を立てる必要があった。
草がボーボーと生い茂り…「一度の失敗が致命傷」に
●入居募集戦略が甘かった
現地の仲介業者をしっかり回らずに、インターネットの集客に強い業者と専任契約を結んでしまった。インターネットの募集に強い業者、地元のネットワークが強い業者など、特徴はいくつかあるが、やはり専任契約はNGだと反省している。仲介業者は両手で手数料を取りたいはずなので、もう少し地元の仲介業者を回らないといけなかった。設計業者との詳細仕様の詰め、合意プロセスが甘かった
本当は駐輪場としてのスペースだったが、植栽置き場になってしまった。植栽は、メンテが大変なので、できれば避けたかった。草がボーボーと生い茂り、頻繁に草むしりが必要だ。植栽も凝り始めれば差別化の一要因となり、面白いのかもしれないが、残念ながら私にそんなセンスはない。自分の得意分野、不得意分野を見極め、不得意分野は、可能な限り排除していった方が良い。自分の不得意分野は、結局外注化せざるを得ず、外部におカネが出ていきやすい。
上記のようにいくつかの反省点はある。しっかりリスクを回避できる堅実な人ならば、予めリスクを洗い出して、先手を打てるのかもしれない。しかし、私は全く後悔してない。むしろ、上記のようなことをしっかり実感できて、次に失敗しないように学ぶことができて良かったと感じている。
物件を拡大するための試金石だ。細かいことはあとから軌道修正していけば良い。大切なのは、問題意識を持ち続けることと、改善点を見つけることだ。1回目よりも2回目、2回目よりも3回目と回数を重ねるごとに精度を上げていけば良い。
不動産は大きなおカネが動くために、1度の失敗が致命傷になりかねない。致命傷にしないために、エリアだけは固いエリアを選んでいる。それ以外のことは正直、全て誤差の範囲で致命傷にはならない。頭で考えるより、実践して覚えた方が時間短縮できる。
自己資金45万で不動産100億買った男の衝撃技
重要なのは「融資の受け方」だった
副業でマンション経営をはじめたい。多くの人が一度は考える副収入の作り方だろう。「サラリーマン大家」は流行語にもなった。ちまたには不動産投資の書籍があふれ、多くの手法を紹介している。しかし、借金を抱えて不動産を買うことに抵抗があり、一歩を踏み出せない人も多いだろう。
筆者は過去10年間、不動産投資と銀行融資を研究してきた。銀行融資を活用しながら戦略的に投資物件を買い進め、結果的には自己資金45万円のみの拠出で100億円を超える規模になった。
それらの物件はコロナ禍でも安定した収益を生んでいる。その経験から不動産投資を拡大するためのポイントを公開しよう。
「コアプラス投資」がお勧め
一言で不動産投資といってもその手法は多様だ。おおよそ次の4種類に分けて投資戦略を練るのが一般的といえる。
・コア型
駅直結のランドマークビルなど高資産性、低収益性の物件を長期保有
当社の会社名にもなっているお勧め投資法。薄利多保有で規模拡大に最適
競売、割安物件の発掘など好機を探す投資で高収益率
廃屋再生、リノベーションなどプロの仕事でバリューアップして転売
コア型は千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区(都心5区)などの一等地にピカピカのビルを保有する手法だ。投資家ではなく資産家の相続や大企業向けの戦略といえる。
オポチュニスティック型やバリューアデッド型は「2倍で転売できた」「利回り50%」などの宣伝文句を見ることもめずらしくないが、百戦錬磨の不動産業者と真っ向から競合するビジネスモデルであり、副業の個人が参入するには障壁が高い。
筆者が行っているのが「コアプラス型投資」だ。都心の一等地はあえて外して、二等地、三等地をねらう。東京でいえば、練馬区、板橋区、北区などの住宅地だ。駅徒歩10分以内、鉄筋コンクリート造、平成初期の築、2020年現在で表面利回り6.5%以上ならば間違いはない。
このような物件を1億円分買ったとしよう。結論的には毎年300万円ほどの利益になる。利益率は高いとはいえないが、10億円分買えば3000万円の利益であり、本業の給与を超える利益を生むことができる。このような薄利多保有で利益を積み上げていくのが不動産投資の王道と考えている。コアプラス型投資では物件選びはそれほど重要ではない。実際、筆者はレインズ、楽待、大手不動産業者など誰でもアクセスできるような仕入れ元しか使っていない。専業投資家にしては意外だと思われるだろうが、特に不自由はしていない。
ただし、次のような物件は避けている。
・賃貸需要が少ない地域
周囲に畑が多い、築浅アパートの激戦区など
古くなると賃料下落と建物価格下落で利回りが悪化
自分で土地を買って新築したほうが安い
建物は経年で価値下落する。土地が広いほうが有利
民泊やシェアハウスであるがゆえに高利回りの物件
1986年以前に建てられた物件で、給排水や耐震に問題。高額な修繕が必要なことも
逆にいえば、これ以外であればどれを選んでも大きくは変わらない。低金利の借り入れで投資ができる今、文字通り「時は金なり」だ。「特選物件」が出るまで長期間待つのは期待値に見合わない。今ある物件から消去法で残ったものを選び、早くスタート地点に立つことが大事だ。
高利回り物件より「規模拡大」が大事
なぜ物件よりも先に融資なのか。それは融資さえ得られれば、自己資金45万円で100億円分の不動産を購入し、毎年、数億円の利益をコンスタントに計上することが可能だからだ。
オポチュニスティック型で不動産投資をはじめてしまうと、利益「率」は高くなるが数億円の保有で頭打ちとなり、利益「額」は小さく終わる。
投資規模を拡大すると、いくつものメリットが生まれてくる点も見逃せない。例えば、規模拡大は失敗へのバッファーにもなる。多少のロスは数十億という金額が動く中での端数として忘れることもできる。
そう考えれば、ますます積極的に買い進めることができる。このように金額の大きさを活用して、個人でも大企業のような動きができるのは不動産の醍醐味だ。
また大規模であれば、管理会社やリフォーム会社とも有利な付き合いができる。実は外部業者との関係性において、価格以上に重要なのは大口顧客として細かい注文や短納期に対応してもらえることだ。
物件管理は最適化の積み重ねといえるが、細かすぎる注文は業者が応じてくれないために最適化の限界を迎えることも少なくない。また電話やメールではなくてプロジェクト管理ソフトで進捗管理したいなど、仕事の進め方から指定できることは大口顧客の特権として効率化に貢献する。
さらに規模を増やせば、物件管理に人的資源を投下できる。筆者はITの知識を生かして、インターホン設備、防犯カメラ、ネットや放送設備などは自作して物件に導入することにより、低コスト化を実現している。
リノベーションのデザイン図面なども自分で描いているが、これも1棟だけの保有であれば研究開発費が捻出できない。大規模になれば、一度作ったひな形を横展開していくだけなので効率がいい。
このような細かな最適化を突き詰めることにより、埼玉県の郊外駅から徒歩30分のような賃貸付けが難しいとされる物件においても高い入居率を維持できている。不動産投資で最も重要なのは、不動産そのものよりも融資だと断言したい。筆者のような専業投資家ならともかく、「一般のビジネスパーソンが1億円を超えるような不動産投資用の融資を受けられるのか」という疑問が浮かぶかもしれないが、決して無理な話ではない。
カギになるのはタイミングの見極めだ。例えば、東京オリンピックの開催決定以降、不動産相場は上昇しており、個人でも融資が受けやすかった。スルガ銀行の不正融資問題が起こってからは、銀行の姿勢が厳しくなっているとはいえ、融資をまったく受け付けていないわけではない。
ただし、融資を得るために金融機関の窓口に行っても、「不動産融資は積極的にはやっていない」で帰らされることが9割以上だ。
相続や株式投資などで多額の資産を持っているということでもない限り、正面から銀行に行っても取り合ってくれないだろう。
ここであきらめるにはまだ早い。銀行融資を得るために筆者が実践してきた秘伝の技を公開しよう。
まず金融機関には表口から入らないこと。表口とはドアノックでの新規開拓だ。それよりも不動産業者や生命保険の営業に購入を約束し、つながりのある金融機関を紹介してもらうなどが効果的だ。
保険の加入は金融機関とつながるための交際費と割り切る。運がよければ最初から銀行の支店長と会えるかもしれない。支店長と会えたらあとは折衝次第だ。最小限の自己資金で買える物件はどのようなものかをヒアリングする。金融機関により好まれる物件は少しずつ違う。
裏技は「取引金融機関を増やす」
無事に打ち合わせを終えたら財務資料の提出だ。財務資料は、単に決算書のコピーを提出するだけでなく、自己紹介、物件一覧、借入金一覧、賃貸状況など見やすいディスクロージャー資料を添える。
スルガ銀行問題以降は、会計の透明性も重要な論点となっている。税金や社会保険をきちんと支払うなど法令遵守面もアピールする。少しでも担当者の仕事を減らして稟議を進めてもらう努力をするのは、借りる側の仕事だ。そうしないと、「面倒」という理由で否決されることも少なくない。
財務資料に嘘が書けない分、資料の見栄えをよくするのは限界がある。ここで裏技として使えるのが、取引先の金融機関を増やすことだ。
筆者は18を超える金融機関から借り入れがあり、近隣の銀行のほぼすべてから借り入れがある。ここまで増やすと、「他行が出しているなら当行も」という流れが加速する。金融機関の横並び体質を利用するといい。
資料の提出を終えれば融資審査がはじまるが、ここにも技がある。自己資金を出したくなければ、既存保有物件を担保として提供して自己資金代わりにすることを提案するといい。これは筆者が少ない自己資金で物件を買い進められた理由の一つだ。
つまりフルローンで買える物件を探す、それを担保に次の物件を買う。規模が大きくなれば信用で運転資金が借りられる。この繰り返しだ。もちろん理想的な融資はいつでも出るものではないが、1~2月の銀行の決算期前などタイミングがよければ実際にできる。銀行も誰かには貸さなければ売り上げを作れないからだ。
このように、有利な融資を得るには、金融庁や銀行の内部システムを理解して「通る」稟議とは何かを知り、時に銀行の悪習までも利用する。そこから逆算して、通る財務資料や物件を持ち込む。
その精度を高めれば、少ない自己資金で投資規模を大きくすることができる。不動産だけを見ていては、不動産投資はうまくいかない。
社会貢献度の高さが高利回りに。真の投資家は空き家を資産に変える
投資家はとにかく「 良い不動産 」を「 安く 」買うことに注力しがちであり、好き好んで問題を引き受けるような投資家はいない。だが、世の中には不動産に関わるたくさんの問題がある。代表的なものといえば“ 空き家問題 ”だ。
「 少子高齢化が進むなか、空き家は増える一方です。総務省の最新の調査結果でいえば、2018年の空き家数は846 万戸と過去最高数を更新しました。
このように誰も住まなくなり、どんどん朽ちていく空き家が日本全国に増える一方で、住む家を誰からも提供してもらえない“ 住宅弱者 ”も急増して社会問題化しています 」
というのは、株式会社ベル代表取締役の礒﨑和彦氏。“ 住宅弱者 ”というのは、高齢者・外国籍・障がい者・生活保護利用者など、賃貸物件への入居を許可してもらえないなど住まいの選択肢に制限がある人を表す用語だ。
「 私が行っているのは、問題回避して高収益の獲得を狙う一般的な不動産投資ではなくて、人が持て余した空き家を購入・再生して、地域最安値の家賃で住宅弱者に供給するという社会貢献事業です。
何かしらの問題を自分が引き受けて解決するからこそ、その対価としてお金がもらえる、という投資家精神を基礎にしています 」
と礒﨑氏は続ける。通常、不動産投資手法というと築年数が経っていてもなるべく良い状態の建物、再生に手間がかからない物件を選ぶといったように、なるべく厄介なことは引き受けない方法が一般的であるが、礒﨑氏の方法はその逆。
雨漏りしていたりシロアリ被害にあっていたり、残置物がたくさんあったりといった人が避けるような物件を引き受ける。
「 問題を避けつつ高利回りを両立するのは、誰しもが考えることですから、そうなると資金力のある人が圧倒的に有利です。資本主義経済とはそのようにできています。しかし一般的な投資家は、これから資本力を身に付けたいと思って投資家デビューしています。それにも関わらず資本力があることが前提の投資手法を身に付けても意味がないのです。
だから資本力ではなくて問題を解決する能力で戦うことが重要なのです。私が持つ空き家投資のノウハウをサラリーマン投資家の皆さんに共有することで、より多くの空き家問題・住宅弱者問題を解決したいと考えていますし、社会はそのような投資家の出現を1人でも多く待ち望んでいます 」
礒﨑氏は一昨年から、この再現性の高い空き家投資手法を教える教育ビジネスを行っている。一体、どんなノウハウなのだろうか。
■ ノウハウのキモは「 徹底したムダの撤廃 」
社会貢献を目的にしているとはいえ、安易にボランティアには決して走らず、しっかりと収益を生み出すことからも逃げない。そのために礒﨑氏の空き家投資手法では、「 徹底してムダを撤廃する 」のが特徴だ。
「 まずは物件購入ですが、安く買いたいがために、その物件の欠点をあげつらう投資家がいますが、それは逆効果です。私のノウハウは、こちらの希望価格で売主さんが気持ちよく譲ってくれる方法です。これまでに5万円という安値で、感謝されながら売ってもらったこともあります 」
と礒﨑氏。売主から感謝されながら空き家を目標価格で購入できるので、お互いWin-Winなのだという。物件が目標価格で買えることはわかった。ではリフォーム費用はどうだろうか。
「 空き家投資ではリフォーム費用をおさえる必要がありますが、どれだけボロボロであっても、それが都会であれ地方であれ、予算内で修繕できます。DIY、分離発注、施主支給は行わず、リフォーム屋さんの利益を削ることもなく、1社に仕事を依頼するだけで、1物件30~100万円程度で修繕できます。もちろん手抜き工事などは行いません( そもそも手抜き工事を引き受けてくれる業者はいませんが )」
これまで数百軒以上の空き家を再生するうちに、物件を一目見れば、修繕費の上限額がいくらなのか、どのように発注すれば予算内で修繕できるか見極められるようになったそうだ。
このノウハウを学べば、「 徹底的にムダを撤廃した投資とは何か 」が理解でき、投資額をおさえることができるため、初心者が失敗するリスクは低い。礒﨑氏の教え子は全国に130名を超え、不動産投資未経験者でも平均4カ月で実質利回り20%以上を達成できるという。



■ 失敗投資から大逆転したサラリーマン投資家の実例
氏の教え子であり、空き家再生を実践している橋本岳氏にも話を聞くことができた。
「 老後の生活のために安定収入が欲しくて、不動産投資に興味を持ちました。都内のワンルームマンション投資からスタートしたところ、半年も立たずにガスコンロなどの設備が壊れて赤字に転落しました。また、地方の築古一棟アパートに手を出すものの空室が埋まらず、ローン返済に苦しむという結果となりました 」
独学で始めた不動産投資で失敗したことを反省し、礒﨑氏から空き家投資を学ぶことにしたそうだ。
「 昨年6月からベルのコンサル生になり、自己資金がほぼゼロの状態から空き家投資をスタートし、1年間に4軒の戸建てを再生し、平均利回り20%、年間の手取り家賃が206万円アップを達成しました。
教えてもらったノウハウを使うと、1,2か月の間に7件も指値が通り、面白いように物件が激安で買えました。買値はもっとも安い家が20万円で、高くても100万円台です 」
と、橋本氏は語る。
「 空き家投資の成否のカギを握るのはリフォーム費用をいかに安くおさえるかです。私は、教えてもらったノウハウで、業者を探し、激安で修繕できました。リフォーム金額をいうと、ものすごくビックリされます( 笑 )。忙しいサラリーマンにとって、DIYしなくても空き家投資で高利回り20%、30%が実現できる、このノウハウは本当にありがたいです 」
これまでの投資の失敗を挽回し、投資家として大逆転。橋本氏は、資産家向けに「 投資代行サービス 」を始め、数多くの空き家を再生しながら、さらに収益を上げているとのこと。
「 私は慎重な性格なので、一か八かのギャンブルのような投資には興味がありません。一夜にして大金を得るような投資方法ではなく、手堅く家族と幸せに暮らせるお金を生み出したい。その点、ベルの空き家投資の手法なら、地域最安値の家賃で貸すので家賃が下がりにくく、長期にわたって安定的な収益が得られるので、ビジネスモデルとして優れています。
しかも、このノウハウは、お金が稼げるだけでなく、社会貢献にもつながるところが気に入っています。私はコンサル生になって1年で、投資代行など不動産関連の収入が会社の給与を超え、人生が激変しました。この素晴らしい空き家投資手法について是非知ってほしいです 」
この礒﨑氏の空き家投資手法を学べるセミナーが、オンラインにて開催されている。具体的な事例をもとに、コンサル生の実体験も聞ける貴重な機会ということで、興味にある方は参加してはいかがだろうか。
実はあまり知られていない不動産投資の“おいしいメリット”…不労所得や税金低減も
はじめに
はじめまして。不動産投資コンサルタントの姫野秀喜です。私の連載する「確実に成功するための不動産投資の学校」へようこそ。
コロナ禍で会社の給与以外の収入源を求める人が増え、不動産投資に注目している人も増え続けています。この記事を読んでくださっているということは、あなたは少なくとも不動産投資に興味がある方だと思います。
そういった皆様に向けて、確実に成功できるための知識や不動産にまつわる時事問題などをお伝えしていきます。読者の方はこの記事を読むことで不動産投資のメリットやデメリット、やるべき具体的なアクション、やってはいけないことなどを理解することができます。
第1回:なぜ不動産投資なのか?不動産投資の魅力とは?
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/11/post_188161.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.投資と聞いて多くの人が一番にイメージするのは「株」でしょう。それ以外にも外貨を取引する「FX」やビットコインなどの「暗号通貨(仮想通貨)」を頭に思い浮かべる人も多いでしょう。
『確実に儲けを生み出す不動産投資の教科書』(姫野秀喜/明日香出版社)
昨今ブームが起きていたとはいえ「不動産投資」は投資全体で見ればマイナーなカテゴリーといえます。それもそのはずです。日本で株式投資をしている人数は約2,550万人(※1)であるのに対し、不動産投資をしている人数は約53万人(※2)しかいないのです。日本人の25%が行っている株式投資と異なり、不動産投資を行っている人は日本人の1%にも満たないのです。
不動産投資は株式投資と異なり、まとまったお金がないとスタートできないという参入障壁の高さや、パソコンで手軽に売買できない不便さなどが理由で、まだまだマニアックな一部の人の投資なのが現状なのです。
しかし、そんなマニアックな投資ですが、それを補って余りある魅力が不動産投資にはあるのです。「不動産投資の学校」では、まず、その魅力について述べるところから始めます。不動産投資の魅力には、下記のようなものがあります。
【不動産投資の魅力】
・働かなくても良い(不労所得が手に入る)
・お金を借りて行える(元手が少なくてもできる)
・生命保険を解約できる(団体信用生命保険に入ることができる)
・税金が安くなる
・動きが遅く安定している(暴落しても逃げ出す時間がある)
・実際の土地・建物が存在する(実物資産である)
・一国一城の主になった気分になる(まぁこれは気分の問題)
働かなくても良い
多くの方が一番にイメージする魅力は「働かなくてもよい(不労所得が手に入る)」ということだと思います。これは半分正しくて、半分は間違いです。確かにキャッシュフローがしっかりと残る優良な物件を購入することができれば、投資家である大家さんがやることはほとんどないので、不労所得といえます。
しかし、キャッシュフローがしっかりと残る優良な物件を探し出すためには、大量に物件を見て探しまくるという行動が必要であり、その点においては労働をしているからです。キャッシュフローがしっかりと残る優良な物件は投資物件全体の1%も存在しないため、多くの場合においてすぐに売れてしまいます。ゆえに誰より早く動いて誰より早く融資を付けて購入することが重要となってきます。そのため、購入するまでは人一倍労働しなくてはならないからです。
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/11/post_188161.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.そうは言うものの、株やFXであれば購入後も日々株価や外貨の推移を見ておかなくてはならないのに対して、不動産は買ってしまえば、後はほったらかしにしておいても大きな問題は起きないので、やはり働かなくてもよいといえるでしょう。
お金を借りて行える
「お金を借りて行える(元手が少なくてもできる)」というのも不動産の魅力です。投資は自己資金で行うのが一般的ですが、不動産投資では物件価格の1~2割の自己資金があれば、残りは融資を使うことができるからです。FXなどを除くと自己資金にレバレッジをかけられる投資というのは、不動産投資くらいのものでしょう。
また、不動産投資のレバレッジはFXのレバレッジに比べ安定的なのが良い点です。不動産投資のレバレッジは長期の事業性融資なので、月々の支払は固定されています。支払いが固定されているので問題なく経営できていれば安定します。
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/11/post_188161_2.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved. 一方、FXのレバレッジはある日突然、通貨が大暴落するとロスカットで預けていた証拠金はすべて消え失せるため、あまり安定的なレバレッジとはいえないでしょう。
生命保険を解約できる
不動産投資ではアパートやマンションなどの物件を購入する際に、銀行が指定する団体信用生命保険(以降、団信)に加入することがあります。この団信は優れた保険で、本人が亡くなった場合や仕事ができないような障害を持ってしまった場合などに、物件の借金がゼロになるというものです。
あまり想像したいことではありませんが、万一自分になにか不幸な出来事があったとしても安心できます。残された家族は借金が完済されたアパートやマンションを手にすることができるため、そのまま保有して月々の家賃収入で生活することも、売却して大金を手に入れることも可能だからです。そのため、今家族のために入っている「生命保険を解約できる」のです。
税金が安くなる
高所得なサラリーマンは税金をたくさん納めていますが、不動産投資では減価償却費などを計上することで、税金を安くすることも可能です。減価償却費についてはまた別の機会に解説しますが、不動産投資家は息をするように減価償却費の使い方を身につけておかなければなりません。
動きが遅く安定している
不動産は「動かない資産」というように非常に動きが遅いです。動きというのは、売買スピードなどを意味しています。株やFXでは1秒ごとに価格が上下し、一瞬で大暴落してしまうこともありますが、不動産ではまずありえません。
不動産の売買は一般的には3カ月や6カ月、1年以上かかることもあり、非常に時間がかかります。逆説的ではありますが、そのため不動産は非常に動きが遅く安定しているのです。動きが遅いため、仮に暴落しはじめたとしても、逃げ出す余裕があるのです。
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/11/post_188161_2.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.実際の土地・建物が存在する
それから不動産は実際の土地・建物が存在する実物資産です。企業が倒産するとただの紙切れになってしまう(すでにデータ化され紙すら存在しない)株に対し、実際にその場所に存在する土地・建物を購入するわけですから当然です。
実際にモノが存在するわけですから、少なくとも価値が0になることはないのです。ただし、もちろん都心の価値の高いエリアでキャッシュフローがプラスになる優良物件を購入していることが大前提です。
一国一城の主になった気分になる
これに加え、株式やFXのようにデータではなく土地・建物が存在するため、「一国一城の主になった気分になる」ことができるというのも、ある意味で不動産投資の醍醐味といえます。まぁ、これは気分の問題ではありますが、パソコン画面に映し出された株式やFXのチャートを見るよりも、自分のアパートやマンションを見るほうがモノを保有する欲求を満たすことができるのではないでしょうか。
このほかにも不動産投資にはさまざまな魅力が存在するわけですが、これらの魅力を手にすることができるのは、あくまで努力して成功した不動産投資家だけです。不動産投資も投資である以上、当然リスクが存在します。不動産業者の口車に乗せられてダメな物件を高値で買ってしまうなど、失敗した人はごまんといるでしょう。
不動産投資は他の投資に比べ金額が大きいため、失敗するとリカバリーするのが非常に困難です。そのために必要なリスクについて、またそのリスクを回避する方法については今後少しずつ解説していきたいと思います。
ということで、次回は不動産投資のリスクについて解説します。
(文=姫野秀喜/姫屋不動産コンサルティング株式会社代表)
※1:日本証券業協会による「顧客口座数」より
※2:統計局データより不動産賃貸を行っている116万世帯から、相続によるものを除いた
【プロフィール】
姫野秀喜(ひめのひでき)
姫屋不動産コンサルティング(株)代表。九州大学経済学部卒。アクセンチュア(株)で日本を代表する大企業の会計・経営コンサルティングに従事。独立・開業後、年間100件以上の実地調査から得られる詳細な情報と高い問題解決力で、一人一人に合致した戦略策定から購入、融資、賃貸経営の改善までを一貫してサポート。不動産に関する記事は週刊ダイヤモンド、週刊ビル経営、ニュースサイト等に掲載されている。発行するメルマガは2万5千部を超え、現在行っている無料相談は不動産を見極める力が身につくと評判。融資が厳しい現状でも、変わることなく1億円大家さんを多数プロデュースしている。著書に「確実に儲けを生み出す不動産投資の教科書」(明日香出版社)、「誰も教えてくれない不動産売買の教科書」(明日香出版社)、「売れない・貸せない・利益が出ない負動産スパイラル」(清文社)がある。
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2020/11/post_188161_3.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.
購入前に知っておきたい!中古マンション投資のメリット・デメリット
中古マンション投資におけるメリット・デメリット
投資を行うにあたり、投資物件のメリットやデメリットを知っておくことは非常に重要です。
投資をしてしまってからでは、思わぬ落とし穴があっても取り返しがつきません。投資する物件のメリット・デメリットをあらかじめ知っておくことで、投資におけるリスクを抑えることも可能です。では、中古マンション投資におけるメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
まずは中古マンション投資におけるメリットをご紹介します。
中古マンション投資をするなら、これからご紹介するメリットを最大限活用できるような物件を選ぶことが重要です。
- 物件の購入価格が新築マンションに比べて安い
中古マンションは、新築マンションに比べて物件の購入価格が安く設定されています。
これは築年数の経過により、不動産価値が下がっているためです。
物件は築年数が長くなるほど、購入価格が安くなる傾向にあります。
そのため、同じエリアの新築マンションに比べると、中古マンションは安く購入することができ、元手となる資金が限られている場合でも投資しやすいといえます。
ただし、全ての物件価格が中古になれば安くなる、というわけではなく、地価が高いエリアの場合、築年数が経っても高い価格を維持し続ける物件もあります。
- 入居者の募集をしなくて済む
中古マンションは既に人が住んでいることが多くあります。
その場合、人が住んでいる状態のマンションの経営を、購入後に引き継ぐということなので、新たに入居者を募集する必要がありません。
SUUMOなどといった物件サイトへ物件掲載の依頼をする必要がないため、時間や手間、そして広告を掲載する費用の節約にもつながります。
また入居者がすでにいるということは、すぐに家賃収入が得られるということです。
購入後すぐに収入が得られるという点もまた、中古マンションのメリットといえるでしょう。
- 利回りが新築マンションに比べて高い
多くの人が中古マンションを選ぶ理由の1つに「利回りの高さ」があります。
利回りとは物件ごとの収益性、つまり購入価格に対する収入の割合を%(パーセント)で数値化したものです。
「(年間家賃収入÷不動産の購入価格)×100」という式で算出することができます。
計算式を見ても分かるように、利回りは家賃収入が大きく、購入価格が安いほど高くなります。
中古マンションの場合、新築マンションに比べて購入価格が安い傾向にあります。
つまり利回りが、新築マンションに比べて高いということになるのです。
利回りの基本はこちらの記事がオススメです。
関連記事:不動産投資の利回りの計算方法を正しく理解しよう
中古・新築の利回り比較についてはこちらの記事を参照ください
関連記事:不動産投資では新築マンションと中古マンションどっちが良い?利回りの違いから解説
- 家賃収入の試算が簡単
中古マンションですでに入居者がいる場合、今までの家賃を引き継ぐことがほとんどです。つまり購入前に現在の家賃や空室率を確認することができるので、購入する前から家賃収入の試算が簡単にできるというメリットがあります。
一方、新築の場合は物件の種類や近隣物件の平均的な家賃相場などを調べたうえで、家賃を仮定するしかなく、必ずしも予測通りに家賃収入が得られるとは限りません。
その点、実測値に基づいたデータを購入前から知ることができるのは、中古マンションならではのメリットといえるでしょう。
- 資産価値が極端に下落することがない
物件は築年数が経つほど、その価値が下落します。
しかし下がるところまで下がると、その後の下落はゆるやかになる傾向があります。
特に築20年を過ぎた物件は、そこから極端に資産価値が下がることはほとんどないとされています。
つまり築年数の経った物件は、資産価値が比較的安定しているのです。
一方、新築マンションは、場合によっては20年経った頃には坪単価が100万円以上下がってしまうというケースも考えられます。
のちに売却することを考えたときにも、資産価値が比較的安定している場所を選ぶことは大きなメリットといえるでしょう。
- 優良物件がお得に購入できる
先ほどご説明した通り、中古マンションは新築マンションに比べて一般的に安く購入することができます。
これは都心の一等地など、入居者の需要が高い場所においても同様です。
中古マンションを購入する際、その古さから空室が出てしまわないか心配に思う人は少なくありません。
空室を作らないためには、入居者の需要が高い場所にある物件を選ぶことが重要です。
こうした場所にある物件は、新築のマンションだととても手が届かない値段設定のものも多くあります。
しかし中古マンションなら、良い立地の物件を購入できるチャンスがあります。
このように優良物件を安く手に入れることができるのも、中古マンション投資のメリットといえます。
デメリット
メリットがあれば、当然デメリットも存在します。
デメリットをあらかじめ知っておけば、物件の欠点に後から気付いて投資に失敗することもありません。
では、中古マンション投資のデメリットを見ていきましょう。
- 設備の交換や修繕に高額な費用がかかる
中古マンションへの投資で最も気を付けるべきポイントは、修繕やメンテナンスにかかる費用です。場合によっては、購入後すぐに全世帯の給湯器を取り換えなくてはならない、などといったトラブルが発生するかもしれません。
設備が壊れていなかったとしても、あまりに古い設備のマンションでは入居者が集まりにくいため、最新の設備への交換が必要になります。
物件を綺麗に、そして機能的な状態で維持するためにも、こうした費用は必要不可欠です。
購入前には設備の設置年数や、点検の状況などについても細かく確認しておきましょう。
そして必要と思われる修繕費などは、全てローンの返済計画に組み込んで計算することをおすすめします。
リノベーション中古物件の怖い落とし穴もありますので、ぜひ下記記事も参考にお読みください。
関連記事:リノベーション中古物件のリスクとは?
- 金融機関からの融資を受けられない可能性がある
不動産投資をするにあたり、金融機関からの融資は必要不可欠です。
融資を受けることで、少ない自己資金で投資を始めることができます。
しかし、中古マンションであまりに築年数の経っている物件の場合、資産価値がほとんどないとみなされ融資が受けられない可能性があります。
もし融資を受けられたとしても、全額ではない可能性があります。
こうなった場合、融資が受けられない部分は自己資金で賄うしかありません。
- 空室率が高くなる可能性がある
立地と家賃が同じ中古マンションと新築マンションがあった場合、多くの入居者は新築のマンションを選ぶでしょう。
中古マンションの設備が古い場合や、見た目がいかにも古い場合はなおさらです。
「古びている」という印象は、入居者からの需要を下げてしまいかねません。
結果的に中古マンションには、新築マンションよりも空室率が高くなるリスクがあるのです。
もちろん、定期的なメンテナンスやリフォームを行うことで、古さを感じさせないマンションへと変貌させることは可能です。
しかしそれにはそれなりの費用が必要になります。
例えば70~80㎡の中古マンションを新築同然に全体をリフォームする場合、500万円~600万円の費用がかかるとされています。
物件を購入する際にはこうした費用を加味したうえで、価格交渉などを行いながら慎重に検討しましょう。
以下、リノベーションにおける失敗例についてまとめています。
関連記事:不動産投資初心者は要注意!中古物件リノベーションの3つの失敗例
- 修繕積立金が計画通りに積み立てられていない
中古マンションの定期的な修繕に必要な費用は、「修繕積立金」として入居者から集められます。
しかし、マンションによってはその集金が計画通りに行えていないことがあるのです。
この場合、修繕費用は自身で立て替える必要があり、個人の投資家にとっては非常に大きな出費です。
また、その後入居者に対して、改めて修繕積立金を集金しなくてはなりません。
こうした事態を避けるためには、今までの修繕積立金の集金状況をあらかじめ確認しておくことが重要です。
企業オーナー必見! コインランドリー事業投資による節税策
工夫次第で顧客数を増やせるコインランドリー事業
中小企業の社長を悩ませている事項のトップ3は、「従業員の教育・管理」「在庫管理」「売掛金の回収」だといわれます。 逆にいえば、「従業員が不要」「在庫が不要」「売掛金が不要(現金回収)」という条件が揃ったビジネスは、ある意味で理想的です。そして、それにあてはまるのが、まさにコインランドリー事業なのです。
まず、不動産投資は基本的に資産投資です。コインランドリー事業投資は、資産投資と事業投資の「ハイブリッド投資」とでも呼ぶべき性格を持ちますが、基本的には事業投資です。収益利回りを比べると、不動産投資の賃料利回りは全国平均で5~7%、東京都内だと4%程度ですが、我々のコインランドリー事業投資の場合、事業収益の利回り9%程度が最低ラインとなっています。
また不動産投資は、周辺家賃相場によって、ほぼ収入(家賃)の上限が決まってしまいます。対して、コインランドリー事業の収入は、理論上は上限がなく、顧客が増えれば増えるほど、収入が増えると考えられます。コインランドリーの機器稼働率は12~15%程度のため、まだまだ余力があるといえるでしょう。努力や工夫次第で顧客数を増やせる可能性を秘めているのが、事業収益の魅力だといえます。また初期投資額は2,400万円程度からと、収益不動産投資に比べ、比較的少額での投資が可能です。
不動産投資はあくまで資産投資であり、最終的には売却するといった出口戦略を含めた投資スキームです。ところが現在では、物件の供給過剰と長期的な人口減少により、その出口戦略がうまくいくのかという懸念も強まっています。
「一般動産」として評価されるコインランドリー店舗
コインランドリーの「事業投資」という側面は、実は企業の財務戦略で大きな効果を生みます。収益不動産投資と比べても高い節税効果を得られる点が、コインランドリー投資の大きな特徴なのです。
まずコインランドリー事業の場合、土地は借地を利用するので費用(地代支払)になります。投資する対象は店舗(機器+建物)であり、金額的には機器が主です。これを会社で購入すると、コインランドリー店舗は、国税庁が定める財産評価基本通達129にある「一般動産の評価」にあたるため、減価償却後の簿価がその時点での時価となります。ここがポイントなのです。
コインランドリー事業は、よく収益不動産への投資と比較されます。収益不動産投資は、「従業員が不要」「在庫が不要」「売掛金が不要(現金回収)」という3条件を満たすため、コインランドリー事業に似ていることも確かです。そこで、コインランドリー事業への投資と、収益不動産への投資との違いを確認しておきましょう。不動産(土地)の場合は、路線価や公示価格で時価評価されます。いわば「相場」どおりです。ところが、コインランドリー店舗は上記のように簿価で評価されますので、評価額が非常に低くなります。たとえば、購入時に3,500万円(建物1,200万円、機器2,300万円)の店舗だとすると、15年後の簿価は、たったの246万円です。
コインランドリー事業に投資をしてから15年後、社長が退任するとします。そのときに、この時価246万円の店舗を、社長への退職金の一部として現物支給したとします。簡略化のため、退職金がこの現物支給だけだとすると、この退職金への課税はゼロになります。
他の形態との資産との比較ではどうなるでしょうか?
●現金1億円
●15年前に1億円で購入したマンション
●15年前に1億円(2.85件分)で購入したコインランドリー店舗
で課税関係を比較してみましょう。すると、それぞれの課税額は下記のようになります。
●現金1億円 税額:2,104万円
「10,000万円-40万×15年」の2分の1に課税
●15年前に1億円で購入したマンション 税額:756万円
「4,700万円-40万×15年」の2分の1に課税
●15年前に1億円(2.85件分)で購入したコインランドリー店舗 税額:5万円
「701万円(2.85件分)-40万×15年」の2分の1に課税
財産評価基本通達129により「一般動産」とされるコインランドリー店舗の節税効果は明白です。
さらに重要な点は、購入して15年後のコインランドリー店舗は、それからも事業収益を生みつづけるということです。つまり、「金のなる木」をほぼ無税で、会社から社長に移転できるわけです。
これは支給する側の会社にとってもメリットがあります。すでに減価償却を済ませた現物資産の移転ですから、キャッシュアウトを伴いません。もし仮に、その時点で会社の業績が芳しくなく現金が不足していたとしても、退職金の現物支給は可能でしょう。
ここでは、もっとも節税効果が大きい社長の退職金と絡めた財務戦略をご紹介しましたが、課税を抑えながら相続や事業承継に利用するなど、他にも使い方はいろいろ考えられるでしょう。いずれにしても、収益を生む事業でありながら、一般動産として簿価評価されるという点が、コインランドリー事業投資における財務戦略での最大のポイントです。
「投資金額の約70%」の「即時償却」も可能に
ちなみに、上記は「出口」の話でしたが、入り口=投資時においても、財務戦略に結びつくスキームがあります。コインランドリー事業への投資は、現在施行されている「中小企業経営強化税制」の適用が可能です。これを適用すると、投資金額の約70%の即時償却が可能になります。この割合は、物件や投資タイミングによっても異なり、65%から80%を超えることもあります。
もし当年度に大きな事業利益が見込まれる場合、この制度を利用してコインランドリー事業投資をすれば、大きな課税の繰り延べ効果が得られます。
なお注意点ですが、「中小企業経営強化税制」は令和3年3月末で終了の予定です(2020年10月時点)。令和3年3月末の時点で、実際にコインランドリーが稼働していないと適用が受けられません。コインランドリー事業の立ち上げには、通常5~6ヵ月程度かかりますので、もし「中小企業経営強化税制」の利用を検討される場合は、早めの準備をおすすめします。
JR東日本の終電繰り上げは他人事にあらず。不動産投資家、市場に与える影響とは?
JR東日本は10月下旬、2021年春に予定しているダイヤ改正で、首都圏17線区の終電を繰り上げると発表した。対象となるのは山手線や中央線、京浜東北線など、東京駅を中心とした100㎞圏内を走る路線ばかり。首都圏の主要路線が一律で終電時刻を繰り上げるのは、1987年にJR東日本が発足してから、初めてのことだ。この令和の大改正は、人々の住まいやライフスタイル、不動産市場にどう影響するのだろうか。

線区によって繰り上げの幅はさまざま
近距離区間でインパクトが大きい
なお、終電の繰り上げにあたっては、混雑による三蜜に配慮し、一部区間では終電前に列車を増発。金曜日などは、必要に応じて終電前に臨時列車を運転するという。また、同じタイミングで京浜東北線・根岸線、中央線や総武線の各駅停車など5線区で初電の繰り上げも行われる。郊外から都心に向けた列車でも終電時刻の繰り上げは行われ、実施日や詳細は12月に発表する予定だ。
具体的に繰り上げ時間は、下図をご参考いただきたい。
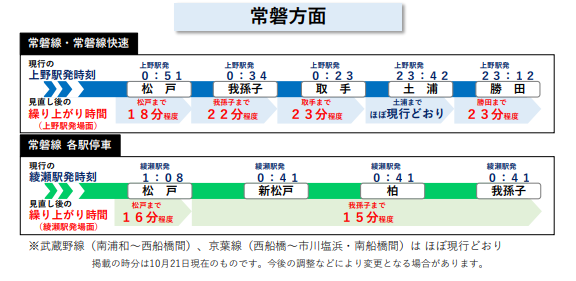
出典:JR東日本プレスリリース
例えば山手線の外回りだと、渋谷駅発池袋駅行きは現行の0時52分を19分程度、内回りは新宿駅発大崎駅行きが現行の1時00分を19分程度繰り上げる。ただし、品川駅(0時26分)~東京駅(0時39分)~上野駅(0時47分)から池袋駅は、ほぼ変わらない。
他の線区だと、京浜東北線・根岸線で最大33分程度、中央線快速で最大30分、同各駅停車で最大25分程度、青梅線なら最大で37分程度も終電が早くなる。どちらかというと、東海道線や横須賀線、宇都宮線など中距離の列車の繰り上げ幅はそれほど大きくないが、京浜東北線・根岸線の川崎駅~桜木町駅(33分程度)、中央線快速の新宿駅~高尾駅(30分程度)、青梅線の宮ノ台駅~奥多摩駅(37分程度)など、近距離の便はインパクトが大きい。その結果、深夜1時以降に走る列車は、ほぼなくなるようだ。
また、JR東日本は、このダイヤ改正を私鉄各社にも提示し、終電時刻の最終的な調整に入るが、私鉄側も終電繰り上げを検討していると報じられている。これにより、首都圏の主要電鉄は、一気に早じまいに向かっていくようだ。
終電が早くなることで早帰りが習慣化
それとも夜更かしが増える?
線区で違いはあれど、沿線に住む人にとって、影響は甚大だ。業種・業界によっては終電まで働くことは珍しくないし、徐々に開催傾向にあるライブや舞台を遠方から観に来ていた場合、終電に間に合うのか? アンコール途中で帰るのは気の毒だ。いくら新型コロナで減っているとはいえ、酔客がいないわけでもない。終電を気にして1次会で切り上げ、早々と帰路に着くサラリーマンも増えるだろう。飲食店やバー、カラオケ店などの経営者、これら業態に店舗を貸す不動産オーナーは不安に違いない。
他方、終電を逃がす人が増えることで、タクシーや深夜バス業界は恩恵を受けるに違いない。24時間営業のネットカフェ、ビジネスホテルは帰宅難民の避難先になるかも。あるいは、都心の繁華街ではなく自宅の最寄り駅まで帰ってから、ひとり晩酌を楽しむサラリーマンが出てきてもおかしくない。住宅街が広がるエリアの駅近くで居酒屋などの飲食店が流行る可能性もある。
仕事やプライベートで帰りが遅く、終電を逃す機会が増えてタクシーの利用が増えるなら、いっそのこと都心寄りに引っ越そうと考える人がいてもおかしくない。利便性重視の単身者なら、なおさらのことだろう。
ライフルホームズの「ワンルーム・1K・1DK/マンション・アパート・一戸建ての相場表」によると、京浜東北線・根岸線の家賃相場は、大宮(7.19万円)よりも、東京に近いさいたま新都心~西川口(6.80万円~6.67万円)の方が安く、都内に入っても赤羽(8.16万円)より東十条(7.60万円)、王子(7.52万円)の方が賃料相場はリーズナブルだ。
神奈川方面も同様で、大井町~川崎間は8万円台で、横浜も7.90万円するが、その間の鶴見(7.22万円)、新子安(6.50万円)は、ガクンと賃料相場は下がる(いずれも、2020年10月28日時点)。
当然ながら、駅周辺の環境、急行停車駅なのかどうかといった違いも関係するが、終電間近だと各駅停車しかない線区が多く、おまけに首都圏なら駅のそばにコンビニやファストフード店もあり、必ずしも規模の大きなエリアに住む必要はない。終電に追われるくらいなら、こういった家賃的に穴場スポットや、少し家賃が上がっても都心寄りに住みたいと考える人がいてもおかしくないだろう。
このように、終電の繰り上げはサラリーマンを中心に多くの人のライフスタイル、住まいに関する意識を変えるかもしれない。
健美家編集部(協力:大正谷成晴)
東京中古ワンルーム投資の「再現性」が高い3つのシンプルな理由
コロナウイルスの影響で、サラリーマンとしての収入が揺らぎ、本業とは別の収入源を作ることの重要性が浮き彫りとなりました。
書店等では、これからの資産形成を謡う書籍が数多く並び、その中でも目を引くのが、「カリスマ大家」による一棟不動産投資です。
億単位の資産形成が可能と言うこともあり、書籍だけではなくセミナーでも人気を集めています。
ただ、残念ながら、書籍やセミナーで紹介されている方法で不動産投資を始めたとしても、おなじような成功を収めることは至難のわざです。
特別な資産背景があったり、その時代だからできたノウハウ、そして、個人の能力に依存するなど、「再現性」という観点では非常に難度が高いのです。
一方で、不動産投資のなかにも、投資がしやすく、堅実に資産を形成できる再現性の高い投資法は存在します。それが「東京中古ワンルーム投資」です。
今回のコラムでは、東京中古ワンルームの資産形成の「再現性」について、実際のオーナー様の事例を交えながらご紹介したいと思います。
「人」を選ばない
 (画像=naka/stock.adobe.com)
(画像=naka/stock.adobe.com)

東京中古ワンルーム投資の再現性が高い理由は、3つあります。
一つ目は「人を選ばないこと」。
不動産投資と聞いてしまうと、購入できるのは、一部の高所得者に限られると考えられている方もいらっしゃいます。
たしかに、一棟アパート・マンションのような、大型の不動産投資の場合、昨今の厳しい融資環境もあり、投資をはじめられるのは、イメージにあるようなごく一部の方々です。
例えば、都心の一棟不動産をローンで購入する場合、現在ですと2割から3割程度の頭金を用意する必要があります。
都心一等地の鉄筋コンクリート造であれば軽く1億円を超えてきますので、 少なくとも2,000万円程度の資金が必要となります。
一方で、東京中古ワンルーム投資は、一般的なサラリーマン収入でも十分に検討が可能です。
自己資金も100万円ほどの頭金から始めることもできます。
また、金融機関によっては、諸経費をローンで組むことができ、手元に資金を残しつつ、10万円の頭金から不動産投資をスタートすることも可能です。
当社でも約8,300名のオーナー様がいらっしゃいますが、その8割以上がいわゆる「サラリーマン大家」です。
「物件」を選ばない
そして、東京中古ワンルームは「物件」も選びません。
東京23区内のワンルームであれば、賃貸需要が旺盛で、どのエリアでも安定して家賃収入を得ることができます。
当社には、20年以上にわたって中古ワンルームマンション投資を行っている社員がいます。
彼が所有するマンションのうち、最も稼働率が高いものは大田区「蒲田」にある3点式ユニットバスのワンルームマンションです。
所有日数は7,000日以上で空室期間はたったの60日程度と、99.1%の入居率を達成しています。
港区、中央区、千代田区のような都心の一等地でなくても、23区内の駅から徒歩10分以内のワンルームマンションであれば、安定して家賃収入を得られるのです。
「時代」を選ばない
さらに、東京の中古ワンルーム投資はいつの時代にあっても、安定して収入を生み出し続けてくれます。
当社では30年以上にわたって、都内の中古ワンルームマンションの管理を行っていますが、年間平均入居率は98%以上を維持し続けています。
高い入居率の原動力となっているのが、圧倒的な人口数と人口流入です。
1990年から2019年までの30年間で、他の道府県からの転入超過数は120万人以上。
100万人都市はひとつできた計算になります。そして、その多くがワンルームの入居者となる若者です。
また、最近はコロナウイルスの影響で、"転出"超過に陥っている報道も数多く目にします。
実際に、総務省統計局の「住民基本台帳・人口移動報告」によると、今年の5月、7月、そして8月では、東京全体の人口は減少しました。
ただ、大事なことは「どの年齢が減少しているのか」という内訳です。
年代別にデータを紐解いてみると、実は減少しているのは30代以降のファミリー世帯で、10代後半から20代の若者は、緊急事態宣言が発令された4月以降、増加し続けています。
この若者層をメインターゲットにしている不動産こそ「ワンルームマンション」です。
誰もが資産運用が必要な時代こそ「東京中古ワンルーム」を!
老後2,000万円問題で、改めて老後に向けた準備が注目を集めたように、これからは誰もが資産運用が必要になる時代になります。
このような時代に求められている投資法は、特別な人だけが成功する方法ではなく、誰もが始められ、堅実に資産形成ができる投資法です。
東京の中古ワンルームマンション投資は「再現性」が高い投資法で、堅実に資産形成でき、安定した収益を期待できます。
将来に向けて、資産運用をはじめるのであれば、ぜひ選択肢のひとつとして検討することをお勧めいたします。
不動産投資が「物件のよさ」だけでは成功できない深い理由
「管理会社」と「仲介会社」の違いを理解しているか?
不動産投資は物件のよさだけでは成功を収めることはできません。特に運用面では、客付け力が重要な指標となります。リーシング力について解説している本はたくさんありますが、うまく伝わっていない部分も多くあると感じています。それは、管理会社と仲介会社の違いです。
当社は賃貸店舗を所有しておらず地場もないのですが、常時96%以上の入居率を保っています。これは、当社のリーシング担当が「管理物件の入居率」を目標としているからだといえます。一方、仲介店舗は「手数料」を目標にしています。例えば、管理物件の入居率よりも仲介手数料や広告費、家賃保証会社など、あらゆるところからマージンを得ることに重きを置いているわけです。つまり、当社のようなタイプはストックビジネスのようなものであり、一方の仲介店舗は単発の手数料商ですので、ビジネスの仕組みが違うということです。
管理だけをしている会社であれば、管理手数料が利益の中心となり、客付け会社であれば賃貸仲介の手数料や広告費が利益となります。また、店舗で営業する客付け会社の場合、店舗運営のコストがかかります。
今はネットの時代ですが、管理会社と客付け会社の連携がどれだけとれているのかがキーとなります。どのような客付け会社が強いのかは一概に言い切れませんし、一社に任せて客付けが決まるという時代ではありませんから、管理会社が複数の客付け会社に入居募集を依頼していくのが重要です。
自主管理をして自分で賃貸仲介会社を一件ずつ回るという方も時々いますが、それを本業にしている管理会社に任せたほうが費用対効果は高いです。

そもそもの話として、一口に「不動産会社」や「客付け会社」といっても、例えばTVCMで見かけるような大手チェーン店は、一見客付け会社のように見えますが、地元では大手の管理会社であるケースが多いです。直営店舗の他地場の不動産会社がフランチャイズに加入しているケースもありますから、見た目は全国区のショップのように見えて、実態は地場の老舗管理会社であるということも少なくありません。
結局のところ大切なのは、しっかりとリーシングすることです。そのためにどうすればいいのかといえば、非常にシンプルな話です。入退去の管理やクリーニングやリフォーム手配を行い、客付け会社にきちんと情報を周知させること。またADなど、かかる経費をしっかりと配分することです。
物件に関していえば、空室を埋めるには、「キレイにすること」が基本です。退去になった部屋は迅速に原状回復工事や必要なリフォームを実施することはもとより、一棟丸ごと管理している会社としてエントランス・廊下・ゴミ置き場・EV・駐輪場など、常に全体をきれいに保っておくことが一つひとつのお部屋の入居促進につながる第一歩です。
賃貸経営は、目先の収益より「長期的な視点」が重要
物件購入はゴールではなく賃貸経営のスタートです。新富裕層は購入後にどのように賃貸経営に向き合うべきか、建物管理などコストについてお伝えいたします。
「お金持ちは3代で家を潰す」という話はよく聞きますが、これは初代の才覚で裕福になったとしても、2代目、3代目はお金の使い方が下手なので、資産を減らしていくという意味です。
使い方が下手とは、長期的視点・経営者視点を持たず、目先の損得で物事を判断するということです。「安ければいい」と短絡的に考えていると、そのときは小さな利益を得ても、のちのち大きな損を被るということが経営上ではよく起きます。
ですから、何事も構造をきちんと理解することが重要です。例えば、家賃が1000円上がると聞けばうれしくなってしまうものですが、わずか1000円のために2カ月も空室となっては元も子もありません。
そのためオーナーは、そうした目先の小さなお金のために、大きなところを見失わないようにしなければなりません。
また、客付け仲介店の営業マンは人の入れ替えが激しい傾向があります。オーナー様自ら顔入り名刺を持って挨拶回りに行ったものの、すぐ担当者が離職してしまったという例は珍しくありません。
特に地方は、地主という、管理会社にとってのビッグクライアントの物件が優先されるケースも多いため、自分の物件を後回しにされないために、現地の仲介会社を回られる方も多いです。そこまでしたのに担当者が離職となれば、不満な気持ちもよく分かります。
ただ、理解しておかないといけないのは、地方物件の多くがそうであるように、家賃が安い物件の場合、客付け仲介会社の収益が家賃1カ月分では割に合わないということです。なので、そういった物件は、賃貸募集の際に、高い広告費が必要であることを見越した価格で購入する必要があります。
つまり、表面利回りが高くても、客付けコストや原状回復費を考慮すると、家賃2、3万円の物件は投資に見合っていないというケースも多々あるのです。原状回復費については、今回の民法改正でほとんどがオーナー負担ということになりましたので、特に注意が必要です。
「必ずX後に売る」というこだわりは不要
高稼働の必要性と、購入後(買い進めや売却など)をどのように考えればよいのでしょうか。
最近、お客様から出口戦略について相談を受けることが増えました。しかし、そもそも30年という長さでお金を借りられることもすごいことですし、完済後も持ち続けるという選択肢もあるわけです。
にもかかわらず、なぜ「5年後に売る」といった戦略を立てる必要があるのでしょうか。5年後の相場は、誰にも読めません。それどころか1年先も、数カ月先でさえも予測が難しいのが経済というものです。
自分にコントロールできないものによって、自身の損益が左右されることは、できるだけ避けなければなりません。
ファンドバブルが弾けたのは、ファンドが「〇年後には必ず売却する」ということを決めていたために、実際5年後に相場が下がっていても売らざるを得なくなったためです。
30年間で好きなときに売れるのに、わざわざ5年後に売ると決めてしまう理由はないはずです。毎年「今は売り時か?」と検討する必要はあるものの、最初に確定する必要はありません。
むしろ「5年後に売れたらいいなと思っていたけど、市況が悪いから持ち続けよう」とか「3年だけど、今売ったほうがよさそう」、もしくは「急にお金が必要になったから売ろう」といった判断を自分でできることが長期投資の強みです。
したがって、イメージを持つことや毎年の定点観測・市場把握は重要ですが、「必ずX後に売る」というこだわりを持つ必要はないのです。
信頼できる管理会社の選択が成功の秘訣
私は物件購入においてバランスを大切にすべきという考え方を提案しますが、購入後もバランスが必要です。長期修繕計画に関しては、新築アパートを買う人の場合、20年経った中古アパートがどうなるのか理解したうえで新築を買うのならいいのですが、新築物件しか見ないのはリスクがあります。
また不動産会社との関係性についても、私は違和感を覚えます。あなたは不動産会社を「コンサルティング会社」として見ていますか、それとも「下請け会社」として見ていますか。「安ければいい」と考えるのは、下請け会社に対しての発想です。下請けだと見ているのなら、下請けのような会社しか選べないでしょうし、逆にコンサルティング会社だと思って見ているのなら、それにふさわしい会社と出会えるはずです。
私自身、管理は「当たり前の積み重ね」だと認識しています。当社のお客様には、すでに他社から物件を購入している方もいます。ただそのなかには、管理状態がひどいケースもあります。
管理については、数の論理が働くので、管理戸数が3000戸もしくは5000戸といったラインを超えないと、ビジネス的に生産性が高いとはいえません。当社の場合、そこまでの戸数にはなっていないのですが、売買があるので会社全体としては成り立ってはいます。そうでなければ管理戸数が多い会社でないと厳しいといえるでしょう。
特に、繁忙期に原状回復の業者に依頼する場合、やはり発注数が多い管理会社の依頼が優先される傾向にあります。繁忙期に暇な原状回復業者というのは、仕事のクオリティが低いから暇なのであって、言い方は悪いですが〝安かろう悪かろう〟のケースはやはり多くなりました。
そういったことを考え合わせると、管理会社のポイントは、質の高い工事業者を迅速に手配したり、入居者様からのリクエストに丁寧に対応したり、送金レポートを1日でも遅らせなかったりということになるのです。
杉山 浩一
株式会社プラン・ドゥ 代表取締役
宅地建物取引士
マンション管理士
入居待ち500件以上!「満室経営」続く、ミュージションの凄さ
快適な居住性と高い遮音性能を実現する賃貸マンション
「ミュージション」は、株式会社リブランが提供している賃貸マンションシリーズのブランド名です。24時間楽器演奏が可能*な優れた防音性能をもつことから、演奏家や作曲家など音楽関連業界のプロフェッショナルから、音楽大学の学生、愛好家などの間で、口コミなどを通して評判が広がり、高い知名度を誇っています。このような音楽に携わる人々の多くは富裕層であり、安定した収益を得られることができます。
*建物によって異なる。また、ドラムなど一部の楽器には制限がある。
「楽器演奏が可能な防音性能がある」とうたっているマンションは他社にもあります。しかしそれらと比べてミュージションの特筆すべき点は、「優れた防音性能」「住まいとしての暮らしやすさ」、そして「適正な建築コスト」が高いレベルでバランスのとれていることにあります。
防音性能は、床スラブや隔壁のコンクリートを厚くしたり、開口部を減らしたりするだけで、ある程度は高めることができるでしょう。しかしそれでは住まいとしては暮らしにくく、建築コストも高騰します。結局、不動産投資の視点でみるとデメリットが大きくなってしまうのです。
ミュージションの高い防音性能は、そんな単純な考え方によるものではありません。
「私たちは、第1号物件となる『ミュージション川越』以来、20年間で計20棟を建ててきました。その過程で、設計や素材選定、施工など、さまざまなノウハウを蓄積し、それらを改良しながら高い遮音性能を実現しています」と株式会社リブラン資産活用部の舘康之氏はいいます。だからこそ、一般のマンションと変わらない明るく風通しがよい住宅でありながら、D-75から最高でD-85という、高度な遮音性能を可能にしているのです(関連記事:『ミュージションへの「入居希望者が尽きない」本当のワケ』)。
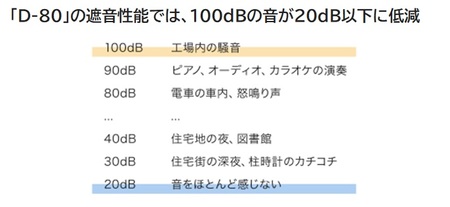
仲間が仲間を連れてくる「満室経営」
ノウハウによって実現される高度な遮音性だけが、ミュージションのすべてではありません。ほかの賃貸物件にはない特徴のひとつが、「ミュージションズクラブ」という入居者を中心としたコミュニティの運営です。いわば、建物というハードウェアと、コミュニティ運営というソフトウェアの両輪で成り立っているのがミュージションだといえるでしょう。

舘氏「ミュージションズクラブでは、セッションパーティやコンサートなど、さまざまな音楽関連イベントを実施しているほか、バーベキューやハイキングなど、音楽以外のイベントも実施しています。こうした活動を通じて、ときには異なるミュージションに住む入居者で新たにバンドを結成したり、音楽関連の仕事でのコラボレーションが生まれたりする事例が後を絶ちません。
賃貸マンションで入居者コミュニティを運営していること自体、珍しいことですが、ミュージションズクラブは、物件のオーナーも参加したり、音楽好きであれば入居者以外でも加入できたりなど、一線を画す存在です。単なる入居者のための連絡・交流組織ではなく、音楽を愛する人たちのためのコミュニティを形成することで、非入居者は自然と入居予備軍になるというメリットがあります」
既に入居している人たちも「ミュージションというコミュニティに所属している」という感覚を抱くことから、たとえば結婚を機により広いミュージションに引越しを希望するというような、帰属意識の醸成にも貢献しているといいます。
周辺相場より3割高い賃料で、入居率100%を実現
高い遮音性能を持ちながら暮らしやすい建物への評価、強い帰属意識が生まれるコミュニティ運営などにより、ミュージションは、供給住戸数よりも入居希望者数のほうが圧倒的に多い状態が続いています。入居希望者に対応するため、株式会社リブランではウェイティングリストを作っていますが、現在の登録数は500組以上もあるといいます。まさに「行列のできる賃貸マンション」といえるでしょう。
舘氏「2020年に竣工した最新の『ミュージション川崎宮本町』では、36戸を3期にわけて入居者募集しましたが、1期(12戸)は3時間、2期(10戸)に至ってはわずか10分で満室になりました」
2020年9月末時点の直近データを見ると、ミュージション20棟の入居率は100%。全529戸(分譲含む)のすべてが満室で、空室は1戸も生じていないといいます。しかも特筆すべきは、ミュージションの賃料は、周辺相場と比べて平均して3割程度、高く設定しているという点です。
オーナー視点でいうなら「高い賃料を設定できて、しかも空室になりにくい……。これは理想のマンションだ」と考えるでしょう。しかし、これまでのミュージションにウィークポイントがないわけではありませんでした。そのウィークポイントとはなにか、さらに、それを克服するために新たに打ち出したソリューションについて、次回、解説します。
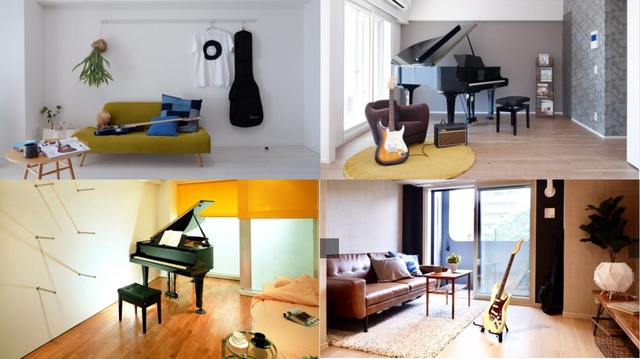
埼玉の父が突然死…「何いってんだ!」長男が切れた、姉の一言
入籍にこだわらないカップル。内縁の夫の死後…
現在は相続件数のうちの相当数がトラブルになっているといえますが、実際にどんなトラブルが多いのでしょうか。一般的によく起こりうるケースとしては次のようなものがあります。
ケース① 内縁の妻(事実婚)
神奈川県に住むBさんが亡くなったのは半年ほど前のこと。Bさんと一緒に住んでいたCさんとは事実婚で、いわゆる「内縁の妻」という関係でした。
事実婚はすでに20年近くにもおよぶのですが、もともとBさんには奥さんがいて、その奥さんは20年以上も前に他界しています。Cさんと正式に結婚すればよかったのですが、Bさんと亡くなった奥さんの間には3人の子どもがいて、その頃まだ結婚前だったために、Cさんと入籍することにためらいがあったのです。
その後、子どもが結婚して家庭を持つようになり、すでに問題はなかったのですが、なんとなくそのまま内縁関係を続けてしまったそうです。
相続では、内縁関係の妻には遺産を受け取る権利が認められていないため、Cさんが現在住んでいる自宅も、Bさん名義のもので、Bさんの子どもが相続することになってしまいます。結局、Cさんが住んでいる物件を売却して相続税を支払うことになり、Cさんは遺産をもらうどころか、自分が住んでいた自宅も追われることになってしまいました。
最近では、入籍にこだわらないカップルも多くなってきていますが、そのような状態でパートナーが亡くなると、相手方は遺産を受け取ることができません。こうした法的に相続の権利がない内縁関係の妻に対しては、遺言書を残すのが結果的に相手方を守る有効な方法といえます。
ケース② 遺産を請求するバックに嫁の存在
千葉県に住むFさんは、母親と同居していましたが、その母親が1年ほど前に亡くなりました。四十九日が終わったときに、税理士のすすめもあって、弟2人と遺産相続について話し合いをしました。
「介護してたからね」で遺産分割に納得のはずが…
母親の遺産は、父親が残してくれた家と土地、そして現金が2000万円ほどありました。Fさんは、土地と家をもらう代わりに、現金は弟2人で分けるという形でどうかと提案しました。家と土地は合わせて3000万円程度の評価で、しかもFさんは長い間寝たきりだった母親の面倒をずっと見てきたこともあり、弟2人は不満もなく納得して帰りました。
ところが、その後1カ月ほど経ってから、弟の1人が「もう少し遺産がほしい」と言い出しました。相続人は子ども3人なんだから、3等分すべきだというのです。

嫁にも責められ…(写真はイメージです/PIXTA)
よくよく聞いてみると、弟の嫁が後ろにいてたきつけているようです。弟の嫁は、美容室をやっており、やり手で通っているのですが、店舗を拡大しすぎて、経営があまりうまくいっていないともいわれていました。
兄弟3人で資産を3等分するためには、現在Fさんが住んでいる家を処分して現金にしなくてはならなくなるので、Fさんは困り果てました。とりあえず、家庭裁判所に調停を申し立てることにしましたが、「こんなことなら、お母さんに遺言書を書いておいてもらえばよかった…」と後悔しています。
「母は、私が一緒に住んでいたから、この家は私が継ぐという前提で何もかも進めてきたのです。私が、母のわがままに耐えることができたのも、ある意味でそういう前提があったから…。弟も、気の強い嫁さんで困っているみたいだけど…」
結局、家庭裁判所の調停が始まってから半年以上経ちますが、話し合いでは結論がつきそうもなく、このままでは裁判所の審判を仰ぐしかなさそうです。
こうした事例は、いずれも「遺言書」を残しておけば防ぐことができたトラブルですが、相続が「争続」になってしまうと予想できる人は、やはり遺言書をきちんと残しておくことが重要といえます。例えば、再婚した人、内縁関係が続いている人といった具合に婚姻関係が複雑な人は、遺言書を残しておくべきでしょう。
一方、こうした複雑な事情がなくても「相続トラブル」は起こるものです。これまで実際に取り扱ったケースの中には、子ども同士でもめてしまうケースもありました。
長女の主張に長男が切れた!「あなたはさ…」
ケース③ 姉と弟が遺産分割でトラブル
埼玉県に住むYさんが定年退職を直前に突然死したのは2年前のこと。生前に自宅のほか、アパートを購入して、退職後は家賃収入で生活。将来的には不動産を売却して、夫婦で老人ホームに入居して生活することを予定していました。ところがYさんの突然死で、奥さんとその子ども(長女、長男)の3人が相続人となりました。
遺産の分割をするために話し合ったところ、長女が突然こんな主張を始めました。
「あなたは、結婚したときにマンションを買うということで、お父さんに1000万円の資金援助してもらったでしょう。あの分も相続財産の中に入れて計算すべきでしょう」
この言葉に対して、長男は切れました。
「何をいってんだ。あれは結婚祝いでもらったもの。そもそもお金の意味も目的も違う」
結局のところ、両者の主張は平行線をたどり、マンション購入費用1000万円の特別受益をめぐって、協議が成立せずに調停が申し立てられました。調停では、お互いに父親の生前にさまざまな特別受益があったと主張し合うことになり、調停は泥沼化してしまいました。
さらに、不動産の評価額についても、長女と母・長男の間に争いがあり、不動産鑑定士を入れて高額な鑑定費用を払うことになってしまいました。2人しかいない姉と弟は当然、険悪な仲となり、相続をめぐる争いはいまも続いています。
■争続を防ぐ最も有効な方法はやはり「遺言書」を残すこと
「争続」にまつわるトラブルが、年々増えていることは冒頭で紹介した司法統計などの数字でも明らかです。しかし、こうした争続のトラブルを見ていると、その原因が何であるかが見えてきます。
「争続」トラブルを防止するため、最も有効な方法は「遺言書」を残すことです。遺言書をきちんと残しておかなかったばかりに、トラブルになるケースは非常に多いのです。
そして、もうひとつが「不動産」にまつわるトラブルです。これまでに何度か指摘してきましたが、先祖代々からの土地や家をどうするかが、しばしば問題となります。
「長男が親の面倒を見る代わりに…」が終わった今
なかでも、昔なら長男が親の面倒を見る代わりに、その土地と家を相続するというパターンが多かったのですが、それが、現在では誰もが相続の権利を主張する時代となり、トラブルに発展してしまうようです。
不動産を相続人の間で共有した場合、単独で所有する場合に比べて問題が起こりやすいので、注意が必要です。
具体的には売買や賃貸したい場合、他の共有者の同意が必要になりますし、もし共有者の中でまた相続が発生した場合、共有者が多数に増えて、いざ処分しようとしても、他の共有者の同意を得るため多大な労力を必要とする場合があります。いずれにしても、こうしたトラブルの原因を認識して、生前に手を打つことが重要といえます。
年収1000万円の独身医師が「不動産に1億円」突っ込んだら…
年収1000万円で独身。住宅ローンはなく…
筆者が不動産投資のアドバイスをしている医師のケースをご紹介しましょう。
彼は年収1000万円で独身。住宅ローンはなく、預金や投資信託などで約2500万円の金融資産を所有しています。
余談ですが、融資に関しては妻帯者と単身者を比較すると妻帯者のほうが有利です。妻も働いて稼ぐことができるとみなされるからです。アパートローンなどでは連帯保証人を求められることが多いのが実情ですが、妻帯者であれば奥さんを連帯保証人にすることができます。
話を戻して、この医師とはいろいろと話をしているなかで、物件価格1億円のマンションを運用してみてはどうか、という話になりました。これだけの好条件なら、金融機関はどこでも融資してくれるでしょう。
とはいえ、やはり銀行へ融資の相談に行く際には不動産会社などの紹介で行くのがベストです。銀行の融資担当者はお金を貸すことが仕事で、それが自分の成績になるとはいえ、信用は大切。しかるべきルートで紹介してもらって行くようにしましょう。
医師は自分にとってどれが得なのか、という視点でローンを選ぶことができます。つまり、投資において重要な金利と融資期間から、有利な資金調達先を選べるというわけです。この医師のケースであれば、最初の物件を購入する時に頭金を2割程度入れておき、家賃収入できちんとローン返済を進めておけば2〜3年でさらに大型物件への投資が可能になります。こうなると、もう資産は雪だるま式に際限なく増えていくというわけです。

現在では、年収の高い外資系企業の会社員よりも、年収の低い医師のほうが融資を受けやすいと言われています。個人で借りるアパートローンはパッケージ型で、融資額は年収の10倍程度が上限。つまり、年収1000万円の会社員であれば、1億円くらいまでしか借りることができません。ところが、金融機関によっても異なりますが、医師であれば、およそ25倍前後までは融資が受けられるというところも少なくないのです。
もちろん、不動産への融資だけではなく、開業する時には開業資金を借りることができるのも医師ならではのメリットと言えるかもしれません。独立行政法人福祉医療機構をはじめ、医師信用組合、国民生活金融公庫、自治体の創業支援融資制度など、さまざまな制度融資を活用すれば、固定金利で有利に資金を調達することも可能です。さらに、資産管理会社などの法人格にすれば、法人融資の扱いとなり、信用保証協会が利用しやすくなります。
つまり医師という肩書きは、資金調達の際にもその威力を思う存分に発揮してくれるというわけなのです。
年収1000万円を超えたら「法人化」の検討を
ここまで融資について詳しく書いてきましたが、注意しておきたいのは、所得税の税率なども視野に入れた真の意味での資産形成です。
たとえば、個人の年収は1800万円を超えると最高税率40%が適用され、住民税10%を合わせると収入の半分が税金となってしまいます。こうなると、必要経費として計上できる建物の減価償却費の割合なども大切になってきます。
もちろん法人化も視野に入れておく必要があるでしょう。現在、法人税率が引き下げられている一方で、個人所得税の最高税率は2015年に45%へ引き上げられることが決まっています。つまり、個人は増税、法人は減税という方向へ向かっているといえるのです。
これから不動産投資を行う場合には、給与所得が年収1000万円を超えるくらいから、法人化の検討は必須といえそうです。
アメリカ不動産投資の現状は?オープンハウスに聞いてみた
仕入れ担当者が語る「アメリカ不動産投資の現状」
【対談者紹介】
もふもふ不動産のもふ…サラリーマンで研究開発の仕事をしていたが、リーマンショックで会社がつぶれかけたのをきっかけに副業を開始。株式投資、不動産投資、ブログ、YouTubeで稼げるようになり、2019年3月末でサラリーマン退職。YouTubeでは投資や経済など役立つ情報を発信し続け、登録者25万人達成。Twitterのフォロワーは約7.5万人。もふもふしたものをこよなく愛する投資家、経営者。
株式会社オープンハウスアトランタ支社長 豊岡昴平氏…高校卒業後に渡米し、Unversity of Central Missouriを卒業。ホノルル国際空港を拠点に航空機パイロットに従事した後、人に惹かれオープンハウスに入社。仲介営業部門での経験を経たのち、ウェルス・マネジメント事業部立ち上げに伴い米国赴任。現在は全米の物件仕入れ業務の責任者を務めている。
【対談者紹介】
もふもふ不動産のもふ…サラリーマンで研究開発の仕事をしていたが、リーマンショックで会社がつぶれかけたのをきっかけに副業を開始。株式投資、不動産投資、ブログ、YouTubeで稼げるようになり、2019年3月末でサラリーマン退職。YouTubeでは投資や経済など役立つ情報を発信し続け、登録者25万人達成。Twitterのフォロワーは約7.5万人。もふもふしたものをこよなく愛する投資家、経営者。
株式会社オープンハウスアトランタ支社長 豊岡昴平氏…高校卒業後に渡米し、Unversity of Central Missouriを卒業。ホノルル国際空港を拠点に航空機パイロットに従事した後、人に惹かれオープンハウスに入社。仲介営業部門での経験を経たのち、ウェルス・マネジメント事業部立ち上げに伴い米国赴任。現在は全米の物件仕入れ業務の責任者を務めている。
もふ「近年新しい投資先として注目を集めているアメリカ不動産投資ですが、『本当のところはどうなんだ』と知りたがっている方が多いと思います。 今回は、株式会社オープンハウスにてアメリカの不動産を取り扱う豊岡さんにお話を伺います。まず豊岡さんは、現地でどのようなお仕事を担当されているのですか」
豊岡「私はオープンハウスアトランタで支社長を務めており、米国の不動産仕入れ全体を統括しています。日本側の販売スタッフと連携を取りながら仕入れた不動産をリフォーム、商品化を行い日本の投資家の皆様へ販売したのち、管理も担うというビジネスモデルを手掛けております」
もふ「アメリカの不動産を、日常的にたくさん見ているのですね?」
豊岡「はい。これまでに5,000~6,000件を見てきました。現在は毎月、約80棟を仕入れています」もふ「そのすべてを決済されているのですか? 責任重大ですね。 本日は何でも質問して良いとのことですので、色々と聞いていきたいと思います。アメリカ不動産投資は、築22年以上の木造建物を購入して4年間で減価償却した際、大きな節税効果が得られることから、富裕層を中心に注目を集めていましたが、昨年12月の税制改正大綱を受けて節税メリットを受けることが難しくなったと聞いています。実際のところはどうでしょうか?」
2020年の税制改正…アメリカ不動産への影響は?
豊岡「昨年12月の税制改正大綱を受け『オープンハウスはアメリカから撤退する』と噂されたりしたようですが、現状のアメリカ不動産の売れ行きは絶好調です」
もふ「絶好調ですか?(笑)」
豊岡「はい(笑)。2020年9月には、月間の販売実績が115棟に上りました。この数字は過去最高の販売実績で、税制改正前の月間112棟の販売記録を更新したのです」
もふ「すごいですね、なぜそうなったのでしょう?」
豊岡「購入者割合が大きく変化したことが影響していると考えています。税制改正大綱が発表される前は、購入者の95%が個人投資家で、主な購入目的は節税でした。ですが現状は個人での購入が50%、法人での購入が50%という割合に変化しています」
もふ「個人が減り、法人の割合を増えたことが販売記録更新につながったのですね。そもそもなぜ法人が増えたのでしょう?」
個人投資家を落胆させる税制改正だったが、法人は…
豊岡「今回の税制改正(※)は、 “個人”に限定された内容でした。築22年以上の木造建物の場合、4年間で建物代金を経費計上する事が可能ですので、経費計上額にご自身の税率をかけた額が節税できるということです。
個人の場合、売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超える物件に関しては、譲渡益にかかる税率が約20%に下がりますので、所得税住民税の税率が55%の方が購入時と同額で売却した場合、差額の35%が丸々節税可能でした。今回の改正はここにメスが入った形なので、法人の簡便法を利用した減価償却は引き続き利用可能です。
あくまで私の推測ですが、法人は経費計上額にかかる税率と売却時の譲渡益にかかる税率が同じで、節税ではなく税の繰り延べにとどまるため、改正の対象外になったと考えます」
もふ「節税した分が、売却時に跳ね返る制度なんですよね」
豊岡「そうですね。 正直、税制改正大綱発表が発表され、以前に個人で購入して頂いたお客様から多くのクレームが来るのではないかと心配しておりました。しかし、ふたを開けてみると重大なクレームは一件も発生しませんでした。そんななか、特に勇気づけられたのが、税制改正大綱発表前に個人でご購入いただいた方に、大綱発表後にも個人でご購入いただいたことです」
もふ「それはなぜですか?」
豊岡「個人購入のメリットが、完全になくなったわけではないからです。 簡便法を利用した最短4年間での減価償却こそできなくなりましたが、『法定対応年数に基づく償却』は引き続き可能です。
また、アメリカ不動産は減価償却可能部分である建物の価値の割合が、日本の不動産と比較すると非常に高く、築年数が古くなってもその価値が維持されるため、税制改正前ほどの恩恵は受けられなったものの、メリットは引き続き存在しています 」
もふ「なるほど。 もう少し中長期で見るというイメージですね」
豊岡「そうですね。今までは4年間で建物価値を全て償却しきるといった商品でしたが、税制改正を受けて商品性を見直し、今までの7~8割の節税効果を10年程で取れるような商品設計に変更しました」
もふ「オープンハウスさんで不動産を購入した場合、自分でしなくてはいけない作業などは特に無いのでしょうか?」
豊岡「はい。融資と管理業務をしっかり押さえ、煩雑な作業をすべて巻き取ったうえで、投資家の方々にビジネスクラスのようなサービスを提供しております」
不動産投資におけるアメリカン・ドリームは未だ健在
もふ「先ほどの質問に戻りますが、法人購入が増えた理由はどのように分析されていますか?」
豊岡「今までアメリカ不動産のライバル商品は、全損保険やオペレーティングリースなどの法人税対策商品でした。しかし、全損保険においては昨年に販売停止になり、オペレーティングリースの代表的な商品である航空機リースは、新型コロナウイルスの影響により航空業界が大きな打撃を受けています。その代替商品として、アメリカ不動産投資が注目されていると考えております。
また、弊社が法人様への融資を開始したことも要因ではないでしょうか。現在、弊社グループで用意している法人様への融資商品は販売価格の50%までのご融資となります。そうしますと、物件価格のうち約80%が経費計上可能ですので、投下自己資金に対して160%分の損金を発生させることができるのです。」
もふ「オープンハウスさんは税制改正を受け、変化の波にうまく乗られたからこそ、過去最高の販売実績を達成できたのでしょうね」
豊岡「そうですね。それに加えて、アメリカ不動産は賃貸の空室率が非常に低く、インカムゲインが安定的に期待できることや、人口増加・物価上昇の影響を受け不動産価格が継続的に上昇している事も、投資家を後押ししていると考えています。節税だけでなく、アメリカ不動産本来の魅力も含めて、投資を検討していただきたいですね」
不動産投資、年収500万円で買える物件は?価格や利回りを事例で解説
1.年収500万円で目指す資金調達
年収500万円の一般的なサラリーマンが不動産投資ローンで資金調達をおこなって収益物件を購入する際、年収以外の属性面についてどのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。また、融資限度額や融資条件の目安はどれぐらいなのでしょうか。
不動産投資ローンの融資では、物件の収益性や担保性が評価されますが、家賃収入からローン返済を賄えなかった場合の返済余力として、借りる人の属性評価(与信)も重視されます。
以下では、物件の評価を考慮しない場合の資金調達と物件取得価額の目安について説明していきます。
1-1.属性評価のポイント
属性評価では、収入以外にも、勤務先と勤続年数、年齢、家族構成、持ち家か賃貸か、金融資産の状況などの項目について考慮されます。
勤務先企業が上場企業であったり、大企業であったりすればプラス評価となるでしょう。勤続年数も長いと高評価となります。
年齢も属性評価での重要なポイントとなります。年収が500万円以上の方でも年齢が高いと金融機関から融資を断られるというケースも少なくありません。
家族構成は、配偶者がいれば配偶者の収入・資産についても加味してもらえる可能性があります。一方、扶養家族がいればその分生計費用負担が増えるため、可処分所得の判断にも考慮されるでしょう。
持ち家か賃貸か、という点についても、賃貸であれば家賃が生計費用として支出されるという面から、返済能力評価においてマイナス評価となります。
返済能力は、毎月の収入に対する返済比率がポイントになります。金融資産の状況も、返済能力という面から、多ければプラス評価となります。
1-2.融資限度額、融資条件の目安
過去の事例から、不動産投資ローンは大まかに年収の7倍~10倍が融資限度額となる傾向にあります。
年収500万のサラリーマンが不動産投資ローンを組んで収益物件を購入する際、資金調達できる金額は5,000万程度まで、融資条件は、金利2~3%程度、返済期間20年~35年(物件の残存耐用年数による)が一つの目安と言えるでしょう。
属性評価は年収だけではなく上述の項目も考慮され、物件によって収益性・担保性の評価が加味されることもありえます。
2.エリア、築年数、物件タイプ、利回りのパターン事例
年収500万円のサラリーマンの方の融資限度額などの範囲で、収益性・担保性による物件の評価も考慮し、無理なく購入できる物件について解説していきます。
不動産投資ローンの融資審査においては、物件の収益性・担保性が評価されます。収益性については、賃料収入で返済が回るかどうかという点を一定のストレスをかけて検証されます。
担保性についても、土地と建物の積算によって売却した場合の回収可能額を評価します。エリア、築年数、物件タイプ、利回りのパターンで分け、実際に売出されている物件に近い事例を3種類取り上げてみます。
2-1.東京23区内、新築区分マンション、4.67%
都心新築区分マンションを購入するという選択肢があります。販売価格3,080万の中央区新築分譲マンションを購入し、相場家賃月12万で入居付けをおこないます。自己資金600万を入れて、期間35年、金利2%の条件であればローンを組める可能性があります。
| 物件種別 | 新築区分マンション |
|---|---|
| 価格 | 3,080万円 |
| 表面利回り | 4.67% |
| エリア | 東京都中央区 |
| 構造・専有面積 | 鉄筋コンクリート13階建て・25平米 |
| 管理費・修繕費 | 12,000円 |
| 参考収支(稼働率90%) | 年間220,000円 |
新築区分マンションは建物の法定耐用年数が多く残っており1戸当たりの価格も安いため、購入検討しやすいメリットがあります。
しかし、築年数の経過につれて家賃収入が減少していくことで将来的に市場価格が下落することも考慮し、貯まった資金で繰上げ返済やリフォームをおこなう、などの工夫が有効でしょう。
2-2.神奈川県横浜市、築3年一棟アパート、8%
首都圏郊外の築浅一棟アパートを購入できる可能性があります。たとえば、販売価格4,695万円、表面利回り8%、神奈川県横浜市保土ヶ谷区の築浅アパートのケースを見て行きましょう。
土地評価が路線価で1,450万、建物評価が1,530万程度、自己資金900万程度、期間20年、金利2.5%の条件でローンを組んだとします。
| 物件種別 | 築3年一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 4,695万円 |
| 表面利回り | 8% |
| エリア | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
| 構造・専有面積 | 木造2階建て・112平米 |
| 維持費率15% | 年間560,000円 |
| 参考収支(稼働率90%) | 年間420,000円 |
先ほどの新築区分マンションと比較して総投資額が大きくなることで必要な自己資金も増え、融資条件も厳しくなることが分かります。一方、投資対象の戸数が増えるため空室が出た際の影響は少なくなり、収益性が高くなります。
アパートは主に郊外での運用となるため、将来的な賃貸需要を見込めるかどうか、エリア選定を厳しく行う必要性が高まります。マンション投資と比較してややリスクの高い投資方法と言えるでしょう。
【関連記事】「マンション投資 vs アパート投資」どちらに投資すべき?両者を徹底比較!
2-3.東京23区内、中古区分マンション、7.8%
首都圏都心部の中古区分マンションを購入することを考えてみます。たとえば、販売価格1,300万、台東区駒形の築28年区分マンションを購入し、相場家賃8.5万で入居付けした場合です。自己資金500万を入れて、期間20年、金利2.5%の条件でローンを組んだとします。
| 物件種別 | 築28年区分マンション |
|---|---|
| 価格 | 1,300万円 |
| 表面利回り | 7.8% |
| エリア | 東京都台東区 |
| 構造・専有面積 | 鉄筋コンクリート9階建て・22.5平米 |
| 管理費・修繕費 | 22,700円 |
| 参考収支(稼働率90%) | 年間150,000円 |
新築区分マンションより融資年数が短く設定されていることから年間の収支が下がっていますが、不動産投資ローンの残債をより短いスパンで解消することが可能です。また、建物価格の下落リスクが少ないことも中古マンション投資のメリットと言えるでしょう。
ただし、中古マンションは新築マンションと比較して空室率が上昇する傾向があります。投資前のシミュレーションは慎重に行うことが重要です。
【関連記事】【決定版】中古マンション投資で失敗しないための10のポイント
まとめ
年収500万円から検討可能な物件では、は都心新築区分マンション、首都圏郊外の築浅一棟アパート、都心の中古区分マンションなど幅広い物件タイプが検討可能です。
収益性・資産性のバランス面からは、家賃と建物価格の下落リスクが少ない分、新築区分マンションより中古区分マンションにメリットがあるとも言えます。ただし、融資条件が厳しくなることから月々のキャッシュフローに注意が必要になります。
年収以外の属性によっても、購入できる物件やローン条件が変わってくるので、各自の事情に応じた投資戦略を立てていくことが大切です。
札幌よりも「青森の不動産」のほうが儲かる信じられない理
人が集まる街は、実は物件も「供給過剰」状態
収益用不動産を所有するなら、たとえば東京など人口動態から見て人が多く集まる街に持ちたいと考えるのは当然のことです。人が多く集まる街なら、家賃収入を得るうえで最大のリスクである空室を避けやすくなります。
ところが、それは不動産投資を考えている人なら誰でも考えます。つまり、人が集まりやすい人気の街には、それだけ不動産が多いというわけです。
その顕著な例のひとつが、札幌の不動産問題です。札幌といえば、北海道最大の都市であり、ビジネスでも旅行でも人気の街。北海道大学もあり、学生も多く暮らしています。ところが、実は札幌の中心街には家賃1万円台のワンルームマンションやアパートがゴロゴロしています。これは一体どういうことなのでしょう?
北海道の中でも人口が集中する札幌は、道内はもちろん、本州などからも人口が流入しています。ビジネスの拠点であり、観光地としても人気、しかも歓楽街もある。だから、誰でも不動産を所有すれば儲かるはずだ、と考えるわけです。物件が売れれば、建設業者はどんどんマンションやアパートを建てます。
その結果、投資物件の供給が極端に過剰になり、家賃を1万円台にしても入居者が決まらないワンルームが溢れました。家賃が1万円台でも入居者が決まらないわけですから、敷金・礼金といった初期費用も極端に安くなっています。一カ月の家賃はホテルに一泊するのとそう変わりません。物件によっては、3泊4日で札幌へ旅行するなら、ワンルームマンションを借りたほうが安い、なんてこともあるかもしれません。
もはやこうなってしまうと、利益が出ないからといって売ろうにも売れないという状況です。投資としては完全に失敗といえるでしょう。
一方、需要も供給も少ない「青森」の物件は…
今、札幌で不動産を所有するくらいなら、過疎化が進んでいる青森で不動産を所有する方がよっぽど儲かります。青森は確かに人口が減少傾向にありますが、その分新築物件もそれほど建ちません。土地を担保にしてアパートを建てようにも、土地が安すぎて建てられないのです。
需要も少ないのですが、供給も少ないわけですから、ワンルームの家賃も3万〜4万円で推移しているというわけです。

この程度のことであれば、ちょっと現地へ行ってみればすぐにわかります。また、実際に行かなくても、賃貸物件情報を紹介するサイトなどで調べれば、賃貸物件の需給感程度ならわかるでしょう。家賃収入で借入金を返済しながら、将来にわたって資産となる物件を所有する。そんな不動産投資を目指すのであれば、地域ごとの需給バランスを調べることが必要になります。
ハリケーン、竜巻…米国不動産投資で考えるべき「災害リスク」
不動産にも大きな被害をもたらす自然災害
自然災害大国と言われる日本。全国各地で毎年のように自然災害が発生し、さまざまな被害を及ぼしています。ここ数年では、2018年の西日本豪雨や同年の台風21号、北海道胆振で発生した地震、さらに2019年に千葉県を襲った台風15号などが、いずれも深刻な被害をもたらしました。
自然災害で、最も避けなければならないのは人的被害ですが、家屋倒壊や浸水などの不動産被害も無視できません。台風15号では1万件を超える家屋被害が報告されました。不動産損害額は自動車保険損失推計を含め、3400〜7400億円に達するという試算もあります(※1)。
日本とは異なる自然環境のアメリカでも、ハリケーンやトルネード、山火事などの自然災害が毎年のように発生しています。
米国ではハリケーンやトルネード、山火事の被害も深刻
日本とアメリカの自然災害を比較すると、地震発生リスクはアメリカ全土で見るとそこまで高いものではないかもしれません。アメリカ西部、特にカリフォルニア州は大きな断層の上に位置しているためにアメリカの中でも地震が発生しやすい場所。一方、東部は、プレート同士がぶつかりあう「プレート境界」から遠く離れているため、地震が起こることは稀だと考えられています。
そのため、2011年に東部バージニア州で発生したマグニチュード5.8の地震は、人々に衝撃を与えました。
アメリカ地質調査所(USGS)によると、バージニア州で発生した地震は、この地域の小さな逆断層に溜まったひずみが解放された非常に珍しい例だということ。しかし、東部で地震が発生したのは実に100年ぶりであったことから、人々の間に不安が広がりました。
一方、ハリケーンの被害は、日本の台風同様、アメリカでも深刻です。
2017年にテキサス州に上陸したハリケーン・ハービーは、2005年にルイジアナ州に甚大な被害を与えたハリケーン・カトリーナに次ぐ社会経済被害をもたらしました。2017年は、ハービー以降も大型のハリケーンが次々とアメリカ南部に襲来。その結果、2017年のハリケーンによる犠牲者は251人にのぼり、全米有数の石油産業の集積地が暴風雨に見舞われたことからビジネスにも大きな影響が及びました。アメリカ海洋大気局(NOAA)によると、この年の自然災害による年間の被害総額のうち、なんと9割弱にあたる2650億ドルがハリケーンによるものだったということです(※2)。
さらに、日本ではあまり例が少ないアメリカの代表的な災害として、トルネードも挙げられます。近年では、2011年4月がアメリカ観測史上、最も多くの竜巻が発生した月とされており、オクラホマ州からノース・カロライナ州にかけて600を超える竜巻が発生しました。特に4月最終週には2日間で合計100以上の竜巻が発生。死者は数百人に及んだといいます(※3)。
そのほか、ここ数年で件数が増え、被害が深刻化しているのが山火事です。2020年8月末にカリフォルニアで発生した山火事は、現在までに1820平方キロメートルを焼き尽くし、今もなお(2020年10月現在)消火活動が続いています。今回の山火事は激しい落雷が原因で発生したと言われていますが、そもそもカリフォルニアで8月に落雷が発生することは珍しいことらしく、気候変動が自然災害の増加に影響を及ぼしているという見方も強まっています。
不動産投資を行う上で考えるべき「自然災害リスク」
こうした自然災害リスクは、物件を選ぶ際や、不動産投資を行う上でも考慮しておくべき重要な要素。日本とは異なる自然環境のアメリカで投資を行うのであれば、なおさらです。
災害規模が大きければ、当然、保有する不動産への被害も大きくなり、最悪、全壊や全焼となるケースも起こり得ます。こうした予期できない自然災害に対し、不動産投資家はどのような対策をとればいいのでしょうか。次回、後半で詳しく解説します。
(※1)一般社団法人環境金融健康機構“台風15号の被害額(保険損失額)、3400億円~7400億円規模に。米リスクモデル会社が推計。過去最高額になる可能性も(RIEF)”2019-09-17
http://rief-jp.org/ct2/93944
(※2)日本経済新聞“米の自然災害、被害額は過去最高の約35兆円
ハリケーンや山火事で 保険業界に打撃”2018-01-09
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25457690Z00C18A1FF1000/
(※3)NATIONAL GIOGRAPHIC“実録2011年の竜巻大発生”
https://natgeotv.jp/tv/lineup/prgmtop/index/prgm_cd/773
不動産も「有事の日本買い」、東京が世界トップに
東京に世界の投資家から視線が集まっている。不動産サービス大手のジョーンズラングラサール(JLL)の調べによると、2020年1~6月期の都市別の不動産直接投資総額ランキングで、ニューヨークやパリを抑えて東京が1位を獲得した。
2四半期を通じて東京が首位となったのはJLLの調査でも初めてだという。同社の河西利信社長は「コロナ禍の影響が世界各国に及ぶ中、安全資産としての日本の不動産が選好されている。為替市場で見られるような『有事の日本買い』が不動産でも起きている」と指摘する。
日本市場に資金を振り向ける海外投資ファンドの動きも目立っている。香港の大手投資ファンド「PAG」は4年ほどかけて最大約8400億円を日本の不動産に投じる計画だ。
不動産投資…金融機関から高く評価される「新富裕層」とは?
今、金融機関が評価するのは「新富裕層」という属性
不動産投資において、郊外中古RCの魅力はさまざまあるのですが、融資のハードルが高いという唯一ともいえる欠点があります。
金融機関にとって不動産への融資というのは、担保価値がある、高く金利が取れる、返済計画が見えやすい、グロスで貸しやすいという理由から人気ですが、融資先を選ぶ際に物件ではなく借り手の属性をより重視するようになっています。
では、金融機関から高く評価される個人属性を持つ〝新富裕層〟とは、どんな条件が当てはまるのでしょうか。
ここでいう新富裕層とは、もともと親から譲り受けた資産がある、あるいは地主であるなどではなく、「自分で高収入を稼ぐ力のある層」を指します。具体的には年収2000万円以上、純資産で5000万円以上です。
あえて「純」と付けたのは、例えば8000万円の自宅を所有しているといっても、住宅ローンで7000万円、現金で1000万円で総資産8000万円では条件に当てはまらないからです。

新富裕層は外資系のITもしくは金融業界に勤めているエリートビジネスマンが主に該当します。なぜ外資系かというと、日系企業よりも賃金が高いからです。正確にいうと、外資系が高所得というよりも、日本人の給料が先進国のなかでは相対的に低いといえます。最近では、東大生の官僚離れが進んでいるといわれています。公務員試験に受かっていても外資系コンサルティング会社に就職する人もいます。
東大卒といった地頭がいい人はもちろん、ITに長けた人、営業力のある人、金融で稼ぐ力のある人が、給料の高い外資系企業には多く勤めています。そうした人たちはお金に対するリテラシーも高く、投資に対してもロジカルに考えるという姿勢です。
不動産投資で成功した人に対して、レバレッジを利かせて一攫千金で億万長者になったというイメージを持つ人は多いでしょう。確かに書籍などを見ても、成功への強い意志があり、逆境を跳ね除けて頑張った人のストーリーがよく描かれています。
しかし、現実にはそうした人は少なく、コツコツ地道な努力を積み重ねてきた人が大きく花を咲かせているパターンのほうが多いのです。こうした人たちは、ゴージャスできらびやかなイメージとは異なり、いわば「新」富裕層と呼ぶにふさわしいタイプでしょう。
本業での「新富裕層」の方々とは、目先の所得税節税であったり、将来不安の解消などが目的ではなく、あくまで本業の給与所得でより高みを目指しながら、充実した資産形成のために安定した収益物件を長期保有する属性の人達です。
つまり「不動産を買って豊かになろう」と考えている人ではなく、「既に豊かさを享受しているなかで、さらにそれを強固にしていこう」と考えている人ということです。そのため「なにがなんでも不動産投資をして、人生を逆転させたい」という人はまずいません。そうした“心のゆとり”を持っているのも新富裕層の特徴だといえるでしょう。
というのも、不動産投資は表面利回りだけ見れば割のいい投資商品のように見えますが、修繕費や賃貸募集費、借入返済や税金などを差し引くと決して手残りが潤沢に残るケースばかりではありません。
不動産を使って目先のキャッシュを増やすというより、資産価値のある物件を長期保有して安定収益でローンを返済して、優良な資産形成をしていくことに本質的価値を見出しているのです。
金融機関が「新富裕層」に融資を出す、納得の理由
新富裕層は金融機関からの評価が高く、融資が受けやすいといえます。収益不動産とは、「収益が安定していて担保がある」という理由から金融機関にとっては「積極的に貸し出したい」商品です。だからこそスルガ銀行の不正融資問題が起こったともいえるでしょう。
スルガ銀行のケースは実体が伴っていなかったので社会問題まで発展しましたが、本来収益不動産は優れた融資対象の一つなのです。そして、融資するのであれば貸倒れリスクが少ない優良な個人・企業を選ぶというのも当たり前の論理でしょう。
ただし、いくら属性がよくても注意点があります。それは、「不動産投資で得たお金を生活資金に充てること」。これをすると、金融機関の印象はかなり悪くなります。生活に余裕がない人だと思われ融資の対象外となります。
新富裕層でそうした方は基本的にはいません。また、不動産の運営に関わる不測の支出に備えるといった意味でも、不動産投資で得たキャッシュの使い方には慎重になるべきです。
ここでお勧めしている投資は生活資金を稼ぐためではなく、あくまで本業で培った高収入を背景とした資産形成なので、毎月得たキャッシュフローは預金口座に入れておくものです。もしくは、金融機関から「定期預金、定期積み金にしてください」と言われることもあるかもしれませんが、これをすることで信用力につながり、お金の管理ができる人だという印象を与えられます。
不動産投資でキャッシュフローが出たら、高級なものを買って贅沢な生活をしたいと考える人もいるかもしれません。しかし本当に成功している人は、浪費などせず、地道に資産を築いています。そして、細かいテクニックに走るのではなく、長期収支、または収益不動産投資の本質的な部分を理解しています。
時代とともに移り行く「銀行評価」の内容
ここからは銀行評価について掘り下げていきます。今でこそ「収益還元評価」や「積算評価」という言葉も一般的になっていますが、こうした評価方法が根付いたのはわりと最近の話です。
新卒で金融機関に入社した私は、それこそ業務として「物件評価」を行っていました。やがて不動産業界に転職をしますが、時とともにその評価方法は形を変えていきます。だからこそ、私は今の時代の「評価基準」も今後変わっていくのではないかと予測しているのです。
【バブル期】取引事例比較法
バブル期に金融機関に勤めていた私が最初に教わったのは、取引事例比較法と呼ばれるものでした。当時、銀行でも一般的だった取引事例比較法とは、多数の不動産の取引事例をベースにして、対象となる不動産価格を求める手法です。
例えば、「査定しているAという土地」と「Aと条件が近い過去に取引されたBという土地」があるとしましょう。このとき、Aの路線価が坪60万円で、Bが路線価50万円で坪100万円で売買された事例がある場合、「60:X=50:100」という計算式でAの時価評価を算出することができます。
路線価とは、相続税の算出のために各道路につけられた価格のことで、「路線価50万円」のとき、その道路に接している土地の相続税算出のための資産としての価値は1㎡あたり50万円とみなされます。この計算式を解くためには、「内項の積=外項の積」になりますので、今回の場合だと外項の積が「6000」、内項の積が「50X」となり、この一次方程式を解くと「X=120」、つまりAの評価は120万円ということになります。
取引事例比較法は、おそらく公的・第三者的な評価で恣意性が配慮された路線価を用いており、計算もロジカルで説得力もあるということでバブル期に大いに使われていました。さらに当時は、金融機関がお金を貸したい時代であり、実際相場も上がっていたため、「時点修正」を加えました。
時点修正とは、例えば「1年前と比較すると現在の地価は20%上昇している。よって、物件売却時となる1年後の評価は1・2倍にする」というものです。
しかし、去年2割上昇したから今年も来年も同じように2割上がるかというと、もちろんそんなことはありません。つまり、時点修正とはある意味で〝まやかし〟のようなものであり、まさに「このまま不動産価格は上がり続ける」というバブル時代の産物ともいえるわけです。
当時は、「10億円の取引事例があるけど、この1年間で2割上がっているから、来年の今頃には放っておいても12億円になっているだろう。黙っていても2億円儲かるわけだから転売だけで事業になる」と考え、実際にビジネスをしていた人が多くいました。いわば〝買ったもん勝ち〟な時代であり、今考えると非常に恐ろしいことを疑いなくやっていたわけです。
さらに恐ろしいという意味では、路線価は土地の収益性や換金性を考慮しているわけではなく、相続税を算出するために存在しているので、本来なら収益性や賃貸需要がない土地であっても、机上価値として価格がついてしまうのです。
そのため、取引事例比較法においては「すべての土地には価値がある」ということになり、その考え方で融資を次々としていくと、収益性のない土地も含まれてしまうため、非常に大きなリスクが伴いました。
そうしたバブル時代の反省もあり、融資対象、投資対象となる不動産にとって大切なのは「収益性」となって収益還元法が生まれたのだと思います。その後、「一時的な収益ではなく、本質的価値を評価することが必要である」ということで積算法も取り入れて立体的に評価されるようになりました。
このように、不動産評価といっても30年のなかでこれだけ変化してきているわけです。評価の方法は時代のなかで変わっていくものなので、今後も変わる可能性は大いにあり得ます。
ここで強調しておきたいのは、「土地を見るときは普遍的価値の見方を確立しておくことが必要」ということです。銀行の評価が出るから、利回りが高いからというのは、本来的な意味での土地の評価ではありません。
普遍的価値といっても、難しいことではありません。例えば、前面道路がある程度の広さがある(道路付けがいい)とか、土地の形が整形地である、周辺環境が良好である、というのは重要な価値ですし、逆に、土地の形が歪んでいるとか、海抜が低い、地盤が緩い、などがマイナス要素といえます。
バブル期には数多くの不動産会社が消えていきました。都心で活躍していたバブル王のような投資家も、土地の値上がりを前提としており、売却益がないと潰れてしまうというスタイルだったので、土地神話の崩壊とともに消えていきました。
では、破たんしなかったのはどのような人・会社かというと、融資を受けずに現金で事業をしていた、もしくは調達コストが限りなくゼロだったケースです。例えば、森ビルは地権者と共同でビルを建てたことで土地の調達コストを削減したため、バブル崩壊後も勝ち残ることができました。逆に、借金をして買いすすめた不動産業者はどこも失敗しました。
そのように企業が潰れていった結果、不良債権が次々と出てくるようになりました。その処理のために、都市銀行は再編をせざるを得ない状況に陥りました。【ファンドバブル期】収益還元法
その10年後くらいにファンドバブルがやってきます。このときは、銀行が疲弊しており、金利が下がっていったにもかかわらず、不動産が売れないという状況が続いていました。そんななか、海外から見ると非常に割安で投資効率がいいと判断されたため、ゴールドマンサックスやリーマンブラザーズなどさまざまな外資系のファンドが20世紀の終わりから21世紀にかけて、日本の不動産を買い漁っていったのです。
そうして、外資が買うことで日本の新興デベロッパーも刺激されるかたちで活気づきました。ファンドバブル期は新興デベロッパーの活躍期だったともいえるでしょう。当時は、期待利回りと換金性を重視して投資をしていました。バブル期のように値上がり益ではなく、投資に対するランニングのリターン(賃料収入)に価値を置いていたのです。
簡単にいえば、「この物件は、年間で1000万円の賃料収入があり、期待する利回りは10%。だから1000万円÷0・1=1億円、つまり1億円の価値」というのが収益還元法です。
では、なぜこのファンドバブルは崩壊したのか。私は「換金のタイミングが決められていたから」だと思っています。
例えば、5年間、ファンドでまわしたうえで、投下資金を戻すとして、5年後の出口の時点で相場が上がっていればいいですが、相場が下がっていると損します。出口の期日が決められている限り、そのときの相場に左右されます。
当然、土地の価格は上がり下がりするものなので、売るタイミングでどうなっているかは誰にも分かりません。出口のタイミングが決まっているというのは、いいときは問題ないのですが、悪いときは破たんします。これがファンドバブルの崩壊だったと思います。
もう一つ理由として挙げるとするならば、不動産の期待利回り(賃料と入居率)が実態とは乖離していた、つまり机上の空論になっていた可能性は十分にあります。ファンドバブル時代は、前述したようにバブル期の取引事例比較法の失敗を受けて「収益還元なら失敗しない」という理屈が受け入れられていました。
そもそも期待どおりに賃料が入ってこなかったり、想定以上にさまざまなコストがかかったり……リスクをよく考えずに買ってしまったツケがあとになって肥大化していったのです。
【現在】積算法
最近のスタンダードは、収益還元だけではなく積算法もしくは再調達原価法といいますが、相続税評価の土地の評価と、建物は再調達価格(もう一度今建てるとしたらいくらくらいかかるか)で算出する評価も、銀行評価として使われています。
土地積算は敷地面積×路線価、建物は延べ床面積×再調達価格×残存年数/耐用年数となります。今まで見てきた評価のなかで、一番担保価値としての意味合いが強くなります。また、積算が出る物件として、「面積が大きい物件」「築年数が新しい物件」になりやすいという傾向があります。郊外型RC物件は広い土地にゆとりのある間取りで建設されていることが多く、積算評価が伸びやすいという特徴もあります。
こうした30年程度のサイクルを見ても、評価の基準が時代とともに変わっていくことが分かります。
そして今後、また基準がより普遍的価値に近づいていく可能性は大いにあり得ます。ですから繰り返しになりますが、今物件を買える立場にある属性の人たちは、「収益性が高いから」「積算が出るから」といった理由ではなく、地形や道路付け、環境、インフラなど「実」の部分を重視すべきです。
ただ、中古物件には注意しなくてはいけないポイントがあります。中古だと、現在は収益が上がっていても、法的な規制がかかったり、トレンドが変わったりして価値が下がり、最悪な場合は価値がゼロになるリスクがあります。
例えば、旗竿の土地は〝今〟はいいとされていますが、法的な網をくぐり抜けて建てているようなものは普遍的価値があるとはいえません。ほかにも、崖地に無理やり建てている物件なども危険でしょう。利用の方法や、収益性で見たときの費用対効果が変わったときに土地としての資産性、価値がなくなってしまいます。
ですから、旗竿地や崖地などの変化球には手を出さずに、普遍的価値の見方や現在の評価方法のトレンドや問題点を知っておくことが求められているのです。
杉山 浩一
株式会社プラン・ドゥ 代表取締役
宅地建物取引士
マンション管理士
不動産投資と株式投資のメリット・デメリットを比較、注意点も
ミドルリスク・ミドルリターンで運用する不動産投資は長期運用に向いており、融資を活用して大きな金額を投資することが可能ですが、流動性が低く現金化がしにくいデメリットがあります。
一方、株式投資は株価変動のスパンが短く変動幅も大きいために、不動産投資と比べるとハイリスク・ハイリターンになる傾向があります。短期的に大きな利益を狙えるものの、相応のリスクを伴います。
このように両者の投資にはメリット・デメリットがあり、不動産投資と株式投資のどちらを選ぶかで迷っている方は、それぞれの特徴をしっかりと把握することが大切です。この記事では、不動産投資と株式投資の内容とメリット・デメリットについて詳しく解説するので、投資選びの参考にしてみてください。
1.不動産投資とは
個人が行う不動産投資とは、マンションやアパートなどの不動産を取得または活用して収益を得る投資方法のことをいいます。不動産投資で収益を得るには、主に「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2つがあります。
インカムゲインとは、資産を保有している間に得られる収益のことです。賃貸経営における不動産投資のインカムゲインは、不動産を第3者に賃貸して家賃収入を得ることを指します。
例えば、家賃6万円の10部屋ある1棟アパートを活用して不動産投資を行なう場合、全部屋を他の人に貸し出すことができれば、月60万円の家賃収入(インカムゲイン)を得られます。
一方、キャピタルゲインとは、資産の値動きを狙って売却したときに得られる収益のことです。不動産投資では、購入した不動産の所有権を売却することで、キャピタルゲインを得られます。
例えば、投資用不動産を3000万円で購入した後、不動産の価額が3500万円まで値上がりすれば、売却時に500万円の売却益(キャピタルゲイン)を得ることができます。
なお、不動産投資を行なうための物件の種類は、区分マンションや1棟物件(アパート・マンション)、戸建、オフィスなど幅広く、選ぶ物件タイプやエリアによって収益性やリスクが大きく異なります。
2.株式投資とは
株式投資とは、購入した企業の株式から収益を得る投資方法のことです。
株式を発行した企業は投資家から得られた資金で事業活動を行ない、そこから得られた収益の一部を投資家に還元する仕組みになっています。株式の投資家は企業から貰える配当金によって収益を得られます。
また、株式を発行している企業の事業拡大や将来性への期待感、決算の業績評価によって株価が変動します。株式を購入した後、その株価が上昇した後に売却して収益を得ることが可能です。
なお、株式の取引方法の種類には、主に「現物取引」と「信用取引」があります。
現物取引とは、時価で計算した売買代金を支払った上で株式取引を行なうことをいいます。取引の際に対象株式の時価相当の売買代金を支払わなければならないため、保有している資金の範囲内でのみ株式の購入が可能です。
一方、信用取引とは現金や株式を担保にして、所有している資金以上の株式取引を行なうことをいいます。信用という形で株式取引を行なうため、自己資金以上の金額で株式を購入したり、売却したりすることが可能です。
信用取引には、「信用買い」と「信用売り」の2種類があります。信用買いとは、一定の資金を担保として証券会社に預けた上で、自己資金以上の金額の株式を購入することで、信用売りとは、一定の資金を担保として証券会社に預けた上で株式を借りて、それを売却することをいいます(=空売り)。
信用取引は、自己資金以上の金額で株式取引ができるため、利益が大きい反面、損失も大きくなるのが特徴です。
株式投資を行なう期間は、「短期」「長期」の2つに大きく分けられます。短期の株式投資は株式を購入してから1日以内に売却する取引はデイトレード、数週間から1カ月以内に売却する取引はスイングトレードとも呼ばれ、短期的な売買により売却益を狙うのが特徴です。
長期の株式投資では、運用期間が数年単位になり、企業の成長性などを考慮しながら、長期的な株価の値上がりや、配当金が期待できる銘柄を選択するのが特徴です。
長期間株式を保有すると、配当金も積み重なっていきます。長期の株式投資では、売却益と配当収益の双方を狙って運用を行なっていきます。
3.不動産投資のメリット・デメリット
不動産投資には、「収益を見込みやすい」「ローンが利用できる」「物件管理の手間は少なくできる」「インフレや老後対策になる」などのメリットがあります。
3-1.不動産投資のメリット
不動産投資のメリットとして下記の4点を取り上げています。
- 定期的な収益を見込みやすい
- ローンを活用して投資を始められる
- 価格の動きがゆっくりで、不動産管理業務も委託できる
- インフレ対策になる
それぞれ詳しく見て行きましょう
定期的な収益を見込みやすい
マンション一室や1棟アパートなどの投資不動産を他の人に賃貸し、家賃収入を得るのが不動産投資の主な収益源です。投資不動産に入居する人がいる場合、定期的に家賃収入を得られます。そのため、他の投資と比較して収益を見込みやすく、収支計画を立てやすいのが特徴です。
特に高い入居率実績のある不動産投資会社の例としては、東証1部上場企業で都心中心のマンション投資を手掛ける「プロパティエージェント」があります。プロパティエージェントでは新築・中古マンションのどちらにも投資可能で、入居率99.70%(2020年9月時点)の実績があります。
新築マンション投資では、土地選定から建物の企画開発までをワンストップで手がけることで品質を担保したマンション供給を実現しており、上場企業ならではの資本力や交渉力も魅力です。
一方、中古マンション投資では資産性・収益性・移動率の3軸から定量的に評価するスコアリングを用いて、将来にわたって高い資産性を維持できる物件のみを厳選し仕入れています。また、建物管理事業を備えているため、中古マンション投資のリスクの一つである購入後のコストについても、当該物件の将来にわたり物件の資産性を維持するための必要なコストを見通すことが可能です。
不動産投資においては立地や将来の資産性が非常に重要ですので、このような不動産投資会社をうまく活用して情報収集や検討を進めてみると良いでしょう。
ローンを活用して投資を始められる
投資目的で不動産を購入する際、銀行や信用金庫等の不動産投資ローンを活用できます。
金融機関の融資審査では対象物件の築年数やエリア、収益性などのスペックに加えて、融資を受ける方の年収や年齢、勤続年数、借り入れ状況などの属性が評価され、融資の年数や上限額がそれぞれ設定されます。
金融機関の評価が得やすい物件のスペック・借り入れをする方の属性であれば、少ない元手資金で大きな運用が狙え、レバレッジ効果により大きな収入を狙える可能性があるのが特徴です。
【関連記事】不動産投資ローンを組むメリット・デメリットは?金利を下げるコツも
価格の動きがゆっくりで、不動産管理業務も委託できる
不動産の価格変動は基本的には年単位となります。株式投資のように毎日価格が変動しないため、本業に専念できるメリットや自分のタイミングでゆっくりと売却の判断ができるメリットがあります。
不動産投資をする場合、定期的に投資不動産の維持管理やメンテナンス、家賃の受領や回収などの作業もする必要があります。
しかし、これらの管理業務は管理会社などに任せることが可能です。忙しくてあまり時間がない人でも、賃貸経営業を続けていくことが検討できます。
インフレ対策になる
資産運用を行なう際、インフレリスク(物価上昇リスク)への考慮も大切です。不動産投資ではインフレにより物価が上がればそれに合わせて不動産の価格も上がるため、資産運用を行いながらインフレ対策できるのもメリットの1つです。
3-2.不動産投資のデメリット
不動産投資のデメリットとして下記の4点を取り上げています。
- 多額の資金が必要
- 不動産を購入・売却するのに時間がかかる
- 短期間で大きな利益を出すのは難しい
- 災害リスクがある
それぞれ詳しく見て行きましょう
多額の資金が必要
不動産投資は、比較的価格の安い中古マンションでも1000万円~2000万円程度の資金を用意する必要があります。融資審査を通過すればローンを借りることはできますが、物件により1割~3割程度の頭金が求められることや、借りた後もきちんと返済をしていくことが必要となります。
不動産を購入・売却するのに時間がかかる
不動産投資は、他の投資と比較して投資対象資産の流動性が低いのがデメリットです。投資目的で不動産を購入する場合、物件の調査、売買価格の交渉、契約、残金決済という流れで手続きを行なうのが通常です。また、不動産を購入するためのローンを利用する場合、その審査にも時間がかかります。そのため、投資不動産を購入できるまで、数カ月単位の期間を要するケースもあります。
一方、投資不動産を売却する場合も仲介業者に買い手を探してもらった上で、売買価格の交渉、契約、残金決済という流れで手続きを行ないます。不動産を購入するときと同様、売却するまである程度の時間がかかります。
短期間で大きな利益を出すのは難しい
不動産投資は、インカムゲインである家賃収入をメインとする運用が中心なので、定期的な収益を見込みやすいですが、得られる利益は限られます。
また、少子高齢化や低成長が続く国内不動産市場において、不動産の価値が数年後に何倍もの価格になる可能性は低いと言えます。そのようなことから、不動産投資では短期間で大きな利益を出すのは難しいというデメリットがあります。また、現金化するまでに3ヶ月~半年程度の時間がかかる点にも注意が必要です。
災害リスクがある
不動産投資は、地震や洪水などが起こった場合に不動産価格が下落するリスクや長期間の空室が出るリスクなどがあります。購入前に少しでもリスクを軽減できるよう、地盤調査やハザードマップの確認をすることが大切です。
4.株式投資のメリット・デメリット
株式投資には、不動産投資とは異なるメリットやデメリットが存在します。具体的にどのようなメリットやデメリットがあるのか見ていきましょう。
4-1.株式投資のメリット
株式投資のメリットとして下記の3点を取り上げています。
- 短期間でも大きな利益を狙える
- 分散投資をしやすい
- 株主優待制度がある
それぞれ詳しく見て行きましょう
短期間でも大きな利益を狙える
株式の売買は、開設した証券会社の口座に入金すれば始められるため、短期間で取引を行えます。そのため、不動産と比較して流動性が高く、現金化しやすいのが特徴です。
また、経済状況が大きく変化した場合、株価が倍以上になるケースもあり、大きなリターンを狙えるメリットがあります。
分散投資をしやすい
複数の資産に分散して運用しやすいのも株式投資のメリットです。不動産投資のように、ある1つの資産に集中して投資した場合、その投資先に問題が生じれば、全体の運用結果に大きな影響を及ぼします。
しかし、複数の資産に分散しておけば、その中の1つの資産に問題が生じても、リスクを最小限に抑えられます。小口での購入ができ、数多くの銘柄の中から投資対象を複数選べる株式投資は分散投資を実践しやすい資産運用です。
株主優待制度がある
株式を保有している場合、運用益のほかに株主優待を受けられることもあります。
株主優待とは、株主に対して企業の商品やサービスに関する特典をプレゼントするなどの特典であり、株主はこの優待制度によって飲食品、日用品、各種割引券や金券などを貰えることがあります。
4-2.株式投資のデメリット
株式投資のデメリットとして下記の2点を取り上げています。
- ボラティリティ(値動きの幅)が大きい
- 信用取引におけるレバレッジのリスクが高い
それぞれ詳しく見て行きましょう
ボラティリティ(値動きの幅)が大きい
株式投資をする際、大きな利益を得ることができる反面、損失の幅も増えるため、投資リスクが高いというデメリットがあります。
投資先の株式を発行する企業の事業が失敗したり、経済環境によって株価が急落したりするケースは珍しくありません。さらには、投資先の株式を発行する企業が倒産すれば、その株価はゼロになります。最悪の場合、投資した資金をすべて失う可能性もあります。
信用取引におけるレバレッジのリスクが高い
不動産投資では金融機関の融資によって、少ない自己資金でも物件購入ができるメリットがあります。株式投資でも信用取引によるレバレッジを活用することで、少ない元金でもより多くの資産を運用することが可能です。
しかし、株式は前述したようにボラティリティが大きく、大きなレバレッジをかけてしまうとロスカット(証拠金不足による強制的な決済)となる可能性を高めることになります。
不動産投資では自己資金の5~10倍の資金の融資を受けられることも少なくありません。レバレッジを効果的に活用できない点も、株式投資のデメリットと言えるでしょう。
【関連記事】株式の信用取引とは?仕組みやメリット・デメリット、注意点も
5.不動産投資と株式投資、選ぶ際のポイント
ここまで不動産投資と株式投資のメリット・デメリットについて解説しました。二つのどちらに投資をするかを選ぶポイントの一つとして、「価格変動リスク」について注目してみましょう。
株式は日々価格が大きく変動しており、経済ニュースやチャートをこまめに確認することが重要になります。不動産の価格も経済的な影響を受けますが、実際の売買スピードは株式と比べて遅く、価格が短期間で急落してしまうようなケースは比較的少ないと言えます。
ただし、不動産投資では該当エリアにおける実際の賃貸需要が物件の収益性・物件価格に大きな影響を与えています。急に需要が大きく減少してしまうことは稀ですが、過去の人口推移のデータや地価推移などを参考に、将来の予測を立てておくことは重要です。
また、「不動産か株式かどちらかだけに資金を集中する」という手段だけでなく、バランスよく分散投資をすることもリスク低減につながります。不動産投資で得たキャッシュフローを株式に再投資するなど、二つを組み合わせたポートフォリオも検討してみましょう。
6.まとめ
不動産投資と株式投資にはそれぞれメリット・デメリットがあります。どちらの資産運用が適しているかは人によって異なるため、自分に合った投資方法を選ぶことが大切です。
資産運用に関する一定の知識があると不動産投資や株式投資における突然のトラブル対応やリスク対策につながります。それぞれの投資手段について、情報収集をしながら比較検討してみてください。
コロナ給付金による投資バブルはそろそろ終焉へ
まず、私の物件での新型コロナウイルス蔓延下の状況を報告します。私の所有物件は金額ベースでJR山手線北部に8割、地方・郊外に2割という配分になっています。
このうち、JR山手線物件について、はじめにお話ししてみます。この地域では26世帯を保有しており、1K・1DK・1LDK等から3LDKまで幅広いタイプの物件に分散させています。
物件種類もRC・重量鉄骨造の一棟マンションや2世帯住宅、新築した一戸建てなど多様性を持たせています。リスクヘッジのためです。
■ コロナの影響による人の入れ替わりについて
コロナが段々と蔓延してきた今年の2月3月、私の物件では何も変化がなく驚きました。普段の繁忙期ならば5~10戸程度は入れ替わりがあるのですが、今年は全然それがなかったのです。
店舗の休業や学校の閉鎖等が報じられたので、解約が何組か出るのかなと思っていたのですが、実際には0件でした。お部屋探しの人も解約希望の人も様子を見ていたのだと思います。
それが8月の猛暑を過ぎ、コロナが落ち着いた頃合いに至ると、解約通知が入るようになりました。多かったのはターミナル駅徒歩圏に位置するシングルタイプの物件です。4件の通知があり、私が運営に関わっている他名義物件でも2件ありました。
解約理由は、「 出費を切り詰める為に、親族やパートナーと同居する事にした 」「 大学や仕事が休業になり、ターミナル駅徒歩圏に住む必要性が薄れた 」など。
このうち「 同居 」が解約理由の場合に関しての転出先は、足立区や小金井市、国分寺市など、多少都心エリアから距離がある割に利便性があり、生活上の買い物に不自由しないエリアでした。
これらの転出先では2DKでも9万円くらいですので、2人で同居すれば45,000円程度の負担で済みます。副都心のワンルームマンションを7万~8万円台で借りるより節約できる上、広さも確保できるわけです。今後の経済落ち込みに備えて、生活防衛を考える人が増加しつつあるのだなと感じました。
退去は発生しましたが、JR山手線沿線の物件は、今でもやはり早めに賃貸成約に結びついています。1~2週間で契約に至る感じです。しかしこれは現時点での話ですので、コロナの蔓延状況次第ではまた状況に変化が生じると思います。
コロナが今後ダラダラ続いたとしても、人間はどこかに住まざるを得ません。オンラインだけで全て完結するわけはなく、整備されたインフラ面から考えると、利便性が高いエリアはいずれ活気を取り戻すのでしょう。
しかし、それまでに紆余曲折があるかもしれません。不測の事態に備えて私は現金ポジションを厚めに保つ事でコロナ禍と価値観の変容という荒波を超えていこうと考えています。
また、所有している郊外・地方物件に関してですが、何の変化もありませんでした。全般的にはむしろ引っ越し費用を節約する為か、今まで以上に解約通知が少ないと地元賃貸業者も語っている状況です。
私がアパートを所有している千葉外房エリアではコロナで人の動きが多少変わったようで、一戸建て物件の売買成約が増加傾向にあると親しくしている地元業者が言っていました。
劇的という程ではないものの、着実に移住者や別荘所有者が以前より増えてきたとのこと。広大な敷地でヤギを飼い農作業をして、オンラインで東京の仕事もするという人もいるそうです。
今後、価値観の多様化につれて様々な不動産需要の変化が進んでいきそうです。
■ 「 給付金を元手に勝負 」の時期はそろそろ限界に
世界経済については、4月11日掲載のコラムに書いた「 6月~8月の株式市場は回復局面とも言うべきサマーラリーが期待出来るでしょう 」の状況になりましたが、私は9月~10月に関して株価調整の月だと予測しています。
今まで、米国や日本では「 コロナ給付金 」としてそれなりの金額を国民に支給してきました。特に日本ではいわゆる「 コロナ融資 」がどんどん実行されています。
結果として、米国ではロビンフッド口座を開設して新規参入の個人投資家が貰った給付金でAmazon株などを買い上がり、ハイテク株急回復の主因になりました。
日本でもコロナ融資や給付金での残余分を株式投資や投資用中古戸建て等に配分する動きがあり、相場底堅さの一因になったと思います。
しかし、米国では例えばスタンリー・ドラッケンミラーのようなベテラン投資家が段々とハイテク株の買いポジションを減らしつつあり、9月調整を予測していた彼らの読みが当たった格好になってきています。
今までの株高の主因である「 給付金を元手に勝負 」という個人投資家達が手元の給付金のかなりの部分を投資してそれが限界にきている以上、もう少し株価の調整は進むと思われます。
しかし、11月12月はまた回復局面が訪れると予測しています。コロナ対策での資金供給は総量としてかなりの金額に上り、それが結局は株価を押し上げるでしょうし、追加で給付金などの対策を更に進める可能性も高いからです。
米国FRBが直接株式ETF買いを進める事を薦める声もあり、まだ米国の場合打てる手が幾つか残されている事でしょう。その点からも、暴落した場合は買いのチャンスと考えられます。
■ 株式投資も不動産投資も様子見
株価に関しては短期的( 今年秋~初冬 )に調整下落→中期( 年末~来年夏 )では上昇→長期( 1年~2年後 )では下落→超長期( 10年単位 )では上昇という大局観を持っています。
長期で下落というのは、コロナを契機とした需要不足は結局マネーの総量を増加させても対処には不十分になると思われるからです。
しかし、地球規模で見れば人口の増加はまだまだ続きます。超長期という視点での株式投資は、コロナ禍を乗り越えて素晴らしい実りをもたらしてくれるものと思います。
去年、私はリスクオフを進めていたので、保有物件の総量が随分減少しました。一時期は売却予定物件迄含めると100戸近く保有していたので、およそ半減させた感じです。
しかし、コロナの蔓延もあり、現在は株式投資も不動産投資も再び急拡大させる気持ちはありません。しかし、本間宗久の言う「 野も山も一面皆弱気ならば 」という局面が来れば、また敢然と拡大していくのだろうとも考えています。
今まで私が資産拡大した局面は、同時多発テロ以降の不景気時やリーマンショック後、東日本大震災後など買い手が少ない時に限定されます。またいずれ買い場がやってくるのでしょう。
今は満室稼働を維持しながら、どのように時代が変化していくのか、これをゆっくりと観察しつつ、また改めて好機を探っていきたいと考えています。
新築アパート経営、失敗の理由は?5つの事例とリスク対策を解説
不動産投資は金融機関の融資が活用でき、少ない自己資金でも大きな収益を得られる可能性がある反面、投資金が回収できずに元本割れしてしまうリスクがある投資手段となります。
そのため、過去の失敗事例を参考にし、その理由を知っておくことでリスクヘッジを図り、事前に準備をしておくことは重要なポイントと言えます。
そこでこの記事では、不動産オーナーが新築アパート経営に失敗した5の事例を紹介します。その上で失敗しないための対策について解説するので、新築アパート経営を検討している人はぜひ確認してみてください。
1.利回りだけでアパートを選んでしまった
1つ目の失敗例は、利回りだけでアパートを選んでしまったことです。以下より、失敗した理由と対策について解説します。
1-1.利回りだけでアパートを選び失敗した理由
アパート経営において、収益を端的に表す「利回り」は重要な指標と言えます。しかし、高利回り物件は、建築費を低く見積もり実際の入居者のニーズを満たしていない場合や、賃貸需要が減少傾向にあるエリアであるなど、運営の難易度が高い傾向があります。
また、新築アパートを建築するとき、不動産会社から提示される利回りが明らかに相場より高いことがあります。何かの理由で利回りが高くなることはあるものの、家賃設定を相場より高く見積もっているケースもあり、注意したいポイントと言えます。
相場よりも高い家賃設定をしていた場合、想定した家賃では賃借人を付けられずに家賃を下げることになります。利回りだけで判断せず、「なぜ高利回りのなのか?」「想定家賃収入は現実的な数値か?」という疑問を抱くことが重要と言えます。
1-2.対策:利回りだけでなく長期のキャッシュフローを考える
この失敗事例への対策は、利回りだけでなく長期のキャッシュフローを考えることです。具体的には10年~20年スパンで発生する、以下の支出を年ごとに読み込んでおきます。
- 外観の修繕費用
- 内装の修繕費用
- 設備入れ替え費用
- ローン返済額
- 管理委託手数料
- 保険料
- 税金
上記に加えて、該当エリアの人口推移や家賃相場の推移を参考に、家賃下落率や空室率も加味したシミュレーションをしておきましょう。上記を自分だけで算出するのは難しいため、不動産会社にヒアリングしながら作成していくと良いでしょう。
【関連記事】アパート経営に強い不動産投資会社一覧
2.立地条件の悪いアパートを選んでしまった
2つ目の失敗例は、立地の悪いアパートを選んでしまったことです。以下より、失敗した理由と対策について解説します。
2-1.立地条件の悪いアパートを選び失敗した理由
立地条件の悪いアパートは地価が安く、アパートの取得費用が安価になり、購入のハードルが低いメリットがあります。もしくは駅からの距離や周辺環境は良好なものの、賃貸需要が減少している立地では安価に売り出される場合が多いでしょう。
立地条件の悪いアパートは価格が安く高利回りになる反面、空室リスクや家賃下落リスクは高く、リスクとリターンのバランスを見誤まると収益を上げられないアパートを購入してしまう失敗につながります。
2-2.対策:周辺物件のリサーチを徹底する
立地の悪いアパートを選び、失敗してしまうことへの対策は、周辺物件のリサーチを徹底することです。上述したように、立地条件が悪いと賃借人が集まりにくい可能性が高い物件と言えます。
そのため、周辺の競合物件のリサーチを徹底し、空室率と家賃下落率を精査しましょう。具体的には、「周辺で同じような物件の家賃はどのくらいか?」「空室募集はしているか?」「過去の募集事例から空室率は高そうか?」などのポイントです。
また、これらのポイントを自身で判断することが難しい場合は、エリア選定や収益率に厳しい条件を設けている不動産会社に相談することも有効な手段です。
3.税金対策をメインにアパートを選んでしまった
3つ目の失敗例は、税金対策をメインにアパートを選んでしまったことです。以下より、失敗した理由と対策について解説します。
3-1.税金対策をメインにアパートを選び失敗した理由
アパート経営に限らず、不動産投資は減価償却費用を計上できるため、税金対策をして不動産投資を検討している方も少なくありません。
減価償却費用とは、建物を取得した費用を経費として計上できる費用です。確定申告で減価償却費を経費計上すると、結果的に所得税や住民税を減額できることがあります。
これらの税制メリットを不動産投資の収益の一部として勘案する方も少なくありませんが、減価償却費用の計上期間は不動産の耐用年数や築年数によって決まり、上限が設けられています。
どの物件も最終的には耐用年数が切れることで減価償却費用を計上できなくなるうえ、売却時には計上した減価償却費は譲渡所得に加算されるなどのデメリットがあります。
不動産投資の税制メリットを収益の一部として見込んで投資判断をしてしまうと、これらの税制メリットが受けられなくなった時や、物件の収益性が悪化した時に税制メリットを超えて収支がマイナスになってしまう可能性が高まることになります。
3-2.対策:あくまで月々のキャッシュフローをメインに考える
アパート経営をはじめとした不動産投資では、税制メリットを勘案せず、長期的に月々のキャッシュフローがプラスになるかどうかを見極めることが大切です。
金融機関の融資を利用する場合、空室率の悪化した物件では家賃収入が月々の返済金に届かず、賃貸経営の存続が困難になるケースもあります。経費や月々の返済額を加味したアパートの収益性をしっかりとシミュレーションし、慎重に検討するようにしましょう。
4.自身の返済能力に対して多額のローンを組んでしまった
4つ目の失敗例は、自身の返済能力に対して多額のローンを組んでしまったことです。以下より、失敗した理由と対策について解説します。
4-1.返済能力に対して多額のローンを組んで失敗した理由
新築アパート経営をするときは、建築費用や土地取得費用を支払うために不動産投資ローンを組むケースが多いでしょう。この時、自身の返済能力に対して借入額を大きくしてしまうと、建物の修繕や入居率の悪化など突発的なトラブルに対応できず、返済が滞ってしまう可能性があります。
空室になった場合は家賃収入が減少しますが、ローンの返済や維持経費は発生しています。このような時には手持ち資金からの捻出が必要になることもあるため、不動産収入以外の自身の収入に合ったローンを組むことは重要なポイントとなります。
4-2.年収や月々の貯蓄額を考慮してローンを組む
返済能力に対して多額のローンを組んで失敗しないための対策は、金融機関からの融資を与信の上限まで利用せず、自身の将来的な年収や月々の貯蓄額を考慮してローンを組むことです。
金融機関から借りられる金額は「返済できる金額」とイコールではなく、不動産を担保にした総合的な評価によって融資額や条件が設定されています。家賃収入によって返済できる、と安易に考えず、突発的なトラブルに対応できるか、家賃収入が減少しても補填できるかどうか慎重に検討してみましょう。
また、アパート経営で得られた家賃収入は消費して使ってしまうのではなく、将来的なトラブル対応や家賃収入の減少に備えて貯蓄しておくことも有効な対策となります。
【関連記事】1億円、本当に返せるの?アパートローンの仕組みと返済イメージをわかりやすく解説
5.サブリースの仕組みをよく分かっていなかった
5つ目の失敗例は、サブリースの仕組みをよく分かっていないことです。ここでいうサブリースとは、空室時も家賃保証してくれるタイプのサブリースを指しています。
サブリース契約を結ぶと、サブリース会社がアパートを一括で借り上げてくれるため、たとえ空室になってもサブリース会社から家賃をもらうことができます。
ただし、最終的にオーナーへ支払われるのは満室想定の家賃から20~30%ほどが差し引かれた金額となります。この差額によって、空室時も家賃を保証してもらうイメージです。
サブリース契約でよく見られる誤った認識のケースとして、「家賃は長期間保証される」と考え安易に契約をしてしまうことがあります。しかし、サブリース契約では「業者側が自由に保証家賃を設定できる」「自由に契約を打ち切ることが出来る」などの条件で締結されているケースが多く、必ずしも収益が補償される契約ではないことに注意が必要です。
対策としては、まずはしっかりとサブリース契約の契約内容を確認し、想定されるリスクについて把握しておくことが重要です。サブリース契約での家賃保証は将来的に収益を保証するものではなく、限定的な契約であることに注意しておきましょう。
まとめ
新築アパート経営を検討している人は、上記の失敗例と対策を参考にしてみましょう。過去の失敗事例を知っておくことで、失敗のリスクを回避し、アパートを選ぶときに長期に渡り収益を生み出せる物件を選定できる可能性が高まります。
不動産投資は長期的に収益を生み出せる投資手法ですが、物件を選ぶ時点で将来的な収益に大きな差が生まれることになります。良質な物件を取得するために、この記事をご参考頂ければ幸いです。
世田谷区、空き家5万戸以上…東京で不動産投資はダメなのか?
不動産投資…都心か、それとも郊外か?
不動産投資において、ロケーションが重要であることは誰もが知るところ。人気エリアで駅から近い物件を選ぶことが成功の第一歩だといわれてきました。そのなかでも東京は、今後も人口増加が見込めるという予測であったり、1年延期になりましたが、東京五輪というビッグイベントを控え、不動産マーケットが好調に推移していたり、渋谷や品川など、大規模な再開発を控えていたりと、さまざまなプラス要因から、注目されてきました。
しかしひと口に東京といってもさまざまな地域があり、大きく都心と郊外と分けられることが多いでしょう。
ただその分け方もさまざまで、よく見られるのは下記の3つの分け方です。
1.都心3区といわれる千代田区、中央区、港区を都心として、それ以外を郊外とする
2.山手線内を都心として、それ以外を郊外とする
3.23区内を都心として、市部を郊外とする
そもそも「都心」とは、「大都会の中心部」のこと。「郊外」とは「都市に隣接した地域」のことを指し、明確な境界線があるわけではありません。1の分け方をして「新宿や渋谷は郊外」といわれてもピンとはきませんし、2の分け方で「北千住や自由が丘は郊外」といわれても納得できる人はいないでしょう。3の分け方で「立川や町田は郊外」といわれると、距離的に納得する人も多くなってくるでしょうが、人気の街ランキングの常連で、23区と接する「吉祥寺」を郊外とするのは、賛否両論、ありそうです。
また距離と時間に注目し、
4.東京駅から25キロ圏内、急行等速達列車で30分圏内を都心とする
などという分け方もみられますが、やはりそこでも隣接する地域を郊外とするか、どうかの論争は続きます。結局「都心」か「郊外」かは、何かを論ずる際の定義づけでしかないことは覚えておいたほうがよさそうです。
2.山手線内を都心として、それ以外を郊外とする
3.23区内を都心として、市部を郊外とする
東京で不動産投資…今後、気を付けるべきエリアは?
東京の不動産投資でよくいわれるのが、「都心はローリスクローリターン」「郊外はハイリスクハイリターン」ということです。都心はどうしても地価が高くなるため、利回りは低くなります。その分、高い賃貸ニーズから空室は発生しにくく、仮に売却する際も高値で売れる可能性がある、つまり賃貸経営においてリスクは低いといえます。
一方で郊外は地価が安いので、都心と比較した際には利回りは高くなります。しかし賃貸ニーズは都心ほど高くなく、空室も発生しやすいといえます。売却の際も高値では売れにくく、賃貸経営においてリスクは高いといえます。
そのようななか、高度成長期以降、郊外へと移転した大学の都心回帰という話題から「郊外の不動産への投資はやめるべき」という論者もいれば、昨今のコロナ禍ではテレワークが浸透し郊外の物件の人気が高まっていることから「これからは郊外の時代」と声高らかに訴える論者もいます。
また最近では、世田谷区の空き家や5万戸以上もあるというニュースも大きく報道されました。
地域経済分析システムで、投資対象となる賃貸物件の分布をみていくと、建物数*は環状7号線を中心に広く分布していますが、区部の西側のほうが多く分布しているのがわかります。また郊外へと向かうと、鉄道路線沿線の主要駅近くに集中し、賃貸物件の少ないエリアが目立つようになります(図表1)。
*500m四方で色分け。~80件青系色、~120件緑、~160件黄緑、~320件黄、~400件薄橙、~600件濃橙、600件~赤
賃貸物件を住居数*でみてみると、同じく、環状7号線を中心に集積していますが、区部の東西の差は気にならない程度に広く分布していることがわかります。また建物数と同様に、郊外では鉄道路線の主要駅近くに限定して集積していることがわかります(図表2)。
*500m四方で色分け。~80件青系色、~120件緑、~160件黄緑、~320件黄、~400件薄橙、~600件濃橙、600件~赤
続いて、賃貸物件の空き家*の状況をみていくと、環状7号線を中心に広く空き家は分布し、郊外では鉄道路線沿線の主要駅近くに集中しています(図表3)。
*500m四方で色分け。~15件青系色、~20件緑、~25件黄緑、~30件黄、~35件薄橙、~40件濃橙、40件~赤
このようにみていくと、分布の濃淡はあるものの、賃貸物件が多いエリアでは空き家も目立つといえます。今回、空き家問題でセンセーショナルに取り上げられた世田谷区だけ特別空き家が目立つわけではないことがわかります。
*2015年と2040年の将来人口の推測を比較し、500m四方で色分け。0~-25%は薄い水色、0~5%は緑、~10%黄緑、~15%黄、~20%薄橙、~25%濃橙、25%~赤もうひとつ、考えておきたいのが将来人口。不動産投資において東京が有望視されてきたのは、安定的な人口増加の推測から。しかしそこには地域差があります。2015年を100とし、2040年の推定人口*をみていくと、都心回帰の流れが鮮明にみられます。一方で、物件数が多い環状7号線沿いは、城南エリアを除き、人口減少の傾向を示すエリアが点在しています。さらに郊外は主要駅の周辺以外は人口減、東京駅から30km、JR中央線「立川」を越えると減少が顕著になります(図表4)。
*2015年と2040年の将来人口の推測を比較し、0~-25%は薄い水色、0~5%は緑、~10%黄緑、~15%黄、~20%薄橙、~25%濃橙、25%~赤
現状の物件数を維持したまま推測通り人口が減少していくと仮定すると、物件数が多く人口減少が推測されているエリアは、投資環境としては厳しいエリアになると考えていいでしょう。
新型コロナウイルスの収束が見えない状況で、専門家の意見はますます割れています。また現在発表されている将来図は、どれもコロナ禍前のもの。今後、大きく変わる可能性は高いといえます。投資家ができることは、情報取集を小まめに続け、方向性を見極めることになりそうです。
【初心者必見】不動産投資で失敗しないための3つのルール
不動産投資をこれから始めたいという方に向けて、不動産鑑定士・不動産投資コンサルタントとして活躍する浅井佐知子さんによる新連載がスタート!
浅井さんは不動産会社に10年間勤務。その後不動産鑑定士を取得して、国土交通省の地価公示評価員、国税庁の固定資産税評価員などの公的な仕事のほかにアパートや店舗の賃貸、不動産鑑定など、5000件以上の依頼をこなしてきた。
第1回目となる今回は、「たったこれだけ! 不動産投資で失敗しないための3つのルール」と題し、不動産投資で失敗する人の特徴、そして失敗しないための3つのルールについて話してもらった。
1.不動産投資で失敗する人の特徴
不動産投資がうまくいっていないという方から、よく相談を受けているという浅井さん。不動産投資で失敗する人の特徴として浅井さんが挙げたのは、「全く勉強せずに業者のセミナーに出てその場で物件を買ってしまう」「電話での営業を断れない」の2つだ。
1つ目は不動産業者の無料セミナーに参加し、業者の話をそのまま信じて、不動産投資に関する勉強を一切せずに物件を購入してしまうケース。
2つ目は、知らない不動産業者からいきなりかかってきた電話で、物件を全く見ることなく購入してしまうケースだ。
不動産投資で失敗してしまう人は、業者の話を鵜呑みにし、自分でシミュレーションなどをせずに物件を購入してしまう。気付いたときには融資の返済が一切できないなどの状態に陥っていることが多いという。浅井さんは、「最初の1棟目からきちんと勉強して物件を購入することが必要だ」と話す。
2.絶対に失敗しないための3つのルールとは?
浅井さんは「不動産投資では、3つのルールを守ることができれば大きな失敗を防ぐことができる」と言う。

1.シミュレーションをする
キャッシュフローはいくらか、税引き後の利益はいくらか、デットクロスは来るのか、売却したときにいくらの利益になるか、などを物件購入前にシミュレーションして、理解しておく必要があるという。
こうしたシミュレーションができれば、借入金の返済ができないという事態に陥ることはないという。
2.市場分析をする
購入予定の物件が良いかどうかを見極めるために、市場分析をする必要があるという。市場分析にはたくさんの項目があるが、浅井さんが特に重要だと考えているのは「地域の賃貸市場」「空室率」「乗降客数」「世帯数の推移」「業者ヒアリング」の5つだ。
良い物件があったら必ず現地に行き、上記の5つの項目について徹底して調査しておくことが、物件選びでの失敗を防ぐことにつながるという。また、浅井さんは「不動産投資はとにかく現場が重要。なので物件を見ないで購入するのはあり得ない」と話す。
3.空室対策をする
どんなに良い物件を購入しても、購入後に必ず空室が発生する。その際に空室対策ができることが非常に重要だという。

空室対策でまず重要なのは、物件の現状をしっかりと把握することだ。「なぜ入居が決まらないのか、実際に現地まで行き確認する必要がある」と話す。部屋の中は綺麗な状態でも、共用部が汚れていることが原因で入居がつかないということもあるという。
次に、管理会社や客付け業者に入居の募集状況について確認する。物件が綺麗な状態でも、入居の募集がされていなくて空室が続くということもあるという。
最後にホームステージングの実行と客付けサイトの利用だ。管理会社や客付け業者に全てを任せるのではなく、オーナー自らホームステージングを実行したり、客付けサイトを利用して入居者を直接募集したりすることも重要になるという。
◇
では、今回のポイントについておさらいしておこう。

今回は、浅井さんに不動産投資で失敗しないための3つのルールについて解説してもらったが、不動産投資でまだまだ知っておくべき知識はたくさんある。ぜひ、楽待新聞の記事やコラム、あるいは初心者向けコンテンツである「はじめての不動産投資」で学んでみてほしい。
次回は、「新築区分マンションを買ってはいけないこれだけの理由」として、新築区分マンションを購入してもいい人と悪い人の特徴、購入してもいい時期と悪い時期についての解説を予定している。
講師:浅井佐知子氏
不動産会社に10年間勤務。その後不動産鑑定士を取得し、2001年に浅井佐知子不動産鑑定事務所を開業。不動産売買や土地活用だけでなく、国土交通省の地価公示評価員、国税庁の固定資産税評価員など、公的な仕事もこなす。著書に「世界一やさしい 不動産投資の教科書1年生」がある。
老いる日本…「医師だけは、不動産投資で超高収益」の真の意味
医療と不動産を絡めた事業展開
現物投資である不動産は、投資対象そのものに価値があり、株式のように紙くずになることはありません。また、巨大地震などの災害などに遭わない限り、物理的になくなってしまうことも、ほとんどないのです。それに、万が一災害によって大きな被害が出たとしても、保険に入っていれば資産のすべてを失うことはありません。
不動産の活用方法は無限大です。たとえば、医師である皆さんがこれから所有する不動産は、将来的に家賃収入を生むだけでなく、医師ならではの活用方法があります。それは医療と不動産を絡めた社会貢献です。
一般的に不動産のオーナーが事業展開を行う場合、業種としては不動産管理会社などの不動産関連業がほとんどです。しかし医師であれば、そのブランド力を活かしてほかにも実現できる事業展開があります。賃貸物件とクリニックの併設はもちろん、様々な形態の医療施設を開業することが可能だということです。

(画像はイメージです/PIXTA)
特養の入居待ち52万人超、高齢者住居は不足している
ニュースや新聞で報道されるように、昨今は高齢化が進む一方で高齢者向け住宅が不足しています。内閣府の「平成27年版高齢社会白書」によると、2013年の高齢者(65歳以上)のいる世帯は2242万世帯で、全世帯の44.7%を占めています。2003年では1727万世帯でしたから、10年間で約30%も増加しているのです。
なかでも高齢者単独世帯は573万世帯(高齢者のいる世帯の25.6%)、高齢者の夫婦のみの世帯は697万世帯(高齢者のいる世帯の31.1%)となっており、半数以上が高齢者だけで暮らしていることになります。
また、総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」によると、高齢者のいる世帯のうち持ち家は82.7%ですが、持ち家のバリアフリー化は進んでいません。2009年以降に高齢者のために工事(将来の備えを含む)を行った世帯は全体で13.3%、高齢者のいる世帯だけを見ても20%しかありません。
「平成25年度介護保険事業状況報告」によれば、2013年の65歳以上の第1号被保険者数はおよそ3200万人で、そのうち要介護認定者はおよそ580万人。さらに、このうちの7割以上が自宅で介護を受けています。特別養護老人ホームの入居待ちが52万人超と言われていることからも、いかに施設が不足しているかが分かります。
療養型病院を退院した後の受け皿となる「サ高住」
しかし、日本は1000兆円を超える多額の財政赤字を抱えており、人口減によって税収の増加も望めないことから、高齢者のケアを病院から在宅へとシフトさせることを目標に掲げています。2011年の「高齢者住まい法」改正によって創設された「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」も、その一つです。
このサ高住は療養型病院を退院した後の受け皿としても有効なので、医師がオーナーとなるのは理想的といえるのではないでしょうか。サ高住は建物に対してだけでなく、高齢者の生活支援にも様々な優遇措置が受けられる施設です。一般的な賃貸住宅の収益のほとんどは「家賃」ですが、この住宅では4つの収益構造が実現します。具体的には「診療報酬」「介護報酬」「生活支援サービスの対価」です。
このうち介護報酬とは、サ高住の事業者が、要介護または要支援者にサービスを提供した場合、その対価として事業者に支払われる報酬です。この報酬は3年ごとに見直され、サービス事業者がサービスを提供した場合の対価は、利用者が1割、保険者(市町村)が9割の負担となります(2015年8月より一定以上の収入がある利用者は2割負担)。
2015年度に見直された介護報酬は次のようになっています。
【身体介護が中心である場合】
所要時間20分未満の場合:165単位
所要時間20分以上30分未満の場合:245単位
所要時間30分以上1時間未満の場合:388単位
所要時間1時間以上の場合:564単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増ごとに80単位を加算した単位数
【生活援助が中心である場合】
所要時間20分以上45分未満の場合:183単位
所要時間45分以上の場合:225単位
通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合:97単位
*単価は「単位」で表し、1単位は約10円
サービスを提供される側からすると、数多くのサービスが整っているほうが快適で、提供する側からするとより多くのサービスを提供するほど対価が得やすくなるわけです。
住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるケアシステム
2012年、サ高住に係る介護保険法と老人福祉法の改正によって、より医師が経営すべきと考えられる状況になりました。この改正でもっとも注目すべき点が「地域包括ケアシステムの推進」です。
地域包括ケアシステムの推進によって、介護が必要になった高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるように「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」の5つのサービスを一括的に受けられる支援体制の強化が図られることになりました。
厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025年には後期高齢者(75歳以上)が約800万人、2042年には団塊ジュニア世代も65歳以上となり、高齢者数は約3900万人となると予測、その人口割合は増加し続けると推計しています。
このまま病院に長期入院する高齢者が増えれば、必要な治療を受けられない人が増えていく一方です。また、日常生活に支援や介護が必要な認知症高齢者も2010年の280万人から2025年には470万人に増加すると見られています。高齢者がたとえ認知症や慢性疾患となっても地域で暮らせる仕組み作りは日本にとって必要不可欠でしょう。
今後の課題は、「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」の5つのサービスを円滑に提供できる体制作りと医師や介護士など専門職とのスムーズな連携です。この課題がクリアされれば入院した高齢者が早く退院し、住み慣れた自宅で生活できるようになるはずです。
国は30分以内に必要なサービスが提供できる環境を目指していますが、スムーズな在宅介護を行うには今のところ高齢者向け住宅が不足しています。たとえ大病を患っている高齢者でも在宅で暮らせるような住宅が求められているのです。
サ高住の推進にも繋がるケアシステム
このような住宅では、利用者のニーズに合わせて適切なサービスを提供できること、さらに入院、退院、在宅医療といったように状況が変化しても利用者一人ひとりをよく理解したサービスが提供できることが重要です。
地域包括ケアシステムの「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」の5つのサービスとは次のようになります。
①医療との連携強化
②介護サービスの充実
③予防の推進
④見守り、配食、買い物などの生活支援サービス
⑤高齢者にとって快適な住まいの整備
これはすなわちサ高住の推進ともいえます。同時に、よりレベルの高いサービスが求められていくともいえます。
たとえば、24時間対応の定期巡回、随時対応サービスなどです。これは要介護高齢者の在宅生活を支援するため、昼夜を問わず訪問介護と訪問看護を連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行うものです。それには介護する側と看護する側、そして地域医療機関とのスムーズな連携が必須です。一般的には非常に難しいことに違いありませんが、ドクターがサ高住のオーナーとして指揮を執り、さらにデイサービスなどの介護施設を併設していれば実現可能ではないでしょうか。
医師への連絡体制等の整備が不可欠な「サ高住」
2012年の介護保険法の改正では、介護を行う人材とサービスの質の向上が厳しく求められるようになりました。
たとえば、介護福祉士や一定の教育を受けた現場経験のある介護職員などは、これまで医師法で医師と看護師以外はできなかった医療行為が行えるようになりました。具体的には次の医療行為になります。
●たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
●経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
今まで介護職員によるたんの吸引などは、緊急措置として一定の要件の下で運用されてきましたが、将来にわたってより安全な提供が行えるよう、2012年に法制化されました。しかし、このような行為は高齢者の命にかかわります。許可される介護福祉士などには制限が設けられ、一定の教育を受けることが義務づけられています。
また厚生労働省は、サ高住などの施設では医療関係者との連携の下で次のような体制の構築を求めています。
●状態が急変した場合の医師等への連絡体制の整備等、緊急時に適切に対応できる体制を確保
●対象者の状況に応じ、医師の指示を踏まえた喀痰吸引等の実施内容等を記載した計画書の作成
●喀痰吸引等の実施状況を記載した報告書を作成し、医師に提出
●対象者の心身の状況に関する情報を共有する等、介護職員と医師、介護職員との連携の確保と適切な役割分担を構築
●喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること
●施設内連携体制の下、業務の手順等を記載した業務方法書の作成
●医療関係者を含む委員会の設置とその他の安全確保のための体制の確保(ヒヤリ・ハット事例の蓄積及び分析体制含む)
これを読むと、密接な医師と施設の連携がいかに求められているかが分かります。
サ高住の建設・改修には補助金制度がある
さらに国は、サ高住の建設・改修には補助金制度を設けており、平成27年度の補助率は次のようになっています。
<サ高住>
新築の場合:工事費の10分の1(上限100万円/戸)
改修の場合:工事費の3分の1(上限100万円/戸)
<高齢者生活支援施設(デイサービスや診療所など)>
合築・併設工事の場合:10分の1(上限1000万円/施設)
改修の場合:3分の1(上限1000万円/施設)
同様に平成27年度の税制面での優遇措置は以下の通りです。
●所得税・法人税:5年間割増償却40%(耐用年数35年未満28%)
●固定資産税:5年間2分の1以上、6分の5以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減
●不動産取得税(家屋):課税標準から1200万円控除/戸
●不動産取得税(土地):家屋の床面積の2倍に当たる土地面積相当分の価格等を減額
※適用期限は所得税・法人税が平成28年3月31日、固定資産税ならびに不動産取得税が平成29年3月31日となっている。
ほかにも国は、建設に対して住宅金融支援機構の長期固定金利の融資が利用できるなどの支援策でサ高住の設立をバックアップしています。
医療・健康サービス付き施設の価値を高められる
サ高住のほかにもシングルマザー向けシェアハウス、メディカルエステ、医食同源をアピールするヘルシーレストランなどドクターがオーナーであることが、そのままメリットになる施設は無数に考えられます。医師だから実現できるこうしたサービスは、不動産の持つ潜在的価値を最大化させることで周辺の競合物件との差別化が図れ、同時に社会貢献にもつながるはずです。
このような医療・健康サービス付きの施設へのニーズは、今後、急速に進む高齢化や核家族化によってますます増大していきます。まさに、時代が必要としているのです。また、サ高住のような介護保険事業への展開を考えるのであれば、医療法人の設立を検討すべきです。
個人クリニックでも、保険証が使える保険医療機関であれば「みなし介護保険事業者」として、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションなどを行うことができます(いずれも介護予防含む)。本格的な介護保険事業者である介護老人保健施設や訪問看護ステーション、デイサービスなどの指定事業者になるためには、法人格を持っていることが必要です。
医療法人の設立は節税対策としても有効
医療法人の設立は、税制上や将来子どもに事業を譲る際にも有利です。
個人の所得税・住民税を合わせた最高税率は55%ですが、資本金1億円超の法人の場合は23.9%です。ただし、資本金1億円以下の場合、年800万円以下の所得金額については19%とさらに低く設定されています。さらに、2017年3月31日までは15%に引き下げられています。
また、個人クリニックの場合は「給料」という概念がないため、収入を経費として計上することはできません。しかし、医療法人なら自身を理事長、家族を理事といった肩書きにして報酬を経費にすることができるうえに、車の購入費や接待交際費など、個人経営よりも認められる経費の幅も広がります。
つまり、法人化によって勤務医としての給与と家賃収入を損益通算ができなくなるものの、別の節税が可能になるということです。ただし勤務医、特に公的医療機関に勤めている場合は、法人の役員や理事になることが禁止されています。退職を希望しないのであれば、妻や親など生計を同一とする家族になってもらえばいいでしょう。
法人化は相続税対策にも有効です。医療法人としてのクリニックや病院は、経営者が代替わりしても相続税の課税対象とはなりません。相続税の税率は最高で55%(法定相続分に応ずる取得金額6億円超)です。10億円なら5億5000万円です。これは決して無視できない金額ですから、子どもの将来のためにも、ぜひ頭に入れておくべきです。
「不動産運用の開始=同時に法人設立」ではない
ここで一つ理解しておきたいのが、「不動産運用の開始=同時に法人設立」ではないということです。ドクターに限らず不動産運用をはじめると、すぐに法人化をしたがるケースが多々見受けられます。まるで法人化ありきのようです。
事業を立ち上げたならば一国一城の主。法人を設立し、「代表取締役」となりたい気持ちは十分理解できます。しかし、資産形成という意味では、すぐに法人化せずにタイミングを見定めるべきです。
その主な理由は、以下の2つになります。
①法人は融資を受けにくい
最初の物件購入の前に法人化をしてしまうと、法人としての実績がないため融資の審査が通りにくくなります。法人化してから2~3年は黒字決算にしないとローンを通すのは難しいでしょう。
②給与所得と損益通算できなくなる
法人化すると収益に対する税金が所得税ではなく、法人税となるため給与所得と損益通算できなくなります。
黒字経営になったときが法人化のタイミング
では、いつ法人化するのか。それは収益が黒字化してからです。
不動産運用というものは、最初は収支がマイナスになりがちです。物件の購入時には、不動産取得税や登記代、火災保険料、リフォーム代など様々な経費がかかるためです。しかし、これらの経費は5年後に資産10億円を実現するための先行投資です。決して無駄金ではありません。
多くの不動産運用は、はじめてから2年ほどはマイナス決算になるものです。この期間を過ぎて黒字になれば、給与所得と合算した節税をできなくなります。このときが法人化のタイミングです。
とはいえ、あくまでケース・バイ・ケースなので、法人化後の節税は事業パートナーまたは会計士、税理士とよく相談するべきです。
老後に向けた資産形成、おすすめの投資方法は?5つの投資方法を比較
1.老後2,000万円問題とは
日本がこれまで経験したことのない長寿社会を迎ようとしている中、政府は2017年に「人生100年時代構想会議」を設置し、人生100年時代を見据えた経済社会システムを創り上げるための政策グランドデザインについて検討を始めています。
しかし、現在の日本における年金事情などを考慮すると国任せの老後は必ずしも安泰ではなく、個人における老後に向けた資産形成などの取り組みが求められています。
2019年には、2,000万円という具体的な金額が取り上げられましたが、以下ではその根拠となった老後に必要な生活費と将来受け取る年金額の収支について詳しく見ていきたいと思います。
高齢夫婦無職世帯の家計収支
 ※総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)平成29年」より引用
※総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)平成29年」より引用
上図は夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦2人の無職世帯における1カ月当たり収支状況を表したものです。上の横棒グラフは年金などによる収入を表していますが、実収入は209,198円となっています。
一方、下の横棒グラフは支出状況を表しており、非消費支出28,240円と消費支出235,477円を合わせた総支出は263,717円です。
実収入から総支出を引くと毎月54,519円の不足となり、この状態で65歳の人が95歳まで30年間生活すると以下のように約2,000万円が不足する計算となります。
- 1年あたりの不足額=54,519円×12カ月=654,228円
- 30年間の不足額合計=654,228円×30年=19,626,840円≒2千万円
この試算によると高齢世帯の多くでは年金収入が必要な生活費を下回るため、毎月生活費の不足分だけ赤字が累積する状況です。
生活費の不足分は貯蓄を取り崩すなどして賄う必要があるため、これが老後に2千万円というまとまった資金が必要になる根拠となっています。
ただし、総務省の試算は65歳の人が95歳まで30年間生きることを想定した試算となっているため、全ての高齢世帯に当てはまるものではありません。ライフスタイルによっても大きく収支は変わってきますので、2千万円という金額自体はあくまで参考値として見るのがよいでしょう。
なお、2020年10月現在、メガバンクなどの定期預金は1千万円単位の大口でも年利0.002%という低金利の状態が続いており、これまでの貯蓄メインの資産形成では効率的に老後の資金を貯めるのも難しい状況です。
このような状況の中、貯蓄より多くのリターンが見込める投資を中心とした資産運用へとシフトしていく必要もありますが、投資は貯蓄よりもリスクのある運用方法となっており時には損失が出ることもあります。
そのため、若いうちから少額でも投資を始めることが推奨されており、知識と経験を身に付けながら長期間にわたって投資も含めた資産形成の取り組みを行うことが重要になっています。
2.老後に向けた資産運用・投資方法5選
老後に向けた資産形成は多くの人が直面する問題です。以下では老後に向けた代表的な資産運用・投資方法を5つご紹介します。
資産運用・投資にはリスクが伴うので、それぞれの運用方法におけるメリットやデメリットについて理解した上で、自分に合った投資判断を行うことが大切です。
2-1.株式投資
株式投資とは、企業が発行した株式を売買して運用益を目指す投資方法です。株式投資では、「購入した株式価格の値上がりによる利益」「配当金による利益」「株主優待」という3つのメリットを見込んで運用することが可能で、資産形成目的の株式投資では主に株式の値上がりと配当金による利益を目指して運用することになります。
株式投資では短期間で大きな利益を狙える半面、リスクも伴うため、株価の暴落や倒産などによって損失を出すというデメリットもあります。
また、株式の購入はそれぞれの株式ごとに決められた単元株数(銘柄ごとに定められた最低取引単位)での取引となるため、投資金額が大きくなりやすい点にも注意が必要です。
しかし、最近は少額から投資可能な株式投資サービスがネット証券を中心にリリースされており、まとまった資金を用意することが難しかった人も気軽に投資が出来るようになっています。
【関連記事】ミニ株・単元未満株のメリット・デメリットは?購入できる証券会社も5社紹介
株式の売買で発生した利益は譲渡所得となり所得税が課されます。ただし、上場株式の売買では証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用することで利益に対して源泉徴収が行われるため、他に所得が無ければ基本的に確定申告は不要です。
また、NISA口座を活用することで毎年の投資金額が120万円までの範囲内であれば上場株式の譲渡益や配当金に対する税金が非課税となる制度もあります。
2-2.投資信託
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金でファンドを生成し、投資のプロが投資家に代わってその資金を運用する金融商品です。
ファンドは株式や債券、金、先物などの様々な金融商品に投資することで運用され、資金を募る際に投資対象などを明示した目論見書を発行します。投資家はこの目論見書を確認するなどして投資判断を下すことになります。
投資信託は、通常ではある程度まとまった資金が必要になる債券や株式などの投資を1万円などの少ない金額から始められることがメリットです。
また、ファンドはまとまった資金で運用されるため、個人では難しい複数の金融商品に分散投資することも可能となっており、リスクを分散しながら運用益を期待できる点も大きな特徴です。運用は高度な知識を持ったプロの投資家が行うため、投資家はファンドを選択することで手軽に運用できるのもメリットです。
一方、投資信託のデメリットは、プロに資金運用を任せる見返りとして信託報酬というコストが発生する点です。買付や解約の際に手数料がかかる場合もあるので費用はさらに大きくなります。なお、プロが運用しても損失が出る場合もあるため、投資信託の価格変動によって元本を毀損するリスクがある点にも注意を要します。
投資信託の売却によって利益が出た場合や収益分配金を受け取った場合には所得税が課されます。こちらは投資信託や配当の種類に応じて課税されますが、株式と同様にNISA口座で取引できる投資信託については、毎年の投資金額が120万円までの範囲内で非課税になります。
【関連記事】おすすめしない投資信託の特徴は?良し悪しを見分けるポイント4つ
2-3.つみたてNISA
つみたてNISAは、NISAと同様に個人の資産形成を後押しする目的で導入された非課税制度で、少額からの長期・積立・分散投資を支援するために2018年から始まった制度です。
つみたてNISAでは、購入できる金融商品の金額は年間40万円までとなっていますが、非課税期間が最長20年間(現時点では2037年まで)と長く、少額でも長期的な運用益を目的に資産運用を行うことが可能となっています。
つみたてNISA非課税枠イメージ
 ※金融庁「つみたてNISAの概要」より引用
※金融庁「つみたてNISAの概要」より引用
制度開始の2018年から利用すると最大800万円の投資に対する運用益が全て非課税となります。2020年から始めたとしても18年間×40万円で最大720万円の資産を非課税で運用できます。
また、年間の投資上限額は40万円となっていますが、その範囲内であれば月1,000円からでも積立できる制度となっているため、投資の初心者でも利用しやすい制度となっています。
一方、購入できる金融商品は長期・積立・分散投資に適した投資信託のみとなっているため、リスクを抑えた運用は可能となっていますが、金融商品の選択肢が少ない点はデメリットです。また、投資信託には元本毀損のリスクもあるため、リスクの低い投資信託を選択しても元本割れする可能性がある点も留意しておく必要があります。
2-4.iDeCo
iDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」のことを指し、毎月掛け金を決めて運用することによって老後の蓄えを用意するのに向いた私的年金制度です。
自分で決めた毎月の掛け金を拠出して運用し、原則60歳になってから老齢給付金として受け取る仕組みとなっています。
毎月の掛け金は5,000千円からとなっており1,000円単位で掛け金を増額することもできますが、掛け金の上限額については加入者の種別によって下図のように異なります。
iDeCoの加入資格等
 ※iDeCo公式「iDeCoの加入資格等」より引用
※iDeCo公式「iDeCoの加入資格等」より引用
自営業の方は国民年金基金と合算で最大月額68,000円まで拠出することができ、企業年金のないサラリーマンの方は月額23,000円を上限に拠出することができます。
企業年金のあるサラリーマンの方は加入している企業年金によって掛け金の上限額が異なるため、詳細は所属企業の総務人事部門などに確認してみましょう。
iDeCoのメリットは大きく3つあります。1つ目は、掛け金が全額所得控除の対象となるため、掛け金に応じた所得税や住民税を節税しながら将来の資産を形成できる点です。
2つ目は、運用益に対する所得税が非課税となる点で、運用益が出た場合、全額を将来の受け取り、年金資産の原資に回すことができます。
3つ目は、60歳以降で年金として受け取る場合、公的年金と合わせて公的年金等控除が適用されるため、所得税を抑えながら年金として受け取ることが可能です。
このようにiDeCoは将来の資産形成の方法ですが、原則として60歳まで運用した資産を受け取れない点はデメリットです。
一定の条件を満たすことで脱退一時金として受け取ることも可能ですが、基本的には将来年金で受け取る制度となっているため、急にお金が必要となる場合には対応できないこともあります。
【関連記事】iDeCo(確定拠出年金)は加入すべき?メリット・デメリットや始め方も
2-5.不動産投資
不動産投資とは、土地や建物などの不動産を購入し、売却や賃貸などによって利益を得る投資方法です。
不動産投資はまとまった資金が無ければできない投資と思われることもありますが、マイホームと同様に事業用ローンを組んで物件を購入し、受け取った家賃からローンを返済していくことも可能です。
そのため、入居者がいる限り定期的な収入を見込めるほか、減価償却や損益通算による税控除や相続税対策などの税制上のメリットがある点も特徴的です。
一方、入居者が決まらなければ収入が途絶えるという空室リスクを伴います。家賃収入が無ければローンの返済が大きな負担にもなります。
また、物件管理には手間や費用がかかります。管理業務は不動産会社に委託することで一定の手間を省くことができるものの、委託費用がかかる点や突発的なトラブルへの対応がある点はデメリットと言えます。
不動産の賃貸収入は不動産所得に該当するため、確定申告が必要です。賃貸物件の管理や修繕などに要した費用は必要経費になるため、収入だけでなく支出の管理も必要になります。
【関連記事】不動産投資の初心者は何に気をつけるべき?始め方・物件購入の流れも
その他、実際に不動産を所有せずに少額投資が出来る「不動産投資型クラウドファンディング」という投資方法もあります。不動産投資型クラウドファンディングは実際に不動産所有しないため、物件保有によるリスクや手間が無い点も大きな特徴です。
例えば、「アイボンド(i-Bond)」というクラウドファンディングサービスでは、予定分配率は年1.5%(税引前)、1口1万円から投資ができるため、「まずは少額から始めてみたい」という方には、はじめやすくなっています。
実物の不動産投資と異なり税制メリットがなく、融資によるレバレッジが使えない点はデメリットとなりますが、「まずは少額から不動産投資を始めたい」という方は検討してみましょう。
【関連記事】不動産投資型クラウドファンディングを選ぶポイントは?注目の3社を紹介
3。まとめ
日本の年金制度では老後の生活費などが不足する可能性もあるため、老後に備えた資産形成の重要性は年々高まっていると言えます。将来のことを不安視しすぎる必要はありませんが、自分が実現したい老後などをイメージして必要な資金を試算してみることは大切なことです。
資産形成をするための投資方法は様々ありますが、投資はリスクを伴うため、それぞれの手法によってメリット・デメリットがあります。それぞれの投資方法を理解し、比較したうえで慎重な投資判断を行うことが大切です。
不動産投資をしている医師が、「酒の席で」漏らした仰天の本音
医師ならではのコンセプトがプラスされたとき…
不動産運用で収益を上げる秘訣は、安く買ってその後に付加価値をつけることであり、これは鉄則ともいえるでしょう。
その付加価値とはいわゆる「コンセプト」です。たとえ一般的には人気の低いエリアでも、医師ならではのコンセプトがプラスされたとき、その物件は周辺のどの物件よりも収益率の良い存在になります。
たとえば詳細は後ほど説明しますが、シングルマザーの多い土地柄なら託児所を併設した
「シングルマザーシェアハウス」や、高齢者が多い地域ならおじいちゃんやおばあちゃんが日帰りで利用できる「デイサービス付き高齢者住宅」といったオーナーが医師であることを活かしたコンセプトです。
ほかにも、かつて医大生だった頃にどんな賃貸マンションが欲しかったか、今オーナー医師として何かアピールできることはないかを考えて、医大や大きな病院近くの物件を医大生や看護師向けの賃貸住宅にするといったコンセプトもあります。定期的に情報交換会を開催したり、エントランスなどの共用部分に専門書の貸出コーナーを設けるなどで差別化を図るのです。
このように医師ならではのコンセプトを明確に打ち出せれば、多少人口の少ない地方都市でも十分に経営が成り立つはずです。同時にシングルマザーや高齢者がイキイキと生活できるといった地域の活性化にも役に立てるでしょう。
逆にいくら都心に近く、いい立地でもコンセプトがない平凡な物件では選ばれる理由がなく、建物が老朽化するにしたがい、入居者募集が困難になるはずです。
ただし、どんなに画期的なコンセプトでも、過疎地のような人が集まらない土地はおすすめしません。町おこしなどの地域の活性化は行政が動かないと難しいものがあります。やはりある程度の人口規模が下地にあった上でのコンセプトといえます。
海外不動産投資・進出でも「コンセプト」を重視
また、「周辺エリアの医師の数」「コンセプト」という土地選びの視点はなにも国内に限ったことではありません。
現在は人もモノもグローバル化しています。かつては「メイド・イン・ジャパン」がもてはやされましたが、今は「メイド・バイ・ジャパン」に変わっています。
このような流れの中では、海外の物件を購入して現地で医療サービスを提供するという手も十分勝算があります。たとえば定年退職した人の移住先として人気の高いマレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、カナダ、カンボジアなどが狙い目です。
所有している物件からきちんと家賃収入があれば、勤務医として過酷な状況で働かなくても物価の安い海外なら十分暮らせるでしょう。海外で気ままにリゾートライフを送りながら、現地で移住者を対象に開業もけっして夢ではありません。
右も左も分からない海外での開業など現実的ではないと思うかもしれませんが、海外でも経験豊富なエージェントに仲介を依頼すれば問題はありません。実際、私は知り合いの医師と一緒にカンボジアで事業を始めています。
コンセプトは不動産会社が立案してくれる
収益物件の経営を軌道に乗せるには、物件にコンセプトがあるかどうかが重要です。さらに医師ならではのコンセプトなら鬼に金棒でしょう。
ところが、コンセプトというものはすぐに思いつくものではありません。まして多忙な医師の皆さんに、そのことを考える余裕はないでしょう。そこで頼りにしたいのが収益物件の仲介や販売を行う不動産会社となるわけですが、当然すべての不動産会社がコンセプト立案に優れているわけではありません。そのため、一般的な営業手法は、立地と利回りのアピールとなってしまいます。
では、どうすれば理想的なコンセプトを立案できる不動産会社やパートナーに出会うことができるのか?
それは話を聞きに行って、実際に担当者の「提案力」と「実行力」を確認することです。まず、「何か提案はない?」と聞いたときに「ありません」と即答するようでは論外です。多少時間がかかっても企画書を持ってくる提案力が必須です。
次にこの提案が絵に描いた餅ではなく、実現可能かどうかを見極める必要があります。実現するためのスケジュールを確認し、1か月後、2か月後にどのような状況になっているか、そして完成はいつなのか。それまでにかかるコストと、その後の収支計画に無理がないのか。ここまでもれなく説明できる実行力があれば、営業担当としてのスキルは心配ないといえるでしょう。
ただし、いくら美しい提案でも皆さんをやる気にさせなければ意味がありません。不動産は高額商品です。「提案の筋は通っているけど、何となくやる気になれない」ということもあるでしょう。私は経験上、その「何となく」の多くの原因は不動産会社の担当者など、パートナーにあると考えています。皆さんが「この人なら任せられる」と思える条件は何でしょうか?
一言でいってしまえば「安心感」だと思います。
Aさんは理詰めの説明、Bさんは趣味の話、Cさんはお酒が一緒に飲めること、Dさんは子どもが同世代、Eさんは医療に対する知識など、安心を感じるポイントは人それぞれです。これは相性としか言いようがないかもしれません。
「本当はこんな医療施設をつくりたい」
「提案力」と「実行力」があることが判断できたら、「このパートナーに本音を話すことができるか?」と自問自答してみてください。医師が不動産運用を行うにあたって、パートナーは女房役です。年収や預金、そして将来の目標などをすべてさらけ出す必要があります。逆にサポートする側からすると、さらけ出してもらわないと、何年ローンがいいか、どこの金融機関がいいかといった最適な提案ができません。
担当者はそのことをよく知っているので「本心で話してください」というスタンスで接してきます。このときに何か違和感があるようなら、あなたはまだその人を信用していないということでしょう。もう少し時間をかけてみる、または打ち解けるために飲みに行くといった手もあります。どうしても合わないなら上司に連絡して担当を代えてもらうか、違う不動産会社などへ相談するべきでしょう。
私はクライアントである医師とよく飲みに行きます。最初はビジネスライクな会話でスタートしますが、やはりお酒がちょっと入ってくるとお互いに腹を割ってくるものです。

(画像はイメージです/PIXTA)
「本当はこんな医療施設をつくりたい」「あとX千万円あれば目標達成なんだ」といった話が聞けて、「ならばこうしましょう」とオフィスではけっしてできなかった仕事の話がとんとん拍子に決まることが多々あります。ある医師は後から「あのときの会話で人生が変わった」と言ってくれたこともありました。
もちろん何もお酒に頼る必要はありませんが、とにかく不動産運用には腹を割ってじっくり話せるパートナーがいることが重要だということです。
不動産投資…「人口減少はリスク」を鵜呑みにする人の浅はかさ
知識があれば賃貸住宅経営のリスクは軽減できる
データをもとに自分なりの仮説を立てる
「不動産投資法に正解なし」
こう話していたのは、サラリーマン時代の2006年に1棟目の不動産を購入し、2019年9月現在、10棟173戸の賃貸住宅を所有する大阪府在住の松田英明さんだ。「関西大家の会」の代表も務める松田さんは次のように指摘する。

「ある物件を購入した場合、その人には良い投資であっても、別の人には悪い投資かもしれない。なぜなら、それぞれが目指すゴール、それぞれの資産背景によって、投資法の正解は変わるからです。特定の投資法だけを取り上げて肯定したり、否定したりするのは全くナンセンス。成功体験は、あくまでその人が目指したゴールや持ち合わせる能力、資産背景から導き出されたもの。成功者の投資法をそのまま真似をするだけで、すべての人が成功できるなんていうことはない。投資家が一番考えるべきことは、ゴールから逆算することです。専業大家を目指すのか、将来の老後対策なのか、単なる資産運用なのか。そういった具体的な目標が一番大切です」
本連載を読んでくださっている方は、まずは老後の安定した収入源をつくるという目的の方が多いのではないだろうか。しかし、本書を読み終わったときには、サラリーマンは早めに卒業して、できれば専業家主として収入を得ていきたいと考える人もいるかもしれない。あるいは現在は違う商売をしているけれど、将来続けていくことに不安を抱いた人が転業を検討するケースもあるだろう。さらに、ある程度資産ができたので、子供に円滑に相続させたいと考える人もいるだろう。いずれにしても、松田さんが指摘するように、どのような手法で不動産を購入し家賃収入を得ていくのかは、目的、これまでの経験によって異なるというわけだ。
「知識があれば賃貸住宅経営のリスクは確実に軽減できる」と話す松田さんは、例えば、人口減少は家主業において決してリスクではないという。リスクとは不確実性であり、人口減少は、さまざまな角度から将来の推計値が公表されていて、経済に関する数値の中で最も確度の高いものの一つだ。その数値を考慮した上で家主業を営めばいい。多くの人は、その背景を理解しようとせずに数値だけを鵜呑みにし、リスクと騒いでいるだけで、自身は本当のリスクとは思っていないというのだ。
仮説を立てるには知識と情報が必要だ
そんな松田さんは、サラリーマン時代、企業の研究所に勤務していた。上司からは、研究者とし て重要なことは「正確なデータを取る」「データから仮説を立て考察する」と教わった。このことが今の家主業に生かされているのだという。
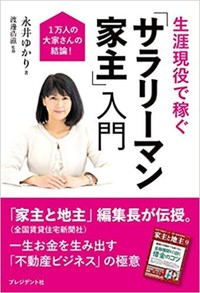
「賃貸物件の表面利回りや実質利回りなどを調べる場合、まずはエクセルに落とし込んでみることが大事。感覚だけでやってしまうと、私のように1代目として始めた家主はバックボーンがないので、足をすくわれてしまうリスクがある」と松田さんは話す。初めて購入した不動産は2億3000万円でフルローンだった。だがシミュレーションし、納得して購入したから恐怖は全くなかったという。
実際、14年経った今でも安定的な運用ができているそうだ。
家主業に限った話ではないだろうが、事業である限り経営判断する上で多くの情報や知識は必要だ。その次に大事なのは、得たその情報や知識を活用することだ。活用する際には分析が必要になってくる。
例えば、賃貸住宅の空室率が高い、とある地域を想定しよう。よく調べてみると、この地域は単身者向けのワンルームが多いために空室率が高く、ファミリー向けの物件はほとんどない。地元の不動産会社の話によると、転勤者向けのファミリー物件が少なく、しかも戸建てだとすぐ決まるようだ。そうであれば、中古の戸建てを購入し、見た目をきれいにリノベーションすればすぐに決まるのではないか。家賃相場が8万円程度だから予算は600万円程度で表面利回りは15%くらいが妥当。リノベーション費用も考えると、築20年後半~30年を500万円前後で購入できれば悪くない――、というように、まず自身で仮説を立てる。
その仮説が見当違いでないかどうかを、家主仲間や付き合いのある不動産会社に話してみるとい うのは有効な手段だろう。ただし、家主仲間に相談するときは、その対象物件には基本的に興味を持ちそうもない人に相談した方が無難だ。その分析を良しとして、先に買われてしまう可能性も無きにしもあらずだからだ。
仮説を立てるには、知識と情報が必要だ。前述の仮説を立てるには、表面利回りはどの程度が目安で、中古物件には改修工事の予算がある程度必要であること、賃貸市場には表面的なニーズと潜在的なニーズがあるという知識が必要となる。情報としては、地域の空室率、空室率が高い理由、想定できる入居者ターゲット、家賃相場などだ。ベースとなる知識と生きた情報を総合して判断することで、リスクを最小限に抑えることができる。
大地震も想定しておけばいざというとき役立つ
600万円程度の不動産ならば、現金で購入できる人も少なくないだろう。表面利回り15%で計算上では7年ほどで投資分は回収できる。入居者が決まって、7年間のうち1度は入れ替わりがある可能性を考え、入れ替わり時期の空室期間による家賃ロス、原状回復費用などを加味しても、8年あれば投資分は回収できる。9年目からは基本的に家賃収入分が新たな収入源となる。だが、築年数は購入当初よりも古くなるため、家賃は少し下げないといけないことは覚悟しなければならない。仮に10年後に家賃が1万円下がったとしても、毎月7万円の家賃収入が得られれば、月々の給与をそれだけ上げることが困難なサラリーマンとしては有難いだろう。
ここで気をつけたいのは、想定外の事態もあり得るということ。もし、大地震が発生すれば、し ばらくは賃貸入居者が募集しにくくなる。あるいは近隣で土壌汚染などが発生すれば、事態はもっと深刻だ。災害などが起きた際にも慌てないように、資金的に余裕を持って不動産を購入すること。そのためにも、早期で投資回収できる不動産から始めることは、「家主業のリスク」を最小限に抑えるという意味でも重要だ。
震災、台風の被害はこれまでも起きている。こうした災害時に家主たちはどのように対応したの か。関心を持ち、調べておけば、いざというとき役に立つはずだ。
永井ゆかり
「家主と地主」編集長
「マンションを買え」先輩医師の言葉に従った勤務医の3年後…
初めて不動産投資に取り組む多忙な医師「A氏」
 多忙を極める勤務医のA氏(32)
多忙を極める勤務医のA氏(32)
(画像はイメージです/PIXTA)

(画像はイメージです/PIXTA)

診療科 整形外科
年齢 32歳
家族構成 独身
居住地 中部地方
勤務医としての年収 1,400万円
救急指定病院で整形外科医として勤務するA氏は、文字通り昼夜を問わず働きづめです。ご存じのように整形外科の患者数は内科に次ぐ多さと言われています。しかも働いている病院は救急指定なので夜中に呼び出されることは日常茶飯事。さらにA氏は同僚の中では若手なので夜間勤務が多くなる傾向があります。
2014年の1月にお会いしたときも「正月の三が日はすべて出勤だったよ」と嘆いていました。また、整形外科は精神的には元気な患者ばかりです。クレームが発生すると激しい言葉や行動に出る患者がたまにいて、そのときの対処にも苦労しているとのことでした。
戦争のような毎日を繰り返しているので、いくら収入が多くても使う時間がありません。デートはもちろん出会いの機会もなく、数年前に60万円かけて道具を揃えた趣味のゴルフも何年もやっていませんでした。このような状況のA氏の唯一のストレス発散方法は、年に一回程度の大きな買い物でした。お金は普段使う時間がないので貯まる一方です。気がつくと預金通帳には1,000万円前後のお金が貯まっていました。それで昨年は新車のBMWを約800万円で購入しました。しかし通勤以外に乗る時間はないのですが。
節税を意識して不動産投資を始めたものの…
あまりに多忙なため、資産運用を考える暇もなかったA氏が収益物件に興味を持ったのは、同じ病院に勤務する先輩がすでに投資用マンションを持っていたからでした。ある日先輩に対して「とにかく忙しい」「お金を使う暇さえない」とグチを言ったところ、「それならマンションを買え。節税にもなるぞ」というアドバイスをもらいました。
節税に対してまったく無関心だったA氏は、先輩にくわしく説明を求めました。すると収益物件による節税の仕組みを丁寧に教えてくれました。そこで資産運用に目覚めたわけです。「今までなんてもったいない納税の仕方をしていたんだ!」。さらに「いつかは結婚したい」「結婚するなら将来に対する保証も欲しい」。毎日怪我や病気で苦しむ患者を診ているうちに、自分が病気をして働けなくなったときのために資産は必要だ、という考えにいたりました。
すぐに先輩に不動産会社を紹介してもらい、大阪府の新築マンションを2戸購入。費用は合計で約5,000万円。多忙なため現地で内見することはありませんでした。決め手となったのは、やはり節税効果でした。毎月の収入からローン返済などの支出を差し引くと1戸当たり1万円程度のマイナスですが、確定申告を行うことで数十万円の節税になる試算だったのです。
晴れて2戸のマンションオーナーとなったものの、毎日の忙しさは変わりません。そうこうしているうちに確定申告の時期が近づいてきました。物件を購入した不動産会社とは、管理委託契約も交わしていました。購入前の商談では、確定申告前に必要書類を送ってもらい、申告方法も教えてもらうことになっていたはずでした。
しかし、2月になっても何の音沙汰もありません。A氏は「このままでは節税にはならない」と不動産会社に電話をしました。すると「担当のXXは退職しました。新しい担当から連絡をさせます」と電話の応対に出た人が言いました。
A氏は、そういうことなら、と待つことにしました。しかし3月に入り、確定申告の受付期間が過ぎても連絡がありません。結局忙しさのあまりに確定申告することなく3年が過ぎました。
まずは過去3年間分の確定申告することから
私がA氏に出会ったときは、このように不動産運用のメリットを活かしきれていない状況でした。
毎月のマイナス分が3年分積もって、合計数十万円の赤字に。たまたま満室状態を継続していましたが、一括借り上げ契約をしていなかったので、いつ空室になるか毎日ヒヤヒヤしている、とのことでした。確定申告の案内をしてくれないような不動産会社では、空室時の入居者募集も期待できない、と言うのです。A氏は、こんなことなら不動産運用を始めなければよかった、後悔していると話していました。
当然販売した不動産会社がフォローするものですが、このときの不動産会社は担当者が代わったということもあり放置状態でした。「買う前ばかり連絡してきて、後はほったらかしか」と、A氏は不動産業界というものにも不信感を持ち始めていました。
しかし、せっかく満室が継続できている物件を所有しているのに、このままではあまりにもったいない。
私は、まず確定申告は5年間さかのぼって行うことが可能なことを伝えました。A氏の場合、1年で100万円近い節税ができていたはずなので、過去3年分まとめて申告すれば約300万円が還付されます。
このアドバイスによって、A氏はそれまでの後ろ向きな状態から、やっと気を取り直してくれました。今まで複数の不動産会社から営業を受けたようですが、この方法は聞いたことがなかったそうです。
実際にどのような手続きになるのか資料を送り、電話で説明し、もちろん何度も直接お会いしました。
するとだんだんプライベートな話をしていただける機会が増え、「いずれは結婚したい」「病気になって収入がなくなるのが怖い」といった不動産運用の目的を語ってくれ、打ち解けていくことができたのです。
将来のライフプランとタックスメリットを考慮した決断
私はこのような将来の希望や不安をお聞きしていると、やはりより節税しながら資産を増やしていくべきだと考えました。
私はA氏に次のような追加投資のメリットを説明しました。
● 現在の収入ならさらに融資を受けて運用物件を購入できる
● その結果、より多くの節税効果が得られ、数百万円の還付が受けられる
説明したのはメリットだけではありません。「節税効果が得られるのは経費計上できるローン金利や減価償却費が高い7年から10年の間だけ。それ以降の収支はマイナスになるはず」といったマイナス要素も話しました。
しかし、投資用物件はなかなか値下がりしないので、10年後でも購入価格の2割減程度で売却できることが少なくありません。ローンの残債を残すことなく売ることができ、再度節税効果のある新築物件を買うという手もあるのです。
また、そのまま所有していても、多くの場合けっして損ではありません。ローンを組む際は、必ず団体信用生命保険に加入します。死亡または所定の高度障害状態になったとき、保険金でローンを返済するためのものです。万が一の事態でも、ローンが完済していれば物件は家族の物。家賃収入を残すことができます。月々1万円程度のマイナスなら、別の生命保険に加入するよりもお得なのです。
それに健在なままローンを完済してしまえば、その後の家賃収入は丸々の収益です。とはいえその当時の家賃収入は2戸分で18万円程度。それでは生活を維持できないでしょう。あと3戸を追加し合計50万円前後の家賃収入は欲しいところです。
A氏はこの説明で即決してくれました。それまでの2戸を維持したまま、新たに都内の3戸を購入。5戸すべてを弊社の管理とし、一括借り上げをすることになりました。
将来の不安も解消して不動産投資に積極的なA氏
このような経緯があって、私は、A氏に都内の新築マンションを勧め、A氏はそれを購入しました。そのうち1戸の収支計画が下図表のようになります。
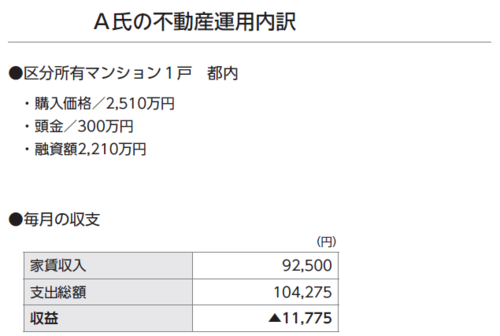
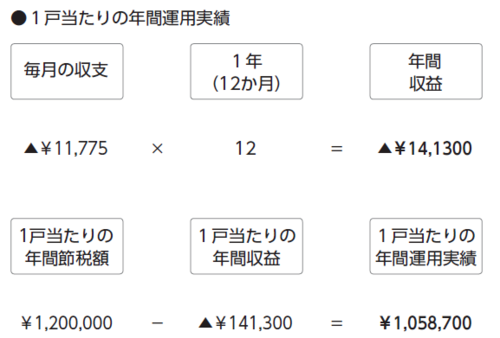
物件価格は2,510万円。頭金は1,000万円あるということだったので、1戸当たり約300万円。融資金額は約2,210万円でした。一括借り上げによる家賃収入は月々9万2500円ありますが、ローンの返済などで収支は毎月マイナス1万1775円になります。しかし、初年度の節税効果は所得税と住民税合わせて約120万円ありました。つまりトータルでは年間約106万円のプラスです。
「今までとは桁違いにお金を貯められそう。将来に対する不安も消えた」と、A氏は会うたびに笑顔を見せてくれます。
不動産ポータルサイトには出てこない「任意売却物件」
実はこの話には続きがあります。A氏とはその後もマメに連絡を取り、生命保険や節税の話をしていました。ある日、アポイントを取って病院に会いに行くと、なぜか浮かない表情です。理由をたずねると「去年はしっかり節税できて本当によかった。でも最近通帳を見ると、毎月残高が減っていく。生活費も切り詰めなければならない気がしてきた」と言います。
A氏の不動産運用は、間違いなく成功しています。しかし、それは節税効果があってこそ。毎月の収支は5戸分で5万円程度マイナスなのです。長期的な視点で考えれば、運用実績は確実にプラスとなりますし、本書ですでに説明した通り、毎月の諸経費は資産形成のための必要経費です。
とはいえ、A氏が心配だと言うのならば、答えは簡単です。毎月の収支がプラスになる物件を購入すればいいのです。この提案をすると、A氏はすぐに乗り気になってくれました。頭金は3,000万円用意できるというのです。
昨年800万円のBMWを買い、さらに物件の購入で900万円の頭金を支払ったのに……。私はあらためてA氏の底力に驚きました。
さっそくお勧めできる物件を探すと、めったに出ない掘り出し物を見つけることができました。なぜ掘り出し物かというと任意売却物件だったのです。任意売却とは、ローンが支払えなくなった物件に対してオーナーが融資を行った金融機関と話し合い、競売手続に入る前に売却することです。
ローンが支払えなくなったと聞くと、何かいわく付きのように感じるかもしれませんが、実はリーマンショック後あたりからかなり増えています。原因として不景気の昨今では法人オーナーの倒産が考えられますし、個人オーナーではリストラやボーナスカットで支払いができない、固定資産税が払えない、また夫婦で共同購入したが離婚したので払えない、といったケースもあります。けっして後ろめたい物件ではなく、むしろ売り急いでいるがゆえに相場よりも安く購入できることもある、お宝物件と言えるでしょう。
「不動産に掘り出し物はない」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、それは一般の人に限ったことです。一部のプロの間では、掘り出し物の情報が行き来し、そのネットワーク内だけで売買が完結します。
その一部のプロになる条件は、即決するかどうかです。金融機関は物件を売り急いでいます。だから情報を流す先は、自社で買い取る、または優良な見込み客を多数持っている、いずれにしても即決する可能性がある業者だけです。
相場から3割引きの物件が、一般市場に出たら想像を絶する争奪戦になるはずです。しかし、任意売却の物件はそもそも金融機関が情報を流さないので、絶対に不動産ポータルサイトには出てきません。
このような物件の情報は、金融機関とコネクションのある不動産業者にしか流れてこないのです。
資産10億円を目指すのであれば「高額物件」が効率的
A氏に提案した任意売却物件は、下表のようになります。
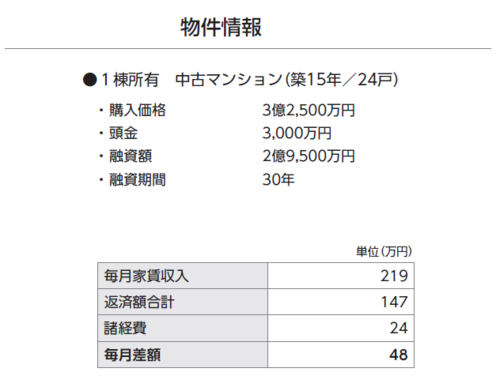
物件は築15年、24戸のマンション1棟です。価格は3億2500万円ですが、頭金3,000万円を入れればローンの返済を差し引いても毎月約48万円の収益が残ります。
正直に書きますが、3億円の中古マンションで毎月の収益が48万円というのは、かなり高い利回りです。その理由は、何といっても物件自体が割安なこと、そして当時4戸の空室がありましたが、すべて一括借り上げにしたこと、さらにA氏がまだ32歳と若いので30年の長期ローンが組めたことなどがありました。
場所は京都府ですが、弊社には大阪支社があるので入居者の募集にはまったく問題がありません。こんなに条件のいい物件は、なかなか出てこないでしょう。ところがA氏には即答で断られてしまいました。
3億円というローンを背負うプレッシャーに耐えられそうにない、と言うのです。提案しておいておかしいかもしれませんが、この反応は当たり前とも言えます。1棟買いを医師に勧めると、ほとんどが「毎日他人の命を預かる責任の上に、今まで扱ったことがないような高額な借金を背負うなんて考えたくもない」といった答えが返ってきます。
区分所有の少額な投資なら失敗してもキズは浅いと思うかもしれませんが、私はそもそも失敗しないことを前提に提案しています。不動産運用が収益を生む構造は、低額物件も高額物件も同じです。ならばより多くの収益を生み、早く資産10億円に到達する高額物件を購入した方が効率はいいのです。
医師ならば頭金は一般のサラリーマンより多く用意できるし、銀行に信用があるので多額の融資を受けられます。医師だからこそ高額物件で効率の良い資産運用が可能なのです。実際に区分所有から不動産運用を始めた医師のほとんどは、最終的に1棟買いに行きついています。
「通貨」の面でもリスクヘッジして将来に備える
私はA氏に過去の成功事例の数々を紹介しました。しかし、もう一歩踏み込めない様子。どんなに低くても、将来無一文になってしまう可能性はつくりたくない、と言うのです。そこで私は「48万円の収益のうち、10万円はドル建て積立型生命保険に回しましょう」と提案しました。
この生命保険は、毎月支払う保険料や満期時の返戻金がドルになります。そのため金額が為替レートによって変化するリスクがありますが、予定利率が円建てに比べてかなり高いというメリットもあります。
ドル建て積立型生命保険でリスクヘッジすることで、A氏は納得。この掘り出しもの物件を購入することになりました。これでA氏の資産は約5億円。「将来の安心がよりはっきり見えてきたし、すぐにでもセミリタイアできそうだ」と考えられるようになって、本業に取り組む気持ちにも余裕が生まれたそうです。
ASEAN諸国「不動産投資」に最適なのは…人気4ヵ国を徹底比較
成長著しいASEAN、不動産投資しやすいのは…
豊富な若い労働力を武器に、近年著しい成長を続けるASEAN(東南アジア諸国連合)。国民所得が向上し、購買力も飛躍的に上昇する中、ASEANの経済規模は過去20年間で約6倍に拡大しています。
しかしそんなASEANにも、マーケット環境や規制面から日本人が不動産投資をしやすい国とそうではない国があります。例えば、シンガポールは東京以上に不動産価格が高いうえに印紙税も高額ですし、2018年にコンド法を改正して外国人に不動産投資の門戸を開いたミャンマーも、同法に基づいて認可された物件がいまだなく、合法的に投資するのが困難な状況にあります。
そこで今回は、日本人でも価格面・規制面から比較的投資がしやすく、実際に投資家人気も高いマレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムの4ヵ国に絞り、経済や不動産市況を比較・解説していきたいと思います。
マレーシア、タイ…投資メリットは低下傾向?
ASEANの先発国であるマレーシアとタイは、日本人による不動産投資の歴史が比較的長く、いまも根強い人気があります。しかし、近年の経済環境や不動産市況を踏まえると、総体的には投資メリットは以前より大きく低下しているように思います。
●マレーシア
まずマレーシアですが、過去30年に渡って平均5%超の経済成長を続けてきたことから「東南アジアの優等生」と称されてきました。しかし、2018年にナジブ政権が巨額の債務隠しを行っていたことが発覚すると、財政赤字削減のためにインフラ計画が次々と中止・延期され経済が停滞。また、後を継いだマハティール氏が消費税を廃止したため、財政再建も思うように進まない悪循環に陥っています。
一方、不動産市場を見ると、積み上がった在庫の解消が課題となっています。マレーシアでは2015年に外国人が購入できる物件の最低価格が原則100万リンギ(約2,500万円)へと引き上げられ、投資が落ち込んだ一方、規制強化後もたくさんの新規供給が続いています。
その結果、デベロッパーが抱える在庫物件は、2018年末時点で過去最高の32,313戸に拡大。2019年に入ると政府もマイホーム購入支援策などを導入して解消に動きますが、同年末時点でも31,661戸と高水準にあります。この状況が改善しない限り、マレーシアの不動産価格には下方圧力がかかる可能性が高く、実際、2017年頃から首都クアラルンプールでは先行して価格が下落に転じ始めています。
●タイ
次にタイですが、ASEAN最大の工業国として過去20年間で平均4%の成長を実現している一方、すでに高齢化社会(65歳以上の人口が7%超)に突入していることが懸念材料となります。日本以上のスピードで高齢化が進行する中、2035年には新興国として初めて超高齢社会(同21%超)に突入する見通しで、今後日本と同様に経済の停滞感が強まることが予想されています。
また、中国マネーがけん引し、堅調な価格上昇を続けてきたタイの不動産市場ですが、その中国依存の高さは諸刃の剣でもあり、人民元安・バーツ高が進んだ2019年には中国人による投資が半減し、バンコク首都圏におけるコンド成約率は46%と過去5年で最低を記録しています。投機的な住宅購入を抑制するため、住宅ローン規制が厳格化されたことも市況を冷やす中、在庫の適正化に最低2年はかかる見通しで、各デベロッパーは計画の中止や見直しを迫られている状況にあります。
マレーシアとタイはASEANの中では生活環境が良好なため、別荘や移住など自己利用を目的とした購入はアリだと思いますが、投資という観点では現在の状況が改善しない限り、積極的にはおすすめしにくいところです。
フィリピン、ベトナム…不動産投資のチャンスは多い
一方、フィリピンとベトナムは潜在的な成長力が高いだけでなく、不動産市況も力強さと健全さを保った状況にあることから、不動産投資のチャンスは依然多くあると考えています。
●フィリピン
かつては「アジアの病人」と揶揄されたフィリピンですが、積極的に改革や外資誘致を進めた結果、2000年以降は平均5%超の高成長が続いています。輸出頼りの国が多いASEANにあって、数少ない内需主導の高成長国であり、1億人超の若い人口や在外フィリピン人からの継続的な資金還流が高い成長力を生み出す中、現在は「アジアのライジングスター」(米格付大手ムーディーズ)などと評価は一変しています。
フィリピンの不動産市場の魅力としては、物件価格の上昇と高い利回りが比較的両立しやすい環境であることが挙げられます。実際に弊社が管理するマカティCBDのコンドミニアム(2018年完成)を例に挙げると、物件価格は新築販売時から約50%上昇したものの、表面賃貸利回りは9.6%と高水準を維持しています。近隣諸国では物件価格の上昇に賃料が追い付かず、利回りが大きく低下しているケースが多々見られますが、所得増や海外からの資金還流が購買力を刺激するフィリピンでは、高い利回りを維持しながらの健全な価格上昇が続いています。
なお、フィリピンではコロナ禍でも高級物件を中心に旺盛な需要が続いており、2020年第2四半期(4~6月)の住宅価格指数は、前年同期比27.1%上昇して過去最高値を記録。コンドミニアムだけに絞ると、同30.1%上昇しています。
大型インフラ計画「Build Build Build」の目玉である、マニラ首都圏地下鉄などの整備も進行しているほか、今年に入りREIT市場が立ち上がるなど支援材料も多く、フィリピンの不動産市場は引き続き成長が期待されます。
●ベトナム
最後にベトナムですが、「ドイモイ政策」によって市場経済に移行し、対外開放が進められたことで、タイに代わる“ASEANの新輸出大国”へと躍進しており、過去30年間の平均成長率は6.8%、さらに一度も4%を下回ることなく安定的に推移しています。また、現在のコロナ禍においても迅速な対応で影響を最小限に抑えており、2020年は多くの国で大幅なマイナス成長が見込まれる中、ベトナムは2~3%程度のプラス成長が予測されています。
堅調な経済に比例するように、ベトナムに対する国際的な評価はうなぎ上りで、コンサル世界大手のPwCは「2050年にかけて世界で最も高成長を遂げる経済大国」と評しています。
一方、不動産市場に目を向けると、ベトナムは2015年7月に外国人による投資が解禁されたばかりで、まだ海外マネーの流入が限定的です。そのため、近隣諸国と比べて相対的に価格は割安に置かれており、ホーチミンの高級マンション価格はバンコクやクアラルンプールの1/2~1/3程度(日本不動産研究所データ)となっています。
外国人に門戸を開いて以降、住宅価格は右肩上がりとなっていますが、それでも金融危機直後の2009年と比べていまだ低い水準にあり、今後投資インフラの整備も進むと見られる中、ベトナムはまだまだ伸び代の大きい市場だと考えています。
中尾 孝久
フォーランド リアルティ ネットワーク ジャパン株式会社
代表取締役
亡父の「多額のローン」に絶望した長男、年金暮らし母を抱え…
「相続放棄」までの期間は3カ月間と限られている
<事例>
死亡した被相続人は、亡くなる前に妻と離婚していました。被相続人には長男と次男がおり、その二人が相続人です。その二人は、被相続人が所有していた不動産もローンの残債が多額にあることを気にして、相続放棄をしたほうがよいのか、相続したほうがよいのかを相談にきたのでした。
さらに、離婚をした母親への慰謝料や財産分与については、どのようにしたらよいのか、全くわからない状況でした。
本事例では、被相続人が不動産投資を行っていて複数の不動産ローンを抱えていました。死亡時には、団信に入っていたかどうか不明であり、そのためローンがなくなるかどうかは、わからない状況でした。
このように、被相続人が多額の債務を抱えているような場合、相続することを決める、すなわち単純承認することにより故人の借金までも引き継ぐおそれがあります。そのため、相続人となった者は、ややもすれば「借金を相続するのはいやだから、相続放棄をするしか選択肢はない…」と思いがちです。
しかし、相続財産の中にまとまった額の預貯金や不動産が含まれている場合には、すべての債務を弁済してもなお財産がプラスの形で残る可能性があります。
そこで、まずは資産をくまなく洗い出して、債務を返済することが可能かどうかを慎重に検討すべきなのですが、ネックとなるのは相続放棄までの期間が3カ月間と限られていることです。
実際問題として、会社勤めしていたりなど日々忙しく働いている人にとっては、わずか3カ月の間で、相続財産を調べ尽くすことは困難といってよいでしょう(しかも、四十九日までは喪に服すという人が多いはずなので、それから動くとなると実質的には1カ月半程度しか時間がありません)。
となると、やはり「面倒だ。借金のほうが多いリスクを考えると、さっさと相続放棄してしまおう」という考えに傾いてしまうかもしれません。
600万円程度で売れる見込みだったが…思わぬ事実が!
■正当な理由があれば相続放棄のリミットを延長できる
しかし、実はこの3カ月という相続放棄のリミットは、正当な理由がある場合、延長することが可能です。「3カ月では相続財産が調査できない」などの理由を挙げて裁判所に申し立てることにより、期間を3カ月以上に延ばすことが認められているのです。
相続放棄の期間を延長することによって、相続財産の調査をじっくりと行うための時間を確保することができますし、さらには、遺産分割の選択肢をより広げることが可能となります。
たとえば、この事例では、その後の調査で、ローンのほとんどについて故人が団信に入っていたことがわかりました。そこで、団信によってローンの消滅した不動産を売却し、その代金を残っていたローンなどの返済に充てました。
また、他県で所有していた不動産については、600万円程度で売れる見込みでしたが、年間200万円の賃料が入る優良物件だったことから、売却せずに、離婚した母親に被相続人が生前借りていた借金の代物弁済として譲渡することにしました。その結果、母親には年金以外に年間200万円の賃料収入が入り、生活も楽になりました。

相続放棄の期間を延ばしたことによって、単純に相続放棄を選んだ場合と比べ、相続人やその母親にとってはるかにメリットの多い結果がもたらされることとなったのです。このように、相続財産の中に、債務ばかりが目につくような場合でも、慌てて放棄をするのではなく、まずは相続放棄の期間延長の申立てをして、善後策をじっくりと検討することが大切です。
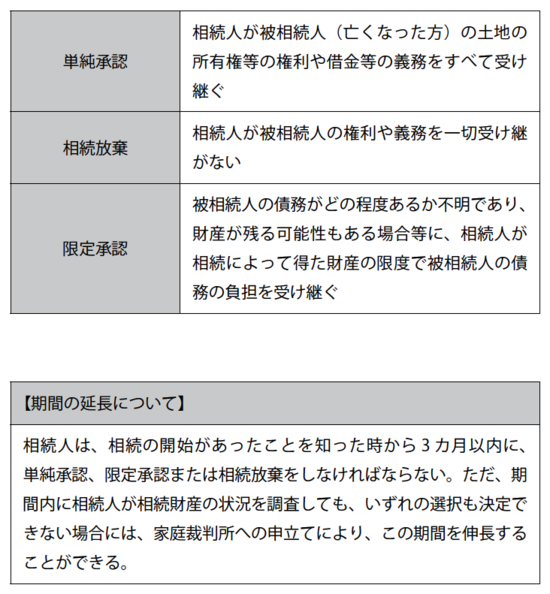
年収1500万円前後だが…勤務医が「資産10億円」になれるワケ
勤務医の年収は1500万円前後だが…
幸い医師の皆さんは一般的なサラリーマンよりも収入が多い。これは資産形成の上で、非常に大きなアドバンテージになります。
勤務医の年収は1500万円前後ということですから、平均月給にすれば100万円から120万円。一方で35歳から39歳男性の平均年収は498万円、40歳から44歳は561万円ですから確かに高所得です。

(画像はイメージです/PIXTA)
この現状をまず確認した上で、それではここから、一体どのくらいの資産を形成することを目指すか? 行動するにしても目標が定まらないと、どのような動きをすればいいかが見えてきません。
悠々自適な老後生活には最低でも「数億円」が必要!?
目標として皆さんは、将来いくらぐらいの資産を希望しますか? たとえば仮に最終ゴールを開業とすればどうでしょうか? 開業資金を蓄えるといっても場所や診療科目によってさまざまですが、土地と建物、そしてX線撮影装置や超音波診断装置などの各設備を含めて、最低でも1億円は必要でしょう。
さらに家庭に必要な資金を忘れてはいけません。子どもの教育費であれば、医学部を目指すなら、その6年間の学費は国公立大学に入学の場合で約350万円。しかし、私立ならば多くが3000万円前後、高い大学なら5000万円近くになります。子ども2人なら6000万円以上です。
そのうえ悠々自適な老後生活を送ることを考えると最低でも数億円・・・。
しかし、心配には及びません。これをサラリーマンの平均年収から資産形成しようと思えば、難しいと言わざるを得ませんが、皆さんは幸運にも医師です。筆者がこれまでコンサルティングしてきた経験から言って、最低でも3億円は堅い。現実的に考えて5億円は普通に達成できます。
しかし、まずは目標ですから、ここは10億円と設定してみましょう。できれば資産10億円あれば理想ではないでしょうか。しかも開業や教育費を考えると、できるだけ早い時期にこの金額を達成したいところです。そこで本連載では5年以内に資産10億円を目指すことにします。
「普通預金・定期預金」で資産は形成できない
医師の高収入を活用する方法はいろいろありますが、医師向けの有名なポータルサイト「m3.com」の2013年の調査では、医師の資産運用に関する調査結果は次のように出ています。
「どのような資産運用をしているか」という問いに対して一番多かった答えが「普通・定期預金」(74.2%)。そして「株式」(21.8%)、「何もしていない」(20.6%)と続き、「不動産投資」は7番目(7.4%)でした。
『金持ち父さん貧乏父さん』の著者ロバート・キヨサキ氏は、資産とは「あなたのポケットにお金を入れてくれるもの」と言っていますが、資産はすなわちそのもの自体がいつでも現金化できて、定期的に収益を生み出してくれるものでなければいけません。
ところが調査結果で一番多かった「普通・定期預金」の金利は0.02%から0.3%(2014年11月現在)といったところです。1000万円預けても年間2000円から3万円の利息です。これでは前述のような「資産」とはいえません。
プロがしのぎを削る世界で10億円を稼ぐのは至難の業
一方で株式はどうかというと、デイトレードの世界ではその売買は1秒を争います。少しでも目を離すとチャンスを失います。比較的長期の保有を前提とするにしても、ビジネスの動静には常に目を配っておかなければなりませんし、そもそも「目利き」ができなければなりません。毎日寝る間を削ってまで激務をこなし続ける皆さんに、株の値動きをチェックする時間があるでしょうか? とても定期的に利益を生むとは思えません。
「株式」と僅差で「何もしていない」が3番目に来ていることから、現状ではほとんどの医師が資産運用を行っていないことが分かります。手軽な副収入ということでは、近年はインターネットショップやアフィリエイトも人気のようです。
しかしインターネットショップは、商品の仕入れから在庫管理、受注の対応、商品の発送などをすべて行わなければなりません。従業員を雇うなら可能かもしれませんが、軌道に乗る前にそこまで準備を整えるかどうか考えものです。
アフィリエイトとは、インターネット広告の課金方式の一つです。最初にウェブサイトやブログを開設し、そこにネット広告を貼り付ける必要があります。その広告を見た一般の閲覧者が、そのリンクを経由して広告主のサイトで会員登録や商品を購入したりすると、一定の料率に従って媒体運営者に報酬が支払われるというものです。
当然、そのサイトやブログを頻繁に更新しないと、閲覧数を伸ばすことができません。結果的に誰からも広告を見てもらえず自然消滅に、ということがほとんどのようです。どちらにしても超多忙な医師の皆さんには向かないでしょう。
そもそも世界中のプロ中のプロが常にしのぎを削っている株やネット関連ビジネスで、10億円を稼ぐのは至難の業です。草野球の経験もない素人が、プロ野球で4割バッターを目指すようなものです。投資した金額を回収するのさえ難しいでしょう。こんな可能性の低いことに時間とお金を使うべきではありません。
不動産運用による資産形成は医師にとっては容易!?
筆者は基本的に時間のない医師にとって理想的な資産運用方法は、以下の3条件に当てはまることが必須と考えます。
1.予備知識がそれほど必要ない
2.管理に時間を取られない
3.10億円の資産形成の道筋が具体的に描ける
この3条件を満たす数少ない選択肢はそうはありません。その数少ない選択肢の一つが不動産運用です。
不動産運用による資産形成は比較的単純なので、それほど苦労せずに身につきます。超難関の医師国家試験に合格した皆さんにとっては余裕でしょう。管理に関しては、プロの管理会社が行います。資産形成の道筋は、収入源が安定した家賃なので着実に描けます。
医師という職業は最上位の個人属性のひとつ
不動産運用が、医師の資産形成にとって最適である理由を2つ挙げましょう。それは、
1.レバレッジを効かせやすい
2.節税効果がある
ということなのです。節税効果を享受できるのは、高収入である医師の皆さんにしか当てはまらないことです。しかも不動産にしかできないものです。
そしてレバレッジが効くというのは、融資額の上限が大きいということです。これは医師という職業が弁護士などと並ぶ最上位の個人属性だからです。しかもこの最上位とその他の差は今後さらに開いていくでしょう。今後も一般的なサラリーマンの収入はあまり上がらないからです。
これから好景気に向かうと書きましたが、それは企業側だけのことです。収益を上げた企業は、経済のグローバル化によって今後ますます法人税の低い海外に拠点を移していきます。
日本の法人税率(法定実効税率)は、約36%と世界でもトップクラスに高い。一方でシンガポールや台湾など東南アジアは10%台。欧米諸国でも20%台後半です。政府は今後5年以内に6%程度引き下げると言っていますが、その程度では企業の日本離れは止められないでしょう。
このような中、企業は海外へ資本を投入し、市場開拓と同時に雇用も行います。現地のことは現地の人間に任せた方が効率はいいし、何より人件費が安いからです。
そこで取り残されるのが、日本のサラリーマンです。新聞やニュースなどでは「ボーナスが○%アップ」などと書かれていますが、それはあくまで一時的なボーナスで、固定給は変わっていません。すでに高い人件費の日本のサラリーマンに、これ以上の収入増は見込めないでしょう。
資産運用を成功させるカギは「レバレッジ効果」にあり
ある銀行員が「年収5000万円の外資系会社員と年収1500万円の医師なら、医師の方にお金を貸す」と言っていました。
また、筆者のクライアントの女医は、育休中にもかかわらず、一発回答で融資審査が通りました。しかも医師だからという理由で、サラリーマンなら絶対あり得ない金額を借りることができました。
信用力がある医師だったからこそ、このように数年先の年収、いわゆる「見込み年収」で融資を受けることが可能だったのです。
政府は景気対策のため、今後も金融緩和を継続するでしょう。すると金融機関にはお金が余っていきます。インフレが進む中、人口の大多数を占めるサラリーマンの収入は上がらず、リストラもあり得る。ならば少数でもお金持ちへ。その中でも将来の安定性が約束された医師、特に勤務医―といったロジックで金融機関は、今まで以上に医師へお金を貸したがるのです。
金融機関はたとえ現在の年収が少なくても、不動産運用のためならば、最上位の個人属性である医師に、より低金利でより多額の融資をしてくれます。
その上限額の目安は、年収の20倍前後。年収1500万円なら3億円です。一般的なサラリーマンなら10倍がいいところ。年収500万円ならば5000万円です。3億円あれば都心近くに20戸ほどの鉄筋コンクリート造マンションが買えます。家賃が月々10万円なら年間の家賃収入は2400万円です。
5000万円ならば、地方都市に8戸ほどの木造アパートといったところです。家賃が月々5万円なら年間の家賃収入は480万円。年収は3倍なのに家賃収入は5倍。レバレッジ効果は運用額が大きいほど有効に機能するのです。いかに医師が不動産運用に向いているかが分かります。
資産運用を成功させるためにもっとも重要なカギは、この「レバレッジ効果」です。レバレッジ=てこ。つまり少ない資産を元手に、大きな取引をすることです。
筆者は医師以外にも高所得者の知り合いが多数いますが、不動産運用をしないで10億円以上の資産を持っている人を知りません(オーナー社長が上場益を得るケースが一部でありますが、医療法人の上場は認められていません)。
確かに10億円以上の資産を持つ人の多くは、不動産運用以外にも株などの複数の収入源を持っています。しかし、彼らはこれらで稼いだお金を最終的に不動産購入の頭金へ回します。結局、安定的に億単位の収入を得る手段は不動産なのです。
借金をしない限り「レバレッジ効果」は生まれない
医師が資産10億円を目指すなら、不動産運用が最短距離といえます。それは資金を融資してもらうことによってレバレッジ効果が期待できるからです。
融資とは借金です。そう捉えること自体は間違いではありません。しかし、借金という言葉には、日本人特有の価値観が埋め込まれてしまっています。日本人は「借金=悪」と考える人が多い。「借金しない?」と聞くとほとんどの人が「とんでもない!」と答えるでしょう。事業資金を借りると聞いても、後ろ向きに捉えるようです。
子どもの頃からお金についての教育を受け、「起業」も盛んな欧米と違い、日本では借金に対して小さい頃からこのようなイメージを植え付けられているからでしょう。しかし、私たち資産運用の専門家から見れば、それはただの「食わず嫌い」です。借金に対する正しい認識を持つ必要があります。
「レバレッジ効果=借金効果」
経営学的にはこのような式が成り立ちます。借金をしない限りレバレッジ効果は望めません。レバレッジ効果(借金効果)を利用すれば、同じ1500万円の年収でもリタイア後には資産数千万円と10億円の違いが生まれるのです。
たとえば借金が怖い人は、住宅ローンを繰り上げ返済でできるだけ早く返そうとします。しかし、よく考えてください。現在の住宅ローンの金利は1%から2%といったところです。こんなに低金利なら放っておいて構いません。繰り上げ返済するお金があるなら、7%や8%の利回りの不動産運用に回した方が得だからです。
確かに運用するには金利2%から3%の借金をすることになりますが、それでも繰り上げ返済をするより手元に残る資産は多くなります。さらに不動産運用には、節税というメリットもあります。
また金融機関は、株やFXの運用資金を融資の対象外にしています。なぜならこれらは価値がゼロになる可能性があるからです。
一方で不動産運用は、不動産自体に担保価値があり、家賃収入も見込めるので、融資の対象になります。経営に対して素人の人間が、一般的な金融機関から借りられる事業資金は、不動産運用以外にあまり見当たりません。
万が一、ローンの返済ができなくなったとしても不動産は売却可能ですし、普段は医師としての収入で生活していれば、路頭に迷う可能性は極めて低いといえます。それどころかそれまでの家賃収入が貯蓄として残るのです。
ちなみに、ほとんどの勤務医、特に公的病院に勤めている場合は副業が禁止されているはずです。しかし、親からの相続といったことも想定される不動産の運用は、禁止対象から外れます。医師だから活かせる最大のレバレッジ効果。この最大の武器を利用しない手はありません。
とはいえ、多忙を極める皆さんが、このような金融知識を得る時間がないことは十分承知しています。そのため医師が不動産運用で成功するには、その道にくわしい不動産会社や会計士などの専門家を事業パートナーに持つことが最重要といえるでしょう。
何もしなければ、収入のおよそ半分は税金に消えていく
本記事では医師の皆さんに効率よく資産形成していただくために、不動産の運用をお勧めしています。その理由のうち、最も直接的に、かつ端的にそのメリットを実感してもらえるのは医師にとって、極めて節税効果が高いということです。
皆さんは毎年納税している額に驚いたことはありませんか?
所得税の税率は年収900万円を超え1800万円以下なら33%、1800万円超なら40%。しかも2015年からは4000万円超で45%となります。年収1500万円なら33%の495万円。さらに10%の住民税もかかるので合計43%の645万円が税金として消えていきます(分かりやすくするために各種控除額は考慮していません)。
つまり税金や保険料を差し引いた自由に使える可処分所得は、数百万円といったところです。額面上は一般的なサラリーマンの倍以上稼いでいるにもかかわらず、実際に自由に使えるお金は、ほぼ同等なのです。
世間では高給取りと思われながらも、稼いだお金のおよそ半分は自動的になくなってしまうこの現実。筆者のクライアントの医師たちの多くは、
「稼いでも稼いでも税金で取られる」
「ものすごく忙しく働いているのに、これだけしか残らないのはむなしい・・・」
「税金のために働いているようだ!」
と言っています。
それはそうでしょう。645万円といえば35歳から39歳男性サラリーマンの平均年収より150万円も多い。たとえるなら自分自身でエリートサラリーマン1人を雇っているようなものです。人々のために一生懸命働いているのに、いくら税金とはいえそんな大金が毎年無くなっていくことが悲しくないはずはありません。
しかし、いくら悲しんでも何もしなければ自動的に納税しなければならない。今の皆さんはまさに武器を持たない「丸腰」なのです。
不動産運用による収入は給与所得と損益通算が可能
皆さんのような高額納税者にとって不動産運用は非常に相性がいい。なぜなら不動産から得た収入は、勤務医としての給与所得と合算する「損益通算」してから確定申告できるからです。
これだけ聞くと当たり前のように思うかもしれませんが、株やFXで得た不労所得は損益通算できません。これらは給与とは別途に計算し、その額に応じて納税しなければならないのです。給与と合算できるのは、事業所得だけです。ここが株やFXと不動産運用の決定的に違うところです。
不動産は日本経済を左右する要です。だから国策として不動産に関する収益は税制上優遇されているのです。
事業所得は、家賃などで得た収入から減価償却費や金利といった費用を、事業損失として差し引いて計上することができます。減価償却とは、事業を行うにあたって必要な建物や高額な設備などの購入費を、一度に経費計上しないで何年かに分けるという考え方です。
建物などは大変高額なので、たとえば法人の場合は一度で経費計上してしまうと、その年の決算が大赤字になる可能性があります。また、このような建物や高額な設備は1年限りの消耗品ではなく数年にわたって使用できるものなので、使う年数に応じて小分けに計上するのが合理的とも言えるでしょう。国はそれぞれの物品に耐用年数を定めています。計上する金額は、購入金額をその年数で割ったものになります。
おもな物品の耐用年数は次のようになっています。
●鉄筋コンクリート(RC造)住宅 47年(病院用は39年)
●木造住宅 22年
●給排水、ガス設備 15年
●普通自動車 6年
●コピー機、テレビ 5年
●パソコン 4年
不動産運用を行えば、必要不可欠な建物やOA機器などの減価償却費を、勤務医としての収入から差し引いて確定申告できるのです。
京王線23区内12駅を比較…不動産投資するなら、どこに?
京王線23区内12駅を、不動産投資の観点でみていくと
「新宿」と「京王八王子」を結ぶ、京王電鉄京王線。「笹塚」から京王新線で「幡ヶ谷」「初台」と進み、「新宿」で都営地下鉄新宿線と相互直通運転を行っています。また「調布」では京王相模原線が分岐し「京王多摩センター」「橋本」方面へ、「北野」では京王高尾線が分岐し「高尾山口」へ向かうことができます。京王線全線が東京都内を走り、都心のベットタウンを結んでいるため、都心と郊外を結ぶ私鉄のなかでも通勤・通学客が多い路線です。
また京王線の名物といえば「ダンゴ運転」。通勤・通学のピーク時間帯には、駅数以上の電車が走り、ダンゴ状態になってしまう状態で、利用者のイライラの原因になっていることは確かです。そんなデメリットも「笹塚」~「仙川」で進められている連続立体交差事業で改善されるかもしれないと期待が寄せられています。
そんな京王線を23区内の駅に絞り、不動産投資の観点でみていきます。対象となるのは、「新宿」から「千歳烏山」まで、新宿区、渋谷区、世田谷区に位置する12駅です。これらの駅の1日の平均乗降人数をみていくと、圧倒的に多いのが「新宿」。1日に80万人近い人が乗降しています。続くのが明治大学和泉校舎のある「明大前」。ただし京王線単体の乗降者に絞ると、「千歳烏山」「初台」につづき、4番目となります(図表1)。
京王線23区内12駅周辺…良好な賃貸市場を形成
■京王線沿線の賃貸市場
沿線のマンション・アパートの分布を色で区分する250mメッシュでみていきます。まず10戸以上のマンション、アパートは、各駅徒歩10分圏内に多くの物件が分布し、80件以上を示す赤で占められています(図表2)。11~60戸と中規模のマンション・アパートの分布をみていくと、各駅周辺で60件以上を示す赤橙を、さらに「幡ヶ谷」~「明大前」と「千歳烏山」周辺は、80件以上を示す「赤」が占めます。さらに「八幡山」の北側の甲州街道沿いにも同様に赤色が確認でき、中規模以上のマンション・アパートが多いエリアであることがわかります(図表3)。
京王線23区内の沿線は賃貸物件の多いエリアですが、特に「幡ヶ谷」~「明大前」と「千歳烏山」周辺に集中がみられます。

1K・1DKでは「新宿」9.8万円でスタート。「初台」~「笹塚」は8万円台で推移しますが、「代田橋」は沿線最高の10.0万円に。近くを縦断する環状7号線沿いに、単身者用新築マンションが増加していて、ワンルームの「八幡山」と同じように、平均家賃をおしあげています。その後、「新宿」から遠ざかるに従い下落傾向にあり、「千歳烏山」では6.9万円と、若手会社員でも十分に検討できる水準になります(図表4)。
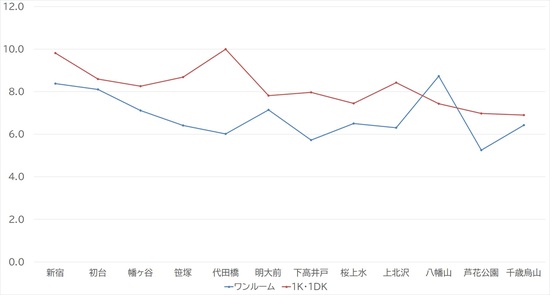
会調べ(10月6日時点)
このような京王線沿線の賃貸市場ですが、昨今、話題になっている空き家の状況はどうでしょうか。250mメッシュでみていくと、賃貸物件の多い駅周辺では空家数が多く、橙(空家数~400件)、赤橙(空家数~600件)が占めています。さらに「幡ヶ谷」「笹塚」「千歳烏山」は空家数600件以上の赤と、特に空き家が目立ちます。賃貸物件が多い一方で、競争が激しく、特に空室対策が必須のエリアといえるでしょう(図表5)。

■京王線沿線の中古マンション市場
続いて、中央線沿線の中古マンションの取引状況や価格についてみていきます。
まず過去5年間の中古マンションの取引件数をみていくと、最も取引件数が多いのは「笹塚」で四半期平均13.94件、続いて「幡ヶ谷」12.88件、「千歳烏山」11.47件と続きます。一方で最も取引件数が少ないのは「上北沢」で4.59件。「下高井戸」4.88件、「明大前」5.06件と続きます。
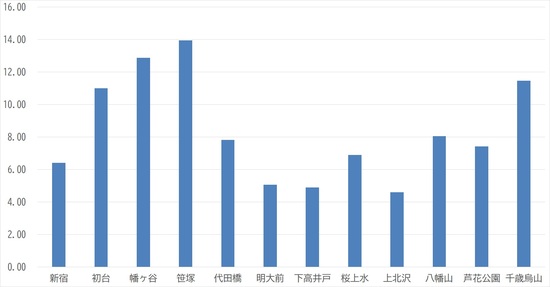
1㎡当たりの価格が最も高いのは、「初台」で137.52万円。続いて「新宿」で123.70万円で、この2駅が100万円/㎡超と、京王線沿線ではひと際平米単価の高いエリアになっています。ターミナル駅である「新宿」から離れていくと、平米単価も下がっていく傾向にあるのは、家賃と同様。「幡ヶ谷」~「代田橋」は90万円で推移し、「桜上水」を越えると、70万円/㎡に。「八幡山」「芦花公園」では60万円/㎡になりますが、速達列車の停車駅である「千歳烏山」は周辺よりも単価があがり、72.33万円/㎡となります。

京王線23区内12駅周辺…20年後の人口は?
■将来人口
不動産投資において、人口は重要なファクターとなりますが、日本は現在、人口減少期で東京も例外ではありません。では、京王線沿線ではどうなのでしょうか。2015年~2040年の人口増加率を500mメッシュ*でみていくと、沿線は安定した人口増加を示す緑~黄緑が多く、特に新宿からも近い「初台」「幡ヶ谷」の駅南側エリアは人口増加が顕著だと予測されています。京王線23区内の沿線では、今後も安定的な人口増加が見込め、不動産オーナーとしては安心材料といえるでしょう。
 [図表8]京王線23区12駅周辺の人口増加率出所:地域経済分析システム(RESAS:リーサス)より作成
[図表8]京王線23区12駅周辺の人口増加率出所:地域経済分析システム(RESAS:リーサス)より作成
※0%以下(人口減少):青系、~5%:緑、~10%:黄緑、~15%:黄、~20%:橙、~25%、25%~
■まとめ
「新宿」を起点に、都心への通勤・通学路線として親しまれている京王線。家賃は「新宿」から離れるに従って下降する傾向にありますが、ワンルームマンションでは「八幡山」、1K・1DKでは「代田橋」で家賃の高まりが確認できます。これは環状7号線、環状8号線沿いに、単身者向けマンションが増加しているためで、今後の建築数によっては、状況が変わると推測されます。
一方で昨今問題視されている「空き家」は、「初台」「幡ヶ谷」「千歳烏山」で特に多くなっています。元々、賃貸物件の多いエリアで、物件間の競争が激しくなっていると考えられます。賃貸ニーズを的確につかむ物件選び、賃貸経営がより求められるエリアだといえます。
中古不動産の平米単価は、「新宿」「初台」で100万円/㎡超で、沿線内では別格。初期投資を抑えたいなら、「新宿」から離れたエリアを選定するのがいいでしょう。さらに今後の人口増加の推移予測からは、沿線ではこれからも安定的に賃貸ニーズが見込めるとされています。
新宿からも近い「初台」~「笹塚」は、中古マンションの取引件数も多く、マーケットも大きいエリアです。ただし空き家も多く発生し、物件間の競争が激しいエリアと考えられます、また利便性の高さから平米単価は高く、初期投資を抑えたいという人にはハードルが高いエリアでしょう。一方「千歳烏山」は平米単価も低く、また今後も安定した人口増加が見込めることから、初期費用を抑えたいという投資家に向いているエリアといえそうです。
現在、京王線では連続立体交差事業が進行中。完了すれば、路線のネガティブ要素がひとつ解決でき、沿線の魅力が向上、さらなる賃貸ニーズを呼び込む可能性も秘めています。
■将来人口
不動産投資において、人口は重要なファクターとなりますが、日本は現在、人口減少期で東京も例外ではありません。では、京王線沿線ではどうなのでしょうか。2015年~2040年の人口増加率を500mメッシュ*でみていくと、沿線は安定した人口増加を示す緑~黄緑が多く、特に新宿からも近い「初台」「幡ヶ谷」の駅南側エリアは人口増加が顕著だと予測されています。京王線23区内の沿線では、今後も安定的な人口増加が見込め、不動産オーナーとしては安心材料といえるでしょう。

※0%以下(人口減少):青系、~5%:緑、~10%:黄緑、~15%:黄、~20%:橙、~25%、25%~
■まとめ
「新宿」を起点に、都心への通勤・通学路線として親しまれている京王線。家賃は「新宿」から離れるに従って下降する傾向にありますが、ワンルームマンションでは「八幡山」、1K・1DKでは「代田橋」で家賃の高まりが確認できます。これは環状7号線、環状8号線沿いに、単身者向けマンションが増加しているためで、今後の建築数によっては、状況が変わると推測されます。
一方で昨今問題視されている「空き家」は、「初台」「幡ヶ谷」「千歳烏山」で特に多くなっています。元々、賃貸物件の多いエリアで、物件間の競争が激しくなっていると考えられます。賃貸ニーズを的確につかむ物件選び、賃貸経営がより求められるエリアだといえます。
中古不動産の平米単価は、「新宿」「初台」で100万円/㎡超で、沿線内では別格。初期投資を抑えたいなら、「新宿」から離れたエリアを選定するのがいいでしょう。さらに今後の人口増加の推移予測からは、沿線ではこれからも安定的に賃貸ニーズが見込めるとされています。
新宿からも近い「初台」~「笹塚」は、中古マンションの取引件数も多く、マーケットも大きいエリアです。ただし空き家も多く発生し、物件間の競争が激しいエリアと考えられます、また利便性の高さから平米単価は高く、初期投資を抑えたいという人にはハードルが高いエリアでしょう。一方「千歳烏山」は平米単価も低く、また今後も安定した人口増加が見込めることから、初期費用を抑えたいという投資家に向いているエリアといえそうです。
現在、京王線では連続立体交差事業が進行中。完了すれば、路線のネガティブ要素がひとつ解決でき、沿線の魅力が向上、さらなる賃貸ニーズを呼び込む可能性も秘めています。
トランプ氏コロナ感染で、105円割れの米ドル…今後の展開は?
「10/5~10/11のFX投資戦略」のポイント
[ポイント]
・米ドル/円は「コロナ後」、90日MA±2%の狭い範囲で小動きが続いてきた。これは、過去の米大統領選挙前も同様だった。過去の大統領選挙では、選挙前後に90日MA±2%をブレークすると大相場が広がった。足元で90日MA±2%に相当するのは104.3円、108.6円。
・トランプ大統領のコロナ感染などが株価にどう影響するかなどを見ながら、米ドル/円が104.3円と108.6円のどちらかをブレークするか、引き続き注目。
 104.3円と108.6円のどちらかをブレークするのか…
104.3円と108.6円のどちらかをブレークするのか…
(画像はイメージです/PIXTA)
[ポイント]
・米ドル/円は「コロナ後」、90日MA±2%の狭い範囲で小動きが続いてきた。これは、過去の米大統領選挙前も同様だった。過去の大統領選挙では、選挙前後に90日MA±2%をブレークすると大相場が広がった。足元で90日MA±2%に相当するのは104.3円、108.6円。
・トランプ大統領のコロナ感染などが株価にどう影響するかなどを見ながら、米ドル/円が104.3円と108.6円のどちらかをブレークするか、引き続き注目。

(画像はイメージです/PIXTA)
先週は一時105円割れの米ドル/円…今後の展開は?
先週の米ドル/円は105円台で方向感のない小動きが続いていましたが、トランプ大統領のコロナ感染が伝わったことをきっかけに、一時105円割れとなりました(図表1参照)。

ではいよいよ円高に動き出すのでしょうか、それともまだ小動きが続くのでしょうか。
米ドル/円は、3月のコロナ・ショックが一段落して後から、方向感の乏しい小動きが続いてきましたが、それを90日MA(移動平均線)との関係で見ると、90日MA±2%といった狭い範囲での展開が続いていました(図表2参照)。

ところで、このように90日MA±2%といった狭い範囲での小動きが続くのは、米大統領選挙前の米ドル/円の特徴でもありました(図表3参照)。

そしてこれまでの場合、選挙前後で90日MA±2%をブレークした方向に大相場が広がってきました。
ちなみに、足元の米ドル/円90日MAは106.5円程度なので、それを2%下回った水準は104.3円程度、逆に2%上回った水準は108.6円程度といった計算になります。先週末の終値は105.3円だったので、「距離感」からすると、104.3円の方が近い位置にあることは間違いありません。
トランプ大統領のコロナ感染症状など何がきっかけになるかはともかく、米ドル/円が90日MA±2%を大きくブレークするなら、それは「コロナ後」これまでなかったことであり、過去の米大統領選挙前後の値動きを参考にすると、大相場が始まっている可能性があるということで、大いに注目されるのではないでしょうか。
米国株、割高の修正本格化は避けられないが…
ところで、米ドル/円は9月に一時104円割れ寸前まで急落する場面がありました。これは、NYダウが1割程度下落するなど、米国株が急落する局面とある程度重なって起こった動きでした。その意味では、上述のように、米ドル/円が90日MA±2%をブレークするかを考える上でも、米国株の動きはやはり注目されるところでしょう。
その米国株、9月下旬で急落は一段落し、先週にかけては反発気味の展開となりました。先週金曜日に、上述のようにトランプ大統領のコロナ感染が伝わると、NYダウも一時400ドル以上の急落となりましたが、引けにかけては下げ幅を縮小するところとなりました。一方でナスダック指数は、反発が鈍いまま、前日終値比2%以上と比較的大きく下落しました。
ナスダック指数は9月に最大で12%以上の下落となりました。これは、短期的な「上がり過ぎ」の反動が一因だったでしょう。株安が始まる前、ナスダック指数の90日MAからのかい離率はプラス20%程度と、きわめて「上がり過ぎ」懸念が強くなっていました(図表4参照)。
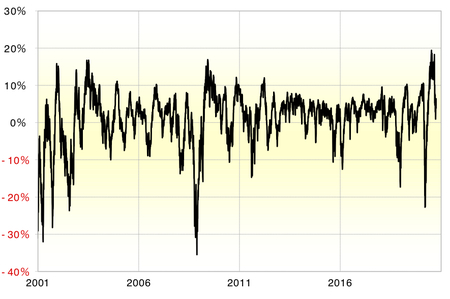
ただ、急落を受けて、同かい離率はほぼゼロに近いところまで縮小しました。株の急落が一段落し、先週にかけて反発に転じたのは、短期的な「上がり過ぎ」の是正が一因といえます。
一方で、ナスダック指数とNYダウの相対株価を見ると、一時0.4倍を大きく超え、2000年ITバブル以来のナスダック指数の記録的な割高となっている状況はなお著変ありません(図表5参照)。

記録的な割高の修正本格化は、基本的には不可避のものでしょう。問題はそれがいつ起こるのか、何がきっかけになるのかということ。トランプ大統領のコロナ感染や、それに伴う米大統領選挙などへの影響が、その「きっかけ」になるかは、引き続き注意が必要です。そして、米ドル/円が90日MA±2%をブレークするかは、そんな米国株の動向が一つの鍵になるでしょう。
吉田 恒
マネックス証券
チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長
不動産市況は二極化、コロナが米国に与えた影響を分析
2014年に永住権を得て米国に移住。現在は日米で不動産投資を行いつつ、リアルター(不動産仲介)としても活動する石原博光さん。
前回に引き続き、新型コロナウイルスの影響を受けた米国の市況をリポート。今回は、リアルターとしての立場から、米国の不動産市況の今後を分析していただきました。
サブプライムローンの教訓が生きる
こんにちは、石原博光です。
前回、米国での生活や経済には「クレジットスコア」が大きな影響を与えるというお話をしました。かいつまんでおさらいをすると、米国では信用調査会社が算出するクレジットスコアの数値によって、銀行からのローン審査可否や金利判断が変わるということです。このクレジットスコアはカード支払いやローン返済などが遅れていないかなどさまざまな指標をもとに算出されるのですが、新型コロナウイルスの影響で、現在、支払い遅延履歴がスコアに反映されない状況が続いています。
今住宅ローンを引いて家を買いたい、という人がいたとしても、そのスコアの正確性が疑わしいため、通常より書類を厳しくチェックしたり、頭金をより多く求めたりと、各金融機関で条件を厳しくし、対策をとっているようです。聞いた話によると、安定職の代名詞とも言える公立学校の教師夫婦でも、上記に加えて現在本当に職に就いているか? なども詳しく調査されたりと、住宅ローンを借りるのに苦戦したとのことでした。
こうした対応は、2007年ごろに起こったサブプライムローン危機の教訓が生きているからこそとも言えるでしょう。僕自身も2016年に米国で住宅ローンを利用した際、本当に審査が厳しかった記憶があります。担当者に聞いたところ、「あの事件から学習した結果」だと話していました。
スコアクレジットの正確性が揺らぎ、利用者の財務状況が十分に把握できない今は、むやみにローンを貸し付けるようなことはしておらず、焦げ付きが頻発しているという話は聞きません。
2割強が廃業危機!?
では、米国の実体経済、企業の動きについてはどうでしょうか。こちらは、「嵐の予感」といった感じです。
例えばコロナの影響を受けた中小企業は、一定の条件を満たすことで運転資金など最大10万ドルの実質給付が受けられる「給与保護プログラム(PPP)」を利用してきました。そのお金で何とか持ちこたえてきたものの、その資金も使い果たしたところが大半のようです。
7月初旬に行われた「全米独立ビジネス連盟」の調査では、約23%が「このまま経済状況が改善しなければ、6カ月以内に廃業せざるを得ない」と回答しているということです。
また、飲食店や小売業などスモールビジネス全体でのデフォルト(債務不履行)は2.7%。リーマンショック後の2009年は6.35%がピークでしたが、来年までに5~6%になると予測をされています。
賃料下落、従来なかったフリーレントも登場
こうした状況の中、大都市圏に多い飲食店や小売店で働いていた人たちがコロナの影響で仕事を失い、生活コストのかかる都市部から郊外へと流れる動きが実際に出てきていると感じます。
CNNでは、ニューヨークでは空室が増えて、賃料が下落中と報道されていました。マンハッタンの空室率(7月時点)は3.67%だったそうですが、これは去年の倍以上で、過去14年間で最悪の数値だということです。平均賃料は3378ドルで、これも前月から4.7%低下しています。
これまで米国(特に都市部)では、いわゆる「フリーレント」はほとんど導入されてきませんでしたが、今は1~2カ月のフリーレントをつける家主も登場したようです。
また、都市部で働いていた外国人や、都市部の大学に留学していた学生が帰国してしまったこともあるでしょう。大学に関しては、オンライン授業となって、学生が戻ってこないのでは、という懸念もあると言われています。
今はまだ郊外への大移動が発生している、という状況ではありませんが、今後失業者への補助金などの給付が終われば、人口の大量流出もあるかもしれません。
余談ですが、コロナで市民の意識にも変化があり、あまり人と接したくないという思いからか、共用エレベーターのない階段の物件が魅力的だとして人気を集めているそうです。
物件は買われなくなっているのか?
コロナ禍もあり、米国の金利は現在、最低レベルで推移しています。住宅ローンも米国ではこれまで考えられなかったほど低く、3%を下回っている状況です。家の買い時が訪れていると言えます。冒頭でお話した通り住宅ローンの審査は厳格化していますが、裏を返せば「買える人は買える」という二極化が進んでいるのです。
不動産関係者に話を聞くと、引き続きミレニアル世代を中心に家を買いたい層は数多く存在しており、住宅需要に供給が追い付いていない構図はコロナ以前から続いていると言います。そして、その舞台は大都市圏から郊外へと移っていると言えるでしょう。
僕の住むカリフォルニア州郊外のベーカーズフィールドの中古物件においても、様子を見ようという人が増えたからか売り物件数が少なく、出せばすぐ売れるような状況になっています。建物における1スクエアフット(約30センチ四方)の取引単価も、昨年8月は147ドルだったのが、今年8月は165ドルと大幅に上昇。平均成約価格は10%以上も高くなり、マーケットとしては順調です。完全なセラーズマーケット(売り手有利)というありさまですね。
金利が低いため借り換えや買い替えを促す動きがある一方、売り物件自体は多くないので、物件価格の上昇は続きそうです。
地域ごとの差を見極める
ニューハンプシャー大学の調査によると、不動産業は全体的にコロナの影響が小さいそうです。カリフォルニアやテキサスの郊外は賃貸も売買も活況。その一方、大都市圏といった賃料や物価が高いエリアでは人々が近郊に移動する流れがあるため、価格下落やフリーレントなどの条件緩和が発生している状態です。地域ごとに差があるため、投資家としてはエリアの見極めが大切だと思います。
そういう点では、地場産業として農業や油田などの基幹産業がある地方都市は、不況に強いのだと改めて実感しました。コロナの影響を最も受けている業種は宿泊業と飲食業(ニューハンプシャー大学調べ:2~7月)ですが、ラスベガスやハワイの観光業は全般的に厳しいと聞いています。
個人向け金融サイト「WalletHub」によると、コロナが原因で最も経済ダメージを受けている州はフロリダを筆頭に南部や東海岸に集中しているそうですが、実際にはどこの州でも業種により苦しい状況が続いています。
一般的には大都市圏ほど収入に占める住居費や生活コストが高く、景気の影響が大きい。かといって一概に地方が有利というわけでもありませんが、中でも産業の多様性に優れ、生活コストの低い地味な地方であるほどボラティリティ(価格変動制)は低く、安定していると思います。
おまけ・石原さんのアメリカこぼれ話
10月31日から11月2日にかけて、アメリカに住むラティーノ(ラテンアメリカ出身者)は、死者の日(Day of the Dead=英語 / Día de Muertos=スペイン語)のお祭りを行います。11月1日は子供の魂が、2日は大人の魂が帰ってくると信じられていて、10月31日は前夜祭です。
各家庭で祭壇(アルタール)を用意し、故人の写真をマリーゴールドで飾り付けて、メキシカンキャンディーや食べ物、お酒などを備えます。まるで日本のお盆のようですが、陽気な音楽を鳴らし、楽しく過ごすというのがラテン流です。

町にあるメキシカンスーパーで売られていた写真の人形は、カトリーナ(エレガントなガイコツ、男性バージョンもある)といい、死者の日の象徴です。100年ほど前に石板作家のポサダが描いた、ヨーロッパ貴族を模したメキシコ先住民の肖像画が起源と言われています。
このお祭りはメキシコで3000年も前からあるガイコツを飾る風習からきていますが、友人曰くアメリカで生まれ育った若い世代(祖先は中南米からの移民グループ)の中には、あえて祝わないという人たちも増えているそうです。
以前、サンディエゴから徒歩で国境を越えてメキシコのティファナに行ったことがあります(日帰りでランチを食べに…笑)。どのお店を覗いてもガイコツの飾り物が溢れていて、不勉強な僕はただ不気味で怖かったことが懐かしく思い出されます。
(石原博光)
ランク外でも住みたい「東上線・大山」投資エリアとしても有望
活気ある2つの商店街がシンボルの街
「大山」は、東京都板橋区に位置する、東武東上線の駅です。「池袋」から数えて3駅目。都営地下鉄三田線「板橋区役所」駅へは、北口を出て徒歩5分ほどのところにあります。駅南口を出ると、長さ約560m、店舗数約200店にも及ぶアーケード街「ハッピーロード大山商店街」が西へと伸び、さらに東上線の線路を渡ると「遊座大山商店街」が国道254号線(川越街道)に至るまで伸びています。
商店街には、チェーン店も増えていますが、まだまだ個人商店も多く残り、いまどきの商店街に珍しくなった青果店や鮮魚店なども。まさに地域の台所といった雰囲気で、いつも多くの人で賑わっています。東京を代表する商店街のひとつなので、テレビのインタビューなどによく登場することも。
一方で、飲食店や娯楽施設も多いので、少々治安を不安視する向きもあります。ただ夜の限られた時間のことなので、それほど懸念することではないでしょう。
周辺は、低層の集合住宅や一戸建てが混在するほか、大通り沿いには単身者用マンションも多く立地。商店街の近くや幹線道路沿いはうるさく感じますが、それ以外は閑静な住宅街が広がります。
また駅北側、徒歩3分ほどのところには、総合病院である「東京都健康長寿医療センター」があります。個人クリニックも多く点在しているので、もしものときも安心です。さらに区役所や板橋区立文化会館など、公共機関も充実。よくある「住みたい街」などのランキングでは名前を聞かない「大山」ですが、交通面でも、生活面でも、利便性は抜群にいい街です。
一方で、注視したいのが、駅周辺の開発計画。大山周辺では、都道420号線(中野通り)の拡張と、東上線との連続立体交差事業が予定されています。中野通りの拡張では、ハッピーロードのアーケードを撤去しなければならず、計画は進んでいません。街の住みやすさ、防災力向上に繋がる一方で、大山=アーケード街というイメージにも関わることもなので、今後の動向に注目です。
■各駅停車のみの利用も巨大ターミナル「池袋」まで5分
「大山」は、各駅停車しか停まりませんが、ターミナル駅の「池袋」まで5分ほど。通勤時間帯には5~6分間隔で電車が来ます。
池袋からはJR線のほか、東京メトロ丸ノ内線、有楽町線、副都心線に接続し、都心の主要エリアにアクセスできます。
また前出の通り、都営地下鉄三田線「板橋区役所」も徒歩圏内。駅東側のエリアの居住であれば、2路線使うのも便利。三田線では「大手町」や「内幸町」など、都心方面にダイレクトにアクセスできます。
駅前にはバスロータリーはなく、バス利用のためには徒歩5~10分ほど歩いて最寄りの停留場に向かう必要はありますが、池袋方面へアクセスすることもできます。
現役単身者からの支持が厚く、不動産取引も活発
■大山周辺の人口構造
国勢調査を中心に、大山エリアの人口構造をみていきます。「大山」のある板橋区の人口は56万人強。23区平均と比較すると、若干、若年層が少なく、高齢者が多い傾向にありますが、ほぼ同程度。一方「大山」周辺には2万人強が居住し、15~64歳の生産労働人口が23区平均を3ポイント近く上回っています(図表1)。
世帯の状況をみていくと、板橋区の単身者比率は23区と同程度。一方で、単身の高齢者が23区平均と比べて5ポイント近くも少なくなっています。大山周辺では単身者比率が区の平均を9ポイント以上上回る60.52%。高齢単身者比率も区平均は上回るも、23区平均は大きく下回る7.72%となっています。(図表2)。
また板橋区では賃貸が優勢の地域で、賃貸率23区平均を上回る56.82%。また「大山」周辺では賃貸率59.46%と6割近くを占めます(図表3)。一方で板橋区は賃貸率が23区平均を上回るも、5年定着率も23区平均を上回り、流動性は低いエリアになっています。しかし「大山」周辺は23区平均も区の平均も大きく下回り、流入出の多い傾向にあります(図表4)。
■不動産マーケットの状況
大山エリアの家賃相場をみていきます。駅徒歩10分の1Kの平均家賃は5.36万円、11分を超えると5.38万円と、20代会社員でも適正家賃内で居住可能な水準です。駅距離による家賃下落率は100%と、駅距離によって家賃は下がらない傾向にあります。「大山」駅の東側には、前出の通り「板橋区役所」が徒歩圏内にあり、特に駅東側のエリアは駅距離に関わらず、家賃が一定に保たれる傾向にあります(図表5)。
中古マンションの価格、取引状況をみていきます。「大山」周辺の1㎡当たり70万円ほど。板橋区の平均は大きく上回り、東京都平均に近い価格になっています(図表6)。過去5年の中古マンションの取引件数をみていくと、四半期平均で14.1件程度と、大山エリアは不動産取引が活発にされているエリアです。直近の2020年第一四半期では平均取引数を下回る12件。コロナ禍の影響を受けたと考えられ、今後の動向に注目です(図表7)。

安定した人口増加、地震・洪水リスクも低い
■将来人口と災害リスク
不動産投資において、人口は重要なファクターとなりますが、日本は現在、人口減少期で東京も例外ではありません。今後、不動産投資において、エリア選定がより重要になります。そこで「大山」周辺の将来人口を、黄色~橙で10%以上、緑~黄緑0~10%の人口増加率を表し、青系色で人口減少を示すメッシュ分析でみていきます。「大山」周辺では、2015年の人口を基準にした際、2040年の人口は100以上。東京でも人口減が予測されていますが、人口増加という点で、「大山」は安心材料の揃ったエリアだといえそうです(図表8)。
さらに不動産経営において気になるのが、災害リスクです。東京都による「地震に関する地域危険度測定調査」では、東京の地盤を12種類に分類し、地震の際にどのような被害が出るのかを町丁別に評価していますが、大山エリアの地盤は安定している「台地」に分類され、総合評価もおおむね「1~2」と、地震リスクの低いエリアだといえます(図表9)。
また板橋区によるハザードマップをみてみると、荒川が氾濫した際、「大山」周辺では浸水被害はなしとされています。一方、東海豪雨と同程度の降雨により「大山」駅周辺では最大1メートルの浸水が懸念されています。内水氾濫の対策は考えておいてほうが安心です。
■まとめ
東武東上線単独駅で各駅停車しか停まらない「大山」ですが、「池袋」まで5分という立地が魅力です。商店街が充実し、公共施設も近くにあり、環境抜群。よくあるランキングの上位にはみられませんが、住むうえで利便性の高いエリアです。
不動産投資の観点でみていくと、現役の単身者からの支持が厚く、また中古マンションの取引件数からマーケットも活発に動いていることがうかがえます。しかし5年定着率の低さから、物件間の競争は激しいことが推測され、いかに入居者ニーズを掴むかが重要だといえるでしょう。また人口増も予測され、災害リスクも低いことから、都内でも比較的安心して不動産投資を検討できるエリアといえます。
一方、計画されているインフラ整備により、街の状況が大きく変化する可能性があり、その点は注視する必要があるでしょう。
不動産投資で初心者は「新築」より「中古」にすべきといえる訳
不動産投資は「投資」という名前のついたある種の「事業」でもある。物件を仕入れ、他人に賃貸し、収入を得ながら、購入費用を返済していくのである。
事業である限りオーナーはそれなりの目利きが必要となる。ただ、誰にでも拓かれたマーケットで人より抜きん出るのは至難の業である。
不動産投資に興味はあるが、何棟も持つような事業主になるにはまだまだ……と思う初心者に向けて、公認会計士・税理士がおすすめする物件のキーワードが著書のタイトルにもなっている「東京」「中古」「1R」だ。この方法なら、不動産投資で新参者も太刀打ちできるかもしれない。
(本記事は、澁谷賢一氏の著書『公認会計士・税理士が教える「東京」×「中古」×「1R」不動産投資の始め方』クロスメディア・パブリッシングの中から一部を抜粋・編集しています)
なぜ新築よりも中古なのか?
 (画像=jeffy11390/Shutterstock.com)
(画像=jeffy11390/Shutterstock.com)

●新築は次の日から中古になる
皆さんは自分が購入したマンションに住むとしたら、新築と中古どちらを選びますか?大半の人は購入して自分が住むなら新築が良いと答えると思います。
賃貸で住む場合であればどうでしょうか?それほどこだわらないと答える方が多いのではないでしょうか。
投資目的のワンルームマンションは、自分で住むわけではありません。賃貸に出して入居者に貸し出し、家賃収入を受け取ることが目的の資産ですから、たとえ築40年だったとしても家賃が維持できて入居者が途切れず、それほど価値が目減りせず、むしろ購入した価格よりも高く売却できるのであれば優良物件であるというのが投資的な考え方です。
他人に貸し出す投資用の不動産であっても、新築を好む方は一定数いますが、購入した1年後には中古マンションの仲間入りです。
私は新築であろうが中古であろうが、マンションの価値は「立地」と「造り」と「管理」で決まると考えています。築10年~20年の中古マンションをお勧めしているのは、同じ立地で同じような造りでしっかり管理されている物件であるならば、新築よりもお買い得で収益性に優れていると判断しているからです。
新築物件でも、立地にこだわっていて、良い物件はあります。ただ、東京都心部では中古の方がお手頃の価格で購入しやすいため、今の不動産市況では中古から始めてみた方が良いと考えています。

●なぜ築10年~20年がいいのか?
なぜ築3~5年ではなくて10年~20年の物件が良いかといえば、価格や家賃が落ち着いてきているのが大きな理由です。築年数が浅い物件だと、まだ物件自体が割高なまま留まっているという印象があります。
現在の不動産市況では、土地の仕入価格や建築費が高騰しているため、ワンルームマンションデベロッパーは販売価格を引き上げなければ利益が取れず、ビジネスになりません。そのため、家賃設定も高く、新築プレミアムが乗っかった新築マンションの価格になっており、マーケット価格と乖離しすぎている物件も散在しています。
かといって、古すぎてもいけません。20年を目安としているのは、金融機関の融資可能期間を考えるとその辺が目安になるからです。現在の金融機関の融資期間の計算は(55年-築年数)が多く、35年のローンを組むことを考えると、築年数は20年がぎりぎりになるのです。耐震構造や設備、間取りの観点からも、築20年よりも新しいものであれば、まず問題はないでしょう。
築年数が20年以上経過している物件は、買ってはいけないかというとそういうわけではないので、誤解をしないようにしてください。1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物については新耐震基準が適用されているのですが、それ以前の物件については、旧耐震基準に基づいた物件群になり、多くの金融機関では物件を評価してくれなかったり、購入層が極端に減ります。そのため旧耐震基準の物件はどんなに安くて利回りが良くても、運用対象としては避けた方が良いですが、それ以降に造られたマンションであれば、金融機関も評価して融資を判断してくれる可能性は十分にあります。
また、最近では融資期間の計算を(60年−築年数)で計算してくれる金融機関もありますので、その場合には築年数が25年でも最大35年のローンが組めることになります。
ここで注意した方がいいのは、2020年現在において築年数30年のような物件、つまり1990年代前半頃に作られてきた物件はバス、トイレ、洗面が一体となっている三点ユニットや、内装が昨今の物件のようにおしゃれで性能の良いものではない場合が多いです。このような物件を購入するにあたっては、賃貸需要の観点で少々懸念があるので、将来リノベーションを行うことを視野に入れた方が良いでしょう。リノベ―ションは空室の状態でないと行うことはできないので、入居者が付いている物件を購入するのであれば、退去したタイミングで行う必要があります。
そもそも、当時はマンションの1部屋あたりの専有面積が小さくてもワンルームマンションを開発することができたため、スぺースを有効活用できる三点ユニットが多く実装されてきました。小さい部屋のビジネスホテルに泊まった経験がある方は、バス、トイレ、洗面が一体となった造りになっているのを目にしたことがあるでしょう。現在の東京23区のワンルームマンションのほとんどは、一部屋あたり25㎡以上の専有面積がないと開発ができないなど、ワンルームマンションの開発規制が強化されています。
リノベーションは、三点ユニットをバス・トイレ別にしたり、キッチンを最新式のIHコンロに変える、壁紙をオシャレに張り替える、ダウンライトにする、フローリングを変えるなど、いくつか手を加えることで物件自体の付加価値を上げることができます。
ここで注意していただきたいのは、何度もお伝えしている通り、投資するための不動産は自分で住むわけではない、ということです。そして、ワンルームマンションの不動産価格は、エリアや築年数で決められている割戻利回りによって決まりますので、リノベーションを通じていかに賃料を上げることができるか、という観点でのみ考えるべきです。フローリングを茶色から白色に変えたところで、賃料の上昇がそれ以上の価値を生まなければリノベーションをする意味は薄いのです。
リノベーションを視野に入れて物件を購入する場合には、リノベーションをすることで専有部分は綺麗に仕上がったとしても、そもそも賃料を上げて入居者が付くエリアなのかという、エリアの賃料相場は把握しておくべきです。郊外のエリアで、どれだけお洒落にリノベーションをしたとしても、大幅に賃料アップすることは難しいのです。
「サラリーマンを辞めてリタイアしました!」の恐ろしい実態
有名投資家たちがよく使う三つのキラーワード
本を出版して講演を行ったり、コンサルティングを行う有名投資家たちの発言には、いくつか共通したキラーワードがあります。
① 不動産投資は不労所得です!
② 私のやり方を真似すれば必ず成功します!
③ サラリーマンを辞めてリタイアしました!
実はこの三つのキラーワードに、有名投資家たちの嘘が含まれているのです。それぞれ解説しましょう。

(画像はイメージです/PIXTA)
① 不動産投資は不労所得です!
有名投資家がセミナーなどでよく使うのは、「不動産投資は不労所得」という言葉です。日本では、家賃収入を「不労所得」といいますが、アメリカでは「受動所得」または「ポートフォリオ所得」という言い方をします。不動産投資をはじめる目的として一番多いのが、この不労所得です。サラリーマンでありながら不動産で家賃収入を得て、やがては会社を辞めて不労所得で生活することを夢見る人がたくさんいます。
不労所得=年金代わりという発想が近いかもしれません。しかし、不動産投資はけっして「不労」ではありません。不労という響きは誤解を招きやすい言葉ですが、最近の新規参入者を見ていると、本当に何もせずお金が入るようなイメージが強くなっていると感じます。当たり前のことですが、手放しで安定的にお金が入ることはありません。
不動産投資では管理運営から修繕、会計といったことまで、すべてをアウトソーシングできる仕組みが整っていますが、その前段階として円滑に運営するためのオペレーションを整えて管理していく作業があります。また、さらなる事業規模の拡大を狙って物件を買い増すときは、最初から仕組みをつくっていく作業が必要です。
仕組みを整えた後は自動操縦で運営するという意味では不労所得ともいえますが、最初からお金を生み出す自動販売機が買えるということはないのです。長期的に賃貸事業としてやっていくことを考えると、不労ではなく受動所得の方がしっくりくるのではないでしょうか。私は「不労」という言葉に惑わされることなく、時間とレバレッジを生かした堅実経営を目指すべきだと思います。
また、融資の特性上、個人の属性で融資をしていることもあり、サラリーマンを辞めたことによって、購入が厳しくなることもあります。すでに購入した物件だけで安定的に家賃収入を得るという考えもありますが、それは間違いです。
不動産投資は出口で初めて利益が確定します。持ち続けている以上は建物が老朽化していきますので、小規模の修繕から大規模修繕なども考慮しなくてはいけません。不動産投資は出口を迎えた段階で資産を組み替える手法が正しいやり方です。
不動産投資の特徴は、レバレッジが効き少ない資金で投資ができることで、将来にわたり購入当時の収入が安定的に入ってくる投資ではありません。安定的に収入が入ってくる投資としては投資信託などを選択されるのも良いかもしれません。
不動産投資とは違いレバレッジが効かないため、ある程度の資金が必要であるためCCR(自己資本収益率)が低くなりますが、換金性は高いため組み替えも容易であるのが特徴です。
② 私のやり方を真似すれば必ず成功します!
二つ目は「私のやり方を真似すれば成功します」という言葉です。初心者がよく誤解してしまうのは、次のようなケースです。「物件を何棟も所有している」「本をたくさん出している」「投資歴が長い」その結果、「すごい・偉い・成功している」そんな風に思ってしまいがちです。
しかし、所有物件を何棟も持っていようとも、キャッシュフローと残債と資産価値のバランスを見なければ、本当に成功しているのかどうかは判別つきません。書籍を出版しているといっても、実際に読んでみると、物件概要や数字について明確に示されていないこともあります。
サラリーマン投資家という言葉がまだ世の中に浸透していない十数年前から投資をスタートしていただけで、実際はそんなに儲かっていないのでは?と思われる人も実際にいます。先駆者という意味では価値があるかもしれませんが、成功を見極めるポイントはどのようにして物件を購入したのか、資産がどのぐらい増えたのかです。
究極的にいえば、物件を売却しない限り、利益を確定することはできないのです。購入・運用・売却―これらを繰り返して資産の組み替えをしながら、結果的にどれだけ儲かったかということが大事なのです。
また、不動産投資における成功の着地点は、人それぞれです。まったく同じ条件の物件が存在しないのと同様に、不動産投資のやり方は多種多様です。有名投資家の手法をそっくりそのまま真似することは不可能ですし、仮に真似することができたとしても、それが自分にとって最良のやり方だとは限りません。
そもそも、その有名投資家が本当に不動産投資の成功者かということを判定するためには、「その人は何で収益を得ているのか」を知る必要があります。
本当にキャッシュフローで生活しているのか。それとも、コンサルティング料や講演料で生活しているのか。それとも、不動産業者や建築業者からの紹介料で生活しているのか。同じようにセミナーや勉強会を行っていても、そこにスポンサーがいるのか、それとも自分自身で開催しているのか――。
最近は、多くの不動産投資セミナーが開催されていますが、「高額ではあるけれど、誠実なセミナー」があれば、「お得なように見えて、特定の物件を売りつけるセミナー」が混在しています。
不動産業者のセミナーでは「騙されないぞ」と警戒する投資家の皆さんなのに、有名投資家のセミナーでは、「自分たちと同じ仲間だ!」と無条件に信じ込んでしまう。私は本当に危険に感じます。もちろん、有名投資家のすべてを指して「人を騙すような悪い人間だ!」と批判するつもりはありません。実際、当社でもお付き合いのある有名投資家さんがいますが、信頼のできる人が大半です。
中には、自分の利益だけを優先する人もいます。世の中に善い人もいれば悪い人もいるように、有名投資家だからといって、全ての人が信頼に足る人間とは限らないのです。
③ サラリーマンを辞めてリタイアしました
三つ目は「サラリーマンを辞めてリタイアしました」という言葉です。これをわかりやすく言い換えると、「不動産投資でサラリーマン年収を上回るキャッシュフローが安定的に得られそうなので、会社を辞めて悠々自適に暮らす」ということです。
投資にはいろいろな種類と特徴があります。不動産投資は数ある投資の一つであって、物件を所有し続けて得られるお金を年金代わりにするような性質のものではありません。例えば退去者が出れば、すぐに修繕を依頼して、入居者の募集をしなければいけません。建物全体のメンテナンスも定期的に必要となります。
このように物件を持っている限り、常に何かしらの労働力を投下しなければ家賃収入は得られないのです。将来的に安定的した収益を得ることを目的とするのではなくて、資産の組み替えを前提とした運用――それが不動産投資なのです。
SNSで憧れの生活を披露したり、楽しく過ごしているように見えても、それは有名投資家のブランディングの一環という可能性もあります。先ほどの不労所得にも通じますが、賃貸業は決して安定的な収入ではなく、物件の出口が決まっていない限りは利益が確定していません。
実際にリタイアしてうまくいっている有名投資家の多くは、今でも物件の売買を繰り返しながら、資産の組み替えを絶えず行っています。つまり、経営者として常にしっかり働いているということです。現場で汗して働かずして、遠隔でコントロールできる、そういった点では確かに不動産投資は場所を選ばず、たとえ遠隔地(海外など)にいても経営することはできます。そうした仕組みを整えられることが、不動産投資における最大のメリットではありますが、それは決して「リタイアして悠々自適」ではないのです。
成功している投資家とは、その仕組みをしっかりとつくり上げ、円滑に経営できている投資家です。あなたも成功したいのであれば、リタイアを目指すのではなくて、有能な経営者を目指しましょう。そして、決して有名投資家の一側面だけを見て判断することはせずに、不動産投資というビジネスをよく理解した上で、何が最適な投資方法なのかを考えましょう。
 プロパティエージェント
プロパティエージェント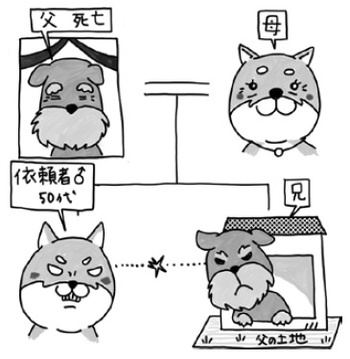
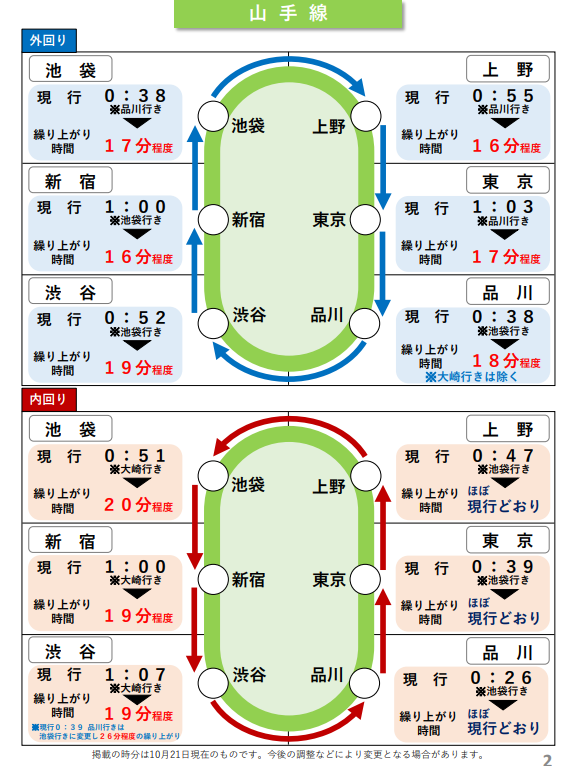
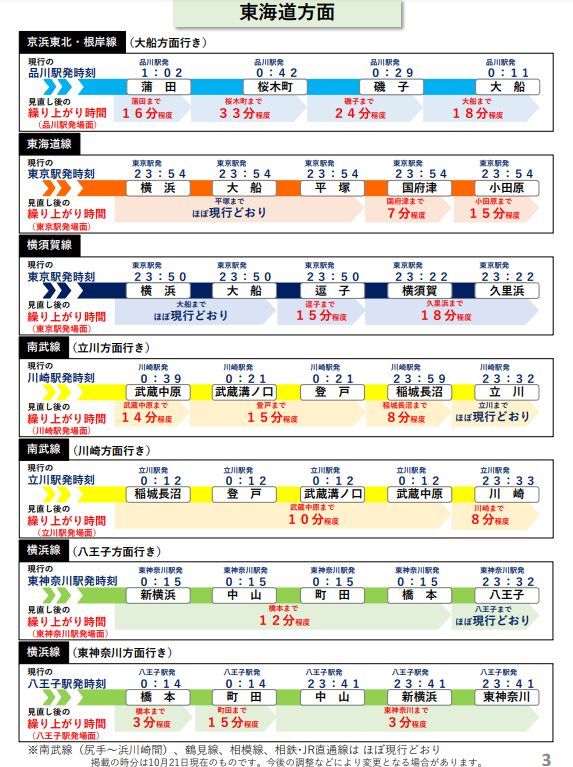

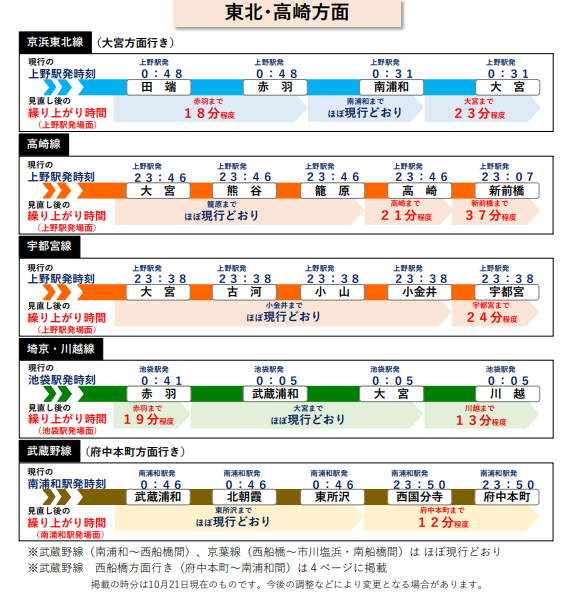
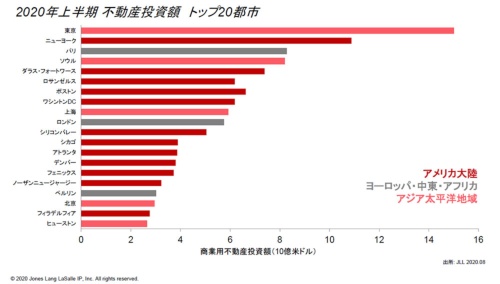
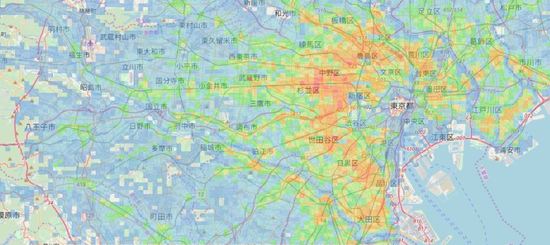



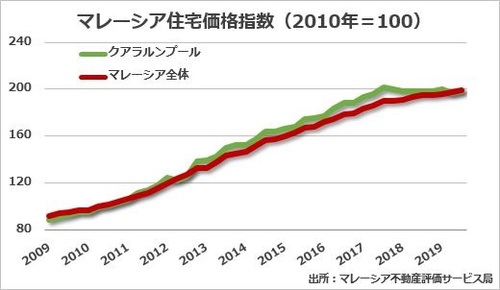
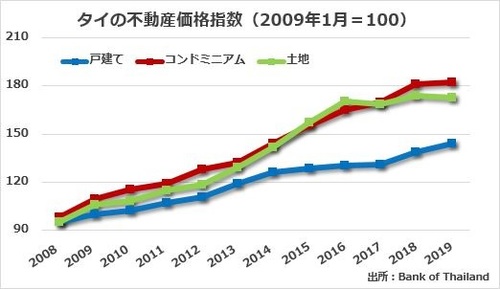
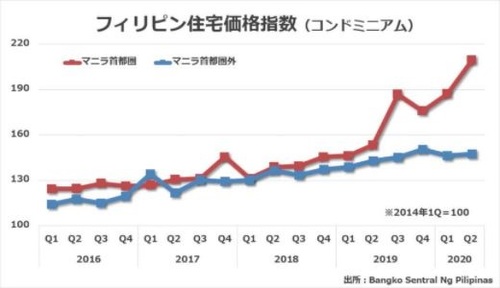
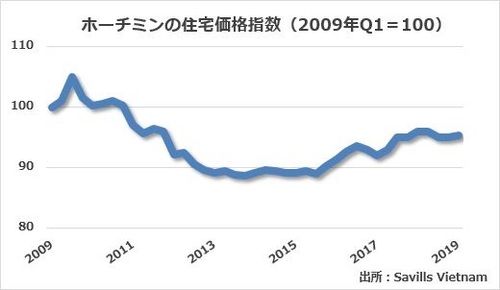


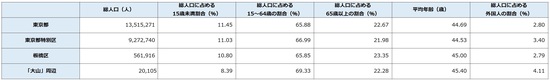
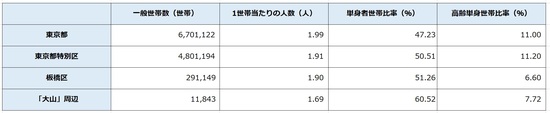


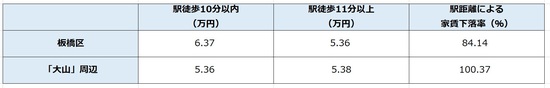


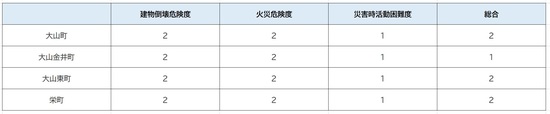
コメント
コメントを投稿